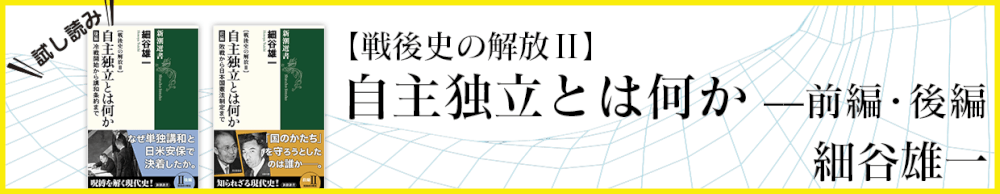「上を向いて歩こう」
その歌は、戦後日本の独特な明るさと暗さの、そのいずれをも象徴する歌であった。
大島九が生まれたのは、日本が真珠湾攻撃をしたわずか二日後の、一九四一年一二月一〇日である。もともと、「坂本九」という名であったが、中学の時に両親が離婚したことにより、母方の姓を用いて大島九となった。この少年は、のちに一七歳の時に「坂本九」という芸名で歌手デビューをし、次々とヒット曲を披露して、昭和を代表する歌手となった。
一九六一年には、永六輔が作詞をして中村八大が作曲した「上を向いて歩こう」というタイトルの歌が、予想を上回る大ヒットとなった。この歌はのちには「スキヤキ(SUKIYAKI)」という奇妙な英語タイトルへと名を変えて、アメリカでもレコードが発売された。アメリカの「ビルボード」誌で一位を獲得したアジア人による最初の、そしていまだ唯一の曲である(註1)。まさに時代に愛され、世界に愛された曲であった。
なぜ「上を向いて歩こう」という曲名が、アメリカではその歌詞とはまったく関係のない「スキヤキ」となってしまったのかについては諸説あるが、タイトルがどうあれ、戦後七〇年を経ていまだに、アメリカでもっとも成功した日本の名曲、いやアジアの名曲といえるだろう。そして、この「上を向いて歩こう」という曲の歌詞は、戦後日本が歩んだ道のりを理解する上で、実に象徴的ともいえる内容となっている。
「上を向いて歩こう」のレコードが発売される前年には、日本社会は安保闘争による深傷を負っていた。安倍晋三首相の祖父である岸信介首相は、困難な日米安保条約の改定を実現すると同時に、国民から激しい批判を浴びて退陣に追い込まれた。後継の池田勇人首相は経済成長に目を向けて、「所得倍増計画」を公約として掲げて総選挙を戦い、一一月の総選挙では与党の自民党が圧勝する。激しく歴史が動揺した時代であった。いまだ多くの人々は、戦争による愛する家族の喪失を覚えており、敗戦による精神的打撃を記憶していた。戦後生まれの少年は、大きくともまだ年齢が一六歳に過ぎない。それを越える年齢の人々にとっては、戦争とは自らの身に降りかかった巨大な悲しみであり、社会を破壊した衝撃であった。その傷が癒えつつあり、豊かさを取り戻しつつある中で、安保闘争によって世論は二分され、政治は硬直し、社会は分断されていた。
そのような政治の激しい動きとは対照的に、坂本九が歌う「上を向いて歩こう」はあまりにも優しく柔らかいメロディであり、また甘美な歌詞が印象的であった。
人々はその頃、戦後の歩みを振り返り、そして将来を展望しながら、複雑な心境でぼんやりとした希望を抱いていた。そのような中で、坂本九が歌う「上を向いて歩こう」という曲は、人々の傷ついた心に染み入るように響いたことであろう。また、独特な明るさとあたたかさ、そして悲しさが感じられたことであろう。そこには切ない希望と、悲しい明るさが同居している。
その歌のはじまりは、次のような歌詞となっている。
上を向いて歩こう
涙がこぼれないように
思い出す春の日
一人ぽっちの夜
これは、失恋の歌である。
つらい失恋を乗り越えるためにも、そしてあふれる涙がこぼれないためにも、上を向いて歩かないといけないのだ。それは、強い意志を持って、悲しみを乗り越えようとする健気な姿勢であった。希望とは感情ではない。意志なのだ。強い意志に支えられなければ、希望というものは蜃気楼のように失われ、見えなくなってしまう。作詞家の永六輔は、そのような思いを込めて作詞したのだろう。
高度経済成長と安保闘争を同時に体験し、またアメリカではジョン・F・ケネディが大統領に就任するとともにベトナム戦争の足音が聞こえるなかで、作詞家や歌い手の思惑を超えてはるかに永く日本人に愛され、また世界でも歌われ続けた。戦後の日本を理解するには、その明るさと暗さとの双方を同時に視野に入れなければならない。そのような明るさと暗さが同居し、希望と挫折が同居する戦後日本社会を象徴するように、人々はこの「上を向いて歩こう」を口ずさんでいたのだろう。
われわれが戦後史を理解するためには、そのような希望と挫折の双方を、そして光と影の双方を、あわせて受け止めなければならない。
語られない歴史
戦後日本社会が抱えた明るさは、あまりにも深い傷と、悲しみ、そして挫折を覆い隠すためのものでもあった。
戦争を経験した日本人は、多くを語らなかった。そして、彼らが「上を向いて歩こう」としたのは、必ずしも希望に溢れていたからではなかった。「涙がこぼれないように」するためだった。上を向かなければ涙がこぼれてしまうのだ。人には自分の涙を見せたくない。自分は強く、明るくいたい。だとすれば、上を向いて歩こうではないか。悲しみの海の中では、希望への強い意志を抱いていなければ、すぐに深い海の底に沈んでしまうであろう。
それは、坂本九の場合もおなじであった。永六輔は、『坂本九ものがたり』の中で、ある秘話を明らかにしている。なぜ「九」なのか。永は次のように記す。
「君は九番目の子供なので『九』であった、とそう思っていましたが、君のお母さんにとって、君は三番目の子供でした。/九番目というのは、お父さんにとってのことだったのですね(註2)」
誰もが「九ちゃん」と愛情を込めて呼ぶときに、坂本九はおそらくは父親が再婚で、自らの上に六人もの異母兄弟がいることを意識しなければならなかったのだろう。自らと同じ母親を共有する兄弟はほかには二人だけであり、「九ちゃん」を含めたその三人兄弟は実に仲が良かったという。
戦争と、戦後の占領期の貧困は、多くの複雑な家庭環境を創り出した。それは、坂本の家族も例外ではなかった。坂本が、女優の柏木由紀子と結婚をして、「理想的な家族像」を演出しようとしていたのも、自分が子供の頃のそのようなあたたかな記憶が欠落していたからだろう。そのような複雑な幼少時代の経験があったから、坂本九は自らの生い立ちについて多くを語ることができなかった。
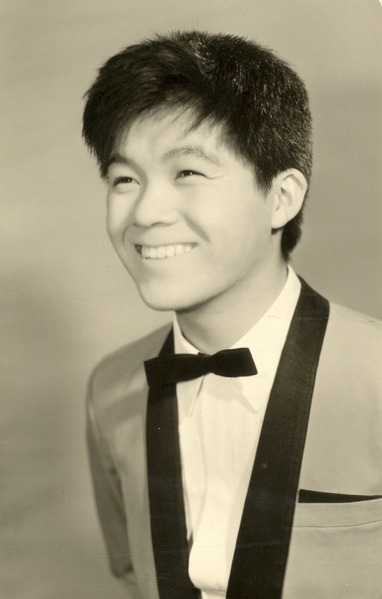
ちなみに、「上を向いて歩こう」を作曲した中村八大の父親は、海を渡った中国大陸にある青島日本人学校の校長であった。中村自らもその学校に通っており、日中戦争の空気を彼の地で吸い込んでいだ。きっと青島では、軍靴の音を聞き、戦闘の傷を負った兵士を幾度となく目にしたであろう。中村のように、幼少期を大陸で過ごし、中国人と日本人との複雑な社会関係を、その背景をよく知らぬまま眺めていた少年や少女は数多くいた。それらの多くの人々は、戦後に引揚者として日本社会に融合するための努力をして、一部の者は不幸にも海を渡ることなく大陸で土に還った。
坂本九と同じように、作曲家の中村八大もまた、自らの苦しい過去をあまり語ることができなかった。幼い頃に、ドイツ人などがレストランでピアノなどの楽器を演奏する様子を見て、中村は西洋音楽に親しみ、音楽家の道を志す。
その後、早稲田国民学校へと留学するために東京市に移り住み、そこで中村は太平洋戦争の開戦を迎える。一〇歳の時であった。そして、そのまま終戦まで内地で過ごすことになる。
自らの私生活を語らない人が多いのは、それがあまりにも過酷で、苦しかったからだ。幼少期を朝鮮半島で過ごした作家の五木寛之も、それゆえ、「戦争体験の継承というけれど、本当に痛みを体験した人は『放っておいてくれ』と思うものです」と語る(註3)。平壌で生活していた五木は家を終戦の年の八月下旬にソ連兵によって接収され、家財を掠奪された。そして、病気で寝込んだ母親をリヤカーに乗せて運び、幼い妹を背負って、雨露をしのぐために転々としなければならなかった。その母も、すぐあとの九月には亡くなっている。そして五木は記す。「『善き者は逝く』。だから、僕は、帰って来た自分を『悪人』だと思っている(註4)」。
だからこそ、夢や希望が必要であった。それがなければ、過酷な現実と、苦しい過去で押しつぶされてしまう。われわれは、そのような戦後史の光と影の両方を知る必要がある。明るさのみでも、暗さのみでも、戦後史を写実的には描くことはできない。両方の絵の具の色を混ぜ合わせることで、より繊細なグラデーションを表現することが可能となり、より現実に近い戦後史を描写できるのではないか。
東京オリンピックの夢
ところで、人々が「上を向いて歩こう」を口ずさんでいたとき、時代は東京オリンピックに向かっていた。いよいよオリンピックが日本にやってくるのだ。世界は高度成長に沸き、そして人々はよりよき未来を夢見ていた。

一九六四年一〇月一〇日から、第一八回夏季オリンピックが東京で開催されて、復興と成長に沸く日本に希望をもたらした。これは、アジアにおける最初のオリンピックである。敗戦国日本を訪れた多くの外国人が、高度成長によって豊かさを謳歌し始めた日本に驚きを感じた。そして、金メダルの獲得数で、日本はアメリカ、ソ連に次いで、第三位となっている。スポーツの祭典で、世界の強豪国と対等に闘い、勝利する日本人選手の姿を見て、どれだけ多くの日本人が鼓舞され、勇気をもらい、感動を覚えたであろうか。日本はまだまだ世界と互角に闘うことができるのだ。あきらめる必要はない。日本人には名誉と成功を手にする権利があるのだ。
一九六四年七月、坂本九は、東京オリンピックにあわせて「サヨナラ東京」というレコードを発売した。世界的に名が知られた坂本は、東京オリンピックのウェルカム・パーティーで、この曲を選手たちの前で歌うことになった。この曲もまた、永六輔、中村八大、坂本九の「六八九トリオ」によるものとなっている。
この曲はだいぶ悲しいメロディとなっており、「上を向いて歩こう」ほどの成功を収めることはできなかった。しかしながら、人々は東京オリンピックの余韻を楽しんでいた。そして、その四年後の一九六八年には西ドイツを抜いて、日本は非共産国で第二位の経済大国となった。日本の上にそびえ立つ経済大国は、もはやアメリカのみとなった。二〇一〇年に中国が日本を抜いて国内総生産(GDP)で世界第二位となるまで、約半世紀にわたって日本はこの地位を楽しんだ。悲しみは徐々に、豊かな生活によって、そして戦争の日々が遠ざかることによって、人々の心から消えていった。
戦争が終わってから東京オリンピックが開催されるまでが一九年。戦後生まれの青年はまもなく成人になろうとしていた。まるで一人の若者が二十歳となって成人式を迎えるかのように、戦後日本も自立し、より成熟した責任のある行動が求められるようになっていた。しかしながら、それから約半世紀が経った現在において、われわれ日本人は国際社会の中で十分に成熟して、十分に自立できているのだろうか。
冷戦後にバブルが崩壊して日本は「失われた二〇年」を経験した。そして、これから日本は二〇二〇年に二度目の東京オリンピックを開催することになる。戦後の日本人が東京オリンピックに夢を見て、希望を語ったように、冷戦後の日本人もまた東京オリンピックを契機に夢を語って、「上を向いて歩こう」とすることができるのだろうか。
時代が動くとき
一度目の東京オリンピックから半世紀を少しばかり越えた二〇一六年七月七日。「上を向いて歩こう」を作詞した永六輔は、八三歳で永眠した。一方の坂本九は、一九八五年八月一二日に四三歳の若さで、飛行機事故で亡くなっている。坂本九が事故死してからの三〇年間、永六輔はもはや「九ちゃん」の満面の笑みを見ることができなくなってしまった。高度成長期の日本において、国民の耳を楽しませてきた二人の人生は、このように分岐点に直面したのであった。
坂本九が亡くなった一九八五年からの三〇年間、日本は激動の変化を経験した。一九八五年九月、中曽根康弘政権下の日本は、プラザ合意によって円高ドル安を受け入れて、日本が責任ある経済大国として世界経済を牽引する姿勢を示すことになった。その頃の日本には自信、驕り、そして横柄な雰囲気が充満していた。昭和の年号も、もう残り四年。戦争と占領を経験した昭和天皇の時代は幕を閉じようとしていた。時代は平成の御代となった。
「上を向いて歩こう」を作詞した永六輔の目に、この三〇年間の変化はどのように映っていたのだろうか。二〇一一年の東日本大震災の後には、戦後を彩った数々の歌手や俳優たちが、この「上を向いて歩こう」をメドレーで歌うCMがテレビで流れた。この歌のメロディを耳にすると、多くの人はこの半世紀に日本人が経験した変化がたちまち走馬燈のように脳裏に浮かんでくるのではないか。そこには何が見えるのだろうか。
坂本九が「上を向いて歩こう」を歌っていたのは、ちょうど自らの短い人生が飛行機墜落事故によって失われるまでの、折り返し地点となっていた二十歳を過ぎた頃のことである。そして、坂本九が亡くなってから三〇年、戦後七〇年を三年前に経験した日本は、これまで何を見て、何を感じて、何を学んだのだろう。そして、何を失ったのだろうか。われわれにとっての戦後史とは、どのようなものであったのだろうか。
「戦後史の解放」とは何か
本書は、戦争が終わり、占領を経験し、豊かさを目指した戦後日本の歴史を、国際社会の動きの中に埋め込むことで、新しい歴史像を提示することを目的としている。われわれは、色鮮やかな物語に溢れている戦後の歴史を語る際に、あまりにも狭い視野の中にそれを無理矢理位置づけようとしてはいないか。たとえば、「冷戦史」という米ソ対立の緊張と抗争のなかに戦後の日本を位置づけようとすれば、人々が感じたあまりにも多くの小さな、しかし大切な物語を見逃すことになってしまう。あるいは、戦前のファシズムから戦後の日本が社会主義や共産主義を拡大しようとする歴史として眺めるのであれば、それは人々がより豊かになり、より安心を感じ、安定を得ていった生活の姿を見逃してしまう。一つのイデオロギーに押し込もうとすれば、豊かな戦後史の物語はとたんに色あせた、単調で退屈なものとなってしまう。
先ほど紹介したように、「上を向いて歩こう」という昭和を代表する名曲の作詞家であった永六輔は戦前に生まれ、歌手の坂本九は真珠湾攻撃の二日前に生まれた。その歌が、冷戦が終わった今でも歌われ続け、愛されているのだ。「上を向いて歩こう」という曲は、それが発表された「一九六一年」という年を越えて長寿を保ち、そして日本の国境を越えて世界で愛されている。冷戦や階級闘争というイデオロギーからでは、その歌の魅力を十分に感じることはできない。たった一つの歌でさえも、われわれが通常歴史を考える際の境界線をはるかに超えた、五つの大陸まで延びる広がりを持っている。
また同時に、われわれは通常あまりにも国境の内側のことに目を奪われるため、国内の問題がいかにして国際的な問題と連動しているのかという視点を見失ってしまう。たとえば、終戦の過程はもちろんのこと、憲法の起草作業、自衛隊創設等、戦後史の多くの重大な出来事が、国際政治に翻弄されている。さらには、戦後の高度成長を支えてきた多くの人々が、実は戦前の教育を受けて、戦争を経験していたという事実を見逃してしまう。
このようにして、われわれは知らないうちに、「イデオロギー的な束縛」「時間的な束縛」「空間的な束縛」の中から歴史を語ろうとしてしまう。それによって見えなくなるものがあまりにも多く、それによってゆがめられる事実があまりにも多い。だとすれば、そのような束縛からわれわれの視点を解放することで、より広い視野を手に入れて、より豊かな歴史が語れるのではないか。そのように考えて、私は「戦後史の解放」という視座から、日本の来歴をとらえ直したいと思う。ここでは、大日本帝国が崩壊した時期から叙述をはじめて、日本が独立を回復するまでの、七年ほどの時代を描写することになる。
希望は可能か
本書では戦後の日本人が何に希望を感じて、何を目指し歩んできたのかを追体験したいと思う。過酷な戦争を体験した後の日本人がそうであったように、人々は明るい希望がなければ生きていけない。今の日本には、希望が足りない。それは世界も同様である。希望を失った人々は、絶望を感じ、死に至る。テロリズム、戦争、災害、貧困など、われわれは暗い死を感じながら、日々のニュースに目を向けている。
希望を感じるためには、広い視野が必要だ。第二次世界大戦で、イギリスがヒトラーの猛攻を受けて敗北を覚悟しなければならなかったときに、ウィンストン・チャーチル首相はスペイン王位継承戦争で活躍した自らの先祖であるジョン・チャーチルの雄姿に思いを寄せ、ナポレオン戦争でのウィリアム・ピット首相の勇気に励まされた。戦後日本を建設した吉田茂首相は、「戦争に負けて外交に勝つこともある」という、ナポレオン戦争後のフランスのタレーランの言葉を多用した。

ピット、タレーラン、チャーチル、そして吉田に共通していたのは、苦しみの中に希望を感じていたことである。ピット首相が政治指導をした時代のイギリスは、ヨーロッパ大陸を支配する巨大なナポレオン帝国を前にして国家存亡の危機にあった。タレーランが外相としてウィーン会議に参加したときのフランスは、哀れな敗戦国となっていた。そしてチャーチルは、ナチス・ドイツがヨーロッパ大陸を席捲して、大国フランスが降伏をする時代に、イギリスという孤独な国家の運命を託されていた。戦後に敗戦国の首相としてサンフランシスコ講和会議に参加した吉田茂は、自らの愛する祖国が国際社会から敵視された現実を知っていた。
苦しい現実の世界で希望を抱くということ。それは自然な感情や惰性ではない。それは意志である。希望を求める強い意志によって、自らの国を正しい方向へと導こうとして、それに成功したのだ。
われわれは、人々の悲しみに目を向けて、それらを心に受けとめなければならない。しかしながら、暗い悲しみにのみこまれることがないように、強い意志で希望を感じなければならない。「上を向いて歩こう」とすることが、大切なのだ。
戦後に日本人が、迷い苦しむ中でどのように明るい希望を感じたのか。それを世界史のなかに位置づけて描き出すことで、今の時代に必要な希望を考えることができるかもしれない。
(註1)^二〇一八年に韓国人グループBTS(防弾少年団)がアルバムチャートの「Billboard 200」で一位を獲得したが、シングルチャートの「HOT100」で一位を獲得したアジア人アーティストは坂本九のみである。
(註2)^永六輔『坂本九ものがたり─六・八・九の九』(中公文庫、一九九〇年)三七頁。
(註3)^五木寛之「生きて帰った自分は『悪人』」橋本五郎編『戦後70年にっぽんの記憶』(中央公論新社、二〇一五年)一七頁。
(註4)^同、一八頁。
-

-
細谷雄一
1971年、千葉県生まれ。慶應義塾大学法学部教授。立教大学法学部卒業。英国バーミンガム大学大学院国際関係学修士号取得。慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程修了。博士(法学)。北海道大学専任講師などを経て、現職。主な著書に、『戦後国際秩序とイギリス外交』(サントリー学芸賞)、『倫理的な戦争』(読売・吉野作造賞)、『外交』、『国際秩序』、『安保論争』、『迷走するイギリス』、『戦後史の解放I 歴史認識とは何か』など。

-
戦後史の解放II 自主独立とは何か 前編: 敗戦から日本国憲法制定まで
細谷 雄一
2018/07/27発売
日本人はなぜ自らの手で憲法を起草できなかったのか――世界史と日本史を融合させた視点から、日本と国際社会の「ずれ」の根源に迫る歴史シリーズ第2弾。敗戦によりマッカーサー率いるGHQの占領下に置かれた日本。戦後日本の新しい「国のかたち」をめぐって、アメリカとソ連、幣原喜重郎や近衛文麿らが、激しい駆け引きを繰り広げる。知られざる現代史。

-
戦後史の解放II 自主独立とは何か 後編: 冷戦開始から講和条約まで
細谷 雄一
2018/07/27発売
なぜ非武装中立や全面講和による平和は実現しなかったのか――世界史と日本史を融合させた視点から、日本と国際社会の「ずれ」の根源に迫る歴史シリーズ第2弾。米ソの対立が深まる中、日本の独立回復の形をめぐり、マッカーサーとケナン、吉田茂とダレス、丸山眞男や吉野源三郎らが、それぞれの理想と現実を激しくぶつけ合う。呪縛を解く現代史。

-
戦後史の解放I 歴史認識とは何か: 日露戦争からアジア太平洋戦争まで
細谷 雄一
2015/07/24発売
なぜ今も昔も日本の「正義」は世界で通用しないのか――世界史と日本史を融合させた視点から、日本と国際社会の「ずれ」の根源に迫る歴史シリーズ第1弾。日露戦争、第1次世界大戦の勝利によって、世界の五大国となった日本。しかし、国際社会に生じた新たな潮流を読み違え、敗戦国へと転落していく。日本人の歴史認識を書き換える、タブーなき現代史。
この記事をシェアする
「細谷雄一『戦後史の解放Ⅱ 自主独立とは何か』(新潮選書)「はじめに」全文掲載」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら