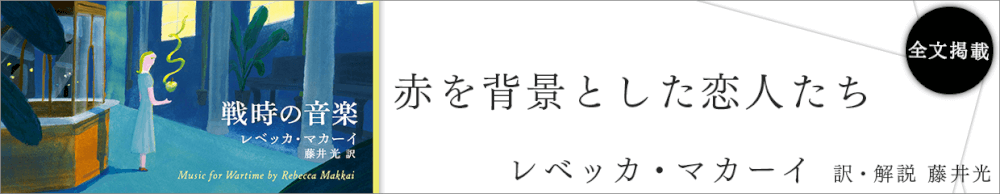赤を背景とした恋人たち
“Couple of Lovers on a Red Background” by Rebecca Makkai
著者: レベッカ・マカーイ , 藤井光
いままでは、彼を「バッハ」と呼んでいた。少なくとも、頭のなかでは。でも、彼が元夫の服を着るようになって、コーヒーメーカーの使い方も覚えたとなると、もう「ヨハン」と呼んであげるべきだろう。一度、管理人がやってくる前にソファからどいてほしかったので「ヨハン」と口に出して言ってみた。彼からの反応はなかったから、その発音で正しかったのか、ちゃんとドイツ語らしく言えていたのかはわからない。そうはいっても、人から外国語でがなり立てられているなかに自分の名前が入っていても聞き取れるかとなると、私だってかなり怪しい。私に抱えられるようにして、彼はようやくソファから掃除機用のクローゼットに行った。あんなに大柄で汗っかきの人を押していくのはひと苦労だった。彼がここに来てから少し痩せたといっても、それは変わらない。本物のドイツ料理を食べに連れていってあげたいとは思うけれど、時空を超えてきた歴史上の人物の世話をするという設定の映画から学んだことがあるとすれば、それは、絶対にその人をタクシーや警察やデパートのマネキンだらけの人前に連れ出してはだめだということだ。
カーテンは閉め切ってあるし、テレビのコンセントも抜いたままにしてあるけれど、毎日私が家を空けているあいだに退屈しないようにと思って、ステレオの使いかたは教えてあげた。自分でも感心するくらい慎重にやった。まず、クリスマスのデコレーションから天使のオルゴールを見つけ出して、音を鳴らしてあげた。彼はオルゴールのことは知っているようだったから、オルゴールとCDプレーヤーを交互に指してからヘンデルをかけた。彼は怖がるどころか喜んだし、いまでは、小さいころからソニー製品をいじってきたかのようにボタンを押してはディスクを入れ替えている。最初のうちはバロック音楽しか渡さなかったけれど、最近ではもっと新しいものも聴くようになっている。モーツァルトを気に入っているのは意外ではないにしても、チャイコフスキーを聴くと、彼はなぜかくすくす笑う。「金平糖の精の踊り」をかけてあげたときは、彼がソファにお漏らしするんじゃないかと思った。五分後、彼はピアノに向かい、覚えている主題を弾いて、旋律のそこかしこで大笑いしていた。そんなことがありえるなら、彼はあてこするように弾いていた。ついでに言えば、彼の笑い声は、マリファナを吸っている中学二年生じみた、高くささやくような音だ。最初、すべては自分の空想だと思っていたときは、『アマデウス』のトム・ハルスからその声を拝借してきたのだろうかと自問した。でも、このあいだ母と電話していたときに「そこで笑っているのは誰なの?」と訊かれた。少なくとも、また誰かと付き合いだしたのだと思っているらしい。
ピアノのなかで暮らしていたことを、彼は忘れているようだ。私だったら、十日間もそこにいたのならば絶対に天板を開けて覗き込むだろうが、彼にはそんな素振りはない。彼がやってきた朝、私はトレーナーの上下を着て、彼が作曲したト長調のメヌエットを弾いていた。ピアノのレッスンを受けたことがあれば誰でも最初に習う、大家による「本物」の曲だ。レーソラシドレーソッソ、で始まるあの曲。私は思い出に浸っていた。その曲が弾けるようになった日は、バリトンのオペラ歌手になりたいと願っていたが記者になった父が、初めて私のレッスンに興味を持ってくれた日でもあった。私は七歳だった。父は後ろに立って、手のひらでリズムを取ってくれた。曲に合わせて歌も作って、私がうまくリズムを取れないときには歌ってくれた。「バッハであそぼ、う、よ、バッハであそぼ、う、よ、おーとうさんもおーかあさんもみんなであそぼ、う!」そんなとき、私は頭が真っ白になりながらも弾き続けて、漫画の本に出てくるベートーベンの絵で、ピアノの後ろに立つ彼の父親の目がドル記号になっていたことを思い浮かべていた。父がお金儲けを考えるほどの才能は、私にはなかった。夕食会の余興でもしてほしかったか、単に自分よりもうまくなってほしかったのだろう。父の目はト音記号だった。
そうしたことを思い出しながら、ワインを何杯か飲んでいたわりにはかなりうまくト長調のメヌエットを弾いていると、何かがのどにつかえたような感覚があった。手は鍵盤を叩いていたから、口に手を当てはせずに横を向き、咳をして、何かを吐き出した。そのとき気を失ったのだと思うけれど、目を覚ました記憶はない。どうしても、少しばかり空白の時間帯がある。あとで台所にいたことは覚えている。紅茶を淹れていたことも。
その翌日、ピアノのなかでひっかくような音がしていたから、またネズミが出たのだと思った。蓋を開けてモップの柄で追い出すのは嫌だった。パニックを起こしたネズミがカーペットを走り回って、私まで恐怖に陥るのはごめんだった。
そのピアノは古いアップライトで、元夫のラリーが、大学を出てすぐに、ソファを買うより先に中古で買った安物のヤマハだった。まあ、まだ「元」ではなくて、元夫になりかけているわけだけれど。元夫になる道なかばという感じだ。私は考えた。ネズミに内部を食い荒らされたとしても、この世の終わりではない。もっといいピアノに買い換えるきっかけにはなる。
ひっかく音は一週間近く続いて、鍵盤を叩くたびに、何かがこそこそ動いて弦に当たるのがわかった。私は弾くのをやめた。ある朝、小さなガラスのテーブルで朝ごはんを食べていて、これから内覧で案内するマンションの書類を揃えていたら、ピアノの蓋が持ち上がった。私は大声で叫ぶようなタイプではない。戦うか逃げるかとなれば、第三の道、固まることを選んでしまう。座ったまま凍りついていると、小さなトロールとしか言いようのないものが出てきた。高さ三十センチくらいで、動きは素早かったから、服も髪もよく見えなかった。ソファの側面に勢いよくぶつかってから部屋の中央に駆け出て、どんどん小さくなっていく円を描いて走り回った。私は書類を盾のようにして脚の前に持って、その生き物を掃除機用のクローゼットに追い込んでから扉を閉めた。ただの幻覚だろうとしか思えなかったから、頭から締め出そうとした。なにしろ、あと二十分もすればタクシーをつかまえて街の反対側に行き、エレベーターなしで廊下が傾いた建物に八十万ドルを投資すべき理由をリンドクイスト夫妻に説明しなければならない。仕事にいかなくちゃ、あと二回へまをしたらクビなのよ、と自分に言い聞かせた。とにかく部屋から出ていく言い訳がほしかったのかもしれない。
「きれいな建物ですよ」と私はリンドクイスト夫妻に言った。「建てたときのままです。それに、本当に地面に近いんです! 大地を感じさせるくらいです!」でも、リンドクイスト夫人はピンク色の爪でマントルピースをこつこつ叩いて、ここは自分たちの場所だという感じがしないと言った。家に戻って、何もいない掃除機入れを見ればすべてが上向くはずだと私は思った。あのときは脱水症状だった、アルコールとコーヒーばかり飲んでいてはだめだ、と自分を戒めた。ところが、帰ってみると珍客はすっかり大きくなっていて、私よりひと回り小さいくらいになっていた。彼は自分でクローゼットから出て、ソファで眠っていた。
彼が誰なのか、最初はまったくわからなかった。古風な服だったけれど、私は服飾史には明るくない。わかるのは古くて汚れたヨーロッパ風の服だということ、カフスのところにはレースがありすぎて私の好みではないことくらいだった。彼は絵とは違ってかつらはかぶっていなかった。ぼさぼさで、赤っぽくて、脂ぎった髪だった。私が三十分ほどじっと見ていると、彼はむくりと起き上がってピアノに歩いていき、おもむろに弾き始めた。最初は手慣らしに音階だけを鳴らしているようだった。それからやおら弾き出し、高校のときに私を散々いらつかせたインヴェンションを二曲披露した。もしやと思って、インターネットでバッハを検索してみたら、どう見ても本人だった。あの肉付きのいい頬、太い眉毛と寝不足の重々しい隈に挟まれた黒い目。
偉人の前ではきちんとした身なりをすべきだろうと思い、私は毎日、家から出るときも、タクシーで帰宅するときも、顔にしっかり化粧をするようになった。薬局でカミソリのセットを買って、また脚のムダ毛を剃るようになった。アパートメントの片付けもした。冷蔵庫にラリーが残したチリソースのジップロックを処分して、遅ればせながら洗面台の上に電球を入れた。鏡にはっきり映る自分の顔にぎょっとした。まぶたの肌はだぶついていて、緑のアイシャドウは塊になっていたし、髪の根元は灰色になりかけていた。まだ三十八歳なのに。白髪であるべきはヨハンのほうだ。私はエステに予約を入れた。
ヨハンには石鹸とデオドラントの使い方を教えてあげた。先日、私が出かけているあいだに、彼はついに服を着替えた。今はラリーの灰色のフランネルシャツと古いコーデュロイのズボン姿になっている。ごくふつうの格好だから、ときどき、雑誌から目を上げると、ラリーがそこに座ってビールを飲んでいるのかと思ってしまう。
私が十歳のとき、父は「この作曲家を当てるまで車を降りちゃダメ」というゲームを始めた。ドライブのときにずっとカセットケースを隠しておいて、車を止めて私を降ろすとなったときに問題を出してくるのだ。私は何ブロックも、父の話は無視して、正解を言えるように集中していた。兄は有名な作曲家を覚えた順にまくし立てるという手を使った。その呪文は、「ラヴェルラフマニノフサンサーンスベートーベン」で始まり、「ブクステフーデショパンシェーンベルクバーンスタイン」で締めくくられた。私はもっと正攻法にして、少なくともおおまかな時代に当たりをつけてから候補を挙げるようにした。一度、正解がスメタナだったときは、ずっと車で座って考えていたから、水泳教室に三十分遅刻してしまったこともある。父がいれば、すぐにバッハだと当てた私を誇らしく思ってくれただろう。
当然ながら、ヨハンは作曲家当てにはかなり強い。新しいCDをかけるたびに、私は大きな声ではっきり名前を言って、彼はそれを繰り返す。シュー、ベルト。CDのカバーを彼が読めるのかどうか、もっとゴチックな書体に慣れているのかどうかはわからない。
彼は英語を覚えてきている。偉大な天才なのだし、耳もいいわけだから、さして意外ではない。このあいだ、オープンハウスから帰ってきたら、彼は部屋のあちこちを指して、「テーブル」とか「CDプレーヤー」といった名前を言い出した。私から学んだのだろう。私は赤ちゃんか犬でも相手にするように、しじゅう喋っている。「さあ、あなたのコーヒーに牛乳を入れるわね。ほーら、これでおいしくなる」なんて調子で。
次の日の朝、エレベーターから出ていくところで管理人が呼び止めてきた。笑顔を浮かべた彼女は大きく頷きながら言った。「あなたのピアノの腕前ときたら! 演奏会みたいよ!」
「練習あるのみですから」と私は言った。扉を抜けて通りを歩いていく私を後押ししたのは、自分の頭が狂ってはいないのだという安心感と、部屋には実際に人がいて、ぱっといなくなりはしないのだという焦燥感だった。そんなわけで、精神分析医に電話するわけにはいかないし、ほかの誰かに電話するのも無理だ。狂っていると思われるだけだろう。ゴーストバスターズがほんとうにいてくれたら、と思ってしまう。
その夜、私はヨハンにいろいろと打ち明け話を始めた。精神分析医に相談できないのなら、彼に代役をしてもらおうと思ってのことだった。精神分析医なんて、どうせ座って話を聞いているだけだ。そこで、私は鶏肉とローズマリーのクリームソース煮込みというとっておきの料理を作り、ドイツ産のワインを開けた。「ねえヨハン」と言った。「あなたって二十人くらい子どもがいたわけよね。赤ちゃんが」私が腕を左右に揺らすと、彼は微笑んだ。「嫌な話をしたいわけじゃないの。だって、半分くらいは亡くなってしまったものね。死んじゃったでしょう?」彼はよくわからないという顔だけれど、まあいい。「そのころの人たちは、仕方がないと思って人生を進んでいったのよね。ふつうのことだったから、人生が止まってしまうほどの大打撃じゃなかった。どうして私がこんな目に? とか、どうして神さまは私が嫌いなの? なんて泣き叫んで回ったりはしなかった。私はいつもそんな感じだったの。つまり、去年のことだけれど、私たちの街は攻撃された。城をふたつ壊されたって言えばいいかしら」私は両腕をばかみたいに使って、それを示そうとした。「それでみんな怯えてしまって、食べることも寝ることもできなくなっている。当然よね。でも、ラリーは知り合いを亡くしたわけでもないのに世界観が揺らいでしまって、信仰に確信が持てなくなっている。私は言ってるのよ。じゃあ、あなたのぼんやりしてさぼり気味な、聖公会の神への信仰は、あのビルが建っていることを支えにしていたわけ? 何も悪いことは起きないのが支えだったの? 彼ったら、それまでは世界に悪が存在するなんて気づきもしなかったようなのよ。そんな人の服を、あなたは着ているわけ。服。そしたらラリーが何て言ったと思う? ビルが攻撃されたときよりも去年流産したときのほうが君は落ち込んでいた、ですって。そうよ、そのとおりだけれど、それはホルモンの作用よ。ヨハン、あなたには化学物質がどう流れ込んでくるのかなんて信じられないでしょうね。あなたの奥さんたちは出産後に鬱になる暇もなかったわけでしょ? すぐに妊娠して、次の赤ちゃんを産んだわけだし」
彼は頷いて、パンにソースを吸わせてあくびをした。頷く仕草は私から学んだものなのか、昔のドイツにもあったものなのかはわからない。そのときの彼は、私が髪を切ってあげていたこともあって、いかにもアメリカ人らしく見えた。それに、電動歯ブラシの使い方を覚えてから、口臭もかなりましになった。私は彼に、青い縁の柄がついた歯ブラシのヘッドを渡した。私はピンク色を使った。それに、彼はそこまで歳をとっているわけではなくて、実はまだ四十歳くらいだった。もう一度インターネットで彼について調べて、人生の途中で彼をさらってしまったことで歴史が変わったりはしていないか確かめた。いまでも、彼は六十五歳で死んだらしいと出ていた。それ以外ではさしたる情報はなかったけれど、彼が最後までピアノを好きではなかったことはわかった。ピアノはすぐに廃れる楽器だと思っていたのだ。
要するに、ヨハンは不細工ではない。となると迷ってしまう。厳密に言えば、彼は妻子ある身だけれど、もっと厳密にいうなら、二人目の妻は三百年前に死んでいる。それに、いまの私が好きなときにデートに出かけて、彼を置いていけるかといえば、そうではない。誰かをここに連れてくるわけにもいかない。それから、明らかに彼は子だくさんの体質で、どの子どもも音楽の才能に恵まれているだろう。息子たちは実際に天才だったのだし、娘たちも、チャンスさえあれば、天才として名を残したかもしれない。そのせいでこんなことになったのだろうか。私がヨハンの娘を産んで、人生でしかるべき挑戦をしてあげられるように、こんなことが起きたのだろうか。
そうすると、十八世紀のドイツ人男性をどうやってその気にさせるかが問題だ。ナイトガウン姿で彼の前に座っても、いかがわしい女だと思われるだけだろう。
まず、ジャズへの手ほどきから入った。時代の順に、『アフリカン・リズム』のCDからディクシーランドに進み、ワインを二本空けて、コールマン・ホーキンスまで来たころには、彼は体を寄せてきて、何やらドイツ語でつぶやいていた。私は大して期待していなかった。『コスモポリタン』では毎月新しい体位が紹介されている。まるで、みんなピューリタンのように産めよ殖やせよでやってきたのが、最近になってようやく快楽に目が向くようになったかのように。でも、ヨハンは、やるべきことをちゃんと心得ている。
彼のいるところでは電話をしないようにしている。彼に話しかけていると勘違いさせてしまうからだ。私が笑えば、彼も笑うだろうし、私の前に立とうとするし、私が何かを訊ねていると思えば頷くだろう。
初めて夜を一緒に過ごした翌朝、タクシーに乗って、二日ぶりに携帯電話の電源を入れると、ラリーからの伝言が入っていた。「僕だよ」と彼は言った。彼が電話を片手に立っていて、簡易アパートの汚れた窓に背を向けている姿が目に浮かんだ。「僕の靴磨きはまだそっちにあるかな。玄関のクローゼットに。連絡してくれ」ラリーが靴を磨くなんてここ十年なかったことだから、デートの予定があるにちがいない。それとも、私にそう思わせたいのか。
彼は仕事中だろうから、家のほうに電話してみた。留守番電話に伝言を入れた。「私よ」と言った。「いまは水曜の朝。靴磨きを置いていったとしても、たぶんもうないわ。友だちがいろいろと物を持ってきたから、スペースが必要になったのよ。ジョンっていう人よ。真剣なお付き合いとかじゃないけど、しばらくはうちにいるから」
私が言い終えると、女性の録音音声が、メッセージを確認されますかと言ってきた。私は確認した。それから、メッセージを録音し直した。「私よ。返事が遅れてごめんなさい。靴磨きは見つからないわ。かなり古いやつでしょ? 新しいのを買えばいいと思う。ぴかぴかの靴を何に使うのか知らないけど、幸運を祈ってるから。それじゃ」
バックミラーに映る運転手の顔は微笑んでいた。もし英語がわかるのなら、私が情けをかけたことが気に入ったのだろう。
いまでは、ヨハンはジャズの虜になっている。とくにブルースの。もっと複雑な音、チャーリー・パーカーのファンにでもなるかと思いきや、不思議なものだ。まだ英語はひと握りの単語だけ、コーヒー、イート、パジャマ、ノー、くらいしか言えないのに、ブルースの歌詞は山ほど覚えてしまった。たいていの夜、食事が終わってアイスクリームを出す前に、彼は「ブラック・アンド・ブルー」なんかを、低く深刻そうなサッチモばりの声で歌い出す。
俺には楽しみもなきゃ
連れ合いもいナインだ
ネズミだって
家から出てイッヒまって
俺の人生はずっと
こんなにも
ブラックでブルーなのさ
ただし、彼は歌いながらにやにや笑っている。きっと自慢したいのだろう。
買ってあげたショパンの楽譜を彼が弾くと、もっとはきはきとしてロマン派色が弱まる感じで、本来とは違った響きになる。幻想的な音楽を、ショパンではなくハノンの指ならしの練習曲のようにさらりとリズミカルに弾きこなしてみせるその腕前は、何とも言えず素晴らしい。その音に、私はシャガールの絵を連想する。街の上空を漂っている人が何人かいる。屋根には牛が一頭いる。毛布のような空には、まばゆい星々が穴を開けている。私の街の夜はまさにそんな感じだ!私は画架を通りに持ち出して、飛んでいく隣人たちを描き、紫色の星明かりをしっかりつかまえようとする。平凡な、平凡な風景。ここにはロマン派めいたものはない。
ここにいるあいだに曲を書いておきたいかと思い、彼に五線譜紙を何枚か渡したけれど、彼はそれを見ると「ナイン、ナイン」と悲しげに首を振るだけだった。もしかすると、ここで作曲をして、天才がいたという足跡を残すのはルール違反なのかもしれない。精子は残せても、直筆の楽譜は残せないのかもしれない。
父はよく、私や兄に作曲させようとした。私たちを座らせて目を閉じさせては、頭からあらゆる音やイメージをきれいに消し去れば何かが湧き上がってくるはずだと言っていた。一度もそんなことはなかった。自分がずるをしていて、あれこれのイメージを濾しとれないせいなのかと思い、私は不安だった。頭が真っ白になりかけたそのときに、ゴリラやら飛行機やらクリスマスやらが浮かんできてしまった。どうすればいいのか、どうすれば座ってただ集中すれば曲ができるのか、ヨハンに訊きたかった。どうすれば音以外のものを頭から締め出していられるのか。世界の五万もの色、四階下で何かが焦げている匂いを。
彼がここにいる時間が長くなるにつれて、ドイツ語を覚えたほうがいいような気がしてくる。そうすれば、どうにか会話ができる。
最初にシャガールのことを私に教えてくれたのは、ブラームス風のあごひげを蓄えた芸術学の教授だった。講義中によくピアノを使っていた。芸術学部の建物の裏にある小さな劇場で集合すると、舞台にはスタインウェイのピアノがあり、教授は蓋を開ける鍵を手に入れていた。彼はプロジェクターのスクリーンからピアノに走っていき、「色は音みたいなものだ。合わさることでコードが生まれる」とよく言っていた。風変わりな教師を気取っていたのだろう。
「これは青と緑」と言って、彼はハ音とニ音を一緒に弾いた。「類似している。似た者同士だから、対立が生まれる。これは青と黄」三つ目の音。「次が青とオレンジ」四つ目。
また別の授業では、雲や女性の胸が描かれたロココ調のひどい絵を説明しようとしてピアノの前に走ったこともある。「フラゴナールの白はこんな感じだ」と言うと、繊細で甘ったるい高音を奏でた。
でも、教授がちゃんと理解したうえで話をしているのかどうか、私にはわからなかった。『ゲルニカ』を取り上げて、私たちが生きているあいだにアメリカ国内で戦争が起きることはありえないと言ったとき(切り刻まれた、色のない死体はない。虐殺された雄牛も、馬を貫く槍も、白い目で苦しむ人の姿もない)、私は彼の授業を取るのをやめた。頭がいいはずの人にしては衝撃的なくらい幼稚で、あまりに世間知らずな言葉だと思った。
それに、教授は色についても間違っていた。「色それ自体には意味はない」と、彼は二回目の授業で言った。「色は我々みなが、社会として、人類として共有する意味を持っている。わかるかな? 緑色は我々を自然に、生命に同調させてくれるから、落ち着いた気分になれる。青は空だから、我々は夢を見ているような軽やかさを感じるし、それは白も同じだ。黒は恐怖感だ。我々は三百万年も電気なしで生きていただろう? 暗闇を恐れるのには、ちゃんとしたわけがあるんだ。赤に、我々は血の色を見る。つまり、暴力やドラマ、興奮や情熱だ」最後の色に限っては、私は違うと思ったし、その気持ちはいまでも変わらない。男たちにとってはそれは正しいのかもしれない。でも、はるか昔から、女性にとって赤とは、今月は赤ちゃんができないということだ。良かれ悪しかれ、赤ん坊の不在という染みがはっきりとそこにあるということだ。
前に言ったことは嘘だった。彼とのセックスはあまりよくはなかった。期待値が低かったぶん、彼がちょっとでも知っていたことで盛り上がってしまった。実際にはかなりぎこちなく、型通りだった。私が二回ほど、現代社会ではいたって当たり前のことをしようとすると、彼は体を引いてしまい、顔をピンク色に染めて、何やらドイツ語でまくしたてた。
最後にしたあと、私は服を着直して、その日はもう彼を無視することにした。窓際に行ってカーテンを開けた。はっきりと考えていたわけではないけれど、心のどこかでは彼を怖がらせたかったのかもしれない。彼は眼下の車や建物のすべてに目をやり、どれくらい高いところに住んでいるのかを初めて知った。泣きはしなかったけれど、泣き出しそうな顔だった。窓の前にずっと立ったまま、体を震わせてぶつぶつ言っていた。それからカーテンを閉めてソファに走っていくときには、落ちてしまわないかと怖がっているように腰をかがめていた。意外にも、私が仕事に出かけているあいだ一度もカーテンを開けなかったのだ。天才にはもっと好奇心があるものだと思いきや、どうやら違ったらしい。
落ち着いてもらおうと、私は本棚から大きな音楽事典を取り出し、「バッハ」の項目にあるすべての写真や絵を見せた。彼の生家、ライプツィヒの教会、長男の肖像画。彼はひとつひとつを指して、あれやこれやと言っていた。その意味はわからなかったけれど、うれしそうだった。ページを戻して「ヴィヴァルディ」の項目に行き、何か冗談を言った。ずっとくすくす笑っているから、私もそれに合わせて笑った。
「そう、ヴィヴァルディ氏ね」と私は言った。「変な人よね」
事典を本棚に戻すと、私は近代美術館で買った小さなシャガールの本を出した。
「これよ」と言って、『バイオリン弾き』のページを開いた。「あなたがショパンを弾くときには、これが思い浮かぶ。この男は街の上空を漂いながら演奏しているでしょう? あなたの音も似ていて、足の下には何もないのに気がつきもしない感じ」
バッハは目を凝らしてその絵を見て、バイオリン弾きの顔を指した。「グリュン」と言った。
「そう、緑色ね。それをからかうつもりはないわ。あなただって、身長三十センチだったときはかなり変だった」
私は『誕生日』という作品までめくっていった。男の人が赤い絨毯の上に浮かんで、上から女性にキスしている絵だ。街角が見える窓と、小さな財布。男には腕がない。次のページは『赤を背景とした恋人たち』で、二人は赤色のなかで横たわり、二人とも赤で塗られて、その色のなかに溺れているけれど、上に描かれた広く青い水たまりが本物の水をたたえていることから、実際に溺れかけているわけではないことがわかる。そこでは、青い男が花束を投げ、魚か鳥が下に向かって跳ねている。
「これも愛を描いた絵」と私は言った。「愛よ」彼は自分の胸に片手を置いた。愛については前の週に教えてあった。「いま見た絵では、みんな愛する気持ちがあるから空に浮かぶことができる。あるいは屋根の上にいるバイオリン弾きだから。あるいは、ただ幸せだから」私は窓の外を指した。「だから、私たちはこんなに高いところにいられる。ありえないと思うでしょうけど、でもありえるの。地上二十七階よ!」私は指で十を二回と七を作った。「私たちが音楽を演奏していて、幸せだからよ」
彼は這いつくばり、カーペットに爪を食い込ませて窓のそばにもう一度行き、手を挙げると、カーテンの端を持ち上げた。私も一緒に、二十七階下で乗客を吐き出すバスを眺めた。すると彼は私を見て、私があげた腕時計を指した。デジタル式ではないからという理由でラリーが置いていった時計だ。
「この建物がいつまで重力に耐えられるのか知りたいの?」とはいえ、別のことが言いたいのかもしれない。いつまでここにいなければならないのか、自分が生きていた時代から何世代が経っていまに至るのか。いま、ドイツは何時なのか。
「タク、タク、タク」と彼は言った。
私は重力の質問に答えることにした。答えられるのはそれだけだった。「長い時間よ。とても長い時間。少なくとも、あなたがいるうちに崩れることはないから」
その午後を境に、ブルースを歌うときの彼の声は、ほんとうにブルースになった。
俺はみじめな男さ
人生なんて哀れ
心は引き裂かれ
なんだって生まれてきたんだ
俺が何をシュタットいうんだ
こんなにブラックでブルーなのは
もう窓の外を見はしないけれど、彼はもう知っている。サイレンの音が耳に入るたびにカーテンを見やる。私は知らぬが仏という立場だったことはないけれど、今回は、ひとりで対処しろというのは酷な話だ。去年の十月ごろ、もう悪いニュースを見ずにすむようにテレビを観るのはやめようとラリーは言った。それで彼にどんな効果があったのかはわからない。私には逆効果だった。私は言った。ニュースを見ないなら、街が燃えていないことがどうやってわかるの? 生き残っているのは私たちだけじゃないと、どうやってわかるのよ? ヨハンが来てからはテレビを切ったままにしているけれど、彼がバスルームに入ったときにはラジオをつける。馬鹿みたいなCMを聞くだけでも、少なくとも世間は平穏だとわかるからだ。家具店の甲高いCMソングは安全の音で、こう言ってくれている。まだ稼ぐべきお金があります。まだ買うべきものがあります。
彼は青白い顔色になってきているし、気のせいでなければ、体も小さくなっている。目元を見れば、目が顔深くに落ち窪んでいっているのがわかる。腕の肌はたるんできているようだ。ほとんどソファから離れなくなっているし、ようやく勇気を出してソファからバスルームに走っていくときは、脚を震わせ、両腕を広げて、いまにも床が崩れるのではないかと不安げな様子だ。ソファの肘掛けを引っかいて、ちぎってしまった。
昨日、彼が乗ってきてくれたらと思ってピアノを弾いてみた。ガーシュインの青い大判の楽譜を開いて、「霧深き日」を三回か四回間違えただけで弾けた。ちょっと錆びついているとはいえ、なかなかの腕だ。高校が終わるときには、芸術学校に願書を出したこともあった。テープを作って、オーディションにも行くつもりでいたとき、私は悟った。出された課題曲は何でも弾けるし、コンクールで優勝したことだって何度かあるとはいえ、有名曲となると必ずどこかでミスをしてしまう。「悲愴」全曲を完璧に弾いて、あと一小節でおしまいというところでほっと一息ついて、最後の和音をしくじってしまう。そんなわけで、私は財政学を専攻した。
「それがあなたなのかも」最後の二小節をしくじったあと、私はヨハンに言った。「抑圧された私の野望が、あなたになって出てきたのかも」しぼんだ口の彼が座って、ぎらついた目で、窓と私をかわるがわる見ている様子からすると、そんなことはなさそうだ。
彼はため息をついた。「俺の心は……真っ白さ」と歌った。
「ヨハン、あなたは外側も真っ白よ」ほんとうのことを言えば、最近の彼は少し色がくすんでいる。
彼のタク、タク、タクが残り少なくなってきているように思う。でも、検査薬を信じるなら、昨日から排卵が始まっているから、あと少しだけ頑張ってもらえればいい。今朝は二度セックスをした。今夜は精のつく夕食を買って帰ろう。
正午になると、私はソファにいる彼を残して扉に鍵をかけ、音がうるさいうえに遅いエレベーターで降りていき、リンドクイスト夫妻に十五軒目の、そして願わくば最後のアパートメントを見せるために出た。最後に見たときのヨハンはまったく元気そうではなく、顔は青白く、クッションに挟まれて体を小さく丸めていた。私が十八世紀のライプツィヒにいたとしたら、同じくらい怯えてしまうだろうか。それとも、現代の世界それ自体に恐ろしいものが潜んでいて、私たちは時間をかけて慣れてきたから対処できるだけだろうか。今日、私はこうも思う。ヨハンがしぼんでいっているのは、私の心のあの部分が甦ろうとしている徴なのだろうか。あるいは、私のなかで新しい命が始まろうとしている徴なのだろうか。
「お金を稼がなきゃいけないから」と、出ていくとき彼に言った。「ドイツマルクよ、わかるでしょ? あなただって、二十人も養う必要がなかったら、ドイツにあるオルガンの半分を訪ねて回って、日曜日もあくせく働くことはなかったでしょうよ。私だって、いろいろなことにお金が必要なの。ピアノのレッスンとか。赤ちゃんとか」
そう言って彼を残してきたわけだけれど、戻ったときにまだいたとしても、彼が夜を越すことはできず、朝になればふっと蒸発してしまっていても不思議ではない。そもそも、彼がずっとここにいるのは当てにしていなかった。彼に子育てをさせたくはない。父親がいないわけは楽に説明ができる。「それが、この子の父親はかなりの有名人なんです」と言えばいい。「子どもがいるとわかると、名声に傷がついてしまいますから。ほんとうですよ。ものすごく有名なんです」
でも、エレベーターを待っているとき、私は自分でも思いもよらないことをした。電話を取り出して、ラリーにかけた。彼が出ると、「何も言わずに聞いて」と私は言った。「みんなが私と違って、世界はぼろぼろにはならないはずだと思って生まれてくるのはいいことだわ。いまならわかる。あなたは足元に屋根もないまま上空でバイオリンを弾いていて、ある日、下を見てみたら、空でしっかり体を支えていられなくなって落ちてしまったのよね。ごめんなさい」
ラリーはしばらく黙っていて、そして口を開いた。「わかった」それから言った。「仕事が終わったら連絡するから」
もちろん、ふと頭をよぎる思いはあった。もし来週、いや再来週にでもラリーとよりを戻したら、赤ん坊が自分の子ではないとは彼には知るよしもないだろう。それに、彼の子どもではないと誰にわかるだろう。このところの私だって、何が現実なのかよくわかっていないのだから。
一階にゆっくりと降りていくあいだに、私はピンヒールの靴にはき替えて、百メートル下に沈んでいくうちに十センチ背が高くなった。口紅を塗って、リンドクイスト夫妻に家を売る態勢を整えた。インディアンたちも代価としてビーズを求めようとは思いもしなかった、街の空高くにある素敵な一角を売るのだ。こう言う練習をした。ご覧ください。この便利さ。堅固さ。何も突入してこなければ、あと千年は持ちます。きっと気に入っていただけます。
(了)
-

-
レベッカ・マカーイ/著
藤井 光/訳
2018/6/29
COUPLE OF LOVERS ON A RED BACKGROUND by Rebecca Makkai First published in Brilliant Corners, ©️2008 by Rebecca Makkai and subsequently in Music for Wartime, published by Viking, an imprint of Penguin Random House
Permissions granted by the author c/o The Marsh Agency, London, in conjunction with Aragi, Inc., New York through Tuttle-Mori Agency, Inc.,Tokyo
-

-
レベッカ・マカーイ
1978年生まれ。言語学者の両親のもとに生まれ、シカゴ近郊の村で育つ。父親はハンガリー出身、父方の祖母は著名な女優・小説家だった。ワシントン・アンド・リー大学およびミドルベリー大学大学院で学び、2011年に長篇The Borrowerでデビュー。2014年発表のThe Hundred-Year Houseは、シカゴ作家協会によって年間最優秀長篇小説賞に選ばれた。刊行は長篇が先行したが短篇の名手として知られ、2008年から4年連続でベスト・アメリカン・ショート・ストーリーズに作品が選出されている。『戦時の音楽』は待望の初短篇集となる。 ©︎Ryan Fowler
-

-
藤井光
1980年大阪生まれ。同志社大学准教授。訳書にテア・オブレヒト『タイガーズ・ワイフ』、セス・フリード『大いなる不満』、ダニエル・アラルコン『夜、僕らは輪になって歩く』等。著書に『ターミナルから荒れ地へ』等。2017年、アンソニー・ドーア著『すべての見えない光』で日本翻訳大賞受賞。
この記事をシェアする
「短篇小説を読む」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- レベッカ・マカーイ
-
1978年生まれ。言語学者の両親のもとに生まれ、シカゴ近郊の村で育つ。父親はハンガリー出身、父方の祖母は著名な女優・小説家だった。ワシントン・アンド・リー大学およびミドルベリー大学大学院で学び、2011年に長篇The Borrowerでデビュー。2014年発表のThe Hundred-Year Houseは、シカゴ作家協会によって年間最優秀長篇小説賞に選ばれた。刊行は長篇が先行したが短篇の名手として知られ、2008年から4年連続でベスト・アメリカン・ショート・ストーリーズに作品が選出されている。『戦時の音楽』は待望の初短篇集となる。 ©︎Ryan Fowler
-

- 藤井光
-
1980年大阪生まれ。同志社大学准教授。訳書にテア・オブレヒト『タイガーズ・ワイフ』、セス・フリード『大いなる不満』、ダニエル・アラルコン『夜、僕らは輪になって歩く』等。著書に『ターミナルから荒れ地へ』等。2017年、アンソニー・ドーア著『すべての見えない光』で日本翻訳大賞受賞。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら