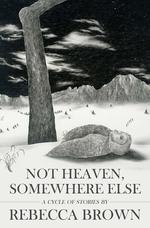(5)21世紀のおとぎばなし――レアード・ハント、レベッカ・ブラウン新作
In the House in the Dark of the Woods by Laird Hunt Not Heaven, Somewhere Else by Rebecca Brown
著者: 柴田元幸
アメリカ小説の文章上の特徴を考える上で、僕が勝手に「ヘミングウェイ指数」と呼んでいるものがある。その計算式は、ある文章がいくつの音節から成っているかを数え、それを単語数で割るのである。この「音節数÷単語数」の数値が低ければ低いほど、シンプルで具体的な単語が多く抽象的な語が少ないことになるわけで、「シンプルな言葉こそもっとも文学的である」という、マーク・トウェインが始動させヘミングウェイが純化させたアメリカ的伝統に則っていることになる。もちろんこれは、その作品の質を保証するものではまったくなく、ヘミングウェイ指数が低くても中身のない小説はいくらでもあり、逆に高くても素晴らしい小説もまたいくらでもある。あくまでも文章上の傾向を測る目安にすぎないが、アメリカ文学の一特徴を考えるためには、けっこう有効な――まあ少なくとも面白い――ツールである。
たとえば、「本家」ヘミングウェイの、いかにもヘミングウェイらしい短篇「清潔な、明かりの心地よい場所」(“A Clean, Well-Lighted Place”)の最初の100語を見てみると――
It was very late and everyone had left the café except an old man who sat in the shadow the leaves of the tree made against the electric light. In the day time the street was dusty, but at night the dew settled the dust and the old man liked to sit late because he was deaf and now at night it was quiet and he felt the difference. The two waiters inside the café knew that the old man was a little drunk, and while he was a good client they knew that if he became too drunk he [would leave without paying] ...
もう遅い時間でカフェの客はみんな帰ったあとだった。残っているのは電球の光が生む木の葉蔭に座っている老人だけだった。昼間は街も埃っぽかったが、日が暮れてからは夜露で埃も収まった。老人は遅くまで店にいるのが好きだった。彼は耳が聞こえず、夜になると静かで、その違いがわかったからだ。カフェの店内にいる二人のウェイターは、老人が少し酔っていて、いい客ではあるけれどあまり酔いすぎると金を払わずに帰ってしまうことを知っていたから……
冒頭のItとwasは1音節、ve-ryは2音節、lateとandは1音節、eve-ry-oneは3音節……という具合に“... too drunk he”までの100語の音節を足していくと、合計118音節。「ヘミングウェイ指数」は1.18ということになる。
これを同じくアメリカ・モダニズムの巨匠二人の代表作でやってみると、F・スコット・フィッツジェラルドの長篇『グレート・ギャッツビー』(The Great Gatsby)最初の100語の指数は1.43、ウィリアム・フォークナー『アブサロム、アブサロム!』は1.33。やっぱりフィッツジェラルドはコンラッドから影響を受けただけあって抽象度が高いですね。
さて、最近出たアメリカ小説2冊は、かねてからヘミングウェイ指数が低い作品を何作か書いてきた書き手による新作である。
まず、レアード・ハントのIn the House in the Dark of the Woods(森の闇の中の家)。この書き出し100語を見てみると――
I told my man I was off to pick berries and that he should watch our son for I would be gone some good while. So away I went with a basket. I walked and picked and ate and took off my shoes. I left them to sit by themselves and tromped my bare feet in the stream. Along I went straight down the watery road, singing and smiling under the sun. The water was fresh and clear and I went farther away from our home than ever I had before. It was nice in the field on the far [bank of the stream] ...
わたしは亭主に、ベリーを摘みにいく、息子を見ていてくれ、しばらくいなくなるからとつたえた。そうしてカゴを持って出かけた。歩いて、摘んで、食べて、靴を脱いだ。靴たちを残して、小川に入って裸足でのしのし進んでいった。水の道をまっすぐ下りながら、お日さまの下で歌をうたってニコニコわらった。水はきれいで澄んでいて、わたしは家から離れていった。こんなに離れたのははじめてだった。小川のむこう岸は野原もステキで……
これは100語で116音節、ヘミングウェイ指数は1.16。
そしてもうひとつ、レベッカ・ブラウンの短篇集Not Heaven, Somewhere Else(天国じゃなくて、どこか違うところ)冒頭に収められた1ページの小品“The Pigs”(豚たち)――
Once upon a time there were the pigs. They all lived in the same house not in three. That might have been better but might have not. It might have been nothing could help but who can tell.
There were two of them big and a little one, not a little girl visitor like Goldilocks, she lived there. She was the baby pig.
There wasn’t a wolf, there was only them, but they would do.
There was huffing and puffing and blowing down and huffing and puffing and blowing each other to smithereens. One day the house went up. Actually …
昔むかし豚たちがいました。豚たちはべつべつに三軒じゃなくて同じ一軒の家に暮らしていました。その方がよかったのかもしれないけどよくなかったかもしれません。何をやってもムダってことだったのかもしれないけどよくわかりません。
豚の二匹は大きくて一匹は小さかったけどゴルディロックスみたいにおさない訪問者とかじゃなくてそこに住んでいました。ちっちゃな赤んぼ豚でした。
オオカミはいなくて、豚たちだけでした。でもそれで足りるんです。
ふー、ぷー、吹きたおす、ふー、ぷー、三匹たがいに、みんなこっぱみじんになるまで吹きたおしあいました。ある日家が吹っとんでしまいました。ほんとは……
こちらは100語で119音節、ヘミングウェイ指数1.19。
というわけで、二人とも依然、内容はヘミングウェイからは限りなく遠くても、文章的にはヘミングウェイの末裔であることが数字的に見てとれる。そして今回は、どちらの作品にも「おとぎばなし」的な要素がかなりあり、シンプルな言葉が使われることがいっそう必然的に感じられる。レベッカ・ブラウンの方は、おとぎ話的であることが上の引用からも一目瞭然だろう。そしてレアード・ハントの方も、主人公の女性が森の奥へ迷いこんでいくなか、物語はどんどん幻想的・寓話的になっていく。進むにつれて、リアリティが付加されていくというよりは、むしろリアリティがじわじわ抜かれていくように感じられる。
これは、最近のレアード・ハント作品から見て、少し意外な気もする。2012年刊の『優しい鬼』(Kind One)は序章でまず「1830年」という年号が与えられ、本編に入ると「インディアナ」「ケンタッキー」と具体的地名が出てきたし、2014年刊の『ネバーホーム』(Neverhome)では南北戦争に妻が従軍し夫が家に残った、という史実に基づいた設定がはじめから明かされ、2017年に出た前作The Evening Road(未訳)では20世紀のインディアナの片田舎で、晩に行なわれるはずのリンチめざして人々が道を行く情景が程なく見えてくる。どの物語も、外の現実に参照枠があるわけで、読み手は現実の歴史をなんとなく頭のなかで参照しながら読み進めることになる。
ところが、今回のIn the House ... は、Eliza, Goody, それにGrandmother Someone(誰か祖母さん?)といった一握りの名前が出てくるだけで、地名などの固有名はすべて排除され、いつの時代の、どこの話なのか、何のとっかかりも与えられていない。森で道に迷ってしまった主人公が、まさに西も東もわからないまま、敵なのか味方なのか、邪悪なのか優しいのかもよくわからない存在に出会う。そのなかで、「書く」という行為に人物たちが激しく興奮したり(どうやらこの世界では書くことが禁じられているらしく、それはほとんど魔術的な営みとして捉えられている)、死体を継ぎ合わせて作ったとおぼしき舟に乗って空を飛んだりするといったエピソードが連ねられ、読み手は自分がいったいこれからどこへ連れていかれるのか、よくわからないままページをめくっていくことになる。はじめのうちは、いささかドライブに欠ける語りではないかと思えるが、じきにこれは、まさに読者を、主人公と同じく五里霧中のなかに置く最良の手段だということが見えてくる。
とはいえ、短篇ならともかく、このように長めの中篇(小ぶりの組みで214ページ)にあって最後まで五里霧中では、さすがにこっちの集中力が持たない。読者を信用して、ギリギリまで霧のなか状態に保った末に、作者ハントはじわじわ、この作品のテーマ、とまでは言えなくても関心の傾き具合、とは言えそうなものを前面に出していく。これについて短くまとめるのは難しいが(まとめてしまうべきでもないだろうし)、ひとつだけ、17世紀セーレムで起きた魔女裁判(および、それが無数の症状のひとつであるところの、女性が理不尽に抑圧される世のありよう)の語り直しという要素ははっきり見えてくる、ということは指摘していいだろう。これが見えてくると、Eliza, Goodyという名にも必然性が感じられてくる――魔女裁判で処刑された女性の一人Elizabeth Proctorをはじめ、魔女と名指された人たちはしばしばGoody(Goodwifeの略)と呼ばれたのである。作品全体としては、それらの「魔女たち」に独自の謎めいた声を与える形になっていて、過去においてその声があまり聴かれなかった人々の声を聴こうとする書き手レアード・ハントの姿勢は今回も貫かれている。
一方レベッカ・ブラウンの短篇集は、よく知られた童話の、より暗い、しばしば辛辣な語り直しがひとつの眼目である。上に挙げた三匹の子豚の語り直しは、狼のいない三匹の子豚の話であり、狼がいなければ平和かというと、いなければいないで三匹のなかで軋轢は勝手に生じ、三匹のうち二匹は焼け死に、“It smelled like a barbecue”(バーベキューみたいな臭いがした)といった黒いユーモアが展開される。“The Girl Who Cried a Wolf”(狼が来たと叫んだ女の子)では狼が本当に来て女の子は手も足も嚙まれているのに、狼なんていないよ、いい加減にしてくれないかなと人々に言われてしまう話。こうしてヘンゼルとグレーテルも、ハンプティ・ダンプティも、より陰惨、より暴力的に語り直される。レベッカ・ブラウン作品としてはいつも以上に「怒り」がストレートに出た一冊になっている。
が、最後の方になると、「怒り」が次第に後退し、「祈り」と言ってよさそうな要素も濃くなってくるように思える。たとえば、終わりから二番目の“Geppetto”(ゼペット)は、人間になんかなりたくない、命なんか欲しくないと言いつづけるピノキオを抱えた老人をめぐる悲しい話だが、その締めくくりの文章などは、レベッカ・ブラウンならではの美しさに貫かれている――
He slept more and more and dreamt more and more and said things asleep and awake to people who were not in the room. The old women couldn’t see them but they saw the old man’s eyes moving under his eyelids and heard him saying things they couldn’t hear to people they couldn’t see and they were glad for him.
He lay on his pillow happily, his son wiped his face with a cloth. His son, sometimes a young boy in a yellow hat, sometimes a full grown man, a kind and strong and loving man. Sometimes a boy, sometimes a man, but always a boy, a man, who loved his father, who held his father’s hand and wiped back his hair and petted his hair and touched his cheek and told him he loved him, he loved him forever and always would and always he was grateful, always living, always glad to be his son.
老人はますます眠るようになりますます夢を見るようになって、眠っていても目覚めていても部屋にいない人たちに向かっていろんなことを言うようになった。老いた女たちにはその人たちが見えなかったが、老人の目が瞼の下で動くのを見て、老人が彼女たちには聞こえないことを彼女たちには見えない人たちに向かって言うのを聞いて、老人のことを思って彼女たちは喜んだ。
老人は幸せに寝床に横たわり、息子が布で顔を拭いてくれた。息子は時に黄色い帽子をかぶった男の子で時にはもう立派な大人、優しくて逞しくて愛情深い大人だった。時には男の子、時には大人、でもいつでも父親を愛している男の子で大人で、父親の手を握って髪を拭ってくれて髪を撫でてくれて頰に触って、愛しているよ、いつまでも愛しているよ、これからもずっと、いつも感謝しているよ、いつも生きているよ、父さんの息子でいられていつも嬉しいよ、と父親に言うのだった。
最新情報
12月1日(土)、シンポジウム「古川日出男、最初の20年」に一発表者として出ます(明治大学中野キャンパス5階ホール、13:30-18:00)。12月5日(水)、江戸川区立葛西図書館で朗読&トーク「世界文学を愉しもう VOL.8」、テーマは「色」(19:00-20:30)。澤西祐典さんと共同で編集した『芥川龍之介選 英米怪異・幻想譚』(岩波書店、11月22日刊)の刊行記念イベントを12月17日(月)にブックファースト新宿店で(19:00-)。RADIO SWITCH(J-WAVE、土曜23:00-24:00)次の出演(朗読・雑談)は12月22日です。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら