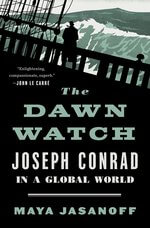(3)ジョゼフ・コンラッドはわれらの同時代人
The Dawn Watch: Joseph Conrad in a Global World by Maya Jasanoff
著者: 柴田元幸
過去の作家が、現代的なテーマを「先取り」していたというのは、どれだけすごいことなのか。
たとえばある作家が、テロリズムという現象をいち早く取り上げ、テロが生まれる背景や、テロに対する不安や猜疑を誰よりも早く描いているとしたら、その作家はどれほど偉いか。
あるいは、西洋による非西洋の植民地化が、おおむね「進歩」「文明化」という呼び方で肯定されていた時代に、植民地主義の悪を先駆けて見通していたら、どうか。
さらには、政治や戦争といった、人間の大きな営みを動かす原理が「理念」ではなく(「理念」がどこまで立派かはともかく)もっぱら「金」になっていく流れを、その始まりから感知していたら。
先取りは偉い、という考えにあまり組する気はないが、一人の作家が、これだけのことを全部やっていたとしたら、やはりその作家は意味ある形で先見の明があったとーーあるいは幸か不幸かそういう先見の明を持ってしまう文脈を生きたとーー認めざるをえないだろうと思う。
というわけで、誰もが言うことだろうが、「ジョゼフ・コンラッドはわれらの同時代人」。
もちろん僕にとっては、コンラッドはとにかく文章が素晴らしいので、上のことがひとつも当てはまらなくても全然構わないのだが、まあでも、上のことがひとつも当てはまらなかったら、もはやコンラッドはコンラッドでなくなるだろう。
“Joseph Conrad in a Global World”(グローバル世界のジョゼフ・コンラッド)と副題のついたThe Dawn Watch(夜明けの見張り)は、まさにコンラッドを、19世紀生まれの21世紀人として捉える本である。
著者マヤ・ジャサノフはハーヴァードの歴史学教授だが、学術用語はまったく使わず、歴史的文脈と伝記的事実を十分に押さえた上で、コンラッド作品の個人的読みもしなやかに盛り込み、歴史書でも伝記でも文芸批評でもない(というか、それらすべてである)本を書き上げた。冒頭で彼女は言う――
In this book I set out to explore Conrad’s world with the compass of a historian, the chart of a biographer, and the navigational sextant of a fiction reader. I tell his life story to link the histories of Europe, Asia, Africa, Latin America, and the oceans in between, and to consider what Conrad said about them in four of his best-known novels: The Secret Agent, Lord Jim, Heart of Darkness, and Nostromo.
(Prologue: “One of Us”)
この本で私は、歴史家の羅針盤と、伝記作者の海図と、小説読者の六分儀を携えてコンラッド世界の探検に乗り出す。彼の生涯を物語ることで、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、そしてそれらのあいだに広がる大洋の歴史をつなぎ合わせ、それらについてコンラッドが、その代表作四冊――『秘密諜報員』『ロード・ジム』『闇の奥』『ノストローモ』――のなかで述べたことを考察する。
(プロローグ「私たちの仲間」)
こうした姿勢でジャサノフが四作について丹念に論じていることを大まかに要約すると、だいたい次のようになる――
『秘密諜報員』(The Secret Agent, 1907)→ロンドンを舞台にテロリズム、スパイ活動、無政府主義を扱ったこの小説は、無政府主義者らの活動が社会不安を引き起こしていた当時の世相を反映し、ポーランドからの移民として彼自身も感じていた外国人に対する猜疑心も再現しているが、加えてコンラッドが愛読していたディケンズの諸作品(特に『荒涼館』)のエコーも随所に聞こえ、人間的・個人的要素が加味されている。
『ロード・ジム』(Lord Jim, 1900)→コンラッドは船乗りとして、帆船中心・イギリス中心の船舶業が蒸気船中心・アメリカ中心に変わっていく流れを体験し、そのなかで、(帝国主義のなかにも辛うじてあった、そしてイギリスの帆船においてもっともよく体現されていた)理想主義的な側面が薄れていくのを肌で感じた。『ロード・ジム』ではその理想が失われつつあることを単に嘆くのではなく、その理想を一度だけ裏切ってしまった人物に焦点を当てて複雑な物語に仕立てている。
『闇の奥』(Heart of Darkness, 1899)→コンゴを統治したベルギー王レオポルド2世の残虐な悪政に基づく話だが、コンラッド自身が1890年に蒸気船船長としてコンゴに赴いた体験も大きい。1899年初出当時、中央アフリカで為されている“the horror”(『闇の奥』でコンラッドが翻訳不可能なほど強い意味を込めて使っている言葉)の実態を知るヨーロッパ人はわずかだったし、ましてや西欧文明を善と捉える前提を疑う人はもっと少なかった。が、コンラッドがアフリカの闇の奥で見出したのは、アフリカの闇ではなく西洋の闇だった。『闇の奥』がテムズ川に始まりテムズ川に終わるのは、闇を光で包み込むためではない――
When the Thames reminded Marlow of the Congo, he wasn’t simply saying: Look, Africa is more primitive than England. He was saying that history is like a river. You can go up or you can go down. You can ride the current to get ahead, but the same force can push you back. By nesting Marlow’s experience in Africa inside the telling of his story in England, Conrad warned his readers against any complacent notion that savagery was as far from civilization as there was from here. What happened there and what happened here were fundamentally connected. Anyone could be savage. Everywhere could go dark.
(Ch. 9, “White Savages”)
テムズ川にいてマーロウがコンゴを思い出すとき、彼は単に「ね、アフリカはイギリスより原始的だろう?」と言っているのではない。歴史は川に似ていると言っているのだ。川は上ることも下ることもできる。流れに乗って先へ進めもするが、同じ力に押し戻されたりもする。マーロウのアフリカ探検を、イギリスで自分の物語を語る営みのなかに組み込むことによって、コンラッドは読者が「野蛮は文明から遠く隔たっていて、あそこ〔アフリカ〕とここ〔イギリス〕も遠く隔たっている」といった自己満足に陥らぬよう警告したのだ。あそこで起きることと、ここで起きることは根本的につながっている。闇はどこでも生じうるのだ。
(第9章「白い蛮人たち」)
『ノストローモ』(Nostromo, 1904)→コロンビアを思わせる架空の国コスタグアナを舞台とする、ラテンアメリカ文学に半世紀以上先駆けて書かれたラテンアメリカ文学とも称すべき作品だが〔これに対する現代ラテンアメリカ作家の「返答」が、コンラッド伝も書いているコロンビアの作家フアン・ガブリエル・バスケスの秀作『コスタグアナ秘史』(2007)〕、コンラッドはラテンアメリカに行ったことはなかった。見たこともない土地について書いたこの小説が、ほかの作品に劣らぬ迫真性を獲得したのは、中南米に住んだ友人から詳しく話を聞き、中南米各国の独裁や革命に関する資料を膨大に読みあさったことも重要だが、それ以上に、それまでの人生でコンラッドがずっと感じてきた、「利益」「金」がすべてになっていく流れをそのなかに盛り込んだことが大きい。
Nostromo wasn’t just Conrad’s only novel about a place he’d never been. It was a novel about every place he’d been. It exuded the political cynicism of the Pole who’d seen his parents wrecked by unattainable nationalist ideals. It projected the nostalgia of the man of sail who saw the craft he admired displaced by industrial technology. It trembled with the shock and revulsion of the white European who saw values of “civilization” and “progress” turned into weapons of mass destruction in Africa and beyond.
(Ch. 11, “Material Interests”)
『ノストローモ』はコンラッドで唯一、自分が行ったことのない場所について書いた小説というだけではなかった。それは彼がいままでに行ったすべての場所についての小説だった。達成不可能な愛国主義的理想によって両親が破滅するのを見てきたポーランド人の政治的悲観がそこには滲み出ている。自分が尊ぶ技能が産業テクノロジーに取って代わられるのを見た「帆船の人」のノスタルジーがそこには映し出されている。「文明」と「進歩」の価値観がアフリカで――そしてその彼方で――大量殺戮の武器に変換されるのを目のあたりにした白人ヨーロッパ人の動揺と嫌悪がそこには息づいているのだ。
(第11章「物質的利益」)
そうした小説のタイトルにコンラッドは、イタリア系の船乗りで、いまひとつ捉えどころのない、コスタグアナの資本家たちのなかに混じって結局はよそ者でありつづける人物ノストローモの名を据えた(そのことで刊行当時は批判もされた)。そして結局のところ、ジャサノフもはしばしで匂わせているとおり、コンラッドがもっとも大きな意味で「未来を予見した」と言えるのは、彼自身が「よそ者」であり(ヴァージニア・ウルフはコンラッドが死んだとき、彼を“our guest”〔私たちのお客〕と呼び、その英語の強い訛りに上から目線で言及した、何度読んでも不快な文章を書いている)、作品でも「よそ者」に目を向けつづけて、その不安、寄る辺なさを描きつづけたという点においてではないだろうか。
そう考えると、特異な絵本作家エドワード・ゴーリーが、ブックデザイナー時代に自分で絵を描いて作ったコンラッド作品の表紙は、そうした「よそ者」の心細さを実に巧みに表わしている。さすがはゴーリー。

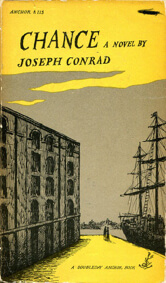
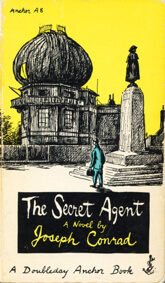
2017年にはコンラッドに関する興味深い本がもう一冊出た。コンラッド文学を踏まえて書かれた小説(一部エッセイ)を集めたアンソロジーConradologyである。
たとえば“Conrad Street”というように、はっきりタイトルにコンラッドが出ている短篇(ちなみにこれは、疫病でいったんはイギリスへ逃れたポーランド人が無秩序化したワルシャワに戻るという、おそらくはコンラッドが晩年にポーランドに帰ったときの違和感を踏まえた作品)を別とすれば、単独で読んだらコンラッドへのオマージュとはわからないと思える作品も多いが、まあそれだけコンラッドがいろんな形で読まれうることの証しでもあるだろう。そのなかで印象に残った作品を挙げるとーー
Zoe Gilbert, “The Inn of the Two Witches: A Find”(魔女二人組亭――掘出し物)→金に困ったコンラッドの未亡人ジェシーが唯一手元に残った夫の手書き原稿を売ろうとする話。原稿の中身は、コンラッドが晩年に金目当てで書いた通俗的短篇“The Inn of the Two Witches”〔これは現実どおり〕。これにOuija Board〔西洋版こっくりさん〕を使ってコンラッドの霊と交信する話が組み合わさり、全体が宿屋の無学な女将が書き殴った文章という体裁になっていて、そのへんの通俗性も「元ネタ」どおり。
Agnieszka Dale, “Legoland”(レゴランド)→「普通の」人間とレゴ人間がいる、「普通」の人間にとっていまひとつ居心地が悪そうなイギリス。どうやらレゴ人間が「生粋」のイギリス人を、普通の人間は移民を体現しているらしく、前者の方が明らかに地位が高い。ここで語られている、「よそ者」としてイギリスに生きることの息苦しさはコンラッドにも大いに通じる。
Jacek Dukaj, “Live Me”(私を生きて; translated from the Polish by Sean Gasper Bye)→『闇の奥』はアフリカの奥地で文明の闇を見てしまった男カーツがまずいて、雇われ船長として現地に赴いたマーロウが言語と想像力を介してカーツの生を生き、そのマーロウの語りを通して語り手がマーロウの生を生き、その語り手の語りを読むことを通して読者が語り手の生を生きることになる小説だが、「他人の生を生きる」ということがテクノロジーの発達によってますます文字どおりの意味で真実になりつつある現在、小説といういわば古典的バーチャルリアリティはどこまで現在のVRと同じであり違うのか。そうした問題を『闇の奥』を通して考察したエッセイ。著者はポーランドの代表的なSF作家である。バーチャルリアリティを考える上でもコンラッドが有効なモデルになるというところが面白かった。
全体として楽しめるアンソロジーだったが、ひとつ無い物ねだりを承知で言えば、一人ぐらいはコンラッドの文体模写をやってくれたらと思った。スコット・フィッツジェラルドにも影響を与えた、あの複雑な、錯綜した文章を真似たら、単純に楽しいと思うのである。
そういえば2016年に出たMarlow’s Landingという風変わりな小説は、象牙を求めた『闇の奥』のカーツの代わりに、ダイヤモンドを求めるゴールドヘイヴンなる男を主人公とした、明らかにコンラッド作品へのオマージュなのだが、文体はコンラッドとは正反対の短くスピーディなセンテンスの連続である。たとえば書き出しは――
Call this a river.
Nothing stirs, nothing lurks beneath its dead grey surface. The tourist barges plod up and down: the Vice-Admiral Golubtsov; the Academician Berdichevsky.
Goldhaven knows about rivers. Real rivers, rivers that gurgle and gush and kill. Rivers bearing riches. Rivers that will snap at you, rivers with things stuck in their murky alluvium.
これを川と呼べ。
何も動かない。その死んだ灰色の表面の下には何も潜んでいない。遊覧客船がのろのろ進んでいく――ゴルブツォフ中将号、ベルディチェフスキー学士院会員号。
ゴールドヘイヴンは川を知っている。本物の川、ゴボゴボ鳴って噴出して殺す川。富を産む川。嚙みつく川、どんより暗い沖積土にいろんな物が引っかかった川。
ところが、こうしたほとんどハードボイルドのパロディのような文体に、真ん中あたりで、一度だけコンラッドばりの文体が忍び込むーー
The river glistens in the moonlight, wending its way through forests and soggy meadows, past the ghosts of bare-bosomed maidens shivering in crumbling towers, weary dragons perched high up on their crags, cobwebs blowing in the frosty night. It rolls slowly down to the sea, carrying sediment and broken wardrobes, worn-out tyres, and now and then, a corpse. It’s swallowed its share of bodies over the years. If the beemer went over the edge, it would nose-dive into the black water and burrow into the soft sand, its backend sticking out like some monstrous gastropod.
川は月光を浴びて光り、幾つもの森や水浸しの草地の間を進んで、崩れかけた塔の中で震える胸もあらわな乙女たちの幽霊、岩山のはるかてっぺんにとまった疲れた竜たち、凍てつく夜に揺れる蜘蛛の巣のかたわらを過ぎていく。川はゆっくり流れて海へ向かい、堆積物、壊れた衣装ダンス、使い古しのタイヤ、そして時おりの死体を運んでゆく。長年の間に、この川もそれなりの数の死体を吞み込んできた。もしこのBMWが縁を越えてしまえば、黒い水の中へと転落し、川底の柔らかい砂に埋もれて、何か奇怪な腹足類のように後部が水面から突き出ることだろう。
本の袖に書かれた著者Tony Vieiraの紹介には“If it wasn’t for Marlow’s Landing, he would probably be spending his free time birdwatching and pursuing an unrequited passion for the works of Joseph Conrad”(もしこの本を書いていなかったら、空いた時間は、バードウォッチングと、ジョゼフ・コンラッドの作品への報われぬ情熱の追求に費やしているだろう)とある。この一節を書くのはさぞ楽しかったにちがいない。
最新情報
ポール・オースター『インヴィジブル』(新潮社)が刊行されました。10月12日(金)〜14日(日)、音楽家トウヤマタケオ、画家nakabanとともに香川・徳島・兵庫で音楽×幻燈×朗読のイベントをやります。詳しくはignitiongallery.tumblr.comを。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら