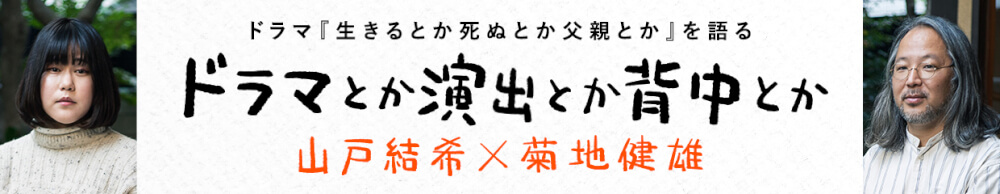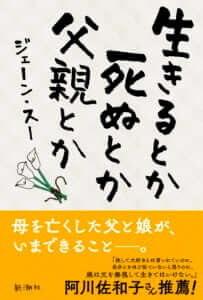2022年2月3日
前編 映画監督ふたり、テレビドラマを撮る
大きな反響を呼んだ、2021年4~6月放送のドラマ『生きるとか死ぬとか父親とか』(テレビ東京「ドラマ24」、現在はAmazonプライム・ビデオなどで配信中)。原作は、父と25年前に亡くなった母のことを綴ったジェーン・スーさんの同名エッセイ。ドラマの監督を務めた山戸結希さん(1、2、9~12話を担当)と菊地健雄さん(3~8話を担当)が、演出における試行錯誤を振り返りながら、あらためて作品の魅力を語ります。
(司会・構成:兵庫慎司)

ジェーン・スーを選んだ理由
──最初はテレビ東京の佐久間宣行プロデューサー(2021年春に同社を退社)が、山戸監督とドラマを作りたいということで、原作候補をたくさん持って来た中から、この作品を選ばれたんですよね。
山戸 はい、佐久間さんとの話し合いの中で、今回のエッセイが俎上に載せられました。単行本のカバーを見た瞬間に、「こんな美しいタイトル、見たことないな」と感じて。読む前から、何か屹立した気配がありました。その表紙は、ドラマの劇中でも何度も映されることになるのですが、最初に見つけたときの感動を、そのまま映像に冷凍保存したような思いです。
──読んでみていかがでしたか?
山戸 個人的なディテールが普遍的な領域にまで押し上げられている本で、ジェーン・スーさんの作家としての闘いが表れていると思いました。その闘いをこそ映像で表現したい、そのためには、当然ながら原作にはないトキコ(吉田羊演じるドラマの主人公。ラジオパーソナリティーにしてコラムニスト。原作者であるジェーン・スーがモデル)が、この本自体の原稿を書くシーンも映像化しなければいけないと考えました。
初めての共同作業
──各話の演出を担当するパートナーとして、菊地監督にオファーしたのは?
山戸 菊地さんのことを、映画作家として本当にすばらしい方だと心から尊敬しているからです。きっと、5年経てばとても手の届かないところに行ってしまわれそうだったので、今のうちに、という思いもありお願いをしました。2021年はずっと制作の現場に入られていて、日本で一番働いている映画監督と言い表して過言ではないので、タイミングをいただけて、幸運でした。
──それぞれの作風の違いや演出プランのすり合わせは、どのようにしていったのでしょうか?
菊地 テレビの連続ドラマは、複数の監督で演出することが多いですよね。ただ我々は映画出身なので、最初はどうすり合わせていけばいいのか手探りではありました。でも、この作品に限って言えば、山戸さんのやりたいことが、最初に台本を読んだだけではっきりと伝わってきたので、撮影に入る前には、その不安は解消できましたね。
当然山戸さんと僕でスタイルの違いはあるのですが、一緒にロケハンをして回ったり、脚本について話をしたり、撮影前の準備期間で徐々にすり合わせていった感じです。山戸さんにも「本当に自由にやってください」と言っていただいて。トキコや父の哲也(國村隼)のキャラクターの部分は、山戸さんが撮るものと齟齬がないように気をつけながらも、カット構成とか具体的な演出面に関しては、好きにやっていいんだと開き直った部分もありました。これまでの山戸さんの作品を観るたびに、決して自分では真似できないような、すごい高みにある監督だと、ある種畏敬の念を持っていましたので。
山戸 いえ、そんな……。
菊地 真似ができないならば、逆に開き直ろうと。自分は何ができるのか、それを考えてベストを尽くすことで、この作品を支えることができるかもしれない。そういった思いが段々と大きくなっていきましたね。
それに、台本以上に大きかったのが、山戸さんからいただいたメモの存在です。全12話の各話でどういったことを伝えていきたいかを、まとめられたメモがあって。それを読んで、自分が担当する話ではこういうことをやっていけばいいんだということを、はっきりつかんだ部分もありますし、自分なりに演出についてのアイデアも浮かびました。
──そのメモによって、かなりクリアになった部分があったのですね。
菊地 はい。僕が担当したのは3~8話で、山戸さんが担当されたのは1、2話と9~12話。最初に「どの話を選んでいただいても大丈夫です」とおっしゃってくださって、非常に迷ったのですが、スケジュールとの兼ね合いもあって、それぞれの担当する話が決まりました。
そのような経緯でしたが、結果的に山戸さんが担当されたのは、トキコと父親との関係性に焦点が当たった回で、「ファミリー・ヒストリー」がクローズアップされていくような話がメイン。一方で僕の担当した回は、ラジオの悩み相談のシーンから始まって、今社会で起こっているいろいろな問題――たとえば、男女の社会的な立場の違いだったり、独身女性が生きていく上での難しさだったり――を扱う回が多くなりました。そこは自分としてもやりやすかったというか、それぞれの作家性みたいなものがあるとしたら、僕自身はそこにうまくマッチできたかな、という感触はありました。
山戸 ドラマ制作における定石とは違うかたちになったとしても、もし菊地さんが「1話と最終話を撮りたい」とおっしゃったら、本当にお譲りするつもりでした。でも結果的に、菊地さんでなければ、決して他の誰にも表現されなかった話を撮ることになりましたよね。後付けの結果論かもしれませんが、そこに必然性が生じたのも、また確かなことだと思っています。

「演出」とは何をするのか
──今日は映画監督のお二人にお集まりいただいたので、この対談では監督の大きな仕事である「演出」について話をうかがいたいと思っています。そもそも「演出」と一口に言っても、たくさん仕事があるじゃないですか。
菊地 そうですね。
──「演出とはなんぞや?」と問われたとしたら……。
菊地 うーん……、一般の方に「演出って何ですか?」と聞かれた時に説明するのが非常に難しいんですよね。「何を映すか」を決めるのも演出ですし、逆に言うと「何を映さないか」を決めるのも演出だと思うので。僕は監督になるまで助監督を長年やっていて、40~50人の監督の姿を見てきました。彼らから学んできた部分もあるのですが、最終的には自分でスタイルを生み出すしかない、というのが、辿り着いた結論です。
監督ごとに演出のスタイルはそれぞれ違いますし、大げさに言うと、その監督の生きてきた人生そのものが色濃く反映されてしまう。それが演出だと思うんですね。例えば、山戸さんと僕が同じ言葉を役者さんに投げ掛けたとしても、受け取り方は当然違うはず、というのが前提なので。役者さんのお芝居を組み立てるのも演出ですし、カメラワークとカット割、美術や照明の設計、音響の構築、役者にどういう衣裳を着せ、ヘアメイクでどのようにキャクターを作っていくか、というのも、演出ですよね。
ただ難しいことに、我々監督というのは、具体的なことは何ひとつやっていないんですよ。映像を撮影するのはカメラマンだし、音を録るのは録音部さんだし、衣裳を選んで持ってきてくれるのは衣裳部さん。お芝居も、「よーい、スタート」と声を掛けた後は、もはや見守るしかない。ただただ息を詰めて、「何とかうまくいってくれ」という思いで見守るだけ。だから、実は何もしていないんです、現場では。
──それは意外な感じがします。
菊地 僕らがやることというのは、キャストやスタッフ、それぞれの仕事の成果を、ジャッジしてまとめていくということ。だとすると当然、山戸さんと僕ではそのポイントが違うわけで……。
──例えばどういうところですか?
菊地 今回ご一緒するまで、山戸さんのことをすごく感覚的な方なんじゃないかと思っていたんです。でもご一緒して、すべてにおいて論理がちゃんと通っていることがわかりました。そこはもう本当に尊敬しかないというか、畏怖と言ってもいいんですけれども。緻密に全部計算していて、ひとつひとつのショットにちゃんと必然性があるし、論理がある。一方で僕は論理的な人間だと思われがちなんですけど、山戸さんに比べたらすごく感覚的だな、と。それを鏡のように突きつけられたのが、このドラマの現場でしたね。
ただ逆に言うと、僕は余白というか、役者さんに対して自分の想像やプランを超えてくるようなものを欲しがってしまうところがあって。偶然性が欲しいというか、自分の頭の中にあるものを超えてきて欲しい。でも山戸さんは、ご自身の頭の中にしっかりしたイメージがある。現場で吉田羊さんもおっしゃっていたのですが、山戸さんの頭の中にあるものをそのまま再現できたら、アメリカのアカデミー賞も獲れるというぐらい。
山戸 (笑)
菊地 そのぐらい役者さんに対する要求も高いのですが、僕はその場で起こったこと、その瞬間を切り取りたい、という思いが強い。役者さんが僕の「こうして欲しい」に応えるのではなくて、自発的にポンと飛び越えられるような瞬間を、どうしたら作っていけるのか、ということを考えています。その点は、真逆なのかなと思いましたね。
そのことに気づけたのも大きな収穫でした。山戸さんと比較することで、自分の演出スタイルがはっきりしたというか。それがこの作品で得た最大の宝物です。この作品以前・以後で分かれるぐらい、自分の中でカチッと何かが変わるきっかけになりました。
山戸 菊地さんのフィルモグラフィーにおいて、あるひとつの定点になりうる場だったということが何よりも嬉しいです。
音には画を超える創造性がある
──菊地さんが求める、予期しないものを現場で生むことも大変だし、山戸さんの頭の中にあるビジョンを形にするのも大変ですよね。いずれにしても、俳優からすると非常にハードな現場だっただろうなあと。
菊地 確かに山戸さんの要求は厳しいかもしれませんが、そこを目指したくなる演出が準備段階から埋め込まれているんですよね。それを超えた時の達成感というのは、役者さんにしか味わえないものだし、ある種の快感と言ってもいい何かが、山戸さんの現場では絶えず生まれています。役者さんが苦しむ瞬間がないとは言えないのですが、そこを乗り越えた時の熱量をはっきりと画面に切り取るのもまた山戸さんなので。役者にとっても、他の監督の作品ではなかなか得られない、その人が画面に刻まれていく過程があると思っています。
山戸 演出について細部と俯瞰を横断するここまでの語り自体が、菊地さんの観察眼と世界を対象化する力を物語っているのだと思います。このように撮影の現場、つまりある種のカオスの場で起きていることを対象化し、再整理し、再構築して言語化できる作家ばかりではないはずです。たくさんの現場に思考しながら立ち会われてきた、菊地さんならではの特殊技能なのだと。
先ほど菊地さんが「自分は演出家として感覚的なタイプだということに気が付いた」とおっしゃいましたが、今回、たしかにそうかもしれないと思わされる場面がありました。映像を撮ろうとするときは、やはり画に意識が行くんですね。それは映画がサイレントから始まったこととも関係があると思うのですが、どうあっても画で語ることが思案される。その上で菊地さんは、「音には画を超える創造性がある」ということを気づかせてくれます。例えば4話中盤、銀座の居酒屋でのシーン。父の手が鳴らして見せる、あの鍵の音。
──ああ!
山戸 この場面は画も特殊で、普通のドラマにはない「リアリティ・ライン」を超えた表現です。でも、音の方がさらに強く遠く「リアリティ・ライン」を超えているんですよね。心の中でしか鳴らないはずの音が聞こえてくる。画の飛躍だけでも跳ねているところを、音においても最大限感覚を拡張しています。それによって、体温や触覚のように映像には映らないはずのものまで体感させられることになる。観る身体に心地の良いバグが起こる、あの感覚は至福です。
菊地 あのシーンは、自分でも印象に残っています。トキコと父が居酒屋でお母さんの話を始めるシーンですね。ワンカットで二人にカメラが寄っていく。その瞬間に照明が暗転。そこからカメラがスーッと引いていくと、それまでいた周りのお客さんたちは消えて、二人以外は誰もいない。突如二人だけの空間になる。このドラマにとって重要な「不在の母」、それに対する二人の関係性を視覚的にも表現したかったんです。
さらに、ご指摘のように音ですよね。バックグラウンドで聞こえていた周りの声や物音を途中でスーッと消して、現実には鳴っていない、存在しない鍵の音を足しました。ただ、それは僕らも日常的に体験することだと思うんです。例えば誰かと食事に行ったとして、最初は周りの話し声や雑音が気になるかもしれないけど、相手との話に集中すると、不思議と周囲のノイズが聞こえなくなる瞬間があるじゃないですか。そういった感覚をドラマなり映画の中で表現したいな、というのは、ずっとこだわっているので。
山戸 その意志が、さりげなくいつのまにか伝わってきて、魔法のような瞬間として胸に残っています。

菊地 山戸さんが担当した1話の冒頭でも、似たようなことを感じました。まずは、いろいろな人たちの「ラジオを聴く日常」を映像として断片的に見せてから、「相談にお答えします」というセリフで、初めてトキコの全体が映る。その後も、相談に答えているトキコの横顔を撮っているのですが、リスナーたちが同じ空間で彼女と向かい合っているように撮られていて、カットバックしていきます。確かにラジオを聴くという行為は、そういうことなんですよね。「今の話は、もしかしたら自分に向けられている言葉かもしれない」と感じるような瞬間、それがラジオというメディアの特性だと思うんです。それを見事に映像化されていた。
山戸 素敵な読みをありがとうございます。空間を超えたカットバックが、あたかもお互いの目が合っているかのように営まれることで、ラジオそのものの比喩になっているということですね。
ラジオといえば思い出されるのが、菊地さんが担当した3~8話は、全て最初と最後、ラジオシーンなんですよね。同じ空間、同じシチュエーション、そして限られた撮影時間のなか、誰もが反復を試みてしまうところで、菊地さんは、一度も同じ撮り方をされていないんです。毎回異なる場所にカメラを置き、それが時に動き、心の変化を表すためにカメラが移ろう……その必然が編集の中で説得されていく。もう職人芸の域ですね。鍛錬された菊地さんの作家的なものと職人的なものが、最高の形で掛け合わされた成果だな、と。
菊地 実際は不安でしたけどね。「どう撮れば画がもつかな」と。さすがに前日は、プロデューサーの平林さんに情緒不安定な電話をしました(笑)
山戸 1話分の2回を撮るだけでも、「この会話をどう映そうか?」と考える分量なのに、それを6話×2回ですものね。
菊地 ただ、実際にアナウンサーとしてラジオを経験していた田中みな実さん(役名は東七海)をキャスティングできたのは大きかったですね。それと、山戸さんが撮影した1話冒頭のラジオのシーン、そこでの吉田さんと田中さんのやりとりを見て、「これは大丈夫」だと安心しました。ですが同時に、その撮り方が想像を上回るものだったので、「ヤバい!」と思ったのも事実です。「これは自分の持っている力を全部ぶつけないと大変なことになるぞ」と。それで全部プランを考え直しましたね。
山戸 そんなふうには現場では全く見えなかったので、菊地さんにバトンをお渡しできる日は、心から安心しきっていました。

変わるものと変わらぬもの
──同じラジオのシーンで、田中みな実さんがデスクに置かれたアクリル板に映り込むシーンもありましたね。
菊地 はい。コロナ禍をどう扱うか、というのも、我々にとっては非常に大きなポイントでした。アクリル板に映り込むというのは、まさにコロナ禍でなければあり得なかったことなので。撮影は2021年1月から2月にかけて行われたのですが、設定としては、コロナ禍が思ったよりも早く収束した世の中、ということにしたんです。撮影当時はコロナ禍がどうなるかまだまだわからなくて、一番悩んだところなのですが、それが功を奏した部分というのもありました。アクリルというものが一枚あったことで、演出や撮り方の幅が広がったというのは、ありがたいことだったな、という気はしています。
山戸 現実のラジオブースにも置かれているアクリル板は、リアリティの補強だけではなく、表現のレイヤーにおいても活かされましたね。語り合う羊さんと田中さんがアクリル板に映り込むと、お互いに共鳴する心の鏡面化の効果にもなれば、自分の心の分裂とも撮れれば 、ラジオ空間でリスナーと親密に向かい合っていることの比喩表現にもなる。コロナ禍である現実との狭間に、発想の転換のようなかたちで、ポテンシャルが発揮されたと感じています。
菊地 銀座の街を撮るシーンでも、主演二人だけがマスクをしていない、という状況になりました。かといって、画からマスクをしている人を完全に排除するのは難しくて。
山戸 コロナ禍の街を撮るというのは、制約から逃れられない行為ですよね。一方で、銀座の背景を含めて代替する街は、当然東京にはありません。原作において描かれた銀座という街の重要性を考えると、それ以外の街では成り立たない。そうした板挟みのなかで映し出される4話の光景には、映像にまつわる根本的な情熱が映されているようでした。現実のありようと引き裂かれながら、それでもなおカメラを置くという選択が、その撮影自体の一回性として、記録としても記憶としても伝播するものがありました。

菊地 その第4話自体が、変わるものと変わらぬものをめぐる話なので、2021年2月の銀座という、その時期にしか撮れないものを画面に収めたと、ちょっとポジティブに考えられるかもしれない。
山戸 完全なドキュメンタリーが存在しないように、完全なフィクションもまた実写表現において本来的に存在し得ない。それをふまえて観るとき、「リアリティの破綻だろう」と容易に打ち捨てられないような、現実の重力とフィクションの浮力との闘いが克明に記録されていることに気付かされます。そのドキュメント(記録物)に胸打たれてしまうのは、自分自身、今を迷いながら生きる作り手であるとともに、今を考えながら生きる受け手のひとりでもあるからだと感じています。
そんなふうに、菊地さんの担当話の上がりを観るときには、同じドラマの監督を務めながらも、それぞれの演出は常に独立して行われていたからこそ、映された演出の特別さを発見してゆける、純粋な高揚がありました。

(後編に続く)
-
ジェーン・スー『生きるとか死ぬとか父親とか』
2021/03/01
公式HPはこちら。
-

-
山戸結希
映画監督。愛知県生まれ。2012年、『あの娘が海辺で踊ってる』でデビュー。2016年、『溺れるナイフ』(主演は小松菜奈&菅田将暉)が全国ロードショー。監督作品に、2019年公開の『21世紀の女の子』(企画・プロデュースも)、『ホットギミック ガールミーツボーイ』がある。RADWIMPS、乃木坂46らのミュージックビデオの映像監督や広告映像も手掛ける。今作『生きるとか死ぬとか父親とか』では、シリーズ構成と演出を担当している。
-
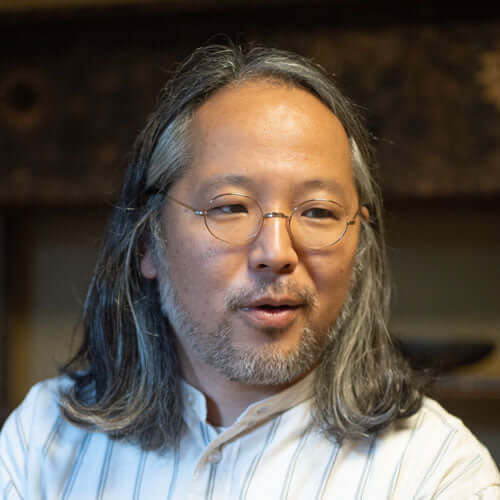
-
菊地健雄
映画監督。栃木県生まれ。大学を卒業後、映画美学校第5期高等科を修了。『ヘヴンズ ストーリー』(瀬々敬久監督)、『岸辺の旅』(黒沢清監督)、『舟を編む』(石井裕也監督)などの作品で助監督を務めた。2015年、『ディアーディアー』で長編映画監督デビュー。監督作品に、2017年公開の『ハローグッバイ』『望郷』、2018年公開の『体操しようよ』がある。最新作は、Amazon Prime Video『ショート・プログラム』とNetflixシリーズ『ヒヤマケンタロウの妊娠』が配信待機中。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 山戸結希
-
映画監督。愛知県生まれ。2012年、『あの娘が海辺で踊ってる』でデビュー。2016年、『溺れるナイフ』(主演は小松菜奈&菅田将暉)が全国ロードショー。監督作品に、2019年公開の『21世紀の女の子』(企画・プロデュースも)、『ホットギミック ガールミーツボーイ』がある。RADWIMPS、乃木坂46らのミュージックビデオの映像監督や広告映像も手掛ける。今作『生きるとか死ぬとか父親とか』では、シリーズ構成と演出を担当している。
-
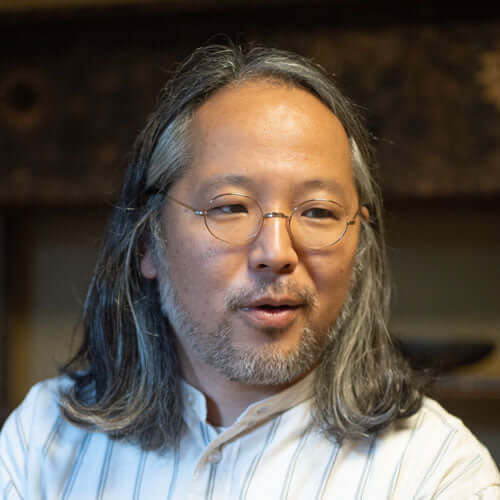
- 菊地健雄
-
映画監督。栃木県生まれ。大学を卒業後、映画美学校第5期高等科を修了。『ヘヴンズ ストーリー』(瀬々敬久監督)、『岸辺の旅』(黒沢清監督)、『舟を編む』(石井裕也監督)などの作品で助監督を務めた。2015年、『ディアーディアー』で長編映画監督デビュー。監督作品に、2017年公開の『ハローグッバイ』『望郷』、2018年公開の『体操しようよ』がある。最新作は、Amazon Prime Video『ショート・プログラム』とNetflixシリーズ『ヒヤマケンタロウの妊娠』が配信待機中。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら