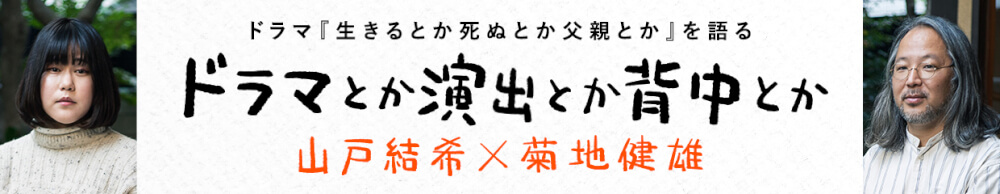2022年2月4日
後編 原作の「背中」を撮る
大きな反響を呼んだ、2021年4~6月放送のドラマ『生きるとか死ぬとか父親とか』(テレビ東京「ドラマ24」、現在はAmazonプライム・ビデオなどで配信中)。原作は、父と25年前に亡くなった母のことを綴ったジェーン・スーさんの同名エッセイ。ドラマの監督を務めた山戸結希さん(1、2、9~12話を担当)と菊地健雄さん(3~8話を担当)が、演出における試行錯誤を振り返りながら、あらためて作品の魅力を語ります。
(司会・構成:兵庫慎司)
(前回の記事へ)

想像力を倍音のように響かせて
──ドラマの後半になると、どんどん話がシリアスになっていきます。20代のトキコを松岡茉優さんが演じるパートです。父と母が同時に入院し、トキコはやむを得ず父の愛人に看病を頼む。そして母は……という後半ですが、ドラマを観た後に原作を読み返すと、ジェーン・スーさんはその部分を意外とサラッと書いているように感じました。ドラマの方が、トキコと父のしんどさを執拗に描いている気がして。
山戸 そのご指摘は、とても重要なものですね……自分の母がこの世界からいなくなってしまうということを、私自身は経験していません。そうしたことについて、(ジェーン・)スーさんはあのように原作で描かれた。(吉田)羊さんも初めてお会いした時、「私も母を4年前に亡くしていて」とお話しくださり、その時の表情も忘れられなくて。
誰しもの身に訪れることですよね。自分のお母さん、お父さんを亡くすというのは。私自身がそのことをもう経験していて、誰もが直面する普遍的な悲しみとして受け止められていたなら、もっと違う描き方になったかもしれません。若い日のトキコに起きたことも、現在のトキコの思いも、そして原作を描かれたスーさんの思いも、それを出会い頭に話してくださった羊さんの思いも、想像することでしか描けなかった。それゆえに、個人の悲しみに対して、想像力が倍音のように痛切に働いてしまう、ということが起きていたのかもしれません。
──エッセイをドラマの原作にする難しさも関係したのではないでしょうか? つまり、小説のような展開があるわけではないので、それをドラマにする場合はどこかでクライマックスを作らなければいけない、という。
山戸 原作を読んだ時に、どうしても想像されるのが、「スーさんはこの本をどんな思いで描かれたんだろう?」ということでした。原作は、読んだ人間にそういう思いを喚起させる書き手の魂というか、生きたものが宿っている文章でしたから。嘘のない文章だからこそ、この嘘のない悲しみというものがどんな思いで絞り出されたのか……その過程に興味が引っ張られてしまって。
それをはたしてどう映像にするか――それについては、まさに菊地さんが「何を撮って、何を撮らないかを決めるのが演出だ」とおっしゃいましたけれど、あるいはこの本において、「何が書かれていて、何が書かれていないか」という選択の結果の書であると言える。スーさんのその選択の背景にどういう思いがあったのか。書かれなかったものにこそ思いを馳せさせ、その映像が立ち上がってくる。映像を撮る人間にとって、そんな魔力を持ったエッセイだなと、あらためて思いますね。
菊地 確かに、エッセイをドラマにする難しさはありましたね。僕らが普段作っている、いわゆるドラマツルギーみたいなもの、冒頭に発端があって、中盤にヤマがあり、最後に落とすというような構成と比べると、もちろん難しい部分がないとは言えない。ただ今回の場合は、原作の中に誰もが共感できるようなドラマ性がある、というのは最初に感じていました。
──吉田羊さん演じるコラムニストが、「過去の辛い出来事を書く」そのこと自体をドラマでは描いていましたが、それも原作にはなかった部分です。
菊地 書くことの辛さを、ドラマで吉田さんがその肉体をもって演じることで、自分の体験を外に向けて表現していくことの苦難は、より描けたのかもしれません。
──その象徴が、二人のトキコの会話ですよね。20代のトキコを演じる松岡茉優さんと現在のトキコを演じる吉田羊さんが対話するシーンです。
菊地 過去と現在のトキコが、同じ空間で対話するというのは、もちろん現実的にはあり得ないことです。ただ、誰しもが自分の過去を振り返る時に、心や頭の中では行っていることだとは思うんですよね。ドラマはそれをビジュアル化できる。非常に伝わりやすい形で表象化した、山戸さんの英断というか。
忘れかけていた自分の思いを取り戻した時、過去の自分からのメッセージが来るという、ドラマの脚本構成上の山場にもなっている一方で、書くという行為に対する山戸さんの批評性が、見事にあのシーンに表現されていますよね。
さらには最終回のトキコが歌うところまで含めて、地上波のドラマではなかなか観られないシーンがたくさんあったと思います。それは、もともとスーさんの鋭い批評性がある原作だからこそだろうし、それを受け取った山戸さんの演出によって表現されたというのは、特筆すべき点なんじゃないかな、と。
関わった自分がこんなに褒めるのも気持ち悪いのですが(笑)。本当にそこは胸を張れますね。ご覧になっていない方がいたらぜひ観ていただきたいと思いますし、すでにご覧になった方も、また観直すと新たな発見があると思います。
山戸 心からありがたいです。的確なご指摘から見てくださる方へのメッセージまで……もうここで締めてもいいぐらいですね(笑)

エッセイをドラマにする難しさ
──先ほどの質問に戻ると、シリーズを構成する立場として、エッセイをドラマ化することならではの難しさというのはあったのですか?
山戸 脚本を立てる際の実務的なお話をすると、原作本から立ち上げてゆくとき、放送枠の12話分に満たなかったですね。なのでオリジナルエピソードを入れる必要性がありました。それとは別に、できあがっていた話分を先行して、スーさんとの話し合いの場も持っていました。スーさんから「ここはこう言うんじゃないか」など、台詞のアイデアまで出していただけるような、長時間の打ち合わせとなって。その時間は、その場で語られなかったことも含めて、作劇に影響を与えてくれました。何を話したのかそのものに留まらず、スーさんがどんなものを纏った方なのかを目の当たりにできたことによって、世界が広がって、全体を構成する上でのドライブになりました。
──現在の社会状況を強く反映させた部分も、原作と違うところでもありますよね。ラジオの相談のシーンが象徴的ですが。
菊地 原作にはラジオのシーンはあまり出てきませんが、ドラマでは大きな軸になっています。対談の前編で申し上げた山戸さんのメモに、なぜ各話の冒頭とラストにラジオのシーンが入るのかという理由も、明快に書いてありました。それにドラマ各話の前半と後半で、ラジオに寄せられた相談に対する答え方の質が変わっていくことも。前半は、これまでスーさんが生きてきた経験をもって悩みに答えるけれど、後半では自分自身がその相談と似たようなことを経験して、それによって答え方も変わってくるという。
山戸 構成的な意味で言うと、「外部と内部の往復」というものがとても大切で。ラジオの話をごっそり抜いても、この物語自体はシンプルに成立するのですが、ラジオの悩み相談という「外部」があることによって、「内部」にあたる登場人物たちの唯一無二性が輝く、というか。ラジオという広く社会と接点があるメディアに、極私的な体験をサンドしてゆく。この外部と内部の往復に、30分に濃縮された映像を観る喜びがある。今回のドラマのコアを強く届けるために、見る人の想像力を喚起させるそのジャンプが要請されたのだと思っています。

食事シーンを演出する醍醐味
──食事をするシーンも印象的でした。
山戸 食事は、まさに生きるとか死ぬとかに直結する、生死に関わる行為なので、中心に置きたくなってしまう、というのもありますよね。食事のシーンが出てくると、すごく気を張ってしまいます。これは、どう撮るか、どう伝えるかが問われているのだ、と。
──たとえば目玉焼きを作るシーンでも、二つの卵が微妙に離れていたり。それが父と娘の距離を表しているようにも感じました。
菊地 僕は映画学校を出ているのですが、脚本の授業で最初に教わるのは、「気持ちは書くな」ということなんです。気持ちは映像に映らない。映像というのはそもそも具体なので、キャラクターの悲しい気持ちだったり、嬉しい気持ちだったりを、映像としてどう描くか。それが脚本家の腕の見せどころ。もちろん演出家も同じで、そう教えられてきました。登場人物の内面を映すために、役者の表情で見せるのか、それとも目玉焼きのありようで見せるのか。そこは演出家として力が入るところなのかな、と思いますね。
食事にしても小道具にしても、当然それはお芝居にも影響してきます。お芝居というのは水もので、生身の人間がやることですから、ちょっとした一言や小道具でガラッと変わってきます。食事のシーンは、お芝居の枷にもなるんですよね。演技のどの瞬間に食事を口に運ぶのか、そのタイミングなど細かい部分をお芝居に落とし込むのは難しいのですが、同時に演出の喜びも、そこにあるというか。
山戸 お芝居というのは、基本的にはそのフリであり、嘘ということになります。怪我をして血が映されたとしても、それは血糊を使って、本当に出血したわけじゃない。性交渉のシーンがあっても、本当に性交渉をしているわけじゃない。寝顔が映されたとしても、本当に眠っているわけじゃない。作り手も受け手も、そのことを共通了解としながらドラマや映画を観ていますよね。しかし、食べるお芝居のときには、本当に食べている。お芝居であると同時、その身体においてはカメラの前で本当に起こっている。その真実性に裏打ちされるかたちで、演じる肉体にリアリティが担保されているとも言えます。
──確かにそうですね。芝居とはいえ、「食べている」のは本当のことですから。
山戸 「今、この人は本当に食べている」という営みの一回性によって、フィクションと現実とが逃れがたく重なってくる──食べるお芝居の演出に、思わず力が入るのは、そうしたリアルとの皮膜が表裏一体だからなのだと思います。

原作の「背中」を撮る
山戸 先ほど原作にない部分をドラマでどのように描くか、という話になりましたが、ひとつフレーミングするとしたら、このドラマは原作の「背中」を描こうとしていたのかなと思いました。エッセイはその人自身がまなざす光景を描くからこそ、筆者の背中が描かれることはない。私たち他者が映像化というかたちで介入することで、初めてその「背中」をドラマで描けるんですね。そうした起点から、このドラマの創作が始まっていたのではないかと。それで気づいたのですが、そのような抽象的議論もさることながら、端的にこのドラマは、人物の背中の画で終わるんです。
菊地 まさに! 山戸さんは、背中のショットを象徴的に使いますよね。1話のトキコは目のアップから入っていきますが、全身がわかる瞬間はバックショット。父の哲也も、叔母役の松金よね子さんも、バックショットから入っている。すごく背中が印象的なドラマと言えるかもしれない。
山戸 ドラマのラストは、原作のラストとは少し違うかたちですが、原作に触発されてこそだと考えています。最後に娘と別れた父が、地下鉄の階段を降りて行く、その描写に胸を突かれて。ちょっとその部分を朗読してもいいですか?
──もちろんです。
山戸 「日本橋で父の背中を見送りながら、私は母に話し掛ける。振り返らぬまま、軽く右手を挙げ父が地下鉄の階段を降りていった」
ここですね。原作の父と娘というのは、どんなに互いに思っていても、絶対的にわかり合えない領域があって、近づけば近づくほど、他者である境界にヒリヒリと触れてしまう。そんなかけがえのない怪我の傷跡であり、スーさんの人間的な格闘によって紡ぎ出された証言であり。この描写が、初めて読んだときから最終回を撮るまで、ずっと頭にありました。だから、最後まで背中のショットを選択し続けていたのかもしれません。
菊地 僕も台本を読み進めるにつれて、この話をどう終わらせるのかな、というのはずっと気になっていたところで。結果、山戸さんがあのような形で背中のショットを選択して終わったというのは……。でも、言われてみれば僕もラジオのシーンなどで、けっこう背中を撮っていますね。偶然か必然かわかりませんが、不思議ですね。

「もうひとつのリアリティ」をどう描くか
山戸 前編で「演出とはどういう仕事ですか?」という質問があり、菊地さんが明確にお答えになっていましたが、私もそれについて少しお話をしてもいいですか?
──もちろんです。
山戸 そもそも、「監督」と「演出」は違いますよね。監督するということについて、庵野秀明監督が「監督の仕事はただ一つで、『自分の判断でそうした』と覚悟を持つことなんだ」と印象的な発言をされていて、ふかく納得します。作品の責任を持つことは、役職としての監督の仕事。一方、演出というのは職能であり、行為です。行為としての演出、その総体を指して菊地さんは「何を撮って、何を撮らないかだ」と表現されたのかなと。
菊地 はい。そう言いましたね。
山戸 その見事な語りに耳をすましていたら、「演出とは何か?」についての考えを、すっかり述べ損ねてしまって……。今回の対談の要なのに(笑)
菊地 ぜひぜひ続けてください(笑)
山戸 例えば、怒っている人が、相手にコップの水をパッと掛けてしまうシーンだとします。それを、「怒っているから、思いっきりやっちゃおう」とするのか、「怒っていたとしても、実際の社会に生きている人はそんなことはできないのだから、抑えながらも思わずコップから溢れてしまった感じにしよう」とするのか、はたまた「いや現実では滅多に起こらないけれど、全力で水を投げ掛ける方が、このドラマでは筋が通っているんだ」とするのか。つまり、物語におけるリアリティ・ラインを、どの水準に設定するのかというのが、演出家が考えることなんだと。
現実に起こりそうなことだけを撮っていたら、フィクションのふくらみを放棄しかねない。時には思い切って、何のためらいもなく水を掛けたりするような、もう一つのリアルを、観客との共通認識として立ち上げることが演出の仕事なのではないかと思っています。
菊地 今の話を聞いて、黒沢清監督から助監督で付いたときに聞いたことを思い出しました。黒沢さんは、「映画のリアリティというのは、我々が現実に生きている世界のリアルと完全に大嘘なフィクション、その間にあるんじゃないか。そこの匙加減が監督の腕の見せどころなんだよ」とおっしゃっていました。山戸さんもおっしゃるように、そもそもお芝居というのは嘘なんだと。現実に存在していそうなキャラクターではあるけれども、台詞を与えられてそれを演じるということに、もう嘘が含まれている。それがすごく日常的な光景だったとしても、すでに現実のリアルからちょっと浮いたところにあって、それこそが映画のリアリティなんじゃないか、ということですよね。
もうひとつ、瀬々敬久監督から言われたことですごく心に残っている言葉が、「演出は監督業の一部でしかない。演出家と監督は違うんだ」というものです。無数の判断の積み重ねで作品が成立するわけですが、その作品そのものに責任を持つのが監督業で、演出というのは、その監督が持っている方法論であったり、具体的な手段であったり、その作品を作り上げる中での一貫した態度の表明の仕方なのかな、と。
山戸 はい、その通りだと思います。
菊地 だから難しいんですよね。監督としてどのように責任を持つかという部分と、具体的な演出をどうするかという部分を、割と一緒くたに考えてしまいがちなんですが、演出は監督としての仕事の一部に過ぎず、監督業というのは、それよりもっと大きい範囲の中で、責任を請け負ったり引き受けたりする態度なのかな、と。
山戸 くわえて演出に関して菊地さんは、「監督ひとりひとりが生きてきた道のりが違うので、演出スタイルも違ってくる」という表現をされていました。
菊地 はい。
山戸 それぞれの人生において、何を現実と捉えるのかというのは、本来であれば映画に限らない話ですよね。「真実」というものは一つではなく、各自にとっての「真実」がある。突き詰めるとそれは「信仰」「信条」の問題にまで行き着いてしまう。それはフェイクニュースが横行する現在の問題でもあって。この手の中にある水を「怒っているなら、人の目があったって水を掛けるでしょう」と思うのか、「社会の同調圧力の中で生きている日本人は、そういうことはしないよ」と判断するのか。そうした中で、この人の怒りを実感を伴って観客に伝えるにはどうしたらいいだろう、ということを考えるのが演出だと言える。ただ、あらゆる「現実」同士は、緊張関係に置かれている。作品にとっての現実と、作品が世に出てからあらゆる視点によって相対化される現実の差も当然あるわけです。届けたい現実と、届いてしまう現実との……。
菊地 差だったり、距離だったりね。
山戸 はい。その誤差をできるだけ予期し、責任を持つという意味において、演出と監督という領野が重なってくると言えるかもしれません。
このドラマの場合、主人公のモデルであるジェーン・スーさんは実在しています。著名な方であり、視聴者のみなさんがそのことも楽しみにしてくださって。つまり、見る人にとって、「このドラマは嘘なんだ」ということが、より実感しやすい前提がありました。
一旦話が変わりますが、普段の生活で、話し相手の顔を見るときに、テーブルに対面していたとしても、正確に真正面からその人の顔を把握しているわけではないですよね。すこし斜めから見ていたり。横並びの席であれば、もっと横顔になり、顔の全貌は見えない。でも、対面している時よりもお互いリラックスして気持ちを伝え合えたりします。さらに、家族として同じ部屋に一緒に暮らしたときには、お互いの背中を見る機会がもっと増えるはずです。顔そのものを把握していなくても、声、匂い、気配といったものから、その人の存在を感じている。見えなくても、そのとき家族がどんな表情をしているのかは、わかりますよね。それは、大切な人の「顔」を想像する力によって成立している。
そして、現実とフィクションの境目をどう越境するかについて、前提として嘘であると伝わっている本作だからこそ、背中を撮ることが求められていたのだと思います。見る人の想像力を、より切実に必要としていたのではないかと。私たちが常に想像によって「顔」を把握する、その現実に作動している認識を用いて、カメラが人物を捉える。想像力による共犯関係を切り結ぶことによって、背中を撮るショットは、ドラマ内の人物と、それを見つめる人とを繋ぎ止めようとしていた、と。

菊地 それが背中を撮る理由ですね。
山戸 今日、お話しするなかでそう思いました。撮影中は次から次へと……でしたが、こうして振り返ってみたら、選択の必然性が浮き彫りにされるものですね。
菊地 なるほど。普段は、撮り終わった作品のことをこうして詳しく振り返ることもないのですが、当時は気づかなかったことにも気づくことができて楽しかったです。山戸さんにも久しぶりにお会いできたし。
山戸 こちらこそ、菊地さんと素敵なドラマでご一緒できたことを嬉しく思います。監督として、より良い演出について考え続けてくださり、ありがとうございました。
(了)

-
ジェーン・スー『生きるとか死ぬとか父親とか』
2021/03/01
公式HPはこちら。
-

-
山戸結希
映画監督。愛知県生まれ。2012年、『あの娘が海辺で踊ってる』でデビュー。2016年、『溺れるナイフ』(主演は小松菜奈&菅田将暉)が全国ロードショー。監督作品に、2019年公開の『21世紀の女の子』(企画・プロデュースも)、『ホットギミック ガールミーツボーイ』がある。RADWIMPS、乃木坂46らのミュージックビデオの映像監督や広告映像も手掛ける。今作『生きるとか死ぬとか父親とか』では、シリーズ構成と演出を担当している。
-
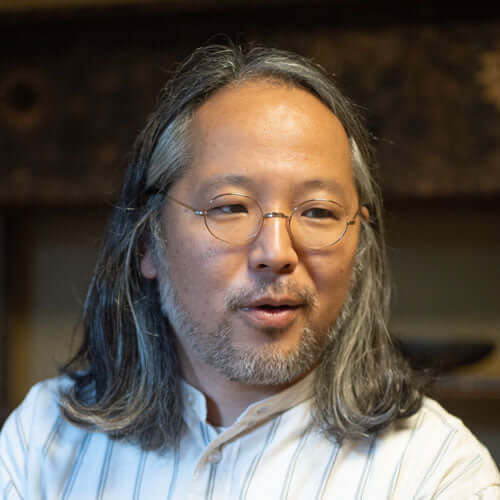
-
菊地健雄
映画監督。栃木県生まれ。大学を卒業後、映画美学校第5期高等科を修了。『ヘヴンズ ストーリー』(瀬々敬久監督)、『岸辺の旅』(黒沢清監督)、『舟を編む』(石井裕也監督)などの作品で助監督を務めた。2015年、『ディアーディアー』で長編映画監督デビュー。監督作品に、2017年公開の『ハローグッバイ』『望郷』、2018年公開の『体操しようよ』がある。最新作は、Amazon Prime Video『ショート・プログラム』とNetflixシリーズ『ヒヤマケンタロウの妊娠』が配信待機中。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 山戸結希
-
映画監督。愛知県生まれ。2012年、『あの娘が海辺で踊ってる』でデビュー。2016年、『溺れるナイフ』(主演は小松菜奈&菅田将暉)が全国ロードショー。監督作品に、2019年公開の『21世紀の女の子』(企画・プロデュースも)、『ホットギミック ガールミーツボーイ』がある。RADWIMPS、乃木坂46らのミュージックビデオの映像監督や広告映像も手掛ける。今作『生きるとか死ぬとか父親とか』では、シリーズ構成と演出を担当している。
-
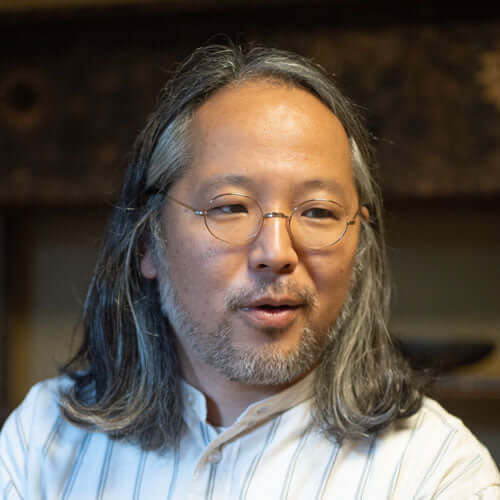
- 菊地健雄
-
映画監督。栃木県生まれ。大学を卒業後、映画美学校第5期高等科を修了。『ヘヴンズ ストーリー』(瀬々敬久監督)、『岸辺の旅』(黒沢清監督)、『舟を編む』(石井裕也監督)などの作品で助監督を務めた。2015年、『ディアーディアー』で長編映画監督デビュー。監督作品に、2017年公開の『ハローグッバイ』『望郷』、2018年公開の『体操しようよ』がある。最新作は、Amazon Prime Video『ショート・プログラム』とNetflixシリーズ『ヒヤマケンタロウの妊娠』が配信待機中。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら