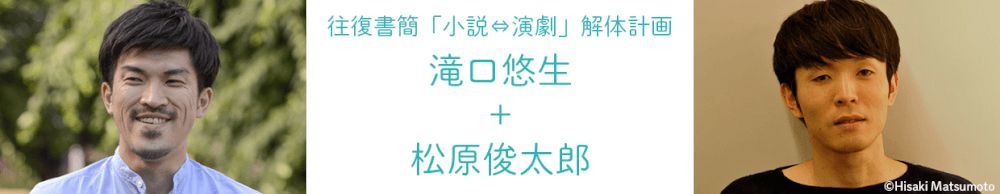【往復書簡・特別編】
[岸田賞受賞記念対談]松原俊太郎作品のここが面白い!
2018年7月から2019年3月まで、15回にわたって連載してきた「往復書簡『小説⇔演劇』解体計画」。小説と演劇、それぞれジャンルの枠組みを問い直し、二人の作家の創作の秘密に迫るような刺激的な対話でした。
連載終了直後に松原俊太郎さんが、新人劇作家の登竜門とされる岸田國士戯曲賞を受賞。受賞を機に、久しぶりに対面したお二人が、日本の演劇と戯曲の最前線について、そして再び創作の秘密について、往復書簡とはまた一味違ったキャッチボールを繰り広げます。

異例の受賞?
滝口 岸田國士賞受賞、おめでとうございます。岸田賞は「演劇界の芥川賞」って言われたりもしますよね。
松原 ありがとうございます。演劇界の芥川賞、たしかによく言われますね。
滝口 だとすると、芥川賞は「小説界の岸田賞」ってことですかね(笑)。松原さんの「山山」はどんな評価だったんでしょうか。
松原 かなり異例の受賞だったようだな、という印象です。選評にもそれが表れていたように思います。困惑しているようなものも多くて。
滝口 選評読ませていただきました。すごく面白かったです。「わからない」という評もちらほらありましたね。ケラリーノ・サンドロヴィッチさんとか。でもそれも含めて、率直で面白い。誰が何を評価したのかがよくわかりますね。宮沢章夫さんの評なんかはけっこう長くて驚きました。文学賞の選評とはだいぶ違いますね。
松原 そうですよね。文学賞の選評は文芸誌に載るからでしょうか。文字数も決まってるでしょうし。
滝口 芥川賞の選評とかはもっと長くても良いのになと思うんですけどね。柳美里さんの評を読むと、選考の流れがすごくよくわかりますよね。「あ、このままだとこの作品がとれないからこっちの支持に回ろう」みたいな様子も。
松原 候補作のうち、「山山」はポストドラマ派の作品ということになるようなんですよね。選考会ではドラマ派からも受賞作を出そうという動きがあったけれど、今回はドラマ派の「推し」が決められなかったということのようです。
滝口 今回の候補で言うとポストドラマ派が古川日出男さんと松原さんでしょうか。
松原 松村翔子さんもですね。
滝口 そのポストドラマ派というのは、演劇界ではもうわりと一般的に使われている用語なんですか。
松原 一般的とまでは言えないですね。戯曲が語られること自体があまりないですし。西洋発祥の言い方だと思います。ドイツとか。
滝口 そちらの演劇理論とか批評とかから来ているということですね。もう一方の「ドラマ派」については、どんなものをイメージしたらいいんでしょうか。
松原 近代劇、会話劇ですね。普通に会話が進行していく。
滝口 実験的ではないもの、大衆的なものというような感じ?
松原 たとえばテレビドラマは会話劇ですよね。登場人物が母なら、母が母の台詞を言って、会話で進んでいく。
滝口 配役とか会話とか、いろんな整合性が保たれていて、そこにズレとか齟齬みたいなものがない、物語として無理なく理解できるものというか。
松原 そうそう、無理のない物語。
滝口 そしてそこを意図的に壊しているとか、ずらしているようなものが、ポストドラマと言われるんですね。
松原 そうです。
滝口 たとえば平田オリザさんの「現代口語」というのもよく言及されますが、それともまた違うんですよね。
松原 現代口語というのは使われる言葉の形式というか、タイプみたいなことですよね。ポストドラマでもドラマでも使われうる。ポストドラマは、会話劇の構造をずらしていくような方法を取るものだと思います。
人の中にある言葉を全部書く
滝口 松原さんの戯曲で使われる言葉は、いわゆる現代口語ともまた違った、かなり独特なものですよね。その独特な言語感覚や、それによって松原さんが何をしようとしているのかを伺いたいんですね。ただ、往復書簡をしていても思ったけど、その説明って、するのも聞くのもかなり難しいと思うんです。なので逆に、松原さんは「何をしないか」を伺えますか。こういう言葉は使わない、とか。
松原 現代口語っていうのは、やっぱり「会話」に適した言葉だと思うんです。日常生活の実際の会話の中で、コミュニケーションが円滑になるような崩れ方をしているのが現代口語。だからそれをそのまま使うと、ナチュラルになってしまう。そのナチュラルさは使わないようにしています。
滝口 ナチュラルさが禁じ手……。それは、ナチュラルさに対する抵抗とか、反抗みたいなことなのか、それとも不自然さをより積極的に指向しているということですか。
松原 とくに抵抗したいとかいうことではないんですが、ナチュラルなものは日常にいくらでもあるから、それをわざわざ舞台で観たいとは自分が思わない。だからそういうものは書かない。
滝口 なるほど。舞台上には、非日常的な様態のものをあげるべきだと。
松原 そうです。普段あまり耳にしないような言葉が異物として舞台にあがったほうが、より聞こえてくるというか。それから、僕は書き言葉を読んで自分の中に取り込んできた人間なので、口語的なものにそもそもあまり慣れ親しんでいないんです。だから、それを自分で使おうというふうになかなかならない。日常的で親しみのあるものというよりは、何かこう、もっと厳密な意味を持ったものとして言葉を扱っている。
滝口 それは松原さんの戯曲を読むとよくわかります。
松原 濱口竜介さんの映画『ハッピーアワー』なんかもそういう感じがすごくありますよね。人物が会話してるんだけど、書き言葉と口語の間みたいな文章が台詞として発せられている。日本の映画でああいう言葉が語られるのは珍しい。
滝口 よくわかるんですが、とはいえその不自然さを指向するというか、自然さを否定するというか、そのモチベーションを維持するのって大変なことだと思うんです。往復書簡の中でも何度かそういう話になりましたが、例えば時間や場所の安定性、それも自然さの一つだと思いますが、そういう安定性が足場として存在していないと、異物としての言葉を発していくのは難しいんじゃないでしょうか。松原さんの場合、その足場すらもけっこう不安定というか……。
松原 いえ、安定した足場は大事だと僕も思っています。「山山」は、じつはチェーホフを土台にしてるんです。『桜の園』とか。一応、一人の登場人物が一人一役で語って、最後まで一貫してその形を保っている。
滝口 なので土台は安定している……?(笑) それは土台といっても、もうかなり地盤の奥の方みたいな土台という感じがしますが。
松原 そうかも知れないですね(笑)。
滝口 一人一役とか、そういうレベルの土台の安定性は確保しているけど、登場人物たちが発する言葉にはズレとか齟齬がある。自然な会話にはならないというか、ある言葉の次の言葉が、その応答になっているとは限らない。観ている人が普通に期待したり予測するような応酬にはならないですね。
松原 そうですね。
滝口 みんなそれぞれの軸を持って言葉を発したりしていて、その軸がみんな違うから、一向にかみ合わないようにも見える。でも、これは大勢の人のモノローグとしてではなくて、あくまで会話として、対話として書かれているわけですよね。
松原 そうです。やっぱり前の句を受けて、次の句を継ぐという形になっている。
滝口 順番は入れ替えられないということですね。
松原 はい。まあ地点の上演では入れ替えられるんですが。前の言葉を聞いて次の言葉を発するという形にはなっている。普通の、自然な対話ではないけれど、対話ではありますね。
滝口 僕も小説を書くときに、小説での会話文で使われがちな言葉、小説の典型的な言葉遣いのようなものにはやっぱり抵抗があって基本的には避けるんですが、それは実際の発話の自然さみたいなものを指向してるからだと思うんです。ゼロ年代くらいの岡田利規さんの「超口語」の影響も大きかったです。でも松原さんが戯曲でやろうとしているのはそれとはまったく別のことですよね。
松原 たぶん普段の会話では、実際には口に出して言わないことがけっこう多いと思うんです。僕はそれを全部書くというか。
滝口 人が会話するとき、実際に声に出してその場に現れる言葉はごく一部だけれど、そうじゃなくてそこにあるもの全体というか、そのときその人のもとにある言葉全部を書くみたいなことでしょうか。
松原 そういう感じです。会話らしい言葉を使ってしまうと、すごく予定調和的になる。会話らしい会話を積み重ねて、いろいろな背景を少しずつにじませて、一人のキャラに感情移入させる、というのがドラマの常套手段です。バリエーションはいろいろあるにせよ、そのパターン自体はもうやり尽くされている感じがする。それをやるぐらいなら、会話に何かをにじませるんじゃなくて、とりあえずその人が持っているものを全部さらけ出したい。実際の日常の会話ではそういうことはできない。戯曲でしか書けないものなんじゃないかと思います。


・
演劇に出会うまで
滝口 松原さんが演劇と出会ったのは、2014年の3月に地点の『ファッツアー』を観たときだと、何度か語ってますよね。『山山』の単行本にも繰り返し出てくる。それ以前には演劇には馴染みがなかったんですか。
松原 そうですね。先に興味を持ったのは小説なんです。学生時代にベケットやジョイスとかを読んで、「小説、おもしろいな!」と思った。
滝口 何かきっかけがあったんでしょうか。
松原 大学生協で、ドゥルーズの本(河出文庫)が並んでいるのが目にとまって、まずはそれを読み始めたんです。本の佇まいがかっこよくて。その文庫本を1冊ずつ、読んでは買って、とやっているうちに、ベケットに興味を持った。そこからジョイスに、そしていろいろな海外文学に、という感じですね。
滝口 現代思想の授業に出ていたとかではなく?
松原 授業には出ていなくて、個人的に。最初に触れたのがベケットとかジョイスとか、そういうちょっと普通じゃないものだったので、普通の小説がだんだん読めなくなった。「日本のやつとはだいぶ違うな」と思いました。
滝口 その頃は何か書こうという気持ちはあまりなかったんですか。
松原 ぼんやりと何か書きたいなとは思っていたんですが、書き方がよくわからなかった。登場人物を設定して、場所を決めてとか、そういうようなことが。でもベケットを読んでみると、それをすっ飛ばして書かれていた。
滝口 それなら書けるかも、と思った。
松原 そうそう、言葉の紡ぎ方が、自分と合っているかも知れないと思いました。文学賞に応募したりもしましたが賞には引っかからず、でも書くことは続けていました。大学を卒業したあと二年ほど東京にいたんですが、いろいろあって、京都の友達のところに居候することになった。地点の『ファッツアー』に出会ったのはその頃ですね。
滝口 『ファッツァー』を観たときの衝撃については往復書簡でも触れていただいたんですが、何かが聞こえてくる、という言い方をされてますよね。そこで発されている言葉が物理的な音声としてだけではなく、別の思わぬ形で現れて自分に届くというようなことだったと思います。松原さんが戯曲でやろうとしていることもまさにそういうことだと思うのですが。
松原 そうですね。演劇を観たときに、観た人の中に台詞が残るということがありますよね。それはたぶん「いい台詞だったな」というようなことだと思うんです。自分が知っていること、薄々思っていたことを、いい台詞で代弁してくれた、というような。「聞こえてくる」というのはそうではなくて、言葉がまったく未知のものとして、見ず知らずの他者として現れてくるということです。言葉の意味だけではなく、その声に含まれているものや舞台上の状況が、その時の個人に聞こえてくる。
戯曲は小説と詩の間にある
滝口 やっぱりなかなかわかりにくいですね(笑)。往復書簡では戯曲と小説の対照が多かったですが、『山山』の単行本に収録されている「戯曲の読み書きについて」では詩についても触れていますね。これを読んで、小説だけでなく詩を含めて考えると、松原さんの戯曲や創作姿勢のことが理解しやすいのかなとも思いました。
松原 確かに、詩は読んでいる段階で未知なる他者が現れるということは普通にありますね。小説だとあまりない。
滝口 小説は先ほどの言い方で言うと足場のリアリティが強い傾向がありますからね。詩はそうではない。
松原 小説はやっぱり連なりで読み進めていかないといけないので。
滝口 ああ、そうか。松原さんの戯曲には断絶があるんですよね。散文の中にも断絶はあるけれど、それはもっとこう、意匠とか決め技みたいに機能しがちで。でも詩は散文と比べればほとんど断絶が前提みたいなところがあって、そういう意味では松原さんの戯曲は小説よりも詩に近い位置にあるのかもしれない。
松原 自分としては、戯曲は小説と詩の間ぐらいにあるものだという感じがするんです。
滝口 一般的に、ということではないですよね。
松原 一般的にではなくて、僕の戯曲の場合ですね(笑)。
滝口 それは、最初に出てきた「ポストドラマ」ということともつながりますね。
松原 確かに、その断絶というか、飛躍みたいなものを極力入れないでやるのが「ドラマ」ですね。典型的な会話劇は流れるように連続的に読めて、断絶や飛躍は、滝口さんがおっしゃったように「キメ」みたいなものとして使われる。
滝口 松原さんはそういうものは拒むわけですね。でも松原さんの作品にも、なんだか急につかまれるというか、ぐぐっと引き込まれるような言葉や文章が出てきたりするんですよね。それがさっきの「聞こえてくる」ということと同じなのかはわからないんですが。たとえば、
可能性がわたしたちに夢見させた時代もあったのかもしれない。でも、可能性はいつだってただの可能性でしかなくて、実現されれば可能性ではなくなるし、信じるべき可能性を持つことは信仰を持つことと変わらない。あなたはその山山の可能性のなかから、どの可能性を信じるというの?(『山山』83ページ)
ここだけ抜いてきてもよくわからないし、アフォリズムのようなものとして機能しているわけでもないんですが、ただ、ばっとこの一節が出てきたときに、謎の説得力みたいなものを感じて線を引いたんですよ。こういうのが随所にある。で、それはやっぱり散文的な手応えだと思うんです。連なりのなかで打たれる感じというか、ある種の起伏というか、読んでいる人のなかでなにかが醸成されてそれがある時点で弾けるみたいな。でもやっぱり小説とは違うから、そのメカニズムがよくわからない。典型的な「決め」みたいなものを拒みながら、こういうある種の高まりみたいなものを表現するには、具体的にはどういうことをやってるんだろうと不思議です。
松原 書き直しが肝ですね。かなり書き直します。しっくりこない部分は、とにかく一行、一行に手を入れ続けて、まだ言われてないことを明るみに出すようにします。あとはリズムです。やはり声になるものなので、声に出した時のリズムが重要で、それは手を入れることで確実に良くなっていく。
滝口 リズムは良くなるけれど、わかりやすくなっていくわけではない。
松原 ドラマの説明的な部分を削っていくので、だんだんわかりにくくなっていくはずなんですよ(笑)。
滝口 それはある種、恐怖ですよね。手を入れれば入れるほどわかりにくくなっていく。でも、ちゃんと手応えとしては、だんだん「聞こえてくる」ものになっていくんでしょうか。
松原 書いている段階では、そこまでの確信はないですね。でもリズムは確実に良くなる。できるのは、前の句を受けて次の句を継ぐ、そのリズムを作るために手を入れ続けるということだけです。
滝口 ああ、今の言葉は松原さんの作品の姿勢そのものって感じがしますね。
往復書簡から見えてきたもの
滝口 往復書簡の終盤で、僕は「書き手」観がすごく変わったんです。それまでは、作品の中の語り手と作品の読み手の間のコミュニケーション、というような感じで小説を捉えていて、書き手の自分は何なのかうまく説明ができないところがあった。いったん作品が書かれてしまえば、書き手は蚊帳の外みたいなイメージだったんです。でも、「戯曲」や「上演」について考えているうちに、じつは作品と読者の間にいるのは、語り手ではなく書き手だと考えればいいのではないかと思った。国語の試験にあるような、作者が設計図みたいなものに基づいて作品を作り上げて読み手はその書き手の意図を考える、みたいな図式とか、作者のプロフィールやプライバシーを作品に持ち込む読み方は依然として拒みたいんですが、いま言っている「書き手」というのは「作者」つまり僕自身ともイコールではないんですよ。
松原 その「書き手が上演である」というところは、実は僕にはちょっと難しかったんです。演出のことなのか、それともその舞台における上演全体のことなんでしょうか。
滝口 演劇では、戯曲があって、観客がいて、その間に上演があるわけですね。戯曲の中にある声を聞き取ってそれを再現し、観客に伝えるのが「上演」。それを小説で考えたら「上演」としての「書き手」という構図が見えてきて、「書き手が上演である」と考えたらしっくり来る感じがした。僕にとって小説のなかの最重要人物は常に「語り手」なんですが、そこに〈語り手と書き手〉という関係性が見えてきた感じです。
松原 書くことは「声を聞くこと」だというのも、往復書簡の中で繰り返し出てきたテーマですね。
滝口 そうでしたよね。往復書簡の中で松原さんと共有したある種受動的な感覚、聞くようにして書いているというイメージも、作品と読み手の間に書き手が挟まっている、という構図とつながっています。聞き手としての書き手。
松原 この往復書簡がなければ、僕は戯曲というものについて、戯曲を読んだり書いたりすることについて、こんなに考えていなかったと思うんです。なぜ自分は小説でも詩でもなく戯曲を書いているのか、それは戯曲固有のものがあるからだろうと漠然と思ってはいたんですが、それが声なんだということがはっきりわかった。滝口さんが、小説の声というのは「未然の声」なんだと書いていらっしゃいましたが、それを読んで戯曲とはずいぶん違うものなのだということが如実にわかりました。そのことが一番の発見だったと思います。それから、今またお話に出た、書き手が作品の語り手の声を聞きながら書く、ということもとても重要なことで、それは創作する上で最低限の倫理のようなものだと強く思います。でもそれを実践している人は意外に少ない。演劇の場合には演出ということとも関係してきますが、書き手は作品の外側にいるような構図で考えられがちです。
ポストドラマの戯曲を、ドラマの劇団で?
滝口 今後のお仕事の予定はいかがですか。
松原 来年以降の計画もあるんですが、直近では今年の10月にスペースノットブランク、12月に文学座の公演があってどちらもそれぞれ新作戯曲を書き下ろします。今は文学座のほうを書いています。
滝口 地点以外の劇団による上演は初めてですよね。スペースノットブランクも前から気になりつつ未見なのですが、委嘱する側の振れ幅もなんかすごいですね。やっぱり文学座だとだいぶ違った感じになるんでしょうか。
松原 そうなるでしょうね。やはり近代劇、会話劇をやってきた劇団ですので。
滝口 ポストドラマの戯曲を、方法的にはドラマの方法で上演する、みたいなことになるんでしょうか。言うのは簡単だけど、どうなるのか想像できない。
松原 ドラマ的な方法以外のものを取り入れないと「聞こえてくる」ものにはならないでしょうね。
滝口 でも松原さんは演出をするわけではないですものね。
松原 はい、僕はテキストを渡すだけです。それから今回、地点と違うのはカットされずに全編が上演されるということですね。僕にとっては初めてのことです(笑)。
滝口 ようやく編集されずに上演される! 戯曲全部が舞台上で演じられると、松原さんの作品はどんなふうに見えるんだろう。本当に楽しみです。
松原 僕も楽しみです。

写真:広瀬達郎(新潮社写真部)
-

-
松原俊太郎
作家。1988年熊本生まれ。2015年、処女戯曲「みちゆき」で第15回AAF戯曲賞大賞受賞。2019年、『山山』で第63回岸田國士戯曲賞受賞。他の作品に戯曲「忘れる日本人」、「正面に気をつけろ」(単行本『山山』所収)、小説「またのために」など。
-

-
滝口悠生
1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 松原俊太郎
-
作家。1988年熊本生まれ。2015年、処女戯曲「みちゆき」で第15回AAF戯曲賞大賞受賞。2019年、『山山』で第63回岸田國士戯曲賞受賞。他の作品に戯曲「忘れる日本人」、「正面に気をつけろ」(単行本『山山』所収)、小説「またのために」など。
連載一覧
-

- 滝口悠生
-
1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら