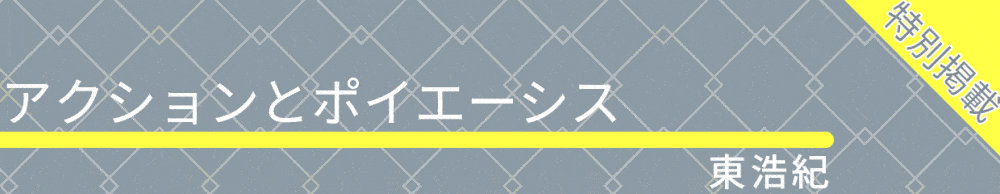アクションとポイエーシス
著者: 東浩紀
1
二〇世紀を代表する哲学者のひとり、ハンナ・アーレントは、『人間の条件』という有名な著作で、人間の行いを「活動」と「仕事」と「労働」という三つの領域にわけることを提案している。
そこで「活動」とは言語的な表現やコミュニケーションを、「仕事」とは職人的なものづくりを、そして「労働」とは肉体をもちいた賃労働を意味している。活動、仕事、労働という表現は日本語の定訳に拠っているが、英語の原文ではそれぞれ「アクション」「ワーク」「レイバー」となっている。アクションは、「行動」と訳せばわかるように、アーレントにおいては政治的な意味を強く帯びている。他方でワークは、「作品」という訳が可能であるように、かたちの残るものの制作、とくに工芸品などの制作を示唆する。
つまり、アクションとワークの対立には、政治と芸術の対立が重なっている。古いギリシアの言葉をつかえば、プラクシス(行為)とポイエーシス(制作/詩作)の対立である。じっさいこの著作にはアーレント自身のドイツ語訳があるが、そちらではワークに相当する概念は、ドイツ語で制作を意味する言葉(ヘアシュテレン)があてられている。日本語、英語、ドイツ語、いずれを使っても特定のニュアンスが強調され、べつのニュアンスが消えることになるが、要は人間の行いには「他人に言葉で働きかけること」と「ものにかたちを与えること」のふたつがあり、それがアクションとワークとして区別されていると考えればよい。アーレントはそれに労働を加えて、人間の行いはこの三つのどれかに分類されると考えた。
さて、アーレントはこの区別のうえで、もっとも尊重されるべき行いは活動だと、かなりはっきりとしたヒエラルキーを導入したことで知られている。彼女の考えでは、活動は制作=仕事や労働より上位であり、人間は活動を通してのみ、私的な関心を超え、公的な大きな世界に接続することができる。ひらたくいえば、ひとは小遣い稼ぎのためにコンビニでバイトしたり(労働)、自己満足のために孤独に作品をつくったり(制作)しているだけではだめで、公共の空間に出て、見知らぬ他者とともに、ともに直面する政治的な課題について語りあい意見を表明する(活動)ようになってはじめて充実した生を送れるのだと、そのようにアーレントは主張したのである。
この主張は、詳細な哲学的議論を知らなくても、いかにももっともらしく聞こえる。バイトで消耗する人生に未来はなさそうだし、マンガや小説を書き溜めるばかりでも未来はなさそうだ。しかし、裏返せば、彼女の主張は、そんな一般常識をたいして超えたものでないようにも思われる。そもそもそんなヒエラルキーを認めてしまったら、身体的あるいは精神的な障害で公けの議論に参加するのがむずかしい人々(二〇一九年は重度障害者の国会議員が誕生した画期的な年でもあった)は、原理的に私的な領域に閉じ込められ、生も充実しないことになってしまう。それでよいのだろうか。『人間の条件』はなかなか問題含みの著作なのだ。
したがって、アーレントのこの著作はしばしば批判されている。ぼく自身も批判を記したことがある(『観光客の哲学』)。そのときは活動と労働の区別を焦点にした。その区別が、二〇〇一年の『動物化するポストモダン』以降、長いあいだぼくの関心の中心にある人間と動物の区別に重なると思われたからである。
アーレントは、人間は活動においては人間としてふるまっているのでよいが、労働においては動物として働かされているにすぎないのでよくないのだと主張した。しかし、人間が人間であるときと人間が動物であるときが、はたしてどこまで明確に区別できるものだろうか。それがぼくの疑問である。この問いは、ぼくたちの生一般の問題としても重要だし(たとえば愛を交わすとき、ぼくたちは人間としてそれをしているのだろうか、それとも動物としてだろうか)、また接客や介護のような「感情労働」と呼ばれる労働の本質を考えるときにも欠かせないもののはずだ。この問いはこの問いで、ぼくはいまでも考え続けている。
けれども、ぼくは最近、それに加えて、活動と制作の対立のほうも問題にすべきではないかと考えるようになってきた。アーレントは、活動(政治)はひとを公共的で人間的な充実した生に導くが、制作(芸術)はそれだけでは導かないと考えた。それは正しいだろうか。
というよりも、それがもし正しいとされるとしたら、いったい制作はどうなってしまうのだろうか。
2
活動はひとを他者と公共性に導く。制作は導かない。いちどそう問題が設定されてしまえば、人々がどのような結論を出すかはたやすく想像がつく。
近代においては、ひとを公共性に導くことは絶対善である(ぼくの理解では、それがヘーゲル主義のひとつの本質である)。したがって、いちど活動と制作のあいだに以上のようなヒエラルキーが設定されるのであれば、制作を行動に、つまりはポイエーシスをアクションに近づけるのが正義ということになるにちがいない。ひらたくいえば、なにをつくるかよりも、いかにして他者に働きかけるか、他者と交流するかが重要だという話になるはずである。じっさい二〇世紀においては、そのような考えかたにもとづいた作品が、現代美術、現代文学、現代音楽、現代演劇……と多くは「現代」の冠がついた一群の芸術家たちによって大量に生み出された。キャンバスを破いたり、楽器をまえにしてなにも演奏しなかったり、街中で突発的に演劇をやってみたり、といった作品群である。『人間の条件』の英語版は一九五八年、日本語版は一九七三年に出版されている。それがまさにジョン・ケージやフルクサスや「ハプニング」や寺山修司らの時代であることは、おそらくは偶然ではあるまい。
制作の活動化。ポイエーシスのアクション化。つまり芸術の政治化。それは当時は、閉鎖的で保守的な「芸術」を変革する重要な契機になったことだろう。そしてじっさいにそのように評価されてもいる。
けれども、ここで考えねばならないのは、その戦略がもつ意味は、世紀が変わりSNSが現れたことでいまや大きく変わりつつあるのではないかということだ。
どういうことだろうか。アーレントの時代、アクションこそが人間を人間たらしめ、他者と公共性に開くものだと信じられたのは、そこではアクションが、いわば「見えないもの」だと考えられていたからである。
制作=作品(ワーク)は見える。触ることもできる。つまりその成果を知覚によって確認できる。けれどもアクションは見えない。触ることもできない。自分の活動=行動がほんとうに他者を動かしたのか、他者とのコミュニケーションでなにが生まれたのか、その成果は知覚によって確認できるようなものではない。アーレントはこの性格について、アクションはつねに「過程」であり、アクティヴィスト自身はその本質を掴むことができないというかたちで表現している(興味ある読者のため付記しておけば、ぼくがここで参照しているのは『人間の条件』二七節から三二節あたりである)。だからこそ活動は、ひとを、作品の制作よりも困難で、おそろしく、本質的な人間の謎に直面させるものだと考えられていたのである。
しかし現在はどうだろうか。ぼくたちはSNSの時代に生きている。SNSとは、その本質においてアクションを計量するメディアである。だれかがだれかのツイートを「いいね」する、だれかがだれかの写真を「シェア」する、だれかがだれかに「返信」し、だれかがだれかと「友だち」になる、それらの行動すべてを記録し、集計し、可視化して交換財に変えるのがSNSのビジネスモデルである(関心経済と呼ばれる)。アクションの効果はいまや、見えないどころか、リツイートや「いいね」の数によって残酷に瞬時に計測されてしまうのだ。ケージにしても寺山にしても、いまの時代に生きていたら感想やハッシュタグの検索に余念がなかったにちがいない。
ぼくたちはアクションが計量できる時代に生きている。それはもしかしたら、ある種の表現にはプラスに働くこともあるかもしれない。けれども、少なくとも、芸術の政治化の意味は大きく変えてしまうはずだ。
二〇世紀においては、制作のアクション化は、見えない他者に出会い、コミュニケーションの暗闇に足を踏み出すことを意味していた。ところが二一世紀においては、それはSNSでの関心獲得競争に足を踏み入れることしか意味しない。
これはきわめて具体的な話である。この数年、日本でも若い世代の作家やアーティストが政治的な発言を行うことが増えてきた。署名の呼びかけやデモへの参加表明もめずらしくなくなった。それじたいは歓迎すべきだろう。
けれども、そのアクションの舞台はたいていはSNSである。SNSを舞台にするかぎり、そこには必ず効果の測定が入り、数の競争が生まれる。そして、SNSで歓迎される文体、リツイートや「いいね」を効果的に引き出す表現やリズムはそもそも限られている。結果として、多様な作家をフォローし、多様な知見の投稿を楽しみにしていたはずが、それぞれの作家が効果的なアクションを目指したばかりに、いつのまにかタイムラインは判で押したような画一的な政権批判の言葉と、同じ政治家の発言、同じニュースのリツイートで埋め尽くされることになる。――本誌(「新潮」のこと)の読者にも似た経験をしているひとが少なくないと思うが、それがいま日本のSNSで現実に起きていることである。いまやアクションの画一性こそが、ポイエーシスの多様性を塗りつぶし始めているのだ。SNSの出現は、『人間の条件』の条件そのものを変えてしまったのである。
むろん、読者のなかには、そんな計量されるアクションなどほんとうのアクションではない、そんな話はアーレントの哲学となんの関係もないと反論するひともいるだろう。そう考えてもいい。それならば、いまはアクションが計量できると思われてしまう時代だと、そう表現を追加してもいい。
どちらにしろぼくの言いたいことは変わらない。いまは体制側も反体制側も資本家も労働者も、みなが政治は数だと考えている。そしてその数はSNSで調達できると考えている。その成功例がアメリカ大統領のトランプだ。だからこそ、右派に対抗し左派のほうもポピュリズムによって大衆を動員すべきだ、といった単純な戦略論も出てくる(ふたたび関心のある読者のため付記すると、シャンタル・ムフの左派ポピュリズム論はかつてぼくが『観光客の哲学』で批判した「否定神学的マルチチュード」の論理そのものであり、なぜそれがいまさら一部論壇で新しい議論であるかのように持ちあげられているのか、その理由がぼくにはさっぱりわからない)。いま「アクションを起こす」とは、本人がそれを望むと望まないとにかかわらず、その不毛な数取りゲームに参加することしか意味しないのである。
ベンヤミンは『複製技術の時代における芸術作品』の末尾で、政治の美学化(芸術化)ではなく芸術の政治化が必要だと記した。芸術の政治化は、彼にとって、全体主義から身をかわす技法として考えられていた。
ベンヤミンが一九三〇年代に複製技術に支援された全体主義の台頭に直面していたように、ぼくたちはいま、SNSに支援された全体主義の台頭に直面している。そしてそのときアクションがSNSの論理に支配されているのであれば、芸術の政治化は抵抗の技法になりえない。もしいま「SNSの時代における芸術作品」を主題にするとしたら、芸術と政治の関係について、ぼくたちはベンヤミンとはまったく異なった回答を編み出さねばならないはずだ。
3
ところで、ぼくはなぜこんなことを書いているのだろうか。察しのいい読者はすでにお気づきかもしれない。
ぼくは昨年と一昨年、本誌新年号に連続してエッセイを寄せた。今年もぜひと執筆の依頼をいただいたとき、これは「あいちトリエンナーレ」について書かざるをえないだろうと直感した。それが、二〇一九年の後半で、思想的にも実存的にも、ぼくをいちばん悩ませた問題だったからである。
あいちトリエンナーレの騒動についてはいまさら説明する必要はないだろう。ぼくはじつは、その美術展で「企画アドバイザー」なる役職を務めていた。そして、八月に騒動が起きて数週間後に辞任した。トリエンナーレの芸術監督を務めていた津田大介氏は、ぼくの古い友人であり、たいへん近い仕事仲間である。それゆえ辞任にはさまざまな意味で痛みが伴った。また、当然のことだが、多くの人々に批判を受けた。なかには誹謗中傷に近いものもあった。ぼくにはぼくなりの信念があったが、騒動は日を追うごとに大きくなり、いちどは内部の人間だったがゆえに中途半端に発言することもむずかしく、マスコミの取材はすべて断り、個人のSNSや自分が経営にかかわる会社(ゲンロン)の放送以外では――いちどだけ、べつの口実で行われた新聞インタビューで不意打ち的に活字にされてしまったことがあったが――騒動について意見を発表することはしてこなかった。本稿は、具体的なことにはなにひとつ触れていないが、ぼくなりの騒動に対する評価であり回答である。
しかしそれだけでもない。ぼくは批評家と呼ばれている。批評家は、さきほどまでの分類でいえば、ポイエーシスではなくアクションを担当する職業にあたる。
小説家は小説を制作する。美術家は美術作品を制作し、映画監督は映画を制作する。それに対して、批評家はそれらの作品にコメントを加え、制作=作品と社会をつなぐ役割をする。それは、批評家とはなにかを制作するひとではなく、むしろ他者の制作=作品を題材として、べつの他者に働きかけたり、その働きで社会を変えたりするひとだということを意味する。だから、小説を書かない小説家、美術作品をつくらない美術家は存在しないが(存在するとすればそれは「批評家的」だとみなされる)、批評を書かない批評家は問題なく存在する。批評にはかならずしも批評文は必要ない。
けれども、ぼくはむかしから、そのような批評家観に、なかば惹かれつつも、なかば大きな反発を抱いてきた。批評家はたしかに文章を書かなくていいのかもしれない。それどころか、批評家という職業の効率を考えたら、長い文章を書くことなどは単純に愚かな選択で、テレビの出演や新聞のコラムや座談会やSNSを組み合わせ、影響力を最大化するほうがよほど賢いのかもしれない。じっさいにそのような選択をしているひとは年上にも年下にも存在する。ぼく自身、ゲンロンという会社を立ちあげてからは(そもそもは自分の文章を出版するために会社を立ちあげたにもかかわらず)、ぼく自身が文章を書くことがいかに経済的に非効率で経営にとって害でしかないか、痛感することが増えていた。しかしそれでも、ぼくにはどうしても書きたい文章があり、ぼくにとってはその理想こそが批評家としての影響力よりもゲンロンの経営よりもはるかに重要なのだと、そう感じることをやめられないでいたのである。その想いと焦りは、ここでは触れるに止めるが、いちどはぼくを深刻な鬱状態に導いた。
ぼくには書きたい文章がある。ぼくはその理想のかたちについて、この数年、哲学と批評と紀行文の融合という表現で伝えようとしてきた。そしてこの夏ようやく、「悪の愚かさについて、あるいは収容所と団地の問題」と題した五万字ていどの論考を、その最初の実現として世に送りだすことができた(『ゲンロン10』)。加藤典洋の『敗戦後論』への隠れた応答であり、変わったハイデガー論であり、『ねじまき鳥クロニクル』論であり、またハルビンとキエフとクラクフの取材報告でもあるその文章が、いったいだれにどのように読まれたのか、ぼくにはよくわからない。そもそも文芸誌の読者であるみなさんに、どれほど存在が知られているのかもわからない。
ただ、ぼくはその文章を書いているとき、とても充実していた。ぼくはそれを、だれよりも自分のために書いた。
ぼくが読みたい文章がこの世界にないから、ぼく自身で産み落とす。ぼくはそれだけの思いで五万字を書いた。そこには他者がいない。だからそれは、アーレントの前述の基準からすれば、政治的なアクションよりもよほど低く評価されるふるまいにちがいない。けれども、その名も『批評空間』という雑誌でデビューし、批評=アクションの呪いをかけられてから四半世紀、ぼくはようやく、制作の快楽に身を沈めることで、その呪いを切り捨て、物書きとしての原点に立ち戻り、批評家として再生することができたように感じていたのである。あいちトリエンナーレの騒動は、ぼくにとって、ちょうどそんなときに起きた。
ぼくは、アクションとポイエーシスのどちらかを選ばねばならないのだとすれば、ポイエーシスを選ぶ人間である。多少おおげさにいえば、そうでしかぼくは生きることができない。それが、ぼくがこの原稿で伝えたかったことである。
むろん、このような態度表明は、思想的にも、また政治的にもさまざまに批判されるにちがいない。それらの批判に対しては、批評家としてというよりも哲学者として、SNS政治と関心経済に覆われたこの二一世紀の世界においては、ゲーム化したアクションに参入し左派ポピュリズムの駒になるよりも、ポイエーシスが開くべつのかたちの公共性に賭けたほうがよほど知的に豊かであり、誠実であり、そしてほんとうの意味で政治的なのだと答えていくしかない。その答えを説得的に練りあげていく作業こそが、これからのぼくの仕事=制作の軸となるだろう。
(「新潮」2020年1月号より転載)
-

-
東浩紀
あずま・ひろき 作家・思想家。1971年生まれ。著書に『存在論的、郵便的』『クォンタム・ファミリーズ』『一般意志2.0』『観光客の哲学』『ゆるく考える』『テーマパーク化する地球』など。
この記事をシェアする
「アクションとポイエーシス」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 東浩紀
-
あずま・ひろき 作家・思想家。1971年生まれ。著書に『存在論的、郵便的』『クォンタム・ファミリーズ』『一般意志2.0』『観光客の哲学』『ゆるく考える』『テーマパーク化する地球』など。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら