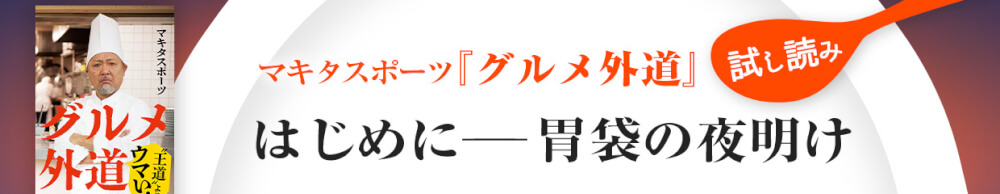2025年3月17日
はじめに――胃袋の夜明け
著者: マキタスポーツ
「考える人」で連載していたマキタスポーツさんの「土俗のグルメ」が、『グルメ外道』として新潮新書より3月17日に発売となりました。10年前に自身のラジオで提案すると大バズりした「10分どん兵衛」や「窒食」「志村けんに教わった水割り」「私のモスバーガー物語」など、積年の思いをこめて、“食”へのこだわりを書き切っています。
本書発売を記念して、「はじめに――胃袋の夜明け」を公開いたします。世間の流行や他人の評価に背を向け、己の舌に忠実に“食道”を追求――それ即ち「グルメ外道」なり。マキタさんの「美味しい能書き」をお楽しみください。
自分が“主役”
大事なことは、私が「美味い」と思うかどうかだ。話題の行列店やグルメ情報、識者による評価は重要ではない。
それが私の本音で、上等だの、下等だのと、メシを区別するのも苦手だ。
21900食。50歳を超えた私があと20年生きたとして、日に三度の食事をするとこの回数になる。するともうカウントダウンである。残されたメシの回数を思うと一食も外したくない。
人様の評価は、たしかに失敗しないためには役立つかもしれないが、それに頼って失敗を免れたとしても、「それがどうした」だ。“自分のメシ”じゃないか。上等も下等も、自分の舌や喉、口蓋、鼻、目を使って感じれば良い。失敗したと感じたとしても、それを“含み益”とし、脳内に刷り込み、細胞に組み込むだけである。
「俺が芋食って、おまえの尻からプッと屁が出るか!」
映画『男はつらいよ』で、寅さんが前田吟の演じる博に言った名台詞である。私はこの台詞に激しく同意する。
そんなことを書きながら、私は今かまぼこを食っている。理由は小腹が空いたからである。膝から崩れ落ちるほど美味い!と言うほどのこともない、なんてことのない可愛げのないかまぼこだ。
しかし、この日、原稿を書きながら、空いた小腹にひょいと口にしたかまぼこを私は忘れないだろう。いや、忘れるかもしれない。でも、「こんなのもいいな……」と思った感触は誰のものでもなく私のものであり、ちょっと忘れられない体験となっている。大事なのはその気持ちを、〝自分〟にどう刻むかだ。だって、「メシ」という行為は“自分が主役”なのだから。
「背景食い」という楽しみ
断っておくが、レビューサイトやタイヤ会社のグルメガイドなどの指標を否定するのではない。あれを頼りにしている人にも「食人生」はあって、それにより、幸せなひと時を得ているのであればそれはそれでいいと思う。物を食らっているのでなく、まるで情報を食らっているように見える人もいるが、どうぞご勝手にと。
私は「他人の作った情報」を食いたくないのである。たとえ他人から“外道”と言われようが、私が得たいのは、「私がいただく食べ物」であって、それを“私”がどう感じるかが重要なのだ。
それを食した時に、誰と、どんな場所で、季節はどうで、誰かが汚く食っていたけど美味そうだった――とか、大切なのはそういったディテールであり、また、その食べ物が作られたバックボーンを自分なりに見たり、聞いたり、勝手に想像したりして、それも〝味〟として楽しむのである。
それを私は「背景食い」という。
山梨の一地方に「マキタさん」と言われる食い物があるらしい。それはワンタンの皮にひき肉を入れて包み揚げた物で、生姜醤油につけていただく。以前私が出演していたラジオに届いたタレ込み情報だったのだが、聞いて驚いた。
「それって、アレのことか!?」
我が家で、お袋がおやつ代わりに作っていた「名もなきアレ」。アレがその地域では「マキタさん」と言われているのか。聞けば、そのレシピをうちのお袋から教わった方が、自身の嫁ぎ先で流行らせたことから、その地域では「マキタさん」と呼ばれるようになったという。
私はにわかに感動した。そのエピソードにトライブ(部族、仲間。共通の趣味や感心を持った集団のこと)性を感じたからである。もちろん、今は亡き母親の痕跡が残っていたことにも感動するのだが、それ以上にあるのが「食いもんってそういうことで伝播していくものなのか……」という感嘆だ。
たとえば、麺の起源について諸説あるのは、その当時のはっきりとした記録がないからである。だから中国発だの、いや古代エジプトにもうその起源はあったとか、やっぱり古代ローマだよ、などと揉める。誰が最初にホヤを食ったのか、などについても同様である。でも、「マキタさん」の発生のルートははっきりと掴めたのだ。それは極小のコミュニティで流行り、人々の何気ない食欲に寄り添い、バカに美味いというほどのことでもなく定着する。
子「ただいま~、腹減った~」
母「アレあるよ、マキタさん」
子「え~? またマキタさん?」
母「だって、簡単なんだもん」
子「ま、いいか~、アレついつい食っちゃうんだよな~」
そんな、やっつけ気味の母と、舐め腐った子どもの声が聞こえて来そうだ。どうだろう、興奮しやしまいか。私はもう腹が減っている。
空腹の境目
私は満腹が嫌いだ。
なぜならそれ以上何も食べられないからである。同時に、自分の食いしん坊ぶりには原罪のようなものを感じている。満腹になると、ついさっきまであった自分の卑しさに羞恥を感じる。「また、変身してしまったのか……」と、まるで月夜の狼男のような落胆した気分になる。しかし、そのような自己矛盾が自分のガソリンになっていることも知っている。
例えば、朝食バイキングはどうだ。私はあれが大好きで、大嫌いなのである。毎回「どんな気がする?」と人生観を突きつけてくる。
私は朝食バイキングのメニュー攻略を“課題”と考えている。「食欲vs.満腹」は永遠のテーマだ。いつもそれに挑んでいる。
あのバイキングにおける「卵料理多い問題」はどうだ。スクランブルエッグ、だし巻き卵、ゆで卵、温泉卵、目玉焼き、シェフの実演オムレツ……。あるいはカズノコ、明太子、イクラといった魚卵も地域によってはある。全部は食べ切れない。はたしてどうすればいいのか――。
「えいや!」と意を決し、トレイの容量と己の胃袋のキャパシティを見比べ、今日のメニューをキュレーションする。
「和だ!」
しばしの静寂を経て、ようやく方向性を和風に決定したその刹那、漂い来たるは「カレー」の匂い。仕方なしに、無理矢理「カレーうどん」を味噌汁代わりにこさえる。悪手。
うっかり味噌汁代わりに用意したカレーうどんを食った途端、“満足感”が脳味噌を支配し始めた。暗雲が漂う、とはこのことか。胃袋の温度が上昇すると同時に、その蒸気が私の心に薄暗い雲を垂れ込めさせ始めた。絶望感。
「あゝ、また私はやってしまったのか……」
その絶望をおくびにも出さず、何事もなかったかのように食べ尽くし、私はひとり感想戦に入る。
「なぜ独自のホテルカレーに気を取られたのか?」
「あれ以降、全てが消化試合になってしまっただろう!」
「“実演オムレツ”はやはりパフォーマンス先行で、味はイマイチだったな」
やがて懐かしく思い出される「空腹感」。あの時、私は確かに大志を抱いていた。しかし、気づけば満腹。手前にあった欲望に負けて、しかもそこそこ美味しくいただき切ってしまった。
終盤、納豆とお粥の組み合わせにたどり着いた時には、「蛍の光」のあの侘しいメロディが脳内にこだましていた。だってもうこれ以上食べられないのだ。これを絶望と言わずしてなんと言おう。そして私は次の空腹を性懲りも無く待つのだ。
普段は行いと行いの間に“食”がある。しかし、私の場合は食と食の間に“行い”があるだけである。暗い気持ちで、仕事に向かう。数時間が経つ――と、突然、腹から後光のようなものが差すのがわかる。それはまるで雨と晴れの境目――ここから先が雨で、あっちは晴れというあれだ。なんとも言えない、頭上でくす玉が割れたようなご褒美感が私を包む。
「来た! 空腹なり!」
恋愛も、成就してしまったら次の段階に入る。実り、結ばれる前が一番ときめくように、私はこの焦れったくもキュンキュンする胃袋の状態が大好きだ。
これを「空腹の境目に立つ」と私は言う。満腹でも、空腹でもなく、今からようやく日の出が始まる、その兆し――すなわち「胃袋の夜明け」である。
そして、また何かを食らい、満腹になり、絶望する。日々、これを繰り返す。その無常観に私はうっとりとしている。
さあ、「グルメ外道」のスタートである。
(続きは本書でお楽しみください)
【目次より】
はじめに――胃袋の夜明け
第一章 私の「ライスハック」
1.「10分どん兵衛」の誕生
2.「ライスハック」という極意
3.「窒食」という秘かな愉しみ
4.「納豆チャーハン」の最適解
5.恥ずかしいバーベキュー
6.外道寿司
7.素晴らしき哉、メニュー!
第二章 カレー・ラーメン・焼肉――定番をもっと美味しく
1.私のカレー観
2.余は如何にしてラーメンを語ってきたか――外道のラーメン論Ⅰ
3.「美味しい」だけでは疲れてしまう――外道のラーメン論Ⅱ
4.私のラーメン物語――外道のラーメン論Ⅲ
5.50代からの焼肉革命
第三章 芸人とメシ
1.芸人を「食」にたとえる
2.志村けんの水割り――酒とコントは定位にあらず
3.コロッケとナルシシズム
第四章 その思い出に“用”がある――「グルメ外道」の原点
1.歌舞伎町のつくね煮――外道の料理の原点Ⅰ
2.私のモスバーガー物語――外道の料理の原点Ⅱ
3.食はいつも未知なもの
4.義母が作る奇跡のお雑煮
第五章 外道のグルメ論
1.人の“食欲”を覗く
2.生まれた時からナポリタン
3.〝実存〟としての焼き鳥
4.餃子、その完全なるもの
5.現地メシ――その地方の息吹と生活を食べる
6.分けて食べるか、混ぜて食べるか――「丼もの」をめぐる議論
7.淡さ論――「味巧者」への道
おわりに――ピュアな外道
-

-
マキタスポーツ
1970年生まれ。山梨県出身。芸人、ミュージシャン、俳優、文筆家など、他に類型のないエンターテインメントを追求し、芸人の枠を超えた活動を行う。俳優として、映画『苦役列車』で第55回ブルーリボン賞新人賞、第22回東スポ映画大賞新人賞をダブル受賞。著書に『決定版 一億総ツッコミ時代』(講談社文庫)、『すべてのJ-POPはパクリである』(扶桑社文庫)、『越境芸人』(東京ニュース通信社)など。近刊に自伝的小説『雌伏三十年』(文藝春秋)がある。
この記事をシェアする
「マキタスポーツ『グルメ外道』試し読み」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら