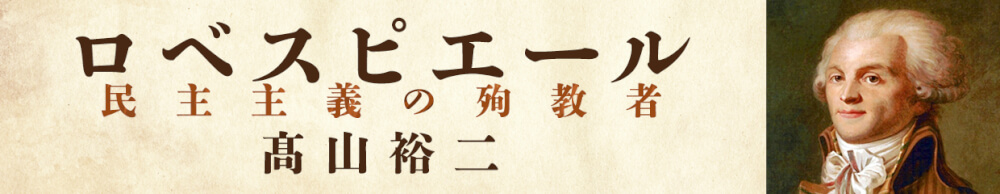それはプレリアル22日法から始まった
「ジェルミナルのドラマ」のあとも有力者の処刑は相次いだ。1794年4月22日、憲法制定議会の議長にして、労働者の団結を禁止した法(91年6月14日)の提唱者として歴史に名を残すル・シャプリエが、反革命の容疑で逮捕・処刑された。ジャコバン・クラブの前身、ブルトン・クラブの創設者もギロチンの刃を免れなかったのである。そして同日、前年12月に家族と共に逮捕・収監されていた、あのルイ16世の弁護人、マルゼルブもついに処刑台に送られた。享年72歳。自由と法に身を捧げた生涯だった。
5月8日、公安委員会が県革命裁判所の廃止を再確認したこの日、「近代科学の父」と称されるアントワーヌ=ローラン・ド・ラヴォワジエも、27人の元徴税請負人とともに処刑された。「ジェルミナルのドラマ」(第16回)の際にすでに触れたように、革命の理想に背く具体的な犯罪というよりも、旧体制期の役職や地位に付随する憎悪や怨念に基づく処刑、その象徴的な事例だったと言えよう。ラヴォワジエを研究面でも献身的にサポートしたと言われる14歳年下の妻マリー=アンヌ・ピエレット・ポールズ(1758-1836年)は、徴税請負人の娘だった。

さらに、有力なジロンド派議員もこの頃、不遇の死を遂げている。「ジェルミナルのドラマ」が展開する中、獄中にあったコンドルセはひっそりとみずから命を絶った(3月29日)。また、逃亡を続けていた元議員たちもいた。元パリ市長で一時はロベスピエールを凌ぐほどの人気があった、国民公会の初代議長ペティヨンは、他の議員と共にボルドー近くのサンテミリオンに潜伏していた。だが、サールやガデ、バルバルーが逮捕・処刑される中、ペティヨンはジロンド派の有力議員だったビュゾとともに拳銃で自決した。38年の生涯だった。
かくしてパリでの裁判と処刑が増え、そのさらなる簡便化・効率化が求められた。そこで提案されたのが、プレリアル(草月)22日法である。6月10日に発出されたこの「革命裁判所に関する法令」は、5月8日法によって増えたパリの裁判を効率化し、事実上処刑を迅速化することを目的にしていた。パリの監獄は囚人で溢れ、7千3百人の「反革命容疑者」がそこに詰め込まれていたのである。
そのため、同法は尋問を公開とし、物証で足りる場合には証人の喚問は実施せず、有罪の場合は極刑のみ、「陰謀家」の裁判には弁護士は認めないようにした。そこには、ダントンがその雄弁で裁判を長引かせたことへの教訓があり、また長引く審理の中、民衆が裁判に介入する余地を少なくしようという意図があったとされる(山﨑耕一『フランス革命』)。特定の人物を告訴する場合には、公安・保安委員会の事前の承認が必要とされた。
フランス革命の恐怖政治の中でも、プレリアル22日法の制定は「大恐怖政治」の始まりと言われる理由が確かにあった。パリでは、革命裁判所が設置された93年3月10日から同法が制定された6月10日まで、死刑判決の数は1日平均3名弱だった。それが、その日から7月28日(テルミドールのクーデタの翌日)まで、死刑判決の数は1376名、1日平均28名強に激増したのである。だが、山﨑耕一氏も指摘するように、それは裁判および死刑判決がパリに集中した結果であり、むしろ全国的には処刑は減ったほどである。それでも、「大恐怖政治」と語られるようになったのは、もちろんパリの住民が連日のように処刑を目撃していたこともあるが、なにより「政権」に対して批判的な勢力が抱いた不安の表明という側面があった(同上)。
「政権」と言っても、その実、ロベスピエールとその周辺に対する不安である。5月8日法に続いて同法を提案したのも、サン=ジュストとともにロベスピエールの盟友だった、ジョルジュ・クートンである。フランス中部オーヴェルニュの町に生まれたクートンは、クレルモン=フェランで弁護士として活動し、「虐げられた人々」の弁護を担当して評判を得たという。もともと幼い頃から関節炎に悩まされ、20代後半頃から歩行が徐々に困難となり、移動には車椅子を必要とするようになったが、それでも革命が勃発すると、これに賛同し、クレルモン=フェランの裁判所裁判長に就任、さらに91年9月35歳のときに憲法制定国民議会の議員に選出された。

続いて国民公会議員に選出されたクートンは、山岳派の熱狂的な支持者となり、ロベスピエールの思想に共鳴、側近となる。演説の名手でもあった。プレリアル22日法も、ロベスピエールの指示でクートンが作成したという印象を持たれてきたが、実際はクートンの主導で作成されたと今では考えられている。ロベスピエールがこれを支持したのは確かだが、彼が同法について作成段階から積極的に関与した証拠はない(Leuwers, Robespierre, 2014)。
いずれにせよ、恐怖政治に批判的な議員たちにとって、ロベスピエール「一派」が不安の根源であり、側近が主導していようがいまいが、不安の元凶はロベスピエールにあった。少なくともそのような心象、「イメージ」が同法の制定によって先行して膨張していったのである。
フルーリュスの勝利
プレリアル22日法は「大恐怖政治」の始まりとともに、今から見れば恐怖政治の終わりを予告するものでもあった。その点で重要なのは、次に逮捕・処刑されるのは自分かもしれないという議員たちの恐怖だけではなく、同法をめぐって公安委員会内部に亀裂が生まれたことが決定的に重要だった。クートン、そしてサン=ジュストは革命の再編を急ぎすぎたのである。
その中でロベスピエールの演説が同僚議員たちの不安と対立をいっそう深めたことは間違いない。クートンの提案を支持した国民公会での演説で、「今日ほど難しい状況はない」と切り出したロベスピエールは、いまだに陰謀家ないし「祖国の敵」がこの中にいると宣言、自由に対する犯罪を罰する革命裁判所の機能の強化を目指す同法案への支持を表明した。それは「真理」であり、同案への反対者はそれだけで分裂をもたらす〈敵〉であるとさえ言うのだ。
公共善への愛に等しく燃える人々の間に分断があるのは自然ではない(拍手)。祖国の救済に献身する政府に対して、ある種団結して立ち上がるようなことは自然ではない。市民諸君、あなた方を分裂させようというのか[議場では「違う、違う」と至る所で声が上がる。「分裂させることはない」]。市民諸君、あなた方をたじろがせようとする者がいるのか。(中略)われわれは公共的な暗殺者を追及するため、個人的な暗殺者に身をさらしている。われわれは立派な死を欲するものであるが、国民公会と祖国は救われただろう(拍手喝采)。
そして、演説はこう締め括られた。「祖国への愛に燃える人なら誰しも、その敵を捕え、打ち倒す手段を熱く歓迎するだろう」。それはあたかも「状況」(必然性)の論理に従って、革命裁判所を効率化する同法に反対する議論の余地は最初から排除されているかのようだった。また、ここで「政府」の位置づけが変わっていることにも注意したい。いまや自分たち(公安委員会)が「(革命)政府」であって、これに団結して反抗することは認められえないのだった。
翌日、委員不在の議場では、オワーズ県選出のブールドンが前日に提案されたプレリアル22日法に対して、議員の弾劾・逮捕には国民公会の承認を必要とすべきだと主張、それを条文として同法に付け加えた。しかし次の日、クートン、そしてロベスピエールがすぐさま反駁した。
先の発言者は議論の中で、委員会を山岳派(モンターニュ)から切り離そうとしたのだ。国民公会、山岳派、委員会、これらは同一のものである(拍手)。自由を真に愛する人民の代表者はすべて、祖国のために死を覚悟する人民の代表者はすべて、山岳派である[議場では新たに拍手が広がり、国民公会議員たちは立ち上がって賛成と忠誠の意を示した]。
ブールドンは、自分が「党派の長のように」されるのは本意ではないと言って反論を試みようとしたが、ロベスピエールは私がまだ発言していると制して演説を続けた。「そう、山岳派は純粋で崇高であって、陰謀家は山岳派ではないのだ」。彼らは党派を結成するや、陰謀家たちを集め匿うことを目的に偽善的な反対を行っている。それは架空の話ではなく、現に今、委員会提案に反対する者たちがいる。陰謀は「事実」によって証明されたのだ。こうしてロベスピエールの陰謀論が再び前景化し、このダントン派に近い議員が前日に行った提案は取り消された。
これに対して、ロベスピエールとその周辺への批判や怨恨が徐々に顕在化してくる。この頃公にされた事件として、5月12日に保安委員会に逮捕されたカトリーヌ・テオ(1716-94年)という女性の事件があった(6月15日に議会で同件が報告された)。彼女は自称預言者で、ロベスピエールは「最高存在の代理人」で神聖な使命を帯びていると唱導していた。そこで、保安委員会は彼女を逮捕したのだが、それはサン=ジュスト主導で公安委員会に――それまで保安委員会の管轄だった――警察の部局が設置されたことへの腹いせだったとも言われる。彼女を敵国イギリスの手先として扱い、ロベスピエールの評判を落とそうとしたのである。
他方で、対外戦争の方は戦況が好転しつつあった。94年春には、ヴァンデーの「反乱」がほとんど鎮圧され、その兵力を対外戦争に向かう部隊に差し向けることができ、旅団の再編成が進んだ。南部では、革命軍がピレネー山脈付近の各地を奪還しスペイン軍を追い払うことに成功した。北部ベルギー戦線でも勝利が続いた。6月25日には、7万5千人のフランス軍が5万2千人のオーストリア軍と対峙し、翌日フルーリュス[シャルロワから約20キロ北東にあるベルギーの町]付近でフランスの勝利が決定的となった。このフルーリュスの戦いでは、初めて気球が戦地に投入され、フランス軍の情報収集に大いに活用されたことはよく知られている。
戦勝の知らせは国民公会にも逐一届けられ、毎週のように祝われたが、フルーリュスの勝利を大々的に祝賀する行事は行われなかった。政府が暴動に発展することを警戒したためとも言われる。また、対外的な危機感が薄らいでゆくと、国内の対立が露見するようになる。政府(公安委員会)内部では、主に軍事部門を担当するロベール・ランデやラザール・カルノと、その戦いの勝利にも派遣議員として立ち会ったサン=ジュストらとの主導権争いが活発化した。なお、サン=ジュストがほとんど北部に派遣されていたプレリアル1ヶ月間の法令約6百のうち、ランデとカルノがそれぞれ約210と180通発令したのに対して、ロベスピエールはわずか14、クートンは8通の発令にとどまった(Palmer, Twelve Who Ruled, 2017 [1941])。
フルーリュスの勝利の翌日(6月27日)、ロベスピエールはジャコバン・クラブで、対外的な危機がいったん去ると対内的な危機が顕在化する、あるいは裏で拡大すると訴えた。
ここで素直に打ち明ければ、われわれが外国の敵を打ち負かせた瞬間は、国内の敵がこれまでになくぬけぬけと彼らの卑しさと図太さをさらけだす瞬間である。われわれは暴君に対する勝利を勝ち取ったとき、隠れた中傷や裏切りの陰謀が目覚め拡大することで、国民公会を消滅させ、われわれの仕事の成果を剥奪しようとしていることに気づかされるのだ。
さらに次のように言うとき、議場にいた議員たち、例えばかつてパリに召喚されたような、脛に傷をもつ元エベール派議員たちはどう思っただろうか。ひどく恐怖したことは想像に難くない。「公安委員会は国民公会の議員全体、また尊敬すべき個々の議員を攻撃しようとしていると信じさせようとする、堕落した人間の一団がいることを知ってほしい」。
同演説では、テオ事件にも言及されている。ロベスピエールによれば、その事件を明るみに出そうとした人々の背後で真の陰謀が隠されようとしている。彼はそれを狂信家たちの「エベール主義」と呼ぶ。「あらゆる狂信家たちは、危険な信心家〔=テオ〕の仮面の下にみずからを隠し、さらけ出されるのではないかという恐怖を隠している」。「エベール派」(の残党)が一人の女性を使って「最高存在の祭典」をパロディー化することで、祭典の「崇高で感動的な印象を消し去る」手段として同事件を利用し、己の罪から逃れようとしているのだと糾弾した。

ロベスピエールが内部に党派=〈敵〉が存在すると発言し、「良き市民の第一の義務は、だからそれを公に告発することである」と言えば言うほど(7月1日ジャコバン・クラブ)、内部の人間は不安に駆られ、この苦境をなんとか脱しなければならないと思うのはなかば必然だった。
「孤独な愛国者」
プレリアル22日法は、政権内部の対立を決定的にし、対外的な危機の後退がそれを表面化させる遠因となった。ついにメシドール(収穫月)11日(6月29日)、公安委員会と保安委員会の合同会議の席上で、ラザール・カルノがサン=ジュストに向かってこう言い放った。「君とロベスピエールは愚かな独裁者だ」。
ロベスピエールはどう反論したか。いや、彼は反論することなく、退場してしまったのである。その後、失脚する直前まで彼が委員会そして議会に姿を現すことはない。この態度をどう理解したらいいだろうか。このとき、ロベスピエールの人気はかつてほどではなく、「独裁者」と批判する手紙もいくつか届いていたとはいえ、なお根強い人気を保持していた。ただ、その発言は議会ではなく、彼らが孤立しつつあった委員会でなされたことは記憶されていい。
政治家ロベスピエールの精神はここに立ちすくみ、前進を止めたわけではない。自身のフィールドであるジャコバン・クラブの演壇に立ち、弁論を続けたのである。2日後、同クラブで登壇したロベスピエールは、「神が私を暗殺者の手から引き離すことを真に望んだのであれば、それは私にまだ残る時間を有効に使うよう責任を負わせるためである」と、革命の成就に身を捧げる覚悟を改めて示した。そのうえで、革命裁判所は国民公会を打倒し自由を破壊するために組織されたというデマが広がっていると指摘、ロンドンでは自分のことが「独裁者」と呼ばれ、パリでも同様な中傷がなされていると訴えた。
パリでは、革命裁判所を組織したのは私であり、この裁判所は愛国者と国民公会の議員を破滅させるために組織されたのだと言われる。そして私が国民代表の暴君であり圧政者として描かれている。(中略)まさにそうすることで、人々は〔真の〕暴君たちを許しているのであり、勇気と美徳だけを持つ孤独な愛国者を攻撃しているのだ……。
ここでみずからを「孤独な愛国者」と称している。この言葉には、そのときの彼の思いが表白されているだろう。これに対して傍聴席にいたある市民が「ロベスピエール、すべてのフランス人があなたの味方だ」と叫ぶ声が聞こえたが、「清廉の士」は決然としてこう吐露した。
真理は犯罪に抗する私の唯一の隠れ家である。私は信奉者も賛辞も欲しない。私を弁護するものは、自分の良心の内にあるのだ。私に耳を傾けてくれる市民には、思い出してほしい。もっとも無垢で、もっとも純粋な歩みが、中傷にさらされたことを……。
なるほど、暴君の権力では「私の勇気」を挫くことはできず、依然として「私は自由と平等を同じ熱情で擁護するだろう」。しかし、その擁護は「自分の良心」の内で行われると言うのである。ここには、修辞(レトリック)以上の意味があっただろう。彼の精神史を振り返れば、青年ロベスピエールが目指したのは「名誉」ではなかったことを思い出して頂きたい。
第3回「「名誉」を超えて」に記したように、彼はかつて君主政のもとで人間が求めたような他者に評価される「名誉」を否定し、それ自体として価値のある(共和政の原理であるとされる)「美徳」の必要を説いた。それは哲学的《名誉》とも言い換えられ、次のように説明されていた。再掲しよう。
哲学における名誉とは、気高い純粋な魂がそれ本来の威厳さのために持つ甘美な感情以外のものではなく、理性をその基礎とし、義務感と一体となるものです。それは、神以外に証人はなく、良心以外を判断としないもので、他人の視線からも離れて存在するものでしょう(1785年11月アラス王立アカデミー入会演説)。
ロベスピエールが合同委員会から退場したとき、彼の精神は自分の良心、内面のうちに退却してしまったと言わなければならない。しかし、それは他人から見れば文字通り「後退」だったかもしれないが、彼本人にとってはおそらくそうではなかったはずである。彼が希求したのはいわば〈内面の共和国〉だったのだから。それは内面(心)で一致した〈われわれ〉の共和国でなければならなかった。ところが、「最高存在の祭典」を構想・実行する中、革命の理想が「公私が重なるかたちで一つの信仰へと結晶し」たように見えたまさにそのとき、実際には公私が一致することなく、すでに乖離し始めていたのではなかったか。
その後、何度かジャコバン・クラブの演壇に立つが、その多くは革命政府への敵対者たち、カリエやフーシェ、バラス、フレロン、タリアンといった、有力議員の「陰謀」を告発するものだった(7月9日)。彼らはいずれも、諸地方で反革命と称して市民を容赦なく弾圧した者たちである。ある事件をめぐって同クラブを追放されたフーシェに至っては、「卑しい軽蔑すべき詐欺師」と呼んで糾弾した(7月14日)。「恐怖は彼ら〔=旧エベール派〕が愛国者たちに沈黙を強いる手段だった。彼らは沈黙を破る勇気を持つ人々を監獄に投げ込んだのだ。これこそ、私がフーシェを非難する犯罪である」。その日は奇しくも、フランス革命5周年の記念日だった。

議員同士の不和が深まる中、民衆の間でも革命や戦争疲れが徐々に広がりを見せ始める。フルーリュスの勝利に続いて7月半ば頃になると、首都パリでは友愛宴会なる市民運動がにわかに活発になる。それは、夜になると住民たちが集まって議論し、革命の終わりを願うものだったが、そこには、革命政府や革命裁判所は終わってほしいという期待が暗に含まれていた。
7月16日、ベルトラン・バレール[フランス南西部タルブ出身で、弁護士を経て全国三部会議員となり、のちに公安委員会入りを果たす]は議会で、同宴会について「エベールやショーメットの遺言執行人」による新たな陰謀であり、「純粋な感情と不実な意図、共和的な行為と反革命的な原理の危険な融合」だと非難した。
その夜、ジャコバン・クラブでバレールに続いて登壇したロベスピエールは、彼らは「友愛」という意味を履き違えていると批判した。「友愛は美徳の友のためにしか決して存在しえない」のであって、「不協和(=革命政府批判)」があるところに友愛は存在しえず、それは友愛に値しない、愛国者ではない。「友愛は心の一致であり、原理の一致である。愛国者は愛国者としか調和することができない」。そのような熱情的な[=真の]愛国者に反対する運動には、陰謀家が巧妙に紛れ込んでいるのだ。
そう告発したロベスピエールが披瀝するのは、《単一性(同質性)》を宿した〈民衆=人民〉の原像と、友敵の論理である。「人民がそれに真に値する態度の中で現れ出るのは、その敵から分離されたときだけである。(中略)しかし、われわれが人民をテーブルによって分断させるなら、それはもはや人民ではない。それは党派でしかなく、愛国者と貴族の混合である」。
さらにはこう述べる。「われわれを一致させるのは、美徳と友情の神々しい魅力である」。ここでロベスピエールにおいて〈民衆=人民〉のイメージが再び昇華され、〈内面の共和国〉が完成されようとしていたが、その反面、彼は現実に運動する民衆からはかなり飛躍したところに行ってしまったのではないだろうか。
「ロベスピエールはパリを理解せず、もはや耳を傾けていない」と、著名な伝記作家は友愛宴会に対する彼の態度について記している(Leuwers, op. cit.)。なぜ、このようなことになってしまったのか。それは彼自身が唱えた革命の論理、「必然性」の結果だったのだろうか。クーデタ前夜だった。
-

-
高山裕二
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
この記事をシェアする
「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 高山裕二
-
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら