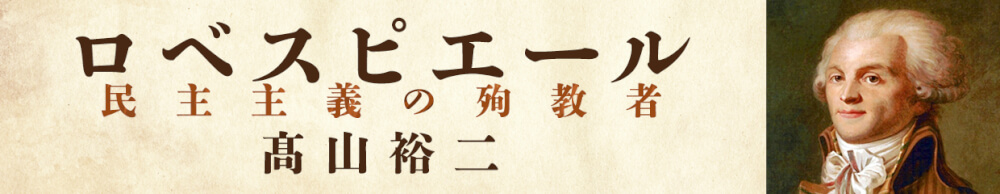革命の再編と「制度化」
1794年4月1日(ジェルミナル12日)、政府にあたる執行会議を廃止、代わりに12の委員会が設置され、公安委員会が名実ともに執行権力機関となった。また、同委員会のなかに警察局が新設された。さらに同月15日、サン=ジュストが、国民公会で公安委員会を代表して治安全般に関する演説を行い、両派の粛清後の革命再編プランを提示したのである。
冒頭、「市民諸君、党派を破壊するだけでは十分ではない。彼らが祖国に対して行った悪事をさらに埋め合わせる必要がある」と演説し始める。そこでサン=ジュストが訴えたのが、治安の強化であり、そのために刑事裁判所の権限を強化することだった。「刑事上の裁判官の弱さが陰謀を大胆にし、あなた方の権威を弱め、法令の威厳を侵害するとともに人民を党派の悪意に委ねたのだ。(中略)そのように処罰されない状態を終わらせる時だ」。彼が演説で強調したのは、主要な党派を粛清した今、例外的な恐怖政治に頼らない革命の「制度化」の必要だった。
なるほど、「すべての悪は〔政府〕権力の濫用に由来する」一方、「人民は正しい」。それでも、彼らは有力者に――実際に党派やその指導者が支持されたように――騙されることがあり、権力の濫用を防ぐ「市民制度」が必要である。サン=ジュストは、議員たちにこう訴える。
市民制度を作ろう。そうした制度について人々は考えてもいないが、それなしに自由は存続しないのだ。革命が終わっても、それが祖国への愛着や革命の精神を維持するのである。それによってこそ民主主義の完成を知らしめることになる。つまり、あなた方の計画の偉大さを知らしめ、それに比べて敵たちが歪んでいると示すことで、彼らの消滅の時期を早めることになるのだ。
この種の主張は、エベール派とダントン派、両派の追放によって初めてなされたわけではない。ヴァンドーズ法令(第16回)につながる彼の演説ですでに指摘されていた(2月26日)。「君主政には政府しかないが、共和政には多くの制度があり、習俗を抑制したり、法律や人間の腐敗を止めたりする。こうした制度を欠いた国家は、見せかけの共和国でしかない。(中略)われわれには、共和政の魂である制度が欠けているのだ」(強調原文)。「このように、悪徳を変形させる強力な制度によって道徳が実践されない統治では、政治の運命は才気をひけらかす人間や隠された情念に任せて変化することになる」。粛清は革命の再編、「制度化」を急がせた。
サン=ジュストがその演説に基づき提案したのは、公安委員会の権限強化や革命裁判所のパリへの一極集中、元貴族やフランスの交戦国の人間をパリや港町から排除する法令だった(地方の革命裁判所の廃止は、クートンが提案する5月8日の法令による)。これらは「共和政の魂である制度」自体ではなく、その設置に向けた環境整備とも言うべき政策だった。
では、政治に道徳を実践させるという「強力な制度」とは何か。それに答えを出すのは、後述するようにロベスピエールである。それは政治的であると同時に、宗教的・道徳的な制度となるだろう。この点で触れておくべきは、同月19日(ジェルミナル30日)、非キリスト教化運動を主導し、派遣先で過酷な弾圧を繰り返した議員たちが再びパリに召喚された事実である。バラスやフレロン、カリエやフーシェに続いて21名の議員が一挙に召喚された。これは弾圧の行き過ぎを抑止する警察・治安上の措置であると同時に、宗教・道徳上の装置だった。
とはいえ、同日、ロベスピエールはまたしても体調を崩し自宅療養に入る。休養は、恐怖政治にとって、また政治家ロベスピエールにとっても一つのクライマックスを迎える「最高存在の崇拝」演説を行う5月7日まで、2週間以上に及ぶ。彼については伝記作家が身体の弱さを指摘しているが、それに精神的ストレスが加重され、心身ともに疲弊していたのは確かだろう。
それでも、サン=ジュスト同様、革命の混乱を収拾する必要に迫られていたロベスピエールには、革命の理想に身を捧げる強い覚悟があった。それは、「ジャン=ジャック・ルソーの魂への献辞」(第4回)以来一貫していただろう。2年前の演説でも、ブリソへの反論が目的だったが、その中で自己の運命について次のように語っていた(92年4月27日)。
自由に情熱を傾ける魂を授け、暴君たちが支配するなかで私を産ませた神、党派や犯罪が支配するなかでも私を存命させた神は、我が国を幸福と自由に導くに違いない道を私の血で示すことをおそらく求めている。私は喜んで、この甘美で栄光ある運命を受け入れよう。
このなかば運命論的な自己規定のうちには、神(天国)へのある種の信仰さえ読み取れる。そして、ロベスピエールの革命への想いは、革命の経過とともに公私が重なるかたちで一つの信仰へと結晶しようとしていた。今回の療養期間に、彼はそれを形にするべく苦闘し、自己の革命の理想を〈公共の信仰〉にまで昇華する「制度」を考案していたのである。それが5月7日の演説で発表された「最高存在の崇拝」、いわば革命のための宗教=革命宗教だった。
前述のように、革命の「制度化」の必要がサン=ジュストらによって意識され始め、なによりその構想にはロベスピエール個人の精神史が深く関係していただろう。とはいえ、「革命礼拝」は彼の発案ではなく、それ以前の革命を祝う祭典によって徐々に形作られてきた。特に彼自身が意識したのは、前年に催された「自由と理性の祭典」(理性の祭典)(第15回)である。
では、「最高存在の祭典」の特色とは何だったのか。それを理解するには、「理性の祭典」とともに、それに先立つ一連の革命祭典について瞥見しておく必要があるだろう。そのうえで、彼の「最高存在」をめぐる思想とその祭典の反響を確認することにしたい。
革命下に音楽が流れる
革命礼拝とは、革命を祝う祭り(祭典)の一種である。その全国規模での最初のものが、1790年7月、革命勃発1周年を祝って開催された全国連盟祭だった。連盟祭自体は前年11月から各地方で連盟兵が主体になって行われていたものだが、これらが全国規模で初めて統一され実施されたのが全国連盟祭だった。
すでに見た通り(第8回)、そこに設置された「祖国の祭壇」に地方から詣でに来る旅はさながら「巡礼」の様相を呈していた。その祭りは革命初期のハイライト、革命のポジ像として語られてきたものである。例えば、歴史家のジュール・ミシュレは『フランス革命史』(1847-53年)の中で、「あまたの連盟祭はもういらない、無用だ。必要なのは一つの連盟祭のみ、フランスのみだ」と書いたあと、興奮さめやらぬかのように「連盟祭」の項目をこう語り始める。
1世紀ものあいだつづいた論争の果てに、この信仰、この無邪気さ、この和合への大飛躍。これは、あらゆる国民にとって大きな驚きであった。まるで不思議な夢を見ているかのようだ。みな唖然としていた。感動していた(桑原武夫ほか訳)。
ただ、集まるだけでは「国民」なるものに触れ、一体感を得ることはできない。舞台設定もさることながら、市民の能動的「参加」が必要で、それによって熱狂を生み出す必要があった。そこで大きな役割を果たしたのが、歌やダンスである。祭典、礼拝には音楽がつきものなのだ。
革命の時代、革命をテーマにした歌が数多く作曲された。1790年には261曲、91年は308曲、92年は325曲、93年は590曲、94年には701曲の新作が作られたという(アデライード・ド・プラース『革命下のパリに音楽は流れる』1989年)。ただ、1790年の全国連盟祭で演奏されたのは、当時「最高の作曲家」と目されたフランソワ=ジョゼフ・ゴセック(1734-1829年)作の荘厳な『テ・デウム』であり、それは旧来の宗教色の濃い楽曲だった。民衆は基本的に聴くだけで、「参加」は想定されていなかったのである。実際、国王列席のもと、「祖国の祭壇」でミサをあげたのもオータンの司教タレーランだった。

ところが、全国連盟祭の会場になったシャン=ド=マルスの巨大な円形競技場の造成には、すでに民衆たちが「参加」していた。都市パリの観察者として著名な作家のルイ=セバスチャン・メルシエ(1740-1814年)は、「この驚くべき、そして永遠に忘れ難い友愛の実例」を書きとめ、祭典数日前の『パリ通信』も次のように伝えた。
シャン=ド=マルスでの作業の有様を描くのは不可能だし、書かれたものは、とても現実には及ぶまい。市民たちのあの雑踏を、あのひどくつらい仕事をしている人たちのあの活力と陽気さを、実際に目の当たりにしなくてはならないのだ……。祖国の祭壇の建設に率先して協力しているのは同業組合ではない。楽隊がまっ先に進み、人々はシャベルやつるはしを肩にかついで三人ずつ組になる。(中略)全員が声をそろえて歌う。「サ・イラ、サ・イラ、サ・イラ」(長谷川博史訳)。
革命を祝うことで「国民」としての一体感を覚えたのは、祭り後に地元に帰った総勢5万人の連盟兵だけではない。一体感を醸成したのは、このイヴェントに「参加」したパリの労働者たちでもあり、歌いやすく覚えやすい音楽がそれに一役買った。同年、元軍人の大道歌手ラドレの作った『サ・イラ』は、「すでに無償奉仕の労働者たちの伴侶になっていたのだった」。
その後、ミラボの葬儀やヴォルテールの遺骨のパンテオン葬など、革命の祭典が行われたが、国民主体の葬儀のためにゴセックが作曲した『葬送行進曲』が悲痛な情感を演出した。こうして祭典やそこで演奏される歌も「世俗化」していったが、それには「聖職者市民化基本法」(第9回)に始まる非キリスト教化、あるいは国王の逃亡(その後の処刑)が影を落としていた。〈象徴〉、あるいは聖性の代位が生じたのである。1792年の第3回全国連盟祭では、詩人マリー=ジョゼフ・シェニエ(1764-1811年)作詞、ゴセック作曲の『自由への讃歌』が演奏されたが、宗教色の濃い『テ・デウム』を歌うことはもはや問題外となっていた。このとき、マルセイユからやって来た連盟兵が道中歌って有名になったのが『ラ・マルセイエーズ』だった。
こうして革命それ自体が礼拝の対象になってゆく経緯と、革命が既存の宗教(キリスト教)から脱出する過程は表裏の関係に見える。そして、お互いに共通するのは民衆が集まって歌を聴き歌うという「儀礼」だった。さらに、国王処刑の前夜に近衛兵に暗殺されたルペルチエや、マラといった革命の「殉教者」の葬儀を通じて、革命祭典は礼拝対象を加えてゆくが、この流れを過激に推し進め、利用しようとする党派が現れる。それが前出のエベール派で、彼らの影響のもとでパリのコミューンが主催したのが「理性の祭典」だった。
このとき、地方で非キリスト教化運動を先導したエベール派のフーシェは、派遣先のヌヴェール県で十字架や聖者像などの破壊を指示するとともに、「墓地令」(93年10月10日)を発し、それが非キリスト教化運動の一つの範例となる。11月7日、パリでは大司教ゴベルが聖職の放棄を宣言するなか、10日、同県出身のエベール派指導者ショーメットに導かれてパリのコミューンがノートルダム寺院を占拠、カトリックの祭具を取り払い、「理性の神殿」と名を改め「理性の祭典」を挙行したのである。
寺院内に作られた小高い山の周りに小さな円形の神殿が設けられ、その上に「哲学に捧ぐ」という銘が掲げられた。入り口にはヴォルテールやルソーなど「哲学者(フィロゾフ)」の胸像が置かれ、中央にある理性の祭壇は「真理」の松明によって照らされ、その周りを白い衣装をまとった乙女らが囲む。そこに「自由」に扮した女性が神殿から姿を現すと、シェニエ作詞、ゴセック作曲の新作が演奏された。集まった民衆は歌を歌って踊り、熱狂を爆発させた(前掲書『革命下のパリに音楽は流れる』)。

2週間後、パリ市当局はパリ中の教会の閉鎖を決定した。その二日前にロベスピエールがジャコバン・クラブで行ったのが、あの痛烈な「狂信」批判演説だった。非キリスト教化の流れに警鐘を鳴らしたのである。「理性の祭典」を狂信的・無神論的だと糾弾し、それは革命そして共和国の存続に必要な信仰ではないと切り捨てた。「神が存在しないのであれば、それを発明しなければならない」とさえ語ったロベスピエールにとって、確かに革命とその原理の維持にはある種の宗教が必要だったが、それは理性を崇めるような信仰ではなかったのだろう。
ところで、その神の「発明」の一文を聞いたことのある読者がいるとすれば、それはおそらくロベスピエールではなくヴォルテールの言葉として記憶されているだろう。実際、それは彼の『三人の詐欺師の本の著者への書簡』(1769年)という作品に出てくるフレーズである。
確かに、ヴォルテールは旧教を厳しく批判し、理神論を唱えた。理神論とは、一言で言えば、神の存在を啓示によらず理性によって(=合理的に)説明しようとする立場を指す。ロベスピエールも、奇跡・預言・啓示などを前提にしない点では合理的で、理神論的に見えるが、それらの存在をいっさい否定するわけでもない。また、信仰は理性によって説明し尽くせるものではなく、心性に基づき、それに訴えるものでなければならない。だからこそ、「最高存在」の実在を信じる礼拝が必要で、そのために合奏といった「儀礼」も必要だったはずである。
「理性の祭典」が、同じく革命を歌って祝うと言っても、また理性の力を信じると言っても、ロベスピエールによれば、そのためにこそ「最高存在」を信じることが必要だった。
最高存在の祭典
非キリスト教化運動を政治的に率先して利用したエベールらが排除されたあと、療養期間を経て国民公会に復帰した日、ロベスピエールは「宗教的・道徳的観念と共和国の諸原理の関係について、および国民の祭典について」と題する演説を行う(94年5月7日)。
精神の世界は、物質の世界に比べてはるかに対立と謎に満ち溢れているように見える。(中略)物質の世界はすべてが変わったが、精神と政治の世界はすべてが変わらなければならない。世界の革命の半分はすでになされたが、もう半分がなされなければならない。
未完の革命、それは理性によって精神の世界が照らされることで完遂されるはずだ。そのためには、「今日まで人間を欺き堕落させる術」であった統治を、「人間を啓蒙し、より善良にする術」に代えなければならない。つまり、人間の情念を正義へと導くことを目的にした統治、「社会制度」が必要であると言うのだ。これは、前述のサン=ジュストの主張とも共振する。
なるほど、「市民社会の唯一の基礎、それは道徳である」。とはいえ、「哲学者たちの書物に残された道徳的真理」を崇めるだけなら、それは「理性の祭典」の主催者たちが企図したものとさほど変わらないはずである。ロベスピエールにとっては、その祭典を批判した際に宣明したように、「最高存在」=《神》が存在しなければならなかった。
そこで、「人々〔陰謀家たち〕が消滅を望んだあらゆる私心のない感情やあらゆる偉大な道徳の観念を呼び覚まし、昂揚させよう。友情の魅力と美徳の紐帯によって、彼らが分裂を望んだ人間たちを結びつけよう」と述べたあと、次のように続ける。
では誰が、神は存在しないと人民に告げるという使命を君に与えたのか。おお、君はこのような不毛な教義に夢中になり、祖国にはけっして熱中しないでいる。(中略)人間は無であるという観念が、人間〔の霊魂〕は不滅であるという観念よりも純粋で高潔な感情を抱かせることがあるだろうか。同胞や自分自身への敬意、祖国への献身、圧政を打ち倒そうとする大胆さ、死や悦楽への軽蔑の念をいっそう抱かせることがあるだろうか。
まず、《神》(=最高存在)が存在し、また霊魂が不滅であるという観念を信じなければならない理由、それは彼岸でしか救われない事柄があるからだ。それによって、美徳のため、祖国のために、たとえ不遇の死を遂げようと、人は慰められ、道徳・真理への熱意はいっそう強くなるとロベスピエールは考えた。「最高存在と霊魂の不滅の観念は、絶えず正義に立ち返らせるものである。それゆえ、社会的であり、共和的である」(拍手喝采)。
ロベスピエールにとって、「宗教感情」が人間の力を補って道徳を魂に刻み込んでくれるとすれば、最高存在は市民社会にとっても共和政にとっても有用である。ここで、同僚議員に語りかける彼の視点は宗教者ではなく、立法者のそれである。「立法者の目で見れば、世界にとって有益で、実践して良いものはすべて真理である」。つまり、そこには政治家の視点で有益であれば――場合によってはフィクションを含んでも――利用するという姿勢が見られる。それはルソー以上にマキアヴェリ的にも見えるが、肝心な点は、「人民の主権とその全能性以外の教義を認めない」(「墓地令」)というような「理性の祭典」を計画した過激派のように、人間の理性ないし人民それ自体を信仰するような姿勢とは一線を画しているということである。
同様に、「信仰の自由」、すべての宗派の信仰の自由がここで改めて主張されるのも、「立法者」の視点からだろう。すなわち、「公共の秩序」の視点から――特に地方では多くの住人がカトリック信仰を根強く抱いていたことを彼は経験上知っていた――、強制するよりは住民がみずから「自然の普遍的な宗教」と和解していくことが期待されたのである。諸信仰を包摂しうるような礼拝には《神》が必要であって、そのかぎりで無神論は唾棄されなければならない。ここに、革命宗教が「理性の祭典」であってはならないもう一つの理由があった。
では、信仰の自由を保障しながら「最高存在」と呼ばれる《神》ないし霊魂の不滅が崇拝されるとはどういうことか。それはどのように維持、「制度化」されるのか。ロベスピエールはそれを「正しく理解された国民祭典の制度」と表現する。それは一面ではこれまで挙行されてきた革命祭典と似通っている。例えば、「自由への熱狂、祖国への愛、法の尊重」などの覚醒を目指すことや、自由や祖国の英雄の記憶を顕彰することなど。ただし、「すべての祭典が最高存在の庇護のもとで祝われること」を条件とする。つまり、「最高存在」の庇護のもとで従来の革命祭典を一つにまとめ上げることが目指されたのであって、それが「制度化」の実相だった。
逆に言えば、「最高存在」の崇拝を唱えながら礼拝の対象となっているのは共和国、その「政治制度そのもの」と言うこともできる。この点で、他のすべての革命礼拝とは異なることが歴史家によって理解されてこなかったと、革命史家のアルベール・マチエは喝破する(「ロベスピエールと最高存在の崇拝」1910年)。と同時に、マチエによれば、それまで他の多くの議員にとっても祖国は崇拝の対象であり、その「信仰」は既存の宗教の礼拝を妨げるものではなかったという点で、ロベスピエールの唱えた革命宗教は彼の独創というわけではなかった。
演説の最後に提案・採択された法令では、最高存在の実在と霊魂の不滅を宣言し、それを礼拝する義務、および祭典が開催される祝日なども定められた。ひと月後の6月8日に「最高存在の祭典」を開催することも決められた。そして6月4日、プレリアル(草月)16日、全会一致で国民公会議長に選出されたロベスピエールが「最高存在の祭典」を主宰することになった。
それはあの「球戯場の誓い」の名場面を描き、のちにナポレオンお抱えの画家となる、ダヴィドの周到な計画に沿って進行した。まず、国民公会の置かれたチュイルリ宮殿(=国民庭園)前にトランペットや太鼓の音を合図に群衆が集まってくる。そこで、庭園の泉のほとりに置かれた無神論や利己主義をかたどった人形に火がつけられた(それに代わって現れた「叡智」の像は黒ずんでいたが)。その後、ロベスピエールの演説に続いて、やはりシェニエ作詞・ゴセック作曲の『最高存在への讃歌』が演奏され高揚感を演出。最初の詩節はこんな具合である。
ペテンに踏みにじられている真理のみなもと
生きとし生けるものすべてを永久に保護するもの
「自由」の神 「自然」の父 そして
創造主にして秩序を維持するものよ
おお 汝こそは 唯一の非被造の存在 偉大なるもの 必要不可欠のもの
美徳を生むものにして法の原理
独裁権力の変わることのない敵対者だ
フランスはいま汝の前に立つ (宇佐美斉訳)
演奏が終わると、一行はロベスピエールを先頭にシャン=ド=マルス(=統一広場)に向かった。そのなかには、トランペットを首にかけた騎兵隊や、太鼓を抱えた国立音楽院[革命勃発後に教会ではなく国家のもとに音楽教育が集約されるなか、1793年に国民衛兵音楽学校に代わって設立された学校]の学生もいた。祖国の祭壇の広場には巨大な山が造設され、中腹には大きな柱の頂に〈人民=民衆〉を表す男性像を設置、山の頂上にはフランス人民の解放の象徴である「自由の木」が植えられていた。人々がその山を登っていくと、頂上に配置された楽団によってトランペットが吹かれ、再び讃歌が演奏された。『ラ・マルセイエーズ』も鳴り響き、群衆の昂揚は一気に高鳴ったのだった(前掲書『革命下のパリに音楽は流れる』)。

「最高存在の祭典」は、新たな時代の幕開けを予感させた。55万人集まったとされる祭典はパリだけでなく、全国各地に大きな反響を呼んだ。祭典への祝辞は全国から1600通以上届いたという。従来と違って、警察官らによる形式的な祝辞だけでなく、一般民衆から感動を伝える文章がいくつも届けられた。もともと祭典前から讃歌や礼拝について各地から提案がなされる熱狂ぶりで、住民が初めて全国的に「参加」できた祭典だったと言える(Jonathan Smyth, Robespierre and the Festival of the Supreme Being: The search for a republican morality, 2016)。
間違いなくロベスピエールは政治家として絶頂にあった。もっとも、冷笑する者もいた。ある議員は、古代ローマを引き合いに「カピトリヌスの丘〔政治経済の中心だったフォルム・ロマヌムを見下ろす丘〕からタルペーイア〔裏切り者が投げ落とされた岩壁〕はすぐそばだ」と罵った。公安委員会の元委員テュリオ(ダントン派)は、「主人になるだけでは飽き足らず、神になるに違いない」と嘲笑った(マクフィー『ロベスピエール』)。
確かに、「最高存在の祭典」以前から、ロベスピエールを独裁者や暴君とする批判はあちこちで見られた。それを象徴する事件も起きた。5月23日(プレリアル4日)、ロベスピエールの住むデュプレ家に侵入しようとしたとして、二十歳の女性が逮捕された。パリの文房具商の家に生まれたセシル・ルノーというこの女性は、取り調べでその理由を問われ、「5万人の暴君より一人の王のほうが良い」と述べたあと、こう打ち明けた。「暴君がどのような様子かを見たかった」。所持品からは、二挺のナイフが見つかった。

また前日には、「国立宝くじ取引所」職員だったとされるアンリ・アドミラという男が、同じ建物に住んでいた公安委員会委員のコロ・デルボワに発砲するという事件が起こった。供述によれば、もともとはロベスピエールを狙ったが現れなかったため、デルボワに2発の銃弾を発砲したという。さらにダントン派議員が24日、敵討を企図していたことが発覚する。これに対し議会では、狙われた政治家を英雄視する発言がなされる一方、容疑者や陰謀家たちの背後にいるとされるイギリス政府(首相ピット)への復讐心が煽られた。
二日後、ロベスピエールは議会で自分の死が迫っていることを確信しているかのような演説を行う(5月26日)。
結局、中傷や裏切り、反乱、中毒、無神論、腐敗、飢饉、そして暗殺と、あらゆる犯罪を惜しみなく生み出してきたが、彼ら〔陰謀家たち〕にまだ残るのは暗殺、次に暗殺、それからさらに暗殺である。だから喜ぼう、神に感謝しようではないか。われわれは祖国によく奉仕したがゆえに、暴政の短刀に値すると判断されたのだから(拍手喝采)。
このとき暗殺に怯えていたとも言われるロベスピエールは、直後に主宰した革命祭典で恍惚としながら何を思ったか。「最高存在」演説でも、自己犠牲の「覚悟」について改めて語っていた。「〔仮に他国に生まれたとしても〕注意深い私の魂は、君〔人民〕の栄光ある革命の全運動に飽くなき情熱で従っただろう。(中略)おお、崇高なる人民よ!私の全存在を犠牲にしよう。君の中に生まれた者はなんと幸福か。君の幸福のために死ねる者はもっと幸福なことだ」。
確かなのは、祭典で悪目立ちしたことが、「暴君」到来の印象をさらに植え付けたということである。6月17日、セシル・ルノーを含む暗殺未遂の容疑者ら54名が「国民広場」で処刑された。マラの暗殺者シャルロット・コルデのときと同様、囚人たちは暗殺者であることを示す赤シャツを着せられていた。「大恐怖政治」とも呼ばれる、恐怖政治の最後の急加速が始まった。
-

-
高山裕二
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
この記事をシェアする
「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 高山裕二
-
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら