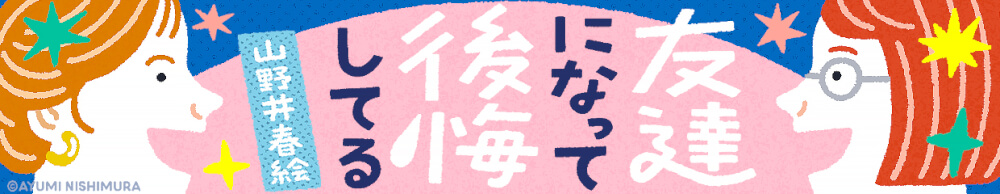第4回 「ニューノーマル」の彼方に消えた仲良し家族
著者: 山野井春絵
「LINEが既読スルー」友人からの突然のサインに、「嫌われた? でもなぜ?」と思い悩む。あるいは、仲の良かった友人と「もう会わない」そう決意して、自ら距離を置く――。友人関係をめぐって、そんなほろ苦い経験をしたことはありませんか?
自らも友人との離別に苦しんだ経験のあるライターが、「いつ・どのようにして友達と別れたのか?」その経緯を20~80代の人々にインタビュー。「理由なきフェイドアウト」から「いわくつきの絶交」まで、さまざまなケースを紹介。離別の後悔を晴らすかのごとく、「大人になってからの友情」を見つめ直します。
※本連載は、プライバシー保護の観点から、インタビューに登場した人物の氏名や属性、環境の一部を変更・再構成しています。
<藤山家>と<田中家>は、ともに一人息子を育てる共働きファミリーで、子どもが0歳児のときからの保育園仲間。一緒に初めての子育てを楽しみながら、心地よい関係を続けていた。2家族の関係に変化が生じたのは、子どもたちが小学校に入学した2020年の春以降。きっかけは、「コロナ禍」だ。今回インタビューに応じてくれたのは、藤山家の“ママ”、香奈さん(42)。新型コロナウイルスをめぐる価値観の相違からひび割れた2家族の友情は、完全に過去のものとなったという。「大人たちの分断はやむを得なかったとしても、大切な友達だった息子たちの別れは、今でも心苦しい」。「ステイホーム」の記憶も薄れつつあるなか、あのときを振り返って、今思うことは……。
「ステイホーム」中にこっそりピクニック宴会
初夏から夏へ。草いきれを感じるこの季節になると、あの日のことを思い出します。
2020年5月、「緊急事態宣言」によるステイホームが続き、気分がクサクサしていたある午後のこと。当時小学一年生だった息子と私はお弁当を持って、近くの丘の上にある公園へ向かいました。街は閑散としていて、道中、誰にも会いませんでした。空にはヘリコプターの音だけが不気味に響き、一瞬、この世の中に私と息子の2人きりになってしまったかのような恐怖を感じたのを覚えています。
丘の上の公園には、中央に大きなタブノキがあります。その下にレジャーシートを敷こうとツツジが茂る小径を歩いていくと、ふと後ろから声をかけられました。
「あれっ、香奈さん?」
振り向くと、仲良しのママ友、田中里美さんでした。
「あっちに、ダンナと翔もいるの。よかったら一緒にピクニックしない?」
息子の聡太は、同級生の翔君がいると聞いて大喜びで駆け出していきます。しかし私は躊躇しました。当時はコロナ禍がはじまったばかり。新しいウイルスがどんなものなのかもよくわからず、不安が広がっていました。誰とも接触してはいけない。食事を他の人と共にするなどもってのほか……夫からも気をつけるようにと強く言われていたのです。しかし、久しぶりに仲良しとおしゃべりができるといううれしさがまさって、私は里美さんと歩いていきました。
目指すタブノキの下、里美さんのご主人である康二さんが、キャンプチェアに座っていました。私の姿を認めて、手を振ってきます。子どもらはお昼ご飯もそっちのけで、虫取りに走っていきました。
「久しぶり、元気にしてた? 会いたかったよ、卒園式以来だね! 宴会をしたのは……ああ、新年会が最後だっけ」
康二さんが言いました。康二さんからはお酒のにおいがしました。足元には、クーラーボックスが置いてあります。暇だからここでよく飲んでいるんだ、と言いました。「ま、大丈夫でしょ!」と笑い合い、勧められて缶ビールやどぶろくをご馳走になりました。里美さんは麦茶を飲みながら、大豆肉の唐揚げやいなり寿司など、手作りのおいしい料理を勧めてくれます。私も持参したサンドイッチを出して、みんなで分け合って食べました。公園には、私と息子、田中家だけ。空は青く、心地よい風が吹いて、とてもいい午後でした。夕方まで宴会を楽しみ、マスクをつけて帰りました。
思えばあの日が、田中家と楽しく過ごした最後です。コロナ禍以前、子どもたちが保育園に通っている間は、お互いの家で宴会をしたり、キャンプへ行ったりと、とてもいいお付き合いをしていました。東北にある康二さんの実家に家族で泊めてもらったこともあります。
今、私のSNSは、康二さんとも里美さんとも繋がっていません。いつの間にか、2人のアカウントは消えていました。
主義は違えども、私たちはうまく付き合ってきた
息子を妊娠中に、関東郊外のN市に夫婦で引っ越してきました。夫は食品会社に勤め、長く東京の本社にいたのですが、N市にある工場の責任者として赴任することになったのです。私も都内の企業で働いており、すでに産休に入っていました。はじめ私は東京からN市への引っ越しには後ろ向きだったのですが、実際に訪れてみて、気持ちが変わりました。山も、川も、大きな公園もあって、ショッピングモールも近い。保育園の敷地は広く、子どもたちが泥だらけになって遊んでいます。子育てをするには理想的な場所かもしれない、と思いました。
田中家と知り合ったのは、引っ越してすぐのことです。市の「母親教室」で里美さんと出会い、意気投合。産後は家族ぐるみの付き合いがはじまりました。康二さんは駅前で鍼灸院を経営しており、里美さんは隣町にある道の駅に勤めていました。
里美さんとは「保活」も一緒に行いました。赤ちゃんを抱っこしながら市内の保育園をいくつか見学してまわったのです。なかでも心惹かれたのは、流行りの教育熱心系保育園ではなく、外遊びを重視するどろんこ系の保育園でした。運よく同じ保育園に入園させることができたのは、子どもたちの月齢が8ヶ月のとき。決定の通知はとてもうれしくて、「復職しても助け合って頑張ろうね!」と、2家族でお祝いしました。
私は都内への通勤に片道1時間半かかりました。時短勤務とはいえ、やっぱり大変でした。何かと里美さんにはお世話になり、よく夕飯をご馳走になりましたし、子どものお風呂をお願いすることも。夫と康二さんも気が合って、2人で駅前の居酒屋へ飲みに行ったり、地域で麻雀仲間を作って朝まで帰ってこないこともありました。でも、私は里美さんと子どもたちがいたので、寂しくありませんでした。生まれ月が同じ子どもたちは誕生会も毎年一緒でした。初めての子育てをあんなに楽しむことができたのは、田中家のおかげです。
多少、方向性が異なるところもありました。里美さんはいわゆる自然派の、マクロビ寄り。子どもにも3歳までは徹底して、甘いものは食べさせないと決めていました。おやつはフランスパン、野菜スティック、かぼちゃ餡という感じです。3歳からは蒸しパンや米粉クッキーなどの手作りおやつを与えていました。一方私は遠方勤務の忙しさを言い訳に、早くから市販のお菓子を息子に与えていました。一緒に遊ぶときは配慮して、市販のお菓子は持って行かないようにしていました。
息子が田中家にお世話になることが多かったのですが、週末には、うちで翔君を預かることもありました。そんなとき、里美さんはいつも手作りおやつを持たせてくれました。
ある日のことです。私と夫はリビングでテレビを観ており、聡太と翔君は隣の和室に広げたプラレールで遊んでいました。そろそろ2人に麦茶でも、と立ち上がって台所へ行くと、冷蔵庫のそばで何やら動く影が……。
それは翔君でした。翔君は、冷蔵庫の脇にある棚を開けて、そこからチョコレート菓子を取り出し、しゃがみ込んで勝手に食べていたのです。聡太がやってきて、「翔、何やってんの! 口の周り、真っ黒だぞ。泥棒みたいじゃん」と大笑い。後ろから夫が言いました。「翔、食べたかったら、ちゃんとそう言いな。ちゃんと言ってくれたら、出してあげるから。勝手に食べるなんて、やって良いことかなあ?」翔君は手にしていたお菓子をダイニングチェアの上に置き、シクシクと泣き出しました。「ごめんなさい、ごめんなさい」。何度も繰り返し謝るその姿が、今でも忘れられません。
その日の夜、夫が言いました。
「翔、けっこうガマンしてんだなあ。アレルギーもないのに、あんな厳しく制限する必要あるのかね?」
「まあ、いろんな考え方があるから。里美さんも翔君も肌が弱いから、気にしているみたいだし。でも里美さんが作るご飯ってヘルシーですごくおいしいじゃない?」
「そうかあ? オレは正直、薄味でちょっと……。康二さんも、『たまには体に悪いものが無性に食べたくなる』って、よくラーメン屋で会うけどな。康二さんと翔が2人のときは、コソコソふつうのお菓子食べてるみたいだよ」
「えー。お父さんとお母さんの考えが違うと、子どもは混乱するよね。しかし人の家のものを勝手に食べるくらいだから、市販のお菓子ってよっぽど中毒性があるんじゃない? 聡太も自然派おやつに変えた方が良いのかな」
「おいおい、頼むよ、オレが食べられなくなるだろ。うちはふつうで良いんだよ、ふつうで」
田中家は市販のお菓子のほか、Eテレ以外のテレビ番組やゲームも禁止していました。うちはそのあたりの締めつけも緩く、早くからニンテンドースイッチを与えていました。わが家で翔君がスイッチをやることについては、里美さんも黙認していました。聡太が田中家へ遊びに行くと、昔からある素朴なドンジャラやボードゲームなどで楽しんでいたようです。
私たち2家族は、お互いの子育てについて干渉することなく、うまく付き合うことができていると、私は思っていました。
いつの間にか広がった2家族のディスタンス
「俺がコロナになったら、どれだけたくさんの人に迷惑がかかるかわかってるの?」
ステイホーム中、偶然公園で出会った田中家とピクニック宴会をしたことを知った夫は、珍しく声を荒げました。私はテレワークになりましたが、工場のラインを止めることができない夫は責任者としてほとんど出勤していたのです。「クラスター」という言葉がニュースで飛び交っているころだったので、過敏になっていました。
私は里美さんに、夫に叱られたことについて、愚痴を交えてLINEで知らせました。里美さんからは、「何も考えずに誘ってしまってごめんなさい」というメッセージが届きました。そんなこともあって、一年近く家族同士の交流は途絶えていました。
第4波、第5波……と何度も感染者数が増減したコロナ禍の間の記憶は、なんだか曖昧です。世の中がコロナ禍に慣れてくると、はじめはピリピリしていた夫も、「そろそろ田中家とキャンプでも行きたいな」などと言うようになっていました。何度かLINEではやり取りをしていましたが、タイミングも合わず、会うことはできませんでした。
マスク登校が当たり前になっていたころの、ある日の朝のことです。家で仕事をしていると、「聡太君がまだ登校していません。お休みですか?」と小学校の担任の先生から電話がかかってきました。いつもと変わらない時間に送り出したはず……慌てて自転車に乗って近所を捜索すると、学校のそばの公園のベンチに腰掛けている息子の姿がありました。ランドセルを抱いて、肩を震わせています。マスクは涙と鼻水でベチャベチャに濡れていました。
「翔が学校に来ないから、オレ、迎えに行ったんだ。そうしたら、来なくていいって。病気がうつるから来るなって言われた」
「翔君が、何か病気なの?」
すると息子は首を左右に振って、「よくわからない」。
うちは誰もまだコロナに感染していませんし、そのときは全員健康でした。「もう来るなって。ドア閉められた!」思い出しては涙を流す息子をなだめて、ひとまず小学校に送り届け、私はその足で田中家へ向かいました。
インターホンを押しましたが、ガサゴソした音が聞こえるだけです。しばらく待ってみると、玄関の扉が薄く開きました。隙間から里美さんの顔が見えました。すっかり痩せて、頬がこけています。
「里美さん、えっ、大丈夫?」
「香奈さん、ごめんなさい。今取り込んでいるの」
家の中はシーンとして、取り込んでいるような様子は感じられません。
「翔君が休んでるって本当? さっき聡太がお邪魔したみたいなんだけど、何かあったのかな?」
「ああ、ごめんなさいね。ちょっと翔は体調を崩してて。また連絡するね」
とりつく島もなく、ドアは閉じられてしまいました。それでも、そうか、やっぱり翔君が、いや里美さんも一緒に何か感染症(きっとコロナ)にかかっており、「自分の病気がうつるから汚いよ」というようなことを言って、それを聡太が誤解して受け取ったのだろう。そう納得して、私も帰宅しました。
数日後のことです。コロナ禍で初めて、小学校の授業参観がありました。密集を防ぐため、保護者は数人ずつのグループで参観時間が分けられていました。その帰り、一緒になったママたちでお茶をすることに。そこで、そのうちの1人が言いました。
「田中翔君、しばらく学校に来ていないんだってね。ご両親が学校と揉めてるらしい。藤山さん、田中さんと同じ保育園で仲良しだったよね? 何か聞いてる?」
「え? 本当に? ……そうなんだ、全然知らなくて」
「子どもにマスクをさせたくないっていう主張らしい。よくわからないんだけど。それで、学校側はマスクをしてきてくださいと言うじゃない? だったらもう登校させないぞ、ってなったみたい」
帰宅後、私はしばらく見ていなかったFacebookを開いてみました。里美さんの投稿は数年前からありませんでしたが、康二さんは、頻繁に投稿をしていました。いわゆる陰謀論のようなものについて紹介し、同調した持論を展開していたのです。
夫にその日仕入れた情報を語り、Facebookの投稿を見せると、「ああ、それな。ヤバいよな」と、すでに知っていたようです。
「実はちょっと前に、康二さんから、署名運動をするから手伝ってほしいって電話があってさ。俺、断ったんだよ」
「そうだったの? どんな署名運動?」
「マスクなしで登校する自由についてだって。わけわかんなくてさ。なんか変な感じになっちゃってるな、あの人。あまり関わらない方がいいかもな」
翔君が不登校になった本当の理由
なんと会わない間に、康二さんはすっかり陰謀論に染まってしまった。康二さんに振り回されて、里美さんも翔君も大変な目に遭っている、これは大変だ。なんとかしてあげたい。いろいろ考えた挙句、私は勝手にそう結論づけ、里美さんにLINEをしてみました。
「翔君が、まだ学校に行けていないんだってね。何も力になれずにごめんなさい。なんとかせめて、学校には行けるようになるといいよね。私にも、聡太にも、何かできることがあったら、いつでも言ってね」
しばらく経つと、返事が戻ってきました。
「香奈さん、連絡ありがとう。いま、わが家は、本当に正しいことは何かを考えて行動しています。この状況で、無策な小学校に行かせることは、とても危険です。翔を守るために、家庭学習を選びました」
……まったく意味がわかりませんでした。よっぽどコロナに感染するのが嫌なのだろう。それでも、おそらく肌の弱さから、マスクも息子につけさせたくないために、独自の予防法をとっているのだろうと考えてもみたのですが、どうも辻褄が合いません。
「コロナは本当に怖いよね。でも、翔君が学校に行けなくなっちゃうのは、かわいそうじゃない? 聡太もすごく寂しがっているよ。そろそろワクチンも広まってきているし、マスクと手洗いをちゃんとしていれば大丈夫だと思うけど? 勉強のこともあるし、子どもにとってコミュニケーションの機会が失われてしまうのは心配だよ」
そう送ると、里美さんからすぐに着信がありました。登校させるための相談かな、と思って電話を取ると、苦しい息切れのような音がします。里美さんの言葉はなく、代わりに、何か動画の音声のようなものが聞こえてきました。男性がボソボソと話しているような、聞き取りづらいその音声は、繰り返しこう言っていました。
「いま、世の中で何が起こっているか、ちゃんとわかっていますか? この状況は、仕組まれたものです。政府がいま計画していることを知れば、すべてがつながっていたことがわかる。騙されてはいけない、騙されるな、騙されるな」
ぷっつりと電話は切れ、再びLINEの通知音がしました。里美さんから送られてきたのは、とあるYouTubeのURLでした。それは、康二さんがしきりにFacebookでシェアしていた動画と同じものでした。
そこで私はようやく合点がいったのでした。そうか、陰謀論の主たる信者は、むしろ里美さんだったのか。康二さんは、その影響を受けた方。性格的に承認欲求が高い康二さんが、SNSで発信をしていたのでしょう。
その後、里美さんからたまに動画やサイトのURLが送られてくるようになりました。里美さんは道の駅を退職して、水や健康食品のネットワークビジネスをはじめたそうで、購入の案内もありました。私はあまり興味を持つことができなかったので……いや、正直ドン引きして、返事ができないでいました。
あの家族と私たちは、本当に仲が良かったのか?
久しぶりに田中家の人物を見かけたのは、小学校の体育館でした。翔君は不登校のままでしたが、学校行事の説明会に康二さんが現れたのです。康二さんは並べられたパイプ椅子の最前列、ど真ん中に座って、足と腕を組み、口をへの字に曲げていました。参加者全員がマスクをつけているなか、康二さんだけがノーマスクです。左右、後ろ、康二さんの周りには誰も座ろうとせず、半円状に空席が広がっていました。新年度からPTAに参加していた私は、運営側として舞台袖からその様子を眺めていました。
役員と先生たちの説明が終わり、行事に関する質疑応答がはじまると、真っ先に康二さんが手を挙げました。当てられるやいなやマイクを手に取り、大声で話しはじめましたが、質疑ではありませんでした。息子がなぜ登校できなくなったのか、一方的に学校側を責め立てる調子で発言し、そこからマスクをしない理由、現政府の危険性、コロナ禍における世界的陰謀まで、延々と語ったのでした。しばらく誰もそれを止めることができませんでした。演説は30分以上続いたと思います。
自分に酔ったようなマイクパフォーマンスを眺めながら、私はぼんやりと「本当にこの人と仲良くしていたことがあったんだっけ」と考えていました。たった1人マスクをしていないその姿が、裸のようにも見えました。私はどんどんしらけていき、「気味が悪い」とすら思いました。
PTA仲間が、チラチラと私に目配せをしてきます。私はドキドキしながら、もう一つのマイクのスイッチを入れました。キーンと大きなハウリングが体育館に響き、康二さんの声を遮ります。康二さんは一瞬静かになりました。そのとき、保護者の1人が声を上げました。
「もう、いい加減にわかったよ! そういう主張は、どこか外でやってくれ!」
「そうだ、そうだ!」
「マスクをつけてよ!」
誰かれともなく、拍手をしました。広がった拍手は体育館中に響き、先生たちは困った顔をして立ち尽くしています。康二さんはマイクを持つ手を下ろして、睨みつけるように周囲を見回しました。瞬間、私と目が合ったと思います。ふと悲しそうな表情を見せたかと思うと、足早に体育館を出て行きました。
ようやく終わった、と、その場ではほっとしたのですが、その後帰宅した私は、何とも苦い気持ちを抱きました。
思い返せば、拍手で康二さんを体育館から追い出した、その図はまるで村八分のようでした。一番の仲良しだったはずの私までが多数派に回っていじめに加担した、そんな罪悪感のようなものが湧いてきて、やりきれない気分でした。一緒に楽しく過ごした日々が、確かにあったのに、なぜこんなことになってしまったのだろう、と悲しい気持ちにもなりました。
とはいえ、今はあの夫婦に近づかない方が無難だと感じ、開いた距離は広がる一方でした。
それからほどなくして、康二さんは鍼灸院をたたみ、家族で東北へ引っ越して行きました。
コロナがもたらした分断とはなんだったのか
今、私は、ほとんどマスクをつけることはありません。手洗いとアルコール消毒の習慣は身につきましたが、感染予防の感覚はすっかり鈍りました。油断大敵とは知りつつも、喉元過ぎれば……ですね。たった数年前の出来事なのに、コロナなんて、本当にあったのかなと思うくらいです。昨年の秋、私たちも東京に戻り、聡太も転校しました。今は新しい友達も増えて、元気にやっています。
もうほとんどの人がマスクもしていませんし、あのとき新型ウイルスに関する立ち位置がそれぞれどうであったかなんて、見回すかぎり、まったくわかりません。何もなかったかのような日常を過ごしながら、私はたまに田中家のことを考えます。きっと田中家も、今は康二さんの故郷で落ち着いた暮らしをしているのでしょう。どうか、幸せでいてほしいと思います。
そもそもコロナって……本当に、なんだったんでしょうか。何が真実で、誰が、どう正しかったのでしょうか? 何もわからないまま自分の中でもうやむやになって、あのころの記憶が薄れていきます。
「あのコロナさえなければ、田中家とずっと付き合っていたよね?」
私がそう言うと、夫はドライに言いました。
「そうかな? まあいずれ、どこかで綻びが出ることになったかもしれないよ」
物理的にも距離があるので、今さら関係を取り戻そうと努力をするつもりはありませんが、寂しさは残ります。
それまで息子はほとんど翔君の名前を口にしませんでしたが、年末にポツリと、「翔の住所を知ってる?」と私に尋ねてきました。授業で年賀状を書くので、翔君に出したいと言います。迷いましたが、康二さんの実家の住所を伝えました。
年が明けてから、息子はしばらく毎日自宅の郵便受けをのぞいて返事を待っていましたが、翔君からの便りはありませんでした。
(※本連載は、プライバシー保護の観点から、インタビューに登場した人物の氏名や属性、環境の一部を変更・再構成しています)
-

-
山野井春絵
1973年生まれ、愛知県出身。ライター、インタビュアー。同志社女子大学卒業、金城学院大学大学院修士課程修了。広告代理店、編集プロダクション、広報職を経てフリーに。WEBメディアや雑誌でタレント・文化人から政治家・ビジネスパーソンまで、多数の人物インタビュー記事を執筆。湘南と信州で二拠点生活。ペットはインコと柴犬。(撮影:殿村誠士)
この記事をシェアする
「山野井春絵「友達になって後悔してる」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら