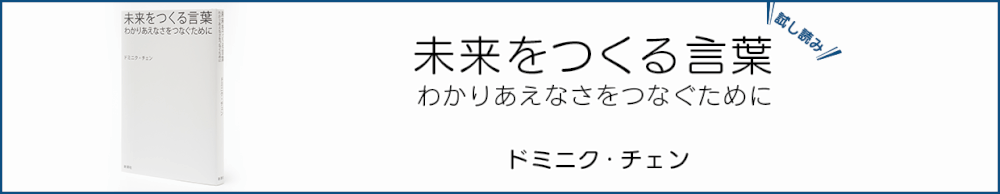生まれてはじめて他者と言葉を交わし、見知らぬ場所に足を踏み入れ、恋に落ちる――無数の「はじめて」を経てもなお、わたしたちが世界を知り尽くすことはない。それは、ただ世界が広大だから、というだけではない。常に「おわり」が別の「はじまり」の源泉となり、その繰り返しの度に新しい言葉が生まれるからだ。
それはいつも、なにかの「はじまり」であると同時に「おわり」をあらわしている。未知の世界を発見する時とは、既知の領域を離れる時でもある。そして、一生の間には、それまで蓄積されてきた経験の皮膜が一度に無化し、未知の時間が始まる予兆で満たされる瞬間がある。
時間と空間がただ一点に圧縮されるのに似た密度をあじわう。そんな局面を、誰しもいくつか思いだすことができるだろう。わたし自身も、これまで経験してきた数多の「はじまり」と「おわり」の瞬間を思い起こすことができる。本を読むなかで新しい概念に出会い、天からの啓示を受けたような衝撃を覚えたとき。鑑賞した絵画や映画作品の表現に包みこまれてしまって、しばらくのあいだ現実に立ち戻れなくなったとき。そして、忘れることのできない人との出会いの数々が、それ以前の状態には遡行することのできない不可逆な変化を起こしてきたとき。
こうした記憶の広がりのなかで、今にいたるまでもっとも強い磁力を発し続けているのは、妻の出産に立ち会ったときの記憶だ。娘が母胎の外へと這いずり出て、最初の産声を上げる準備をしているその刹那、自分の全存在がその風景のなかへ融けこむ感覚に襲われた。
鈍い灰色の光彩に包まれたその小さな身体が、はじめて息を吸いこんだ次の瞬間、一度に全身が赤みを帯び、生命の色に染まる。直後に部屋中に響き渡る産声とともに、原初の「はじまり」が世界に顕現する特異点だ。
彼女の身体がはじめて自律的に作動したその時、自分の中からあらゆる言葉が喪われた。同時に、とても奇妙なことだったが、いつかおとずれる自分の死が完全に予祝されたように感じられた。自分という円が一度閉じて、その轍の上を小さな新しい輪が、別の軌跡を描きながら、回り始める感覚。自分が生まれたときの光景は覚えてはいないが、こどもの誕生を観察することを通してはじめて、自らの生の成り立ちを実感する気もした。
それから現在に至るまで、自分はこの円環的な時間の甘美さに隷属してきたように感じる。まだ一人では生きていけない彼女の成長をいつも側で見守ることによって、自分の生きる意味も無条件に保障されてきた。わたしはそのあいだ、自分自身のために新たな言葉を探ることを必要としなかった。ある意味では、「こどもを育てる」という免罪符を得ることで、自分自身の歩みを振り返ることを怠ってきたのかもしれない。
それでも、全身の力をふりしぼって大泣きしたり、無邪気にあたりをぴょんぴょん跳ねまわったりする娘の姿を見るたびに、わたしの心は彼女の発する色とりどりの感情で充溢していた。そこに付け足すべき言葉など、なにひとつなかった。
しかし、いま、自分とこどもを覆っていた泡の皮膜が弾けようとしている。娘はある時から、自分だけの感覚を獲得して、自由に問いを発しはじめた。一方的に庇護を受ける段階を脱して、目の前に広がる豊穣な世界へと自らのちからで分け入ろうとしている。これもまた、自分とこどもの関係におけるひとつの「はじまり」と「おわり」なのだろう。であれば、彼女がうまれたおきに感得した儚い印象がいつのまにか消え去ってしまわないように、そのあたらしい受容器となる言葉にかたちを与えたい。そのためにも、娘の誕生と共に一度終わった自分の学びのプロセスを起動し直さなければならないのだろう。
求めていきたいのは、娘が生まれた瞬間に体験した、あの不思議な時空を表すための言葉だ。自己が世界の背景に融解していく、あの安堵の正体はなんだろうか。なぜ、自分の死への恐怖が祝福へと転化されたのだろうか。この奇妙な感覚に名前を与えずして、自分の思考を進めることはできない気がする。
親子になるという経験、そして生死という、誰にでも訪れる「はじまり」と「おわり」を見つめながら、自分が言葉を探り出す過程をいつか娘に読んでもらうことで、自分自身の過去を切り開き、わたしの見た未来を想い出してもらえたら、と思う。
わたしはこれまで、哲学とデザインを学んだ後に、美術館で仕事をしながらインターネット上の文化を促進するNPOに参加し、情報技術の会社を起業した。好奇心の赴くままに活動の場を移してきた来歴に共通するのは、「表現とは何か」という問いだ。
いまは大学の場で、これから社会に飛び立とうとする若い人たちと一緒に、新しい表現のかたちを研究している。生きるために必要とする表現の道具や方法を、当事者が構想し、具現化する研究だ。そのためにわたしたちは、芸術とデザイン、文芸と哲学、エンジニアリングと自然科学、文化人類学と認知科学、そしてデジタル・テクノロジーと、あらゆる表現領域の歴史を参照する。
数年間、共に学んだ学生が卒業したと思えば、すぐに研究室の門戸を叩く者が現れる。ここでも、常に「はじまり」と「おわり」が反復している。そうして、若い人たちの瑞々しい感性に触れるとき、まるで自分が生まれなおしているように感じられる。
これまでに出会ってきた数多の他者たち――自分のこどもも含めて――と自分自身の生が重なる瞬間、わたしは彼もしくは彼女でありえたかもしれない世界を生きる。
放っておけば意識からこぼれ落ちてしまう、この儚い縁起の感覚をとらえ、かたちを与えるために、わたし自身を紡いできた「はじまり」と「おわり」のパターンを書き記していくことにしよう。この過程のなかで、読者であるあなた自身の生の軌跡が喚起されるよう、祈りつつ。
関連サイト
『未来をつくる言葉』特設サイト
-

-
ドミニク・チェン
博士(学際情報学)。NTT InterCommunication Center研究員、株式会社ディヴィデュアル共同創業者を経て、現在は早稲田大学文学学術院教授。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)Design | Media Arts専攻を卒業後、NPOクリエイティブ・コモンズ・ジャパン(現・コモンスフィア)を仲間と立ち上げ、自由なインターネット文化の醸成に努めてきた。大学では発酵メディア研究ゼミを主宰し、「発酵」概念に基づいたテクノロジーデザインの研究を進めている。近年では21_21 DESIGN SIGHT『トランスレーションズ展―「わかりあえなさ」をわかりあおう』(2020〜2021)の展示ディレクター、『発酵文化芸術祭 金沢』(2024、金沢21世紀美術館と共催)の共同キュレーターを務めた他、人と微生物が会話できる糠床発酵ロボット『Nukabot』(Ferment Media Research)の研究開発や、不特定多数の遺言の執筆プロセスを集めたインスタレーション『Last Words / TypeTrace』(遠藤拓己とのdividual inc. 名義)の制作など、国内外で展示も行っている。著書に『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(新潮文庫)、など多数。(写真:荻原楽太郎)
この記事をシェアする
「ドミニク・チェン『未来をつくる言葉』試し読み」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら