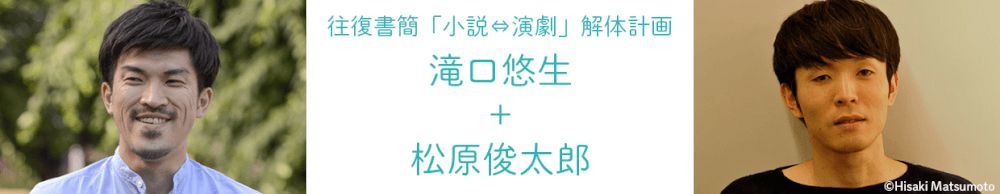松原俊太郎→滝口悠生
アメリカ生活に順応中ということでしたが、その後、いかがお過ごしでしょうか。
こちらは『カオラマ』第二稿を公開し、ようやく一息ついたところです。
《小説の文章というのは、聞こえた誰かの声、という感じがする》《そこに、あるいはどこかに、言葉を発しようとしている誰かがいて、その人の声を聞こうとする。聞こえにくいその声を聞こえるように工夫をする、という感じ》、興味深いです。「はっきり」とはしていない声を聞こうとする、その聞こえてきた声を、あるいは声を聞こうとすること自体を書くのだとすれば、それはその声にかた ちを与えるというイメージでしょうか。その「誰か」というのは登場人物のことですか? 耳抜き、身体をずらす、というイメージも魅力的ですが、その聞こうとする姿勢、「聞こえるようにする工夫」、チューニングの方法をもっとお聞きしてみたいです。
聞くということから思い起こしたのは、映画や演劇を観ているときに、そのときどきの見聞きする姿 勢や体調やまわりの環境次第で、「聞こえてくる」ものが変わってくるという体験です。前回書きましたが、この「聞こえてくる」という現象に異化が含まれるのなら、「その人の声を聞こうとする」ことで「聞こえてくる」声はもちろん自分の聞きたいこととイコールになるわけではなく、自分を異化するものなのではないかと思います。その声が書き記されたとき、それが読む人にとっても自身を異化するものになるかどうかは、「言い方」(書き方)によるのかもしれません。
舞台上の上演を「前提としない」という前提のもと書いている『カオラマ』では、図らずも戯曲が大前提としていることについて考えることになり、第一稿執筆時は「声になる」ということ、第二稿執筆時は「身体」を前提としていることを発見しました。身体がなければ、何を言ってもいいということになりますが、身体があるとそういうわけにはいきません。ト書きによって紙の上で動かされる身体ではなく、発せられる言葉によって作られていく身体、あるいはその逆で、そこにある身体から言葉が作られていく。身体と言葉は不可分です。これが紛れもない形で現れるのが上演ですね。ただ、一方で、身体を必要としないような台詞、いまここに書いているような身体を外側から書いた言葉、身体の外に出て静的に俯瞰するような言葉というのも当然あって、これまで自分が書いてきた戯曲でも使っています。こういった身体の外側にあるような言葉が、舞台上の俳優からどのように発せられればよいのか、どうすれば聞こえるのか、僕にはまだよくわかっていません。
演劇は目の前で身体が演技をして言葉を発する、ごまかしが効かないもので、その嘘やごまかしは映画に比べるとものすごくシビアに表面に出てきてしまいます。小説や戯曲が書かれ始めるときと同様に、目の前にある身体が事実としてそこにあっても、それが動き出し、台詞を言い始めた途端にフィクションが作動します。フィクションとしての言葉が、フィクションとしてそこにある身体から声として発せられる。身体はフィクションと現実、役と俳優の「私」といったように多層的に構成されますが、あるとき、その身体から発せられる声が、フィクションではなく現実の身近な言葉として、意味ではなく身体を獲得した言葉として「聞こえる」こと、そこに演劇のおもしろみを感じます。
僕が書くときに、「言い方を気にしている」(前回を参照)のは、言葉を書く・話すという行為が他者を志向するから、だと思います。書くときに孤独であろうとなかろうと、書くものは他者、誰かに向けて書かれていますよね。モノローグであっても対話の形式を前提としています。滝口さんの「誰かの声を聞く」ということも、対話に近しいように思うのですが、どうでしょうか。適当な対話であれ、真剣な対話であれ、対話によってお互いに起きる変化や反応は、「言い方」によって大きく変わってきます。ある状況のなかのある一言で身体や感情が変化する、対話やモノローグはその連続であって、見えにくくはありますが、声を発する側にも、聞く側にも、一文一文で変化が起きているはずです。「声を聞く」という行為にも繋がるかと思うのですが、この微細な変化を見つめつつ対話するということが「言い方を気にする」ということになるかと思います。
「言い方を気にする」際に、前回は紋切り型との対比を強調した書き方をしてしまいましたが、愛する人の口から聞くと、紋切り型だと思っていた言葉がそうでなくなってしまう、ということがあるように、この言葉は紋切り型だ、と決めつけることはできないんですよね。社会的なコードや習慣に則った紋切り型は今もなお生産され共有されていますが、パロディにしたり配置を変えたりすれば新鮮に聞こえるということもあります。「紋切り型から逃れる」というのは、ある言葉が紋切り型だと思えてしまう構造から逃れることです。たとえば、果てしない口論のような、紋切り型の応酬であっても、それが感情という不可思議なものを通過することで変化を引き起こして、絶えず対話が横滑りしていって何かが決定的に変化してしまうというように……
こんなふうなことを言っていると「終わり方」はますますわからなくなってくるのですが……対話は何をもってなされるのかということを考えてみると、大きく言うと、対話するもののあいだに何かがやってくるから、あるいはやってくるものを待っているからなのではないか、と思います。『ライク・サムワン・イン・ラブ』の人物の怒りとともに投げられた石(?)のように、突然、不意に外からやってくるもの、というような……ただそこにいて、じっと待っているときでも、想像上あるいはリアルな他者と対話はなされています。ベケットの『ゴドーを待ちながら』ではゴドーはやってきませんが、それはゴドーを待っているから来ないんですよね。神やクライマックスやカタストロフを待ち望んでいた観客たちが『ゴドー』を不条理劇と呼ぶのと同じことです(たしかにあるものを待っていたひとがそのあるものがやってこなかったことに対して嘆く、怒る身ぶりというのは不条理を思わせますが)。人物たちが待って、対話しているあいだに、他の何かはおそらく続々とやってきている。対話しているうちに人物のなかに沸き起こってくる感情や、そこから派生した行動によってもたらされる何か、対話とは無関係に思われるような、外から突如やってくる何か……それをもってして終わりなのかどうかはわかりませんが……
『ライク・サムワン・イン・ラブ』の投げられる石は、暴力が喚起するリアルさもあるかとは思いますが、それだけでなく、投げられるまでに蓄積された対話、感情からくるリアリティもありますよね。演出の悪意は感じられず、必然かつ衝撃として受け入れられる見事な「終わり方」だと僕も思います。映画館や舞台であれば席を立たない限り、始まりから終わりまでの体感がありますが、小説を読むのはいつでも中断できてしまうので、体感があるとすれば聞きつつ書いている作者の体感しかないですよね。文章の連なりなので、書き手はどこからでも始められるし終わらせられる。ただ、前述したように文章の志向する他者との向き合い方、書き手や登場人物の対話への姿勢、やり方みたいなものが「終わり方」には如実に現れているように思います。
滝口さんの書く語りは、「聞く」ことから始まっていて、やはり対話であるように感じます。先の問いに似たものになりますが、その聞こうとする誰かはどこからやってくるのか、登場人物がどのように現れ、消えるのか、お聞きしてみたいです。
今日は9.11ですね。
台風の被害が散見される京都で、日々なんとか書きつづけています。
9月11日 松原俊太郎
『演劇計画Ⅱ -戯曲創作-』
委嘱劇作家:松原俊太郎、山本健介(The end of company ジエン社)
演劇計画Ⅱアーカイブウェブサイト http://engekikeikaku2.kac.or.jp/
京都芸術センター http://www.kac.or.jp/
-

-
滝口悠生
1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。
-

-
松原俊太郎
作家。1988年熊本生まれ。2015年、処女戯曲「みちゆき」で第15回AAF戯曲賞大賞受賞。2019年、『山山』で第63回岸田國士戯曲賞受賞。他の作品に戯曲「忘れる日本人」、「正面に気をつけろ」(単行本『山山』所収)、小説「またのために」など。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 滝口悠生
-
1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら