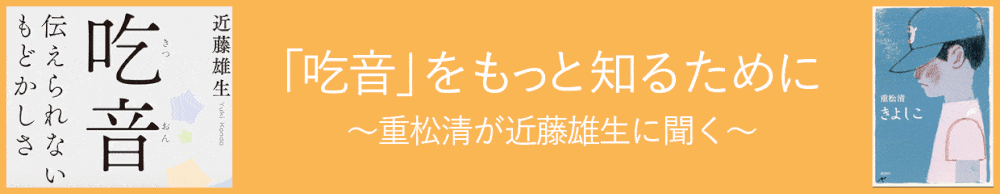2019年12月7日
第4回 待つことは、認めること
吃音とはどういうものか。『吃音 伝えられないもどかしさ』を執筆された近藤雄生さんと、『きよしこ』『青い鳥』といった吃音をテーマにした小説を書かれている重松清さん。リクエストの声にお応えして、貴重な場の記録としてまとめました。第4回、最終回をお届けいたします(全4回)。
(前回はこちら)
2019年1月に上梓した『吃音 伝えられないもどかしさ』は、吃音を持つ人の困難を当事者としての私自身の経験を踏まえて書いたノンフィクションです。その帯推薦文と書評を寄せてくださった重松清さんと、同5月31日に、東京・下北沢「本屋B&B」にてトークショーを行いました。重松さんが聞き手となってくださったそのトークをまとめたのがこの連載記事です。
今回が最終回です。会場からの質問に答える形で進んでいった後半、話がどんどん核心へ。自分自身にとって深く心に残るトークであり、来場者からも「とても幸せな時間でした」といった声をもらった2時間の、締めくくりへと向かいます。
貴重な機会をいただけたこと、改めて、重松清さんに感謝申し上げます。
近藤雄生

娘の名前は、言いやすい音にした
重松 次の二つの質問は、同じ問題を扱っているように思います。一つ目は、吃音当事者で34歳、3児のお父さんから「子どもに自分の吃音を、どう伝えればいいか」という質問。もう一つは、小学4年生の息子さんに吃音があるという親御さんから「子どもに、本人の吃音についてどう伝えるべきか」という質問です。
近藤 まず僕から、二つ目の質問の、子どもに本人の吃音をどう伝えるか、という点について思うところを言いますと、具体的な伝え方はケースバイケースかと思いますが、大切なのは、その子の気持ちに寄り添うようにして伝えることのような気がします。安易に「気にすることはない、大したことはない」などとは言わないこと、というか。ところで重松さんは、娘さんがお二人いらっしゃいますよね。ご自身の吃音について、直接話されたりしましたか?
重松 僕の場合、娘たちが幼いころ、パパは、あまりうまくしゃべれないから……、つっかえてしまうから……と言っていました。でも、「どもる」という単語は、使えなかったな。もしかしたら、俺がメディアなんかに登場していたから、娘も、友達から何か言われたことがあったかもしれないけれども、少なくとも、本人たちはそんなに、うん、僕に何かを訴えるようなことはなかったから、よかったなと。
近藤 そうでしたか。
重松 これも関連する問題かと思いますが、「家庭を持つことに不安はなかったか」という問いもあります。俺は、不安はいっぱいあったし、あと、娘の名前は二人とも、自分の言いやすい音にしてしまったよね。そこは大事(笑)。
一同 (笑)
近藤 娘さんの名前が呼びづらいのは、つらいですものね。僕の場合、同じく娘二人なのですが、長女が、言葉を話しだしてしばらくしたころ、急にどもるようになった時期がありました。その時は、ああ、もしや、と気になりましたが、でも何日間か続いたあとに、さっとなくなって。それ以来ないのですが、その時から、いつか娘に吃音が始まることもあるのかもしれないという不安が、少しあります。
重松 そうだったんだね。そう、家族ということでいえば、前にテレビのインタビューで、自分の小説について質問されたとき、「僕の小説というのは、夫婦とか親子とか」と言った後に、「家族とか」って言いたかったのですが、家族の「か」が言えなかったから、「夫婦とか親子とかファミリーとか」と言ってしまったんですよ。自分の小説の一番大事な言葉が言えなくて言い換えてしまったのは、やはりつらかったですね。
近藤 それは、うん、つらいですね。僕もいま、言えなかった例でふと思い出したことがあります。まだライターを始めたばかりのころ、取材する際、「録音させてもらっていいですか」というひとことが言えなくて、何も言わずに録音しだしたことがあったんです。ひとこと断らなければと思いつつも、できないまま、何気なくスイッチを押してしまって。そのとき相手の人が、「え、なんだ」という顔をされたのもよく覚えているのですが、それでも僕は何とも言えなくて……。それは何度も通うような取材だったのですが、そのような、上手く話せない場面が何度かあるうちに、続けるのがつらくなって取材をやめてしまいました。そのことがいまでも記憶に残っていて、思い出すと、申し訳なく、いたたまれない気持ちになります……。
待つことは、認めること
重松 だから本当にね、こんなふうに話したり、読んだりしていると、どんどんいろんなことを思い出すんだよね。いっぱい記憶に残っている。どれもきっと小さなことだし、生きるか死ぬかというものではないんだけれども……、でも、つらいかつらくないかで言ったら、やっぱり、つらいんだよね。
近藤 そうですね。
重松 そういうものが、いっぱいある。一つひとつの小さな傷は、遠くからは見えづらいし、わからないんだけれど、そばに来てくれたら、結構、傷は……、あるんだよね。僕は文章を書く人間として、そういう小さな傷に対して、敏感でありたいなって思います。
近藤 はい。同感です。小さな傷に、自分が十分に敏感と言えるかはわからないですけれど、自分なりに、小さな傷に対して意識を向けられる人間でありたいです。それはやっぱり、自分の場合、吃音があったからなのだろうな、というのは思っています。
重松 あとは、みんながみんな、言いたいことを言えているわけではないんだな、というのが、あるよね。言えない言葉や出せない本音を、みんな持って生きている。自分を見たらそうだから……。小学校の通知表の項目に「人の目を見て、自分の意見をはきはきと言える」なんていうのがあるけれど。「言えねえよ」って、思うんですよね。
一同 (笑)
近藤 そうですよね。
重松 俺はやっぱり、言えない子どもの側に、いたいなと思うんです。その代表というか、その一人が、大人になっているんだという意識は、ずっと持っていたい。俺はいまも、しゃべるときに、「あー」や「うー」をいっぱい入れてしまって、普通は1分で終わる話に、3分かかることもある。だから、その2分ぶんの余裕を、持っていてほしいと思うんだよね。普通は1分のところを30秒で言ったら大したもんだ、と評価される風潮は、嫌だな。
近藤 そうですね。そういう価値観は、ありますよね。
重松 うん、あるからね。足が遅いやつもいれば、飯を食うのが遅いやつもいるし、酒の弱いやつもいるし、それと同じように、話すのが下手なやつもいるんだよ。それでいいじゃんと、俺は思う。
近藤 『吃音』の最後の方に書いた話なのですが、大阪の中学校に、吃音のある先生がいて、その先生の授業に参加したことがありました。その時、重松さんの『青い鳥』の村内先生の姿と、すごく重なるところがあったんです。先生は、吃音のためにうまくしゃべれなかったり、言葉が出なかったりするんですけど、生徒たちはそのことをよく理解していて、それに対して、「何だよ」みたいな顔をするわけでもない。自然に待っている。なんでも速い方がいいとされる時代の中で、その光景がすごく貴重に思えました。待ってもらうことが必要な人がいて、待つことを求められる人がいる。その間に生まれる温かい関係性のようなものがあるんじゃないかなって、感じました。
重松 うん、そうだね……。待つということは、認めるということなんだもん。肯定だもんね。
近藤 そうですね……。
重松 実は、小学校の先生をやっていらっしゃる当事者の方からも質問がありました。「私なんかが、小学校の先生をやっていいのか」と悩んでいる、と。
……いまの俺たちもそうだけど、一生懸命しゃべってるんだよね。一生懸命しゃべってる先生は……、絶対に、いていいし、たぶんいなければいけないと思う。いまの近藤さんの話でも、また、『青い鳥』でも書いたように、うまくしゃべれない先生がいるということは、教え子にとって、絶対に意味を持つと思っています。だから、この質問をしてくれた先生には……、うん、頑張ってほしいし、信じてほしい。そういう先生を、待っている生徒が、必ずいると……。
近藤 本当に。僕もそう思います。

多くの人の人生が、詰まっている
重松 そろそろ時間が無くなってきたけれど、いま、『青い鳥』の話をしてもらったので、近藤さんの『吃音』の話を改めて最後にしましょうか。まずタイトルが本当にすごいと思いました。『吃音』。ストレートですよね。そのタイトルも含めて、単行本にまとめるときの話を、ぜひ最後に聞かせてください。
近藤 この本は、『新潮45』という雑誌で不定期の連載として書いた7回の原稿を一冊にまとめたものなのですが、連載を終えてから書籍化までは、当初の予定よりだいぶ長くかかりました。というのも、編集を担当してくださった新潮社の足立真穂さんが、本当に、厳しく、丁寧に見てくださったんです。一度、これで完成と思って送った原稿に納得してもらえず、「これで完成でいいんですか」といった言葉とともに、長文の手紙をもらった。その時は途方にくれましたが、手紙を冷静に読んでみると、なるほど、と思わざるを得ない指摘がたくさん書かれてあったんですね。だから、これはどうしてもなんとかしなければならないと、そこからさらに4、5カ月かけて根本から考え直して、修正を加えていきました。そうして自分なりに徹底的に書き直して再度見てもらった結果、ようやく「これで行きましょう」と言ってもらうことができたんです。
タイトルについても、実は僕は当初、「吃音」という語が付かない、ちょっと文芸的な、格好いいタイトルにしたいという気持ちがありました。でも、足立さんに「これでいいんですか」と原稿を突き返されて書き直してみた結果、タイトルについても、これはもう『吃音』しかないなと思ったんですね。連載時のタイトルだった『吃音と生きる』でもなく、『吃音』なんだと。そのときようやく、正面からこのテーマと向き合えた気がしました。
重松 書き直すというのは、技術的な意味でよくなるだけではなくて、その小説やテーマに対する、覚悟が、絶対に育っていくと思うんだよ。そういう意味で、やっぱり時間をかけてつくった本なのだな、というのを本当に感じます。僕は、普段はこういうトークショーは絶対にやらないんですよ。特に、意識高い系の書店でのトークショーはね。
一同 (笑)
重松 すごいアウェー感があるんだよね(笑)。それでも、近藤さんとこの本について話すんだったら、ぜひ参加したいなと思いました。登場してくれる人たちの、人生の一番しんどいところを……、しっかりと聞き出して描いていく、書き手の覚悟が詰まった本だと僕は思っています。その話をしたくて、今日来ました。最後に、近藤さんから皆さんに一言メッセージをもらって、おしまいにしましょう。
近藤 本当にありがとうございます。ありがたいお言葉をたくさんいただいて、胸がいっぱいで、何と言っていいのかわからないのですが……、ノンフィクションというのは本当に、いろんな方が自らをさらけ出してくださることで成り立っているということを、この本を書いて改めて感じています。そのお一人お一人からバトンをもらって、伝えるのが、書き手の役目だと思っています。
今回、思っていた以上に広く読んでいただけて、評価もしてもらえていることは、書き手としてとてもうれしくありがたいです。そして、注目していただくほどに、この本に登場してくださった方たちの人生への敬意を、僕はますます感じるようになっています。ノンフィクションは、一冊に本当に多くの人の人生が詰まっていて、書き手としては、「自分の作品」と単純に思えない部分があります。しかし同時に、自分が書いたものとして、世に出した責任をしっかりと意識し続けなければいけないという気持ちも、いま新たにしています。
この本を通じて、登場してくださった方たちの深いところにある思いに、想像を膨らませてもらえたら本当にうれしいです。

(おわり)
-

-
近藤雄生
こんどう・ゆうき 1976(昭和51)年東京都生まれ。東京大学工学部卒業、同大学院修了。2003年、旅をしながら文章を書いて暮らそうと、結婚直後に妻とともに日本を発つ。 オーストラリア、東南アジア、中国、ユーラシア大陸で、約5年半の間、旅・定住を繰り返しながら月刊誌や週刊誌にルポルタージュなどを寄稿。2008年に帰国、以来京都市在住。著書に『遊牧夫婦』シリーズ(ミシマ社、角川文庫)、『旅に出よう』(岩波ジュニア新書)、『吃音 伝えられないもどかしさ』(新潮社、講談社本田靖春ノンフィクション賞・新潮ドキュメント賞最終候補、本屋大賞ノンフィクション本大賞ノミネート作)、『オオカミと野生のイヌ』(エクスナレッジ、本文執筆)など。最新刊に『まだ見ぬあの地へ』(産業編集センター)。大谷大学/京都芸術大学/放送大学 非常勤講師、理系ライター集団「チーム・パスカル」メンバー。
-

-
重松清
しげまつ・きよし 1963(昭和38)年、岡山県生れ。早稲田大学教育学部卒業。出版社勤務を経て執筆活動に入る。1991(平成3)年『ビフォア・ラン』でデビュー。1999年『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。2001年『ビタミンF』で直木賞、2010年『十字架』で吉川英治文学賞、2014年『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表している。著書は他に、『きよしこ』『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』など多数。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 近藤雄生
-
こんどう・ゆうき 1976(昭和51)年東京都生まれ。東京大学工学部卒業、同大学院修了。2003年、旅をしながら文章を書いて暮らそうと、結婚直後に妻とともに日本を発つ。 オーストラリア、東南アジア、中国、ユーラシア大陸で、約5年半の間、旅・定住を繰り返しながら月刊誌や週刊誌にルポルタージュなどを寄稿。2008年に帰国、以来京都市在住。著書に『遊牧夫婦』シリーズ(ミシマ社、角川文庫)、『旅に出よう』(岩波ジュニア新書)、『吃音 伝えられないもどかしさ』(新潮社、講談社本田靖春ノンフィクション賞・新潮ドキュメント賞最終候補、本屋大賞ノンフィクション本大賞ノミネート作)、『オオカミと野生のイヌ』(エクスナレッジ、本文執筆)など。最新刊に『まだ見ぬあの地へ』(産業編集センター)。大谷大学/京都芸術大学/放送大学 非常勤講師、理系ライター集団「チーム・パスカル」メンバー。
対談・インタビュー一覧
-

- 重松清
-
しげまつ・きよし 1963(昭和38)年、岡山県生れ。早稲田大学教育学部卒業。出版社勤務を経て執筆活動に入る。1991(平成3)年『ビフォア・ラン』でデビュー。1999年『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。2001年『ビタミンF』で直木賞、2010年『十字架』で吉川英治文学賞、2014年『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表している。著書は他に、『きよしこ』『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』など多数。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら