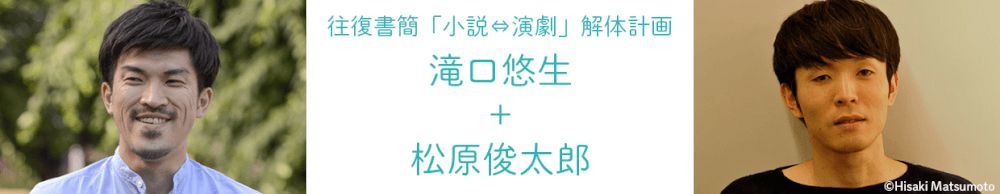滝口悠生→松原俊太郎
年末に東京公演のあった地点×空間現代「グッド・バイ」を観ました。昨年の「山山」「忘れる日本人」を含め、これまでに観た地点の演劇とくらべて、劇中かけ声のように繰り出される断片的なセリフをすんなり聞くことができた気がするのは、この往復書簡を通して考えたことも影響していたと思います。
「グッド・バイ」の公演情報には「原作・太宰治」とありますが、この作品で俳優が発するセリフは太宰の短編「グッド・バイ」だけでなくほかの多くの作品や書簡などから引かれています(当日パンフには四十九もの作品名が記載されていました)。「グッド・バイ」が原作というわけではなく、太宰を原作においた「グッド・バイ」という作品、ということなのですかね。いずれにしろ地点のお芝居を観たことがあれば、この方法はもう織り込み済みなのですが、あらためて考えると、これだけ「原作」とは違う形の「上演」を呈示できる、というのはすごいことだと思います。それができる地点という劇団も、それができる演劇という方法もすごい。「原作」とはなんなのか、みたいなことも思うし、「原作」と「上演」の関係についても考えたくなります。
ある形で表現されたものを、別の形で表現するとき、そこには様々な可能性の幅があると思うのですが、「グッド・バイ」を観ると、ふつう我々が想像する「原作」と「上演」の関係はごく狭い可能性でしかないと思わされます。それは小説とか演劇と聞いた時に想像する小説っぽさ、演劇っぽさみたいなもので、演劇も小説もしばしばとりうる可能性の幅のごく一部分、ごく狭い可能性として想像されてしまう。なにも現代の演劇や小説に詳しくないひとに限った話ではなく、前回の文中にもあった「一般的なリアリズム」は、僕たち作り手もそこから完全に自由にいられるというよりは、毎回毎回そこに立ち戻って、それからその狭さを押し広げていく、みたいな作業をしているように思うし、その作業に現代性とか、現代に小説を書く意味があると思います。
僕は前に映画「男はつらいよ」を題材にした『愛と人生』という小説を書いたのですが、その時に考えていたことは、ここで書いている「原作」と「上演」のあり方に近かったかもしれません。僕はその小説を書く時に、「男はつらいよ」をノベライズする、と考えていました。ふつうノベライズというと物語や登場人物が優先されますが、僕は「男はつらいよ」を物語だけでなく、監督や俳優、スタッフたちによって長年撮影された映画シリーズ、というものとしてノベライズ=小説化しました。事前にそうしようと考えたというか、映画を小説という形にしようとした時に、自ずとそういうおかしな変換が必要になっただけで、書く前はどうなるかはわからなかったけれど、ともかく単に文章化するだけなら意味がない、とは思っていました。
地点の演劇が示すように、「一般的なリアリズム」とは別の可能性がたくさんある。「原作」と「上演」の関係もそうだし、自己と他者の関係も、僕たちがふつうすぐに想像してしまうモデルとは別の可能性があり、その別の可能性を足場にしてみることで、別の言葉とか別の関係性を発見できる。それをすぐさま希望と呼ぶのは拙速かもしれないけど、僕はやっぱり希望的なことだと思っていて、だからその可能性の呈示に現代性が宿るとも思う。それは松原さんが繰り返し書いている、〈異化作用によって聞こえてくる声〉と同じようなものだと僕は思っているのですが、どうでしょうか。
「身体」もまた、そういった可能性の押し広げに際し、外すべきタガのひとつなのだと思います。松原さんが前回書いていたように、演劇あるいは戯曲においてふつう発声が前提とされているということは、声だけでなくその声を発する舞台上の身体もまた前提とされているわけですね。僕が前回書いた「時間」の問題、そしてこれも松原さんが前回書いていた「誰が、どこに」という問題も、「身体」についてまわる。
十二月は年末で雑誌などの締切がいつもより早く、それに追われていて「おじさんと海に行く話」を観に行けなかったのが残念だったのですが、前回の松原さんの説明を読むと、舞台上から「身体」を消し去る試みのようにも思えました(実際にその場にいないとなかなかイメージするのが難しいですが)。演劇計画IIの第二稿の公開を受けての黒嵜想さんの批評文も、ふたつの戯曲を「身体なき声」として読むものでしたね。
小説が「誰が、どこに」から自由になりやすい(動作主や場所がしばしばスライドする)のは、そこに「身体」がないからだと思います。それは小説の特性というよりは、言葉で思考することには身体の制約がないということではないでしょうか。「いつ」つまり時制の行き来も同様で、思い巡らしは、現在から過去、あるいは未来へと文字通り巡ることができる。もちろん演劇も言葉を用いるわけで、舞台上で、ある身体が、過去から未来へとスライドするように語ることは可能だし、それを意図的に手法として用いることもできるでしょうが、そこに俳優の「身体」があることによって時間や場所についての「一般的なリアリズム」がより強く働き、観客はその宙づりに耐えられず今がいつかを気にかけてしまう、ということはあると思います。
「で、今はいつなの?」「で、それは誰なの?」という問いの強さ、不遜さ。年末はここ数年妻の実家に行くことが多く、そうするとおばあちゃんと紅白歌合戦を見るともなく見るのですが、松原さんはご覧になりましたか。今年はサザンオールスターズが出て、最後に「勝手にシンドバッド」を歌っていました。あの歌は「今何時」「そうねだいたいね」といったかけあいのパートがありますが、結局今何時だか全然答えないのがすごいなと酔った頭で思いつつ、「グッド・バイ」のかけ声のようなやりとりも思い出していたのですが、ともかく「今はいつなの?」「それは誰なの」みたいな問いの不遜さを断固として否定し、それに抵抗するものとして、僕は地点の演劇や松原さんの戯曲を読んでしまうようです。小説にそれが可能か、とかも思いながら。
「声」から「身体」に話題が移ったことで、前回まで僕が書いていた「声」は、物理的な音声ではない、というだけでなく「身体」を伴わない「声」なのだということが、はっきりしたように思います。僕は前回、戯曲と上演の関係を語り手と書き手の関係に重ねてみたのですが、「身体」の有無もまたそこにかかわっていたのかもしれません。戯曲には身体はなく、しかし上演には身体が必要。小説の語り手は身体を持ちませんが、書き手は身体が必要。
前回の松原さんの書簡を読んでいたら、保坂和志が「小説にはどうして人間が出てくるのか?」と小説論に書いていたのを思い出して、この問いは僕のなかにずっと残っているのですが、それに対応する答えの方は残っておらず、どこに書いてあったんだっけと探してみたら『小説の誕生』のなかに見つけました(単行本355ページ)。が、その先を読んでいっても、その問いに対応する答えのようなものはここで引用できるような形ではやっぱり書かれていなくて、けれどもその先を読んで僕が考えたことを先の書き手の身体の話につなげると、小説は言葉だけで舞台も俳優もないので、そこで必要となる身体も当然言葉の形をとる、それは描写なのではないか、ということになります。
ト書きとセリフだけで構成される戯曲と並べた時に、戯曲においては上演という来たるべき身体がありますが、小説においては描写がその身体の代わりをなすのではないか。保坂和志がそう書いているわけではなく、保坂さんは人間は抽象的な概念に対してリアリティを持つことができず、そのために自分と同じ認識のしかたを必要とするのではないか、みたいなことを100ページくらいつかって書いているというか考えています。その人間と同じ形をした認識というのを、小説においては描写が担う、と言ってよいと僕は思う。小説の語り手が語り手たりうる要素というのも描写の部分で、セリフのない小説はあっても、描写のない小説はないのではないか。そしてその描写の部分に寄り添うのが、書き手という「身体」(=人間と同じ形)。書くという行為を行う「身体」でもあるけれど、身体を持たない語り手に「人間の形」を貸す役割を果たすのが、書き手の「身体」なのではないか。
小説の身体が現在にいるのか、過去にいるのか、という前回の松原さんの最後の問いとは案の定ずれた答えなのですが、小説の「身体」、語り手の「身体」について今回はそのように考えました。
長くなりますが、
語り手の語りは、書き手なしではなされないものだと思いますが、語り手が「説明しようとする」相手は誰なのか、「どこに」向かって「説明しよう」としているのか、気になります。また、その「説明」は誰あるいは何に要請されているのでしょうか。
という前回の大事な問いかけについても考えたいです。
僕はむかし、ニーチェとかハイデガーは、なぜ言語以外の道具で考えようとしないのだろう、とか思っていました。たとえば音楽を通して世界や人間について考えようとすれば、言葉を使って現れるのとは別様の世界が現れるかもしれない。実際音楽を聴いてすごく感動して、全能感というか、世界が近しく感じられるような瞬間がある。あの瞬間を言葉はそのまま記述できない。なぜ哲学は、厳密でどこまでも間接的でしかない言語だけに固執するのだろうか、と思っていました。もちろんこれは馬鹿で幼稚な問いなのですが、でも今でもこれは謎といえば謎で、簡単に切り捨てきれない問いのように残っています。
小説の描写は、そこに人がいるいないにかかわらず、人間の目や耳といった感覚器官による認識から離れることができません。それは人間が言葉を使う、ということからくる限界だと思う。言葉はどんなでたらめなことも、間違ったことも、意味のないことも言えるし書けるけれど、僕たちはそういう言葉をうまく使用することはできません。自分たちの内にある「一般的なリアリズム」をほどこうとしても、その外には結局は言葉という体系の内でしか何かを語ることができない、というもうひとつの枠がある。
語る動機。小説の語り手が、なぜ、どこに向かって言葉を発しているかという問いは、ここまで考えたことに置き換えると、語り手の「声」と書き手の「身体」による「上演」の動機、ということになる。その「上演」が、先に書いたような「一般的なリアリズム」から逃れて別の可能性を押し広げようとする、それは新たな「声」と「身体」の関係を探るものなのかもしれません。「身体」のないところ(語り手)に「声」(語り)を生むことで、「身体」という制約から「声」を自由にするようなこと。
語り手の「声」はだから、苛立ちとか抵抗によって発せられるのではないか、というのが今回の僕の考えです。なんの苛立ち、何に対する抵抗かといえば、言葉で思考することへの苛立ち、それによって「身体」を要請され、「誰」とか「いつ」とか「どこ」を要請されることに対しての抵抗。松原さんの作品や、ここでのこれまでのやりとり、あるいは黒嵜さんが書いていた「身体なき声」に引っぱられてこういう話になったのでしょうか、きっとそうなのでしょう。
1月15日 滝口悠生
『演劇計画Ⅱ -戯曲創作-』
委嘱劇作家:松原俊太郎、山本健介(The end of company ジエン社)
演劇計画Ⅱアーカイブウェブサイト http://engekikeikaku2.kac.or.jp/
京都芸術センター http://www.kac.or.jp/
-

-
滝口悠生
1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。
-

-
松原俊太郎
作家。1988年熊本生まれ。2015年、処女戯曲「みちゆき」で第15回AAF戯曲賞大賞受賞。2019年、『山山』で第63回岸田國士戯曲賞受賞。他の作品に戯曲「忘れる日本人」、「正面に気をつけろ」(単行本『山山』所収)、小説「またのために」など。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 滝口悠生
-
1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら