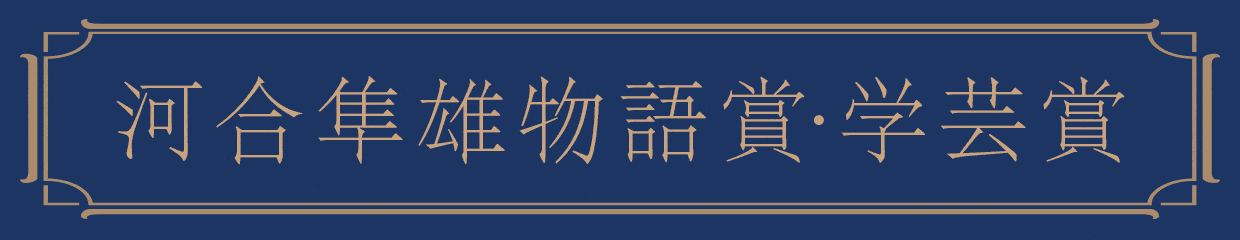2024年6月3日、一般財団法人河合隼雄財団の主催(協力:新潮社)による「河合隼雄物語賞」「河合隼雄学芸賞」の第12回選考会が開催され、授賞作が決定しました。
第12回河合隼雄物語賞

第12回河合隼雄物語賞は、 八木詠美『休館日の彼女たち』(2023年3月刊行 筑摩書房) に決まりました。選考委員のみなさん(岩宮恵子氏、小川洋子氏、松家仁之氏=五十音順)は、「平行の世界に存在するもの同士が魂を交換させることによって、コミュニケーションの可能性を問いかけてくる作品」という授賞理由をあげています。
八木さんは受賞の報を受けて、「物語に生かされてきた者としてこのような賞をいただき、たいへん嬉しく思います」と受賞のことばを述べられました。
著者略歴
八木 詠美(やぎ・えみ)
1988年長野県生まれ。東京都在住。早稲田大学文化構想学部卒業。2020年、「空芯手帳」で第36回太宰治賞を受賞。2022年、同作の英語版『Diary of a Void』が刊行され、「ニューヨーカー」や「ニューヨーク・タイムズ」への書評掲載やニューヨーク公立図書館の年間ベストブックに挙げられるなど話題を呼んだ。現在、世界24カ国語で翻訳されている。2023年、二作目となる『休館日の彼女たち』を刊行。
第12回河合隼雄学芸賞

第12回河合隼雄学芸賞は、湯澤規子『焼き芋とドーナツ 日米シスターフッド交流秘史』(2023年9月刊行 KADOKAWA) に決まりました。選考委員のみなさん(内田由紀子氏、中沢新一氏、山極壽一氏、若松英輔氏=五十音順)は、「日米で産業革命に直面した女性たちが描いた夢と日常的生活実践を克明に描き出した秀作」という授賞理由をあげています。
湯澤さんは受賞の報を受けて、「栄誉ある賞をいただきありがとうございます。過去に生きた人びとの声を現代に伝える一つの物語として、そして学芸として認めていただいたことをうれしく思います。受賞を励みにしてこれからも研究に取り組んでまいります」と受賞のことばを述べられました。
著者略歴
湯澤 規子(ゆざわ・のりこ)
1974年大阪府生まれ。法政大学人間環境学部教授。筑波大学大学院歴史・人類学研究科単位取得満期退学。博士(文学)。明治大学経営学部専任講師、筑波大学生命環境系准教授を経て、現職。「生きる」をテーマに地理学、歴史学、経済学の視点から、当たり前の日常を問い直すフィールドワークを重ねている。『在来産業と家族の地域史 ライフヒストリーからみた小規模家族経営と結城紬生産』(古今書院)で経済地理学会著作賞、地理空間学会学会賞学術賞、日本農業史学会学会賞を受賞。『胃袋の近代 食と人びとの日常史』(名古屋大学出版会)で生協総研賞研究賞、人文地理学会学会賞(学術図書部門)を受賞。他の著書に『7袋のポテトチップス 食べるを語る、胃袋の戦後史』(晶文社)、『ウンコはどこから来て、どこへ行くのか 人糞地理学ことはじめ』(ちくま新書)、『「おふくろの味」幻想 誰が郷愁の味をつくったのか』(光文社新書)等。
授賞作には正賞記念品及び副賞として 100 万円が贈られます。 また、受賞者の言葉と選評は、7月5日発売の「新潮」に掲載されます。
河合隼雄物語賞・学芸賞についての詳細は、一般財団法人・河合隼雄財団のHPをご覧ください。
受賞作発表記者会見
2024年6月3日(月)、一般財団法人河合隼雄財団の主催(協力:新潮社)による「河合隼雄物語賞・学芸賞」の第12回選考会が開催され、受賞作が決定しました。選考会に続いて記者会見が開かれました。はじめに、河合成雄財団評議員、河合俊雄代表理事より開催の挨拶がありました。

(河合成雄財団評議員)それでは、第12回河合隼雄物語賞・学芸賞受賞作決定お知らせの記者会見を行いたいと思います。本日はお集まりいただいて、どうもありがとうございます。まず初めに財団を代表して代表理事河合俊雄よりご挨拶申し上げます。
(河合俊雄代表理事)代表理事の河合俊雄です。よろしくお願い申し上げます。この河合隼雄賞も12回目ということですけれども、年月が経っていくうちに回を重ねるのは嬉しいのですが、昨年、非常に残念なことがありまして、こちらの評議員を務めております私の弟の河合幹雄が11月26日に亡くなりました。お別れ会を3月に開催して、11月3日にここにおられます山極先生と大澤真幸さんをお迎えしての追悼シンポジウムを行いたいと思っています。またご連絡しますので、ご参加いただければと思います。今日は、おめでたい発表の席なので弟の話はこのくらいにして、発表の方に移っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
(河合評議員)ありがとうございます。今年の受賞作の発表に先立ちまして今度新たに河合隼雄物語賞にお迎えした選考委員をご紹介したいと思います。第6回河合隼雄物語賞を『光の犬』で受賞されている松家仁之さんです。
(松家仁之選考委員)松家です。よろしくお願いいたします。
――続いて、第12回河合隼雄物語賞受賞作決定の発表が行われました。
(河合評議員)本年の受賞作は八木詠美さんの『休館日の彼女たち』に決定いたしました。筑摩書房から2023年3月に発行されています。授賞理由は「平行の世界に存在するもの同士が魂を交換させることによって、コミュニケーションの可能性を問いかけてくる作品」ということです。八木さんご本人と連絡を取りまして「物語に生かされてきた者としてこのような賞をいただき、たいへん嬉しく思います」という簡潔な受賞の言葉をいただいております。
――続いて、選考委員より授賞作への選評をいただきました。

(松家選考委員)この授賞作は、ひと言でいえば、大変奇妙な作品です。ちょっと冒頭を読ませていただきますね。
女神が、いた。八角形の部屋で、豊かな肢体を器用にくねらせて。
「あの、こんにちは」
「あなたね。ようこそ」
意外とハスキーボイスだった。メゾソプラノとアルトの間で、どちらかと言えばアルト寄り。もしも合唱をすることがあればだけど。
紹介状を渡そうとすると学芸員が素早くそれを手に取り、女神の前に広げた。私はたちまち硬直する。どうやって女神に手渡すつもりだったのか。しかし彼女は特に気にする様子もなく、やがて口を開いた。
「ホラウチリカさんね。ホーラとお呼びしてもいいかしら」
私はうなずいた。
これはいったいどういう状況なのかというと、大学でラテン語を学んだ女性の主人公が、大学の恩師から、休館日の博物館に行って働くつもりはないかと誘われるんですね。仕事の内容は、展示室のヴィーナスとラテン語で会話すること。無機質なヴィーナスの彫像と日本人の学生が、ラテン語で会話するという突拍子もない設定です。
この主人公の名前はホラウチリカさん。ホリウチではなくてホラウチ。略称、ホーラ。河合先生がもしご存命なら、「ホラですか、ええ名前ですなあ」とおっしゃったんじゃないかと思います。小説にはさりげない冗談、ユーモアの粉もパラパラとかけられています。ただこの主人公はもともと日常的なコミュニケーションをとるのが苦手、人にあまり接しないですむ冷凍庫でのアルバイトを選ぶような人、生きづらいタイプなんですね。そんな彼女が、今は地球上で実際には使われていないラテン語でヴィーナスと会話を始めることによって、だんだんと魂のレベルで、コミュニケーションを取ることができるようになってゆく。
もちろん、さまざまな葛藤もあります。ヴィーナスはほとんど裸体なわけですが、ホーラさんは目には見えない黄色いレインコートを着ていて、このレインコートがだんだん分厚くなっていったりもします。ホーラさんに対して他者から投げかけられる言葉が、分厚い黄色のレインコートにあたって、下にポロポロと落ちていくようなイメージも描かれます。こういう描写がすばらしい。どこか現代詩のような文脈で物語が語られていくところがあります。こんな言葉も出てきます。
私は解放されたかった。誰かを求めることから。私であることから。
幻想的な設定でありながら、こうした内面の問題はとても現代的で、リアルです。私たちはさまざまな端末を通じて、手軽なコミュニケーションの手段をたくさん持っていますが、魂のレベルで他者と繋がることはますます困難になっているのではないか。こうした取り扱いのむずかしい切実な問題にさりげなく深く触れてくる見事な作品です。
ほかにも生身の人間が何人か出てきますが、みんなどこか一筋縄でいかないんですね。ヴィーナスだけだとお話の純度が高まるばかりですが、こうした脇役が濁りとか生臭さとかも送りこんでくる。そうこうするうちにヴィーナスとの関係はしだいにぬきさしならないものになっていきます。
結末は申し上げませんけれども、閉ざされた世界で終わるのではなく、あらたな世界へ踏み出していく物語の余韻があって、作者のたくらみに驚かされます。他者と他者がどう繋がることができるのかという普遍的な問題を書くのは難しいことですが、コンパクトな枚数でありながら深く掘り下げられた素晴らしい作品だと思います。選考委員全員一致で、この作品が選ばれました。
――続いて物語賞の質疑応答に移りました。
(記者)全員一致というのは議論も起こらないぐらいだったんでしょうか。
(松家選考委員)他の候補作にはここで触れられないんですけれども、非常に力のある素晴らしい作品が集まってきたので、議論にはずいぶん時間がかかりました。けれども、最終的な結論を出す段階においては、この作品ですんなりと決まった、ということになります。色合いの違う物語が複数並ぶなかで、一本に絞るのはなかなか苦しいところがあるんですが、この作品は抜きん出てオリジナルなものがある、というのが決定の大きな理由だと思います。
(河合評議員)作品名は申し上げられませんけれども、今の時代に、コロナ後ということで、コロナを振り返って書かれた作品があったのも事実です。
(松家選考委員)受賞作は今の時代に女性が生きることについてどういう困難があるのかにも触れてくるので、設定が突拍子のないものであっても、感覚的に「わかる」と感じる方は少なくないんじゃないかという気がします。言葉でつながるのは難しい、それでもその難しさを乗り越えるのはやはり言葉である、さらに言えば身体性のともなった言葉である、というような言葉に対する確信のようなものが、この著者にはある、という気がします。
(河合評議員)私からもひとつ質問です。松家さんは作家としてもご活躍ですし、編集者としてもいろんな立場、いろんな意見や書きぶりを見てこられたと思うんですけれど、我々選考していて、ここのところ女性の物語が圧倒的に多いと思うんですが、男性の物語の可能性とかそういったところは何かありますか。
(松家選考委員)ジェンダーの話は私の中でもなかなかこうだと言い切れない難しいテーマなので、あんまり迂闊なことは言えないんですけれども、今回上がってきた候補作を読んでちょっと感じたのは、女性があるシチュエーションのなかである種の戦いを戦いながら、なにかをつかんでゆく、というモチーフは結構共通するところがありました。
一方男性はどうかというと、物語を担う人物として何か今ひとつ弱い、力を発揮しきれないという印象なんですね。どちらかといえばなにかを選ぶのは女性で、それに男性が引っ張られていくというような関係性が感じられる気がしました。それがいいとか悪いとかいうことではないんですが。男性主人公がどのような困難にぶつかって、そこにどのような物語が生まれてくるのかというのは、逆に読んでみたい──そんなこと言ってないで自分で書け、ということかもしれませんが。
(河合評議員)ありがとうございます。日本の男性、日本だけじゃなくて世界的にも言えることですが、これまで共有してきた、会社で働くとか外で働く部分が物語の代わりになっていて、そこが崩壊している中で、男性が何を求めて生きているのかというのを誰か描いてくれないかなと。女性であっても男性であっても、あるいは性を超えて書ける、でもかなり女性にフォーカスされた作品がすごく多いな、というのは感じているところです。
(松家選考委員)この作品にも博物館に勤める「ハシバミ」という男性学芸員が出てきますが、この人のセリフにこういう言葉が出てくるんです。「言葉の至るところは失望です。言葉で橋をかけて、橋の長さに彼岸を知る。僕はそれが寂しいんです」っていうんですよね。すごく弱い。(会場笑)そこになにか他人事ではないものを感じながら、読みました。
(小川洋子選考委員)もしかすると特殊な設定を持ってきた空想の、妄想のお話なのかなというふうに思われる方もあるかもしれないんですけれども、実はこの主人公は派遣で冷凍庫の中で働いてまして、現実的な世界の中に出てくるアパートの大家さんであるとか、隣の部屋に住んでいるネグレクトを受けているらしい少年だとか、非常に地に足のついた人物たちとの関わり方にとてもリアリティがあって、決してふわふわした小説ではないと、しかもその大家さんと少年がとても存在感があって愛すべき人物で印象深い。ヴィーナスの彫像っていうのはあまりにも突飛なのでそっちに目を奪われがちですけれど、他の登場人物たちの存在感の魅力というのも、この本の読みどころかなと思います。

(岩宮恵子選考委員)この本を読んでから、この本のことばかり考える日々がしばらく続くような、そんな読後感がありました。このなかに描かれている世界というのは一体何なのだろうということを、いろんな角度から考えたくなるような、そんな本でした。
(記者)私が読んでないので教えていただきたいんですが、ラテン語で語っている設定で日本語で書かれていると思うんですが、そのあたり、ラテン語との言葉の壁を日本語で表現する難しさがある気がするんですけれど、どのように表現されて、そこをどう評価されたのか教えていただければと思います。
(松家選考委員)本来ラテン語で語られる言葉に関しては、日本語で表現されていますが、文字に斜体がかけてあります。イタリック体。それでわかるというのと、これははっきりとわからないんですが、普通にしゃべっているというよりも、ひょっとするとお互い黙って見つめあうだけで、魂のレベルで無言のうちにやり取りしているかもしれない。そこははっきりとは描いてないように思うんですが、ラテン語の表現にはまったく違和感はなかったですね。
(記者)違う言葉で会話していることがわかる、っていう意味での違和感がないっていうことでしょうか。
(松家選考委員)はい、そうです。
(記者)ヴィーナスの石像であるということ、そしてラテン語自体はもう既に死んだ言葉で、喋られていない言葉だというところにも意味があるのかなと感じました。
――他にご質問がなければ、以上をもちまして物語賞の発表を終わりたいと思います。続いて、第12回河合隼雄学芸賞授賞作決定の発表が行われました。
(河合評議員)授賞作品は湯澤規子さんの『焼き芋とドーナツ 日米シスターフッド交流秘史』でございます。授賞理由は「日米産業革命に直面した女性たちが描いた夢と、日常的生活実践を克明に描き出した秀作」。湯澤さんからいただいた受賞の言葉は「栄誉ある賞をいただきありがとうございます。過去に生きた人びとの声を現代に伝える一つの物語として、そして学芸として認めていただいたことをうれしく思います。受賞を励みにしてこれからも研究に取り組んでまいります」ということです。
続いて、選考委員より授賞作への選評をいただきました。

(山極壽一選考委員)この作品はタイトルが面白いですよね。『焼き芋とドーナツ』、このタイトルに惹かれて本を手に取る人も多いと思いますが、これは「19世紀後半から20世紀の日本」「19世紀初頭から20世紀のアメリカ」の話です。同時にではないんですが、両国とも、産業革命初期の女性たちがいかに生きたかと言う話です。
冒頭ですごく衝撃的だったのは『女工哀史』という本、皆さんご記憶にあると思いますが、作者の細井和喜蔵さんの内縁の妻である高井としをさんという女性が、細井さんが亡くなられた後50年近くにわたってさまざまなところに書き綴った文字の断片を、「夜間に学ぶ聖徳学園女子短大の女子学生」たちがガリバン刷りの冊子にまとめた。そこから物語がはじまるんです。
じつは『女工哀史』は細井さんが1人で書いたわけではなくて、そのモデルは、内縁の妻だったとしをさんの生き様だった、ということが刻まれている。としをさんによればまだ書き足らなかった事実がたくさんあった。そのことを、著者の湯澤さんは、「日常茶飯」というふうに報告しています。つまり、『女工哀史』は当時の女工たちが悲惨な労働を強いられていたということが主題で、生活の実態(日常茶飯)が描かれていない。そこで湯澤さんは、執筆のきっかけになった、としをさんの『わたしの「女工哀史」』(先の冊子に加筆したもの)をもとに、悲惨な労働の中で女工たちが実際にはどういう生活をしていたのか、ということを語っていくわけですね。
それが、まずは食べ物です。高井としをさん自身が、縫製工場に勤め転々としながら、同じ境遇にある女工たちとさまざまな意見を交わし、食事の改善を会社に迫っていた。それが次々実現していくという女性たちの連帯が本のテーマです。私達はなかなか想像できない時代ですが、むしろ工場で働く女性たちは農村のしがらみから抜け出てきた喜びにも満ちていたわけです。自分でお金を持ち、自由な時間はいろんなところに出歩き、そして食べ物を買い、自分たちでそれをわけあいながら日々の暮らしをしていた。これを、作者の湯澤さんは“シスターフッド”という言葉を使って表現しました。
ちょっとびっくりしたんですがかつて「魚津の米騒動」という事件がありました。富山県のある漁港で日本全国、なかなか米が食べられないときに米問屋が地元から米をたくさん出すことで、むしろ地元が飢えてしまう。それを女性たちが米問屋を訴えて、日本全国にはこび込むはずだった米の移出を阻止したことに騒動という名前がついて、全国各地に広がりました。
しかしその実態は、魚津では実は騒動ではなかった。ちょうどそのとき大阪にいた大杉栄がマスコミに誇大宣伝をして、それが全国各地に広がって騒動に発展したということが書かれていました。あ、そうだったんだ、と思いました。じつは魚津には伝統的に女性たちが団結して、問屋に訴えにいったり、自分たちの生活改善を様々に女性たちが談判したりという伝統がありました。その伝統に従って、物事は騒動にならずに解決の道に至ったということを、今まで我々はあまり知らなかった。騒動という名前だけが残って、その裏には女性たちの日常生活をしっかり支えようというシスターフッドがあったんですね。これは一例ですが、そういったことが書かれております。
そして同じように、アメリカでは日本とは全く違うシスターフッドがあった。第一次世界大戦に至る過程でアメリカの女性たちが主導権を握った時代があったんですね。それより100年以上前、アメリカでは産業革命がありました。そこでやはり家に閉じ込められていた女性たちが働く機会を得た。貧しい女性たちが家を出て自分たちでお金を稼ぎ、家を支えるということがアメリカでも起きた。
ただ違うのは、食生活が日本とは大違いに豊かだった。自分たちのお金でさまざまな小麦製品を買って、それを食べることができた。そして何より違うのが、文字を手にすることができた。雑誌を発行していたというんですね。工場内の女性たちが自分たちで小説や詩などを書き、編集し、刊行して、同じような境遇にある女工たちと交流をしていた。そういう日本とアメリカとかなり様相が異なるシスターフッドの中で、やはり女性に教育を、そして女性に権利をという運動が起こってきます。そして日本からアメリカに渡って、いまドラマ化されて有名になっていますが、津田梅子たちは当時どういうことを考え、日本に帰国し何をしたのか。明治女学校という学校が最初に作られて、それは理想に満ちたものであったけれども、当時の風潮からすると良妻賢母ということが言われて、女性たちはなかなか教育を受ける権利を得ることができなかった。でも再び津田梅子はアメリカに帰って学者としての道を歩みながら、まさにシスターフッドですね、日米で同じような知己を得て、その影響を受けながら再び日本に帰国してくる。そういうプロセスが描かれている。
両方とも共通しているのは日常からさまざまな活動を立ち上げている。政治に目覚めた女性たちの活動ではないんですね。我々が考えていた歴史観を、事細かに取材をしながら、もう一度生活面から見つめ直して書き綴ったという点で、画期的な本だと思います。日米の様々な歴史的な事情は反映してありますが、そのなかで女性たちのシスターフッド、日常茶飯というようなキーワードを頭に浮かべながら読み進めていくと、共通点もありながら違いもある、両国の歴史が浮かび上がってくると思います。
いろいろと議論をしましたけれども、最終的には物語賞と同じように全員一致で、この本に決まったということでございます。
もう一つ、面白いことが書いてあって、1919年にILO(国際労働機関)が最初にアメリカで開催されたときに、日本から派遣する人が2人候補に挙がったらしいです。
武藤山治さん、これは鐘淵紡績専務取締役だった人ですよね。もう1人は大原孫三郎さん。倉敷紡績を経営していた。結果として武藤さんが選ばれて行った。そのときの議題が、深夜労働をなるべく軽減して労働者の健康を配慮するようにというテーゼだったんですが、当時の紡績工場は深夜労働をしなければ生産性があがらないということで、武藤さんはそれを飲まなかった。
しかし、もしそのときに大原孫三郎さんが派遣されていれば……。大原さんは実は労働者の「人格向上主義」を唱え、教育などによって人格を向上できる存在と考えていた。おそらく深夜労働という規定を廃止するような方向に向かったのではないか。これは歴史の偶然でもあります。
それから先ほど明治女学校ができたことを申し上げました。この創立と運営には当時の文部大臣森有礼の影響が大きく、非常に画期的な女性教育のための学校だったんですね。しかし森はご存知のように暗殺されまして、森が生きていれば、ひょっとしたらもっと早く女性が教育を受けられるような学校が次々にできたかもしれない、そういう可能性も書いておられます。だから歴史というのは、偶然によって左右されるということがありますけれども、日本もいくつかの岐路があったんだということを思い起こさせてくれる話だったと思いました。ちょっと付け足しになりました。

(中沢新一選考委員)『焼き芋とドーナツ』、大変興味深く読みました。この本を読んでみると日本の女性史の問題と、それからアメリカで西部開拓時代から南北戦争を経て女性教育っていうものがすごく理想的な方向に発展していたということがよくわかりました。
この著者は、今まで書いた本を見てもわかりますけど、『胃袋の近代』『ウンコはどこから来て、どこへ行くのか』『「おふくろの味」幻想』、食べることにすごい焦点を合わせた人なんですよね。女性史を書くときに、調理をすること、食べること、それから手仕事、こういう領域の問題は今まで見過ごされてきていましたが、そういうところにだんだん焦点を当てるような女性史が現れてきているんだなっていうのを、とても興味深く思いました。
とりわけアメリカの開拓時代の女性たちがキルトを共同で作るんですよね。若い娘たち、それから年配者が一緒になって端切れを持ち寄って、それによって一枚の大きなキルトを作るわけですが、それが女性の間の強い絆であること、それからキルト1枚1枚の端切れに込められた物語、ちっちゃい物語を通して、その共同体の中で展開したいろんな物語が織り上げられていくような事態が起こっていた。手芸は本当に些細なことのように見えるんですけれども、その奥に大変深い世界が広がっているっていうことをこの著者は気づいています。ですから、調理すること、食べること、手芸や裁縫をやることの中に含まれている女性史を開拓しつつあるんだなっていうことを感じて、大変頼もしく思いました。

(若松英輔選考委員)中沢さんと山極さんが意を尽くしてお話しくださったので、私は内容ではなく、「あとがき――『わたし』の中に灯る火」にある一文が、河合隼雄賞にふさわしいと感じられたので、ご紹介したいと思います。著者は次のように河合隼雄の世界に近づけるような言葉を書いています。
私はこの本を執筆しながら、「対岸」に立つ人びとの心の中に灯った「火」を見つめていた。ここでの「対岸」とは過去であったり、海の向こう側であったり、自分の内面にある他者への認識であったりした。これまで述べてきたように、それらは「一般論」や「通説」、「当たり前」と呼ばれる、いわゆる「こちら側」ではない「向こう側」の世界である。
本書はもちろん学術研究ですけど、私たちのいわゆる「こころ」という世界のもう一つ奥にあって、言葉にならないものにふれながら、人間の生涯の中で作り上げようとした、とても野心的な作品でもあったと思っています。
著者がこの本の中で 「わたし」と「わたしたち」という言葉をとても印象的に用いていて「『わたし』探し、『わたしたち』を生きる」、これが、自分がこれから試みていかないといけないことだとも書いています。歴史を省みるときに「わたし」だけの視座では見えてこないものを、「わたしたち」も含めて見通すことを、今後もおやりになるんじゃないかと、大いに期待している次第です。

(内田由紀子選考委員)この書籍においては、『焼き芋とドーナツ』というタイトルにも象徴的に示されているように、その時代を生きた女性たちが、日常の暮らしの糧を求めて日々努力する、働くことに対するささやかな喜びを通して自己実現する、そこまで大きく価値づけられたものではないにしても、日常を生きていくことと仕事や食事について非常に丁寧に織り込まれながら、学術としても結実した書籍ではないかと評価いたしました。
物語賞の議論の中でもジェンダーの話が出てきましたが、この書籍はジェンダー論としてもユニークなものとして取り上げることができるのではないかと思っています。ジェンダー論の歴史学的、あるいは社会学的な分析というのは、女性がどう扱われてきたかとか、どのように結束して社会運動を起こしたかというような非常にトップダウン的な概念や目標ベースに語られることが多かったと思いますが、この本の中ではまさにシスターフッドという言葉に表現されているんですけれども、女性たちが自分の仕事で生きる糧を稼いでいく、そしてそれを人々と分け合う、例えばキルトというものを通して表現していく、そのささやかな一つ一つを行っているうちに、まさにキルトを織り成していくように大きな社会運動の流れになっていく。それが見事にこの書籍の中で表現されているのではないかと思いました。ジェンダー史という意味からも、日々のささやかな生活のために仕事をされている女工の方々に焦点をあてた点でも、ユニークで価値のある学術文書ではないかと思いました。
(河合評議員)ありがとうございます。内田さんが今おっしゃったことは日本だけではなくて、世界的に見ても新しい視点ということですか。
(内田選考委員)おそらくそうだと思います。やはりどうしてもジェンダー論というのはどちらかというとやはりトップダウン、頭でっかちになってしまうところがあると思うんですね。それは女性研究者としても、例えば女性研究者だからとか、女性としてどう思うかっていうふうなことを問われたとき、実は非常に一番難しい問題だと意識せざるを得ないことが多いですね。
でも実際のこういう女性たちが本当に働き始めるとか、社会のなかに出ていきはじめる発端はこういうところにあるということを、世界的にも多分きちんと示されたっていうことで価値があると思います。
――続いて学芸賞の質疑応答に移りました。
(記者)物語賞・学芸賞の両方でお尋ねしたいんですけれども、12回重ねられて、物語性という観点からいって、時代としてもどのくらい新しいことが出てきているかということと、活字業界に対する期待と課題をお伺いしてみたいです
(河合評議員)ある意味、物語というコンセプト自体が抽象的で、河合隼雄がやってきた本当の実績とか社会的に貢献したのはなにかと考えた時に、キーワードになるのが魂っていうとすごく難しく怪しげである。だから物語というところまで落とし込むと、それなりに社会との接点とか、いろいろと考えながらやっていけるんじゃないかというところがあって、元々このコンセプト自体がそこから発していることもあって、第1回から12回にかけて変わってきたかと言われるとそういうことはあまりないのじゃないかなと。
幸いに第1回の選考委員をされている方がまだ半数残っておられて、ずっと同じそれぞれの視点を持って、選んできているということがあります。河合隼雄が投げかけた社会的な問題とか意識とか、そういうものはやはり解決されない。解決できるものでもないけどもずっと引き継がれているので、どう変わってきたかということが見えるほどの時間も、12年、12回ではまだないのではないかというのが私の個人的な感想です。
(河合俊雄代表理事)私は主に学芸賞の方に関わっているのですが、分かりやすい物語っていうのが難しいのかな、と。これまでも、物語にならないような物語をどうキャッチしていこうかということは物語賞自体が探しているんじゃないか、ということを毎回のように感じます。むしろ学芸賞の方が、物語性のあるものを割と選んでいるのでは。今回も非常に物語性の高い作品じゃないかな、と思っています。そして、必ずしも河合隼雄につなげなくてもいいと思いますが、選んだときはこういう話はなかったのですが、河合隼雄は「女性の意識」ということを非常にテーマにしていて、「女性の意識」って何かというと、内田委員からも話があった通り、頭でっかちな意識ではないんですよね。日常性から、手を動かしながら、生活の中から生まれてくる女性の意識のあり方、つながりなどが、河合隼雄賞にふさわしいな、と。これは後から思っているところなので、議論の中にはなかったのですが、こういう風に変わってきて、色々な局面が見えるところがこの賞の面白いところではないかな、と思っています。
(山極選考委員)河合隼雄賞だということを、すっかり忘れていました。(会場笑)さっき若松さんがおっしゃって、ああそうだったよな、と改めて思いました。僕は一貫して、学芸賞は気づきを与えてくれるものだと思っています。それは1回目から変わらないという気がしました。歴史の見直しっていうことが結構話題に上りますが、いま科学的な事実よりもナラティブが人々を動かす大きな原動力になっていますよね。たぶん、河合隼雄さんはそのことに昔から気づいていたと思うんですね。心のひだに分け入っていくための物語がなにか。事実であってもいいし、事実を組み合わせたメッセージであってもいい。それは一直線に並んでいるものではない。そこが、じつはこの学芸賞の大きなテーマじゃないかなと思いました。
これまで12回を振り返ってみると、それぞれに気づかせてくれたものが非常に強いなと思います。今回もそうです。いろんな視点があるけれども、まさに日常生活の中で大事な食べ物、それからさきほどキルトという話が出ました。ここで私が「おっ」と思ったのは、「哲学は台所から生まれる」って書いてあるんですよ。哲学というと高尚な思想だとか、古今東西の有名な人たちの思索から生まれるんだと思っていたけれども、じつは台所から生まれるんだ。それいいな、って思いましたね。これも気づかされたひとつのことじゃないかと思います。
(松家選考委員)授賞理由に「平行の世界」と書いてありますけど、平行という真理についてもこの小説の中では論じられています。つまり、本来決して交わらないものが「平行」です。人間とヴィーナス像も交わるはずがない。コミュニケーションも成立しない。どこまでいっても平行なもの。
それでちょっと思い出したんですが、河合先生の書かれた『こころの処方箋』という本の中で、結婚相手についてだったと思いますが、川の向こう岸とこっち側とで別々の人生を歩んできた他者同士なのだから、その両岸はあまり離れすぎず、向こう側にも渡りあえるような相手がいいような気がしますよね。ところが河合先生は、川幅は広ければ広いほどいいんだと書いていらっしゃる。どうしてか。川幅が広ければ、網をかけられる範囲がぐんと広がるじゃないかと、収穫物がたくさんとれるかもしれませんよ、と書いていらっしゃる。その話が頭に蘇りました。
平行という言葉を、今の世の中の言葉でしきりに使われるもので言い換えるなら、「分断」かもしれません。分断されたら、もう決して交わらないと諦めてしまうのではなく、交わり得るんだよ、と。読み終えた時に奇妙な希望の兆しが感じられる作品でもある、と思いました。
(中沢選考委員)先ほど学芸賞というものはどういうものかという話が出ましたけれども、僕は最初からずっと審査員をやっていますが、世の中にはいろんな学芸賞がありますけど河合隼雄賞は本当に難しいんですよ。面白い話、斬新な研究であれば授賞というわけにいかないんですね。
先ほどから“魂”という言葉が出てきていて、こんな言葉本当は使っちゃいけないんだろうけど、使わせてください。読んだ人の魂の中に入っていくような研究でないと、河合隼雄賞って言えないんですよね。毎回立派な研究は出てきますけど、これはただの研究だよ、っていうのがあるんですね。ですからその中から毎回ただの研究、プラスアルファというものが入っていたらピックアップしよう、っていうのが河合隼雄学芸賞です。かなり選考委員のハードルが高いんです。そこをお汲み取りください。(会場笑)
――最後に、河合成雄財団評議員より挨拶がありました。
本当に皆さんよく物語とは何か、このことをずっと突き詰めて毎回悩みつつ選んでくださって、非常に嬉しいところです。この賞がどういうふうにできているかという雰囲気なり、背景なりをご理解いただくために、ぜひとも授賞式に足を運んでいただければと思います。またそのときに選考委員からの授賞理由について、いろいろお話を伺うのも面白いんじゃないかと思います。私もいつも楽しみにしております。また、物語賞・学芸賞合わせて、正式な受賞の言葉と選評を月刊「新潮」8月号(7月5日発売)誌上で発表する予定でございます。それでは、これにて終了いたします。本日はご参加ありがとうございました。
-

-
考える人編集部
2002年7月創刊。“シンプルな暮らし、自分の頭で考える力”をモットーに、知の楽しみにあふれたコンテンツをお届けします。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 考える人編集部
-
2002年7月創刊。“シンプルな暮らし、自分の頭で考える力”をモットーに、知の楽しみにあふれたコンテンツをお届けします。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら