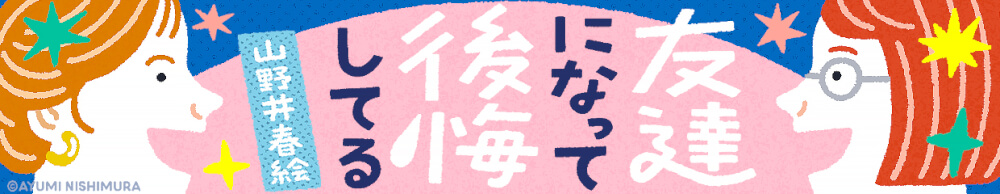第6回 1999年7の月、恐怖の大王とともに去った親友へ
著者: 山野井春絵
「LINEが既読スルー」友人からの突然のサインに、「嫌われた? でもなぜ?」と思い悩む。あるいは、仲の良かった友人と「もう会わない」そう決意して、自ら距離を置く――。友人関係をめぐって、そんなほろ苦い経験をしたことはありませんか?
自らも友人との離別に苦しんだ経験のあるライターが、「いつ・どのようにして友達と別れたのか?」その経緯を20~80代の人々にインタビュー。「理由なきフェイドアウト」から「いわくつきの絶交」まで、さまざまなケースを紹介。離別の後悔を晴らすかのごとく、「大人になってからの友情」を見つめ直します。
※本連載は、プライバシー保護の観点から、インタビューに登場した人物の氏名や属性、環境の一部を変更・再構成しています。
弁護士資格を持ち、企業の法務部に勤務する浩一さん(47)は、男の子2人のパパ。子どものころ仲良くしていた、忘れられない友達がいるという。秀明さん(ヒデ君)とは幼稚園から中学校まで一緒に通った仲だったが、20年以上前から音信不通だ。「子どもたちが成長する姿を眺めているうちに、ヒデ君のことを思い出すようになりました。自分にとって、友達の存在とはどんなものなのかと改めて考えています」。今さら連絡を取ったところでどうなるものでもないと思いながら、もしも機会があるならば、どうしても彼に一言だけ伝えたいことがある……浩一さんはそう言って、幼い日の記憶をたどりはじめた。
森の中に暮らしていた芸術一家
私と秀明……ヒデ君は、とある地方都市の郊外出身です。私の父はインフラ企業のサラリーマンで、当時は団地の社宅暮らしでした。社宅の隣はこんもりとした森で、その奥に芸術大学の職員寮がありました。2、3世帯の小規模な集合住宅があちこちに点在するその森は、ちょっと別荘地のような雰囲気がありました。ヒデ君の両親はともに芸大の先生で、一家はそのうちの一つに暮らしていたのです。うちの団地はよくある殺風景な建物でしたが、芸大の住宅棟はどれもカラフルで、ストリートアートが施されたような壁がいくつもありました。教員や学生たちが自由に描いていたのでしょう。
松ぼっくりやどんぐりがちらばる森の中には、手作りのアスレチックがあり、その脇には、不思議な造形物が転がっていたり、描きかけのキャンバスが立てかけてあったりして、時おり、楽器の音やオペラの練習をする歌声が響いてきました。子ども心にもその森は異空間で、遊びに行くたびにワクワクしたものです。森では探検ごっこ、ヒデ君の家では粘土遊びや工作、ヒデ君のお母さんに紙芝居を見せてもらったりしました。
ヒデ君には兄と妹が、私にも妹が2人いますが、子ども時代はきょうだいよりもヒデ君との思い出の方が濃厚です。特に趣味もない私の母が、個性的なヒデ君のお母さんとどのように付き合っていたのかはわかりません。一番近くに住む同級生ということで、私たちはいつも一緒でした。幼稚園バスでは隣同士。小学校の入学式に手を繋いでいる写真が今でも残っています。
私たちは3、4歳から、森の一角にある教室でピアノを習いはじめました。ヒデ君はどんどん上達して、すぐにツェルニーの練習曲に入りました。私はダラダラと小4くらいまでバイエルを続けていたと思います。ヒデ君と一緒ならば、と、いやいやながら教室に通い、ヒデ君のピアノを聴きながら、私は書棚にあった古い漫画本『プロゴルファー猿』や『ドラえもん』を読み耽っていました。私のレッスンを待つ間、ヒデ君は『火の鳥』や少女漫画を読んでいた記憶があります。
私の長男は今、8歳です。妻の意向でピアノを習っていますが、私に似て音楽の才能はなさそうです。「サッカーの方がいい」とぼやきながら、しぶしぶ鍵盤に向かっている姿は、かつての自分そのもの。私も小中学生のころはサッカー少年でした。
仲間はずれ事件
幼いころのヒデ君は、まんまるなマッシュルームカット。いつも果物や花など、女の子っぽいモチーフがついた洋服を着ていました。本人が好んでいたのか着せられていたのかはよくわかりませんが、小学生になっても夏はかなり短いショートパンツで、冬はベルボトムのジーンズという、個性的なファッションでした。色白で、ヒョロヒョロとして、早くから分厚いメガネをかけていました。街ではよく女の子に間違われ、そのたびに「ボクは男です!」と訂正していました。
小学生の私はスポーツにのめり込んでいきました。学校の休み時間や放課後はサッカー。夕飯時は父親とともにテレビの野球中継にかじりつき、プロ野球カードの収集にも夢中でした。それでも登下校はいつもヒデ君と一緒でしたし、相変わらずお互いの家を行き来していたのです。ヒデ君はスポーツには興味がなく、学校では図書館を好み、女子と話している姿もよく見かけました。そんなヒデ君は、高学年になると、男子の中でだんだん浮いた存在になっていきました。女子と仲がいいことへの嫉妬もあったと思います。やがて誰かが陰でヒデ君のことを「オンナオトコ」と呼ぶようになりました。あだ名はどんどん広まって、そのうち、ヒデ君を仲間はずれにしようというムードが高まっていきました。恥ずかしながら、私も彼を仲間はずれにする側についたのです。
「おい、浩一。お前、オンナオトコの親友だろう。お前もオンナオトコか」
友達の一人にそんなふうに言われ、私は言い返しました。
「僕はオンナオトコじゃない!」
「じゃあ、証明してみろよ。ヒデとは一生口をきかない、絶交するって約束しろよ」
「約束してやるよ!」
こんな感じの、売り言葉に買い言葉だったと思います。勢いで、私が先頭に立って、ヒデ君を仲間はずれにするキャンペーンをはじめることになってしまいました。
「こうちゃん、帰ろう」
下校時、いつものようにヒデ君が誘ってきましたが、私は黙って他の友達と教室を出ました。ヒデ君の家に立ち寄ってから一緒に登校する朝の習慣も、やめてしまいました。ヒデ君はクラスで孤立していきましたが、平然としているように見えました。それが気に入らないと、ますます意地悪をする子が出てきます。
数週間ほど、そんなことが続きました。ある日、私が仲間たちとつるんで下校しようと集まっている教室に、ヒデ君が入ってきたのです。まっすぐ私の正面に立つと、言いました。
「ねえ、ボクの、何が嫌なのか教えて。それをボクは、全部直すから。だから仲間はずれにするのはもうやめてくれない?」
私は驚いて何も言うことができませんでした。すると、一緒にいた男子の一人が、
「バーカ、お前、オンナオトコだろう。気持ち悪いんだよ。髪型とか、服とか」
そう言って、ヒデ君のことを当時人気だったお笑いバラエティ番組に出てくるキャラクターにたとえましたが、テレビをほとんど観ないヒデ君はピンときていない様子でした。
「お前、そんなことも知らないのかよ。ダサいな。テレビないのかよ」
ヒデ君はしばらく考えて、じっと私の目を見て言いました。
「わかった、テレビでそれを観る。それから、髪型と服を変える。それでいいんだよね? ボクの見た目が、みんなに迷惑をかけているとしたら。それを変えればいいんだよね?」
私は目を逸らし、黙って自分の足元を見つめていました。
ヒデ君は静かに教室を出ていきました。仲間はまだヒデ君の悪口を言っています。
「もうやめよう。……別にヒデは何も迷惑をかけてないわけだし」
私はそう言って、一人で帰宅しました。
ヒデ君はランドセルを背負ったまま、うちの玄関の前にしゃがんでいました。そして、テレビを見せてほしい、と言いました。その夜リアルタイムで観たのか、ビデオを見せたのかは記憶が曖昧ですが、とにかく私たちはうちの居間に並んで座り、件のお笑い番組を観たのです。私にとっては面白くて、ずっと爆笑していました。当時の私は、いや大半の大人たちも、そのキャラクターの問題性に何一つ気づいていなかったのです。ヒデ君はコントを観ている間、笑うでもなく、じっと黙ったままでした。特に感想もなく、帰っていきました。
翌日、学校に現れたヒデ君は、スポーツ刈りになっていました。そして、サイズの合わないサッカーウェアを着ていました。お兄さんのものを借りたのだと思います。それ以来ヒデ君に対するいじめはピタリと止みました。ヒデ君は相変わらず図書館や教室で本を読み、女子と楽しく遊んでいました。はじめは腫れ物に触るような雰囲気だった男子も、また自然に会話するようになっていったのでした。
どうしてクマのぬいぐるみはかわいくないと言ったの?
これも小学校時代の出来事です。私とヒデ君は、毎年ピアノの発表会に出ていました。何回目の発表会だったか……私がブルグミュラーの『アラベスク』を、ヒデ君がドビュッシーの『グラドゥス・アド・パルナッスム博士』を弾いたときのことです。ヒデ君の演奏は繊細さと力強さを兼ね備えた素晴らしいもので、子ども心にも私は「ヒデ君は将来ピアニストになるといいな」と思っていました。
発表会の後には、先生が子どもたちにプレゼントを配るのが恒例でした。
その年、先生が用意したのは「猫の指人形」と「クマのぬいぐるみ」の2種類。高学年の私にとって、それらはどちらも「女っぽいアイテム」であり、特別にほしいわけではありませんでした。しかし単なるぬいぐるみよりは、ギミック感のある指人形の方に魅力を感じ、「絶対に指人形をもらおう」と瞬時に判断。ところが、私はどうしてもトイレに行きたくなって、いったんプレゼントに並ぶ列から離脱したのです。
急いで先生のもとへ戻ると、もうクマのぬいぐるみしか残っていません。絶句していると、先生が笑顔でクマのぬいぐるみを手渡してきました。
「浩一君、頑張ったわね。はい、クマちゃんよ。かわいいでしょう?」
「……かわいくない」
私は不貞腐れて俯きました。指人形を選んだ生徒たちは、手放したくないとばかりに、ぎゅっと胸に抱いています。しばらく、誰も口をきかず、膠着状態になりました。テーブルの上には、ひとつだけ残ったクマのぬいぐるみがうつ伏せになっていました。
そこへヒデ君が進み出て、クマのぬいぐるみを抱き上げ、代わりに自分がもらった指人形をテーブルに置きました。ピアノの先生はホッとした表情で、
「まあ、ヒデ君、浩一君に指人形を譲ってくれるの?」
ヒデ君は黙って頷きました。
私は驚きました。ヒデ君は自宅で2匹の猫を飼い、森でも数匹、お気に入りの野良猫を世話している、大の猫好きだったのです。絶対に、猫の指人形がいいに決まっているのです。
「え、ヒデ君、いいの」
「うん。いい」
こうして私は猫の指人形を手に入れました。
発表会から、ずいぶん後のことです。その日ヒデ君は私の家に遊びにきていました。日が暮れて、ヒデ君が帰宅する時間になり、私も見送ろうと狭い玄関に立ちました。そのときヒデ君は靴を履くと、おもむろに振り向いて、言ったのです。
「ねえ。どうしてあのとき、クマのぬいぐるみはかわいくないと言ったの?」
虚を衝かれ、私は言葉を失いました。ヒデ君は、まっすぐ私の目をて直立したまま、身じろぎもしません。
そのまま、30分ほど、私たちは無言で向き合っていました。それは本当に長い時間でした。
今なら、たとえば「自分が中座している間に勝手に分配されたことに不満を持ったから」とか、「猫の指人形の方がよっぽどいいと思ったから」とか、「自分はわがままであり、不貞腐れた、反省している」などと、自分の気持ちを解説できるのですが、当時の私は、そんな表現力を持ち合わせていませんでした。国語の記述式問題を一文字も埋められないかのように、私はとにかく押し黙ったまま、挙動不審に目を動かしているだけだったのです。
やがて、
「……まあ、いいや。バイバイ」
ヒデ君はそう言って、玄関を出ていきました。
変な気分で散らかった自分の部屋に戻り、腹ばいになって漫画を読みはじめました。そのときふと、本棚と机の隙間に、あの指人形が落ちていることに気づいたのです。
「本当はボクじゃなくてもよかったんだよね?」。埃にまみれて空を見つめる猫の指人形が、ヒデ君の声でそう言っているように思えました。なんともいえない、恥ずかしさのようなものを感じながら、私は指人形を拾い上げ、壁に立てかけてあったプラスチックの小さなバットの先にそれを被せたのでした。
「俺」っていう一人称は信用ならない
私たちは同じ地域の中学に進学しました。そのタイミングでわが家は分譲住宅に引っ越し、ヒデ君の家からはずいぶん遠くなってしまいました。森の中のピアノ教室も中学に入る前に辞めてしまいましたが、ヒデ君は、中学を卒業するまでずっと続けていたと思います。妹たちが習っていたので、私の母は毎年ピアノ発表会を観に行っていました。
「ヒデ君のショパン、素晴らしかったわよ! 浩一も観にくればよかったのに」
母が興奮気味にそう言っていたのを思い出します。
私はサッカー部、ヒデ君は囲碁将棋部という名の帰宅部。中学ではクラスも友達も異なり、廊下で顔を合わせれば挨拶をする程度でしたが、私はやっぱりあのヒデ君が暮らす森の家が好きで、たまに自転車で遊びに行きました。
ヒデ君の家の居間には、両親の趣味であるレコード盤と本とが壁一面にぎっしり収められていました。ヒデ君は古いレコードプレイヤーを動かして、私にアントニオ・カルロス・ジョビンやジョン・コルトレーン、YMOなどさまざまな音楽を聴かせてくれました。「いつかこれが弾きたい」と、ジョー・パスのレコードをかけながら、はじめたばかりのギターを握りしめていた横顔を思い出します。その頃、同級生の間で流行っていたのはチャゲ&飛鳥やドリカム、洋楽もボーイズⅡメン、マライア・キャリー。私にとって、ヒデ君が聴かせてくれる音楽はなんだか新鮮でした。窓からは鬱蒼とした緑が見え、外国土産の置物がいくつも飾られたその家には、一般的なサラリーマンのわが家にはない、独特の雰囲気があったのです。
ヒデ君は体育以外の成績はすべて抜群で、私服で通える憧れの公立進学校に合格しました。私もその高校に行きたかったのですが、成績が足りず、管理型の進学校に進みました。ほとんど会えなくなりましたが、高1のとき、ホームステイ先のカナダから帰ってきたばかりのヒデ君に会ったことがあります。ヒデ君は少し日焼けをして、明るい印象でした。久しぶりに家へ遊びにいくと、ホストファミリーに教わった「キャセロール」というひき肉と豆が入ったオーブン料理を手作りしてくれました。
「俺、こんなうまいもの食べたの初めてだよ!」
私が感動していると、ヒデ君はスプーンを持つ手を止めて言いました。
「ねえ、こうちゃん。こうちゃんはいつから自分のことを『俺』って言うようになったんだっけ? こうちゃんは『僕』っていうのが似合うと思う」
「え。そう? 考えたことなかった」
「俺っていう一人称、なんだか信用ならないな。もっと言うと、手紙とかで俺って書いてくるやつが、特に苦手なんだ」
ヒデ君が私以外の男と手紙のやり取りをしているとは意外でした。中学まで、私とヒデ君の共通の友達といえば、女の子だけだったからです。
「ヒデ君、俺が俺って言うの嫌なの?」
「少なくとも、こうちゃんには似合わないと思う」
「ふーん、じゃあ、僕に戻そうか」
「うん」
ヒデ君はその後、アメリカに留学しました。何回かエアメールでやり取りをしましたが、その際「俺」という一人称を使わないように気をつけました。
留学先で、何があったのかはわかりません。途中から、手紙は届かなくなりました。ヒデ君は心を病んでしまったそうです。帰国しても高校には通えず、そのまま退学して、フリースクールのようなところに入ったと聞きました。
「ヒデ君、何回もリストカットをしちゃってるんだって」
母からそう聞いて、とても驚きました。
ボクはこの世界では、溺れちゃう
私は一浪の末、京都の大学に進学しました。数年ぶりにヒデ君と再会したのは、私が3回生の夏でした。当時、私は初めて本気で好きになった女性に振られ、ヤケになってアルバイトとパチンコ三昧、ほとんど大学に行っていませんでした。勉強も、就職活動をはじめる気力もわかず、このまま退学してもいいとすら思っていました。ヒデ君は、そんな私が一人暮らしをしていた狭いアパートに、突然電話をかけてきました。番号は私の母に聞いたそうです。
ヒデ君に指定されたのは、先斗町にある高そうな割烹料理店でした。恐る恐る入っていくと、小上がりの席に長髪のヒデ君と、見知らぬ髭面の男性が座っていました。当時その男性は50代。美術系の仕事をしている人でした。ヒデ君は、東京のその男性の家に居候しているのだと言いました。その日、私は生まれて初めて鱧を食べ、鮎の塩焼きから骨を抜く方法を知り、日本酒をおいしいと思いました。夕食の後、近くのバーに入り、納涼床から鴨川を眺めて、勧められるままにカクテルを飲みました。男性は支払いを済ませると、「俺は先にホテルに戻っているから、お友達とゆっくりしておいで」とヒデ君にいくらかお札を握らせて去って行きました。私たちは店を変えてもう少し飲んだ後、鴨川の河原に降り、カップルとカップルの間に場所を見つけて座りました。
私はこのとき、なぜだか、ヒデ君にあまり深く色々と質問してはいけないと感じていました。高校を中退したヒデ君は大学の先生だったお父さんから、知り合いの男性に預けられ、何かしら修業のようなことをしているのだろう……という想像で、勝手に納得することにしたのです。ふだん飲み慣れない酒で酔ったせいもあり、このときヒデ君と何を話したのか、断片的にしか覚えていません。ただヒデ君が手首につけていたタオル地のリストバンドが赤色だったことと、最後に交わしたやり取りだけを鮮明に覚えています。
鴨川に石を投げて、ヒデ君は言いました。
「こうちゃん、大学、がんばってね」
やけっぱちな毎日を過ごしていた私は、吐き捨てるように答えました。
「すぐに世界は終わるんだから、もう、どうだっていいよ」
1999年7の月、空から恐怖の大王が降ってくる。ノストラダムスはそう予言したそうです。私たちは子どものころから、人類滅亡の日が来ると信じていました。
ヒデ君は笑いました。
「こうちゃん、ボクはね、もうすぐこの世界が終わることに、ホッとしてるんだ。ボクはこの世界では、溺れちゃうから。だけど、こうちゃんの世界は終わらない気がする。こうちゃんは何か、すごく大事な仕事をするんじゃないかな。だってこうちゃんは、この世界で元気に泳いでいられる人だから」
ヒデ君と橋を渡って、駅の入口で別れました。私は改札に向かって階段を降り、振り返って仰ぎ見ると、ヒデ君はゆっくりと私に手を振っていました。
バイバイ。
これが、ヒデ君を見た最後です。
ヒデ君にどうしても伝えたかった一言
ヒデ君が言った通り、私の世界は終わりませんでした。
その夏の終わり、母が脳梗塞で倒れ、軽い後遺症が残ったことをきっかけに、私は司法試験を受けることを決意しました。五体満足で親の脛をかじっている学生の身が、だらだら腐っていることにわれながら嫌気がさした……という感じでした。大学院に進む準備をはじめ、がむしゃらに勉強をしました。5度の挑戦で司法試験に合格して、いくつかの事務所を渡り歩き、現在に至ります。
大学院生のころ、京都のアパートにヒデ君がポストカードを送ってくれたことがありました。私も当時の彼の東京の住所に、自分の近況とメールアドレスを書いた手紙を返しました。その後、旅先だというヨーロッパからエアメールが届き、私はもう一度東京へ手紙を送りましたが、宛先不明で戻ってきてしまいました。それきり、消息は途絶えてしまいました。
私たちの家があった場所は、10年ほど前に整然とした住宅地に変わってしまいました。団地も、森も、きれいさっぱりなくなって、母に聞いても、ヒデ君の家族がどこに引っ越したのかわかりませんでした。
ヒデ君のことを頻繁に思い出すようになったのは、長男が小学生になってからです。長男はよくも悪くも私によく似ていて、あまり文化的なセンスがありません。ほとんど本も読まずゲームばかり、たまにスポーツ漫画を読む程度。テレビやネットでおぼえた下品な流行り言葉を友達と一緒に連呼している姿は、そのまま自分の子ども時代を見ているようです。
いつか息子たちにも、私にとってのヒデ君のような友達に出会ってほしい。自分とは違う世界観を持つ、知的で、ちょっとミステリアスな友達。ヒデ君の家で出合った音楽は、私の世界を広げてくれました。受験中の息抜きにはよく図書館で読書をしましたが、選んだのはヒデ君の家の書棚に並んでいた近代文学や外国のミステリでした。今ふたたびそれらを読み直すと、さまざまな思いがこみ上げてきます。年齢を重ねるほどに、ヒデ君と過ごした日々が自分に及ぼした影響の大きさを感じるのです。
京都にヒデ君と一緒にやってきたあの男性の情報を知ったのは、最近のことでした。たまたま古書店でその人の著書を見つけたのです。調べてみると、すでに70代で亡くなっていました。彼は晩年自らのセクシュアリティを公表しており、若い恋人と暮らす日々を描いた耽美的なエッセイは、登場人物の一人にヒデ君を想像させました。
あの男性はヒデ君を愛していたのだろうと思いますが、ヒデ君はどうだったのでしょう。そういえば一度だけ会ったあの日、あの男性は、自分のことを「俺」と言っていました。エッセイも一人称が「俺」だったので、私は、きっとヒデ君は本当の心を彼に見せることはなかったんじゃないかな、と思っています。
ヒデ君に何があったのか、私にはわかりません。ヒデ君のような人は当時、さぞかし生きづらかったことでしょう。ヒデ君は時代を先取りした審美眼を持ち、真実を追い求める、純粋な青年でした。一方自分は、とにかく単純で鈍感で、ヒデ君のことを何ひとつわかっていませんでした。
でも、これは想像ですが、その何もわかっていなかった自分との関係は、ヒデ君にとって、気楽だったのではないでしょうか。
ヒデ君は今、どうしているのだろう? 何度かネット検索してみましたが、見つけることができませんでした。唯一、お兄さんと思しき人物が、東京で建築士をしていることを知りました。どうしてもヒデ君に連絡を取ろうとするならば、そのお兄さんをたどってみればいいのでしょうが、今は、そこまでしようとは思いません。気まぐれに、ヒデ君が私の実家に連絡をくれたらいいなあ、などとぼんやり考えています。
正直に言えば、私からどうしてもアクションできない一番の理由は、「怖いから」です。ヒデ君は、もう、この世にはいないのではないか。なぜか、そんな気がするのです。確かめることで、それが本当のことになってしまうのが、とても怖いのです。
たまたまばったりと、どこかで再会する。居酒屋のカウンターにでも並んで、近況を軽く話す……もしもいつか、そんな機会があったなら、ヒデ君に伝えたいことがあります。
「僕は君をずっと、尊敬しているよ」。
(※本連載は、プライバシー保護の観点から、インタビューに登場した人物の氏名や属性、環境の一部を変更・再構成しています)
-

-
山野井春絵
1973年生まれ、愛知県出身。ライター、インタビュアー。同志社女子大学卒業、金城学院大学大学院修士課程修了。広告代理店、編集プロダクション、広報職を経てフリーに。WEBメディアや雑誌でタレント・文化人から政治家・ビジネスパーソンまで、多数の人物インタビュー記事を執筆。湘南と信州で二拠点生活。ペットはインコと柴犬。(撮影:殿村誠士)
この記事をシェアする
「山野井春絵「友達になって後悔してる」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら