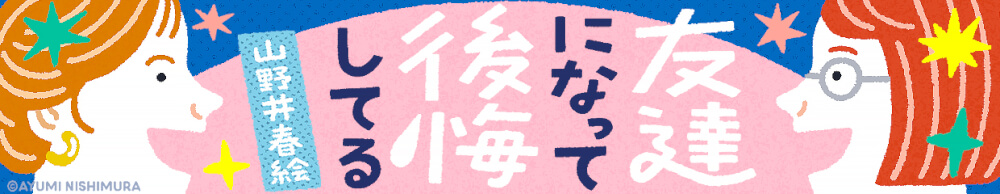第10回 フランス・美しく小さな村の絶縁物語
著者: 山野井春絵
「LINEが既読スルー」友人からの突然のサインに、「嫌われた? でもなぜ?」と思い悩む。あるいは、仲の良かった友人と「もう会わない」そう決意して、自ら距離を置く――。友人関係をめぐって、そんなほろ苦い経験をしたことはありませんか?
自らも友人との離別に苦しんだ経験のあるライターが、「いつ・どのようにして友達と別れたのか?」その経緯を20~80代の人々にインタビュー。「理由なきフェイドアウト」から「いわくつきの絶交」まで、さまざまなケースを紹介。離別の後悔を晴らすかのごとく、「大人になってからの友情」を見つめ直します。
※本連載は、プライバシー保護の観点から、インタビューに登場した人物の氏名や属性、環境の一部を変更・再構成しています。
フランス人男性と国際結婚をしていたキミコさん(57)は、フランス北部の都市で一人暮らしをしている。現在はオンラインで日系企業の仕事に就いているが、離婚前後は田舎町にあるレストランで働いていた。オーナーは、10歳年下のフランス人女性。仕事にはやりがいがあり、彼女に対しては「人種も年齢差も超えた本当の友情」を抱いていたという。しかし、キミコさんが退職を申し出たことをきっかけに、関係は強制終了。「利害関係が崩れたら、これまで見えなかった部分が明らかになりました」。そこからキミコさんが考えたこととは……。
言葉の壁を越え、心が繋がったノルマンディの夜
日本に駐在していたフランス人、ポールと熱烈な恋愛を経て結婚したのは、大学を卒業してすぐのことでした。長男が生まれて数年後、家族でフランスへ。ポールの実家がある北部ノルマンディ地方の都市に家を借り、私にとってはそれが初めての本格的な海外生活でした。ポールはその街で小さな商社を興し、やがて次男が生まれました。
ポールは私たち家族をキャンピングカーに乗せ、仕事でフランス中をめぐりました。最終的にはアフリカにたどり着き、そこで商機を探すことに。電気も水道もない海辺の街で1年間暮らしたこともあります。毎日がサバイバルでたいへんでしたが、今振り返ってみれば、家族4人が寄り添って生きた、いい時間だったのかなと思います。
息子たちの進学を考えて、ポールだけがアフリカに残り、私がキャンピングカーを運転して、3人でノルマンディに戻ったのが、15年ほど前のこと。義両親の助けを借りながらのワンオペ生活がはじまりました。
しばらくして、私は義父の知人が経営しているケーキ屋さんのキッチンで週に1、2度アルバイトをはじめました。隔月くらいのペースで帰宅していたポールでしたが、やがてその間隔が大きくなり、ついには帰って来なくなりました。
落ち込む私を慰めてくれたのは、長男の学校でできたママ友・ルイーズでした。ルイーズの夫はカナダ人で、英語を話したことから、唯一心を許せる友達だったのです。なぜなら当時の私のフランス語は流暢とはいえず、ポールともほとんど英語で会話をしていました。地方都市では、英語を話せる人がまだまだ少ない時代でした。義父母とはフランス語で、日常会話くらいはできていましたが、心の中をさらけ出すような会話は難しいと感じていました。
日本へ帰るべきか。しかし日本語の読み書きはほとんどできない子どもたち(当時長男は高校生、次男は小学校低学年)が、今から日本社会に溶け込むのは難しいだろうと思いました。特に次男は、私が言っていることは理解しますが、日本語を話そうとしません。義実家に2人を置いて、私だけが帰国をする? まさか、それは絶対にできない……。ビザのことを考えると離婚をする勇気も湧かず、悶々とする毎日が続いていました。
ルイーズの家で、彼女の末妹であるクロエに会ったのは、そんな時でした。
若いころやんちゃで、家出を繰り返していた妹はいっぱしの料理人になり、リヨンの有名レストランで働いている……とルイーズからよく聞かされていました。クロエは私たちの住む街から車で2時間の小さな村にあるレストランを買い取ったばかり。開業準備のために1ヶ月ほどルイーズの家に身を寄せて、村と行き来していたのです。
豊満ボディで気さくなキャラ、胆っ玉母ちゃんのようなクロエと私は、初対面ですぐに打ち解けました。10歳年下でしたが、頼りになる人だと思いました。キッチンで料理の試作を重ねていたクロエのタルト作りを手伝うと、「キミコは手際がいい」ととても褒めてくれました。
クロエは何度も私をルイーズの家に招いて、料理を振る舞ってくれました。あの頃、クロエも恋人と破局しており、お互いの別れ話でも盛り上がったものです。お酒に酔ったルイーズがソファで眠ってしまった後は、コーヒーを飲みながら朝方まで2人で話し込みました。私たちには、お酒が飲めないという共通点もありました。
「何年も暮らしていて恥ずかしいけれど、フランス語で、こんなに自分の気持ちを話せた相手はあなたが初めて」と私が言うと、クロエは「言葉は関係ない。心が通じた人が友達だよ。一人でよく頑張ってきたね」と肩をさすってくれました。
「あなたが必要なの」の言葉で、田舎への移住を決意
それから2年ほど、離婚の決意ができず、宙ぶらりんのまま、私はたまにケーキ屋のアルバイトをする生活を続けていました。やがて長男は大学に進学し、入寮して家を出ました。唯一のママ友だったルイーズも家族でカナダに引っ越してしまい、寂しさを感じていたある日、クロエからメッセージが届いたのです。田舎の村でスタートしたレストランは順調に客を増やしているが、どうしても人手が足りない。忙しい夏の間だけでもいいから、手伝いにきてくれないか、という内容でした。
「あなたとなら、きっとうまくやれると思う」
孤独だった私は、その言葉に縋るような気持ちになりました。私で役に立つのかと不安はありましたが、何度か飲食店で働いた経験があったことと、とにかく義実家から離れたいという思いで、すぐにOKの返事をして、次男がサマーキャンプで不在になる2週間、手伝いに行くことを決めたのです。
私はすぐに義実家の庭に停めっぱなしにしてあったキャンピングカーをメンテナンスに出しました。クロエの待つ田舎町へ向かうドライブは、大音量で音楽をかけ、大声で歌って、久しぶりにワクワクしました。何か新しいことがはじまるに違いない、そんな予感に溢れていたのです。
そこはフランス人が「お尻の穴のもっと奥の方」と表現するほどのド田舎で、別荘地と広大なキャンプ場がある村でした。夏はバカンス客で溢れ、毎週末お祭りが開かれます。クロエのレストランはもともと地元の人が経営していた小さなオーベルジュ(宿泊施設を備えたレストラン)でしたが、客室はクロエと住み込みの従業員が使っていました。シェフはクロエ、スーシェフはモロッコ人のオマル、前菜とデザートは同じくモロッコ人のサイードが担当。ホールスタッフは、村で雇った数人の女性たち。2週間の間、私はキャンピングカーに寝泊まりしながら、キッチンでサイードの手伝いを中心に働きました。
毎日、朝から晩までひっきりなしにお客さんがやってきます。朝はコーヒーと軽食、そしてランチとディナー、夜はクラブのようになって、朝方まで賑わうのです。数日の間は何がなんだかわからないまま、あたふたしていた私ですが、すぐにコツをつかんで、先回りをして動けるようになりました。サイードとキッチンでつまみ食いをして笑い合っていると、北陸のホテルでリゾートバイトをした学生時代を思い出しました。
あっという間に2週間が過ぎ、クロエから現金が入った封筒を渡されたとき、私は充実感でいっぱいでした。私は初めて、フランスの地で汗水流して働いて、お金を稼いだんだ、そう思うと、誇らしい気持ちになりました。
「あなたの働きは、私が想像していた以上に素晴らしいものだった。本当にありがとう。この村には小さいけれどエコール(小学校)もあるし、キミコさえよかったら息子と2人で引っ越してきたらどう? 仕事ならここにある。私もあなたたちの生活のために、できることは何でもするから、考えてみてくれない? 私には、あなたが必要なの」
別れ際、キャンピングカーの窓越しにクロエが言った言葉を噛み締めながら、私はハンドルを握りしめていました。そうだ、思い切って引っ越してしまおう。クロエのレストランで働きながら、次男と2人、田舎でのんびりと暮らそう。自宅に到着するころにはもう、心は決まっていました。
“ポールの妻”から、“レストランのキミコ”へ
次の春、私は義両親の反対を押し切って、次男を連れ、ふたたび田舎の村へと向かいました。
以前スーシェフをしていたオマルは店を辞めて村を去り、私と前菜を作っていたサイードがスーシェフになっていました。ホールスタッフの女性たちの顔ぶれも、何人か変わっていました。
到着した夜、クロエは私に打ち明け話をしました。オマルがレジのお金をごまかして、盗みを働いていたこと。これはサイードにとって同郷のプライドを損なうので、オマルは自分から退職を申し出たことにしてある。このことはサイードには黙っていてほしい……。
「キミコにしかこんな話はできない。日本人は真面目だから信用しているわ。もう大丈夫。私とサイードとキミコで、このレストランをしっかりといいものにしていきましょうね。頼りにしているわ!」
クロエはそう言って、私を抱きしめました。
とにかくこの新しい生活を安定させようと、朝から晩までがむしゃらに働きました。はじめはレストランの2階にある元客室で寝泊まりしていましたが、やがて、近くにあるアパートの一室を借りることができました。
フランスらしい恋愛事情からアクシデント、人間関係のゴタゴタなど、小さな村にも本当にいろんなことがあって、目まぐるしい毎日でした。毎日のまかないタイムには、スタッフとみんなでテーブルを囲み、あれこれ話をするのが私の楽しみでした。「同じ釜の飯」とはよく言ったもので、次男もクロエとサイードによく懐いて、まるで親戚のような関係になっていったのです。仕事の悩み、生活の困りごと、ポールとのこれから……私はすべてをクロエに相談していました。クロエもまた、懐深く私たち家族のためにいろいろと動いてくれました。私が体調を崩すと毎日病院へ送迎してくれ、入院した時には、次男の面倒を見てくれたこともあります。私にとって、クロエは年下ではありますが、フランスにおける姉のような存在でした。
フランスでは、長い間“ポールの妻”でしかなかった私にとって、レストランでの仕事は、自分自身を取り戻したような気持ちにさせてくれる体験でした。ピークタイムのキッチンはまるで戦争。早口なスラングが飛び交い、そこで私のフランス語もどんどん鍛えられていきました。若いスタッフたちからも頼りにされて、気づけば、エコールのママ友たちとも冗談を言い合えるようになっていたのです。ポールや義父母に頼らずとも、自分の力で、私は立っている。そんな機会をもたらしてくれたクロエの期待に応えなければ。当時の私は、そんな気持ちから、クロエに強い忠誠心を抱いていたと思います。
村に移住して5年ほど経ったころ、クロエはかねてから不倫関係にあった隣村の既婚男性との間に子どもを身ごもり、紆余曲折を経て結婚。私はその男性の連れ子たち、さらには産後のクロエと赤ちゃんの世話も引き受け、まるで母親のように、あらゆる役割をこなすことになりました。
いつも冬の閑散期には長い休みが取れたのですが、そんな調子で多忙になってからは、なかなか帰国も難しくなってしまいました。週に一度の休みすらほとんど取ることができなかったのです。
「キミコだけが頼りなの」
クロエはいつも言いました。
「ちょっと、ママンはクロエのために働き過ぎだと思う」
大学が休みの間に村へやってきた長男が私にそう指摘したこともあります。次男は「クロエの子どもたちの方が大事なんだよ」と言いました。そんなつもりはない、あなたたちが一番大切だと伝えても、2人は首をすくめるばかり。しかし私は呑気に、まだまだ子どもだな、母親を取られたみたいな気持ちになって嫉妬しているのかな、くらいに考えていました。
私は今、本当に幸せなのだろうか?
やがて私は、クロエが新しく開いたバーで、朝のカフェを任されることになりました。そこには村の変わり者、アダムが毎日通ってきました。コーヒーを注文するのは週に2、3回。ただでカウンター席に座りこみ、話しかけてくるのです。アダムは私と同じ年で、ゴミ屋敷に暮らす、不潔な男でした。日本と中国、韓国の違いがわからないようで、何度訂正しても、「北京は今頃寒いのか」などと的はずれなことを言ってきます。私はそんなアダムが苦手で、時々フランス語がわからないふりをしていなしていたのですが、アダムは独り言のように声をかけ続けてきました。
「キミコ、お前はいいやつだから、本当はこんなところにいたらダメだ。オマルみたいに騙されたらいけない」
ある日アダムがそうつぶやいたので、私は驚いて彼の目を見ました。
オマルみたいに騙されたらいけない……どういう意味だろう? 引っかかったものの、村一番の偏屈が放った言葉です。どうせただの嫌味だろうと、それ以上追求もしませんでした。
妹から、「母の具合が悪いから帰国してほしい」と連絡があったのは、夏の終わりのことでした。クロエに相談してみましたが、パーティーの予約がたくさん入っているから、それらが終わってからにしてほしいと言われ、その時は諦めて働きました。繁忙期が過ぎてからも、クロエの個人的な予定によってなかなか航空券の予約をするタイミングがつかめず、ようやく帰国できたのは、師走に入ってから。母の死に目には、間に合いませんでした。
「なんでもっと早く来てくれなかったの。お母さん、お姉ちゃんに会いたがってた」
妹はそう言いながら泣き、一回り小さくなった父はしばらく黙っていました。妹は都市部に嫁いでいるため、これから父は広すぎる田舎の古い家で一人暮らしをすることになります。
「お前が、幸せだと思う暮らしをしたらいい。俺も、お母さんも、そう思っている」
ポツリと父が言った言葉が、胸に刺さりました。
私は、今、本当に幸せなのだろうか?
無我夢中で働いてきたここ数年間を振り返り、私は初めて自分にそんな問いを持ったのです。母親の死に目にも会えないほど、いまの仕事は、私にとって重要なのだろうか。心に生まれたモヤモヤを抱えて、フランスへ戻りました。
「お母さんが死んだってね。悲しいな。元気出せよ」
朝、いつものようにバーにやってきたアダムが言いました。私はだいぶアダムとのやりとりに慣れ、思ったほど悪い人ではないと思うようになっていました。アダムは読書家で、一定のジャンルに関してはとても物知りでした。私は大学で美術史を学んでいたので、よくアートの話で盛り上がりました。その日も世間話をしていると、アダムがふと言いました。
「キミコ、だいぶフランス語が上手になったな。この辺の方言まで喋れるじゃないか。お前は意外と賢いから、読み書きをしっかり勉強したら、大学くらい行けたかもしれないな」
「私、ちゃんと日本の大学を出ているよ」
「おいおい、嘘だろう、リサンス(学士)なのか。だったら、なんでこんなところで働いているんだ」
私がこれまでの経緯を話すと、アダムは腕組みをして空を見上げ、言いました。
「お前、正直に言ってみろ。今、1ヶ月にいくらもらっている?」
少し悩みましたが、正直に答えると、「やっぱり」とアダムは唸りました。
「まあ、子どもたちにもお金がかからないし(フランスの公立学校はほぼ無償です)、家とこことの往復だけで、ほとんどお金を使うこともないから、特に不満もないけどね」
「フン、ずいぶん幸せな脳みそだな。お前、搾取されているぞ。お前がもらっているその金額は、マリー(村在住のフランス人女性で、当時ホールスタッフでした)の半額くらいだろうな。オマルも、最初にここにいたマダガスカル人の女も、みんな酷い搾取をされて、クロエに文句を言ったとたんにクビになった。村の奴らはみんな知ってる。まあ、マダガスカル女は働きが悪かったから妥当だとは思うけど……それにしたってお前、リサンスなのに、あのろくに教育も受けていないチンピラ女の下で、そんなはした金で朝から晩まで働かされているのか。おお、神よ」
コーヒーカップを洗う私の手は震えていました。
「チンピラ女なんて、酷い言い方しないで。クロエは私の恩人だよ」
「お前の脳みそはどうなっているんだ。みんなに給料の金額を聞いてまわって、よく考えろ」
クロエに対して疑念が生まれたのは、この時でした。しばらく悩んだ末、私はマリーに、本当に私の倍額の給料をもらっているかを聞き出すことにしました。もちろん、いくらなの? とは聞けません。マリーと一緒にネットショッピングのサイトを見ながら、めぼしい金額の家具を指差し、「次の給料をピッタリ全部突っ込んで、これを買おうかな」とつぶやくと、マリーは笑いながら言いました。
「ほんと、それを買ったらちょうど一ヶ月すっからかんだね」
その金額は、確かに私の給料のほぼ倍額だったのです。私は愕然としました。
「キミコは私を困らせたいの?」
私は、本当に、クロエに搾取されている?
黒いモヤモヤが胸の中で広がっていきましたが、次男の進学のタイミングもあり、身動きがとれませんでした。それに、クロエにはやっぱり恩を感じます。顔を突き合わせて話していると、善人にしか見えません。心に蓋をして、私はそのまま働き続けました。
それから1年が経ち、パンデミックで村のレストランも休業を余儀なくされました。クロエは隣村で夫の仕事を手伝うことになり、ほとんど会うことはなくなりました。国から飲食業界に給付された補助金で、私たち従業員にも少し保証金が支払われました。
何もない村でのステイホームは、精神的に苦しいものがありました。とはいえ、仕事やクロエたち家族の雑用に追われる日々から解放され、冷静に考えてみると、もう一度あの生活に戻れるかどうか、自信がなくなってきます。村に来て約10年、私は50代になっていました。最初のような体力もなければ、クロエに対する気持ちも変化していました。
そんなとき、日本の友人から、英語とフランス語を使う仕事を手伝ってくれないか、という連絡がありました。やりとりを重ね、リモートワークの可能性を知った私は、レストランの退職を考えるように。そして、次男が進学するときが来たら、大学がある街へ一緒に引っ越そうと決めました。
しかし雇用が確約されるまでは、生活を維持するために失業保険を受け取る必要がありました。
フランスの役所事情は、自国民でさえうんざりするほど複雑で厳しいことで知られています。外国人の失業保険手続きは、さらに煩雑です。パンデミックがはじまったころ、不安になった私は、一度クロエに確認したことがありました。するとクロエは「保険は私が手続きするから安心して。責任はちゃんと取るから」と言ったのです。
そこでクロエに「レストランはこのまま退職するので、以前話したように、失業保険が受け取れるように手続きをお願いしたい」とメッセージを送ると、クロエからは「レストランはもうオープンできないかもしれないから、キミコにいい仕事が見つかってよかった。新しい仕事を応援しています。近々、また連絡するね」と、失業保険については一言も触れない返事があったきり、そのまま時間が経ちました。
世の中が落ち着いてくると、クロエはまずバーだけを再オープンさせ、カウンターに1人で立つようになりました。私はそのバーへ客として毎朝通い、ふつうに会話をしていました。先々の見通しが立っていたこともあり、クロエに対する疑念は、あえて忘れようとしていたのです。
ある朝、バーでコーヒーを飲んでいると、クロエが言いました。
「そろそろ、レストランを本格的にオープンさせる。また、忙しくなるわよ。キミコ、当てにしているからね。また一緒に頑張ろうね!」
え、ちょっと待って? 私は驚いて言いました。
「あの、私はもう退職したはずなんだけど。以前、失業保険の手続きをお願いしたよね? そういえばあれ、どうなっている?」
クロエも驚いた顔をして、
「そうだった? えー、それは困っちゃう。だって誰もレストランを手伝ってくれる人がいないんだから。サイードもまだ国から戻ってこないし。私はどうしたらいいの? ねえ、キミコは、私のことを困らせたいの?」
さらにこう続けたのです。
「あと1年だけでも、働いてもらえない? これまでの恩を返すと思って、やってもらえないかな?」
笑顔で言い放つクロエに、私は心底仰天していました。
「ううん、もう、それはできないわ。私がお願いしたのは、ずいぶん前だよ? 私は引っ越すことに決めているし、その前に日本に帰って、父親に会いたいと思っているから。もう母親のときのような思いをしたくないの」
私に復帰の意思がないとわかると、クロエは突然、能面のように無表情になりました。
「そう。キミコってすごく薄情なのね。私は困っていたあなたたち家族を、これまで何年も、ずっと助けてきたと思うんだけど」
安月給でね、と言い返すことは、その時の私にはできませんでした。
「今までのことは、本当にありがとう。感謝しているわ。レストランの再オープンを手伝えなくてごめんなさい。でも、決めたことだから。とにかく、保険の手続きだけは、お願いします」
クロエは私の言葉に答えませんでした。そこへ、新しい客が入ってきて、その後私は完全に黙殺されたのです。私はお金だけ置いて、嫌な気持ちでバーを後にしました。
私はあなたからお金を借りたことはない!
それからはバーへも行きづらくなり、私は何度かクロエに保険についてメッセージを送りました。クロエから返事はなく、たまに、村に1つだけある小さなスーパーで会っても、クロエは目すら合わせてくれません。
ある夜、アダムが私を訪ねてきて、村で私についての悪い噂が広まっていると言いました。
「あのチンピラ女は、キミコに貸した金が戻ってこないとか言ってるぞ」
……やっぱり。はじめにクロエがオマルについて語ったことが、私の身にも起こったのだ、と思いました。オマルは盗みなど働いていなかった。待遇改善を申し出たことでクビになり、クロエによって情報操作をされていたのです。
翌朝、私は意を決し、バーへ行きました。常連客たちが私の顔を見て、「アダムの女が来た」と囃し立てました。クロエはニヤニヤしています。
私はクロエの耳元で、「訴えられたくなければ外へ出て」と言いました。クロエはハッとした表情になり、エプロンを外しました。
「何度かメッセージをしたと思うんだけど。なぜ答えてくれないの?」
バーの裏にあるガレージで、震えながら詰め寄ると、クロエは吸っていたタバコを地面に投げ、踏み潰しながら言いました。その様はまさに「チンピラ女」そのものでした。
「だから、失業保険の手続きは、税理士に依頼しなきゃいけないから、それ自体に金がかかるわけ。そんな金、今、私にはないから」
クロエは悪びれることもなく、さらにこう言いました。
「だって、そんな話、最初からしてないでしょう? あなた必要って言わなかった。それに私はあなたに働いてほしいんだから、完全にあなたの都合でしょう」
そうくるだろうと思って、私は用意しておいた書類をクロエに渡しました。それは、これまでの勤務状態と給与の相関、法的な問題、クロエが取るべき手続きの順序まで、長男のアドバイスに従ってテキストにまとめたものでした。
「……この通りにやってくれなければ、私はあなたを訴えることになる」
退職後、私が失業保険を受け取るための手続きには、税理士の費用として1000ユーロほどがかかる予定でした。
「仕方がない、わかった。その代わり、その費用はいったん、キミコが負担してほしい。その金は今私にはないから」
私はクロエに言われるままに、空の小切手を渡しました。
「引き落としの金額と時期は伝えるから」
クロエはそう答えるとバーへ戻ろうとしました。私はその背中に向かって、大きな声で言いました。
「私は、あなたからお金を借りたことはない。村の人たちに訂正して。たった今、私からお金を借りたのはあなただから!」
クロエは振り向きませんでした。
クロエが私に気づかせてくれたもの
クロエから連絡もないまま、ある日突然、私の口座から1200ユーロが引き落とされました。「責任は取る」「いったん負担を」などと彼女は言いましたが、そのお金が返ってくることはないと私は知っていました。しかし、雇い主ではなく、外国人である私が個人で手続きを行うことで保険が受け取れなくなるよりは、ずいぶんましだと思いました。息子たちやアダムは弁護士を入れて正しくクロエを追及しろと言いましたが、私はもう関わりたくなかった。手切れ金だと思って、くれてやることにしたのです。 その後、無事に数ヶ月の間、失業保険金を国から受け取ることができました。しばらくして、私たちは次男の大学がある街へ引っ越しました。
一年後、私は一人でノルマンディに戻りました。義母が体調を崩したためです。ポールとは離婚が成立しましたが、めったに帰ってこない息子よりも、孫たちと元嫁である私の方に、義父母は心を寄せるようになっていました。私は義実家のそばにアパートを借り、2人のケアをしながら、リモートワークを続けています。
クロエとの出来事を通して、私はさまざまな気づきを得ました。
レイシストとまではいいませんが、クロエには外国人労働者への差別意識があったと思います。それを友情の仮面で隠して巧妙にコントロールし、私たちから搾取した。今もおそらくレストランでは、安く使える移民を雇い続けているはずです。それは欧米ではよくあることであり、日本にも、たくさんの外国人労働者がいます。コンビニなどで外国訛りの日本語で懸命に働く彼らに接しながら、「頑張っているな、大変だな」と思うことがあります。しかしそこに、自分の姿を重ねたことはありませんでした。
長い間、私がそれに気づかなかったのは、私が「日本人」だからなのでした。私には、アジア人である前に「先進国」の人間だという自負がありました。特に私が中高生だったころ、まだまだ日本は上り調子。豊かな国で、きちんと教育を受け、何不自由なく育ったという意識から、私は、村での自らの境遇を客観的に知ることができなかったのだと、今になって思うのです。
クロエにとって、私は「かわいそうなアジア人」だった。いや、クロエだけではありません。ポールの両親にも、おそらくそういう意識はあります。
舐められている。お人よしすぎる。もっと怒れと、たびたび息子たちは言います。日仏ハーフとして生まれた彼らにも、私とはまた違う感情があるのでしょう。
でも、村を去って何年か経った今、私にはクロエを恨む気持ちはありません。クロエは友情を使って私を利用しましたが、私も、クロエを利用したと言えます。あのとき、あの村へ行かなければ、孤独を埋めることができなかった。今ほどのフランス語を身につけることはできなかった。日本人としての自分を、こんなふうに客観視する機会を得ることは、きっとなかったのです。
(※本連載は、プライバシー保護の観点から、インタビューに登場した人物の氏名や属性、環境の一部を変更・再構成しています)
-

-
山野井春絵
1973年生まれ、愛知県出身。ライター、インタビュアー。同志社女子大学卒業、金城学院大学大学院修士課程修了。広告代理店、編集プロダクション、広報職を経てフリーに。WEBメディアや雑誌でタレント・文化人から政治家・ビジネスパーソンまで、多数の人物インタビュー記事を執筆。湘南と信州で二拠点生活。ペットはインコと柴犬。(撮影:殿村誠士)
この記事をシェアする
「山野井春絵「友達になって後悔してる」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら