2020年5月11日
映画の「現在」という名の最先端 ――蓮實重彦ロングインタビュー
第4回 ショットが撮れる、要注目の監督
聞き手:ホ・ムニョン 翻訳:イ・ファンミ
著者: 蓮實重彦
(第3回はこちら)
――先生は、巨匠らのほかにも同時代のアメリカ監督たちにも特別な関心と愛情を示してきました。ジェームズ・グレイやウェス・アンダーソン、マイケル・マンはもちろんのこと、多くのシネフィルたちがあまり関心を持たないトニー・スコット、ジェームズ・マンゴールドの映画もよくベスト・リストに挙げてきました。彼ら世代より若いアメリカの監督の中で、特に注目している監督はいませんか? ケリー・ライヒャルトKelly Reichardtの映画を高く評価していることは存じており、また1980年生まれのデヴィッド・ロウリーDavid Lowery監督の映画『さらば愛しきアウトロー』(The Old Man and the Gun、2018)、『ア・ゴースト・ストーリー』(A Ghost Story、2017)、『セインツ -約束の果て-』(Ain't Them Bodies Saints、2013)をすべて、その年のベスト・リストに選ばれていたのも非常に印象的でした。彼らに大きな期待を抱いているのであれば、それはどういった理由からでしょうか。
蓮實 この質問については、部分的にはすでにお答えした問題が含まれていますが、ほとんどの作品の上映時間がほぼ90分というデヴィッド・ロウリーの強みは、あらゆるショットが簡潔きわまりないという点につきています。もちろん、ある被写体をどのようなショットに収めるかという問題に、正しい回答などありはしません。にもかかわらず、優れた監督たちは、被写体に向けるキャメラの位置やそれに投げかける照明、そしてその持続する時間など、どれもこれもがこれしかないという決定的なものだというかのように作品を仕上げてみせます。だから、正解はないにもかかわらず、見ている作品のショットはすべて完璧に思えるのです。こうした作品を撮る映画作家たちを、わたくしは、「ショットが撮れる監督」と呼んでいます。そして、ケリー・ライヒャルトKelly Reichardtもまた、「ショットが撮れる」監督なのです。ウェス・アンダーソンWes Andersonは、そのストップ・モーション・アニメでありながらも、あえて完璧なショットを模して物語を語っています。この完璧なショットという概念がスコセッシには欠けているように思えてなりません。
現在、わたくしは、『ショットとは何か』という書物を準備しています。それは、インタビュー形式で語られる自伝的、歴史的かつ理論的な考察であり、全部で五章からなるその第一章は、「『殺し屋ネルソン』に導かれて」として『群像』2020年5月号に掲載されています。そこで述べられていることは、「ショット」とはあくまで実践的な問題であり、決して理論的に語られるものではないということなのです。被写体に向けるべきキャメラの位置に正解はないにもかかわらず、優れた監督は正解があるかのように撮ってみせるという点を、実例を挙げながら考察しているのです。
――1970年代生まれ以降の欧州の映像作家の中では、ペドロ・コスタ、ホセ・ルイス・ゲリン、レオス・カラックスのほかによく言及している監督はあまりないように思えます。ペドロ・コスタと同じ世代、もしくはその下の世代の監督の中で注目している欧州の監督はいますか。フランスの監督アラン・ギロディについてはどのようにお考えですか(私と親しい仲間たちはどちらかというとギロディが大好きです)。
蓮實 ギロディについては、すでにお答えしてあります。これもまたすでに触れておきましたが、フランスの新人監督としては、ギヨーム・ブラックGuillaume Brac監督を高く評価しております。彼もまた、ペドロ・コスタPedro Costaとは異なる意味で、「ショットの撮れる監督」なのです(昨年、彼の東京滞在中に撮った写真を最後に添付しておきます)。ちなみに、『熱波』(Tabu, 2012)や『アラビアン・ナイト』(As 1001 Noites, 2015)などのミゲル・ゴメスMiguel Gomesは、どうもあまり好きになれません。彼も「ショットの撮れる監督」ではあるのですが、そのショットが、なぜか古典的な映画の意図せざるパロディーのように思えてならないからです。
――南米やアフリカの映画に関してはどうお考えですか。最近、アルゼンチンの映画がリサンドロ・アロンソLisandro Alonso、マリアーノ・リナスMariano Llinásなどによって注目を浴びていますが……。
蓮實 不幸にして、その二人の作品はまだ見ておりません。
――同時代の日本映画に対する韓国のシネフィルの関心が一時期は疎遠になりつつありましたが、濱口竜介、五十嵐耕平のような若手監督たちによりその関心が蘇りました。濱口竜介のほかに、先生が韓国の映画ファンにぜひ紹介したいと思う日本の若手監督がいるとしたら誰ですか。
蓮實 現在、わたくしが濱口竜介監督とともにもっとも高く評価しているのは、『きみの鳥はうたえる』(And Your Bird Can Sing, 2018)の三宅唱監督です。また、『嵐電』(Randen, 2019)の鈴木卓爾監督も、きわめて個性的かつ優秀な監督だと思っています。さらには、『月夜釜合戦』(The Kamagasaki Cauldron War, 2017)の佐藤零郎監督など、16ミリのフィルムで撮ることにこだわるという点において興味深い若手監督もでてきています。また、近く公開される『カゾクデッサン』(Fragments, 2020)の今井文寛監督も、これからの活動が期待できる新人監督の一人です。
ドキュメンタリーに目を移せば、この分野での若い女性陣の活躍はめざましいものがあります。『空に聞く』(Listening to the Air, 2018)の小森はるか監督、『セノーテ』(Cenote, 2019)の小田香監督など、寡作ながらも素晴らしい仕事をしており、大いに期待できます。また、近年はあまり長編を撮れずにいましたが、つい最近、中編『だれかが歌ってる』(Someone to sing over me, 2019)を撮った井口奈己監督も、驚くべき才能の持ち主です。
――視野をアジアの方に広げてみましょう。アピチャートポン・ウィーラセータクンとワン・ビン以降、未だそれほど熱い注目を浴びている監督はいないようですが……。
蓮實 胡波Hu Bo監督の『象は静かに座っている』(An Elephant Sitting Still, 2018)にはひとなみに興味をそそられましたが、しばしば比較されるエドワード・ヤンEdward Yangに較べると、さほど才能ある作家だとは思えませんでした。なぜか、発想が文学的なものと思えてならなかったからです。もちろん、あいかわらずジャ・ジャンクーJia Zhangkeにもそれなりの興味を持っていますが、これまでの作品を超えるものを最近の彼が撮っているかといえば、どうもそうとはいえません。また、見るたびにもっと面白くなるはずだと呟いてしまうホン・サンスHong Sang-soo監督にも何とか興味を持とうと必死に努力しているのですが、これだけはどうもうまく行きません。それは、若くしてアメリカに渡った彼の作品のショットやデクパージュに、古典的なハリウッド映画への郷愁といったものがまったく感じられないからではないかと、むりやり自分自身を納得させているところです。それは、たとえば濱口竜介監督の演出には、間接的ながら古典的なハリウッド映画のショットやデクパージュへの郷愁のようなものが感じとれるのですが、才能を欠いているわけではない五十嵐耕平監督には、それがほとんど感じとれないということと無関係ではなかろうと思っています。わたくし個人としては、彼の『息を殺して』(Hold Your Breath Like a Lover, 2014)に、充分納得してはおりません。
ここで、いささか唐突ながら、ジャン=リュック・ゴダールを召喚したく思います。世界の批評家たちは、二十歳になったばかりのゴダールが、「古典的なデクパージュの擁護と顕揚」(《Défense et Illustration du découpage classique》, Cahiers du Cinéma, septembre 1952)というきわめて重要なテクストをハンス・リュカスHans Lucas名義で『カイエ・デュ・シネマ』誌に発表していたことの意味を、改めて問いなおしてみなければならないと思っているからです。ここでの若き批評家ゴダールは、編集長だったアンドレ・バザンAndré Bazinによって否定されがちだったデクパージュの概念をむしろ肯定的にとらえ、最終的にはハワード・ホークスHoward Hawksの擁護を目ざしていたのですから、ゴダールが「古典的デクパージュ」を過去の産物と捉えていたのでないことは明らかです。
実際、ハリウッドの「古典的デクパージュ」というものは、決して歴史的な「過去」に属するものではなく、不断の「現在」として、今日の映画をなおも刺激し続ける永遠の現象にほかなりません。映画における新しさとは、決まって生々しい「現在」としてある古典的なハリウッド映画との関係で語られるものだからです。そうした視点から、『FILO』にもしばしば登場しているエイドリアン・マーチンAdrian Martin氏の重要な著作『ミザンセーヌとフィルムスタイル』(Mise en Scène and Film Style, Palgrave, 2014)と向かいあわねばなりません。その書物が、「古典的ハリウッドからニュー・メデイア・アートへ」《From Classical Hollywood to New Media Art》と副題されていることの意味がきわめて重要だと思えるからです。エイドリアン・マーチンにおいても、「新しさ」が「古典的ハリウッド」との関係で語られていることに注目したいと思っているのです。あるいは、「古典的ハリウッド」とは、いまだ充分に「古くなってはいない」何か、すなわち、いつでも「現在」と接しあっている貴重なものだといえるのかもしれません。
わたくしがジョン・フォードを論じるときも、それとまったく同じ姿勢をとっています。小津安二郎を論じたときもそうでしたが、フォードや小津は、間違っても「過去」の偉大な映画作家ではありません。小津やフォードにかぎらず、ラオール・ウォルシュRaoul WalshでもホークスHoward HawksでもウェルマンWilliam A. Wellmanでもかまいませんし、清水宏でも成瀬巳喜男でも山中貞雄でもかまいませんが、そうした「古典的」と呼ばれる作家たちの作品がいまでもわたくしたちを刺激しつづけているのは、彼らがまぎれもない「現在」の映画作家にほかならないからです。それは、彼らの作品をかたちづくっているショットが、見ているわたくしたちを、決まって映画の「現在」という名の最先端と向かいあわせてくれるからなのです。
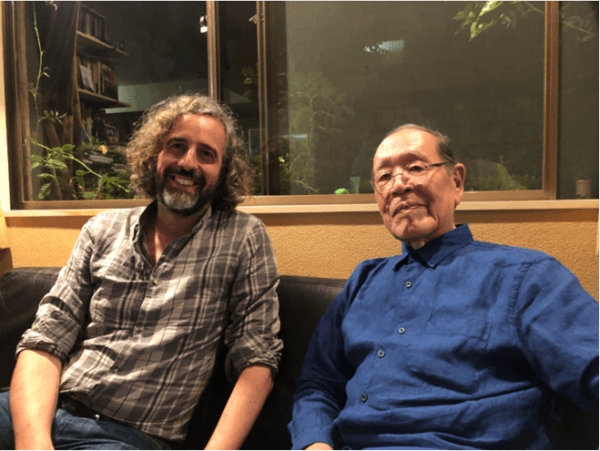
(第5回へつづく)
-

-
蓮實重彦
はすみ・しげひこ 1936(昭和11)年東京生れ。東京大学文学部仏文学科卒業。1985年、映画雑誌「リュミエール」の創刊編集長、1997(平成9)年から2001年まで第26代東京大学総長を務める。文芸批評、映画批評から小説まで執筆活動は多岐にわたる。1977年『反=日本語論』で読売文学賞、1989年『凡庸な芸術家の肖像 マクシム・デュ・カン論』で芸術選奨文部大臣賞、1983年『監督 小津安二郎』(仏訳)で映画書翻訳最高賞、2016年『伯爵夫人』で三島由紀夫賞をそれぞれ受賞。他の著書に『批評あるいは仮死の祭典』『夏目漱石論』『大江健三郎論』『表層批評宣言』『物語批判序説』『陥没地帯』『オペラ・オペラシオネル』『「赤」の誘惑―フィクション論序説―』『「ボヴァリー夫人」論』など多数。1999年、芸術文化コマンドゥール勲章受章。
この記事をシェアする
「映画の「現在」という名の最先端 ――蓮實重彦ロングインタビュー」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 蓮實重彦
-
はすみ・しげひこ 1936(昭和11)年東京生れ。東京大学文学部仏文学科卒業。1985年、映画雑誌「リュミエール」の創刊編集長、1997(平成9)年から2001年まで第26代東京大学総長を務める。文芸批評、映画批評から小説まで執筆活動は多岐にわたる。1977年『反=日本語論』で読売文学賞、1989年『凡庸な芸術家の肖像 マクシム・デュ・カン論』で芸術選奨文部大臣賞、1983年『監督 小津安二郎』(仏訳)で映画書翻訳最高賞、2016年『伯爵夫人』で三島由紀夫賞をそれぞれ受賞。他の著書に『批評あるいは仮死の祭典』『夏目漱石論』『大江健三郎論』『表層批評宣言』『物語批判序説』『陥没地帯』『オペラ・オペラシオネル』『「赤」の誘惑―フィクション論序説―』『「ボヴァリー夫人」論』など多数。1999年、芸術文化コマンドゥール勲章受章。
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら





