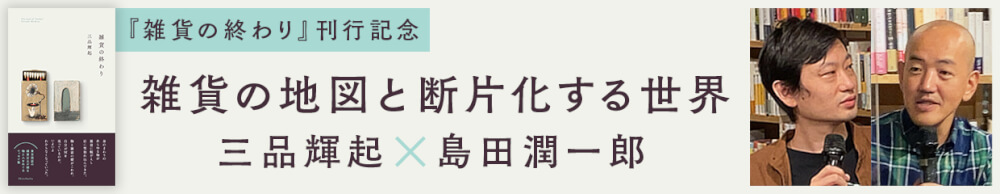2020年11月5日
前篇 すべてが「雑貨化」するというパースペクティブ
東京・西荻窪で雑貨店「FALL」を営む三品輝起さんが、「考える人」に連載したエッセイに書下ろしを加えた『雑貨の終わり』が2020年8月に出版されました。刊行を記念して、9月16日には下北沢の本屋B&Bで、三品さんのデビュー作『すべての雑貨』の編集・出版を手がけられた夏葉社の島田潤一郎さんとのオンライン配信のトークイベントを開催。三品さんが半径10メートルの店内から観察した「雑貨化」と、パラレルに進行する断片化する世界。もはや資本に覆われた世界の外部に私たちは立つことができないのか?! 白熱した対話の模様を前後篇に分けてお届けします(司会・構成:小林英治)。
――さっそくですが、まずは島田さんに、『雑貨の終わり』を読んだ率直な感想をお聞きしてみたいです。
島田 一言でいうと「すごく良かった」ということに尽きるんですけど、文章がずいぶん変わった感じがしました。より精緻な文章になって、より私的な文章になっている気がして、僕はそこがとても良かったです。
三品 ありがとうございます。
島田 実は、最初に三品さんから「考える人」で連載を始めるとうかがったとき、見方によっては、前作の『すべての雑貨』に雑貨に関する考察みたいなことは全部書いてあるような気がしていたから、何を書くんだろう?と思ったんです。
三品 まさしく、1冊目に全部書いちゃったんですよね(笑)。
島田 そういう気持ちでいたので、本を開いて、冒頭の「息を止めて」という、三品さんのおじいさんのことを書かれている文章を読んで、ああ、こういうふうに世界を掘り下げていくのかと、鳥肌が立つような感覚がありました。大げさかもしれないですけど、小説家というのは、ひょっとしたらこういうふうにして最初の小説を書き始めるんじゃないかなと思ったんです。
三品 えっ、小説ですか? でもまあ、いきなり戦場で血が噴き出す描写から始まりますからね。
島田 ディテールを書く喜びみたいなものが、はっきりとここにはあって、それを作り話として書いているというよりは、書きたくて細かいところまで書いている気がして、それが非常に小説家らしいというか。三品さんが『すべての雑貨』から『雑貨の終わり』を出すまでの3年間に考えてきたことがこの本になっているはずなので、そのことはすごく感動的でした。『すべての雑貨』を出したときにいろんな感想を耳にしましたけど、その中でも人気があったのが、最後のレゴにまつわる私的な物語だったんです。
三品 数少ない希望の部分ですね。ひとつ書き上げるたびに原稿を送っていたんですけど、島田さんに「希望を入れてください」と毎回言われたんですよね。「希望がない、希望がない」って(笑)。でも結局、希望を最後までひねり出せずに、「レゴの話を最後に置いたら希望になるんじゃないですか?」ってごまかしたんです。
島田 僕はそのときは、見立てとしての希望を要望していたんですよ。でもそうではなくて、三品さんから私的なものが出てきた。『すべての雑貨』は雑貨に関する見立てがほとんどを占めていたけど、最後はその私的な文章で締めることになりました。当時僕は、編集者としてそれをはっきりと希望と捉えていいのか分からなかったけれども、その感じが今回の『雑貨の終わり』でさらに膨らんで、強まって、こう言ってよければ、雑貨化する社会にあらがうということを書かれたんだなと思いました。
――いきなり本書の核心に迫っていただきましたが、そもそも島田さんが三品さんに原稿を依頼されたのは、どういった経緯だったのでしょうか?
島田 きっかけは、ここに現物がありますけど、今日司会をされている小林さんが編集に関わる『なnD』に、「雑貨の歌を聴け」という文章を三品さんが書かれていて、それが非常に良かったからです。2015年のことですね。
三品 恥ずかしいタイトルですね(笑)。
島田 ここに「すべてのものが雑貨化する」ということが簡潔に書かれていて、非常に感銘を受けました。どうしてかというと、僕はひとりで夏葉社という出版社をやっているので、営業にも自分で行くわけです。すると、どんどん書店の店頭の風景が変わっていくのに気づいたんです。それは三品さんが指摘されている通りに、インターネットが全盛になっていくに従って、だんだん本が物のように扱われるようになったことと関係しています。本が物になると、書店はもうあらゆる物が入りこむ場所になっていくわけです。
三品 雑貨化していくわけですね。
島田 そうです。僕が覚えている忘れられないエピソードがあります。そこは本以外に雑貨も扱っているおしゃれな本屋さんで、営業に行ったとき店員さんから、「お客さんが、夏葉社さんの本とハンカチのどっちを買おうか迷って、ハンカチを買っていきました」と聞いたんです。何でそんなこと僕に言うかなって思ったんですけど(笑)、それはつまり、そのお客さんからするとハンカチと本の価値がフラットになっているということですよね。そのことは、インターネットのない世界で本と接してきた経験をもつ僕からすると、驚きなわけです。
――島田さんにとって、本屋は本を買うところだと。
島田 本は本のカテゴライズであって、僕の中ではハンカチとはまったく違うものでした。けれどもどうやら世の中はそうではないようだと。何かが変わってきてるんだろうなという感じがあって、それがいいことなのか悪いことなのかは分からないわけですよ。もちろんいいこともあります。例えば僕が作っているような古い文芸書の復刊本というのは、昔であったら文学好きの人、古書マニアの人にしか買ってもらえなかったと思うんですが、物事の価値がフラットになっていくと、装幀が美しいとか、タイトルが良いというだけで買ってくれるようなお客さんが出てくる。それは新しい未来であって、僕は実際そういうふうなところで商売をしてるという気持ちもあるけれど、一方で、これは何か悪い方に転がっていく可能性もあると思うわけです。同じ金額を払うもので、生活を豊かにしてくれるものであれば、それは別に本でなくてもいいし、ハンカチであっても、食器であっても、パンであってもいい。そういった世界の出現をどう考えていいか分からないと思っていたときに、三品さんの文章に出合って、「すべてが雑貨化する」という考え方、モノの見方に非常に惹かれたんです。それで原稿を依頼しました。
「雑貨の終わり」の果てで紡ぎだした希望
島田 『すべての雑貨』を出した2017年から『雑貨の終わり』を出された2020年まで3年ありますよね。逆に三品さんにうかがいたいのは、その中で感じた時代の変化についてです。
三品 この3年間で、雑貨化は着実に進んだと思います。結局、自分も雑貨化しているし、売り手としてそれを推進してる側だから、正確に記述できないところがあるんですけど、『すべての雑貨』を書いたときは、「雑貨化という概念を思いついた!」と喜んで(笑)、俯瞰した位置からこれは雑貨化してるとか、雑貨化してないとか言ってたんです。より正確には、俯瞰しながら書いた話と、そこから地面に落ちて「自分の店が大変だ」という話と、そのふたつの上下運動で進んでいくような本だったと思うんですけど、3年経ってみたら、雑貨化と言って驚く時代はとっくに終わって、もう自分が雑貨化の外部に立てる気がしなくなっていたんですね。すっかり雑貨化に呑み込まれた渦中にいるから、ミイラ取りがミイラになるみたいな感じで、俯瞰した客観的な記述ができないわけです。だから今回は、地べたを這いつくばるというか、いろんなものの周りを長い時間かけてぐるぐる回っている感覚で書きました。
――今回も原稿を書くきっかけは編集者さんからの依頼だと思いますが、連載時はどういうオーダーだったのでしょうか?
三品 担当の編集者の方は、吉祥寺のパルコブックセンター(当時/2018年7月に閉店)で、何かデザイン的に面白い本がないかと探していたときに、たまたま『すべての雑貨』を見つけたらしいんです。だから、そもそも雑貨的な出会いなんですよ(笑)。でもせっかくだからと思ったのか読んでみたら、中身も面白いと思っていただいたみたいで、感想のお手紙をいただきました。そして「何でもエッセイを自由に書きませんか?」って。よく覚えてないですけど、内容については特にオーダーがなかった気がします。
島田 ちなみに最初に書いたのはどの話ですか?
三品 覚えてないですけど……、(担当編集者から聞いて)「息を止めて」だったみたいです。
島田 「息を止めて」が最初ですか? それはすごい。やっぱりそこが出発点なんですね。意識的におじいさんのことを選んだというか、書きたかったことだったんでしょうか?
三品 基本的に雑貨化がどうのこうのという話は1冊目であらかた書いてしまったので、そうじゃないものを考えたんだと思います。あと、やっぱり島田さんに「希望がない」と言われたのが3年間ずっと頭に残ってたんでしょうね。結果、『雑貨の終わり』の中に希望があるのか自分では判断つかないですけど、堀江敏幸さんにはそこから希望を汲み取っていただきました。
――新潮社のPR誌『波』の9月号に掲載されている、作家の堀江敏幸さんによる書評のことですね。
三品 はい。本人は、また希望のないやつ書いちゃったなと思っていたんですけど、「世界の『雑貨化』にあらがうのは、ひとりひとりの身体に染みついた記憶であり、積み重ねてきた時間なのだ」というありがたい言葉をいただいて、それは本当に嬉しかったですね。本人はそんなふうに思って書いてなかったので。
島田 でも、僕もそういうふうに読みましたよ。雑貨化にあらがうものとしてこういうものを書いているんだろうなと。意図的に書いたのかなと思ったぐらいです。
――『波』には三品さんのインタビュー(「雑貨界の地図をつくる」)も載っていて、本書のタイトルについても述べられています。雑貨化が進んですべてが雑貨になるのだとしたら、それはもう物とニアイコールじゃないか。そういう意味での『「雑貨」の終わり』だと。
三品 そうです。要するに雑貨化の一番簡単な定義は、「雑貨屋に置けるものが増えていく」ということです。その定義からいけば、目の前にあるこのコップや水だって雑貨になるわけじゃないですか。これ(飛沫防止用のアクリル板)もイイ感じにすれば置けるかな?(笑) まあ、だからだいたい置けるんですよ。そうなると全部が雑貨だと。そういう中で雑貨化してないものは何だろうと逆に考えたときに、じいちゃんの彫ってた仏像とかね、ある人を救った古いライカのカメラとか、そういう限られた時間のなかでだけは、雑貨化とは無縁の場所にあるものが思い浮かんだんです。誰のためでもなく、自分の記憶を重ねていける物理的なもの。このような記憶を重ねていけるものに対して、「他人の物語を受け入れる耳を持ち、自身の物語を人に押しつけず、双方を包む言葉に近づくこと」が雑貨化にあらがう方法だと、堀江さんに評していただきました。

断片化によって加速する世界と本がもつ「長い時間」
――今日のイベントのタイトルは「雑貨の地図と断片化する社会」で、これは三品さんの案です。「断片化」ということを少し説明していただけますか?
三品 そもそも「雑貨」というものの定義が曖昧なんですよ。「人々が雑貨だと思えば雑貨」って、よく考えたら何も言ってないじゃん!っていう定義じゃないですか。「それを左右するのが雑貨感覚で」と補足されても、なおわかりづらい。だから、この曖昧な「雑貨」という言葉に乗っかるかたちで使われる「雑貨化」という用語は、何にでも使えるマジックワードになってしまいがちなんです。僕としては雑貨化を観察するのは、半径10メートル以内の自分の店の中で起きてることにとどめておきたいんです。もちろん、雑貨化という概念をちょっとずつ敷衍していくと、資本の最先端にあるAmazonのようなところで起きてるような現象にも適応できるのですが、あえてそこには「断片化」という言葉を使って、「雑貨化」と区分けして考えるようにしています。
島田 断片化する世界では何が起きているんですか?
三品 Amazonに行くと何でも売ってるわけじゃないですか。それって結局、もう当たり前になったから論じるのも恥ずかしいですけど、物には本来、専門店に置かれていたころにはそれぞれ固有の物語があって、文脈があったわけですね。その文脈が切り取られる、つまり断片化することで、流通速度が上がって、1秒でも速く1個でも多く売るという論理に適応していくわけです。
島田 断片化が起きると、そこには固有の物語がないから、今度は逆に物語をねつ造するようにもなるわけですよね。
三品 ねつ造もできるし、自由に組み合わせられる。その自由度が人々の買うスピードを上げてるんですよ。物(モノ)の断片化というのは、事(コト)にもかかると思うんです。例えばツイッターも言葉や時間の断片化なわけじゃないですか。何でもそうやって細切れにすることで、流通速度が上がるんです。だからバズるわけであって、バズりも設計に組み込まれていて、それで広告収入が増えるわけでしょ。よって今はどんな世界でも大きい資本がテクノロジーを手に入れれば必ず断片化に向かっていき、流通速度を上げ、マッチング速度を上げていくわけです。それがインターネット以降の経済のトレンドになっていて、そのことと雑貨化は明らかに関係しているわけです。逆に言えば、その断片化した世界を、身近なところに引き寄せて自分の店の中で観察したら「雑貨化」という現象として現れていて、僕はそれを記述しただけだと言えると思います。
島田 でも、三品さんの新しさというのはそこにあるわけですよね。インターネットと切り離して雑貨化というものを語ったとしたら、ここまでにはならなかった気がします。『すべての雑貨』も、そうでなかったら60年代、70年代からある消費文化論的なものと変わらなかったかもしれないけど、そこにインターネットの世界が入りこむことによって、新しい見取り図が生まれた。
三品 インターネットの普及以降を「後期雑貨時代」と僕は勝手に呼んでるんですけど、今回は、その中で自分だけ雑貨化してないかのように高踏的に振る舞うことだけは止めようと思いました。
島田 そこが三品さんの一番良いところだと思います。
三品 自分も雑貨化の中に組み込まれてて、同じようなことを縮小しながら再生産している。その自覚ぐらいですね、僕に倫理があるとすれば。
島田 特徴的な商売人がこの本の中に出てきますよね。普通ならそれを批評として、三品さんが一段高く立ったところから彼らを語るというふうになりがちなんだけども、そうはなっていない。同じ地平にいるんですね。
三品 だからずーっと、地べたで自問自答ですよ。自問自答地獄(笑)。今作は雑貨の地図の上に無印良品やディズニーランド、ポートランドやシェーカーの共同体なんかを見つけ出して、いそいそと訪ねていっては悶々と何かを考えるようなエッセイです。さっきお話ししたように俯瞰はできないですから、てくてく歩いていくんですけど、行ってもあんまり中に入らず犬みたいにぐるぐる回って、また次に行ってぐるぐる回るという、そういうイメージなんです。この物事の周りをぐるぐると周回して考えつづけるって行為には、結論もないし、逃げてると捉えられるかもしれない。だけどそのことは、島田さんが去年書かれた『古くてあたらしい仕事』(新潮社)の中で提示していた「長い時間」というアイデアにも通じると思っているんです。
――どういうことですか?
三品 島田さんは、本を読むということは「長い時間」「長い思考」というものの中に入っていくことだと書かれてますよね。SNSには短い時間で、短い思考があるから、そこにフィットしなかった人たちは、違う時間がある本の世界においでよって。
島田 はい。本の良さみたいなものを、世の中に対して提案しなくてはいけないときに、僕は長く考える時間を担保してくれるものとしての本という価値を言っています。
三品 すごく消極的な擁護にも聞こえますが。
島田 でもそれしかない気がします。やっぱり本の中には、そういった断片化できないものがあって、そこに価値がある気がしていて、それは何なんだろうってずっと考えるわけです。自分の気力さえあれば、1冊の本を1カ月とか1年かけて読むことができるわけじゃないですか。そこに僕は救いみたいなものをずっと感じています。三品さんの本も、雑貨の地図を描こうとしながらも、何かに回答を与えるという本ではないですよね。
三品 だから、僕のやってることも、ぐるぐる回ってそこで「長い時間」「長い思考」を作ろうとしてるわけです。くり返しになりますけど、結局、自分だって雑貨を売ってるわけだから、雑貨化が終わってもらったら困るわけで、そういう中で自問自答している。それを倫理といったら大げさだと言われるかもしれないけど、自問自答しないのとするのでは大きく違うと思うんです。
(後編はこちら)

-
島田潤一郎
2019/11/27
新潮社公式HPはこちら
-

-
島田潤一郎
1976年高知県生まれ。東京育ち。日本大学商学部会計学科卒業。大学卒業後、アルバイトや派遣社員をしながら小説家を目指していたが挫折。2009年9月に33歳で夏葉社を起業。ひとり出版社のさきがけとなり、2019年に10周年を迎えた。著書に『あしたから出版社』『90年代の若者たち』『古くてあたらしい仕事』がある。
この記事をシェアする
「三品輝起×島田潤一郎「雑貨の地図と断片化する世界」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
連載一覧
著者の本
イベント
-

- 島田潤一郎
-
1976年高知県生まれ。東京育ち。日本大学商学部会計学科卒業。大学卒業後、アルバイトや派遣社員をしながら小説家を目指していたが挫折。2009年9月に33歳で夏葉社を起業。ひとり出版社のさきがけとなり、2019年に10周年を迎えた。著書に『あしたから出版社』『90年代の若者たち』『古くてあたらしい仕事』がある。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら