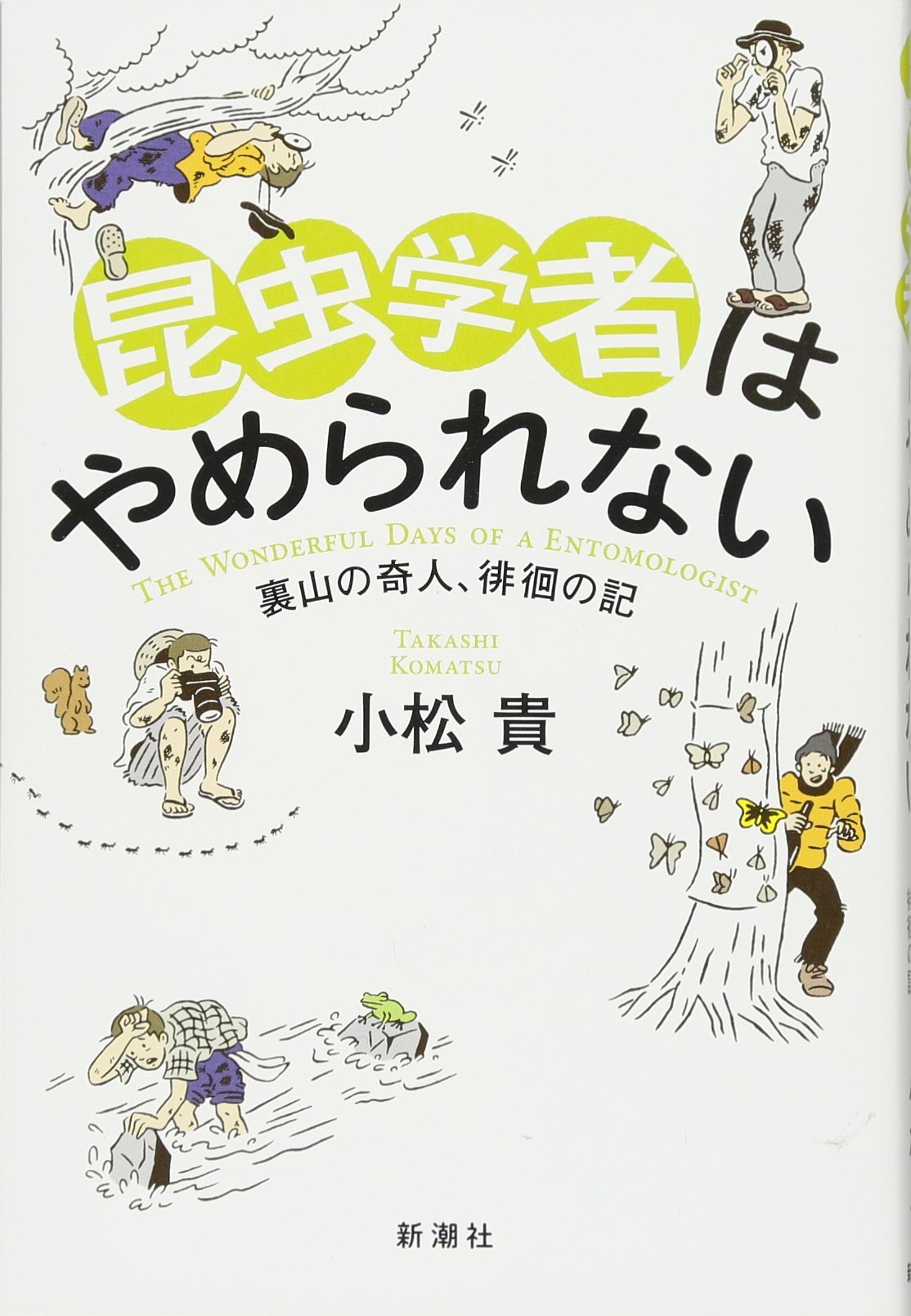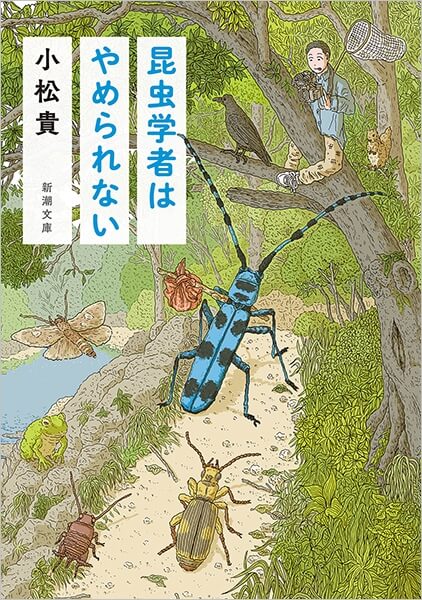私は少し前まで、九州・博多の近郊にある九州大学で、アリの巣に寄生する生き物の研究をしていた。
私がそんな珍妙な生き物の研究を始めた背景には、過去に私自身が体験したいろんな出来事が複雑に絡んでいる。2001年、長野県松本の信州大学に入学した私は、それまで住んでいた埼玉の地方都市から山国へと移り住むことになった。当時、大学の周囲には娯楽施設など皆無に等しく、ひたすら山と川しかなかった。もともとあらゆる生き物が好きだった私は、大学の空き時間を利用して自転車で大学の裏山へと向かい、そこに息づくいろんな虫を採ったり観察したりするのが日課となっていった。長野の山々には様々な種のアリが生息し、それに寄り添って生きる好蟻性生物の種数も豊富だ。私は、やがて将来飯の種とするこれらアリや好蟻性生物たちを、地に這いつくばって夢中で観察したものだった。しかし、裏山には他にも巧妙かつ不思議な行動を見せる
私が松本市に住んでいた頃、季節に関係なく日没後には近所の裏山へ分け入り、そこにいる様々な生き物を観察するという習慣があった。もはやこれは本能というか習性というか、自然と体が裏山のほうへと向かってしまう、抗いようのない摂理であった。裏山は日中でも時間さえ工面できれば出かけるのだが、夜は日中とは全く異なる生き物が出てくる。また、日中見かける生き物も、夜はまるで違う動きや反応を見せてくれるため、それを見るのがたまらなく面白かったわけである。ここで紹介する、とある不思議なクモもその例に漏れない裏山の舞台役者の一人だ。
私の足しげく通っていた裏山には遊歩道が作られており、点々と小さな街灯が設置されている。日没後、これらは自動的に点灯し、赤みを帯びた光で周囲をぼうっと一晩中照らす。本来、赤みを帯びた光というのは虫をあまり誘引しない。虫は赤い光があまりよく見えていないからだ。だからこそ、夏に昆虫採集をする人々はなるべく青い光を使って森に張った白い布を照らし、虫を集める。また、コンビニの入り口近くに設置されている電撃殺虫灯も、効率よく虫をそこに集めて殺すべく青い光を放っている。しかしながら、この裏山の赤い街灯には思いのほか多種多様な虫が季節を問わず飛来する。だからこそ、私は裏山に到着するとまず先にこの街灯をチェックするわけだ。そんな街灯の周囲で、割と年中いつでも見かけるクモがいる。
体長は最大で1センチメートル程度。全体的に茶褐色でぱっとしない色彩だが、個体によっては体にスッと黒い直線が走っている。長めのおみ足に細身の体型もあいまって、なかなか端正な外見のクモである。見かけるときは、いつでも街灯周辺の細い雑草の葉上にいて、まるでその細い葉の形に合わせるかのように脚を伸ばしてじっとしている。そして夜行性の気が強く、日没後にならないと街灯周辺の目に付く場所には出てこない。網は張らず、目の前にたまたま飛んできたガなどに高速で飛びつき、捕食する。彼らの名は、アズマキシダグモという。北海道から九州にかけて広く分布し、草原や雑木林などに生息する地表徘徊性のクモだ。さほど珍しい種ではなく、クモそのものは年中見られるが、成体は初夏にだけ姿を現す。この一見何のとりえもなさそうな小グモ、実は現在知られている限りの世界中のクモ全部を見渡してもあまり例のない、非常に変わった習性を持つことで知られている。オスがメスに餌をプレゼントするのである。
通常、徘徊性である彼らは獲物を捕らえると、そのままその場でこれを食ってしまう。しかし、繁殖をひかえた成体が出現する初夏の頃になると、少し勝手が違ってくる。日没後、オスの成体はいつものように獲物を待ち伏せ、これを捕まえる。ところが、オスはこの獲物を自分で食らおうとせず、奇妙な行動に出る。獲物を自分の体の下に置いた後、尻から盛んに糸を繰り出して獲物に巻きつけ始める。20分近くもかけてその行為を続けると、ついには獲物の体は完全に真っ白い小包のような風貌を呈するようになる。オスはこの小包を口にくわえて、周囲をふらふらと
生物の中には、交尾の際にオスがメスに対して餌を提供するものが多数知られており、この行動を「婚姻贈呈」と呼んでいる。昆虫ではいくつかの分類群で、こうした行動をとるものが知られており、動物行動学的な観点から盛んに研究されてきた。一方、クモにおいてこうした行動をとるものは、アズマキシダグモを含むキシダグモ科の他、数種のクモに限られるらしい。日本では長らくこのアズマキシダグモただ1種のみが知られていたが、近年その近縁筋のハヤテグモというのも婚姻贈呈の習性を持つことが確かめられている。
昨今のファッション雑誌などを立ち読みするかぎり、人間の男が女を口説く際には、プレゼントだけではなく映画に連れて行ったり服装を褒めたり、いろんなことをせねばならないらしい。それを考えると、プレゼントを1個渡すだけで簡単にメスが落ちるクモの世界の、なんと気楽なことか。私は当初そう思っていたが、実際に観察してみるとそんなに簡単なものではないことがよく分かった。オスは自分が食うでもない獲物をわざわざ捕らえて、丁寧にラッピングまで施し、それを抱えてひたすらメスを探し歩かねばならない。運よくメスに出会っても、クモのメスは気難しい奴らばかりで、餌さえ持っていればどんなオスにもなびく訳ではない。私が野外で観察した複数の雌雄の組み合わせのうち、最終的にプレゼントの受け渡しにまで至ったのは一組だけ。その一組というのも、短時間でメスが機嫌を損ねてオスを追いやってしまった。クモの世界にはクモの世界なりの苦悩があるのだろう。
クモのオスは、ただあてどなくどこにいるか分からないメスを求めて彷徨っているわけではない。クモは歩く際に「しおり糸」と言って、わずかに糸を出している。オスはメスの出したしおり糸を辿り、メスの元へと向かうようである。首尾よくメスに遭遇できたオスは、早速に複雑かつ巧妙な繁殖行動を展開することとなる。
メスの正面方向からオスは慎重に近づく。メスへの接近方法は、オスにとって非常に重大な案件だ。クモは基本的に視力があまり発達していない生き物なので、オスがいきなり不用意にメスに接近しようものなら、危機を感じたメスに反射的に攻撃される可能性が高い。だから、なるべくメスに認知されやすいよう、正面からアプローチする。しかも、ただ近づくだけではない。オスは、盛んに脚を動かしたり体を振動させたりして、ダンスを踊る。目に付く動きに加えて振動を起こすことにより、これから近づくけど敵じゃないから攻撃してくるなとメスを牽制するのだ。この段階でメスが乗り気ではなかった場合、メスはきびすを返して逃げ去ってしまうか、逆にオスを威嚇して追い払ってしまう。メスが逃げない場合、オスの求愛を受け入れる用意があるということである。慎重にメスのすぐ手前まで来たオスは、小包をくわえたまま体を捻り、腹面を上に向けるような無理な体勢をとる。そして、メスの腹面下に滑り込むようにして、直接メスの口に小包をくわえさせる。メスがこれを受け取れば成功。この時に、オスは口元に生えている膨らんだヒゲのようなもの(触肢)を、メスの腹側の生殖器に突き刺して受精を完了させる。クモの繁殖は、昆虫の交尾のような体勢をとらない。あらかじめ触肢に精子を蓄えた状態のオスが、メスの生殖器にそれを突き刺すというもので、交接と呼ばれている。
クモは人間とは違い(いや、あながち違うとも言い切れないが)、一般的にメスのほうが体が大きくて力が強い。このため多くの種のクモにおいて、しばしば交接を行う前後で力の弱いオスがメスに捕まって食われてしまうケースが見られる。こうした事例はカマキリで有名だが、クモの場合はカマキリ以上に高頻度で交接時の共食いが起き、交接に成功したオスは必ずメスに食われるという種もいるほど。そのため、アズマキシダグモなどに見られる婚姻贈呈の理由は、メスに食われたくないオスが自分の身代わりとして餌を用意し、メスの機嫌をとるためだとかつては解釈されていた。しかし、少なくともアズマキシダグモに関しては、雌雄でさほど体格に差がなく、オスはメスに攻撃されることはあっても丸ごと食われてしまう可能性は低い。近年では、身代わりというよりも交接の時間稼ぎとして餌を用意する意味合いが強いのではないかと考えられているようだ。交接の時間が長ければ長いほど、オスは自分の精子をより多くメスの体内に送り込むことができる。餌に食いついている間、メスは比較的オスの振る舞いに対して無頓着になるため、より大きくて食べ終わるのに時間のかかる餌を用意してメスに渡せば、それだけ長い時間オスは交接を許される。また、産卵前に大量のタンパク質を労せずして得られる点では、メスにとっても有益だ。
交接をすませたメスは、やがて産卵する。地面などに糸でシートを作り、その上に数十もの卵を塊で産み落とし、これを糸で包み込んで卵嚢を作る。メスは卵嚢を口にくわえて持ち歩く。口が塞がっているから、当然餌は摂れない。敵に襲われたときなどは、卵嚢と自分のすきっ腹とを抱えて死に物狂いで逃げ回らねばならないのだ。
盛夏前に卵は孵化するが、孵化が近くなるとメスは林の下草の間に粗末なテントを張って、そこに今までくわえていた卵嚢を吊るす。その傍でメスは餌もとらずじっと見守っており、頃合を見て卵嚢を破り、中の子供たちを外へ出す。それから数日間、テントの中で1ミリメートルサイズの大量の子供たちとメスは同居するが、やがて子供たちは文字通りクモの子を散らすようにばらけて独り立ちしていく。それを見届けてから、メスは痩せ細ってやがて死ぬ。
秋から冬にかけて、子グモたちはめざましく成長していく。しかし、途中で大半のものたちは、親グモが歯牙にもかけないようなアリ、他のクモなどに捕まって餌食になるため、最終的に生き残るのはごく僅かの個体だ。裏山から大概の虫たちが姿を消す厳冬期、夜の遊歩道沿いの灯りにはフユシャクという、寒冷な時期にしか出現しない小蛾の類がちらほら集まる。これを捕らえるため、アズマキシダグモの若齢個体たちも寒い中、街灯の周囲に集まってくる。この時期、彼らにとって唯一の餌であるフユシャクは、この裏山では1月から2月末くらいの間は完全に姿を消す。冬に活動するガですら、この期間はあまりにも寒すぎて活動できないのだ。だから、クモたちはその前に、なるべく多くのフユシャクを捕まえて体力を養わねばならない。しかし、一晩で灯りに飛来するフユシャクの個体数はさほど多くない上、罠も何も持たないクモがこれを捕らえるのは容易ではない。恐らく、ここで多くのクモが命を落とすことになる。無事、この試練の季節を乗り越えたものだけが、翌年の繁殖期を迎えることができるのだ。
民家のすぐ近くの林で、ひそやかに行われている生と性のドラマ。それはどんなテレビのドラマよりも、神聖で巧妙かつ愛おしい。
【他の章の試し読みはこちら】
-

-
小松 貴/著
2018/4/26
『昆虫学者はやめられない: 裏山の奇人、徘徊の記』の刊行を記念して、小松 貴さんサイン入り単行本を3名様にプレゼントいたします。
5/31(木)23:59まで
>>プレゼント応募はこちらから<<
-

-
小松貴
こまつたかし 研究者。1982年生まれ。信州大学大学院総合工学系研究科山岳地域環境科学専攻 博士課程修了 博士(理学)。2014年より九州大学熱帯農学研究センターにて日本学術振興会特別研究員PD。2014年に上梓した『裏山の奇人 野にたゆたう博物学』(東海大学出版部)で、「南方熊楠の再来!?」などと、各方面から注目される、驚異の観察眼の持主。趣味は美少女アニメと焼酎。最新刊は『虫のすみか―生きざまは巣にあらわれる』(ベレ出版)。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら