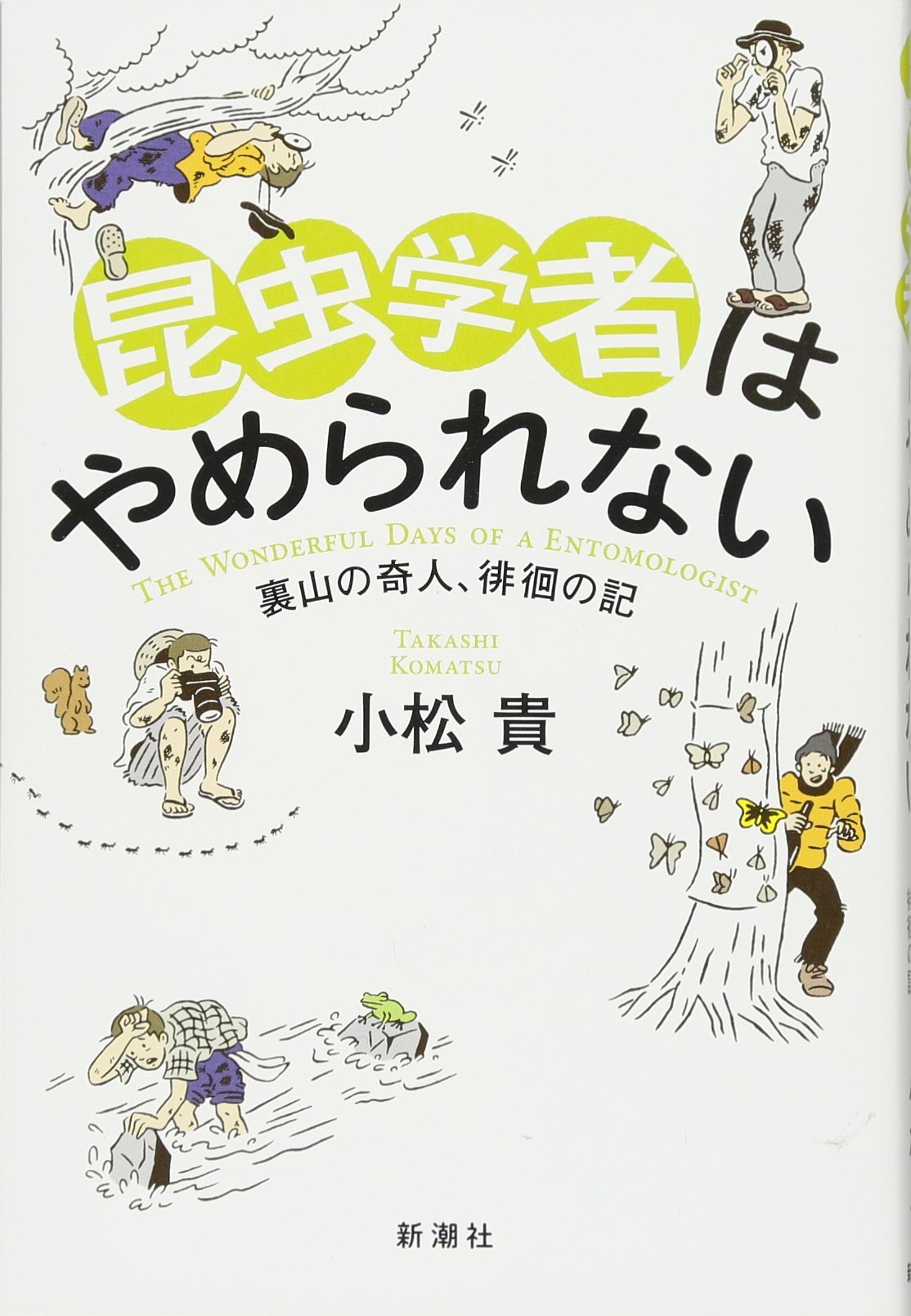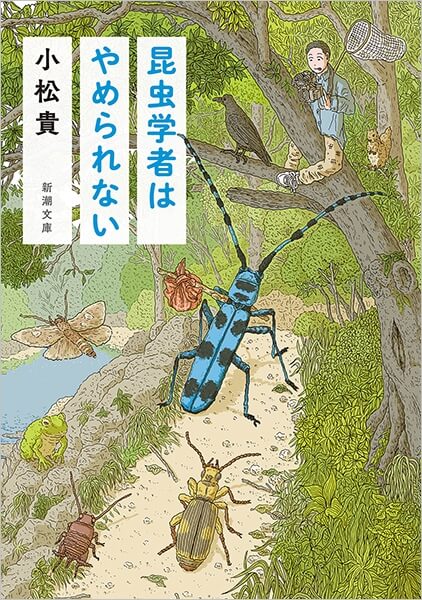私には好きな虫がある。一つは、眼の退化した虫。もう一つは、翅の退化した虫だ。理由などない。しかし、どうしようもなく奴らは私を惹きつけるのだ。
昆虫の中には、翅が退化して飛べなくなってしまったものが少なからず知られる。その内訳は様々で、その分類群に含まれるもの全てが飛べなくなったというのもあれば、他の近縁種が軒並み飛べるのに、ただ1種だけ飛べなくなったものがいる、など。翅はあるが飛翔筋が退化して羽ばたけないもの、翅自体がなくなり飛べないものもいる。
昆虫が飛ぶ能力を失う理由も千差万別だ。島のような環境に隔絶され、飛ぶ必要がなくなったもの。自分より遥かに大型の生物に取り付いて移動するため、体毛羽毛に潜り込むのに邪魔な翅を捨てたもの。さらに、寒冷な条件下に住むものは、飛ぶ行為が身体に負担をかけるとか、体表面積を減らして寒さから受けるダメージを減らすなどの理由から、翅を捨てたと考えられるものもいる。実は身近な裏山で、そんな奇妙な昆虫を普通に見ることができる。真冬に出現する、翅のないガがいるのだ。
シャクガ科のガは、幼虫がいわゆる尺取虫として知られるガの仲間で、世の中に莫大な種数を誇る。そのうち一部の種は、秋の終わりから春先にかけての寒冷期に限って成虫が活躍し、俗にフユシャクと呼ばれている。日本では30種前後のものがフユシャクとみなされている。
フユシャクと呼ばれているシャクガ類には、一貫して共通した生態的、形態的特徴がある。まず、成虫が寒冷期にしか現れない。春から初夏にかけて卵から孵化、成長し、盛夏前には地中に潜り蛹化する。そして、羽化の時まで休眠するのだ。また、彼らは食事をするための口吻が退化している。真冬にそもそも餌になる花蜜や樹液がないのもあるし、時に気温が氷点下にまで下がる真冬に、変温動物たる彼らが水分を体内に入れてしまうと、文字通り身体の芯から凍って死ぬ恐れがある。彼らの体液には、不凍液の役目を果たすグリセリンが含まれるため、水さえ入れない限りは氷点下でも体内が凍ることはない。さらに、彼らはメスに限り翅が退化している。種によりその退化の程度は異なり、頑張れば飛べそうな程度には翅を残す種もいれば、痕跡すらない種もいる。後者に関しては、もはや外見がガですらなく、丸っこいクモにも見えることから、英語でスパイダーモスとも呼ばれる。
飛べないメスは、代わりに尻からフェロモンを散らして、たまたま近くを飛びかかったオスを呼び寄せて交尾する。交尾後、メスはまもなく樹幹の裂け目などに大量の卵を産み付ける。フユシャクのメスの腹部はでっぷりとしてふくよかだが、まるで子持ちシシャモの如く細かな卵で満たされているため、全部産卵し終えると、空気の抜けた風船みたいにしなしなになってしまう。オスもメスも、口がないゆえ餌が取れず、羽化時に体内に蓄えていたエネルギーを一方的に消費するのみのため、成虫はわずか1週間かそこらで死ぬ。その短期間のうちに、彼らはやるべきことを済まさねばならないわけだ。
こんな風に総じて似通った特徴を持つ彼らだが、実はこのフユシャク、分類学的にまとまった仲間内ではない。シャクガ科の中ではさらに複数の亜科(サブグループ)に分かれているが、それらのうち直近同士とは言い難い三つの亜科に含まれる種の中から、たまたま寒冷期に発生するよう適応進化した種が現れた結果に過ぎないのだ。よりによって、なぜ親戚というほど近くもない間柄の中から、ただただクソ寒くて辛いだけの冬に狙い澄まして発生するようなものが誕生したかについては、まだはっきりと分かっていない。
私が根城にしていた長野の裏山では、狭い範囲ながら国内で知られるうちの実に半数ほどにあたる16種のフユシャクが生息していた。それらは概ね種ごとに発生時期を微妙に違えており、だいたい1~2週間単位でその地域の種構成が次々と移り変わる。だから、秋から春先まで毎日そこの裏山に通うだけで、全く同じ地点で様々な種のフユシャクを見ることができたのだ。
多くのフユシャクの種は夜行性だ。だいたい日没後から2時間くらいの時間帯が、どの種も活動のピークとなる。この時間帯になると、それまで落ち葉の下などに隠れていたガ達がボチボチ草木の枝葉に登り始める。目立つのは、やはり大きな翅を持ったオスだ。彼らは皆一様に褐色がかった地味な色合いで、日中は周りの枯葉の色と紛らわしい。しかし、本物の枯葉よりも明らかに白っぽい上、暗闇にて人工のライトで照らした際のテカり方が、本物の枯葉のそれと全く異なる。なので、枯葉や樹皮など紛らわしい場所に止まっていても、夜ならば比較的発見は容易い。オスと同時かやや遅れをとり、メスも高所に登る。その後、尻から小さくも奇妙な角らしきもの(フェロモン嚢)を出し入れしつつ、オスへと信号を送り始める。このメスの行動は、コーリングと呼ばれる。
枝葉から飛び立ったオスは特に目的地もなく、闇夜の森をやみくもに飛び回る。こうして少しでも広範囲を巡りつつ、どこかにいるメスが発するフェロモンを感知する機会を増やすのだ。昔、ファーブルはヤママユガを使った実験を行い、ガのオスはメスのフェロモンを何キロ先からも嗅ぎつけ飛んでくるといった内容を昆虫記に書いたが、それは正しくない。ガのメスが発するフェロモンの射程範囲は、せいぜい半径1~2メートルくらいといわれている。たまたまメスの近くをやみくもに飛んでいて射程範囲内に入ったオスが、フェロモンに気付いて誘引された結果に過ぎないのだ。
メスのフェロモンを感知した途端、フユシャクのオスの動きは激変する。それまで直線的にゆっくり飛んでいたのが、突然螺旋を描くように墜落する。そして、苦しげにのたうつように、激しく羽ばたきつつ地べたを歩き回る。この時のオスは、飛びそうで飛ばない。ジグザグの軌跡を描きつつ、羽ばたき歩きをしばらく続けると今度は、ある時いきなり立ち止まり、羽ばたきもやめる。何事かと思ってよくよく見れば、オスはその場に止まっていた小さなメスと連結して交尾を始めているのだ。オスに比べてメスは翅がない分、小さくて目立たない。人間が広大な森の中からこの微小生物を見付け出すのは至難だが、オスのガはすぐ見付け出す。しばしば、コーリング中のメスがいる草むら周辺に、おびただしい数のオスが群がる時があり、オスの群れからメスを見つけることもできる。
コートを着込まねば外にも出られない、小雪舞う極寒の夜の裏山で繰り広げられる、白いガ達の舞踏会は、何度見ても異様な光景だ。しかしどれだけ大勢のオスが群がろうと、最終的にメスと連結するのはただ1匹のみ。誰かと連結完了した途端、メスはフェロモンの放出をやめるため、あぶれたオス共は瞬く間に我に返って各々散ってしまう。ガ達の舞踏会は、ある瞬間あっさり幕切れとなるのだ。
フユシャクの大半種は、日没後から2時間の活動となるが、中には変則パターンを示す種もいる。チャバネフユエダシャクは、比較的大型のフユシャクの一種で、日本各地に広く分布する。フユシャクの中では割と普通種ではあるが、この種の雌雄の形態差は、フユシャクの中でもことさら顕著な部類に入る。オスは全体的に黄色っぽい色彩なのに、メスの姿がとんでもない。翅が全くないのは言うまでもないとして、体色がメリハリのある白地に黒のまだら模様。まるでミニチュアのホルスタインだ。何も知らない人がこの2匹の昆虫を見たら、間違っても同種の夫婦だなんて思う訳がない。しかし、紛れもなくこの2匹は同種であり、ちゃんと交尾をしているはずなのだ。
なぜ、「している」ではなく「しているはず」というかと言えば、私はこの虫が交尾している様を一度も見たことがなく、本当にそんな事をしているのかと腹の内で疑っていたからに他ならない。私は、このフユシャクが交尾している様をどうしても一目見てみたいと探し続けて来たが、どう頑張って探しても見つからなかったのだ。フユシャクは、裏山の遊歩道沿いに並ぶ街灯に夜間オスが集まるため、その集まり具合を見ることで、今はどの種の発生がピークかを推測できる。そのやり方で、チャバネフユエダシャクのオスが一番多く飛来する時期を選び、集中的に夜の裏山を徘徊する、というのを、私は長野に移り住んで以後10年以上も続けてきた。なのに、他の種の交尾はいくらでも見るのに、チャバネフユエダシャクのそれだけはなぜか一切見つけられなかった。
これは私だけの問題ではなかった。当時、インターネット上の画像検索で調べても、他の種はともかくこの種の交尾している姿の写真は1件も引っかかってこなかった。世の中には私みたいに、身の回りにいる虫の写真を撮るのを趣味とする偏屈な者たちが沢山いる。だが、しかし、その数多の監視網をもかいくぐり、奴らは頑なに交尾の様を人間共の眼前に晒さなかったのである。北海道から沖縄まで、日本各地に分布するド普通種だというのに(※)。
長年に亘るこれ程執拗な探索にもかかわらず、チャバネフユエダシャクの交尾のみ見られなかったのは、その活動時間帯が根本的に他のフユシャクとは異なるせいではないか。そう考えた私は、2011年の初冬に思い切った作戦を敢行した。深夜に出かけて探すのだ。通常私はフユシャクを観察するために、夜7~9時の間に裏山へ行き、そして帰る。これをもっと遅くずらして、夜11時に出かけて見ることにした。いつもなら布団に入る準備にかかるこの時間帯、ましてクソ寒い信州の山の中である。いるかいないかも知れないものを見るために外へ出かけるのは、正直億劫でしかなかった。しかし、ここでやらなければ必ず後悔する気がした。
夜中の裏山は、寒さにくわえて近隣民家からの生活音も消え、漆黒の闇の中、空気はピンと張り詰めていた。いつも庭のように闊歩している場所なのに、何か違う材料で見慣れた景色を再構築したような、妙な感覚を覚えた。鼻水を垂らしながら、真っ暗な森を歩いてガを探す。やはり遅い時間帯なので、日没前後から活動するような種は軒並み動かず枝葉に止まっていた。どこを見回しても、動いている生き物の姿が見当たらなかった。チャバネフユエダシャクなど、言うべきにもあらぬ状況。だんだん心細くなってきたのと、ただ一人こんなクソ寒い場所に居続けることが空しくなってきたのとで、私は帰ることにした。
こんな時間こんな所までこんな無駄なことをしに来るくらいならば、とっとと帰ってオフトンの中で温まっていたほうが遥かにマシだったんじゃないのか。何だか、無性に腹立たしい気分になりながら裏山の道を下りきる手前でのことだった。ふと目の前2 メートル位の所に、1匹の黄色いガがチラチラと降りてきた。チャバネフユエダシャクのオスだ。この晩、ようやく見つけた最初の活動中のオスだった。
チャバネフユエダシャクのオスは大型ゆえ飛翔力が他のフユシャク類よりも強く、普通は人の目線の高さの2倍以上の高所を飛ぶことが多い。それが、なぜか低い所に突然降りてきたのだ。風で煽られたわけでもなく、何らかの目的意識をその動きに感じた私は、そのまま歩みを止めてじっと彼奴を凝視した。ガはホバリングするように、道脇から伸びていた細い枯れ草の周囲を飛んだあと、ふいに数回その草に体当たりをかました。そして、体当たりの末に枯れ草の茎の中ほどにしがみつき、羽ばたきながら茎を伝って歩いた。そいつがふと立ち止まったのを見計らい、私はそっと近寄ってみた。ただただ、ため息をつくほかなかった。目の前には、姿かたちが似ても似つかぬ2匹の昆虫が、物言わず相反する方向を向きながら連結していた。私がこの虫のその様を見つけてやろうと思い立ってから、実に11年目の事だった。
※1986年に出版された『冬尺蛾 厳冬に生きる』(中島秀雄 築地書館)の表紙に、デカデカとチャバネの交尾写真が載っており、これ以外に長らく私は本種の交尾写真を拝める文献・媒体を知らなかった。その後、このガの活動時間が比較的遅いという知見が知れ渡ったせいか、2013年辺りを境に多くの虫マニアが各地でこの種の交尾を撮影し、ネットに写真を上げるようになった。
【他の章の試し読みはこちら】
-

-
小松 貴/著
2018/4/26
『昆虫学者はやめられない: 裏山の奇人、徘徊の記』の刊行を記念して、小松 貴さんサイン入り単行本を3名様にプレゼントいたします。
5/31(木)23:59まで
>>プレゼント応募はこちらから<<
-

-
小松貴
こまつたかし 研究者。1982年生まれ。信州大学大学院総合工学系研究科山岳地域環境科学専攻 博士課程修了 博士(理学)。2014年より九州大学熱帯農学研究センターにて日本学術振興会特別研究員PD。2014年に上梓した『裏山の奇人 野にたゆたう博物学』(東海大学出版部)で、「南方熊楠の再来!?」などと、各方面から注目される、驚異の観察眼の持主。趣味は美少女アニメと焼酎。最新刊は『虫のすみか―生きざまは巣にあらわれる』(ベレ出版)。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら