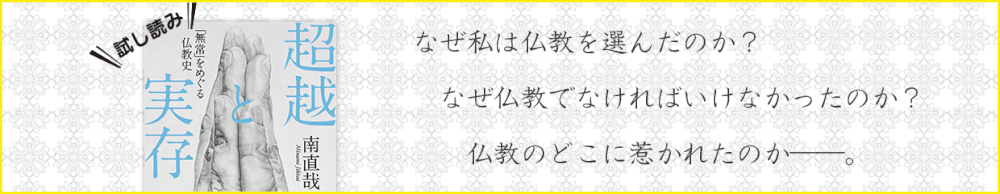2018年1月24日
南直哉『超越と実存 「無常」をめぐる仏教史』試し読み
著者: 南直哉
なぜ私は仏教を選んだのか? なぜ仏教でなければいけなかったのか? 仏教のどこに惹かれたのか――。
曹洞宗の総本山・永平寺の門を叩いてから30年余。「恐山の禅僧」南直哉師が、出家以来ずっと続けてきた仏教探求の旅。その成果としてまとめられたのが、1月25日刊行の『超越と実存 「無常」をめぐる仏教史』(新潮社)です。
「私がねらうのは、ゴータマ・ブッダに淵源する、私が最もユニークだと思う考え方が、その後の言説においてどのように扱われ、意味づけられ、あるいは変質したかを見通すことである。(中略)「無常」という言葉の衝撃から道元禅師の『正法眼蔵』に出会い、果てに出家した自分の思想的遍歴を総括しようとするものである」(序章「問いの在りか」より)
と、本書にもあるように、ブッダから道元までの思想的変遷を、「超越と実存」の関係から読み解いたものです。
その刊行を記念して、本書所収の「プロローグ――私の問題」を公開します。

プロローグ――私の問題
修行僧になって五、六年経った頃、師匠が突然言った。
「直哉、お前、誰かに随身するつもりはないか」
「随身」とは、力量のある高僧に仕え、寝食を共にしながら、その膝下で教えを学ぶことで、禅宗では非常に重要視される修行である。
後で聞いたところでは、道場で五年以上たち、ほとんど掣肘されずに自分の好きなように振る舞っていた私を心配した人が、「アレは、どこかのちゃんとした師家(指導者)について、ゴリゴリ磨いてもらわないとモノにならん」という苦言を、師匠に呈したらしい。
「どうだ、誰か付きたい師家はいるか。たとえば、○○老師はどうだ?」
師匠は当時高徳の師家として大変有名だった老師の名前を挙げた。私は言下に答えた。
「その人はダメです」
「そうか、ダメか、ワハハハハ……」
すると師匠は破顔一笑、本当に大爆笑して、以後まったくその種の話をしなくなった。
私はその高徳の老師を直接知っていた。ある研修会で指導者として来ていた老師のお世話係を四、五日する機会があったのだ。修行一筋で生涯を貫き、その高潔な人格で多くの若い修行僧に敬愛されている禅僧だと聞かされていたが、本当にそうだった。
引きも切らぬ指導の要請に応えて、寸暇を惜しんで各地を訪れていた老師は、当時まさに疲労困憊の様子であった。ある朝の坐禅で、老師は鋼鉄の板を背骨に差し込んだような剛毅な坐禅姿のまま、驚いたことに目を開いた状態で、寝息を立てていたのだ。
「君にはわかったかな。恥ずかしい限りだ」
控室に戻るとき、老師は後ろに随う私を振り返ってそう言った。私は泣きそうになったことを覚えている。
しかし、それでも、この老師の考え方と生き方が、私には自分の役に立たないとわかっていた。
私は、仏教に何らかの「真理」を見て、それを獲得するために修行しようと思ったわけではないからだ。
もし「真理」が目的なら、この老師の一徹な生き方を支えるものが何か、それが仏教の「真理」かどうか、もう少し慎重に時間をかけて観察しただろう。あるいは、その「真理」の体現者と目される釈尊と道元禅師への、あの坐禅が表すような一途で純粋な思慕に、深く傾倒したかもしれない。
だが、私は事情が違った。私には昔から、どうしても解決したい問題があった。そのための道具として、仏教を選択したのだ。釈尊や道元禅師の言動が「真理」かどうかではなく、敢えて言えば、使えるかどうか、だったのである。
私には幼いころから引きずる問題がこれ以上なく明瞭に意識されていたから、道具としての適否は、いつでもどこでも、ほとんど一目瞭然、感覚的にわかったのだ。
師匠は、私の問題に共感も理解も持たなかったかもしれない。ただ、私が他の大抵の僧侶とはまったく違った方向を見ていることだけは見抜いていたから、私の「ダメ」を笑って終わったのである。
結果的に、私はとんでもなく生意気な修行僧になってしまった。
ある勉強会の席上で言いたい放題のことを言っていたとき、道場の師家の一人に、気の毒そうに言われた。
「ああ、直哉さん。君はまだ正師に逢っていないな」
私はそのときも即答した。
「いいんです。私が自分で正師になりますから」
師家は、若造のあまりに想定外の言い草に、度肝を抜かれたのか、あきれ果てたのか、何か言いかけて黙り込んでしまった。
仕方がなかった。私の問題を私のように理解しているのは私だけだ。同じような人間に偶々出会うことはあるかもしれないが、今までまったくお目にかからなかったのに、これから探したからといって、確実に見つかる保証はない。だったら、よそで「正師」を探す時間を、自分で考えることに集中させた方がよい。つまり、自分以外の誰も当面は「正師」として役に立たない。それが私の結論だったのである。
ただ、一番堪えたのは、当時仕えていた上司に「直哉さんは辛いよね」と突然言われたときである。彼は「正師」などと言わなかった。
「君には生身のモデルがいないもの。モデルがいれば、自分のやっていることを考えやすいのに」
その通りであった。当時の私の最大の泣きどころは、自分が考え、実践していることが、本当に問題の解決に向かっているのか、皆目見当がつかないことだったからである。自分に似たような先達がいれば、それを例にして反省したり考え直したりできるはずだった。
しかし、結果的にそういう人物はいなかったし、私は早々に諦めていた。それというのも、当時の道場での修行方法が、私の問題とまったく噛み合っていなかったからである。このシステムから、私のモデルとなるような人物が出てくるはずがない。
およそ修行だの教育だのは、まず行うことの意味を教えて実践させるか、とにかくやらせてから、意味を説明するかである。いずれにしろ、この理屈と実践はペアで、どちらを欠いても、まともな修行にも教育にもならない。
ところが、往々にして禅門で言う「不立文字」を単純に考えて、問答無用的実践を標榜するような道場では、修行の「意味」を考えることが蔑ろにされがちであった。
私はそうはいかない。少なくとも自分の問題と脈絡がつかなければ、それこそまるで無意味である。なんとしても、自分の現在の実践を「理解」する必要があった。
結果的に、私は孤独になった。誰からも教えられず、それが正解かどうかもわからぬまま、私は経典や祖録(祖師の言行録)を手掛かりに、毎日の修行のそれぞれの意味を、考え続け、言わば案出していたのだ。
そういう私のやり方は次第に極端になった。
後に「ダース・ベイダー」などと呼ばれる元になった、一時期の苛烈な修行と後輩の指導は、実を言うと、自分が疑念を持つ道場の修行システムを徹底的に追及してみたら、結果どうなるのかという実験だった。問答無用の修行もやってみれば、それなりの成果があがるのか?
やってみて、わかった。これはダメだと。
ダメだが、七百五十年続く修行がすべて無意味とも思えない。ただ、その「意味」を考え、現代の我々の「生」と関連付ける知的努力が致命的に不足していた。だから、釈尊の教えに照らしても、道元禅師の遺訓からいっても、もはや無益だったり、むしろ妨げになるような道場の指導が、「伝統」ではなく「前例」として積み上がり、修行自体を硬直化させていたのである。私は丸四年でそれを見切った。
ある同輩が言った。
「お前は先を見すぎる。多分、他の人間が見ないものを、見ようとしないものを見すぎる。だから、周りが理解しない。理解したくても追いつかない」
そうかもしれなかった。だが、もう後戻りもできず、他の方法に転ずる余地も無かった。私は自分が今ここでしていることを、仏教の過去と結び付け、未来に臨んで、これまで「伝統」と呼ばれてきたものを再解釈しようとしていた。それもこれも、自分の問題に効くアプローチを発見するためである。
私の抱え込んできた問題が何で、再解釈がどのようになされたのかの一端は、以下の本文で論じられるだろう。ただし、本書では、私の問題意識と再解釈を繋いだ、当時の修行の実際が語られることはない。それは直接のテーマではないからだ。
しかし、あの頃、私は確かに自分の存在を賭した修行を理解し意味付けるために、経典と祖録の言葉を執拗に追及していたのである。そこから結果的に、ほとんど副産物の如く導き出されたのが、本書の基本的な骨格となる「超越と実存」のストーリーである。
実を言えば、私自身の問題は、どう修行しようが、何を考えようが、決して解決されないことは、最初からわかっていた。あとは、解決されないから放り出しておくか、それでも考え続けるかである。
私は後者を選んだ。なぜか。この問題は消えない。そして私以外の誰かの問題でもある。釈尊や道元禅師の問題が私の問題であったように。ならば、いかに拙いとはいえ、それを考え続けるサンプルとして、私のような者の存在も、あながち無意味とは言えないのではないか。
道場では、釈尊や道元禅師を供養する法要が定期的に行われる。
入門以来、私はそれらの法要を言われるままに、作法にしたがって、仕事を片付けるがごとく繰り返していた。それが実際だったのである。
修行生活も七、八年を数えた五月のある朝、雨上がりの青葉が冴えていた道元禅師の廟所で、月例の法要があった。
淡く透き通った光が差し込む堂内で、係の修行僧が鳴らす鐘に合せて礼拝をしようとしたそのとき、私の頭に全く突然にある思いが浮かんだ。
「ああ、よかったな。本当によかった」
何がよかったのか。釈尊と道元禅師がかつてこの世にいて、言葉を遺したことである。私はその朝、初めて掛け値なしで仏祖の恩を感じ、まさに「頭が下がる」という文字通りの礼拝をした。
私が考え続けられるのは、彼らの遺した言葉故である。その言葉に自分と同じ問題を発見したが故である。
ならば、私にはもう、問題の解決は必要ではなかった。問題を共有する人間が、かつて確かに存在していたということこそが、救いだったのだ。
これからも、どこかで誰かが、釈尊のように、道元禅師のように、そして私のように、問題を背負うだろう。たとえ解決がつかなくても、考え続けるだろう。
本書での私の非力な論考から、それでも仏教を頼りに考え続けようとしてきた者の、それなりに切実だった胸の裡を察していただければ、望外の幸いである。
-

-
南直哉
禅僧。青森県恐山菩提寺院代(住職代理)、福井県霊泉寺住職。1958年長野県生まれ。84年、出家得度。曹洞宗・永平寺で約20年修行生活をおくり、2005年より恐山へ。2018年、『超越と実存』(新潮社)で小林秀雄賞受賞。著書に『日常生活のなかの禅』(講談社選書メチエ)、『老師と少年』(新潮文庫)、『恐山 死者のいる場所』『苦しくて切ないすべての人たちへ』(新潮新書)などがある。
この記事をシェアする
「南直哉 『超越と実存 「無常」をめぐる仏教史』」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら