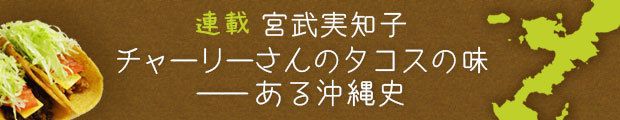(前回までのあらすじ)「チャーリー」こと勝田直志さんは、コザの有名なタコス専門店の創業者。沖縄戦の生き残りでもある。1945年9月に投降し、屋嘉と牧港の捕虜収容所を経て、1946年10月の船で故郷の喜界島へ引き揚げた。

勝田さんが復員した当時の奄美群島は本土から分離され、アメリカ軍の占領下にあって、臨時北部南西諸島政庁(Provisional Government of Northern Ryukyu Islands)という行政機構になっていた。
喜界島の郷土史『喜界町誌』に当時の様子が記されている。
敗戦から半年もたたないうちに、どこからともなく「奄美や沖縄はアメリカの植民地にされるらしい」という噂が流れた。デマだろうと気に止めない人々もいたが、1946(昭和21)年2月2日午前7時のラジオニュースで突然、「北緯30度以南の南西諸島および小笠原諸島などは、日本の行政権から分離される」という衝撃的な発表が流れた。
ラジオも新聞もあまり普及していない終戦後の混乱期、奄美の人々はパニックに陥った。「奄美は永久にアメリカの植民地にされる」、「奄美の将来は英語が共通語になる」、「若い男性はアメリカへ連行されて、強制労働に従事させられる」などの流言飛語が飛び交い、社会不安はいっそう深刻なものとなった。
このような世相におびえて、戦前から奄美に進出していた本土商人の中には、全財産を二束三文で売り払って、あたふたと本土へ引き揚げた人たちもいたという。
一方、青雲の志をいだいて、本土の上級学校へ進学していた奄美出身の学生の中には、親元からの学資が途絶えるのを危惧してか、せっかくの学業を断念して、志半ばで島へ引き揚げて来た人たちもいた。(『喜界町誌』500頁)
この衝撃的な宣言は、布告された日付で「2・2宣言」と呼ばれる。
3月13日、北部南西諸島初代米国海軍軍政官ポール・F・ライリー少佐の一行が奄美大島に上陸。大島の市庁構内の旗が日の丸から星条旗に代わり、4月には通貨の切り換えがおこなわれ、奄美群島は「アメリカ世(ゆー)」となった。
この年の11月に復員した勝田さんが早町(そうまち)村の役場で働き始めたのが、翌1947(昭和22)年5月から。混乱の続く奄美の役場は人手不足で、勝田さんは役場の税務課と食糧係で勤務した。
当時、公務員の月給は安かったが、ほかに仕事もない。働き始めた頃の月給は、B円(米軍発行の軍票)で250円ほど。「3年間で500円くらいに上がったが、その程度だ」と勝田さんはやけによく金額を覚えていた。
偶然にも、『喜界町誌』に当時の勝田さんと同じ早町村役場に勤めていた人の給与額が載っていた。

40歳から50歳代の人の額なので、おそらく勝田さんより高給だろう。昭和22年からわずか6年で給与が9倍近くに上がったことにも驚かされる。B円とドルのレートが1950(昭和25)年4月に変更されたせいもあるが、経済の不安定さについては、奄美の事情は沖縄本島以上に厳しいものだった。
特に飛行場のあった喜界島は空襲が激しく、島の中心となる集落の大半を焼かれた。農作物の栽培もままならないうちに復員軍人をはじめとする人々が次々と帰還する一方で、主食の甘藷に害虫が蔓延。分離された本土からは物資の輸入も自由にできなくなり、未曽有の食糧難に陥った。衣料品をはじめとする物品全般も不足し、闇商人が本土に密航して調達したものが高値で売られていた。
昭和29年までアメリカ占領下にあった奄美では、物資調達のためだけでなく、出稼ぎや進学のために鹿児島へ密航した人もかなりいたらしい。「戦後の奄美は密航が作ったといっても過言ではない」とされ、多くの聞き書きがある。山に囲まれた盆地で育った私にとって「密航」は非現実的な響きだが、奄美の人にとっては日常の延長線上にあったのかもしれない。
奄美ではインフレ抑制のために低物価政策が推進され、公定価格が設定された。違反者には「本群島の経済を破壊し復興を妨害するもの」として罰則が適用される厳しいものだったが、この政策も翌年には廃止。闇商売が横行して統制が機能していなかったためと言われる。
混乱に乗じて密航や闇商売で財を成す人がいる一方、役場の職員は低物価政策の影響を直に受ける。当時は公務員に将来の保証もなく、明るい見通しがない。実業家になってみたい、と勝田さんは夢を膨らませるようになった。
同じような話を、違う人からも聞いたことがある。その人は終戦後、沖縄本島で学校教師になった。その給料がラッキーストライク(通称・赤玉)の1箱と同じ、200円だったという。1ヶ月、一所懸命に働いて、米兵が無造作に吸う煙草1箱。米軍施設で働いている人たちは、その煙草をチップ代わりに入手してくる。「やっていられない」と、その人も教師を辞めて実業家を目指した。
貨幣価値が不安定な地域では、輸入物の嗜好品が通貨の役割を果たすことがある。ソ連崩壊の時期に「マルボロ本位制」が見られたことを、当時モスクワで大使館員だった佐藤優が書いているが、戦後の沖縄はさしずめ「赤玉本位制」だったらしい。「赤玉1箱分」という言い方を、戦後の混乱期を経験した人からよく聞かされる。
そんな頃、勝田さんの隣の家にMさんという男性がアメリカから帰国した。
戦前、船乗りとしてアメリカへ渡り、船に戻らず陸に逃げたという噂だった。戦時中もアメリカにとどまり、何の音沙汰も手紙もないまま20年。突然ふらりと島に帰ってきて、家族さえも仰天した。ボストンあたりで何か事業をしていたらしいが、帰ってきた時は無一文で、日本語も話せなくなっていた。
初めてそのエピソードを聞いた時、浦島太郎のような話にびっくりした。「なぜアメリカへ? 一人で? 何しに? 向こうで何を?」 つい質問攻めにする私に勝田さんは困惑ぎみで、どうも話が噛み合わない。「密航じゃないかね。昔はちょくちょくあったのよ。船員か何かになって行くんじゃないかな。そこはあまり聞いてないのよ」と事もなげに言う。不思議で仕方なかった。
のちに『喜界町誌』で人口の推移を読んでいて、ヒントを得た。江戸時代には1万人前後で推移していた島の人口が、大正期に入る頃、2万人へと倍増。それに伴い、島の外へと出稼ぎに出る者が増えたという。「大正末頃から阪神方面へ、昭和初期頃から東京方面へと島を離れた。中にはアメリカへ移住した人もいる」とある。アメリカへ移住したのは、M氏だけではなかったようだ。
さて、話を戻そう。こうしてアメリカから帰ってきた隣人に、勝田さんは興味をもった。ある時、M氏の話から脱線した勝田さんがぽつりと漏らした。
Mさんは20年ぶり、音沙汰も手紙も何もないから、死んだかどうしたか分からんという話だったですね。で、私なんかも沖縄で生きて、……ほとんどは戦死しておりますからね、生きて帰ると、みんなびっくりするんですよ。当時の喜界島から、私の知り合いだけでも10何名かが沖縄へ行って、生きて帰ったのがたった3名ですから……。
なるほど、と腑に落ちた。私の想像に過ぎないが、同じ「生きて帰ってびっくりされた」者の居心地の悪さと親しみがあったのかもしれない。英語しか話せなくなったM氏を周囲の人が遠巻きにするなかで、勝田さんは収容所で覚えた片言の英語を使って話しかけ仲良くなった。
そのうちM氏が、「自分は何もできないから、沖縄へ行く。向こうで事業を始めてみようと思う」と言い出した。そして、本当に単身で沖縄本島へ渡っていって下調べをして戻り、「また行く。レストランをする」と言った。
勝田さんはM氏に「連れて行ってくれ」と頼みこんだ。勝田さんより先に、兄が大陸から帰還していたので、家は大丈夫だ。役場を辞めるのは勿体ない、良い仕事なのになぜ辞めるか、と止める人もあったが構わなかった。
「でも、沖縄に来ることに抵抗感はなかったんですか?」と尋ねてみた。想像を絶するような地獄を見た沖縄へ、終戦からわずか5年で戻る気になるものだろうか。「だって、当時は軍政下だから内地へは行けないんだよ。沖縄だったら、同じアメリカ統治下だから、わりと簡単に来られたの」。
「アメリカ世」である。戦前のように大阪や東京へ出稼ぎに行く道が断たれ、鹿児島本土に渡ることすらできない。鹿児島と切り離された奄美諸島では、基幹産業の大島紬やサトウキビの生産販売もままならなくなり、経済的に大打撃を受けていた。奄美からは若い人たちが続々と沖縄へ渡っていた。
沖縄本島は奄美と同じ軍政下とはいえ、米軍基地の建設ラッシュで、復興に向かう活気と可能性に満ちていた。そこで米軍相手の商売をすることは、反感や警戒より好奇心や憧れがまさる冒険だったのではないか。勝田さんは収容所でアメリカの豊かさを目の当たりにして「これは負けるのが当たり前だ」と思い、「もう一回、沖縄へ行こう」と心に決めていた。
それだけではない。確かめたいこともあった。
首里の陣地とかね、大砲のあたり、ああいうのを調べてほしかったんですね。ほしかった、というより見たかった。沖縄に来て最初に、首里へ行って、陣地に上がっていって見たんですよ。それで、看護婦だった人、あるいは首里の姉弟ふたりが生きているのに、また会いたいという気持ちもあった。
アメリカの軍人への恨みや憎しみもまったくなかったそうだ。だから、占領下の沖縄へ渡ることにも、米軍相手に飲食業をすることにも、抵抗はなかった。
「もう一つ、沖縄はね、自分が生き返った島だと思った。第二の人生へと、ね」と勝田さんは格好いいことをさらりと言った。「人の真似できないことをやれ」という気持ちもあったそうだ。
そして、貯めた5000円を手に沖縄本島へ渡った。1950年12月のことだった。

-

-
宮武実知子
みやたけみちこ 主婦・文筆業。1972年京都市生まれ。京都大学大学院博士課程単位取得退学(社会学)。日本学術振興会特別研究員(国際日本文化研究センター)などを経て、2008年沖縄移住。訳書にG・L・モッセ『英霊』などがある。「考える人」2015年夏号「ごはんが大事」特集に、本連載のベースとなった「戦後日本の縮図 タコライス」を寄稿。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら