『能 650年続いた仕掛けとは』(新潮新書)の刊行記念イベントとして、著者である能楽師、安田登さんと、『数学する身体』(新潮社)の森田真生さんの対談が、東京のカメリアホールで開催された。「能を数学で、聞く」という顔合わせも内容も異色の対談だが、ふたりは奇妙にも根底で繋がってゆく。200人近い参加者の熱気にあふれた会場の様子を、ふたりを知る哲学者・下西風澄さんにレポートしてもらった。
言葉と歌
かつて、言葉と歌はひとつだった。
古代ギリシアでは、ラプソードスと呼ばれる吟遊詩人が神話を歌い、デュオニソスの神を言祝ぐ祝祭では、熱狂する群衆はきらびやかに仮装し、笛を鳴らし、昼夜にわたって世界と一体化して乱舞した。彼らは詩を歌い、劇を演ずることで、文明を維持するために必要な社会的記憶を血肉化させた。
人間が文字を発明したとき、歌と言葉が別れた。
言葉は「歌われる声」ではなく、「書かれる意味」となったのだ。記憶を頭の外に取り出して保存することができるようになったとき、思考は外在化し、知の形式化が加速した。ソクラテスは偉大な詩人ホメロスの詩に、その「意味」と「根拠」を問い、プラトンがその全てを文字に書き起こしたとき、「哲学」がはじまり、「歌われる言葉」としての詩の魔力は封じられた。経験は韻律と演劇によって記憶されるべきものではなく、検証され思考される対象となった。一心不乱に歌い、踊ることによって世界に「参加する」という人間存在のあり方は文字の登場によって失われ、代わりに言葉によって「私」が「世界」を「認識する」という、人間と世界の新しい関係性のモデルが誕生したのだ。以来、西洋世界では「芸術」と「知」は別々の道を歩むこととなる。
ワーグナーの音楽をこよなく愛したドイツの哲学者ニーチェが、古代ギリシア悲劇の研究から、西洋に眠った知と芸術の合一を掘り起こそうとしたのは19世紀の末である。そしてニーチェは、「わたしは踊ることのできる神だけを信じるだろう」と言ったのである。
能の大成者・世阿弥は身体をもって踊る舞のなかに思想を具現化した。「花は心、種は態(わざ)」(『風姿花伝』)。一粒の種が季節の風に育まれていつしか花を咲かせるように、身体と心は一体として離れない。それが、日本が連綿と紡いできたひとつの思想であり、能はそれを象徴する文化であった。
能楽師が謡い、舞うとき、私たちは、言葉と歌が分かちがたく絡まっていた原始の記憶を想うだろう。能楽師・安田登の語る能の魅惑とは。その秘密を、数学を語る森田真生との対話の中から考えていきたいと思う。

「初心忘るべからず」の本当の意味
「みなさんの多くが能を観たことがないし、観たことがあっても、眠ってしまったのではないですか?」
安田登は対談の冒頭で、こう問いかけた。能はなぜ、一見するとつまらない芸能なのに、650年一度も途切れずに続いてきたのか。その問いこそ、新著『能』で解き明かされるテーマである。
「初心忘るべからず」という世阿弥が伝えた言葉は、「初めての時の気持ちをいつまでも忘れない」という意味だとよく言われるが、その真意は別にあるという。「初」という漢字は「衣」に「刀」と書く。真っ更な布に刀(鋏)を入れて裁ち切ること、新たなステージに差し掛かった時、過去の自分を思い切り裁ち切ること、それが「初心」である。
“折あるごとに古い自己を裁ち切り、新たな自己として生まれ変わらなければならない、そのことを忘れるな”
—安田登『能 650年続いた仕掛けとは』,14頁
能は「伝統芸能」というイメージを強く持つが、その形式は世阿弥の「初心」に従って、幾度となく形を変えている。たとえば安田の新著では、江戸時代までは能の謡のスピードは、現在の2~3倍の速さで、ほとんど現代の「ラップ」にさえ近いものだったという驚くべき事実が語られている。
長い時を経て、その伝統の形式がようやく確立したとき、「初心」という「時限爆弾」のようなものが起動し、伝統は全く新しい姿へと生まれ変わる。能には、誰もが継承できる「伝統」と、それを自ら裁ち切って壊す「初心」の二つがあった。伝統を維持する仕組みのなかに、自ら大きく変化し続ける仕掛けがあったからこそ、能は永く続いてきたのだと安田は語った。
日本と西洋の数学
「日本の数学の大きな変化は、外部から到来した」と森田真生は語る。
明治以前には、「1」「2」「3」と書く算用数字を用いる習慣がなかったため、筆算もできなかった。筆算ができれば「そろばん」がなくても、紙と鉛筆だけで計算ができるのだ。これは当時の日本人にとっては衝撃的なことだった。

明治以前に発達した日本の数学は「和算」と呼ばれる。そこでは様々な「特殊算」が愛好された。たとえば「鶴亀算」では、「鶴と亀を数える」という特殊な状況に寄り添った計算手続きを学ぶが、西洋数学では同じ問題を連立方程式によって解く。連立方程式による解法は、鶴亀算以外の様々な場面でも使える普遍的な問題解決の手続きである。逆に言えば、私たちは方程式を使うとき「計算の意味を忘れても、正しく計算ができる」。アルゴリズムに従った機械的な操作で計算ができるようになるのだ。
数式という新しい道具を手にした私たちは、意味を切り離して有用な計算を実行できるようになった。その究極の形式がコンピュータであると言っていい。コンピュータは、実際には何も考えていなかったとしても、外から見ると知的に振る舞っているとみなすことができる。
数学を通して普遍性を追究してきた西洋でコンピュータが生まれた。しかし、日本が西洋数学を知ったのは、たった150年ほど前である。「いったい、日本の風土と思想のなかで、どんな数学が可能なのか?」。著書『数学する身体』で森田は、この問いを真剣に受け止めた日本の数学者、岡潔に注目した。
「論理も計算もない数学」を夢見た岡潔は、日本の数学に思想的な「根」を与えなければならないと考えて、道元や芭蕉、夏目漱石を読んだ。いかにして伝統を紡ぎながら、自身で新たな方法を作っていけるのだろうか。そのヒントが安田の新著に隠されているのではないかと思ったと森田はいう。
人間を変える「能」
能が続いてきた理由として、能は「はまる」と脱け出せない人が多いのではないか、と安田は推測する。例えば、謡を習っていた夏目漱石も、最初は能を小馬鹿にしていた節があるが、ある時期からだんだんとのめり込んでいって、小説『草枕』では物語全体がまるで能の「夢幻能」の構造として読めるほど影響を受けていったという。
650年という長い歴史のあいだには、能の伝統が途絶えそうになる危機もあった。長らく能をパトロンとして支えていた江戸の大名達が力を失い、終いには最大の支援者たる幕府が倒れ、明治に突入した時期は危機の一つだった。しかし能楽師はそれでも能が大好きだったため、能を辞めてしまうどころか、その辺の橋のたもとで謡(能の詞章部分)を謡ったという。「能をいったん覚えると、後戻りできないくらい別の人間になってしまうのではないか」。自ら能を舞い、また多くのワークショップで能を教えてきた安田はそう実感していると話す。
ここに、能の特異性があるのかもしれない。たとえば、「映画」は監督が作りこんだ世界を観客は受け入れる。しかし、能の舞台背景には一本の松しか描かれていないにもかかわらず、能を観る者はここにありとあらゆる景色を読み込む。いわば、脳内でAR(オーギュメンテッドリアリティ:拡張現実)を発動させている。能を覚えてしまった人間は、知覚レベルでの強力な変容をこうむるのだ。
これは、実際のAR技術とも異なる。ARはデバイスをつければ誰でも映像を観ることができるし、全員が同じ映像を観ることができる。これはいわば、人間を「心がない存在」として考えているメディアだと言える。しかし、能は人間が仮想的な現実を自ら立ち上げる「心のある存在」として捉え、自身で映像が見えるようになるまで、すなわちその人間が変容するまで訓練(稽古)を求めるのだ。「だから、能をほんとうに楽しもうと思ったら、「能を分かる」のではなく、「能と共に生きる」ことが必要なのです」と、安田は熱く語った。

「メディア」としての能
森田は『能』を読んで、まさに能とは「人間を変えるメディア」だと思ったと応えた。単に能の知識が書かれているのではなく、読み進めると能を自分自身でも習って謡いたくなるように書かれているし、実際に能を始めるための手引として師匠の選び方から月謝についてまで書いてあって、「安田さんは本気だ(笑)」と感じたという。
「メディアとは本来、人間を変えるものです」と森田は話す。たとえば、「文字」というメディアも、喋っていることを単に文字に置き換えているのならばつまらない。文字ができたことで、話し言葉によっては不可能な、抽象的な思考を可能にするように人間が変化した。つまり、文字の登場によって人間が別種の存在になってしまったことが、文字というメディアの偉大さだった。
パーソナル・コンピュータの父、アラン・ケイは現代のスマホ社会を見てがっかりしている、というエピソードを森田は紹介した。文字も書けるし映像も見られる、ゲームもできる。赤ちゃんからおじいちゃんまで使えるこの新しいメディアは、しかし人間を本質的には変えていない。コンピュータというメディアの本質を「メタ・メディア」、すなわち「メディアをつくるメディア」だと考えた彼は納得しなかったのだ。アラン・ケイの要求するメディアのレベルは高い。しかし、本来のメディアの意味を考えれば、コンピュータという新しいメディアが登場したならば、人間が別物にならなければいけない。
ここにも能に学ぶところがある。お客さんに高い要求をしながらも、能を観る人間を変えてしまう。その秘訣が能の伝統にあるのなら、「メディアがあまりにも人間に寄り添って優しくなってしまった現代にも、その潜在的な可能性を問い直すヒントがある」。そう森田は解釈し、能の伝統から現代のメディア環境にまで及ぶ視点を投げかけた。
(「後編」へ続く)
(撮影・新潮社写真部 佐藤慎吾)

-
安田登/著
2017/9/15発売
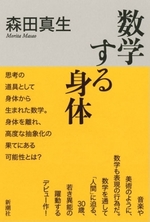
-
森田真生/著
2015/10/19発売
-

-
下西風澄
しもにし・かぜと 1986年生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学。哲学や文学を中心に、研究と文筆活動を行う。主な論文・執筆に「生命と意識の行為論」(『情報学研究:学環』,2015)、「色彩のゲーテ」(『ちくま』2014年8-10月号)、「文学のなかの生命」(『みんなのミシマガジン』連載中)、「詩編:風さえ私をよけるのに」(『GATEWAY 2016 01』)など。kazeto.jp
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら





