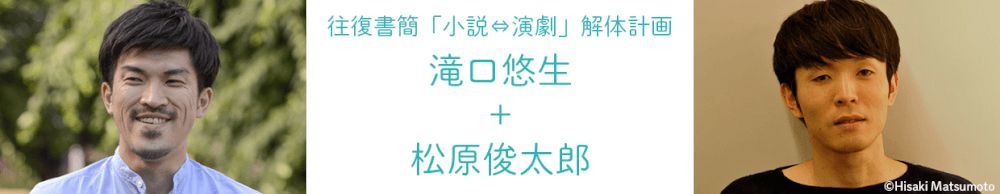滝口悠生→松原俊太郎
こんにちは。11月の半ばに日本に帰ってきました。自分でも驚くほどあっという間に日本の感覚が戻ってきてしまい、むしろアメリカにいた3か月がすでに夢のなかの出来事のような感じがします。カレンダーを見ればもうすぐ年末ではないですか。日本を出た8月はひどい暑さだったのに、戻ってみると秋で、冬もすぐそこ、時間が過ぎるのは早いし移動というのは不思議なものですね……と、旅のあとというのはどうして凡庸なことばかり言いたくなるのでしょうか。
さて、前々回僕が書いた、演劇の観客を戯曲の読み手として考えたときに、「観客は戯曲の読み手としての足場を奪われ、観客席にとじこめられ、戯曲と上演=書き手と読み手の関係が舞台上に現れるのを観る」というところに触れて、松原さんは「これが常態化しているのであればもう演劇なんて観に行きたくないと思ってしまいますね……」と書いていましたが、僕としてはネガティブな意味で書いたわけではなかったので、少し齟齬があるかもしれません。
僕が言いたかったのは、戯曲に対して主体的な読みを一旦舞台(上演)に預けることで、自分の読みとは違う可能性を目撃する・経験することができる、というようなことです。第3回で「わからない」ということについて(というか「わかる」ことの退屈さについて)松原さんが、
「わかる」というのは自分のすでに持っている基準との照らし合わせでなされることで、その基準が通用しない、揺らぐ「わからない」ものが訪れて、そこでこそ思考が始まる。
と書かれていたことに通じると思います。同じところで、
安定した状態とは考えずに済む状態とも言えて(中略)すぐに飽きがやってくるように思います。
とも書いていましたね。読み手たる観客にとって、退屈な上演とは〈既にわかっている読みの提示〉と言えるのではないでしょうか。戯曲という上演を前提とした形式のテキストは、観客にとって、やはり常に上演の向こう側にあるように思います。そして松原さんが前回書いていた、戯曲を読むことで「別の上演を経験することができる」というのは、観客が上演の向こう側にあるものをこちら側に引き寄せて読むことなのではないかと思いました。
僕は前にラジオのチューニングとか耳抜きを例にあげて、小説の語りは声を発するというよりも誰かの声を聞こうとすることなのではないか、というようなことを書きました(第4回)。それは小説の書き手が(つまり僕が)どうやって小説の文章を書くか、という文脈での話でしたが、たぶん僕は小説の文章が単純に語り手の声であると考えることに抵抗があるのだと思います。といって、それはもちろん書き手の声でもない。じゃあなんなのか。僕にもなんだかよくわかりません。が、先の上演と戯曲と観客の関係について考えながら、それを小説に重ねてみると、もしかしたら語り手と書き手の関係を、戯曲と上演の関係のように考えることができるのでは? と思いました。
小説の語りとは誰かの声を聞こうとするようなことなのではないか、というアイデアは書き手である僕のもので、たぶん語り手のものではありません。僕は、松原さんがたびたび用いる「異化」という言葉を借りて「書き手であると同時に、仮想的に語り手として異化される」とも書いていました。これもあらためて読むとなんとなく演劇めいています。
僕は、自作について書き手である自分がどういう位置にあるのか、「書き手である」という以上にうまく説明する言葉を持っていません。どんな小説でも、書き手は紛れもなく存在するわけですが、作品が読まれるときに書き手はどこにいるのかがよくわからない。このわからなさは、僕が戯曲を読むことについて考える時に、上演から離れられない感覚と似ています。松原さんはすでにそういう感覚をお持ちだったかもしれませんが、僕にとってはこの書き手=上演という見立てはちょっと新鮮でした。
で、観客の位置に入るのが小説においては読み手になるわけですが、舞台も上演もない小説においては、読み手は書き手をスルーして語り手の言葉を読むことができる……でしょうか? 戯曲と小説とでその「読み」がどう違うか、という話もこれまで何度も出てきてはいますが、ここで僕はもう一度声について考えてみたいです。戯曲を読むことは、松原さんの言葉を借りれば「別の上演を経験する」ことで、その上演とはおそらく実際の上演と同様に音声を伴う、音声が聞こえるものなのではないかと思います。もちろんそれは仮想的な音声ですが、松原さんも書かれていたとおり、やはり戯曲のセリフは発声されることを前提にしており、それを読む時にもその文章は発声されるものとして読まれるし、読み手は、その声を聞こうとします。そして戯曲はその大部分がセリフによってできています。
一方、小説を先の見立て(書き手=上演)に当てはめれば、読み手は「別の書き手を経験する」ということになります。少し言い換えれば、書くように読む、ということかもしれません。そこにはたぶん、音声は伴わない。僕の考えでは、書き手は語り手の声に耳をすませるのであって、読み手が書き手を経験する(書くように読む)のであれば、読み手もまた語り手の声に耳をすませることになる。なら音声があるじゃん、と思われるかもしれませんが、この声はたぶん、戯曲の、演劇の発声とはやっぱり違うと思う。ひとりごととか、内心での呟きとか、物理的な音声であることが重要ではない声。だから声とは言わない方がいいのかもしれない。誰かが、どこかに向かって、言葉を用いて、何かを説明しようとすること。僕が考えている小説の語りは、そのようなものなのではないかと思います。たぶん大事なのは、「説明している」ではなくて「説明しようとする」であるところで、それはまだ音声ではない。だから、たぶん、小説を読んでいるときに読み手が聞こうとする声、読み手に聞こえてくる声というのは、声になる前というか、語ろうとする意志というか、これから語られる声というか、そういう未然的なものなのではないか。
これも前に松原さんが、「劇を観ているときに、言葉、あるいは声が「聞こえてくる」というこの経験自体が、掛け値なしのものだと思っています」と書かれていました(第3回)。この「聞こえてくる」経験について、僕はうまく捉えきれずやや棚上げしてしまったのですが、やはりちゃんと考える必要がある。この「聞こえてくる」ものは、どの時間から聞こえてくるのでしょうか。
小説には、戯曲にはない「地の文」があり、「描写」があります。これはふつう発声されない文章たちです。そして、小説の語りには上に書いたように未然の意志、未然の声がある。ならばそれは現在から未来へと向けられるのかといえば、それは違って、小説の語りは基本的に過去の時制に属していると僕は思います。なぜなら書き手がいるから。語りと読み手のあいだに書き手が噛むことで、すべての言葉が過去に送り込まれる、たぶん。読み手が聞く声も過去における未然であり、意志であると思います。
では、戯曲は、演劇はどうでしょうか? ここに小説との違いがあるのではないか。僕が自作(「高架線」)の演劇を見て、同じ言葉なのに全然違う、と感じたその違いも、今回書いたようなことがベースにあったのではないかと思っています。
11月28日 滝口悠生
『演劇計画Ⅱ -戯曲創作-』
委嘱劇作家:松原俊太郎、山本健介(The end of company ジエン社)
演劇計画Ⅱアーカイブウェブサイト http://engekikeikaku2.kac.or.jp/
京都芸術センター http://www.kac.or.jp/
演劇計画Ⅱ -戯曲創作- 関連企画 松元悠『カオラマ』
松原俊太郎の創作中の新作戯曲『カオラマ』の第一稿・第二稿を基に、リトグラフ作家の松元悠が作品を創作・展示します。
日時:2018年12月13日 (木)-2019年1月6日 (日) 10:00-20:00
※2018年12月26日(水)~2019年1月4日(金)は休館
会場:京都芸術センター ギャラリー北・南
戯曲:松原俊太郎『カオラマ』(第一稿・第二稿)
展示:松元悠(リトグラフ作家)
http://www.kac.or.jp/24664/
-

-
滝口悠生
1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。
-

-
松原俊太郎
作家。1988年熊本生まれ。2015年、処女戯曲「みちゆき」で第15回AAF戯曲賞大賞受賞。2019年、『山山』で第63回岸田國士戯曲賞受賞。他の作品に戯曲「忘れる日本人」、「正面に気をつけろ」(単行本『山山』所収)、小説「またのために」など。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 滝口悠生
-
1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら