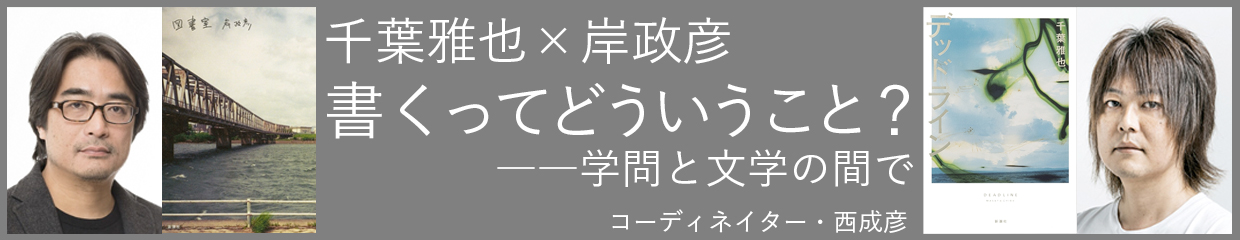文章に滲み出る自我
西 我々三人は、立命館大学の先端総合学術研究科で教員をしています。ここは火山が海底から噴き出すように2003年に生まれた大学院で、分野ごとのディシプリンに縛られることなく相互に行き来しながら、21世紀にふさわしい知の体系を作ることを目指している。私はその初期からのメンバーで、2012年に千葉さん、17年には岸さんが着任し、同僚となりました。先端研には文学を専門とする学生も一定数いて、私は比較文学者の立場から指導にあたってきましたが、哲学や社会学を究めたお二人がいらしたことで文章表現の上でも新たな環境ができつつあります。
これまで作家を志す人は、古今東西の名作を読み尽くし、先行作品を踏まえて自らの文学を立ち上げようとするタイプが多かった。しかしお二人の場合は必ずしもそうではありません。学問を通して世界に触れ、言葉の力でこの世界の在り方を少しでも変えようと思ったときに、上から相手を説伏するのではなく、小説という形で下から自然と文章が湧き上がってきた。そのような流れで、それぞれがいま作家としても頭角を現しておられるのだと私は捉えています。
千葉さんは先日、初小説『デッドライン』で野間文芸新人賞を受賞されました。まずはこの小説にたどり着いた経緯から話を始めていただきましょうか。
千葉 そもそも僕は、文章を書くようになったきっかけが高校時代に愛読していた稲垣足穂にあるんですね。足穂はエッセイみたいなものだったり、小説みたいなものだったり、あるいは詩みたいなものだったり、その時々の都合で様々な形式の原稿を書き散らした人で、僕はそうした自由な書き方に憧れてきた。大学に入ると実は足穂のような文章は本当には知的だと見なされていないことが分かり、きちんとした論文を書くという通過儀礼を経ましたが、30歳前後から自分自身も依頼を受けて文章を書くようになって、次第に物語的な書き方にも挑戦してみたくなってきたんです。
もともと僕の哲学的エッセイには小噺のような要素があって、例えばある原稿では新宿二丁目に実在するラーメン屋でのエピソードを使ったこともある。そうした抽象的な思考とゴロっとした具体性が隣り合わせになったスタイルで書いてきて、後者の方を膨らませていったら小説になるかもしれないという考えもありました。ですから、今回初めて小説を書いたといっても、自分としてはいままでの仕事と繋がっているという意識が強いんです。岸さんはどうですか?
岸 僕が小説を書くようになったのは、これはもうそこらじゅうで喋ってることですが、ある編集者に熱心に依頼されたからなんです。スティーヴン・キングやカート・ヴォネガットは好きだったけど文学なんて全然まったく読んでいない、興味すらなかった自分に、そのひとは「小説を書いてほしい」と言ってきて。三年がかりで口説かれてさすがに根負けし、そこまで言うなら書いてみましょうか、と自分なりのホラー・ファンタジーSFの構想を話したら、まさかの反応ゼロだった。「向いてないです」と一蹴されて(笑)。
編集さんからは「むしろ自分自身の話を書いてください」と言われ、人生で一番つらかった日雇いで建築労働者をしていた時期のことを思い出して3~4日で書いたのが、「ビニール傘」という短篇です。この作品がたまたま芥川賞の候補になり、二作目の「背中の月」とあわせた単行本が今度は三島賞の候補にもなったんですね。まあ、落ちましたけど。ちなみにそのあと書いた「図書室」という小説も三島賞候補になって、これも落ちてます。
西 お二人とも最初から小説を書こうとは思っていなかったのかもしれませんが、形式ばった論文とは違う、崩した書き方に取り組む中で、いろんな文体を試みてきたわけじゃないですか。そこから実際に小説としての文章を書くにあたっては、どれくらいの距離を感じました?
千葉 そういう意味では、「ビニール傘」の前に書かれた岸さんの『断片的なものの社会学』は、出だしのところなど既にかなり小説に近い印象を受けました。
岸 確かにそれは当時よく言われましたね。ただ、本人としては全然そのつもりはなく、あの本に入っているのは普段飲み会で話してるような絶対受けるネタだったり、自分のブログで書いたりしてきたことだった。僕なりに感じてきた世界の美しさを、ばらばらに横たわるような文章で表現できないかなと思って。そしたら友人の星野智幸さんや雨宮まみさんから、「これはすぐ小説になる」と言われて驚きました。
でも面白いことに、さっき話に出した小説執筆を勧めてきた編集さんは、僕が2013年に最初の本『同化と他者化』を出した直後にはもうそのオファーをしてきてるんですよね。沖縄の本土就職者について調査して書いた、非常に地味な社会学の学術的な本なのに。あとからそのことについて、どうしてあんな文学から一番遠い本を読んで小説が書けると思ったんやと聞いたら、「文章にどこか過剰なものがあった」と言うんです。自分としてはオーソドックスな社会学の本を書いていたつもりなんだけど、そこに書き手の自我が滲み出ていて、こいつは絶対小説を書けるに違いない、と確信したと。
そういえば千葉さんと最初に会ったときにも、小説を書くかどうかという話になったよね。
千葉 岸さんがベースをやっているジャズトリオのライブが大阪の十三であって、そこに僕が遊びに行ったんですよね。ライブの後に自分もちょっとピアノを弾かせてもらいました。そのあと一緒に、近くの羊肉を出す串焼き屋へ飲みに行ったんじゃなかったでしたっけ。
岸 初めて会う僕に対して千葉さんは、「ドナルド・デイヴィッドソンみたいな分析哲学的なアプローチで自分の社会学を基礎づけるのは、向いてないからやめた方がいい」って、はっきり言ってきたのを憶えてます(笑)。でも、そのあと真顔になって、「小説を書いた方がいいですよ」と。
千葉 そしたら岸さんは「いや、実は前からそういう話はあるんだけど、自分はやっぱり社会学の人間やから……」と、ごにょごにょ言ってごまかしていた。いまはもう、小説を書くのが楽しくて仕方ないという感じになっちゃってますが。
岸 なってへん(笑)。実際に書いてみたら一作では済まない感じになっちゃって、泥沼にはまってるけど。
千葉 ともかく、十三で会ってから程なくして岸さんが「ビニール傘」を発表し、僕はついに出たな、と思ったんです。
比較文学者の分析手法
岸 今日の話の大きなテーマでもあるんですけど、僕ら二人とも、「研究と創作ではアプローチの仕方が違うんですか?」とよく聞かれるじゃないですか。いつもこういう質問をされるたびに困るんですが、千葉さんならなんて答えます?
千葉 僕はあまり違わない、と言いますね。もちろん、まったく同じだということはないですよ。論文だったら、きっちり下調べをしてから書くわけで。でも、アイディアをメモ書きして、それをベースに執筆するという基本的なプロセス自体は変わらない。
西 ただ、読者として読んでいて、そうは言ってもやっぱり違うなと思うのは、小説の場合は文章がぶつ切りになってできた隙間が逆に芸になったりするんですよね。そこは哲学や理論的な文章とは大きく異なる部分です。千葉さんの『デッドライン』の場合、一作の中でいくつかの文体がグラデーションをなしていて、途中で切断されたりもする。そのことが小気味よい読後感を与えているような気がします。
千葉 なるほど。しかし断片性ということで言うと、もともと僕の哲学的な文章は普通の研究者の論文と比べて、飛躍が多いタイプの論の運び方をしているとは思います。
岸 ちなみに西さんは文学研究者の立場から、『デッドライン』をどのように論じますか?
西 ちょっと身も蓋もない言い方になってしまうけど、文学研究者がいかにダサいかということの一例として作品を分析してみましょうか。千葉さんも僕も地方出身者で、高校までを地元で過ごしてから東京の大学へ進学したわけですよね。したがって『デッドライン』を読めば自分も同じように上京したばかりの時代のことを思い出すし、文学に関わっている以上、実際にその作者が影響を受けたかどうかは別にして、既存の型に当てはめて作品を読んでいくことになる。
『デッドライン』が優れて現代的な作品であることを抜きにして形だけを見ると、これは夏目漱石の『三四郎』と相似形なんですよ。ただし、三四郎が東京帝大で勉強しながら性愛の方へは手を伸ばせず、広田先生の威圧感の下でもがいていたとすれば、『デッドライン』の主人公はハッテン場に出入りし、非常に奔放な生活を送っている。だから、まずはその差を楽しみました。
僕はかつて多和田葉子さんの作品を論じるときに、これは森鴎外の『舞姫』の男女逆転版だと書いたことがあるんですね。ドイツへ留学して言語を習得した日本人が、ヨーロッパをさまようという物語の骨格は共通していますから。同じ型に当てはめて作品を見ていき、なぜこれだけ違う印象を与えるのかと考えると、個々の作品のオリジナリティが浮かび上がってくる。それが比較文学者の分析手法です。
岸 つまり、『デッドライン』も昔からある普遍的な問題を扱っているということになると思うんですが、では近代文学の描かれ方とは具体的にどこが違ったんでしょうか。
西 『三四郎』との比較で言うなら、実家との関わり方、同世代の同性・異性との関係、東京という土地への目くるめく感覚というのが、重なるところもありつつ、漱石と百年後の千葉さんとでは全然違いますよね。主人公が環八を車でぶっ飛ばすところなんて、すごくいいじゃない。
岸 逆に千葉さんがこの作品に取り組むにあたって、何か意識した先行作品はあったんですか。それとも完全に自分の中から湧き上がってきた文章だけで書いた?
千葉 影響を受けた作品はあるにはあって、ちょっと意外に思われるかもしれないですけど、草稿段階ではかなりサミュエル・ベケットを意識していたんです。ベケットが晩年に書いた小説、『見ちがい言いちがい』や『いざ最悪の方へ』を見ながら、短いパッセージで同じようなことがずっと続くのは面白いなと。いざ自分が小説を書くとなったとき、意識的に書こうと頑張っても多分難しいので、非人称的に「書けちゃう状態」を作り出せないかなと思っていて、ベケットのどこか機械的な感じを参考にしました。機械的あるいは自動生成的な感じというか。
西 『デッドライン』という作品がベケットのような引っかかる感じを意図的に作っているのはよく分かる。冒頭で唐突に出てきた、ドトールでジャーマンドックを食べていたら舌を噛んでしまった、というエピソードとか。
岸 いま千葉さんが「書けちゃう状態」を意図的に作ろうとしたと言ったけど、なぜ文章が書けるんだろう、ということは僕も前からずっと考え続けている問題なんです。書くってどういうことなんかな、と。学部生のときにウィトゲンシュタインを読んでいて、ざっくり言うと彼は、規則に従った行為はどこから出てくるのか、という問いを立てていた。それで、規則と行為の話を自分なりに音楽に置き換えてみると、ジャズのベースは基本的にアドリブ演奏で、コード進行だけが決まっているんです。あるコードのトーナリティ(調性)の中であれば、どの音を使ってもいいわけ。で、大体ルート(基準音)から弾き始めるんだけど、その次にどんな音を出すのかは自分でもよく分からないんですね。例えば最初はB♭を弾いて、次はCを弾いて、Dを弾いて、最後はFという形で移っていったとしても、はじめからラストはFの音で決めようと思って弾いてるんじゃないんですよ。だから演奏するときの楽器との関係はいわゆる中動態というか、身体が独特の状態になる。
同じように文章にしても、「あ」という文字を書いたから次は「か」を書こうとか、その都度意識的に判断しているわけではないですよね。あくまで書いている主体は自分なんだけど、文章が自然と出てくる、「書けちゃう」ような感覚がある。なので、いつも不思議になるんです。『デッドライン』は千葉さん自身の実体験がかなり入った私小説と言うこともできるでしょうが、中にはフィクションの部分も当然あるはずです。僕の小説にしてもそう。小説の中で架空のひとが出てきて架空のことをしているという嘘のエピソードを書くときに、いったい自分は何をしているんだろうと思います。
千葉 よく分かります。お互いいろいろと実感があると思うんですが、僕は文章を書くときはいつも、じかに何かを規定するわけではない間接的なフレームやルールを設定するんです。完全にフリーの状態だと、かえって何もできなくなるじゃないですか。僕の場合、たまにピアノの即興演奏をやるわけですけど、タモリがよくネタにする「誰でもチック・コリア」というテクニックがありますよね。ピアノを白鍵だけを使って気持ちを込めて弾けば、あたかもチック・コリアの演奏のように聞こえるという。「白鍵を弾きましょう」という指示だと自由に聞こえるかもしれないですが、ここで重要なのは「絶対に黒鍵を弾かない」という禁止の方です。これもひとつの制約で、その中で初めて表現できることがある。
(第2回につづく)
コーディネイター:西成彦(にし・まさひこ)
1955年生まれ。比較文学者。立命館大学先端総合学術研究科名誉教授。 主な著書に『ラフカディオ・ハーンの耳』『森のゲリラ 宮沢賢治』『耳の悦楽』『外地巡礼―「越境的」日本語文学論』など。
-

-
千葉雅也
ちば・まさや 1978年栃木県生まれ。東京大学教養学部卒業。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士課程修了。博士(学術)。立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。著書に『動きすぎてはいけない――ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』『勉強の哲学――来たるべきバカのために』『意味がない無意味』『アメリカ紀行』など。『デッドライン』が初の小説作品となる。
-

-
岸政彦
1967年生まれ。社会学者。著書に『同化と他者化─戦後沖縄の本土就職者たち』『街の人生』『断片的なものの社会学』(紀伊國屋じんぶん大賞2016受賞)『愛と欲望の雑談』(雨宮まみとの共著)『質的社会調査の方法─他者の合理性の理解社会学』(石岡丈昇、丸山里美との共著)『ビニール傘』(第156回芥川賞候補作)『図書室』など。最新刊は『リリアン』(2/25発売)。
この記事をシェアする
「千葉雅也×岸政彦「書くってどういうこと?――学問と文学の間で」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 千葉雅也
-
ちば・まさや 1978年栃木県生まれ。東京大学教養学部卒業。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士課程修了。博士(学術)。立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。著書に『動きすぎてはいけない――ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』『勉強の哲学――来たるべきバカのために』『意味がない無意味』『アメリカ紀行』など。『デッドライン』が初の小説作品となる。
対談・インタビュー一覧
-

- 岸政彦
-
1967年生まれ。社会学者。著書に『同化と他者化─戦後沖縄の本土就職者たち』『街の人生』『断片的なものの社会学』(紀伊國屋じんぶん大賞2016受賞)『愛と欲望の雑談』(雨宮まみとの共著)『質的社会調査の方法─他者の合理性の理解社会学』(石岡丈昇、丸山里美との共著)『ビニール傘』(第156回芥川賞候補作)『図書室』など。最新刊は『リリアン』(2/25発売)。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら