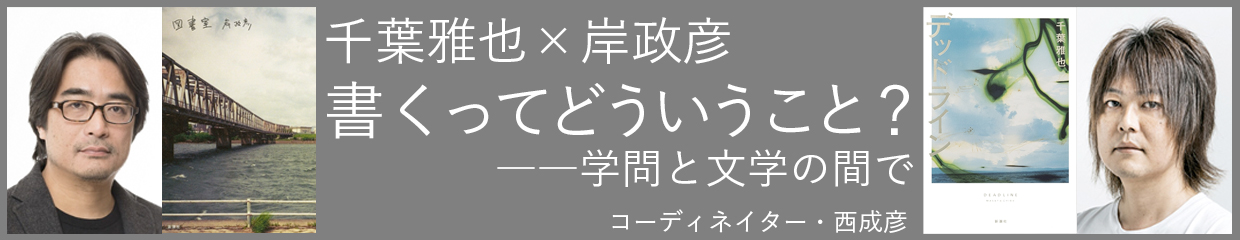(前回の記事へ)
中間の秩序をどう作るか
千葉 僕は普段からツイッターで細かな気付きをメモし、それをもとに執筆に取り掛かることが多いのですが、ひとつのツイートの字数が上限140字に制限されていることが書きやすさをもたらしてくれる要因になっている。これもフレームの一種だと思うんです。事実や取材に基づいて執筆することもそうですね。何もない白紙の状態でいまから自由に書きますよ、と意気込んでもなかなか上手くいかない。書くための技法として捉えると、有限の字数設定をすることと具体的な土地について書くんだと問題設定することは、よく似ている。だから実話ベースって書きやすいんですよ。
岸 確かに僕も、小説の中でこれは完全にフィクションのエピソードやなと思って書いているとき、自分が何か意図的に話を作っているというより、そのエピソードに従って書き写しているという感覚の方が近いかもしれない。こちらは流れてくるものを書き留めているに過ぎない、というか。
西 文章を書くときに、ペースメーカーのような存在が自分の少し前を走っているという感じですか?
岸 そうそう。ウィトゲンシュタインが言っているのは、完全に恣意的な表現は実はなかなか難しいということです。なぜかと言うと、僕らの頭の中には既に文法構造がインプットされているから。人間というのは誰しも、ある言語の中に生まれ落ちるわけですよね。そうすると、言葉を使いだした瞬間からその言語が持つ文法の中で思考するわけで、日本語なら日本語の五十音をランダムに使って完全に自由な表現ができるかというと、実はできない。既に存在する規則に従う方がはるかに簡単なんですよ。ベースの話に繋げて言うと、ミクロな個々の音とマクロな曲のメロディーの中間にはコード進行があって、これが重要なんです。
千葉 まさにコード進行というのは中間の秩序ですね。
岸 さっき千葉さんが説明していたのも、中間の秩序をどう作るかという話で。何か書くときはいつも最初に、ひとつのエピソードを語ろうという心構えをするじゃないですか。その構えをすることによって、文章が自動的に出てくることがある。ここで急に学生さん向けの話になるけど、論文も一緒なんです。僕はゼミの指導で、もうしつこいくらいに問題設定とそのストーリーを作りなさい、と言っている。みんな個々のデータと社会に対するマクロな関心は持っているのに、その両者を接続する中間の物語を作れる人は意外と少ないんですね。
千葉 そう、中規模構造が大事。書店に行くと小説を書くための技法をまとめた本がいろいろとあるじゃないですか。起承転結の展開とか、キャラクター設定の作り方を教えるような。例えば大塚英志さんは、いくつかのパターンが書かれたタロットカードみたいなものを使うプロット作成法を提案しています。小説を書くときにわざわざタロットカードを引くなんて、と不思議に思うかもしれませんが、なぜそれが意味を持つかというと、繰り返すように選択肢の制約を作るためなんですよね。すごく極端な言い方をすれば、どこかの地域に入って真面目に調査しデータを集めて書くことと、任意のタロットカード一枚を参考にして書くことも、原理的に同じなんです。
岸 一緒のことですよね。僕は『マンゴーと手榴弾』という本で、コミットメントという言葉を使いながら一部のポストモダン的な社会学の手法を批判しました。構築主義の立場を取る社会学者は往々にして、人々の語りをストーリーの方に還元していくわけです。「これはあくまでナラティブであり、語り直しに過ぎない。しかし現実はたくさんあるんです」という形で。でも、実際に現場に入って調査してみると、我々に話をしてくれる人たちが取りえた選択肢は、意外と少ないんですよ。そして沖縄戦について語られたことを聞いてしまった以上は、語りをその通り忠実に書かないといけない。
僕の場合、調査対象である沖縄と二十五年間にわたって密なやり取りをしてきたわけですが、関係性の蓄積は自分にとって制約の方向に働きます。だから、ナイチャー(本土のひと)とウチナーンチュ(沖縄のひと)の壁は絶対に越えられないことを思い知ったりもするし、当事者性に対するこだわりがものすごくある。以前、同じ社会学者の稲葉振一郎さんからは「岸さんには他者というオブセッションがある」という指摘をされて、上手いこと言うなあと思いました。
また『デッドライン』の話に戻ると、この作品は非常に爽やかな青春小説として読めるんですが、主人公がセクシャルマイノリティーであることや論文が書けなくなっちゃうこと、あるいは父親の会社が傾いて実家の家計が破綻していくといった条件は、すべて彼の未来の選択肢を狭めていく方向に働くわけですね。その制約の中でドラマが発生して、最後に出てくるオカンの一言でみんな泣く(笑)。
千葉 ああ、言われてみれば確かにそうです。さっき僕が話していたのは書き始めに何らかの縛りが必要だということだったけど、ストーリーの展開にも制約が関係している。
岸 だから作品を重ねるほど、書かざるを得ないことしか書けなくなってくるんでしょうね。僕は三作目の小説「図書室」では、ちょっとかわいらしい話を書きたかったんです。自分自身には子供はできなかったけども昔から子供が好きなんで、小学生の物語にしようと。でも、いま書いている四作目の小説はまた「ビニール傘」に戻ったような、果てしなく暗い話なんです。大阪市の南の隅っこにある、我孫子町という下町のどん詰まりのようなところで、大きな出来事は何も起きずにずっと雨が降っているという……。
西 そういえば岸さんの小説には、いつも雨が降っているような印象がありますね。
岸 昔から水が好きなんです。だから小説では海や川もよく描いていて。でも、考えてみれば天候や空気も、僕にとっては一種の制約ですね。もちろん、カラッと晴れた空の下で「わーい、楽しいなあ」と盛り上がるような場面に興味はないけど(笑)。ひたすら雨が降り続いて行き場もないジメジメした状況下で、この二人はどんな会話をするんだろうと想像することが、実は書く上でのエンジンになっている。
小説は「社会学以前」の表現
岸 千葉さんに、『デッドライン』の技法についてちょっと細かな話を聞きたいんですが、物語の佳境に差し掛かったところで、主人公が女友達の知子に電話を掛けるじゃないですか。知子は電話で話しながら自分の部屋の冷蔵庫を開けて、ブロッコリーを腐らせかけていたことに気づく。そのことが突然、彼女の視点から描かれます。もちろんわざとそう書いたと思うんだけど、ここにはどんな意図を込めたんですか?
千葉 いや、正直こういう言い方をしてよいのか分からないものの、僕としては多くのひとがその部分を読んでギョッとしたということが意外だったんですよ。あそこで使った人称の移動は「移人称」と言われたりもして、本来なら主人公の一人称に固定されてきた視点からは知りえないはずの情報が書かれているからおかしい、というわけですよね。
でも僕にとっては、ああやって主人公が疑似的に幽体離脱し、見えないところのものが見える、というような感覚には実はあまり違和感がない。映像表現だったら、電話のシーンで相手の部屋にショットが切り変わるのは普通にあることですしね。なので最初は主人公と知子との分身関係を他の部分でも描いていたんですが、編集者と原稿の読み合わせをする中で「読者が混乱するから、ここでの表現を際立たせるためにも使いどころは限定した方がいい」と言われて、いろいろと削ってあの場面に絞ったんです。
岸 僕はいっそ、あそこのシークエンス全体が知子との人称の入れ替わりを中心にして書かれるか、反対にあえて言えば、入れ替わりの描写自体がなくてもよかったのかなとすら思ったんですよ。それくらい衝撃を受けたんです。ある意味、『デッドライン』の中で一番感動したポイントでもある。ストーリーの制約のもとで展開する端正な青春小説から、あそこだけ書いている千葉さん自身が出てくる気がするんだよね。「どうも、先端研の副研究科長の千葉雅也です」みたいな感じで(笑)。
技法ということで言えば、僕の「ビニール傘」にもよく勘違いされることがあるんです。あの作品の第一部はたくさんの「俺」の間を主観カメラが移っていくと要約されることが多いんですが、書いた側としては「俺」はひとりに固定してて、世界の方が予告なしに変わっていくんですよね。世界が変わるときに記憶や人格ごと変わっていってるから、本人もそのことに気づいていないだけで。そこには自分が日雇いをやっていた頃のリアリティを込めました。ただ、世界が一つでたくさんの「俺」が移り変わることと、「俺」がひとりでたくさんの世界が移り変わることは、「数学的」に見ると等価なんです。だから作者の自分としてはそのつもりじゃないけど、自己が変わっていくという読み方も否定はしない。
「ビニール傘」は第二部で女性の生活史に入ると主人公と世界の関係がピタッと固定されますが、第一部の主人公は外界の流れにその都度反応するだけの、匿名の男として描かれます。それが、僕にとっての男性性の認識なんでしょうね。
西 前に直接伝えたんだけれども、岸さんは社会学者としてこれまでずっと聞き取り調査をしてきたから、いろんなひとの語り口が頭の中に格納されていると思うんです。特に私は、岸さんの小説における女性の語りがとても好きですね。
岸 でも、自分としては怖かったですよ。「ビニール傘」の後半もやし、「図書室」に至っては全篇丸ごと自分と同世代の女性の一人称で展開する小説です。いかにも男の作家が書いた女みたいになってたらどうしよう、不自然な感じになってへんかな、ということは最後まで悩みました。幸い、いまのところ違和感があったという感想はいただいていませんが。
千葉 僕も違和感は持ちませんでしたね。自然だった。
岸 よかった。ただ、さっき西さんがおっしゃったように僕が社会学の生活史調査でしてきたことと小説でやってることがよく繋げて論じられるんですが、あくまでも自分の中ではその両者の文章を切り離して考えてるんですよ。千葉さんは学問と文学はあまり違わないと言わはったけど。小説は僕にとって、もっとすごく個人的なもので、言ってみれば「社会学以前」の表現なんですよね。だからどうしても大学院に入る前の話が多くなってしまう。
西 当面は社会学者になる以前のことしか書いていないと。そこは岸さんの小説を考える上でのポイントですね。
岸 それに、僕は社会学の調査で得たことって、実は小説に一切使っていないんですよ。沖縄のひとや在日韓国人、被差別部落に生まれたひとたちが話してくれた内容は、本業である社会学の論文に他者の語りとして載せるから、個人的なことを書く小説には絶対使ったらダメだと思っていて。僕は自分がマジョリティの側にいるということに、異常なくらいこだわるんですね。だからマイノリティの話を小説のネタにすることは、一番したらいかんことにしている。
ちなみに、四作目の小説の主人公はジャズミュージシャンで、これはもし自分が大学院に進学せず、社会学者にもなっていなかったら、と想像して書いている部分もあります。
千葉 そういった設定は、自己分析のプロセスの結果として出てくるものなんですか?
岸 前に千葉さんから、僕の生活史調査でのインタビューの仕方が、精神分析の手法に近いと言われたことがあったよね。
千葉 ええ、関係しているとは思いますよ。
岸 それで言うと僕にとって小説は、自分の話を聞いて書いている感じですね。自分自身の生活史、あるいはあり得たかもしれないもうひとりの、いまとは違った人生を歩んでいる自分の生活史を書き留めているというか。小説を一人称でしか書けないのも、もしかするとそのせいかもしれない。
(第3回につづく)
コーディネイター:西成彦(にし・まさひこ)
1955年生まれ。比較文学者。立命館大学先端総合学術研究科名誉教授。 主な著書に『ラフカディオ・ハーンの耳』『森のゲリラ 宮沢賢治』『耳の悦楽』『外地巡礼―「越境的」日本語文学論』など。
-

-
千葉雅也
ちば・まさや 1978年栃木県生まれ。東京大学教養学部卒業。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士課程修了。博士(学術)。立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。著書に『動きすぎてはいけない――ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』『勉強の哲学――来たるべきバカのために』『意味がない無意味』『アメリカ紀行』など。『デッドライン』が初の小説作品となる。
-

-
岸政彦
1967年生まれ。社会学者。著書に『同化と他者化─戦後沖縄の本土就職者たち』『街の人生』『断片的なものの社会学』(紀伊國屋じんぶん大賞2016受賞)『愛と欲望の雑談』(雨宮まみとの共著)『質的社会調査の方法─他者の合理性の理解社会学』(石岡丈昇、丸山里美との共著)『ビニール傘』(第156回芥川賞候補作)『図書室』など。最新刊は『リリアン』(2/25発売)。
この記事をシェアする
「千葉雅也×岸政彦「書くってどういうこと?――学問と文学の間で」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 千葉雅也
-
ちば・まさや 1978年栃木県生まれ。東京大学教養学部卒業。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士課程修了。博士(学術)。立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。著書に『動きすぎてはいけない――ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』『勉強の哲学――来たるべきバカのために』『意味がない無意味』『アメリカ紀行』など。『デッドライン』が初の小説作品となる。
対談・インタビュー一覧
-

- 岸政彦
-
1967年生まれ。社会学者。著書に『同化と他者化─戦後沖縄の本土就職者たち』『街の人生』『断片的なものの社会学』(紀伊國屋じんぶん大賞2016受賞)『愛と欲望の雑談』(雨宮まみとの共著)『質的社会調査の方法─他者の合理性の理解社会学』(石岡丈昇、丸山里美との共著)『ビニール傘』(第156回芥川賞候補作)『図書室』など。最新刊は『リリアン』(2/25発売)。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら