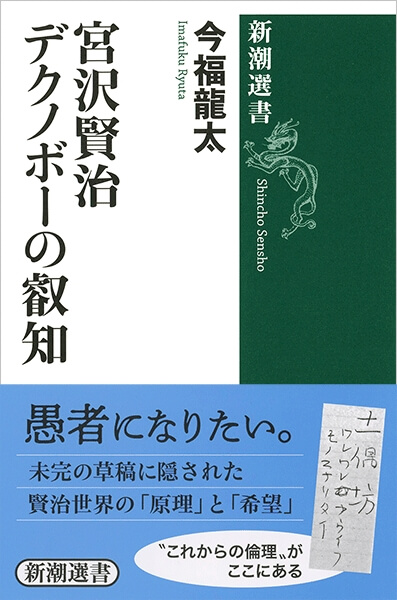2020年10月31日
第2回 人類の絶滅への想像力
『宮沢賢治 デクノボーの叡知』(新潮選書)の著者・今福龍太さんが、第30
(第1回へ戻る)
今福 現代を生きるわれわれは人命の喪失にたいして過度に感情的な受けとめをしがちで、自分の肉親、とりわけ子供の命が失われることが究極の悲劇として捉えられます。過剰なまでの悲嘆と哀悼の意識は、失われた生命が自らの所有物であるという潜在的な感覚と強く結びついていると言ってもいいでしょう。今回ぼくが宮沢賢治について深く考えることになったきっかけには、本書の「序」でも述べたように、二〇一四年に起きた御嶽山の大規模噴火の受け止められ方への違和感がありました。噴火によって多くの生命が失われたとき、メディアはそれを被災という側面だけから捉え、修羅が営まれる人間の生が、火山そのものの存在を組み込んで成立してきたという事実を顧みることはありませんでした。
しかし、東北人であった賢治の周辺には火山がつねに煙を吐き、過去の大噴火によってできた複雑で豊かな地形がたくさんあって、彼はしばしばそうした火山弾や火山礫である大石の傍らに行って、長い歴史を語る溶岩の声に耳を傾けていたのです。童話「気のいい火山弾」の主人公はベゴ(東北方言で牛のこと)と呼ばれる丸い黒い噴石です。ベゴは周りの尖った火山弾から馬鹿にされながらも、苔と一緒に戯れ歌などを歌っては自分の置かれたデクノボー的な境遇を慎ましく受けいれ、静かに楽しく生きていた。物語の最後にベゴは「東京帝国大学校地質学教室」の人たちに見出され、「立派な火山弾」の標本として大事に持ち去られるのですが、賢治はそのときのベゴの気持ちを誇らしさというよりは悲嘆として描き出しています。本来ベゴは目立たない、「地」の世界の住人として生きていたはずなのに、地質学者たちの標本にされた瞬間に「図」の方に取り込まれてしまうわけです。火山や噴石が人命を奪う悪者扱いされているいま、賢治がベゴに託して示したのは、人間中心主義的なヒューマニズムを自然の側から乗り越えようとする試みだったように思います。
真木 おっしゃる通り、今の社会を覆っているのはヒューマニズムというより人間中心主義だと思います。今福さんが今度の本の中で詳しく論じている石牟礼道子さんも、ヒューマニズムに警鐘を鳴らした作家でした。『苦海浄土』で石牟礼さんが書くように、水俣病というものが明らかになる何年も前から、漁師は魚たちの泳ぎ方がどこかおかしいことに気づいていたんです。魚の次には猫が狂って踊り始め、今度はカラスが変な飛び方で落ちたりもした。それでも、行政をはじめ一般市民はそれがまさか人間にまで波及するとは思っていなかったわけですよね。あくまで人間社会の外側で起きていることだと、甘く見積もっていた。でも、もしも動物の世界が人間の世界とも繋がっていることを敏感に察知していたら、排水内のメチル水銀の量を早い段階で調べられたでしょうし、水俣病の被害はあそこまで拡大しなかったはずなんです。
ですからぼくに言わせると、真の意味のヒューマニズムというものは、人間だけが大事だと考えたらそもそも成り立たないんです。動物たちをないがしろにする態度から水俣病が発生したことからもわかるように、本当の人間主義は人間主義を超える感覚によってしか支えられない。そうした逆説について考えることが大切なんじゃないでしょうか。
今福 今のお話とも繋がりますが、先日、高校生の環境活動家グレタ・トゥンベリさんが国連気候行動サミットで行った演説が話題になりました。一六歳の少女がスウェーデンからアメリカのニューヨークまでやってきて、大人たちの気候変動問題への不作為に対して本当に痛烈なスピーチをした。そのスピーチの内容が世界中で大きく取り上げられ、称賛もされましたが、逆にバックラッシュもひどく、今はどちらかと言えば彼女がクレイジーだという論調が大勢を占めているように思います。「早く国に帰って、気候変動のことをもっと勉強しなさい」と諭したり揶揄したりしている。でも、地球全体が温暖化の傾向にあるのに大人たちはそのことを軽視し、成長と金のために削減の数値を緩くしているという指摘はまったくその通りです。
真木 彼女は“fairytales of eternal economic growth”(経済発展がいつまでも続くというおとぎ話)という言い方をしていましたよね。
今福 まさにそうでした。そして、ぼくがグレタさんの英語のスピーチを追う中でもう一つ重要だと思ったのは、“We are in the beginning of a mass extinction.” という発言です。彼女は地球上の生物種がいま大量絶滅の入り口に立っていると、はっきり述べたのですが、そこには人類の絶滅への想像力も含まれているとぼくは見ました。これはとても強い言葉です。大人たちの不作為を問いただすために、人類という種そのものの絶滅の可能性にまで言及したのは、ひょっとすると彼女が初めてかもしれない。
我々は自らが属する人類という種の絶滅についても考えなければいけない時期に来ていることを薄々感じつつも、近代の倫理や道徳はそのことを隠蔽し、「全体の死」という問題を「個体の死」の問題にすり替えてごまかしてきました。行政も科学も、福祉や医療の名を借りて「個体の死」を少しでも遅らせることにのみ力を注いできたと言ってよいでしょう。近年、フーコーの言うバイオポリティクス(生の政治学)を超えてネクロポリティクス(死の政治学)という概念も使われていますが、どちらにせよ優位にある人間が劣位にある人間の生死を握っているのが今の世の中です。医療福祉など個体の死をめぐる政策は、権力の再強化と切り離して考えることはできません。そんな状況下でグレタさんが登場し、権力者たちが本当は考えずにおきたい痛点を鋭く突いたわけですね。
さらに付け加えて言うと、賢治がものを書き始めたのはちょうどニホンオオカミが絶滅したとされる頃です。記録によれば、賢治が九歳だった一九〇五年に奈良県で捕獲されたオスが最後の生存情報で、「狼森と笊森、盗森」でオオカミの森のことを賢治が書く二○年ほど前に、すでに日本の野生オオカミは絶滅していたわけです。賢治はそうした種の絶滅という出来事を鋭敏に感じ取り、狼森と呼ばれるオオカミの棲息していた森の記憶をいまに呼び出す形で、作品に反映させていたのではないでしょうか。「なめとこ山の熊」にしても、ツキノワグマの棲息域が当時すでに東北の森の奥に追いやられ、九州や四国、中国地方あたりでは絶滅していたという認識のもとで書かれていたと推測できます。グレタさんと同じく賢治も、“mass extinction” の危機を切実に捉えていたに違いありません。
真木 グレタさんの国連演説を受け、世界中で四〇〇万人もの若者が気候変動対策を求めるデモに参加したと報じられていますが、同時にぼくがとても興味深く感じたこととして、彼女の演説に対してアメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が揃って冷ややかな皮肉を言っているんですよね。トランプは「ほほ笑ましい姿だ」とからかうツイートをし、プーチンは「彼女の周りには世界の複雑さを教えてあげる人が誰もいない」と発言した。つまり東と西に別れた二十世紀的な冷戦構造は完全に崩壊していて、ある意味ではアメリカの指導者もロシアの指導者も同じ一つのラインに立っている。それに対し、まだあと何十年も生きる若者たちが大陸を超えた連帯を求めているという構図です。世界の対立軸が、これまでとは大きく変わった気がしました。
今福 政治家が重んじる時間は非常に近視眼的で、彼らはせいぜい自分たちのレジームが続く限りの近未来しか見通していない。大国のトップであっても、今の社会が百年なり数世紀先にどうなるかという展望のもとで意思決定することは今やほとんどないはずです。逆にグレタさんや賢治の目線の先にあるのは決してそれぞれの人生には留まらない長さを持った、地球史的なスパンでの時間です。数百万年先から、ひょっとすると数億年先のことまで考えている。そうでなければ、“mass extinction” という表現は出てきません。人間が森羅万象へと解き放たれて存在するあり方を想像しながら賢治が好んで使った「微塵」という言葉も、そのような大きな視座に立って初めて出てくるものです。
創られるという経験
真木 先ほど名前を挙げた石牟礼道子さんも、人間のせかせかした時間が砂に埋もれて、地質学の時間のように眺められるようになる日のことを語っていました。そうした視線が、水俣病をつぶさに見つめ、将来的な人類の絶滅をも覚悟しながら作品を書いていた彼女の想像力とも大きく関わっているように思います。
今福 『宮沢賢治 デクノボーの叡知』では、「天と内臓をむすぶもの」の章で石牟礼さんに触れました。この章は石牟礼さんが二〇一八年二月に亡くなられた直後に書いたものです。彼女と生前にお会いすることはなかったものの、全集の一巻に解説を寄せたことがきっかけで何度か手紙を交わしていたので、石牟礼さんの死を深く受け止めることになりました。ぼくは自分が水俣に行くことでこのテーマを過度に政治化してしまうことを恐れ、むしろルーツである天草の方から石牟礼作品への接近を試みてきました。石牟礼さんが生まれたのは熊本県天草下島の不知火海に面した宮野河内という小さな村ですが、母親の故郷は同じ天草でも少し離れた天草上島の下浦で、ここには昔から石場があります。彼女の祖父や父親も石工職人でした。そもそも一家が水俣市に引っ越した背景には、チッソの工場ができたことで道路や湾岸の大規模な整備が必要になり、石を敷いたり側溝を作ったりするため多くの石工が必要とされたからという事情があったんですね。
今も天草の村々を巡ると、百年以上前に組まれた美しいアーチ型の石橋や神社の石垣や石の鳥居が使われています。かつては石工がさまざまな鑿を細かく使って石を穿ち、制作していたものの、現在は人造ダイヤモンドのついた電動ノコギリで中国から輸入した御影石を削り、墓石にする仕事がもっぱらなのだそうです。ぼくが地元の職人に、今ではもう使わなくなった道具を見せてほしいと頼むと、彼は「そんなものがどうして見たいの?」というような怪訝な表情で、父親の形見だという埃をかぶった鑿や槌を持ってきてくれました。そして道具の使い方をぼくに説明するうち、職人の目が次第に輝きだしたんですね。その目は自分が以前習った手わざを思い出して高揚しているだけでなく、父親や祖父の手の記憶が昔の道具を通じて蘇ってきて、そのことに感動しているように見えました。こうした形で、石工には手を媒介にした集団的な記憶というものがあり、石牟礼さんも石を媒介にしてそうした身体感覚を受け継いでいたと言えるんじゃないでしょうか。
真木 今のお話を聞きながら思い出していたのですが、石牟礼さんは一時、水俣の市内から離れた谷あいみたいな場所を仕事場としておられた時がありました。石牟礼さんが「ここに一人でいると、もう、いろんな声が聞こえてくるんですよ」と語っていた姿を憶えています。今福さんがお書きになっている「風聞と空耳」という表現とも重なりますが、石牟礼さんは水俣病患者の声や動物の声、自分が生まれる前の先祖の声まで、無数の重層的な声を聞いていたわけです。「聴く」ということではなく、「聞く」という、聞こえてくるということですね。まだこの世に生を享けていない時からの先天的な水俣病患者の子供の声なども聞いて、それを文章にしていく――石牟礼作品の本質は、まさにこの「聞く文学」だったんじゃないかと思います。
宮沢賢治に話を戻しますが、ぼくが大好きな「龍と詩人」という短篇があります。少し内容を説明すると、主人公のスールダッタが詩の審査会に出て、最高の栄誉を得る。スールダッタはそれまで一番偉いとされてきた詩人アルタの座を奪い、アルタはこれからはあなたの時代だと言い残して、その場を去っていくわけです。ところが、スールダッタは、心から喜ぶことができません。なぜなら彼が審査会で発表した詩は、洞窟に暮らす龍のチャーナタが歌っていた素晴らしい詩を聞いて、そのままうたったものだったからです。それで、スールダッタは龍に謝るため洞窟まで行って、龍にそのことを告白します。すると、龍は、スールダッタよ、あの詩はわたしが、風の声や海の声から聞いたものだ、だからあの詩は、雲や風や水や空の詩であり、またわたしの詩であり、そしてスールダッタよ、お前の詩でもあるのだ、と。これもまた、近代的な文学観、主体観、価値観を根底から覆すような話です。近代文学は作者の絶対性を前提とするものですから。
現代美術の中心にいた宇佐美圭司によれば、ニューヨークのアート界でも、オリジナリティーが何よりも重視されていて、とにかく変わったものだったり、アーティストの個性がきわだつものが評価される。そうしたオリジナリティー信仰が二〇世紀の終わりにかけて強くなっていき、主体性を持った新しい表現こそがより価値がある、と評価されるようになりました。
今福 近代以降、文学であれ美術であれ音楽であれ、表現に携わる人の独創性は常に固有名詞化されていきますよね。そしてオーサー(作者)の名がオーソリティー(権威)となり、単独の価値が与えられる。
実は、真木さんはいま目が不自由でいらっしゃるということで、今回の対談に向けてぼくを含む何人かで手分けをして『宮沢賢治 デクノボーの叡知』の全文を朗読した録音データを作り、お送りしました。そのうち「風聞と空耳」の章では「風の又三郎」の新しい読解を試みるため、歌の起源をめぐってぼくの奄美大島での経験についても書きました。そのなかで奄美のシマウタの詞を引いていたのですが、今回朗読中にふと思い立ち、ぼくの三線の師匠である里英吉さんのウタと三線のかつての録音を朗読のなかに挟み込みました。ここで引用するシマウタの詞は、文字情報で伝えるだけでは不十分だと思ったんですね。里さんの歌には、風や潮騒など周囲の自然と同調してゆく親和性があり、可能な限りそのままの形で真木さんの耳へと届けたかった。テープを聴きながら、きっと奄美の風が少し感じられたんじゃないでしょうか。
ぼくは里さんのことを師匠と呼んできましたが、これは勝手に弟子入りしただけで、彼は誰かに教えるなんてことをそれまで一度としてしたことがありません。楽譜はもちろん、体系化された技術だったり、三線のメソッドと言えるようなものは何一つない。だから彼が三線を弾きながら歌う傍らにいて、身体感覚すべてをはたらかせて、見よう見まねで覚えるしかないわけです。けれども、ぼくにとってはそのやり方が何より刺激的な経験でした。これまで学校教育を通じて理解していた頭脳的な「学び」のあり方とは根本的に違う、「模倣」としての学びがここにはあると思った。
考えてみると民謡は、自然の声を歌に置き換えたものだと言えるのかもしれません。「風の又三郎」には、「どっどど どどうど どどうど どどう」という有名な歌が出てきますが、これは賢治が風の音を表記したものだと考えられます。面白いことに、賢治が教え子に、今度はこの作品を音楽にしたいので曲をつけてくれと言ったとき、彼は同じ部分を「どっ どどどう どどどう どどどう」と、まったく違うリズムで書いています。風はその時々によって、様々なリズムで吹くものですからね。四・四・四・三という音の連なりだけを近代詩のリズムのように小気味よく受け止めるだけでは、風の声を聞いたことにはならないのでしょう。模倣的な言語というものの典型的な流動性・可塑性がここにありますね。
ぼくはこの本を書く中でふと思い立ち、世界の音響的なリアリティをもっとも鋭敏に捉えるものとして「風聞と空耳」という表現を使いましたが、一般的には「風聞」はあやふやな噂のことを、「空耳」は聞き間違いのことを指すと理解されますよね。でも、本来なら「風聞」や「空耳」ほど精確な聴取の仕方はないはずなんです。風を聞くこと、空に聞き耳を立てること。自然のアコースティックな音響を直に受け止めることを示すのであれば、これらの表現こそがふさわしい。それなのに、「風聞」にも「空耳」にも噂や幻聴というような否定的な意味がはりついてしまったことは、我々の文明の堕落を示している気がしてなりません。
三線の師匠である里さんは、「曲げ」という表現を好んで使っていました。演奏が上手い人の真似をしてみても、そっくりそのままコピーすることはできない。必ずどこかで曲がってしまって、違うものになる。一人ひとりが持っているその「曲げ」こそが個性なんだというのです。ぼくは里さんのこの話を、狙って出した創造性はつまらないものであり、本当の創造性は図らずも自然と出てしまうということだと理解しました。
真木 そういえば、バタイユが彼の芸術論の中で非常に重要なことを言っています。曰く、創るという行為が近代芸術の中心になっているけれども、大事なのは創作の中で自分自身が創られるという経験なのだと。ぼくはこの考えに強く共感しました。芸術でも文学でも理論でも同じだと思いますが、自分自身が創られるという経験を土台とするときに、最も素晴らしい創造があると思います。
(第3回へつづく)
-

-
今福龍太
いまふく・りゅうた 文化人類学者・批評家。1955年東京に生まれ湘南の海辺で育つ。1980年代初頭よりメキシコ、カリブ海、アメリカ南西部、ブラジルなどに滞在し調査研究に従事。その後、国内外の大学で教鞭をとりつつ、2002年より群島という地勢に遊動的な学び舎を求めて〈奄美自由大学〉を創設し主宰する。著書に『クレオール主義』『群島―世界論』『書物変身譚』『ハーフ・ブリード』『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(読売文学賞受賞)など多数。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 今福龍太
-
いまふく・りゅうた 文化人類学者・批評家。1955年東京に生まれ湘南の海辺で育つ。1980年代初頭よりメキシコ、カリブ海、アメリカ南西部、ブラジルなどに滞在し調査研究に従事。その後、国内外の大学で教鞭をとりつつ、2002年より群島という地勢に遊動的な学び舎を求めて〈奄美自由大学〉を創設し主宰する。著書に『クレオール主義』『群島―世界論』『書物変身譚』『ハーフ・ブリード』『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(読売文学賞受賞)など多数。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら