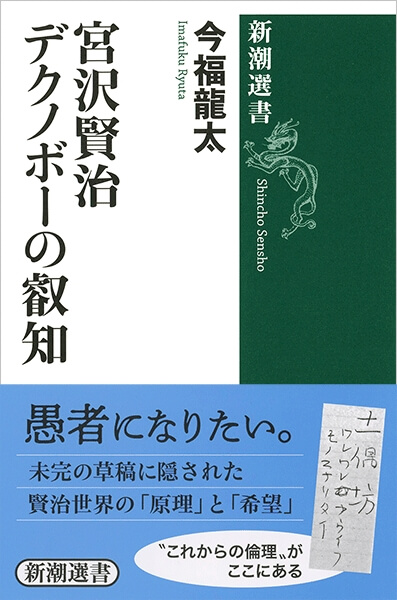2020年10月30日
第1回 互いの湖を呼応させる
『宮沢賢治 デクノボーの叡知』(新潮選書)の著者・今福龍太さんが、第30
今福 はじめまして。今日は必然と偶然の錯綜する環が巡り巡って、ついに真木悠介(見田宗介)さんとの邂逅が叶い、心が昂ぶっています。本来なら真木さんとはもう二○年も前に、あるシンポジウムでお会いするはずでした。東京で多木浩二さんらが企画された「世界化する都市と建築」というシンポジウムに、二人とも呼ばれていましたね。ぼくはそこで「都市と想像力」をめぐって発表する予定になっていたのですが、会の直前、当時引っ越したばかりの札幌の自宅へ本の段ボールを三百箱ほど運び込んだことが引き金となり、腰を痛めて動けなくなり入院することになってしまった。そこで病室で発表原稿を書き、多木さんに託しました。会場では多木さんがぼくの原稿を紹介し、敷延しながらそれについて語ってくださり、真木さんもそれにたいしてコメントをしてくださったので、バーチャルな形ではあれ、お互いの言葉が触れ合ったことがありました。
また、二〇一八年の暮れ、屋久島に暮らしていた詩人・山尾三省による宮沢賢治論である『野の道』(野草社)の新版が刊行され、東京でその刊行記念イベントを行いました。そのとき真木さんは会場にいらっしゃることはなかったものの、特別にメッセージを寄せてくださいましたね。もともと一九八三年に刊行された『野の道』には真木さんが「呼応」というタイトルの素晴らしい序文を書かれていて、新版の刊行に当たってはぼくがあらたに解説を書き下ろしました。イベントのために頂いたメッセージには「呼応Ⅱ」と題が付けられ、宮沢賢治―山尾三省―真木悠介からなる三者の呼応の関係にこのたび今福龍太が加わったという文脈で書かれていて、とても心動かされました。
真木さんが一九七七年に出版された『気流の鳴る音――交響するコミューン』(初版、筑摩書房)は、ぼくにとってとても大切な本でした。正直に言えば、この本に背中を押される形で二六歳のときにメキシコ行きを決めたと言ってもいい。真木さんはずっと「湖の呼応」という表現で、人間の存在の芯にある静かな湖に語りかけることを続けてこられましたね。『気流の鳴る音』が生まれた場所が南米アンデス高地のチチカカ湖に浮かぶトトラ葦の浮島の上だとすれば、ぼくが知的な自己形成をした特別の場所はメキシコの火山高原の標高二千メートルのところにある、パツクアロ湖の湖岸の葦が生えた湿地帯です。プレペチャ族が住むその湖の周囲で、二〇代半ばの二年ほど調査をしていました。ですから真木さんの内部にチチカカ湖という原風景があるのと同じように、ぼくの内部にはパツクアロ湖という原風景がある。今日の対話はぼくの『宮沢賢治 デクノボーの叡知』(新潮選書)の刊行が一つのきっかけではありますが、この本の内容に限らず、お互いの湖を呼応させるようにして自由にお話しできればと思っています。
真木 よろしくお願いします。こちらも今福さんとの初めての対話を楽しみにしてきました。ぼくはパツクアロ湖のあるメキシコ中西部のミチョアカン州には行ったことがないのですが、お話をよく聞いていたあの島は浮島なんですか。
今福 厳密に言えば、トゥーレと呼ばれる葦が密生するハニツィオ島という小さな島が湖の真ん中にぽっかり浮島のように浮かんで見えるという地形です。ここは毎年十一月一日から二日にかけて行われる死者の日の祭りで有名ですね。島自体がこんもり盛り上がった山のような形になっていて、斜面に並ぶお墓がとても立体的に見えて美しい。死者の日の夜になるとそれぞれのお墓に灯火が点され、花や食べ物といった先祖への供物が捧げられて、そこでインディオの家族たちが静かに一夜を過ごすという風習があります。今ではその様子がテレビで毎年中継されたりもして、観光的な見世物になってしまった部分もありますが。
真木 お墓が一晩中、煌々と明かりに照らされるのですよね。ぼくがメキシコに滞在していたのは一九七四年から七五年にかけてですが、その当時すでにあのあたりを観光地化しようという話が持ち上がっていました。ミチョアカン州の観光政策として、島からもう一つの島へ橋を渡すという話があったと聞いていました。ところが、これに対して大規模な反対運動が起きたんですね。地元住民に反対された理由としては二つの説が言われていて、一つはあの辺りにはとにかく頑迷固陋な連中が住んでおり、何が何でも変化することを拒んでいたという説。もう一つは左翼的な反体制グループが反対運動を扇動していたという説です。それで結局どちらが正しいのかとアメリカ人の女性社会学者が現地に住み込んで聞き取り調査をしてみたところ、どちらも違っているらしいということがわかった。
そもそも、そうした小さな島に生まれた人たちの多くは、昔からメキシコシティをはじめ大都市で出稼ぎしてきたわけです。女性だったら女中さん、男性だったら車洗いや道路掃除などの仕事に就いては生計を立ててきた。すると、彼らにとっての近代的な大都市メキシコシティのイメージは、台所や路上のゴミを通して経験されている。いわば彼らは、都市の繁栄をゴミの側から見ている。それで、自分たちの生まれ育った故郷が、あのような場所になるのはいやだ、と感じて、観光地化に反対したのだと、その社会学者は結論づけていました。
今福 七〇年代にそうした研究がされていたんですね。その後おそらく八〇年代になってからより顕著になったと思いますが、メキシコの若者たちは次々と国境を越え、アメリカで働き口を探すようになりました。一定期間アメリカで働いてお金ができると自国に戻り、またしばらくすると働きに出てというように往復運動が進み、それまでは彼らにとって近代文明の象徴は首都メキシコシティだったのが、次第にカリフォルニアへとシフトしていった。だから今ではメキシコで選挙があると、その候補者がわざわざ国をまたいでカリフォルニアまで演説をしに行ったりするわけです。アメリカへ出稼ぎに来ているメキシコ人たちはいつ地元に帰ってもおかしくないですし、彼らの家族の投票行動にもアメリカ在住のメキシコ人たちの意思は大きな影響を持つからです。
インディオの思想
真木 死者の日と聞いて思い出すのは、メキシコシティから遠く離れた先住民の村で過ごしたときのことです。メキシコシティに滞在していた当時、知人の家で働いていたお手伝いさんに彼女の地元を紹介してもらいました。日本だとお盆を迎える際に、どの先祖が帰ってくるかの共通認識が家族の中でありますよね。でも、その村に行ってぼくが気づいたのは、メキシコのインディオたちは一緒に暮らす家族のメンバーであっても、帰ってきてほしい死者の範囲が互いに違っている。例えばお父さんにとっては大事だけれど子供にとっては知らない人が入っていたり、逆におばあちゃんにとっても子供にとっても大切な人がいたりして、戻ってくるであろう死者をそれぞれに思い浮かべながら当日に向けて準備をするわけです。
ただ、そうして家族全員でもてなすことになった死者の数が仮に八人いるとして、面白いのは彼らは必ず一人分多く、つまり九人分のご馳走を用意するんです。なぜかと聞くと、死者たちの中にはもう現世に自分のことを思い出してくれる生者がいなくなったり、あるいは初めからいなかったりして、誰からも声がかからない人がいるはずだと。そんな彼らが死者の日に寂しい思いをするのはかわいそうなので、呼ばれた死者の一人が、「おれといっしょに来いよ」と連れてくると理解されているのですね。ですから、招き入れる家族にとっても未知の友人のために、一人分多く料理を作っておくのだそうです。
今福 メキシコでは、生者の普通のパーティでも、呼ばれていない人がたくさん来ていたりしますものね。ところでぼくにとって印象深かったのは、死者の日が近づくに従い、街の風景が徐々に移り変わっていくところです。人々の精神が静かに死者の方へ向かっていくだけではなく、商店には祭壇に捧げるための髑髏形の砂糖菓子が置かれたり、パン屋では「死者のパン」という骸骨や骨の姿をしたパンなどを売り始めたりと、目に見えて変化していく。真木さんも「骨とまぼろし」というメキシコに関する文章の中で、骸骨を大切にするインディオの文化について書かれていますが、彼らは人の骨に見立てたパンを、祭壇に置くだけでなくむしゃむしゃ食べてしまうというようなことも平気でするんですね。死者をうやまうだけでなく、死を諷刺し、死と戯れる。こうしたことは、祖先と深い一体化を果たすために必要な手続きなのでしょう。死者の日に向かっての人々のスピリチュアルで精神的な帰依と、食べ物をはじめ日常の具体的な事物の祝祭的な氾濫。メキシコでは、その聖と俗の両者の深い結びつきがとくに印象的です。
真木 メキシコで長く暮らす画家の竹田鎭三郎さんから、以前こんな話を聞きました。竹田さんがインディオの弟子に日本人は家族が亡くなったらどうするのかと訊ねられ、火葬して骨の一部を骨壺に納めるのだと答えたところ、その弟子が身ぶるいして、「おそろしいことだ」と言ったそうなんです。彼らは今でも土葬をするので、死者の骨は土の中にそのままの位置で残ります。骸骨が人間の存在の根っこにあると考えるインディオたちにとっては、火葬で骨がバラバラになり、ましてその一部しか保管しないなんてことはありえないと。
今福 インディオの目線は非常に示唆に富んでいますね。真木さんが『気流の鳴る音』で書いておられ、ぼくもメキシコで暮らす中で実感したことですが、彼らの物の捉え方は近代的な「図」と「地」の構図をひっくり返すところがありますね。われわれは背景を「地」、そこに描かれている絵柄を「図」として認識します。「図」と「地」の関係はそのまま、「光」と「影」の関係と言い換えてもいいでしょう。普通は「図」や「光」の方に有意性を見出し、「地」や「影」の方はネガティブなものとして処理される。
真木 西洋では光が知恵や価値のメタファーとしても理解されていますね。「啓蒙」を表す “enlightenment” という英単語が象徴的です。日本語にすると、「光を与える」という意味だから。
今福 それに対してインディオは、むしろ影の方にこそ有意性を見出します。そして、今日の主題にも引きつけて言うと――宮沢賢治にも同じような視線を見ることができるのではないかと思います。真木さんは『気流の鳴る音』の中で、賢治の詩を一篇、引用していらっしゃいますね。「岩手山」という、わずか四行からなる詩なので、全文を紹介してみましょう。
そらの散乱反射のなかに
古ぼけて黒くゑぐるもの
ひかりの微塵系列の底に
きたなくしろく澱むもの
(宮沢賢治「岩手山」『春と修羅』所収)
ぼくも『宮沢賢治 デクノボーの叡知』のなかでこの詩に込められた意図を検討しましたが、見逃せないのは、我々がふだん絵はがきで見るような美しい光に満ちた岩手山の風景を、賢治はなんと「きたなく」「澱む」陰画として描いている点です。真木さんはこの詩を引きつつ、さらに「すること」より「しないこと」を重んじるインディオの思想にも踏み込んでいらっしゃいました。
真木 ぼくが宮沢賢治という人を最初にすごいと思ったのは、大学の時にこの「岩手山」の詩と出会ったときのことでした。それくらい衝撃を受けたんです。今福さんがおっしゃる通り、この詩は岩手山のことを歌ってはいるんだけれども、肝心の山そのものはネガティブな形で示されます。逆に「そらの散乱反射のなかに」「古ぼけて黒くゑぐるもの」と、一般的には地として流される背景の部分こそが本当に感じるべきものとして描かれる。
こうした賢治の感覚は他の作品にも共通していて、彼の生前に唯一刊行された詩集である『春と修羅』の同名の詩には、「四月の気層のひかりの底を/唾し はぎしりゆききする/おれはひとりの修羅なのだ」という有名な一節がありますね。賢治はここでも、「四月の気層」という「地」の部分にこそ光を見ます。続けて自分自身を「修羅」という暗い存在として描いている。
言うまでもなく西洋的な思想の流れからすると、主体である自分に光を当てるのが普通です。すべてのことを疑っても、その疑いを持つ自我という存在だけは信用できる――これがデカルトの言うコギトの思想ですよね。自我だけが確かで、自然とは意味のないものであるという前提に従い、サルトルに至るまで近代思想は展開してきました。ところが、賢治はこの命題を鮮やかに裏返してしまったわけです。賢治作品における自我は怒ったり悔しがったりする、暗い存在として描かれます。『銀河鉄道の夜』のジョバンニも、楽しい祭りの晩なのに、病気のお母さんのために一人で牛乳を取りに行かねばならない。「岩手山」における、「黒くゑぐるもの」としての岩手山は、明るい祭りの晩をゆくジョバンニの孤独と重なっている。
今福 真木さんが本名の見田宗介名義で書かれた『宮沢賢治――存在の祭りの中へ』(岩波書店、一九八四)は、賢治を媒介にしながら自我というものを根源的に問い直した本でした。まさに従来の哲学は、人間の自我や人間精神を「図」として中心に据え、自然を含めた「地」の部分を人間が存在するための条件として後景に退けていました。そうした構図を反転させる契機を賢治の思想が孕んでいたのではないかと考え、ぼくは真木さんの問題提起を引き継ぎつつ、今回の『宮沢賢治 デクノボーの叡知』で根源的なヒューマニズム批判を試みたんです。ヒューマニズムは一般に人道主義と訳されますが、その背後にあるのは人間中心主義――あらゆる生命系の中で、人間を常に優位に置く思想です。したがって、ヒューマニズムに即した人間観というのは、それがどんなに倫理的なものであったとしても、「地」の部分を疎外する面があるのだと言わざるをえません。
(第2回へつづく)
-

-
今福龍太
いまふく・りゅうた 文化人類学者・批評家。1955年東京に生まれ湘南の海辺で育つ。1980年代初頭よりメキシコ、カリブ海、アメリカ南西部、ブラジルなどに滞在し調査研究に従事。その後、国内外の大学で教鞭をとりつつ、2002年より群島という地勢に遊動的な学び舎を求めて〈奄美自由大学〉を創設し主宰する。著書に『クレオール主義』『群島―世界論』『書物変身譚』『ハーフ・ブリード』『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(読売文学賞受賞)など多数。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 今福龍太
-
いまふく・りゅうた 文化人類学者・批評家。1955年東京に生まれ湘南の海辺で育つ。1980年代初頭よりメキシコ、カリブ海、アメリカ南西部、ブラジルなどに滞在し調査研究に従事。その後、国内外の大学で教鞭をとりつつ、2002年より群島という地勢に遊動的な学び舎を求めて〈奄美自由大学〉を創設し主宰する。著書に『クレオール主義』『群島―世界論』『書物変身譚』『ハーフ・ブリード』『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(読売文学賞受賞)など多数。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら