鶴見俊輔は晩年のほぼ20年間、「もうろく帖」と名づけた手控えのノートをつけていた。合わせて23冊――。
興味はありましたよ。でも私的なノートだからね、とうぶん読む機会はあるまいと、そう考えていたら、思いがけず、京都の「SURE」という編集グループがその1冊目を活字化してくれ、おかげで意外に早く読むことができた。
SUREといってもなじみのない人が多いと思うので、ざっと紹介しておくと、作家の黒川創、画家でエッセイストの北沢街子(妹)、編集者で、やはりエッセイストの瀧口夕美(妻)の3人がいとなむ家族出版社。それがSUREです。2002年に活動を開始し、遠い近いの差はあれ、幾人もの知人を仕事場に招いて、おもに座談のかたちで、ちょっと薄めの本をだしつづけてきた。
で、そのSUREが発足8年後刊行したのが、その間、1992年から2000年にかけてポツポツと書きつがれた「もうろく帖」の第1冊だったのです。鶴見さんはこのグループをよほどふかく信頼していたのだろう。なにしろ、発足以来、弱ったからだを押して一連の座談の場に加わりつづけただけでなく、『ちいさな理想』『悼詞』、詩集『もうろくの春』などから最後のエッセイ集『敗北力』まで、何点ものじぶんの本の出版をかれらの手にゆだねることになったのだから。
ちなみにいうと、出版といっても、かれらのだす本は町の書店では入手できない。アマゾンでもだめ。宣伝もしないから、いちいちウェブで定価を確認し、郵便払い込みで注文するしかない。とうぜん発行部数もすくないし、たしかめてはいないが、本をだしても印税収入はたぶんあまり期待できないんじゃないかな。あったとしても、ごくわずか。それを承知で自著の刊行をかれらに託した。「よほど信頼していたのだろう」というのは、そういう意味でもある。

では、その「もうろく帖」とは、いったい、どのようなものであったのか。あとがきで鶴見さんがじぶんで書いている。
七十に近くなって、私は、自分のもうろくに気がついた。
これは、深まるばかりで、抜け出るときはない。せめて、自分の今のもうろく度を自分で知るおぼえをつけたいと思った。
このときかれの正確な満年齢は69歳と8か月――。
私も体験があるのでわかるのだが、この年ごろになると、体力、記憶力、集中力など、心身のおとろえがおそるべきいきおいで進行し、それまであいまいに対していた老いの到来――鶴見さんいうところの「自分のもうろく」ぶりに、いやおうなしに気づかざるをえなくなる。
死がすぐそこまで迫ってきている。でも、なにしろいちども経験したことのない事態だから、このさき老いの急坂をどう下ってゆけばいいのか、さっぱり見当がつかない。その点では、われわれ凡人にかぎらず、鶴見さんのような度外れに賢い人だって、なんの変わりもなかったみたい。
――さて、ならば私はどう老いてゆこうか。
そこで鶴見さんが思いついたのが、あとがきにあるように「もうろく帖」と名づけた小型のノートを用意することだった。読んだ本や、人の話から、老いにかかわる印象深いことばを短く書き抜いておく。そのために使うつもりだったらしい。
したがって最初のうちは俳句や短歌、ことわざ、日本や外国の詩や散文の数行などが、1ページにひとつずつ、そのまま書き写されているだけ。ところが2年後、1994年9月に検査入院で大腸癌が発見され、別の病院で癌手術と胆石摘出。その退院の日に「今ここにいる。/ほかに何をのぞもうか。」としるしたのち、書き入れのピッチが急に上がって、なかみも、じぶんのメモが中心になってゆく。わずか2行か3行の走り書き。たとえばこんなふうな――。
○みずからをよぼよぼと見さだめることのむずかしさ、/それには日々の努力がいる。
○ぼけはもうひとつの舞台。その舞台のルールをおぼえて、あるいは工夫して、ぼけのステージごとに演技をつづけたい。
○しばらく人間になれて/おもしろかった。
いい忘れたが、このころ鶴見俊輔は公開の場でも、老化にともなう「ぼけ」や「モーロク」といった現象を人生からのみじめな脱落ではなく、社会がはめる枷からの自由として明るく理解したいと、繰りかえし書いたり語ったりするようになっていた。
老いをいやなもの、やっかいなものと見なしがちな社会にあって、みずからの「よぼよぼ」をすすんで受け入れ、そういうものとして周囲の人びとに納得してもらう。ただし、それには相応の覚悟と演技力がいる。そこに向けての「日々の努力」のあかし。もしくは、そのためのツール。どうやらそれがかれの「もうろく帖」だったようなのだ。
「しばらく人間になれて……」
輪廻転生かなにかで、ほんの短いあいだだったが、人間として生まれ暮らすことができた。「おもしろかった」と、ひとりでつぶやいて消えてゆく。
――ははあ、これも鶴見老の老人演技なのかね。
――と思うよ。でもかなり初期だな。私の経験では「ぼけのステージ」の1か2。そんな気がする。
*
SURE版『もうろく帖』の刊行後しばらくして、鶴見さんは、のこり22冊のノートの束からえらんだ短いことばを編んで2冊目の本をつくろうと考え、その準備にとりかかっていた。しかしその作業を終えることなく没し、あとを黒川創がひきついで、家族の人たちとも相談の上、今年(2017年)の2月末に『「もうろく帖」後篇』がSUREから刊行される。
倒れる直前の、最後のメモの日付は2011年10月21日。
「私の生死の境にたつとき、私の意見をたずねてもいいが、私は、私の生死を妻の決断にまかせたい」
そのあと、星じるし(*)をひとつはさんで、編纂者(もしくは家族のどなたか)の手になるこんな記述が付されている。
〔二〇一一年一〇月二七日、脳梗塞。言語の機能を失う。受信は可能、発信は不可能、という状態。発語はできない。読めるが、書けない。以後、長期の入院、リハビリ病院への転院を経て、翌年四月に退院、帰宅を果たす。読書は、かわらず続ける。
二〇一五年五月一四日、転んで骨折。入院、転院を経て、七月二〇日、肺炎のため死去。享年九三。〕
名うての「話す人」兼「書く人」だった鶴見俊輔が、その力のすべてを一瞬にして失ったということもだが、それ以上に、それから3年半ものあいだ、おなじ状態のまま本を読みつづけた、そのことのほうに、よりつよいショックを受けた。
鶴見の読書史はかれが3歳のとき、宮尾しげをのマンガ『団子串助漫遊記』を熱中して読んだことにはじまる。小学生のころは平均して1日4冊、授業をサボり、古本屋で立ち読みして、マンガや大衆小説を中心に1万冊以上の本を読んだのだとか。そこには『評判講談全集』『鞍馬天狗 角兵衛獅子』『相撲番付表』『苦心の学友』『小公女』『巌窟王』などのほか、丘浅次郎『進化論講話』や西村真次『人類学汎論』といった学術書、さらには『荘子』や『プルターク英雄伝』などの古典までが混じっていたという。
いくばくかの誇張があるかもしれない。でも、たとえそうだったとしても、当時、かれが日本一のモーレツな雑書多読少年だったことはまちがいなかろう。こうした特異な読書習慣は、15歳で渡米したのちは外国語の本も加えて、その後も途切れることなくつづく。そしてその延長として、話す力や書く力を完全に失ったのちも、鶴見は最後まで、ひっきりなしに本を読みつづけることをやめなかった。すなわち発信は不可能。でも受信は可能――。
――ふうん、もしそういうことが現実に起こりうるのだとすると、老いの底は、いま私が想像しているよりもはるかに深いらしいぞ。
ショックを受けてそう思い、またすぐにこうも考えた。もしこれが鶴見さんでなく私だったらどうだろう。たとえかれほど重くなくとも、遠からず私がおなじような時空に身をおく確率は、けっこう高い気がする。そうなったとき発信の力を欠いた私に、はたして3年半も黙々と本を読みつづける意力があるかどうか。
いまのところ「ある」といいきる準備は私にはないです。でも鶴見俊輔にはあった。どこがちがうのかね。そう思って晩年のかれの文章をいくつか読んでみたら、2002年(脳梗塞で倒れる9年まえ)にでた『読んだ本はどこへいったか』中の「もうろくの翼」という文章で、こんな記述にぶつかった。
ふだんは自分の意志で自分を動かしているように思っていても、その意志を動かす状況は私が作ったものではない。(略)今、私が老人として考えているのは、何にもできない状態になって横になったときに、最後の意志を行使して自分に「喝」と言うことはできるのかという問題です。
この本は2000年から02年にかけての京都新聞の連載をまとめたもので、ちょうど「もうろく帖」の執筆時にかさなる。

おわかりでしょう。
すでにこの時期、鶴見さんは「何にもできない状態になって横になった」じぶんを思い浮かべ、そのステージでのじぶんの行為が「自分の意志」(自力)によるものなのか、それとも老衰をもふくむ「状況」(他力)にもとづくものなのかを、最後の病床で、実地にためしてみようと考えていたらしいのである。
そしてもうひとつ、『もうろく帖』第1冊に、以前は見すごしていたこんな1行(幸田文「勲章」からの引用)があったことにも、あらためて気がついた。
書ければうれしかろうし、書けなくても習う手応えは与えられるとおもう。
原稿や手紙やこの「もうろく帖」を書くことや、日常のおしゃべりができれば、もちろんうれしい。だが仮にそれらのすべてが失われても「習う手応え」はのこる。「習う」は「教えられて自分の身につける。まなぶ」(広辞苑)という意味。本による「まなぶ」もふくむが、それだけじゃないな。からだの不自由度がまし、極端に狭くなった生活環境にあっても、ささやかな日常の体験によって考え、「習う手応え」を得ることぐらいはなんとかできるはずだ。
まだ発信能力を保持していたこの段階で、鶴見さんはいくつかの仕事(書くこと)のプランを抱え、そのための読書をつづけていた。
しかし、この状態が死ぬまでつづくとは思えない。私とおなじく、鶴見さんも「そのとき私はこれまでどおりに本が読めるだろうか」と自問し、自力であれ他力であれ、ともかく「読める」と考えることに決めたようなのだ。モーレツな雑書多読派(「私は赤川次郎の小説を二百冊以上読んだ」など)の習慣をつらぬいてきた鶴見さんにとって、じぶんをためす手段として最後にのこるのは、やはり読書しかなかったのだろう。
ただし、なにかのためでなく、じぶんひとりの「習う手応え」や「よろこび」を得るためだけの読書。『団子串助漫遊記』に熱中した3歳児のころを考えてみよ。かつて私はそのようにして本を読みはじめた。とすれば終わりもおなじ。私の読書史はまもなくそのように終わってゆくにちがいない。
*
あらためて「習う手応え」という幸田文のことばに遭遇し、「あれ?」と思った。そういえば、おれはいつだったか、おなじようなことばにどこかで接したことがあるぞ。そこで本棚をさがして見つけたのが堀江敏幸の文集『象が踏んでも』だった。

そこに収録された「途切れたままの雰囲気を保つこと」という文章で、堀江は、「私の年代であっても、『学ぶ』というときには、取り込んだものを少しでも消化して、遠い将来、なんらかのかたちで外に出したいとひそかに願ったりするものだ」とのべ、その上で、学生のころ、それとは対照的な「学ぶ」のかたちに串田孫一の「ドン・キホーテと老人」 というエッセイで出会った、としるしている。
このエッセイでは、串田によく似た語り手の男が不治の病におかされた老人を訪ねて行く。『ドン・キホーテ』をスペイン語で読みたい。そんな老人の希望を知った男は、町の大きな書店で原書を買って病床にとどけた。ベッドのかたわらにはラジオのスペイン語講座のテキストと辞書がおいてあった。しかし老人は数日後に亡くなり、その報せを受けて、男は「人の死に巡り合っていつももてあます儚さが感じられず、学ぶという営みの、その途切れたままの雰囲気が妙に貴く思われた」と語る――。
そして、この文章をひさしぶりに再読した堀江は、そこで見つけた「学ぶという営み」の「途切れたままの雰囲気」という1行について、こうのべる。
老人は、しかし老人になるまえから好奇心旺盛で、余命いくばくもないと悟ってから急に勉強をはじめたわけではなかった。語り手が観察してきたように、この人物はむかしからずっとそんなふうに過ごしてきて、死を直前にしても変わらなかったというだけの話である。(略)具体的な目的があっての勉強ではない。理屈抜きに知ることが楽しくて、それを糧にしてきた人間にだけ許される「通過点」なのだ。到達点ではなく通過点を重ねてこの世から消えるような、そういう勉強の仕方を身につけた方々が、たしかに存在する。
なにかの目標があってというのではなく、いまここで生きるじぶんのよろこびのために読む。串田孫一や堀江敏幸のいう、点数や成果のための「学ぶ」とはことなる、こうした「通過点」としての「学ぶ」が、そのまま鶴見(幸田)の「習う」にかさなってゆく。
「到達点ではなく、通過点を重ねてこの世から消えるような――」
まさしく「死を直前に」した鶴見俊輔じゃないの。そういえば鶴見さんも、若いころから、到達すべき真理などというものはない、真理はぼんやりした方向の中にしかないのだ、と好んで書いていたっけ。
この文章を書いたとき堀江さんは46歳。つまり壮年まっただなか。いい文章だと思うけれども、ちょっとだけ「本を読む老人」を理想化している気配が感じられないでもない。その点、「もうろく帖」の筆者は老人そのものだから、理想化をドライに茶化して、このようにも書くことができた。
インテリはみんなつまらん つまらんが
つまらんなりに本を読みつぐ
もうろくの最終ステージにあって、枕元に積んだ本の山を横目に、頭の中でそう黙ってつぶやく鶴見さんのすがたが見える。思わず笑っちゃうね。鶴見さんも半睡半醒のまま笑っていたんじゃないかな。
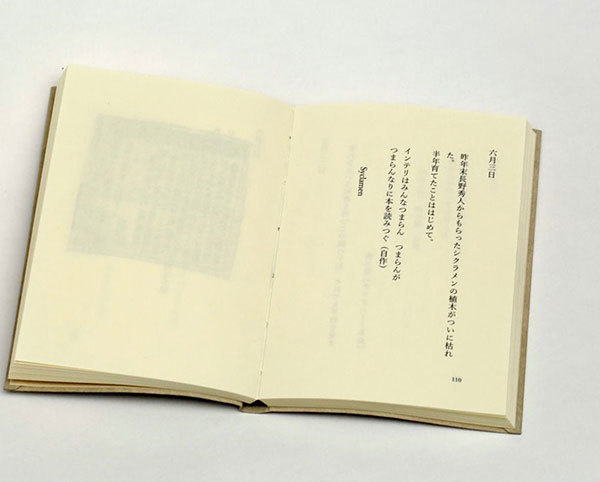
鶴見俊輔『もうろく帖』2010年、『「もうろく帖」後篇』2017年、いずれも編集グループSURE
鶴見俊輔『読んだ本はどこへいったか』聞き手・山中英之、潮出版社、2002年
堀江敏幸『象が踏んでも――回送電車Ⅳ』中央公論新社、2011年(引用はこちらから)→中公文庫、2014年
串田孫一『ドン・キホーテと老人』青娥書房、1976年
SURE については下記をご覧ください。
http://www.groupsure.net
〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町47
電話 075-761-2391
ファックス 075-320-1799
メールアドレス [email protected]
-

-
津野海太郎
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 津野海太郎
-
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら








