むかし見て感動したからというよりも、死ぬまでにあと1度、いや、できれば2度か3度は見ておきたい。それを基準に「ベスト10」をえらぶことにした、と前回の終わりに書いた。
しかしそうはいっても、『青春残酷物語』はいいとして、あとの2本、『灰とダイヤモンド』や『勝手にしやがれ』まで、平然と切って捨てられるかしらん。むずかしい。なにしろそのどちらもが、いま見ても、すばらしい作品であることは否定しようがないのだから。
おまけに、『灰とダイヤモンド』で主人公のテロリスト、マチェックに扮したズビグニエフ・チブルスキーが、のちに駅で列車に飛び乗ろうとして死んだとか、『勝手にしやがれ』の短髪のアメリカ娘ジーン・セバーグが、やはりのちになぞの自殺をとげたとか、やけにショッキングな事件がそこに重なってきた。
おどろきましたよ。なにしろ大学生だった私にとって、この2人は、それ以前、まだ少年だった私を魅了した『エデンの東』のジェームズ・ディーンや、『ローマの休日』で街の短髪娘に一変してみせたオードリー・ヘップバーンの再来のように感じられていたのだから。じっさい、チブルスキーは「ポーランドのジェームズ・ディーン」と呼ばれていたしね。しかもジーン・セバーグは私とおなじ1938年生まれだし……。
と、それやこれやで、若い私は『灰とダイヤモンド』や『勝手にしやがれ』を、頭がくらくらするほど感情移入して見つづけることになった。
でもね、老いた私が、いま、あのころとおなじ感動をまるごと味わうことができるかというと、なかなかそうはいかんのですよ。こんど見なおして、あらためてそう思い知った。おそらく私はこれらの作品を、それにふさわしい年齢で、十分すぎるほど十分に感動して見たのだろう。したがって、このさき1度ぐらいは見るかもしれないが、かといって2度も3度も見るとは思えない。となると、ざんねんながら、私ごとき老いぼれの「ベスト10」からは外すほかないのです。
あと問題は、洋画なら『黄金狂時代』『市民ケーン』『8 1/2』など、邦画でいえば『羅生門』『東京物語』『浮雲』といった、「ベスト10」の定番ともいうべき古典的名作をどう扱えばいいのか――。
かなり迷ったすえに、こちらは機械的に外すことにした。研究者や批評家諸氏が、映画史上、欠かすわけにいかない名画をえらぶ、といった類いの「ベスト10」ではないのでね、私までが、わざわざ首をつっこむ必要はないだろう。
ただし例外として『天井桟敷の人々』『第三の男』『雨に唄えば』――この3本だけは、いかに折紙つきの名画であろうとも外すわけにはいかない。なにしろ半世紀以上もまえから、映画館やテレビやビデオやDVDで繰りかえし見つづけ、それでも飽きずにいる、私にとっては生涯不動の「ベスト3」なのですから。
ええっとね、最初に見たのは3本とも高校生のとき。それも街の映画館ではなく、『天井桟敷の人々』と『第三の男』は東大法学部の大教室で定期的に開かれていた映画鑑賞会で。そして『雨に唄えば』は、たしか夏休みの最中だったと思うが、帝劇の音楽映画フェスティバルといった催しに、中学生の弟をつれて見に行った。
そんな年齢だったので深いところまではわからない。
とにかく『天井桟敷の人々』の冒頭、19世紀半ばのパリの芝居町「犯罪大通り」を埋めつくす群衆のなかで、アルレッティ扮する妖艶な美女が、いいよる男を「好いた同士にパリは狭いわ」と、にっこり笑ってはねつける場面とか、『第三の男』中盤で、オーソン・ウェルズの演じる死んだはずのペニシリン密売人が、とつぜん深夜のウィーンの街に出現する場面とか、もちろん『雨に唄えば』のジーン・ケリーが、ざんざん降りの雨の路上で歌って踊る場面とか、見せ場満載の展開に、「これこそ映画だ!」と手もなく魅せられてしまった。
それが運のつきで、以来、この3本を10回も20回も見つづけ、そのことで映画というものの見方が私なりにできていった。それにしても、なぜこの3本だったのだろう。わからん。気がつくと、いつのまにかそうなっていた。だからまァ、結婚みたいなものですよ。理由がどうこうよりも、そうしたことが現につづいたという歴史がたいせつ。その歴史ゆえに、私はこの3本を「ベスト10」から外すわけにはいかないのです。
などと、あれこれ理屈をつけ、なんとか10本にしぼり込もうと、この半年、ジタバタ奮闘してみた。それでわかったが、いまの私の力では「ベスト10」への挑戦はむりみたい。全映画史からわずか10本! そんな荒技を平然とやってのけるには、私の腕力や脳力はあまりにもおとろえすぎているのです。
そこで、いそいで結論をいうと、当初、じぶんにかけた枷を、勝手にゆるめさせていただくことにした。つまり「ベスト10」を外国映画と日本映画の二手に分け、それぞれに「ベスト10」を選定することにする。「ハハハ、そうきたか」と笑われるのは覚悟の上。なにしろ、そこまでやっても選択のむずかしさは、さして変わってくれそうにないのですから。
――といった次第で、まずは外国映画から10本。あたまの数字は古い順です。
(1) 『M』(フリッツ・ラング、1931年)
(2)『天井桟敷の人々』(マルセル・カルネ、1945年)
(3)『第三の男』(キャロル・リード、1949年)
(4)『雨に唄えば』(ジーン・ケリー/スタンリー・ドーネン、1952年)
(5)『波止場』(エリア・カザン、1954年)
(6)『突然炎のごとく』(フランソワ・トリュフォー、1962年)
(7)『屋根の上のバイオリン弾き』(ノーマン・ジェイソン、1971年)
(8)『蜂の旅人』(テオ・アンゲロプロス、1986年)
(9)『悲情城市』(侯孝賢、1989年)
(10)『わたしは、ダニエル・ブレイク』(ケン・ローチ、2016年)
(1)の『M』は、ナチス勃興の直前にベルリンで起きた幼女の連続殺人事件を題材に、フリッツ・ラングが撮った最初のトーキー映画で、このたび2001年のリマスター(修復)版をはじめて見て、いかにすぐれた作品だったかを知った。
いや、そのまえに触れておくと、おなじ1931年、おなじ新興の映画会社ネロ・フィルムから、G・W・パプスト監督の『三文オペラ』が公開されている。こちらは、3年まえに上演されたベルトルト・ブレヒトの戯曲の映画化で、クルト・ヴァイル作曲の「メッキー・メッサのモリタート」(ルイ・アームストロングが歌って大ヒットした「マック・ザ・ナイフ」の原曲)の力もあって、欧米圏で広く知られるようになった。
私には、若いころブレヒトに入れあげた時期があるので、その後、たしかあれは前世紀の終わりごろだったと思うが、友人に借りて、ビデオ化されたパプストの『三文オペラ』を見たことがある。ただし、さしもの伝説的な名画も時間の腐食力には勝てず、あまりにも欠落箇所が多すぎ、音や映像も悲惨なまでにぼやけていて、心底、がっかりさせられたという苦い記憶しかのこっていない。
そのせいもあって、きっとフリッツ・ラングの『M』も同様だろうと、あえて見ないままでいたのです。ところが、こんど念のために見て一驚した。あの切ないビデオ版『三文オペラ』とはことなり、DVD版の『M』では、戦時下のヨーロッパ各地に散らばっていたフィルムの断片を徹底的に収集し、音も映像も最新のリマスター技術を駆使して、みごとに原型を復元している。そのシャープさたるや、見る者をして、もしかしたらこれは原物以上かもしれないぞ、と感じさせてしまうほどにね。

あらためていうと、世界初のトーキー映画とされる『ジャズ・シンガー』の公開が1927年。その4年後、練達の無声映画監督だったフリッツ・ラングが、意を決してトーキー採用に踏み切る。長年、モノクロのサイレント映画できたえた芸術性に、トーキーという破壊的な新技術を組み合わせることで、どうすればより高度な芸術性を実現できるか。その歴史的な挑戦の場が、ほかならぬ『M』だったのです。
――映画がはじまってまもなく、「なぞの殺人鬼をさがせ・賞金10000マルク」というポスターを貼った広告塔のまえで、学校帰りの、ランドセルを背負った幼女が毬をついている。そのポスターに帽子を深くかぶった男の大きな影が映り、その影が「かわいい毬だね。お名前はなんていうの?」と幼女に話しかける。
そこで思いだすのがアルフレッド・ヒッチコックです。
9歳上のラングと同様に、ヒッチコックもイギリスで、サイレント映画の監督として映画人生をはじめた。後年、ハリウッドでカラー映画(当時でいう天然色映画)の巨匠となったかれが、「最近のあなたの作品から『影』が消えたようだが」と問われ、「やめたよ。カラーでは黒色がきれいにでないのでね」と答えている。ここからもわかるように、都市の街路や室内の壁や階段などに映る黒い影は、モノクロ/サイレント映画の目玉ともいうべき重要なイメージだったのです。
そしてもちろん、もうひとつが音の効果――。
幼女が路上で毬をつく音や、なぞの殺人犯(まだ27歳だったブレヒト劇の新人ピーター・ローレが演じて評判になった)の不吉なささやきもだが、とくに印象的なのが、かれが犯罪現場で吹くかすれた口笛のメロディ。あるいは、殺人鬼を追って対立する2つの組織――警察とギャング・乞食連合の双方で、たえず繰りかえされる滑稽な議論もそう。いま見ればどうということないが、そのどれもがトーキー化ではじめて可能になったシーンだったのです。しかも警官隊がドッと押し寄せるといったハデな場面では、わざとサイレント映画式に音を消してみせたりね。そこから「この大転換期にあって、試せることはすべて試してみよう」と腹をくくったラング監督の気迫が、ひしひしとつたわってくる。
白状すると、むかし私は、植草甚一さんや淀川長治さんが、往年のサイレントやトーキー初期の映画が到達していた高度な芸術性について熱心に語るのを、なかば「ほんとかね」と眉に唾をつけてきいていた。でも、これはまちがいだった。こんど修復された『M』を見て、植草さんたちの昔語りが、ただのおセンチな回想ではなかったことが、ようやく私にもわかってきたのです。
そして、もしそうだとすると、このさき、1920年代、30年代の古い映画のデジタル・リマスター化がいっそうすすんだら――すなわち『戦艦ポチョムキン』や『三文オペラ』や『巴里の屋根の下』などの、これまでは寝ぼけたような画面で見るしかなかった名作のかずかずが、『M』に匹敵するレベルで着々と修復されていくとしたら、つぎの世代、つぎのつぎの世代にとっての映画史は、かならずや、私たちのそれとはかなり異質なものになるにちがいない。
ようするに過去の私が名画座で見たものよりも、かれら、いってみれば未来の私たちのほうが、おなじ映画を、はるかに精密なサウンドや映像で見る可能性があるのです。「私(すなわち津野)の時代」などはあっさり跳びこし、未来に過去が直結する。しゃくだけどね。でもまァ、そのとば口を、ほんのすこし体験できただけでもよしとします。
思わず(1)の説明が長引いてしまったので、あとは簡単に――。
(2)の『天井桟敷の人々』は、マルセル・カルネ監督、ジャック・プレヴェール脚本の超大作で、ジャン=ルイ・バロー、ピエール・ブラッスール、アルレッティらの名演もだが、まずは、野外に復元された19世紀半ばのパリの芝居街にひしめく群衆の数と熱気に圧倒された。後年、これがナチス・ドイツ占領下のフランスで3年半かけて製作された作品だったと知り、よくもまァ大胆なことを、と仰天した。(くわしくは山田宏一『天井桟敷の人々』を参照のこと)
――それにしてもこの迫力を、はたして、いまのデジタル特撮でつくりだせるだろうか。
できないと私は思う。しかもこの空前絶後の傑作が、『M』からかぞえて、わずか14年後の作品なのだ。モノクロ/トーキー映画は、なぜこれほどの速さで成熟できたのだろう。私には、トーキー以前の、いまもまだ完全には復元できずにいるサイレント映画時代の蓄積が、よほど大きかったのだろうとしか思えないのですが――。
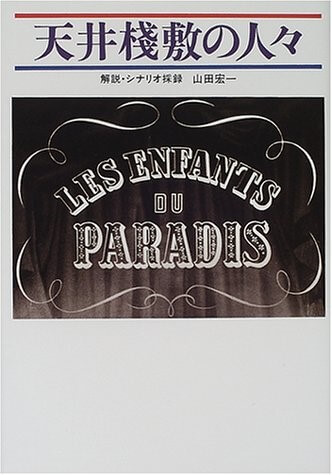
むかし植草さんに「いつごろの映画がいちばんよかったですか?」とたずねたら、ただちに「50年代です」という答えがもどってきた。
1950年代といえば、戦後のモノクロ映画の最盛期で、(3)の『第三の男』は、そのはじまりのあたりに位置する。つまり『天井桟敷の人々』の4年後で、黒澤明の『羅生門』も同時期。キャロル・リードもカルネも黒澤もほぼおなじ年齢で、ともにトーキー映画監督の第1世代に属する。なるほどね、まさしく私は「かれらの時代」のまっただなかで映画の魅力にめざめたのであったか。
――第2次世界大戦が終結し、アメリカ人の三文作家(ジョセフ・コットン)が、学生時代の親友(オーソン・ウェルズ)の招きで、米英ソ仏4国による分割統治下のウィーンにやってくる。ところがかれの到着まえに親友はなぞの死をとげていた――。
ここからはじまる硬派のミステリー映画(グレアム・グリーン脚本)が『第三の男』で、私はといえば、荒廃したウィーンを舞台に、なぞめいた多国籍の登場人物たちが織りなす物語を切れ味よく解きほぐしていくキャロル・リードの演出に、たちまち引きこまれてしまった。夜の街路や地下水道を駆ける人びとの黒い影など、モノクロ映画に特有の、おどろおどろしいシーンもたっぷり。
長年、この映画を見つづけるうちに、いつしか、オーソン・ウェルズの大芝居よりも、英国軍のキャロウェイ少佐に扮したトレヴァ・ハワードの渋い演技のほうが好きになった。私が見た米国版では三文作家のホリー・マーチンが語り手になるが、英国版では、キャロウェイ少佐がその役割を担ったらしい。ぜひ見たい。なのに見られない。それがくやしい。
小林信彦さんは「映画史上、最高のミュージカル映画」はフレッド・アステアの『バンド・ワゴン』だというが、6歳下の私にとってのそれはジーン・ケリーの『雨に唄えば』。――と私が考える理由は略す。とにかく若かったので、トップハットとステッキで粋に踊るアステアよりも、白いシャツの袖をめくり上げ、地べたにからだを叩きつけるように踊るジーン・ケリーのほうが、はるかに新鮮に感じられ、その印象がとうとう今日までつづいてしまったのです。
映画の背景は1920年代の終わり、『ジャズ・シンガー』ショックで、サイレントからトーキーへの移行を余儀なくされたハリウッドの映画スタジオ。――『雨に唄えば』がMGMスタジオで撮影されたのが50年代のはじめだったので、サイレント時代に使われた施設や機材が、まだあちこちに放置されていた。それを探しだして撮ったから、この映画は「映画考古学」の展示場みたいなものなんだよ、とケリーが語っている。

ただ20回以上も見るうちに、いやな部分もでてきた。サイレント時代のわがままな主演女優が、きつい訛りのせいでスタジオを追われそうになる。そこで……とはじまる箇所が、いま見ると、かなりつらい(つまりはイジメ)。小林さんや私が好きなMGMミュージカルの『踊る大紐育』は基本的に白人だけで、黒人もラティーノもアジア系も存在しない。そんな時代だったということが徐々にわかってくる70年でもあったのです。
(5)の『波止場』では、ニューヨーク港を仕切る暴力組合を市の犯罪調査委員会が告発し、その一員だった主人公(まだ若くてきれいだったマーロン・ブランド)が仲間を裏切って、じぶんもかかわった殺人の事実を公聴会で証言する。
この映画の背景には、監督のエリア・カザンが2年まえ、議会下院の非米活動委員会に喚問され、親しい仲間たちを反米的な共産党員、もしくはその同調者(つまりは非国民)として、むりやり告発させられたという暗い現実があった。当時、カザンは演劇と映画を股にかけた先鋭的な演出家として、かれなら非米活動委員会の暴走に正面から立ち向かえるだろうと期待されていたので、この裏切りは大きなスキャンダルになり、以来、かれはその汚名を背負って生きつづけるしかなくなった。じっさい、「この映画で裏切り者にされた主人公の苦しみは私のそれなのだ」と、のちにカザン自身が語っている。
でも、ほんとかなァ。あのしぶとい演出家が、みずからを無垢で無知で繊細な元ボクサーにかさねあわせ、そのことでじぶんの魂を救えるなどと、本気で思っていたのかしらん……。
わからない。しかも厄介なことに、こうした暗さの一方で、この『波止場』は、まれに見る美しい映画でもあるのです。なかでも主人公が鳩を飼うビルの屋上や侘しい裏町での、ブランドとエヴァ・マリー・セイント(殺された男の妹役)の控えめなラブシーンが忘れがたい。なんどでも見たくなる。レナード・バーンスタインの音楽もいいし、ボリス・カウフマンのドキュメント・フィルムふうの撮影もすばらしいしね。
そしてさらにいえば、そのブランドやバーンスタインは、カザンの裏切りに深く失望させられていた。その一方で脚本のバッド・シュールバーグや、組合のボス役のリー・J・コッブは、カザンとおなじ「強要された密告者」だった。そんな人びとがなぜかひとつの映画に結集している。なかなか単純にはいかない作品なのです。
60年代の後半、ロベール・アンリコの『冒険者たち』とジョージ・ロイ・ヒルの『明日に向って撃て!』という、1人の女と2人の男の友愛的三角関係を描いた2本の映画が相次いで封切られ、おおくの観客をあつめた。前者は、ジョアンナ・シムカスとアラン・ドロンとリノ・ヴァンチュラ。後者は、キャサリン・ロスとポール・ニューマンとロバート・レッドフォード。
そして、その先駆けとなったのが⑥の『突然炎のごとく』だったと、かねがね私は推測してきたのだが、はたして、どんなものだろうか。
第1次世界大戦をはさんで、ジャンヌ・モロー扮する奔放な女性と、オーストリア人(オスカー・ウェルナー)とフランス人(アンリ・セール)の2人の青年との微妙なバランスの三角関係が延々とつづき、そのはてに……。
といった展開がモノクロの画面で、ゆっくりと優雅に語られていく。それが私たち、たがいに独占的な男女関係にうんざりしていた若者には、気持ちのいい夢のように感じられた。『突然炎のごとく』だけでなく、3本とも夢の終わりに、とつぜんの死がおとずれる。その死までもふくめてね。そんな「ロマンチック・トライアングル」映画を、息苦しい男女関係とはとうに無縁になったはずの私までが、もっと見たいと思っている。ふしぎだ。
ちなみに、いまとなっては想像もつかないが、当時、日本でのフランス映画の人気は、ハリウッド映画に優に匹敵するほど高かったのです。たとえば私より3歳上のジブリの高畑勲監督。かれはなぜアニメ映画『やぶにらみの暴君』の脚本家で詩人のジャック・プレヴェール(『天井桟敷の人々』の脚本家、シャンソン「枯葉」の作詞家でもあった)に、終生、あれほど入れあげていたのだろう。私には、あの時代にかれが東大仏文科の学生だったから、としか考えられないんですよ。
――説明はできるだけ短くと、いちおうは努力したつもりなのに、思わず知らず延びてしまった。しかたない。以下の4本は次回にまわさせてください。そのあとに「日本映画ベスト10」を、こんどこそ、きりっと簡潔に。
フリッツ・ラング・コレクション『M』DVD解説リーフレット、IMAGICA TV(発売)、紀伊國屋書店(販売)、2007
山田宏一『天井桟敷の人々』ワイズ出版、2000
小林信彦「映画史上、最高のミュージカルを一本あげれば……」『週刊文春』、2020.12.10号
-

-
津野海太郎
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 津野海太郎
-
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら








