前回が(6)の『突然炎のごとく』で終わったので、今回は(7)の『屋根の上のバイオリン弾き』から。前者の製作年は1962年で、後者が71年。私の年齢でいうと24歳から33歳にかけて。いまにして思うと、あの10年間が生涯でもっとも忙しく、なおかつ、もっとも多くの映画を見た時期だったな。
それはまた、モノクローム(白黒)からカラーへの変化が、娯楽映画以外の映画にまで広く定着していった時期でもあった。トリュフォーでいえば、『突然炎のごとく』まではモノクロだったのに、1966年の『華氏451』以降はカラーに変わるというようにね。おなじヌーヴェルヴァーグ派でもゴダールはいっそう早く、1960年の『勝手にしやがれ』で登場した1年後には、もう『女は女である』をカラーで撮っていた。
そして60年代も後半になると、ごく少数の例外をのぞいて、ほとんどすべての映画がカラーに移行する。そのため、このリストも(7)以降はすべてカラー映画という結果になったのです。
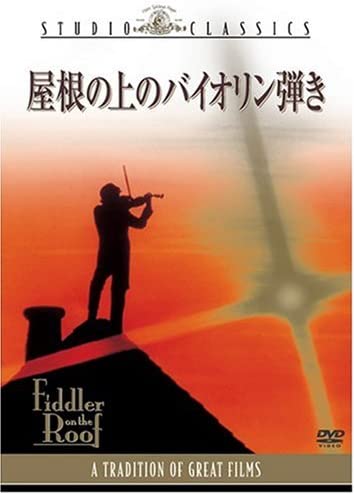
ただし私が(7)の『屋根の上のバイオリン弾き』を見たのは、それよりもはるかにおそく、日本公開(71年)の30年後、ようやく今世紀にはいってからだった。きっかけは1998年に、この映画のもとになった舞台の演出・振付家で、映画版の振付家でもあったジェローム・ロビンスが79歳で死んだこと。そしてそのしばらくのち、アメリカのインターネット新聞で、かれが1953年にアメリカ下院の非米活動委員会に喚問され、したしい友人たちを「反米的な共産主義者」として名指していたことを知った。
そりゃあ、おどろきましたよ。なにしろ『王様と私』や『ピーター・パン』や『ウエスト・サイド物語』のジェローム・ロビンスが、かつてエリア・カザンと同様の裏切りをせまられ、あえなくそれに屈してしまっていたというのだから。
――それにしても、なぜロビンスまでが?
気になってしらべるうちに、もっとも大きな理由がユダヤ人差別にあることがわかってきた。かれは20世紀はじめに旧ロシアの寒村からニューヨークに逃れてきたユダヤ人難民二世だったのである。しかも元共産党員で同性愛者でもあったから、いわば三重のマイノリティとして、あからさまな脅迫の対象にされてしまったらしい(脅迫の詳細は、のちに『ジェローム・ロビンスが死んだ』という本に書いたので、関心のある方はそちらをのぞいてみてください)。
その結果、カザンと同様に、ロビンスもまた、みずからの裏切りによって深い傷を負うことになった。そうした苦しい時期につくった、いわばカザンの『波止場』に当たる作品が『屋根の上のバイオリン弾き』だったのです。
――おなじ寒村でユダヤ人と仲よく暮らしていたロシア人たちが、とつぜん狂熱的なポグロム(反ユダヤの暴行と殺戮)の徒に化してしまう。そのことの底知れない恐怖ね。かつて旧ロシアで両親や祖父母が味わった恐怖を、逃亡先の自由の国アメリカ合衆国で、じぶんが体験するはめになった。日本では森繁久弥主演で名高いあのミュージカルが、よもやこんな作品だったとは。そんなこと、長いあいだ見逃していた映画を世紀をこえてDVDで見るまでは、考えもしませんでしたよ。
テオ・アンゲロプロスの『旅芸人の記録』が日本で公開されたのが1979年。この映画にただならぬ衝撃をうけ、以来、ギリシャ現代史を背景にした一連の叙事詩的映画を、ことごとく追いかけつづけることになった。したがって『旅芸人の記録』でもいいのだけれども、さんざん迷ったすえに、なぜか(8)の『蜂の旅人』という、アンゲロプロスにしては例外的にわかりやすい作品をえらんでしまった。

マルチェロ・マストロヤンニ扮する老いた養蜂家が、家族と別れ、花蜜採取のための最期の旅をする。したがってこれもアンゲロプロス好みのロードシネマのひとつなのだが、ほかの作品に見られるような複雑に入り組んだ時空のしくみはない。「わかりやすい」というのはそういう意味です。
なかでも旅の途中、第二次大戦後の激しい内戦時代に、ともに戦った左派のゲリラ仲間を病院に見舞ったのち、もうひとりの太った友人と3人で海岸で酒を酌み交わす短い場面――そこでの病人役のセルジュ・レジアニがじつにいいのだ。その昔、『情婦マノン』や『肉体の冠』などのフランス映画で、色男の小悪党役を溌剌と演じていたレジアニが、老いたのち、こんなにすばらしい演技をしていたとは――。
レジアニは1922年、マストロヤンニは1924年の生まれだから、ちょうど内戦で右派勢力に敗北した青年ゲリラの世代にあたる。そしてアンゲロプロスは1935年生まれ。したがって、じぶんよりも10歳ほど年長の、いわば若い叔父たちの経験をあつかった映画を撮ったことになる。
――「海よ! おれは歴史とすれちがって、このザマだ! おーい、聞こえるか!」
冷たい海辺で大きな鴉のように両腕をひろげ、よろよろと踊る老優レジアニにこう叫ばせたとき、私と同世代の監督はなにを考えていたのだろう。老いた元ゲリラたちが古傷をなめあっている? かもしれないけど、ちがうかもしれない。さいわいアンゲロプロスのDVDボックス(全4巻)が手もとにある。もういちどあれを、ぜんぶ見なおしてみるか。
ここまで書いてきて、どこからか、こんな声が聞こえてきた。
――なんだい、「わが人生のベスト10」といっても、現代史がらみの社会派映画ばかりじゃないの。
でも、これはやむをえない。なにしろ私が育った20世紀半ばの日本は、敗戦と占領という厚い障壁のうちに封じ込められていたのでね。あの当時、世界でなにが本当に生じていたのか――それを知るには10年も20年も、ときには50年を軽く越えるほどの時間が必要だった。その時間のずれを縮めるきっかけを与えてくれたのが、往々にして、この種の映画だったのです。
たとえば――
わずか30年ほどまえまで、われわれ日本人が、中国や韓国などの近隣諸国で、人びとがどのように暮らしているかを知るのはきわめてむずかしかった。台湾も例外ではない。それまでの半世紀、大日本帝国の植民地だったこの島に、戦後すぐ、中国本土で共産党軍に敗れた国民党軍がなだれこみ、新しい支配者として君臨するようになる。そのさい発布された戒厳令の解除されたのが、なんと40年後の1987年。情けないかな、その間、私たちはいま隣国がどんな状態に置かれているのかを、まったくといっていいほど知らずにいた。
私の場合、それを生々しい現実として知ったのは、戒厳令解除の2年後に公開されたホウ・シャオシェン(侯孝賢)の(9)『悲情城市』と、さらにその2年後の、早逝したかれの盟友、エドワード・ヤンの『牯嶺街〔クーリンチェ〕少年殺人事件』という、ふたつの大作によってだった。なかで『悲情城市』をえらんだのは私が老人だから。もうすこし若ければ、かならずや『牯嶺街』のほうをえらんでいたにちがいない。
天皇の玉音放送で植民地時代が終わり、あらたに自由な国を築こうと活動をはじめた台湾人たちに、新来の国民党軍の陰惨な暴力(白色テロ)がおそいかかる――。
この「2・28事件」にいたる1年半に、台湾の老若男女(この時期、青年たちは日本語を流暢に話していた)はどのように生き、死んでいったのか。そのいきさつを、港町・基隆の船問屋一家を中心に、しっかりと歴史に刻み込んでゆく。こんなこと映画にしかできんよ。すごいと思いましたね。
いったんは解放された国家が、かわって登場した政治権力によって、ふたたび戒厳令下におかれる。その点は韓国や中国の戦後もおなじ。そして、やはり台湾とおなじ1987年に、韓国では長期にわたる戒厳令体制が大規模な民主化運動によって終わり、前後して中国でも、それまではないに等しかった表現(映画・文学・音楽など)の自由の領域が、すこしずつ拡張されはじめた。そして30余年後、あろうことか、こんどは香港が中国政府の圧政(赤色テロ?)下に追いこまれている。『蜂の旅人』も『悲情城市』も、まだまだ忘れ去るわけにはいかないのですよ。
好きな老人映画を一本、ぜひ入れておきたい。となると、やはりベルイマンの『野いちご』かな。――などと考えていたら、(10)の『わたしは、ダニエル・ブレイク』にぶつかった。アイルランド革命を背景にした大作『麦の穂をゆらす風』以来、まめに見つづけてきたケン・ローチが80歳をこえて撮ったかれの最新作。となれば、もうこれで行くしかあるまい。
主人公のダニエルは腕のいい大工で、さいきん老妻を亡くし、じぶんも心臓発作で働くことがむずかしくなっている。しかたなく失業交付金にたよる決心をしたが、いかんせん書類づきあいが苦手で、パソコンもインターネットも触れたことすらない。その上、いくら役所に重い足をはこんでも、相手がいまどきの冷ややかな応対しかしない公務員とあって、いっこうに事態が先にすすんでくれない。「いまどきの」というのは、サッチャー首相の過激な新自由主義改革によって、戦後の福祉国家(分厚い公的補助)の骨組みが突き崩された1980年代以降のイギリスでは、という意味――。
「こいつは拷問だ。おれには屈辱でしかない」
でもね、たしかに話は息がつまるほど辛いのだが、映画そのものは、かならずしも辛いだけではない。底のほうに、時折、明るい光がちらりと見えたりね。この明るさは私の個人的な印象ではなく、おそらく意図されたものなのだろう。そのことは監督のケン・ローチが、ダニエル役に、わざわざデイヴ・ジョーンズという老コメディアンを配したことからも推測がつく。
映画も終わり近く、そのジョーンズ氏扮する禿のダニエルが、役所の外壁に「私はダニエル・ブレイク」「ひとりの人間だ。市民だ。敬意を求める」と、みずからの独立宣言を塗装用スプレーでいくつも大書し、そのまえに坐り込む。
――ほほう、ダニエルさん、なかなかの役者じゃないか。
しだいに増えてきた群衆が「いいぞ、がんばれ!」と口々に叫んだり、「よくいってくれた。ダニエル・ブレイク。あいつに爵位をやれ!」とホームレスの老人がふらふらと怒鳴って歩いたり、真昼の路上が、あっという間に、ちょっとしたシェークスピア劇の一場面のようになってしまったのだから。
私はダニエルとちがって、もう30年以上、パソコンとつきあっている。
でもそれは私がじぶんの小世界で辛うじてそうしているだけ。もしダニエルのような状態に公的に放りだされたら、たちまち手を上げてしまうに決まっている。いや私だけじゃないぞ。パソコン環境の変化のいきおいに追いぬかれ、じぶん一人ではコロナ・ワクチン接種の手つづきも満足にできなくなった、現今の老人諸氏の大半がね。
かくして、なんとか「日本映画」までたどりついたと思ったら、あれれ、コメントの余地がほとんど残ってないじゃないの。いちおう注意はしていたつもりなのに、うっかり書きすぎてしまったらしい。しかたない。今回は「ベスト10」のリストを紹介した上で、あたまの3本についてだけ(見本として)コメントし、あとは全体の感想をざっと述べるだけにさせてもらいます。
(1)『有りがたうさん』(清水宏、1936年)
(2)『人情紙風船』(山中貞雄、1937年)
(3)『たそがれ酒場』(内田吐夢、1955年)
(4)『洲崎パラダイス 赤信号』(川島雄三、1956年)
(5)『流れる』(成瀬巳喜男、1956年)
(6)『どん底』(黒澤明、1957年)
(7)『おとうと』(市川崑、1960年)
(8)『砂の女』(勅使河原宏、1964年)
(9)『風の谷のナウシカ』(宮崎駿、1984年)
(10)『海街 diary』(是枝裕和、2015年)
(1) の『有りがたうさん』は私が生まれる2年まえに封切られた映画だが、喜寿をすぎて、はじめてそれをDVDで見た。よかったなァ。なによりも登場する人びとのかわす会話が、あっけにとられるほどのろいのがいい。清水宏のほかの映画はこれほどではないから、おそらく意図して試みられた「のろさ」なのだろう。
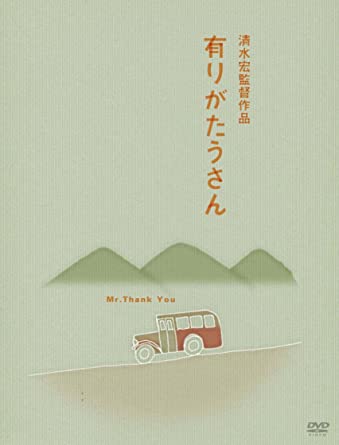
映画の舞台は下田から天城街道経由で三島に向かう乗合バス。上原謙(いわずと知れた加山雄三のお父さん)の演じる運転手が、すれちがったり追い抜いたりする人たちに、そのつど「ありがとう!」とのんびり声をかける。そのため「ありがとうさん」と呼ばれるようになった街道一の人気者なのですよ、かれは。
このバスで、東京に売られていく少女とその母親、流れの水商売の女、インチキくさい付け髭男、トランクを抱えた行商人、あわてて出産に駆けつける産科医など、たまたま乗り合わせた人びとの演じる、そうねえ、さしずめグランド・ホテル方式の庶民的な集団劇といった感じかな。
終わりに近く、白いチマチョゴリの朝鮮の女たちが、大きな荷物を背負った男たちと連れだって街道を行くのに出会う。長期の道路工事を終え、つぎのトンネル工事の現場に向かうところらしい。「せっかくつくった道なのに、じぶんでは一度も歩かずに行ってしまうの」と女のひとりがいう。もちろんのろのろと。「死んだお父さんを置いて行くので、ありがとうさん、ときどきお花と水をやってね」――。
はるか戦前の映画で、こんなシーンに出会うとは思ってもいなかったので、すくなからず感動した。ふうん、むかしの映画も結構いろいろやっていたのだな。
ただ残念なことに、この『有りがたうさん』もふくめて、古い日本映画は保存状態が極端にわるく、映像も音声も、「おそらく本当はこんな作品なのだろう」と、もとの状態を懸命に想像しながら見るしかない。
ところが、つい最近、テレビでひさしぶりに (2) の『人情紙風船』を見ておどろいた。2020年の東京国際映画祭のため、この作品をふくむ山中貞雄の遺した3作と、稲垣浩監督の『無法松の一生』の4本が、「4Kデジタル・リマスター版」として、見ちがえるほどの質のよさで修復されていたのだ。そう、ほとんどフリッツ・ラングの『M』レベルでね。
――河竹黙阿弥の歌舞伎劇をもとに、大店の主人や博打打ちの一党に、いなせな髪結職人(中村翫右衛門)が立ち向かい、おなじ長屋に暮らす浪人(河原崎長十郎)夫婦の悲劇がそこに縒り合わされていく――。
といった筋立ての力もだが、それ以上に、この修復によってよみがえった江戸の街の生気に感嘆させられた。
第一に、街の奥にたたずむ屋台のそば屋や、夜祭りの山門にひしめく群衆など、暗闇を照らす提灯や行灯や常夜灯のおぼろな光のすばらしさ。撮影はアメリカ帰りの三村明。カラー化やデジタル特撮とひきかえに、いまの映画は、つまり私たちは、この繊細な効果を惜しげもなく手放してしまった。くやしい。そう思わせるほどの美しさなのです。
そして第二に、長十郎と翫右衛門を中心に、市川莚司時代の加東大介など、独立系の歌舞伎劇団「前進座」の集団演技のすばらしさ。修復以前は、うすぼんやりとしか見えなかった長屋の住人たちの表情や所作が、細部まで、いきいきと映し撮られている。かれらの演技力もだが、これまで伝説としてしか知らなかった山中貞雄のセンスのよさを、はじめて実感できた。これも長生きしたおかげ。
まだ開店まえの巨大な大衆酒場で、若い歌手がシューベルトの「菩提樹」の練習をしている。そこに小杉勇扮する常連の老画家が裏階段を上って登場――。(3) の『たそがれ酒場』はこんなシーンからはじまっていた。
この映画が封切られた前年に私は高校にはいり、新宿かどこかの三番館でそれを見た。戦時中に満映(満州映画協会)の一員として海を渡った内田吐夢が、敗戦8年後に帰国し、日本映画界に復帰して撮った2作目がこの映画だったのです。
第一作が片岡千恵蔵主演の時代劇『血槍富士』だっただけに、新作が、現代の大衆酒場を舞台に、おおぜいの客や店のスタッフが織りなす一夜のできごと、という趣向でつくられていたので、ちょっと意外な感じがした。大学教師と学生たちが腕を組んで「若者よ」(当時はやりの革命歌)を合唱すると、苛立った元軍人(東野英治郎)とその部下(加東大介)が軍歌を挑発的にがなってみたりね。となりでは若い自衛隊員がふたり、知らんぷりして飲んでいる。なるほど、1955年というのは、警察予備隊が陸上自衛隊として本格的に再発足した翌年でもあったのだな。
つまりは乗合バスや江戸の長屋と同様、これもまた巷の大衆酒場を舞台にしたグランド・ホテル方式の映画なのである。なにせ貧しい時代だったので、製作コストを下げるため、新宿西口の「しょんべん横丁」に実際にあった酒場をモデルに、大がかりなセットを一つだけつくり、ロケは一切しない、というやり方で撮ったらしい。
ただし空間も時間もきちんと限定されているから、どうしても演劇的になってしまう。その演劇的な世界をどう映画的に構築するか――それがグランド・ホテル式映画の見せどころになる。その点、『たそがれ酒場』はけっこう健闘していたな。喧噪のまっただなか、何十もあるテーブルの彼方で、東野と加東がひそひそ話しているのが、小さく見える。これこれ、これこそがグランド・ホテルものの醍醐味なのよ。
こうして見ると、私はこの種のつくりの映画がなかなかに好きらしい。あとにくる (6)の『どん底』はもとより、(4) の『洲崎パラダイス 赤信号』や (5)の『流れる』、さらには (8)の『砂の女』にさえ、そんな好みの証しが見てとれる。ロバート・アルトマン監督の映画が好きなのもそのせい。なのに、かれの『ショート・カッツ』を「ベスト10」から外してしまった。ちょっと早まったかな。
このあと『洲崎パラダイス 赤信号』から、市川崑のカラー作品『おとうと』をあいだにはさんで、『砂の女』までがモノクロで撮られている。
――日本映画のカラー化についていうと、1951年に木下恵介の『カルメン故郷に帰る』が「国産初の総天然色映画」として賑やかに登場したのち、溝口健二が『楊貴妃』をカラーで撮ったのが1955年。ついで58年に小津安二郎の『彼岸花』と成瀬巳喜男の『鰯雲』がつづき、すこし遅れて『おとうと』が1960年――。
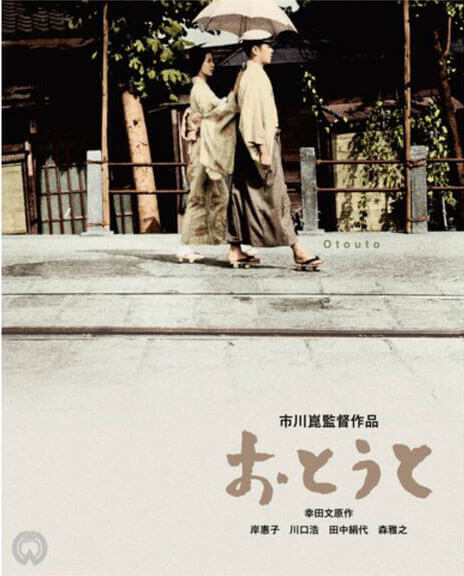
ただし遅れた代わりに、市川崑と宮川一夫(撮影)のコンビは、先行者たちとはことなる凝りに凝った工夫を用意していた。通常はフィルムや印画紙から取りのぞく銀をわざと残す「銀残し」という手法で、カラー・フィルムの彩度を低くおさえ、いかにも大正ふう(関東大震災前後の幸田露伴一家の物語なのでね。原作は幸田文)に、渋く落ちついた画をつくりだしてみせた。その色味のよさに、さすが、と思いましたよ(市川崑の初カラー作品は1956年の『日本橋』だがこれは未見)。
ただし「総天然色映画」のケバケバしさを嫌って、わざと彩度を落としたという点では、すでにジョン・ヒューストンの『白鯨』という前例があった。こちらは「銀残し」ではなく、カラー・フィルムにモノクロ・フィルムを重ねて焼くという手法だったと思う。エイハブ船長役はグレゴリー・ペック。あの映画が製作されたのが1956年で、日本でも同年に公開。やけに暗い映画だったけど、高校生の私は目白駅そばの名画座で見て好感をもった。市川たちの頭には、もしかしたらあの映画があったのかもしれない。
――と、ここまで「わが人生の映画ベスト10」稿を延々と書いてきて、洋画と邦画を問わず、往年のモノクロ映画の地力をあらためて確認することになった。そのため大量の DVD とつきあい、ちょいと疲れましたがね。遠からず消えていく私にとって、これは思いもかけない幸福な発見でしたよ。
より具体的にいうと、1960年前後に開始されたモノクロからカラーへの転換は、たんなる進化(進んだカラー映画が遅れたモノクロ映画を駆逐する)ではなかったということ。たとえ短期的にはそう見えたとしても、長い映画史の目で見れば、この転換は進化というより複線化、すなわち「これまでモノクロ一本でやってきた映画が、モノクロとカラーの二方向に分岐していく」という方向で考えたほうが、より適切なのではあるまいか――。
映画研究者でも批評家でもない、ひとりの町場の映画ファンが、こんど『M』や『人情紙風船』のデジタル・リマスター版に接したことで、思いがけず、そう考えるようになった。そしてそうなると、エイゼンシュテインの『戦艦ポチョムキン』とか、パブストの『三文オペラ』とか、ルネ・クレールの『巴里の屋根の下』とか、ぜひとも原型に近い、もしくはそれを超える精度で見てみたい作品が、どんどん登場してくる。
日本映画でいうと、たとえば『按摩と女』や『簪』や『小原庄助さん』といった、さきの清水宏の諸作がそれ。いまでもかなりのかずを DVD で見ることができるけれど、どれも保存状態がひどく、見る側が、もとの(あるべき)音や映像をじぶんの想像力の限りをつくして復元する(したつもりになる)という難業が必要になる。
でも、この先はちがうでしょうな。デジタル・リマスター技術の成熟その他によって、この種のむなしい想像力の酷使から解放されるにつれ、モノクロ映画の見方も、これまでとは大きく変わっていくにちがいない。
その結果、「見る側」でも「つくる側」でも、人びとが「モノクロ映画にできることとできないことがあるように、カラー映画にもできることとできないことがある」と、ごく自然に考えるようになる。なにしろ、木下も溝口も小津も成瀬も、そこに後発の黒澤明(1970年の『どですかでん』で初のカラー化)もふくめて、カラー化したのちの作品より、モノクロ時代にかれらが撮った作品のほうが明らかにスゴイのだから。その事実が、モノクロからカラーへの変化の肝どころが複線化であることを、逆方向から証明している――。
このことと関連して、もうひとつ乱暴なことをいわせてもらうと、いまの女優にくらべて、なぜか私の目には、モノクロ時代の女優の演技のほうが圧倒的によく見えてしまうのです。この「ベスト10」でいえば、『洲崎パラダイス 赤信号』の新珠三千代、『流れる』の高峰秀子、『どん底」の香川京子、『おとうと』の岸惠子、『砂の女』の岸田今日子といった女優たち――。
で、だれでもいいが、たとえば『洲崎パラダイス 赤信号』の冒頭で、安物のきものをゆるく着た細腰の女(新珠三千代)が夕暮れの橋上にふらりと立っている。その立ちすがたがじつにいいのです。新珠三千代といえば宝塚出身の上品な美人女優。その新珠が元娼婦という最下層の蓮っ葉女を、一分の隙もなく完璧に演じきっている。まずはその演技力に圧倒された。
新珠だけでなく、この1年半、彼女たちの映画をまとめて見て、「いやはや、むかしの映画女優や新劇女優の力量は大したものだったのだな」と、あらためて舌を巻いた。いや女優にかぎらないぞ。『洲崎パラダイス 赤信号』での新珠の相手役――気弱で無気力な、とことん情けない男に扮した三橋達也にしても、見ちがえるほどよかったのだから。「えっ、これがあの?」と度肝を抜かれたほどにね。
――と、こう書いてきて、反射的に、以前、この連載の「樹木希林と私たち」の章で書いたことがらを思いだした。もう30年以上まえになるが、ひさしぶりに会った樹木希林と話していて、「このあいだ黒澤明の『生きる』をテレビで見たけど、あのお通夜のシーン、やっぱりすごいよ。俳優たちも、めちゃくちゃにうまいしさ」と私が口走ったら、「でもね」と樹木希林がいった、という話です。
「うまさという点では、いまの俳優のほうがうまいと思う。だって、あのお通夜のシーンは何週間もかけて撮ったものなのよ。いまは映画でもテレビでも、稽古も読み合わせもなしで、すぐ本番だもの。もしむかしみたいに時間やお金がつかえれば、いまの俳優だって……」
たしかにこれは彼女のいうとおり。いまの俳優にくらべて、むかしの俳優が「圧倒的によく見えた」のが事実だとしても、だからといって、その理由をただちに、ふたつの時代の俳優たちの「演技力」の差にもとめてしまうのはまちがい。圧倒的にすぐれた演技を可能にするには、それなりの「時間とお金」がいる。その「時間とお金」をどんどん剥ぎとってしまった果てに「いま」の製作現場がある。そのことを見ないふりして、すべてを俳優のせいにしてしまうわけにはいかない――。
彼女がそういうのはわかるし、私も同感する。ただね、だからといって、そのすべてを現今の製作現場の劣化のせいにしていいのかしら。一方で、そんな気がちらっとしてくるのもたしかなのです。
たとえばテレビCM――。
いまの人気俳優たちが普通にそうしているように、もしもあの時代、新珠三千代や高峰秀子や香川京子や岸惠子が毎日のようにテレビに登場し、明るい笑顔で化粧品や生命保険や旅行やビールや自動車の宣伝をしていたら、とムリを承知で考えてみる。答えは明白。そんな環境下で、かつて彼女たちが発していたような重厚な輝きが生じようわけがない。とすれば、いま私が記憶しているような新珠三千代や高峰秀子や香川京子や岸惠子といった女優たちは、どこにも存在しなかったということになってしまう。
では、新珠も高峰も香川も岸も存在しえない環境での輝き――希林のいう「いまの俳優のうまさ」とは、いったい、どんな性質の「うまさ」で、どんなつよさの「輝き」なのだろう。じつをいうと、この「ベスト10」に成瀬巳喜男の『流れる』と是枝裕和の『海街 diary』を並べてえらんだのも、そのことをじっくり考えてみたいと、ひそかに企んでのことだったのです。
1956年 の『流れる』と 2015年の『海街 diary』は、老若ひっくるめて、それぞれの時代を代表する女優たちの集団劇(いわば腕くらべ)という共通点をもっている。すなわち『流れる』でいえば、栗島すみ子、杉村春子、田中絹代、山田五十鈴、高峰秀子、岡田茉莉子たちの。そして『海街 diary』でいえば、樹木希林、大竹しのぶ、キムラ緑子、綾瀬はるか、長澤まさみ、夏帆、広瀬すず……というように。
どちらの映画も私は大好きだし、女優たちの演技もすばらしい。いのちあるかぎり、このさき二度も三度も見ることになるだろうことは、まちがいない。
でもね、テレビCMのある時代とない時代とでは――たとえば樹木希林と杉村春子、綾瀬はるかと高峰秀子、長澤まさみと岡田茉莉子とでは、演技の質は大きくちがっているはずなのですよ。では、どこがどうちがうのか。もはやそのことを考えている余裕はない。ざんねん。別の機会に、またあらためて。
この「最後の読書」も今回でおしまい。開始したのが2017年5月だから、ほぼ5年という長い連載だったことになる。
年齢でいえば79歳から83歳にかけて。その間、多くの人がしるす老いの光景とつきあい、それをじぶんの体験と付き合わせることで、老人とはどういう生物なまものなのかが徐々にわかってきた。それは私にとっても、けっこう新鮮な発見だったのですよ。
でも、その新鮮さもいつしか薄れ、おそらく「老人」という在り方に飽きがきたのでしょうな、かたわらに「あれ、これでおしまい? もうこの先はないの?」とボヤく私がいることに気づいた。そこで見つけたのが「もうじき死ぬ人」という在り方です。すなわち「老人」の先、あちらに向かって出発するすこし前に、「もうじき死ぬ人」という短いステージを想定してみたらどうだろうか――。
ゆっくり考える時間がないので、いそいでいってしまうと、いま終えた連載の「老人=私」は、おびただしい過去の記憶に支えられていた。対するに「もうじき死ぬ人=私」には、過去だけでなく、私がいなくなったあとにくる世界、つまり未来に向かって広がろうとする意欲が、わずかながら感じられる。死が目前に迫っているだけに、かえってね。
――「老人」との付き合いはもういいや。ここらで一気に「もうじき死ぬ人」になってしまおう。いまはそんなことをぼんやり考えています。
(おわり)
※「最後の読書」は今回が最終回となります。ご愛読ありがとうございました。当連載の後半をまとめた単行本『かれが最後に書いた本』は、新潮社から2022年3月28日に刊行予定です。連載の前半は『最後の読書』として刊行されています(読売文学賞受賞)。
映画『屋根の上のバイオリン弾き』製作・監督ノーマン・ジュイソン、原作ショーラム・アレイハム、脚本ジョセフ・スタイン、製作ミリシュ=カーティア・プロ作品、配給ユナイト、1971年
津野海太郎『ジェローム・ロビンスが死んだ』平凡社、2008年→小学館文庫、2001年
映画『蜂の旅人』監督・脚本テオ・アンゲロプロス 製作テオ・アンゲロプロス=ギリシャ映画センター=マラン・カルミッツ=RAIトレ作品、配給フランス映画社、1986年
映画『悲情城市』監督・侯孝賢、1989年
-

-
津野海太郎
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 津野海太郎
-
つのかいたろう 1938年福岡生まれ。評論家。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『花森安治伝』、『百歳までの読書術』、『読書と日本人』ほか。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら









