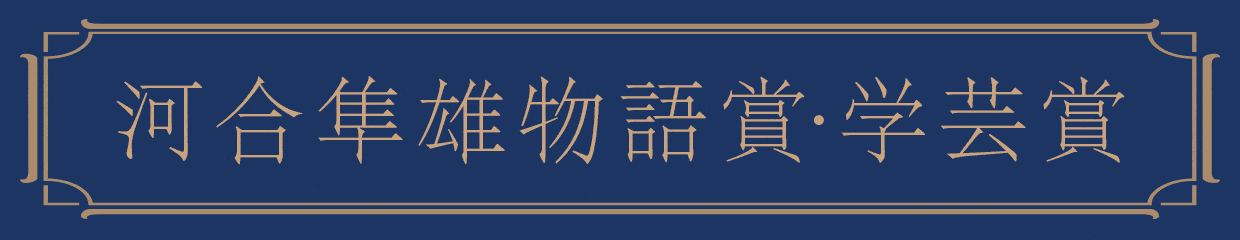5月29日、一般財団法人河合隼雄財団の主催(協力:新潮社)による「河合隼雄物語賞」「河合隼雄学芸賞」の第7回選考会が開催され、授賞作が決定しました。
第7回河合隼雄物語賞

第7回河合隼雄物語賞は、三浦しをんさんの『ののはな通信』(2018年5月 KADOKAWA刊)に決まりました。選考委員のみなさん(上橋菜穂子氏、 小川洋子氏、 後藤正治氏、 中島京子氏=五十音順)は、「思春期にはじまる二人の女性の二十数年にわたる関係を、書簡体によって見事に物語へ昇華させた作品である」ことを授賞理由としてあげました。三浦さんは受賞の報を受けて、次のように述べたそうです。「突然のことに驚いておりますが、このような賞を頂けて大変光栄です。本当にどうもありがとうございます」。
著者略歴
三浦しをん(みうら・しをん)
小説家。1976年東京生まれ。2000年『格闘する者に〇(まる)』でデビュー。以後、『月魚』『ロマンス小説の七日間』『秘密の花園』などの小説を発表。『悶絶スパイラル』『あやつられ文楽鑑賞』『本屋さんで待ちあわせ』など、エッセイ集も注目を集める。 06年『まほろ駅前多田便利軒』で直木賞を、12年『舟を編む』で本屋大賞を、15年『あの家に暮らす四人の女』で織田作之助賞を、19年『ののはな通信』で島清恋愛文学賞を受賞。ほかの小説として、『むかしのはなし』『風が強く吹いている』『仏果を得ず』『光』『神去なあなあ日常』『天国旅行』『木暮荘物語』『政と源』『愛なき世界』などがある。
第7回河合隼雄学芸賞
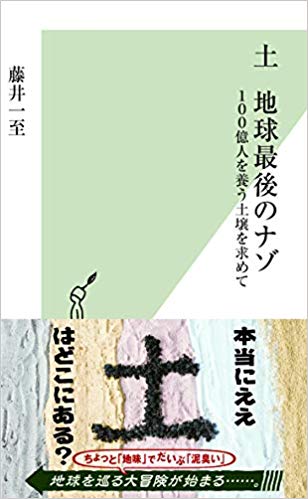
第7回河合隼雄学芸賞は、藤井一至『土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて』(2018年8月 光文社刊)に決まりました。選考委員のみなさん(岩宮恵子氏、中沢新一氏、山極壽一氏、鷲田清一氏=五十音順)は、「地球を構成する12種類の土を求めて、あらゆる地域でそれを体で確かめ、これをもとに現代の環境問題や食糧問題、人口問題を含めた地球課題を闊達な筆致で論じ、新しい視点を提供する一冊」という授賞理由をあげています。藤井さんは受賞の報を受けて、こう述べたそうです。「このたびは、身に余る賞を頂きありがとうございます。河合先生の研究しておられた文化(カルチャー)の語源は地を耕すことにある、と聞いており、そこにご縁を感じております」。
著者略歴
藤井一至 (ふじい・かずみち)
土の研究者。国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所主任研究員。1981年富山県生まれ。京都大学農学研究科博士課程修了。博士(農学)。京都大学研究員、日本学術振興会特別研究員を経て、現職。カナダ極北の永久凍土からインドネシアの熱帯雨林までスコップ片手に世界各地、日本の津々浦々を飛び回り、土の成り立ちと持続的な利用方法を研究している。第1回日本生態学会奨励賞(鈴木賞)、第33回日本土壌肥料学会奨励賞、第15回日本農学進歩賞受賞。著書に『土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて』『大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち』(山と溪谷社)など。
両賞とも、授賞作には正賞記念品及び副賞として 100 万円が贈られます。 また、受賞者の言葉と選評は、7月5日発売の「新潮」に掲載されます。
河合隼雄物語賞・学芸賞についての詳細は、一般財団法人・河合隼雄財団のHPをご覧ください。
授賞作発表記者会見

まず、物語賞の授賞作について小川洋子さんから。
この小説は、女子高で出会ったののとはなという二人の少女が、友情という言葉には留まらない、もっと切実な、神様の存在をも否定する究極の愛を二十数年かけて育てていく、その過程を書簡体で描き出した作品です。どんなに大事な記憶もやがて時間とともに薄れていく、その空しさがテーマになることが文学では多いですけれども、この小説は逆で、二人の距離や立場が遠くなればなるほど彼女たちの育んだ記憶が不変なもの、強固なものになっていく。そこがユニークなところだと思いました。その記憶が彼女たちを生かす糧になる、記憶こそが支えになるというテーマが本書の根底を支えています。記憶を繋ぐことと物語をつくることが非常に近しいという意味で、物語賞にもふさわしいのではないかと思います。最初はののという少女のほうが主導権を握っていて、もう一人のはなを積極的に誘うんですけれど、やがてそのはなが自分の身のうちに抱えている、暴れまわるようななにか、翼を持ったなにかに突き動かされてラストでダイナミックな変化を見せる。しかし、取り残された形ののののほうにもちゃんと自分の居場所がある。そういう二人の女性が成長し、変化して自分の生き方を見つけていくというところも、読み応えがある小説だなと思います。

続いて学芸賞授賞作について、山極壽一さんが語りました。
藤井さんは土壌の研究者なんですね。もともと京都大学の農学研究科の大学院を出られて、土に惚れ込み、土に憧れ、いまは森林総研(森林総合研究所)の主任研究員としていまだにその研究を続けていらっしゃる。私たちは土の魔術というものをおぼろげながら知っています。例えばほんのわずか5gの土の中にも、たくさんのバクテリアが棲んでいて、キノコの菌糸も何キロにもわたってそこに折り畳まれている。それが土をつくり、土を栄養としている植物や動物を育てるという魔法のような力が土にはある。藤井さんが行ったのは地球という非常に大きなスケールで、地球を構成する土は12種類にしか分けられないのですが、それをすべて体験するためにスコップを持って世界中を旅します。その過程でまずは旅をするお金をどうやって作ったらいいかずいぶん思い悩みながら、自分の夢を達成するために苦難を乗り越えて土に巡りあい、スコップで掘り、手で触り、舌で舐め、そこまでして土の実態を知る。そして日本に限らず世界中の人々が使ってきた土という存在を、土壌学の見地から明らかにする。例えば、一般に肥沃な土壌といわれるものはウクライナと北米の一部、中国東北部にしかない。それは古来、人々の生産の現場であった。農業ですね。それをめぐって様々な争いも起こり、人口移動も土壌の質によってもたらされた。とくに古代文明の三大文明は肥沃な土壌、プラス雨量が大きな風土の変化をもたらしてきた。乾燥すると下から水が上がるときに塩も運んできて、表面の水が乾くと塩分だけが残る。その塩化作用によって穀物ができなくなって文明が滅んだという歴史的経緯があります。
いま地球の人口が73億人から100億人になろうとしている、その巨大な人口を支える土壌がどういうものであるべきかにまで考察を加えて、自分が求めていた夢の土というものをもとに、地球のさまざまな環境問題や人口問題、食糧問題について言及した。そういう膨大な地球の動きを、土という観点から分析した書物はこれまでなかった。非常に目新しく、なおかつ目から鱗の分析が随所に見られる好著だと思っております。
今回の授賞は河合隼雄賞としては初めて自然科学系の分野の作品になります。個人的な感想を申し上げると、私自身も研究者ですが、ある対象に惚れ込んで長年それを追い求めて地球を歩くのは大変な苦難の連続です。ときには「なんでこんなことやってるんだろう」と自問自答する瞬間が何度も訪れますが、そういうことも正直にこの著者は書いていて、研究という世界の深みについてもきちんと教えてくれる好著であると思います。

続いて、質疑応答が行われました。まずは物語賞から。
Q.書簡体であることの成否はありますか?
A.二人の女性の二十年以上にわたる人生全体を書簡体で描き切るのは、技術も要りますし、冒険だったと思うんです。ここは選考委員の間でも意見が少し違っていて、私自身はじつは書簡体じゃない文章で読みたかった部分もありました。しかし、いろいろ議論を重ねていくなかで、彼女たちがなにものにも代え難い二人だけの記憶を宝石のようにしてずっと持ち続ける、それが宝石になった瞬間は書簡体であるがために描かれていない。二人が初めて関係を結んだときになにがあったか、その現場は言葉にできなかった、ということが書簡の形式を使ったことで成立している。じつは書けないことがある、それを受け入れるのが書簡体であると。だから本書は成功だったんだと、自分自身気づかされました。
Q.書簡体でない文章で読みたかった部分とは?
A.二人がどういう一夜を過ごしたか、そこを描写で読みたかったと一瞬思ったんですけれども、選考委員としてはわがままだったなと。自分で書いてみろと言われたら書けないと思います。
Q.東日本大震災の描写が出てきますが、震災文学としての評価はなにか話し合われましたか。
A.震災のことが議論の中心になる時間はありませんでした。ただ、最初にグリコ森永事件が出てきたり、震災の話題が出てきたりということで、主人公の二人がどういう年代かがわかるようになっていまして、じつは三浦さん自身よりも少し上の世代に設定されていることが話題になりました。つまり手紙を書くことが不自然でない最後の世代です。
Q.物語ってなんだろう、ということを意識させるのはどのあたりでしたか?
A.小説をずっと読んでいくと二人の間にいろいろなことがあって、醜い別れがあったり裏切りがあったりするわけですけれども、そういうものが全部淘汰されて美しい記憶だけが残る。「記憶だけが私たちを生かす糧になる」という重要な文章が出てくるんですが、やはりそこが、記憶を持つことが物語をつくって生きるということで、今回物語賞としてこの小説がふさわしいな、という話になりました。
Q. 今回の授賞については満場一致で決まったのでしょうか。
A.それは非常に難しいところで、どんな選考会でもそうですけれど、他の作品を推す人ももちろんいらっしゃいました。先ほど申し上げたように話をしていくうちにだんだん読み方にちょっと新しい光が射して気持ちが変わってくるというか、でもそのほうがいい作品が選べると思います。
Q.三浦さんのこれまでの作品との違いや成長は感じられましたか。
A.三浦さんご自身の変化や成長を語る資格は選考委員にはないので、純粋に作品と一対一で向き合ったということなんですけれども、とくにこの物語賞の場合は作家というより作品ですね。この作品と自分が向き合ったときに物語に対する思いがどれだけ揺さぶられるか、というようなことは作品を選ぶときの重要なひとつのポイントになっていると思います。
続いて、学芸賞の質疑応答が行われました。
Q.藤井さんは他にも著書がありますが、今回は集大成、決定版というようなものなのでしょうか。
A.藤井さんの前の著作を読んで評価したわけではなく、この本そのものがどれだけインパクトがあるのかを評価しました。やはり視点の斬新さ、これは学芸賞ですから、学術の上での信憑性と大きなインパクトが我々の議論の対象になります。これまでの常識を一変させるような新しい視点が展開され、我々の知らない事実の展開がある、そこが評価の対象になりました。
Q.カジュアルな文体で書かれていて読みやすい印象ですが、それも含めての評価なのでしょうか。
A.学術書は気づきをもとに証明をしていくことが必要ですが、これは一般書ですから複雑な証明はとりあえず脇に置いて、自分の気づきが深く入り込んだ事実をきちんとわかりやすく解説しているところ、それから我々がいままで常識としていた“未開だから文明が発達していない”と言われていたようなことが、じつは土壌が原因で生産性の問題が起こり、その土地と文明の発達に大きな影響を与えているという観点などは「お、そうなんだ!」という感動が出てくる。そういう意味では非常に優れた筆致です。
Q.今後さらに土に関して研究し、発信してもらいたいですか?
A.それは選考委員の間でも話題になりました。今回「地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて」と、かなり未来に期待を持てるようなタイトルになっていますが、本人は土が好きで地球上を歩き回って、その地を這うような仕事のなかから見つけ出した事実や気づきを通じてさまざまな定義づけをしてくれています。見方を変えればこの事実をもとに色々な展開が可能です。未知数ではあるけれども、未来に大きな価値をもたらしてくれるかもしれないなと思いました。これは他の選考委員の先生方のコメントもぜひ聞いてみたいと思います。
中沢新一さんは、学芸賞授賞作についてこう語りました。
自然科学のもっともらしい話をしてますが、いや、実際もっともですが、面白い本です。僕はこれを読んで「これは漫画の原作に一番いいな」と思いました。タイトルは「土壌バカ一代」。(一同笑)読んでいて土壌バカ以外の何者でもないという京都大学の伝統をものすごく感じました。京都大学は自然科学からときどきすごくとんでもないことやる人が、ゴリラ学とか、いろいろなところにいますが、その一人ですね、この人は。これで世渡りできるのかと思うぐらい土壌バカなんです。だけど一個一個の事実は正確で、ギャグも入っていて、これを生かすとすぐ漫画の原作になる。いま発酵菌の漫画とか農業関係の漫画とか、いっぱいありますけど土壌関係としてはこれがピカイチ。タイトルも気に入ってます。

会場が笑いに包まれるなか、「中沢さんの京大アホバカ論になにか反論は」と山極さんから求められると、鷲田清一さんはこう語りました。
反論なんかありません。アホでないとダメなんですよ、京大は。(一同笑)この授賞理由の中に「環境問題や食糧問題、人口問題を含めた地球課題を闊達な筆致で論じ……」と書いてありますが、ほんとはもっと論じて欲しいんです。「え! 土の視点からこんなことが見えてくるのか」というところにむしろ驚いて、この本に対する僕らのイマジネーションもすごく働くんですね。この本はいろんな問題を示唆していますけれど、本人はなんだかんだいってもやっぱり土が好きなんです。世界には12種類しか土がないんですけれども、それを求めて北極圏から赤道まで全部行って、スコップで掘って「育つかな?」とゴボウを植えたりして何ヶ月も居てまた次に行く。お金もない。先生にちょっと助けてもらってまた行く。その視野の狭さというか(一同笑)それがすごくいいんですよ。中沢さんが先ほど言っていた世代、今西錦司とか梅棹忠夫とか岡田節人とか山極壽一まで色々いたんですけど、ちょっと最近破格の人が途切れていたものですから。この人が38歳。それから他のところでバッタ研究した人(前野ウルド浩太郎『バッタを倒しにアフリカへ』光文社新書刊)、この人は結果的にアフリカ研究でアフリカの農作物の被害を減らすのにすごく貢献したんですけれども、本人は虫一直線で虫がワーッと顔にくっついてくると恍惚とする、そういう人がね。オタクなんだけど結果として現代的課題を解決するものに繋がっている。そのダイナミクスが学問の面白いところかなと思います。30代にこういうタイプの人が増えてきてるのがすごくいい。貧しそうなのでちょっと応援も。(一同笑)

再び中沢さんから。
ちょっと僕はエロチック文学だというふうにも感じました。世界中を捜し求める、スコップを使ってね。あ、これはエロチック文学だなと。こういう素敵なアホの方たちが切り拓いていく世界って、普通の文学とはちょっと違うけれども、それに匹敵するなにかを感じました。
「エロチックといわれると岩宮さんは」と意見を求められた岩宮恵子さん。
こういうお話を聞かせていただいて、初めて、そういう読み方もあるのかと気づきました。理系のオタクってすごいなと思いました。(一同笑)
選考委員の方々の言葉を受けて山極さんが「京大の総長としては忸怩たる思いがありますけれども、近年稀に見る逸材であります」と述べ、会場には再び笑いが起こりました。また中沢さんが「新書だけど結構カラーの頁が多くて写真がふんだんに使ってあって」と本の体裁について触れると「単行本にしてもっと写真を大きくして見せてもらえたら、本人の思いが伝わってよかったんじゃないかと。ほんとはね、たぶん現地に案内したいんだと思います。土そのものを見せたいんだと思いますよ」と、研究者としての感想も出ました。終始、ざっくばらんで和やかな雰囲気のなか、記者会見が終了しました。
-

-
考える人編集部
2002年7月創刊。“シンプルな暮らし、自分の頭で考える力”をモットーに、知の楽しみにあふれたコンテンツをお届けします。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 考える人編集部
-
2002年7月創刊。“シンプルな暮らし、自分の頭で考える力”をモットーに、知の楽しみにあふれたコンテンツをお届けします。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら