2017年8月23日
民衆の情念、思想の煽動
五木 ここまで思想の問題に重心を置いて伺ってきましたが、それだけではなく、いわゆる思想などとは無縁の民衆のエネルギー、という面も考えなくてはいけません。
三井甲之や蓑田胸喜らが論壇で大活躍し、それと同時に軍部や政治家たちの複雑な動きがあり、そして天皇機関説事件のような排撃運動が盛り上がっていく。その背後には何があったか、ということです。
たとえば在郷軍人会がありますね。予備役に回されたり、すでに退役したり、軍に対しては脇役の立場にいる人びとで、町にも農村にも一般庶民の中に大勢いました。そうした人々の情念が蓑田らのアジテーションに火をつけられ、澎湃として盛り上がっていった面も無視できない。私はそう思うのです。
中島 たしかにそうですね。
五木 思想は言論の世界では認識されていたけれども、その一方では、「親鸞様」とあがめながら『歎異抄』も読んだことがない、そういう門徒さんは少なくありません。
門徒もの知らずなんて言いますが、以前、私が書いた『蓮如』という本を、あるお寺の住職に差し上げたら、「ほお、この本はまだもらってませんな」と(笑)。もちろん知的な勉強家もいますが、自分で本を買うよりやはり聞法が大事、百遍聞いて暗記してるような話でも自分の血肉と化すまで聞く、そういう感覚があるんですね。
暁烏はそういう人たちと直にふれあってきて、三井や蓑田のような論客はそんな民衆の地熱に火をつけて回った。そういうことではないでしょうか。
中島 その通りだと思います。
五木 『愛国と信仰の構造』で私が多少不満だったのは、出てくるのが一高から東大出の人ばかりということでした。三井も蓑田も東大出ですが、かといって大蔵省や外務省に行くようなエリートではなく、それぞれに煩悶青年でした。
でも、農村辺りではそういう精神的な煩悶より、具体的な生活の問題に悩む人がたくさんいたはずで、彼らのフラストレーションはもっと高かったはずです。こう言うと、何だか中島さんが統制派で、私が皇道派みたいな気もしてきますが(笑)。
中島 たしかにそうですね。前に『血盟団事件』という本で書きましたが、あの事件を起こしたのは茨城大洗の農民たちでした。彼らはとにかく貧しくて、東京に出てきて、銀座で毎日遊んでいるような金持ち連中を見て、それに比べて自分たちの実家は……という不満を抱くんですね。1920年代の後半から事件が起きる1932年までには、こうした時代背景が色濃くあります。
五木 話はそれますが、私は昔からすごい偏平足なんですよ。足裏が未発達な幼い時期から重労働をしていると、筋肉がついてアーチ構造ができず、平らになる。田舎のほうではワラジ足なんて呼びますが、これは働き者の象徴だから「ワラジ足なら嫁にやろうか」という言葉もあったぐらいです。
そういう農村では生活すること自体がたいへんで、でも家にはしっかり御真影が飾ってある。あの時代はそういう民衆感情の力学も考える必要がありますね。
中島 おっしゃる通りですね。
五木 軍部というのも、そう馬鹿ではなかったはずです。実際、軍部には秀才が集まりましたから。
満州事変にしても、戦後になって朝鮮軍が無断で越境したとか、軍部が独走したとか言われますが、あの連中だって国民の支持があると考えたから、ああいった行動に出たのではないか。政府は文句を言うだろうが、国民は絶対に自分たちの味方となって後押ししてくれる、という期待なり自信がなければ、よほどの馬鹿でないかぎりできないと思うんです。
中島 そうですね。たとえば、金子大栄がいつから国体論的なものを書きはじめるかというと、その満州事変の後ぐらいからです。金子は1928年に異安心問題で教団からパージされ、付き従ってきた安田理深や松原祐善らと興法学園という私塾を始めます。いわば一種のサンガで、そこには主に北陸出身のお寺の子弟たちが集まってきて共同生活をしていましたが、満州事変のころから彼らがどんどん揺らいでいくんですね。
彼らにしてみれば、故郷の貧しい門徒さんたちが兵隊にとられ、上海事変などがあるとお骨になって帰って来る。それにどんな言葉をかければいいのか、若い自分たちが京都にこもって経典を読んだりしている場合なのか、と訴える。そこで金子も、ここできちんと筋をつけないといけないと考えはじめるんですね。
五木 まさしくヴ・ナロード、人民の中へ、ですね。
中島 金子は文部省の国策団体などに接近し、最終的には、大御心こそが弥陀の本願である、という若者を戦場へ送り出していくロジックをつくりました。
そして金子も暁烏も、ここで親鸞の太子信仰を使っているんですね。弥陀の本願と大御心とがつながり、一体化するための重要なファクター、それが聖徳太子でした。
五木 いや、私も聖徳太子は謎なんですが。
中島 彼らの論理ではこうなります。聖徳太子こそが仏教を日本に受け入れた。太子は皇室の人で、天皇を基とした国体の中に仏教というものを包摂していった。ここにおいて国体即仏法という世界が表れている。だとすれば、弥陀の本願は大御心というものと一致している、というのです。そのロジックが作られて、金子などは、その聖徳太子を最も礼賛したのは親鸞である、とさらに話を盛り上げていくわけですね。
五木 なるほど。
中島 そういう地平がある中で、五木さんが言われるように、蓑田などがある種の狂気を発揮して、全面的に自力を否定していきます。帝国大学の学者どもはマルクス主義のような自力によって何か善きことをしようという、ああいう連中こそが国体に反する、いわば漢意である、そうやって親鸞を基にして徹底的に否定していった。それが両輪のように進んでいったのが、1930年代だというのが私の印象です。

五木 それにしても、なぜ親鸞はあれほど聖徳太子に傾倒したんだろう。
中島 直接的には、あの六角堂の夢の中に太子が出てきたということですが、実際、親鸞の和讃の三分の一ぐらいは太子和讃ですよね。
五木 まあ、夢告については「お話」だろうと私などは思いますが、仏教の日本導入者であり、妻帯していたことに共鳴したという説明も、どうも納得がいかないのです。
ところで、世間的には親鸞と言えば『歎異抄』ですが、中島さんの考えでは、あの中にも何か全体主義と通底するものがあるんでしょうか。
中島 歎異抄のここがそうだ、と具体的に言うのは難しいですが、しいて言えば、宿業という感覚が挙げられるかもしれません。ただ、はっきり言えることは、当時のロジックは、親鸞の論理と日本の国体をどんどん結びつけていくことに相当はまり込んでいる、ということですね。
五木 戦後になって大谷派は、それについて厳しく自己批判をしているんですか。
中島 ある程度は。でも私は、その自己批判の仕方がズレていると思うんです。大谷派にせよ本願寺派にせよ、その総括は真俗二諦という問題に終始しています。
少し説明しますと、真諦とは仏法の世界であり真宗の考え方のこと、俗諦とは世間の様々な決まりごとで、法律とか国体もこれに含まれます。つまり、親鸞の教えである「真諦」を心の中で持ち続けながら、世間の取り決めは「俗諦」として受け入れていく。
こうした二分法によって、ファシズム的なものをずるずると受け入れてしまったのだとすれば、真俗二諦という考え方そのものを否定しなければいけないと総括されてきました。
五木 なるほど。真俗二諦といえば、蓮如は「額に王法、心に仏法」といいましたね。では例えば、神祇不拝という問題はどうなんでしょう。
ピュアな門徒は正月に門松を立てず、とよくいわれますね。私の知っている住職は非常に厳格な一仏主義者で、寺の駐車場に来る車に交通安全の札が下がっているだけで、中に入れないという。また別の真宗のお寺さんでは、村の鎮守のお祭りに一度も寄付をしなかったら、消防団に屋根瓦を吹っ飛ばされたとか。で、そのお寺の娘さんは一度でいいから七五三をやってみたかったとこぼしてました(笑)。
実際、私が小説の中で、親鸞が直江津を去るときに通りがかった神社の前で頭を下げたと書いたら、あちこちから批判されました。でも、それと似たようなことは親鸞も言ってますよね。
中島 そこは難しいんですね。親鸞が真俗二諦を唱えていたという解釈は間違っているという人もいれば、その通りだという人もいる。でも少なくとも戦前期は、親鸞もそう言っているという説が強かったんです。
五木 関東で布教していた頃の親鸞は、いろいろな批判や弾圧を受けました。神社仏閣の前でも絶対に頭を下げないと突っ張って、世間と無用なトラブルを起こすより、神や仏は阿弥陀仏を支えてバックアップしてくれる大事なものだから、そう軽んじてはいけない、と言うのも分かる気がします。
この冥衆護持という考え方は、親鸞から蓮如へ真っ直ぐ伝わっていると私は思います。ただ露骨に言うから、蓮如がすべてをかぶっているという感じがしますね。
中島 そうですね。この神祇不拝の問題については戦前期、こんなことがありました。大正天皇の病状が深刻になり、国民を挙げて病気平癒の祈願をすることになったのですが、真宗教団がそれを断った。その考えは国体に反する、と政府から強い介入が入ったことで、教団は神祇不拝の解釈をめぐってぐらぐら揺れはじめるんですね。
五木 もとが鎮護国家の他教団と比べて真宗はそういう面が弱かったから、国体論が盛んになるにつれて、政府に協力、迎合しないとやっていけないと考えたんでしょうか。
中島 1941年、太平洋戦争が始まる少し前には、真宗教学懇談会というのが開かれていて、その記録が残っています。金子や暁烏や曽我をはじめ、大谷大学の学長など教団の偉い人たちがみんな参加していて、時下の戦局に教団としてどう対処するのか、三日間にわたって討議しているんです。
五木 それは興味深い集まりですね。
中島 当然ながら、神祇不拝をどうするか、本地垂迹をどうするか、伊勢神宮の大麻を受け入れるか、靖国神社にいくべきか、この世を凡夫の棲む穢土とする考え方をどうするか、等など、非常にリアルかつシビアな討議です。 この議論をリードしているのはやはり暁烏・金子・曽我で、すべてを国体論のほうへと読み替えていくんですよ。
五木 では、蓑田のようなアジテーターは別として、たとえば日蓮宗における石原莞爾のように、軍人あるいは政治家で強い影響を受けた人はいるんですか。
中島 どうでしょうか。軍や政治方面ははっきり言えませんが、金子大栄は文部省をはじめ国体について考える講演会で、仏教との関係について繰り返し説いていますね。もちろん、暁烏もそうです。
五木 やはり魅力があったんでしょうね、暁烏は。それにしても、金子や暁烏、他にも曽我量深とか、彼らが戦後も教団の中で大きな指導力、影響力を発揮するというのは、どういうことだろう。
中島 その辺は、宗門も総括の仕方を間違えたのではないかと思います。真俗二諦があったがゆえにファシズムを取り込んでしまった。だからそれを否定しようという話で結着をつけていますが、私が読んだ限りでは、実は戦時教学は真俗二諦を否定しているんですね。
五木 そうなんですか。
中島 なぜかというと、俗諦として国体を受け入れて真諦は別にあります、というのでは軍人たちが気に入らない。国体は世間の決めごとだから受け入れます、とは何だ、となるわけです。
五木 それはまずいね。本当のことは別だとなると。
中島 そこで暁烏や金子は、それはちがう、真と俗は一体のものだといい始めます。いわゆる真俗一元論で、つまりは仏法即国体でなければならない。これが戦時教学の中核となる考え方です。だから、真俗二諦を否定すれば戦時中の責任問題が解決する、というのは相当ずれた話なんですね。
しかし戦後すぐ、例えば田辺元などもそうですが、知識人たちは一気に総懺悔みたいな風潮になりました。すると今度は、自分たちの悪を見つめることで弥陀の本願に照らされて、他力の光に包まれていくんだ、という話になる。
五木 でも、それを受け入れる人々が、門徒にかぎらず大勢いたということですよね。自分たちもそうだった、悪を見つめて反省しよう、と共鳴するんでしょう。
中島 そうだと思います。みんなで愛国の旗を振って死んでいこう、それで浄土へ旅立ち、ついには世界全体を浄土にするのが自分たちの使命であり、君国の使命なんだといって生きてきたわけですからね。
五木 ですから先ほども話したように、暁烏も、大衆が揃ってまちがった方向に流されるなら、それを背負って流されていくところがあった。つまり、自分もそうだが、あなたたちもみんなそうだった――民衆は、暁烏や金子、曽我らの戦中の言動を厳しく糾弾する雰囲気はなかったんでしょうね。
中島 むしろ、そうして反省している自分たちこそが救われる、という話になり、それがずるずるになっていく。島薗先生が「真宗の寝そべる思想」と言っておられたように、常に自力というものを遠ざけて、言葉はよくありませんが、他力のぬるま湯につかってしまうところがあるんです。
五木 なるほど。その従順で扱いやすいところが、南米やハワイへの移民に真宗門徒が多かったという話につながるのかもしれません。
中島 真宗は外からやってくるもの、上に対するある種の受動性それ自体に思想を見いだしています。つまり、自分というものの主格、あるいは近代的な理性主体を解体する魅力がある反面、逆に外からの力には弱い側面があるんですね。
でも、清沢などは、自力を完全に捨てよ、とは言っていないと私は思います。むしろ、他力というものに出会うためには、ある程度は自力でやってみないとその限界にさえ出会えない。そこで決定的な自力の限界に出会った人間こそが他力に出会う。そういうロジックですから、自力そのものを否定しているのではなくて、自力の末にある他力、五木さんの言われる「無力」と通じる構造だと思うんです。
五木 他力すなわち弥陀の本願とは、たとえば自力と見えるものであってもそれは他力の誘いなのだから、自分の力で成し遂げたなんて思ってはいけない。そういうものだと思います。その辺がマルクス主義による計画経済とか、日蓮信奉者の満州国経営などとの違いに現われるんでしょうね。
中島 ええ、その通りだと思います。
-

-
親鸞と日本主義
中島岳志/著
2017/08/25発売
-
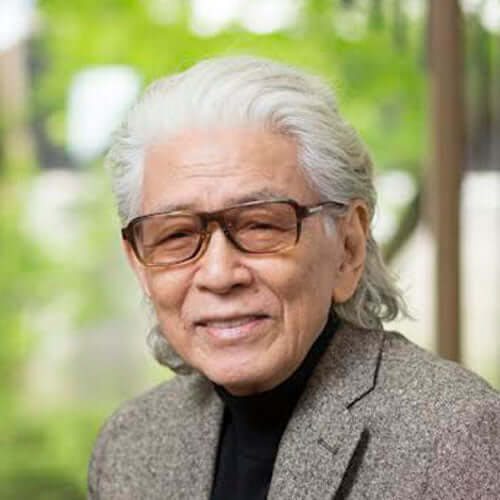
-
五木寛之
1932(昭和7)年、福岡県生まれ。1947年に北朝鮮より引き揚げ。早稲田大学文学部ロシア文学科に学ぶ。1966年「さらばモスクワ愚連隊」で小説現代新人賞、1967年「蒼ざめた馬を見よ」で直木賞、1976年『青春の門』で吉川英治文学賞を受賞。著書は『朱鷺の墓』『戒厳令の夜』『風の王国』『風に吹かれて』『親鸞』『大河の一滴』『他力』『孤独のすすめ』『はじめての親鸞』など多数。バック『かもめのジョナサン』など訳書もある。
-

-
中島岳志
1975年、大阪府生まれ。政治学者、東京科学大学(旧東京工業大学)リベラルアーツ研究教育院教授。専門は、インド政治、日本思想史、現代日本政治。大阪外国語大学外国語学部ヒンディー語学科卒業、京都大学大学院博士課程修了。北海道大学公共政策大学院准教授を経て、現職。2005年、『中村屋のボース インド独立運動と近代日本のアジア主義』(白水社)で、大佛次郎論壇賞とアジア・太平洋賞大賞を受賞。主な著書に、『「リベラル保守」宣言』(新潮文庫)、『血盟団事件』(文春文庫)、『親鸞と日本主義』(新潮選書)、『保守と立憲』(スタンド・ブックス)、『思いがけず利他』(ミシマ社)、『テロルの原点 安田善次郎暗殺事件』(新潮文庫)など。
この記事をシェアする
「五木寛之×中島岳志特別対談 親鸞思想の危うさをめぐって」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-
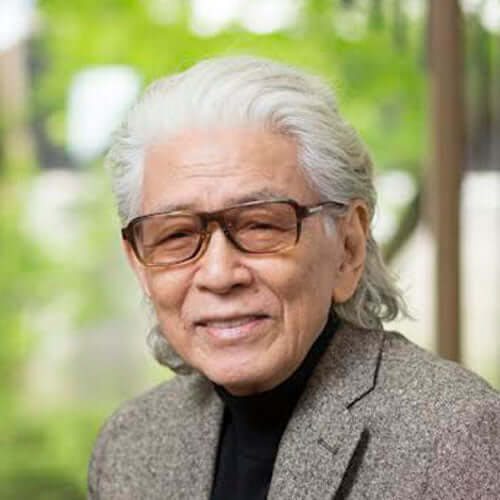
- 五木寛之
-
1932(昭和7)年、福岡県生まれ。1947年に北朝鮮より引き揚げ。早稲田大学文学部ロシア文学科に学ぶ。1966年「さらばモスクワ愚連隊」で小説現代新人賞、1967年「蒼ざめた馬を見よ」で直木賞、1976年『青春の門』で吉川英治文学賞を受賞。著書は『朱鷺の墓』『戒厳令の夜』『風の王国』『風に吹かれて』『親鸞』『大河の一滴』『他力』『孤独のすすめ』『はじめての親鸞』など多数。バック『かもめのジョナサン』など訳書もある。
対談・インタビュー一覧
-

- 中島岳志
-
1975年、大阪府生まれ。政治学者、東京科学大学(旧東京工業大学)リベラルアーツ研究教育院教授。専門は、インド政治、日本思想史、現代日本政治。大阪外国語大学外国語学部ヒンディー語学科卒業、京都大学大学院博士課程修了。北海道大学公共政策大学院准教授を経て、現職。2005年、『中村屋のボース インド独立運動と近代日本のアジア主義』(白水社)で、大佛次郎論壇賞とアジア・太平洋賞大賞を受賞。主な著書に、『「リベラル保守」宣言』(新潮文庫)、『血盟団事件』(文春文庫)、『親鸞と日本主義』(新潮選書)、『保守と立憲』(スタンド・ブックス)、『思いがけず利他』(ミシマ社)、『テロルの原点 安田善次郎暗殺事件』(新潮文庫)など。
対談・インタビュー一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら






