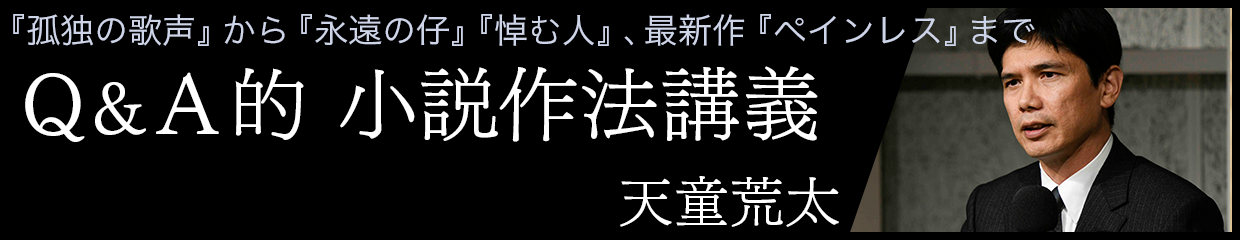(前回はこちら)
痛みのない世界を想像する
『ペインレス』に登場する、心に痛みを感じない人物というのは実在せず、あくまで仮定だと申しました。
そもそもの始まりは、肉体に痛みを感じない人物が現実にいるというのを知ったときに、その人を通してこの世界を見る、向き合うという物語によって、様々な痛みに満ちているこの世界に対するアンチテーゼになる、問題提起になるのではないか、と思ったことでした。
ですが現実に調べていくと、生まれながらに肉体に痛みを持たない人というのはやはり大変なんですね。幼い頃から骨折を繰り返してしまって、なかには車椅子の生活を余儀なくされる方もいらっしゃるし、通常の生活を送ることにも困難を感じる状態の方もいらっしゃる。
そうした方々の現実を考慮せずに、フィクションとしての物語を表現するというのは、どれだけ配慮しても不遜になることを免れない。悩んで考えるうちに、ふと「痛み」には、肉体だけでなく心のそれもある。とすれば、「心の無痛」もフィクションの可能性としてはあり得ると考えるに至ったわけです。そして「心の痛み」というものは、あらゆる人間にとってはごく日常的なものである一方、ことによれば一番つらいものだし、ときには自分や他者の命に関わる重いものであろうと気が付いた。肉体の痛みは薬や医療によってある程度抑えられても、心の痛みは一般的に医療では抑えられない。なので、もし心に痛みを感じないという人間がいれば、この世界に対する、より深遠かつ根元的なアンチテーゼ、異議申し立ての存在になるだろうと、あるいは、この世界の成り立ちをより浮き彫りにする存在になるだろうと思って、主人公に据え、物語を創造することにしました。
精神的に強い衝撃を受けて「解離」という、感情を持てない状態になる人はいます。でも、そういう人はもともとは繊細に心の痛みを感じる人だったはずです。発達障害で他者の気持ちを汲み取りにくい人や、サイコパスと呼ばれる人も、自分の痛みには敏感です。自己中心的な怒りや攻撃性の発露に積極的な人は、背景として自己の痛みへの恨みがあると考えられます。
私が創造したかったのは、「進化としてのペインレス」であって、人間がさらに進化していくとすれば、それを促すプレッシャーには、痛みからの脱却が基本としてあるのではないか、と考えたのです。
飢えや寒さという痛みからの脱却として道具や火が発明されて、人類は発達した。掟や法律も、他者や社会に痛みを与えたら罰するということで作られ整えられてゆく。自分が飢えていて、どこかに飢えていない地域があったら、自分の飢えという痛みを脱却するために、武器を持って相手の領土を奪いに行く。武器はそのためどんどん殺傷能力を高め、領土や同胞の命を奪われた側はその痛みによって、より激しい攻撃を返す、というように、戦争の歴史も痛みが基本にあるだろうと思います。より痛みを与えるために兵器は近代化し、与えられた痛みを治すために医療も発達してきた。
そう考えていくと、生活の不便さという痛みの軽減を目的としている様々なインフラ、交通手段、情報通信、医療、防御用の武器、あらゆる文明が進んできた根底には、痛みからの脱却があるのではないか。状況がどんどん進んで、いまわれわれが暮らしているのは、他者から痛みを与えられないために核兵器、化学兵器を備えて、ボタン一つで人類が滅亡するかもしれないというところまで来てしまった世界です。
人間は限界に達しているのか?
われわれは「愛」を最高の価値観に置いていて、これ以上のものを人類はいまだ生み出せていない。愛が最も崇高なもので、愛さえあれば何もかも解決する、問題点は解決していくというように信じられているけれども、本当のところは、その愛によってわれわれは、愛する人を奪われたという痛み、あるいは愛する人を奪われたくないという強い痛み、あるいは愛する国を奪われた、愛する土地を奪われたくない、という痛みを感じていて、そのことで相手を攻撃しているわけです。愛ゆえに痛みが生じ、結果として暴力の連鎖はやむことがない。とすると、「愛」という美しい価値観に縛られていることによって、われわれ人間はある限界に達しているのかもしれない。
今現在の世界の状況において、人間は永遠の平和を作れる、誰もが飢えずにいる平等な世界を打ち立てられる、ということを、願いはともかくリアルに信じている人は、まずいないと思います。長い歴史と現実を見れば、人間にはそれは無理なのだというふうに考えざるを得ない。だから、『ペインレス』の基本認識は、「今の人間のまま」では無理かもしれないということです。「今の人間のまま」の状態では袋小路に嵌まって、戦争をなくすことも、誰もが平等に生きていけることも、新しい世界を見出すことも難しいのではないか。
じゃあ、どうすれば、と考えて、仮定としてのペインレス、心に痛みのないヒロイン野宮万浬という存在が生まれてくる、という流れになったわけです。
痛みがないことで、進化した世界に行けるというのは、物語上の表現としては比喩です。本当に大事なのは、「愛」という自己中心的な欲望かもしれない囚われから逃れて、あるいは、命や財産や地位や故郷を奪われることへの怯えや恐怖から一旦身を離して、知性と理性で50年後、100年後、われわれの子や孫やその先の世代が存続し得る可能性を探れるかどうかです。

『ペインレス』の中には、壁という言葉がよく出てきます。愛とか旧来の常識という壁によって、様々な痛みの予感に囚われて怯えたり、不安なあまり理性的に物事を考えられなくなったり……自己中心的な欲望にからめとられて、目先の利益や保身のために平気で嘘をつき、半年先、長くても数年先の利益のためにかなりあくどいこともやっているのが現代で、そのことを多くの人も薄々知りながら、今さえ平穏ならばと、やり過ごしているという状況だろうと思います。
このままならそう遠くない将来に、危機的な状況になるのは間違いありません。必要なのは、刹那的な欲望や不安に囚われずに、しっかり理性的に、知性的に物事を見ていく、そういう新しい形の脳を持つ世代なのではないか。
人間の脳というのはずっとホモサピエンスが誕生する前の時代から、石器時代、さらに鉄器を発明して、より生産的な集団生活を営む時代へと進化しつづけてきたのは間違いないわけで、今のわれわれのこの人間の状態が終着点だと思うのは合理的ではないと思います。
細胞レベルでは常に進化を求めて働き続けているでしょう。そこに私は、希望があると考えていて、その希望を何かの形で表現できないかなというのが作品の基底にはあって、万浬というヒロインを創造したわけです。
キャラクターを造形するということ
ただ、こういう新しい存在の造形は前例がないので難しい。一つ一つ骨格から作り上げていかなければいけません。心に痛みがない、というのはどういうことなのかを僕も実際にはわからないので、誕生以前の、祖父母の代までさかのぼって履歴を作っていくわけです。これはあらゆるキャラクターについても、程度の差はあれ、同じなんですけれども、どういう生まれをして、どう生きてきたのか……周囲からの働きかけに対する一つ一つの反応をエピソードとして作っていく。
万浬も、生まれてきたときにはほかの赤ん坊と何も変わらない。でも、自我が芽生えてくるにつれ、他との違いがあらわれてくる。たとえば子どものころに物語に触れると、知的な教育的物語や言葉遊びはわかっても、情動を基底にした自己犠牲や別れの話などがなぜ泣けるのかわからない。ほかの子にオモチャを取られる。普通の子は泣く。でも彼女は、所有しているモノや人を失っても心の痛みを感じないので、泣くことはない。こういうことを一つ一つ細かく点検しながら積み上げていって人物を作っていきます。
社会と自分との関係にあつれきや違和感をおぼえながら、思春期まで彼女が成長すると、この社会のほとんどが、情動をもとにした物語や文化で溢れていることに気づきます。一般的に自分がいまいる場所に合わないときには、人はまず自分を責めます。周りではなく、自分がおかしいんじゃないのかな、なんで人と同じように感じないんだろうと。そのため多くの子どもは成長の途上で、絶望や虚無から自殺をするか、暴力に走るか、精神的に自分から引きこもっていくかです。だから、万浬が子ども時代の危機をかわして、心の無痛をむしろ肯定的にとらえて生き延びてゆくには、彼女を精神的に支える人が要る。すると今度は、彼女を育てた祖母のキャラクターが生まれるわけです。
キャラクターはそういうふうに増殖していきます。だから、最初にキャラクターを作って当てはめていくというよりは、伝えたいテーマなりプロットなりがあって、展開次第で必要とされるキャラクターが用意されていくわけです。
オリジナルな物語のためには、それぞれのキャラクターもまた類型を超えて、オリジナリティを持った人物にする必要があります。
いかにキャラクターを人物に、生きている人間として読んでもらえるよう成長させてゆくかといえば、固有の具体的なエピソードを、それぞれの人物ごとに考えていくことが大事です。つまり、登場人物を物語を円滑に進めてゆく上での役割として考えるのではなく、この人にはどんな過去、経歴があって、今そこにいるのか。いることになったのか。必然性とともに、性格を特徴づけるために一人ずつ、三つか四つかはエピソードを考える必要があります。
例えば、子どものときに犯した罪。それと、初体験。これは、あってもなくてもいい。ないなら、ないなりの理由がある。子どもの場合は初失恋ですね。それから、大切な人との別れ。少なくとも三つぐらいのエピソードが用意されていれば、キャラクターが役割を超えてオリジナリティを持って生きはじめる。こうしたエピソードを物語上に実際に書くかどうかはまた別問題で、まあ、ほとんど書く余裕はなくなりますけど、それがあると人物の言動に独自のニュアンスが見え隠れするようになって、物語自体がリアリティを持って生き始めていきます。
そして、それぞれの人物がオリジナルな履歴を持って動き始めると、物語もそれに従って豊かに動いていきます。始まりは簡単なプロットなんです。例えば今作は、「体に痛みを感じない男性と、心に痛みを感じない女性が出会ったらどうなるだろう」という1行で書ける着想から始まっている。心に痛みを感じないからハートブレイクがない、ゆえに愛の物語にはならない。でも、性愛の物語は書けるのではないか。その2人は普通の人物ではないので、性愛のあり方も特別なものになるに違いない。女の性愛には心理的な情動が関与しない。男は肉体的快感の裏打ちとなる痛みを失っているので、快感も薄いものに変化している。2人がお互いの性愛のあり方を探りあうなら、しぜんとわれわれ一般の性愛のあり方の本質をえぐっていくような形になっていくだろう、というような感じで進んでいくわけです。
『永遠の仔』であれば、虐待を受けた子どもたちが施設で出会う。そして、秘密を持つ。その子たちが十数年後、成人してから再会したら何が起きるだろう。何かここに新しい物語が生まれそうだ、人々に伝える価値があるテーマなり言葉がきっと隠れている、と感じたときに、プロットは確かなものになっていく。
『悼む人』では、この世の中で亡くなった人々をただ悼んで歩く人がいる。なんでそんなことをこの人はするんだろう。その人に出会ったら、われわれはどう思うだろう。あるいは、彼の家族は何を思っているんだろう、ということが最初のプロットです。
以後プロットをどんどん膨らませて、組み上げていくんですけれども、その組み上げていく作業というのは、小説の原型となるストーリーを形にするというより、登場する人物、必要とされる各キャラクターたちを、ストーリーの流れの底から掘り出していくためにこそ大事なんです。
その人物たちに、エピソードを与えていけば、物語が活き活きと動き始める。あとは、その動き始めた人間たちを追いかけていけば、私が考えた初めのプロットを超えて、作品になっていくわけです。だから面白いんです。
もし当初のプロットを超えられないとしたら、登場人物の作り込みが足りないということなんですね。それぞれが人格を持ち、自分たちの行動規範を持ち、自分たちの欲望を持ち、自分たちの願いを持って動き始めるまで育てなければいけない。それが育てば、彼や彼女は作者の思惑を超えて勝手に行動し、互いに出会って、思いもかけなかった衝突の起きるときにエキサイティングな物語が生まれます。
だから、最も苦労するのは、それぞれの人物をどこまでちゃんと育てられるか、ということです。自分のプロットの中にうまく収まる人物を作ろうとした時点で、もう各人物は永遠に作者を超えないので、既視感をおぼえる作品や、よくあるステレオタイプなものに堕ちてしまう。
実際に小説の原稿を書き始めると、もう各人物たちの言動を追いかけていけばいいから、わりと楽しいんですね。執筆というのは、下地作りに比べれば、思いもかけない表現が次々と生まれてきて、そのつどライターズ・ハイを味わえるので、嫌いじゃない。「あ、自分を超えてる」と思うときの喜びは多分アスリートが感じる感覚に近いんじゃないかな、と思います。その感覚が、つらくてもこの仕事を続けていけるモチベーションになっていると言えるでしょう。
書いていて、登場人物がどうしても動かなくなるときがあります。動いても妙にそらぞらしい。口にする言葉にも力がない。そういうときは大体、自分がどこかで手を加えていて、「こっちのほうに行ってくれたほうが、物語はうまくいって感動するのになあ」と無意識にその人を操作しているときです。こうした場合は、どれだけ原稿が進んでいても、未来がないので、あきらめて捨てます。数十ページにわたるときもありますが、そこはためらっても、どうせ納得のゆくものにはならないので意味はありません。ここまでは間違いなく彼らが動いていたというところまで戻って、もう一回彼らに任せるのです。
自分が長く学んできたドラマトゥルギーに合わせて、「こっちに行ってくれれば、そこそこワクワクして、そこそこ感動できて、枚数も400枚程度で済むのにな」ということがわかっていても選ばない。私の小説はわりと長くなりがちなんですが、それは登場人物に任せて話が紆余曲折するからです。型にはまったストーリー展開にならないので、ときには混乱したり読みにくかったりするかもしれないけど、そちらのほうにこそ新しい物語はあるはずです。
構成も、最終的には登場人物たちが決めていく。もともと細かいプロットを作ってあるんですけれども、人物主体で書いていくのでどんどん崩れていきます。逆に、崩れないと自分はいやなんです。崩れていったときに「自分を超えている」感覚を得られて、本当の意味で面白くなる。
今回の構成は、当初は、今ある小説の第一部と第三部の二部構成で、第二部はなかったんですね。ところが書き進めていくうちに、ペインレスである野宮万浬という人間が、どういう生まれ育ちによっていま現在に至ったのか、過去を知ることが必要だというふうに作品が訴えてくるときが訪れたんです。小説の中の万浬のパートナーになる森悟という男性も、「君の過去を知りたい」と願い始める。となれば、彼女の過去を書かざるを得なくなる。作品も求め、人物も求めるので、第二部を書くことになり、結果的に三部構成になりました。
小説内で生じているすべてがそういう感じで、ラストシーンも彼らに任せた結果です。古い人間の世界、つまり私を含めて我々がいまいる世界に、「愛がたとえ錯覚だとしても、それは捨てられない」と訴える存在として森悟がいる。
もう一方に、愛や感情に囚われているこの世界に留まっていては、新しい世界は開けない、その世界にいることに意味を感じない、「壁を超えてこっち側に来るべき」と訴えている野宮万浬がいる。
その2人が最後、衝突したときに何を見出すのか、私もわからずに書いていたんです。わかっていないから面白い。自分が驚かないものには、読者もきっと驚かないだろうという勘だけはあって、それは長年やってきた経験からくるものでもあるんですけど、予定調和になってしまわないことが重要だと思ってます。
自分が信じて一緒に歩いてきた登場人物たちをどれだけ信頼しうるか。物語というのは、根本的に信頼が大事です。自分に対する能力への信頼、自分が育ててきたキャラクターへの信頼、読んでくれる読者への信頼。
そして、古代から人類に多大な影響を与えてきた物語それ自体への信頼、というのが大切になってきます。
(第3回へつづく)
-
ペインレス 上巻
天童 荒太/著
2018/4/20
-
ペインレス 下巻
天童 荒太/著
2018/4/20
-

-
天童荒太
1960年、愛媛県松山市生まれ。1986年『白の家族』で野性時代新人文学賞を受賞して文壇デビュー。1993年『孤独の歌声』で日本推理サスペンス大賞優秀作、1996年『家族狩り』で山本周五郎賞、2000年『永遠の仔』で日本推理作家協会賞、また2009年『悼む人』で直木賞を受賞、2013年に『歓喜の仔』で毎日出版文化賞を受賞した。人間の最深部をえぐるそのテーマ性に於て、わが国を代表する作家である。ほかに『包帯クラブ』『あふれた愛』『ムーンナイト・ダイバー』等、著書多数。
この記事をシェアする
「「Q&A的 小説作法講義 ――『孤独の歌声』から『永遠の仔』『悼む人』、最新作『ペインレス』まで」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら