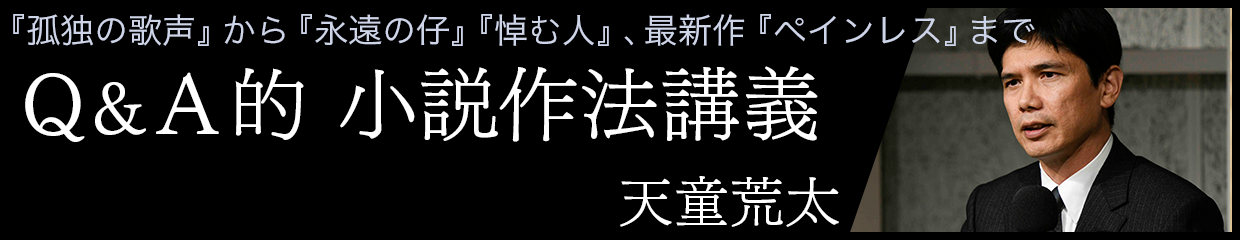(前回はこちら)

小説に取材は必要か
取材はもちろん必要です。できる限り、現場に立つ、というのが私の主義です。が、それは舞台となる場所の実際のスケールや,
位置関係を知ること。流れている空気や聞こえている音を感じ取り、目に入る人や物の姿を頭にインプットして、自分なりの表現に置き換えることの必要性からで、当事者に会うということは、私はしません。なぜかといえば、当事者に一回や二回会ったからといって、本当のことを話してくれるとは限らないというか、本当のことなんか普通話すはずがないと思っているからです。少なくとも小説を書きたいからって会いに来た人に、本音なんて話すわけがない。なのに、話をちょっとでも聞けたことで得々として、「この人はこんなことを思ってるんだ」と表現したら、それはもう不遜極まりない。
それにまた、人間を書くというのは、いい面だけでなく、ダークサイドというのか、人としてのずるさとか、どうしようもなさなども書くことです。取材に協力して懸命に話したのに、いやな面とかずるい面とかを書かれたらいやじゃないですか。なのではじめから当事者には会わない。モデルに会わない分、文献を幾つも当たったり、登場人物の履歴をしっかり作りこんだりして、間違いなくリアリティを持った人間ができるよう自分を追い込んでいく、ということをします。
社会のいろんな局面で、重い傷を抱えたり、つらい立場に立たされたりしている人たちに、何かできることはないだろうか、という質問を受けました。
例えば虐待を受けた子とか、大切な人を失った人、重い差別を受けてきた人など、つらい思いをした人の存在を知ったときのことですが……私には物語にして届けるという一つのミッションがあるので耐えられるという面があります。そういうミッションや、現実に職業として担っている役割が何もないのに、一般の人が同情だけで深入りすべきではないと私は思っています。
『永遠の仔』を発表したあと、虐待をされた子どもたちのために自分たちに何かできないか、と多くのマスコミや読者に聞かれました。私なりに5年以上この件に関して勉強を重ねていましたし、当事者の心を生きるという経験もしました。それに加えて、発表後に、多くの実際に虐待の被害を受けた当事者からお手紙をいただいてきました。その内容は多岐にわたり、かつ深く、きっと精神科医などの専門家にも話したことがないだろうと察せられる個人的な秘密と願いとが打ち明けられていました。その重さに私の心は耐え切れず、一時期からだを床から起こせなくなったほどです。
これらの経験から、一般の人々の「何かできないだろうか」という問いに、私が答えられるのは、「何もできない」ということです。問題意識を持っている人々にとって、何もできないということを認めるのはつらいだろうと思います。この答えについて、何かできることがあるはずだと考えていたマスコミの方と険悪になったこともあります。
じゃあ実際に現場を取材した記者の方が当事者の方々に、「こんなことをしてほしい」と求められたことがあるのかどうか、お尋ねしたけれど答えはありませんでした。私たちが問題を知るのは、虐待がもう起きたあとです。重い傷を受けながら、その傷がはたして何であるか痛みがどこに起因しているか、どうすれば避けられたのかも、当事者にはわからないし、つねに自分が悪かったからだろうかと、自責の念を抱いているケースが多いんです。だから、手を差しのべたいという人に、どこまで自分をさらしてよいのかわからず、どこまで相手に許容量があるかもわからないなかで、とても何々をしてほしいと言えないのが、被虐待の当事者なんです。彼や彼女らは懸命に生きている。つらさを抱え、痛みに苦しみながらもどうにかサバイブしている。むしろ「何かできる」などと安易に思わないでほしい。
何かしたい気持ちがあるなら、まず知ってほしい。実際に虐待とは何か。どういうことが虐待で、どういうことで生じるのか。どんな影響を被害者に与え、いつまでその影響は残りつづけていくものなのか。日常の生活において、人生において、被虐体験が何を起こしてゆくのか。ときにそれが連鎖してゆく可能性も含めて。
本当によく知る、ということが基本なのです。かわいそうな報道にふれ、そのときの同情で何かしようと行動しても、長続きすることは少なく、ときに被害者には逆効果になることさえある。子どもを傷つけた親を、かつては彼や彼女も被害者だったのでは、という視点を欠いて、非難したり指導したりするだけでは、転居したり閉じこもったりして事を悪化させることがあるようにです。
本当によく知れば、あなたの生き方が変わります。人との接し方が変わります。その変化が広がってゆくことが、人が人を虐げたり、いじめたり、見ないふりをしたりする世界を少しずつ変えてゆく。当事者がうまく言葉にできないながら願っていることの一つは、「私たちには何もしてもらわなくてもいい。ただ、あなたが今後出会う人の中に、そういう思いをしている人もいるというふうに感じて生きてもらえたら幸いだ」ということだろうと思います。他人と同じように課題をこなせない人、どうしても失敗してしまう人、何か重そうな感じでフリーズしてしまう人。そういう人に対し、きっとそれなりの事情があると思って付き合うことだけで、その人は救われる。別にくわしい事情を聞かなくても、優しく接するだけでも、この世界は変わってくる。つらい思いを抱えている人たちも、少し生きやすくなるはずです。ですから、大切なのは、その人にすることではなくて、私が、あなたが、生き方をどう変えるかという問題です。
タイトルと人物名
タイトルは大事だし、最も難しいものの一つですね。例えば『永遠の仔』というのは苦しんでつけたタイトルで、ぎりぎりまで考えて、ようやくこれだというものができた。あの「仔」は動物の子どもに使う漢字ですけども、多くの方からいいタイトルだと言われる一方で、なぜあの「仔」を選んだのかと尋ねられ、ときには批判的に、「心を病んだ子どもたちを『仔』と呼ぶのは差別ではないのか」と言われてショックを受けました。
生き物の子どもというのは生まれたらすぐ、目が見えないのにお母さんのおっぱいに吸い付いていく。おっぱいは肉体の栄養でもあるけれど、ぬくもりであり、生きてゆくことを肯定されている証でもある。人間も基本的に同じではないのか。生まれたときに、生きていてもいいんだよという肯定感を欲し、以後もずっと支えにし、また求めつづけることこそ、生き物の本質だろうと。そのためにあの「仔」を使ったんですけれども、すべての人には理解されないのが表現です。
登場人物の名前も悩みます。通常に使われる名前を私はあまり付けません。それは、高校時代だったと記憶していますが、松本清張さんが自作の登場人物について「私は安易に名前を付けない。安易に名前をつけると、安易な人物になってしまうからだ」というようなことを書かれるか発言されたものを目にし、かなり共感したんです。
その影響が、いまは自分の流儀にもなって、わりと難しい字も当てます。『家族狩り』には「馬見原」という登場人物がいます。由来については文庫版のあとがきに書きましたが、母方の実家近くの地名から来ています。『ペインレス』では「亜黎」という名前の人物が出てきます。原爆を体験した彼がアジアの黎明から自ら名付けたという設定です。『悼む人』の「静人」は、本当は鎮魂の鎮を使って鎮人にしたかったんですけども、彼の両親がその字を当てるかなと疑問に感じ、静かな安穏な生活を願っている2人の心情を思い、静人にしたんです。
つまり登場人物の名前を付けるときには、字の見た目や語感のことだけではなくて、その名前を付けた人の思いを考えなければいけない。主人公をロック的なカッコイイ名前にしたくても、その名前を付けそうな親かどうか配慮が必要です。どんな名前を付けたかによって親や名付け人のパーソナリティーがあらわれるので、注意が必要です。
『ペインレス』の万浬の「浬」は海上の距離の単位で、約1.8キロぐらいなんですけど、彼女はフランスと日本のダブルなので、外国でも通用する名前にしたかったのにつけ加え、人間として進化しているという距離感を出したかったんです。ただし、どちらかと言えば平凡な性格の父親に、この字を当てる発想はないと思い、彼女が新しい人間のモデルであればと願う祖母が付けたことにしました。作中の登場人物の名前がすべての読者に気に入ってもらえるわけではないでしょうが、作者は作者なりにいろいろなことを考えて付けているというのをご理解いただければと思います。
(第5回はこちら)
-

-
ペインレス 上巻
天童 荒太/著
2018/4/20
-

-
ペインレス 下巻
天童 荒太/著
2018/4/20
-

-
天童荒太
1960年、愛媛県松山市生まれ。1986年『白の家族』で野性時代新人文学賞を受賞して文壇デビュー。1993年『孤独の歌声』で日本推理サスペンス大賞優秀作、1996年『家族狩り』で山本周五郎賞、2000年『永遠の仔』で日本推理作家協会賞、また2009年『悼む人』で直木賞を受賞、2013年に『歓喜の仔』で毎日出版文化賞を受賞した。人間の最深部をえぐるそのテーマ性に於て、わが国を代表する作家である。ほかに『包帯クラブ』『あふれた愛』『ムーンナイト・ダイバー』等、著書多数。
この記事をシェアする
「「Q&A的 小説作法講義 ――『孤独の歌声』から『永遠の仔』『悼む人』、最新作『ペインレス』まで」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら