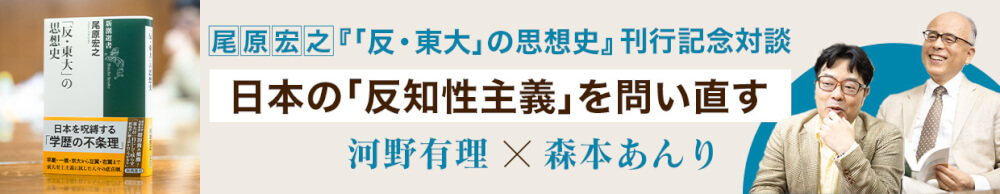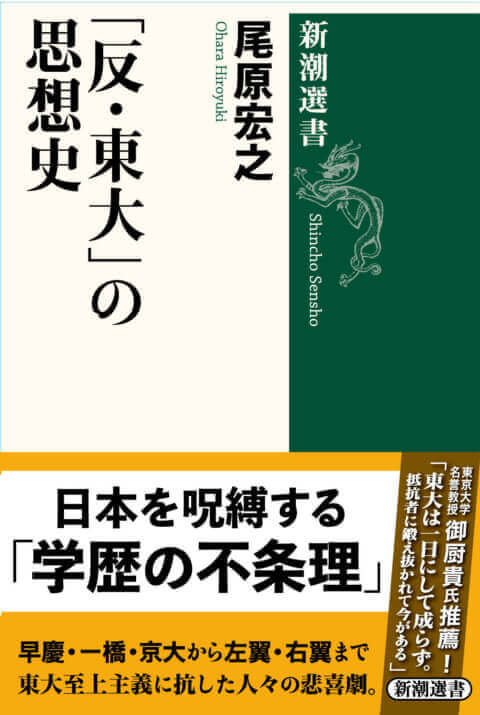2024年6月13日
尾原宏之『「反・東大」の思想史』刊行記念
前編 東大の学費は値上げすべきなのか?
尾原宏之さんの「考える人」連載をまとめた『「反・東大」の思想史』が、新潮選書から刊行されました。刊行を記念して、東京大学の出身で、尾原さんと同じく日本思想史を専門とする河野有理・法政大学教授と、『反知性主義:アメリカが生んだ「熱病」の正体』(新潮選書、2015年)の著者、森本あんり・東京女子大学学長が、本書をめぐって対談しました。
日本における「反知性主義」?
河野 尾原宏之さんの『「反・東大」の思想史』(以下、『反・東大』と表記)を読んで、この本をめぐって対談をするなら、ぜひ『反知性主義』の著者である森本あんりさんにお願いしたいと思いました。というのも、まさにこれは日本版の『反知性主義』として読めますし、またそのように読むべきだと思ったからです。
森本 ありがとうございます。アメリカにおける反知性主義(anti-intellectualism)とは、名門大学出身のインテリ階級が権力と結びつくことへの反感であり、キリスト教の信仰復興運動(リバイバリズム)から生み出されたイデオロギーです。それは「ハーバード主義・イェール主義・プリンストン主義」(Harvardism, Yalism, Princetonism)への反抗という側面があると拙著でも説明しましたから、日本で言えば、たしかに「反・東大」になりますね。
河野 尾原さんの本は、労働運動における「反・東大」を扱った第7章以外は、すべて大学を舞台にした話になっています。それだけに、われわれ大学教員にとっては非常に身につまされる話が多いですね。
森本 たしかに(笑)。教員の目線からしても学長の目線からしても、現在の大学改革の話に通じるような議論がすでに明治大正期から行われていたことを知って、とても興味深く思いました。
「国立大学の学費値上げ」は慶應義塾の悲願?
河野 大学改革と言えば、最近、中央教育審議会の特別部会で、慶應義塾長の伊藤公平さんが、「国立大学の学費を100万円値上げすべき」と提言して物議を醸しました。「教育費を値上げしろなんて、とんでもない」と思った人も多いかもしれません。
しかし興味深いことに、『反・東大』の第1章には、すでに同じようなことを福澤諭吉が1887(明治20)年の時点で主張していたことが書かれています。「官学が政府の力をバックに不当な安値でよい品物を叩き売るダンピング行為をするから、私学の発達が阻害される」というのが、その理由です。そのような経緯を知ると、なるほど慶應義塾長がそのような提言をするのには歴史的必然性があるんだな、と思いました。
森本 伊藤塾長は以前から国立大の授業料の値上げについて提言されていたのですが、じつは私もそれには大賛成なんです。もちろん、奨学金の拡充とセットであることが前提ですし、また地方の国立大学まで一律に値上げする必要はないと思います。
しかし、現実問題として教育にはお金がかかりますから、それを誰がどのように負担するかです。とりわけ東大は、統計的に裕福な家庭の子女が進学しているというデータが出ているわけですから、裕福ではない学生向けの奨学金をしっかり手当てした上で、一般学生の授業料を値上げするというのは理に適った話です。日本の大学の学費は安すぎて、一方でアメリカの大学の学費は高すぎて、どちらも問題だと思います。
なぜ東大に税金を使うのか?
河野 なぜ莫大な国費を投入してまで東大の学費を安く抑える必要があるのかと言えば、それは東大が「国家枢要の人材」を養成しているからである――明言するかどうかはともかく、こういうロジックが少なくともある時期までは広く社会に共有されていたように思います。
森本 つまり社会全体の利益になる人材を育てるためだから、税金を使うのも正当性があるという考え方ですね。実は大学教育の総コストを見ると、公金と家計の負担割合は日本もアメリカもそんなに変わらないのです。違うのは学生数の割合で、私立大学に通うのはアメリカでは3割弱なのに、日本は8割です。バランスから言えば、今の東大への国費投入はさすがに大きすぎるのではないかと思います。
河野 戦後の一時期までは、たとえば法学部であれば相当数の東大卒業生が役所に就職して、決して高いとはいえない給料で、お国のために頑張って働いてくれているというのは実感できるストーリーだっただろうと思います。したがって、彼らの学費を税金で賄うというのも分かりやすい話でした。
しかし近年は、役所に就職する東大卒業生が減る一方で、かわりに外資系の金融機関やコンサルティング会社に就職してバリバリ高給を稼ぐタイプが目立ってくる。あるいは、「東大王」などのテレビ番組やYouTubeなどで人気者になるタイプも出てきました。
もちろん、職業選択は完全に自由なのですからそのこと自体は決して非難されるいわれはありません。ただ、やっぱり納税者のロジックからすると、なんで彼ら彼女らのためにそこまで税金を使わないといけないんだという疑問が出てくるのは避けられない。その意味で、昨今の東大ブームにおける「ユニークな東大出身者」の取り上げ方は、何かをきっかけに世間の空気を一気に「反・東大」に反転させかねない、やや危ういものを感じますね。
森本 そんな空気を察したのか、東大も学費を10万円ぐらい値上げすることにしたみたいですね。私学の立場からすれば、もう少し値上げしても良いんじゃないかと思いますが、しかし世間の批判が高まると、それをすぐさま取り入れて自己変革を遂げていくというのは、まさに『反・東大』に描かれた東大の<生き残り戦略>でもありますね。
ロースクールを合併して「一大法律学校」を作る?
河野 もう一つ、『反・東大』で私が身につまされた話は、第3章の「私立法律学校の試験制度改正運動」です。これは、現在のいわゆるロースクール(法曹を養成する法科大学院)の問題にもつながる話で、私はいま法政大学の法学部に勤務していることもあり、とても興味深く読みました。
森本 この本を読んで初めて知ったのですが、かつて帝大法科卒業生には無試験で判検事・弁護士になれるという「特権」が与えられていたんですね。
河野 そうです。そして、それに反発した私立法律学校の学生たちが、そのような制度を改正しようと運動を起こすのです。その流れの中で、1897(明治30)年に、「貧弱で教育程度の低い」私立法律学校6校(現在の中央、明治、早稲田、法政、日大、専修)を合併して、帝大法科に匹敵する「一大法律学校」を作ろうというアイディアが出されました。結局うまく行かなかったのですが、現在の各大学のロースクールの苦境を見ていると、再びこのような再編・統合の話が出てきてもおかしくはないような気がしました。
森本 たしかにありうる話ですね。そういう動きに対する東大側の焦りや対応も面白かった。
「おカネ」は反知性主義の軸になるのか?
河野 このように、『反・東大』に出てくる大学ネタを話していると、面白くてキリがないのですが、せっかく森本さんをお呼びしたので、もう少し大きな視点から本書を論じてみたいと思います。
この本には、単なる偏差値教育批判などを超えた、もっと本質的な思想史的な意義があるというのが私の感想です。最初に申し上げた通り、私はこの本を「日本における反知性主義」として読むべきだと考えていますが、森本さんはどう思われますか?
森本 反知性主義と言うからには、単に上下の逆転を狙う「下剋上」の思想ではなく、知的権威に対抗しうる「別の軸」を提示することが必要になると思います。アメリカの場合で言えば、キリスト教の信仰復興運動(リバイバリズム)という宗教的な軸がありました。日本でそのような軸が出せるかどうかですね。
河野 森本さんのご著書『反知性主義』で興味深かったのは、アメリカでは知性主義に対抗する連合として信仰とビジネスというある意味正反対のものが結びついていくんだというお話でした。『反・東大』で描かれた、慶應義塾や一橋大学が実業・ビジネスという軸で官僚養成の東大に挑戦していこうとする構図も、その意味でのビジネス的反知性主義、実務家的反知性主義の系譜とは見ることはできませんか。
とくに福澤は「官尊民卑」を打破する力として、カネの力に強く期待しています。大富豪になれば、東大出身の高級官僚にも対抗できると考えた。それでしきりに「カネ儲けのすすめ」を説き、世間からは「拝金宗」などと批判されるほどでした。ベンジャミン・フランクリンと福澤の類似性というのは時折語られるテーマですが、福澤はアメリカの反知性主義の影響をかなり直接的に受けているのかもしれません。
森本 たしかに19世紀アメリカでは、富の力が知的権力に対抗する「別の軸」になっていました。鉄鋼王カーネギー、鉄道で財を成したスタンフォードやヴァンダービルトらは、大学教育を受けずに実業の世界で大成功し、アメリカ社会の平等や民主主義を体現する存在となりました。
しかし、そんな彼らも、やがて「自分たちの時代は教育がなくても成功できたが、新しい時代には教育が必要である」と痛感するようになり、その巨万の富を使ってそれぞれの名を冠した大学を設立するようになります。やはりお金だけでは、知性主義に対抗する「別軸」としては、少し弱い。
河野 なるほど、そう考えると、いまや東大生も外資系に就職したり起業したりというのは、反知性主義を支える「別の軸」だった「カネ儲け」の世界にも、新たに東大が進出してきたということなのかもしれませんね。これもやはり、尾原さんが指摘するような「敵」や「外部」を取り込んで自らを変えていく東大の強さという話につながります。これからの「反・東大」の軸をどこに立てるべきか、あらためて尾原さんの本を読んで考えなければなりませんね。
(「後編 政治家が高学歴化しないのは日本の知的伝統?」につづく)
-
尾原宏之 /著
2024/5/22発売
公式HPはこちら
-

-
河野有理
1979年、東京都生まれ。東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。日本政治思想史専攻。首都大学東京(当時)法学部教授を経て、現在、法政大学法学部教授。主な著書に『明六雑誌の政治思想』(東京大学出版会、2011年)、『田口卯吉の夢』(慶應義塾大学出版会、2013年)、『近代日本政治思想史』(編、ナカニシヤ出版、2014年)、『偽史の政治学』(白水社、2016年)、『日本の夜の公共圏:スナック研究序説』(共著、白水社、2017年)がある。
-

-
森本あんり
1956年、神奈川県生まれ。東京女子大学学長。国際基督教大学(ICU)人文科学科卒。東京神学大学大学院を経て、プリンストン神学大学院博士課程修了。国際基督教大学人文科学科教授を経て、現職。専攻は神学・宗教学。著書に『アメリカ的理念の身体』(創文社)、『反知性主義:アメリカが生んだ「熱病」の正体』(新潮選書)、『宗教国家アメリカのふしぎな論理』(NHK出版新書)、『異端の時代』(岩波新書)、『キリスト教でたどるアメリカ史』(角川ソフィア文庫)、『不寛容論;アメリカが生んだ「共存」の哲学』(新潮選書)など。
この記事をシェアする
「河野有理×森本あんり「日本の『反知性主義』を問い直す」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 河野有理
-
1979年、東京都生まれ。東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。日本政治思想史専攻。首都大学東京(当時)法学部教授を経て、現在、法政大学法学部教授。主な著書に『明六雑誌の政治思想』(東京大学出版会、2011年)、『田口卯吉の夢』(慶應義塾大学出版会、2013年)、『近代日本政治思想史』(編、ナカニシヤ出版、2014年)、『偽史の政治学』(白水社、2016年)、『日本の夜の公共圏:スナック研究序説』(共著、白水社、2017年)がある。
-

- 森本あんり
-
1956年、神奈川県生まれ。東京女子大学学長。国際基督教大学(ICU)人文科学科卒。東京神学大学大学院を経て、プリンストン神学大学院博士課程修了。国際基督教大学人文科学科教授を経て、現職。専攻は神学・宗教学。著書に『アメリカ的理念の身体』(創文社)、『反知性主義:アメリカが生んだ「熱病」の正体』(新潮選書)、『宗教国家アメリカのふしぎな論理』(NHK出版新書)、『異端の時代』(岩波新書)、『キリスト教でたどるアメリカ史』(角川ソフィア文庫)、『不寛容論;アメリカが生んだ「共存」の哲学』(新潮選書)など。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら