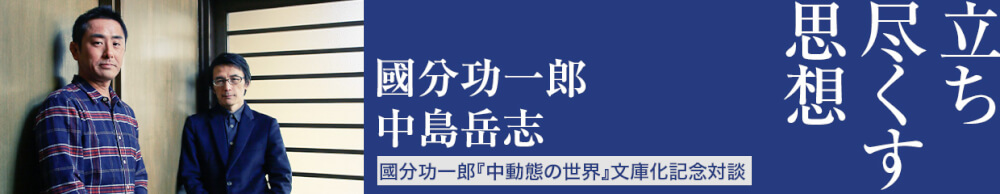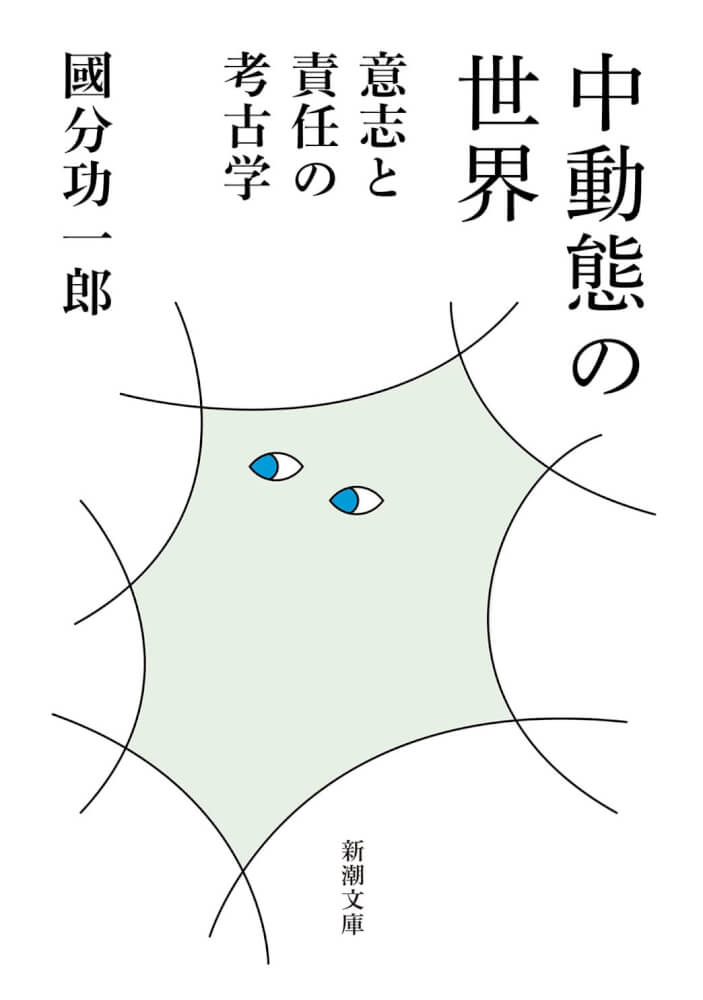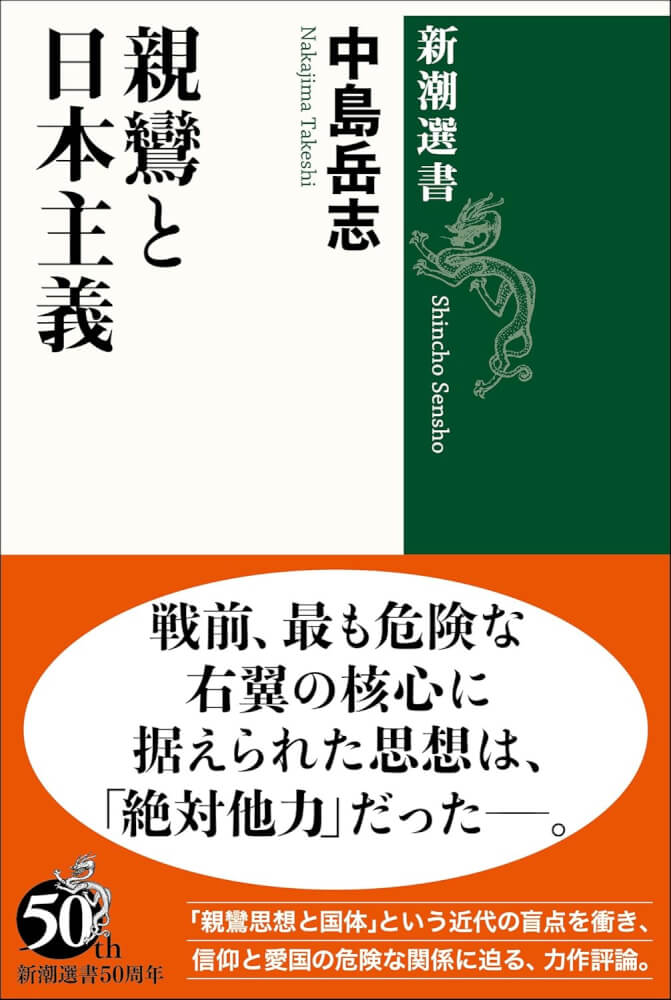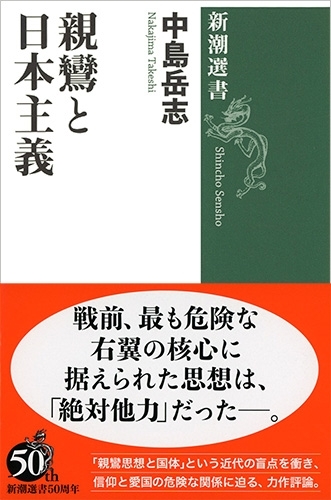2025年4月11日
第2回 尻の政治――立憲主義と民主主義
哲学者・國分功一郎さんの『中動態の世界 意志と責任の考古学』がついに文庫化! それを記念して、政治学者・中島岳志さんとの対談をお送りします。
対談は6年前、2019年1月に実施。当時、東京工業大学(現・東京科学大学)の「同僚」で、かつ「同学年」のふたりが、それぞれの著作(『中動態の世界』や『親鸞と日本主義』など)について語り合いました。『中動態の世界』で國分さんが、「いまわれわれは言語と思考の関係を社会や歴史のなかで考えるという、ある意味では当たり前の出発点に立っている」と述べたように、「言葉」についてスタートした対談は、やがて政治や思想といった領域にまで広く深く展開していきます。知性と覚悟にみちあふれた濃厚な議論をお見逃しなく!
(目次)
【第1回】 言葉はどこからやって来るのか――中動態と与格構文(4月4日配信)
【第2回】 尻の政治――立憲主義と民主主義(4月11日配信)
【第3回】 立ち尽くす思想――スピノザと親鸞(4月18日配信)
【第4回】 もう一隻の船をつくる――熱狂と懐疑(4月25日配信)

(第1回 言葉はどこからやって来るのか――中動態と与格構文)
死者の民主主義
中島 私自身、保守思想というものを研究し、自分の中でも大事にしていますが、中でもエドマンド・バークやアレクシス・ド・トクヴィルの影響が大きい。
トクヴィルは、20代で初めてアメリカを旅行します。その時の大統領は、第7代アンドリュー・ジャクソンで、この人はドナルド・トランプの原型のようなポピュリストでした。史上唯一、議会から不信任決議を突き付けられた大統領で、後世の評価も当然高くありません。
トクヴィルは母国であるフランスの政治に失望し、アメリカを視察しようと考えました。アメリカのデモクラシーがフランスよりも機能しているように見えたのは、大統領のリーダーシップが優れているからだろうと仮定していたはずです。一方で、民衆が自分たちの手で掴んだはずのフランスのデモクラシーは、革命以降、恐怖政治に陥り、ナポレオンによる専制政治を呼び込み、崩壊の危機にあると。
ところがアメリカに行ってみると、ポピュリストで差別主義者のジャクソンが、トップに立っている。トクヴィルはジャクソンを徹底的に批判していますが、一方で、「それでもなぜアメリカのデモクラシーは機能しているのだろうか?」という別の問いが浮かぶわけです。そこで彼は、アメリカの制度や“habits of the heart”つまり「心の習慣」に注目します。とりわけ関心を寄せたのは、教会や「〇〇協会(アソシエーション)」といった宗教的・地域的なコミュニティです。
こうした国家と個人の間に存在する「中間領域」であるコミュニティが、アメリカのデモクラシーを下支えしていることにトクヴィルは気づきます。さまざまな人々がそこで交流している。自分とは主義主張が異なる他者と交わり、合意形成していくというプロセスを、アメリカの特に地方政治では大事にしていて、それこそがアメリカのデモクラシーにおける最大の特長であり、叡智ではないかということをトクヴィルは見出した。いくらとんでもない奴が選挙でトップに選ばれたとしても、デモクラシーは機能する。そのための制度がアメリカにはきっちり存在している――ということを書いたのが、『アメリカにおけるデモクラシーについて』(中公クラシックスなど)です。
私が考える立憲主義にもその発想があります。つまり今生きている人間がいくら民主的手続きに沿って選択をしようと、だからといって「やってはいけない価値」はある。それを踏みにじることは、これまでずっと積み上げてきた過去の経験や教訓を反故にすることである。また、そうした経験や教訓は、さまざまな習慣や中間領域に組み込まれているので、それらの制度改革については慎重にならざるを得ない――それが私の考える保守というものの中核にある考え方です。
この時にずっと考えているのは、主体の違いです。つまり立憲主義と民主主義が対立する理由として、主体の違いがあるのではないか。その対立には主語の違いがあるのではないかと考えるわけです。
過去の歴史において、さまざまな失敗があった。未来を考えるためには、その経験を活かさないといけない。「こんなことをやってはいけない」という制約を、過去に遡って考える。その過去における主体は、すでに今この世からいなくなった死者であろうと。一方で民主主義は、主体を生きている人間に限定しているのではないか。つまり、民主主義の中から死者が除外されているのではないか、いわば生者至上主義が問題ではないかということを、このところずっと考えています。
國分 なるほど。死者を考えるべきというのはそういった意味だったのですね。
中島 はい。だから保守を標榜するものは、すべからく立憲主義的立場を取るべきであると私は考えます。過去の歴史によって我々は制約をされている。あるいは、それが制度の中にあらわれている――そういった感覚を持って、政治というのを考えなければいけないだろうと。
そして、ここでまた与格の問題が出てきます。
國分 そうか。ここで与格が出てくるのか。
中島 そうなんです。「私にあなたへの愛がやって来てとどまっている」というように、「現代の政治に言葉や制度が過去からやって来てとどまっている」と、与格構文的に考える必要性がある。言葉や制度が過去や死者からやって来るようなものとして、政治制度あるいは民主主義というものに突き刺さっていかなければいけないと考えるべきではないでしょうか。
そのあたりが、ネグリの議論に対して私が距離を感じる理由でもあります。それは一義的には神の除外の問題だと思っていたのですが、「民主主義と立憲主義」つまり「生者と死者」という問題も根深くある。
精神的貴族――ハンナ・アーレントから学ぶべきこと
國分 しかし立憲主義というものが、こんなにも重要になるとは思いませんでしたよね。
中島 まさに。10年ぐらい前、今申し上げたような立憲主義についての文章を新聞に寄稿したのですが、それを読んだある憲法の専門家から、「中島君は、立憲主義なんて若いのに随分古いことを言うね」と言われたことがあります。
その人は左翼的スタンスを取っている人で、「中島君はやっぱり保守思想の人だから、立憲主義を尊ぶのだね」と、まあ揶揄されたわけです。憲法学者にとって、立憲主義というのはそういった扱いなんですよね。前時代的かつ保守的なものであると。統治行為論(註 国家機関の行為のうち極めて高度の政治性を有するものについては司法の審査の対象とならないとする理論)なんかもそうですが、民主的に選ばれた政治主体の決定にこそ価値があって、司法はそれを制約すべきではないというのが、いわゆるリベラルな考え方になる。
なるほどそういうことかと思っていたのですが、そこを突いてきているのが安倍政権です。つまり安倍晋三や橋下徹というのは、ある意味で、「超民主主義者」だと言える。
國分 その通りですね。あの人たちは、自分たちこそが民主主義を体現していると考えているはずです。
中島 多数決によって自分たちは選ばれた、その政治家の意志こそが“民意”だろうと考えるわけです。しかし保守というのは、先ほども申し上げたように、それでもやってはいけないことがあると考える。過去や歴史や死者による制約を無視できない。なのに「保守」を自称している人たちが、超民主主義であるという、さて、このズレをどうしたらいいのか。
國分 今、危機感をもって立憲主義の重要性を語っている人物のひとりが憲法学の樋口陽一先生です。僕も樋口先生の立憲主義理解をもっと勉強したいと思っています。最初の著書である『近代立憲主義と現代国家』(勁草書房、1973年)を出された時は、民主主義への反動みたいな批判もあったようですが、その頃から一貫した主張をなさっている。そこで議論されていた問題が、最悪の形であらわれてきたのが今という時代(註 対談は2019年1月に実施)でしょう。
以前、中島さんが新聞に「死者の民主主義」ということを書いていて、これはどういう意味で言っているのかと思っていましたが、今の話でようやく見えてきました。民主的主体に死者は含まれていないが、立憲的な主体には死者が含まれている――まずはこうまとめてもいいのではないでしょうか。
中島 そうですね。
國分 ただ、「死者」という言葉はとても大事だと思いますが、そこで止まってしまっては、見えづらくなる部分もあると思います。なので、そこからもう少し話を展開していきましょう。
中島 もちろんです。
國分 先ほどトクヴィルのくだりで、アメリカのデモクラシーを根っこから支える「中間領域」という話をされました。それこそが、民主主義を正常に機能させる重要なものであると。政治学者のハンナ・アーレントも同じようなことを言っていますね。
アーレントは『全体主義の起源』で、大衆社会になって一番大きな出来事のひとつは階級の消滅であると書いています。それまで階級というものが、最も強力な「中間領域」として機能していた。中島さんの議論を受けると、階級というのは、そこを媒介にして「死者」という存在を伝えてきたとも言える。制度や習慣、そして言葉も、かつては階級に帰属していた。暮らし全般を規定するものとして、階級というものがあったわけです。つまり、ある種の価値の源泉にある立憲的主体――そこには死者も含まれます――が、階級を通して伝わってきたと言える。
それが資本主義の導入と大衆社会の成立によって解体され、バラバラになっていく。主体が平均化して孤立し、砂粒のようにバラバラになる。そのバラバラの砂粒が、ある時一気にまとめ上げられて全体主義が誕生する――これがアーレントの見立てです。
中島 そうですね。
國分 白状すると、僕はこれまでアーレントが嫌いだったんですよ。彼女はスピノザが嫌いだったから、それも当たり前なのですが。でもこの5年ぐらいは、アーレントを読まなければ何もわからない、アーレントを読まなければ今の日本の政権がやっていることを批判できないという強い確信を抱くに至りました。そして読めば読むほど、「あ、これだ!」と今の社会とパラレルな問題を彼女が論じていたことに気づいたのです。
特に20世紀初頭のドイツ、いわゆるワイマール期についての議論です。最近になって当時のことを勉強しているのですが、1919年にワイマール憲法が成立し、共和政が始まりますが、第一次世界大戦の多額の賠償金に苦しめられるなど、問題は山積みで政府は舵取りに苦心します。1920年に初めて行われた国会選挙では、政府に批判的な極右と極左がそれぞれ勢力を伸ばし、次第に議会制民主主義が機能しなくなる。一方で、差別やテロも横行していく。行政の力が拡大して、立法府がその機能を失い、最終的にはナチスの台頭を許すわけです。多くの人がすでに指摘していますが、今の日本の政治状況と非常にパラレルな状況でした。
この歴史をどう考えるかといった時に、やはりアーレントを持ってこなければいけない。ただもちろん彼女の議論をそのままトレースすることはできません。はたしてアーレントが民主主義者か、というのも議論の分かれるところだし、僕は違うのではないかと思っていますが。彼女は階級の崩壊を嘆いているところもあるし、『人間の条件』では、「精神的貴族性」の消滅を嘆いている。これに僕は共感するところもあります。「精神的貴族性」というのは、何か生まれや血統による特権ということではなくて、簡単に言えば、価値を内面化した主体ということでしょう。
中島 そうですね。
國分 徳というものを内面化した主体が「精神的貴族性」ということで、僕もこれは大事なことだと考えます。もちろん階級制度というものを今さら肯定するわけではありませんが。

尻の政治――オルテガから学ぶべきこと
中島 先ほどワイマール期のドイツの話が出ましたが、私はオルテガの『大衆の反逆』がその時代を考えるポイントになると思っています。先日、NHKの「100分de名著」に出演したのですが(註 2019年2月放送)、そこでは『大衆の反逆』を取り上げました。國分さんは、同じ番組でスピノザの『エチカ』についてお話されていました。
國分 はい。僕が出演した回は2018年12月の放送です。
中島 先ほど、アーレントの「精神的貴族性」の話が出てきましたが、実はオルテガも「貴族」という言葉をほぼ同じ意味で用い、それを重要なものだと考えていたんです。
オルテガが『大衆の反逆』を刊行したのは1929年、ワイマール時代の後期にあたり、ヒトラー内閣が成立する4年前です。1917年にはロシアで革命が起きて、1922年にはイタリアでファシスト党のムッソリーニによる政権が樹立する。つまりオルテガは、共産主義や全体主義が徐々にその姿を見せ始めた時に『大衆の反逆』を書いている。オルテガは、ボリシェヴィズムとファシズムを「二つの偽りの夜明け」と批判しています。
オルテガの言う「大衆」とはどのような人間かというと、「エリート」と対置されるような階級的な意味ではありません。英語だと「mass-man」、つまり「大量にいる人」という意味です。彼は、トポス(場所)を失い群衆化してしまった人間のことを「大衆」と呼びます。つまり居場所や個性、社会的役割を見失ってしまった人々のことです。
こうした「大衆」が権力を握り、熱狂によって暴走するとどうなるか――。オルテガによると、それこそが当時のヨーロッパで起こったことだと批判するわけです。つまり、大衆の熱狂が結果的に多数者の専制を生み出す危険性を指摘していました。まさに同時代的にドイツやロシア、イタリアで起きていたこととシンクロしています。
そうした全体主義にいかにして抵抗するか――。オルテガが言っているのは、先ほどのアーレントの「精神的貴族性」と通じるところがあります。もちろん彼も階級社会を復活させろと言っているわけではありません。そうではなく、リベラルであることを尊ぶためには、貴族的な美徳を大事にしろというわけです。他者に配慮し、多数は少数を認め、その意見を傾聴する。オルテガにとってリベラリズムであることは、高貴であることとイコールでした。
國分 確かにアーレントと非常によく似ていますね。
中島 『大衆の反逆』に私の好きな一節があるので、引用します。
敵とともに生きる! 反対者とともに統治する! こんな気持のやさしさは、もう理解しがたくなりはじめていないだろうか。反対者の存在する国がしだいに減りつつあるという事実ほど、今日の横顔をはっきりと示しているものはない。ほとんどすべての国で、一つの同質の大衆が公権を牛耳り、反対党を押しつぶし、絶滅させている。
ここでオルテガが指摘しているように、「大衆」は敵対する勢力とともに生き、相容れない主張や意見にも耐え得るといった人間像を放棄している。みなが群れるようにして平均人化して、しかも平均人であることに喜びを見出している。逆に平均化されない人間を疎ましく思うような人間ばかりが溢れ返っていることが、20世紀の大きな問題で、そうした人たちが最終的に訴えるのは暴力であるとまでオルテガは言っています。
國分 まさに今の世界にも通じる話ですね。
中島 私はオルテガの「支配するとは、拳(で撲ること)より、むしろ尻(で坐ること)の問題である」という言葉が好きなんです。つまり、政治に関わる人間は、じっくりと座って相手と話すべきであると。拳に訴えて支配するのではなく、そこにドカッと座りながら話を聞き、反対意見をふまえながらバランスを取らなければいけない。それが政治の本質であるはずなのに、みんな尻ではなく、いかに拳で制圧するかという話ばかりしている。そうではなく、とにかくまずは座れと、オルテガは言うわけです。
國分 「尻の問題」とは、いい言葉ですね。僕はイギリス滞在中に当地の議会政治のあれこれを見ていて、“sticky”という言葉を思い浮かべました。“sticky”というのは、「ねばねばする。べとつく。粘着する」という意味で、何かが起こるとすぐに右から左へ砂のように動くのではなく、そこにベトベトと居座る。イギリスの議会政治の伝統はさすがだなと思っていたのですが、オルテガの「尻の問題」というのは、まさに“sticky”であることとイコールのような。
中島 ピッタリですね。オルテガも保守的なビジョンを持っていた人で、イギリスの保守政治というものが念頭にあったと思います。だからこそ彼は、「イギリス人は、国家が限界をもつことを望んでいる」という言葉を残したのでしょう。
共産主義やファシズムといった急進的改革を求める勢力に対して、伝統や慣習、良識というものをベースにした漸進的改革こそが政治の本質であると、保守思想は訴えます。だから、保守の中核にあるのは自己に対する懐疑なんですよね。あるいは人間の理性万能主義に対する懐疑。もちろんその懐疑の念は、自分にも向けられるわけです。常に「そういう自分だって間違っているかもしれない」という人間像や自己認識を持っていれば、自然と他者の意見に耳を傾けてみようとなるはずだろうと。
それが「尻の政治」であり、「stickyな政治」である。自分とは異なる主張をしている人の意見をまずは聞く。その結果、「なるほど」と思えば、合意形成へと進んでいく。それが保守の政治で、保守は必然的にリベラルな態度をとらざるを得ない。それこそが伝統的な保守であり、オルテガの主張でもある。
オルテガが一番恐れたのは、このリベラルという観念が失われることでした。オルテガには、保守でありながら自分こそがリベラルだという意識があったはずです。一方で、ロシア革命なんてリベラルでも何でもないと考えているわけです。このオルテガの問いというのは、とてもアクチュアルなものだと思います。
國分 オルテガとアーレントが大事なところで呼応するのが、実に興味深いですね。

「“右”と“左”」ではなく
中島 私がオルテガを知ったのは、師匠である西部邁さんの著作を通してです。彼もオルテガから圧倒的な影響を受けています。
國分 僕にもオルテガと言えば西部さん、というイメージがあります。
中島 先ほどのアーレントでも、オルテガでもいいのですが、とにかく従来の政治における右と左の対立ではなく、別の補助線を引かなければいけない。
さらに「保守とは何か」を本質的に考えれば、安倍政権が保守だとは到底思えない。彼らが保守を標榜すればするほど、私としては批判的にならざるを得ません。
構造的な論理をきっちりと考えて、従来の左右の対立軸に依らない「もう一隻の船」をどうにかしてつくりたいと考えています。それはおそらく國分さんと大体のところでは一致する部分だと思う。二人の背後にはスピノザがいて親鸞がいる。あるいは、アーレントがいてオルテガがいる。さらに中動態と与格構文もあるかもしれない。
右と左だけでは語れない政治の枠組みというものを、哲学や思想や人間観というものをフル動員してつくる――その作業の礎となることを、今回の議論でできればいいなと考えています。
國分 それはこちらも望むところです。
それで思い出したのですが、ドゥルーズも一時期アメリカでは「右翼思想家」と叩かれました。先ほども言ったように、その根っこには保守主義的な心性があるので、そこを批判された。スピノザについても、フランソワ・ズーラビシヴィリというフランスの哲学者――僕もお会いしたことがあるのですが、2006年に40歳という若さで亡くなりました――が、『スピノザの逆説的保守主義』(2002年、未邦訳)という本を書いているように保守とみなされることもある。
スピノザの有名な概念に「コナトゥス」というものがあります。これは直訳すれば「努力」ということになりますが、「頑張って何かをする」ということではなく、「自分の存在を維持しようとする力」というニュアンスがあります。この「コナトゥス」も考えてみれば、とても保守的な概念です。しかしそれまでスピノザの保守性はあまり顧みられることはなかった。それがちょっと不思議ではあります。ネグリのスピノザに対する理解で一番欠けているのもこの部分かもしれません。
どちらかというと、これまで「コナトゥス」というのは、活動能力が高まればいいという話になっていて、実はそれが全体主義に近づくこともある。
中島 そうなんですよね。先ほどから議論している中動態や与格構文、あるいはスピノザの「能産的自然(註 生み出された自然[所産的自然]に対して、これを生み出す力としての自然のこと。多くは神や絶対者を意味する)」が、全体主義的思想につながってしまう危険性もあるわけです。それらが誤解され悪用されて、例えば憲法制定権力みたいなものにダイレクトにつながってしまう危険もある。
そうならないためには、中動態的・与格的な人間観を大切にしながらも、それに歯止めをかけるものとして、死者や歴史、価値や制度が重要になってくる。さらにその背景としてある保守思想。それらをふまえて、次の時代に向けてどのような政治を構想できるか――それが私のビジョンですが、右と左の問題ではないことは明らかです。
-

-
國分功一郎
1974年千葉県生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、東京大学大学院総合文化研究科修士課程に入学。博士(学術)。専攻は哲学。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授。2017年、『中動態の世界――意志と責任の考古学』(医学書院)で、第16回小林秀雄賞を受賞。主な著書に『暇と退屈の倫理学』(新潮文庫)、『来るべき民主主義 小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題』(幻冬舎新書)、『近代政治哲学 自然・主権・行政』 (ちくま新書)、『スピノザ 読む人の肖像』(岩波新書)など。最新刊は『目的への抵抗 シリーズ哲学講話』(新潮新書)。
-

-
中島岳志
1975年、大阪府生まれ。政治学者、東京科学大学(旧東京工業大学)リベラルアーツ研究教育院教授。専門は、インド政治、日本思想史、現代日本政治。大阪外国語大学外国語学部ヒンディー語学科卒業、京都大学大学院博士課程修了。北海道大学公共政策大学院准教授を経て、現職。2005年、『中村屋のボース インド独立運動と近代日本のアジア主義』(白水社)で、大佛次郎論壇賞とアジア・太平洋賞大賞を受賞。主な著書に、『「リベラル保守」宣言』(新潮文庫)、『血盟団事件』(文春文庫)、『親鸞と日本主義』(新潮選書)、『保守と立憲』(スタンド・ブックス)、『思いがけず利他』(ミシマ社)、『テロルの原点 安田善次郎暗殺事件』(新潮文庫)など。
この記事をシェアする
「國分功一郎×中島岳志「立ち尽くす思想」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 國分功一郎
-
1974年千葉県生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、東京大学大学院総合文化研究科修士課程に入学。博士(学術)。専攻は哲学。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授。2017年、『中動態の世界――意志と責任の考古学』(医学書院)で、第16回小林秀雄賞を受賞。主な著書に『暇と退屈の倫理学』(新潮文庫)、『来るべき民主主義 小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題』(幻冬舎新書)、『近代政治哲学 自然・主権・行政』 (ちくま新書)、『スピノザ 読む人の肖像』(岩波新書)など。最新刊は『目的への抵抗 シリーズ哲学講話』(新潮新書)。
対談・インタビュー一覧
-

- 中島岳志
-
1975年、大阪府生まれ。政治学者、東京科学大学(旧東京工業大学)リベラルアーツ研究教育院教授。専門は、インド政治、日本思想史、現代日本政治。大阪外国語大学外国語学部ヒンディー語学科卒業、京都大学大学院博士課程修了。北海道大学公共政策大学院准教授を経て、現職。2005年、『中村屋のボース インド独立運動と近代日本のアジア主義』(白水社)で、大佛次郎論壇賞とアジア・太平洋賞大賞を受賞。主な著書に、『「リベラル保守」宣言』(新潮文庫)、『血盟団事件』(文春文庫)、『親鸞と日本主義』(新潮選書)、『保守と立憲』(スタンド・ブックス)、『思いがけず利他』(ミシマ社)、『テロルの原点 安田善次郎暗殺事件』(新潮文庫)など。
対談・インタビュー一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら