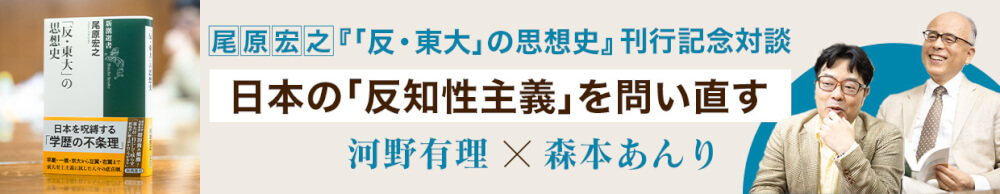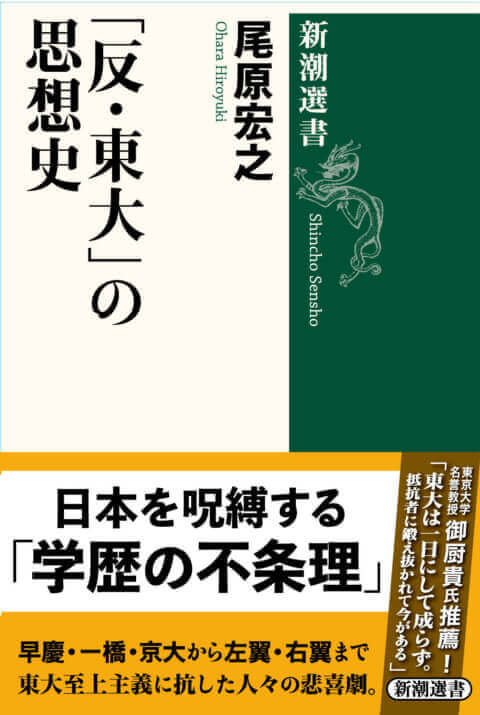2024年6月13日
尾原宏之『「反・東大」の思想史』刊行記念
後編 政治家が高学歴化しないのは日本の知的伝統?
尾原宏之さんの「考える人」連載をまとめた『「反・東大」の思想史』が、新潮選書から刊行されました。刊行を記念して、東京大学の出身で、尾原さんと同じく日本思想史を専門とする河野有理・法政大学教授と、『反知性主義:アメリカが生んだ「熱病」の正体』(新潮選書、2015年)の著者、森本あんり・東京女子大学学長が、本書をめぐって対談しました。
(「前編 東大の学費は値上げすべきなのか?」はこちらから)
日本の知的伝統は「反・科挙」?
森本 アメリカの反知性主義には、「神の前ではみな平等である」というキリスト教的な軸があります。だから、ハーバード大学やプリンストン大学の出身者と対峙しても、一歩も引かない強さがある。もし「反・東大」が日本版の反知性主義だとするなら、何がその思想的な軸となるのでしょうか?
河野 その軸をひと言で説明するのは難しいのですが、私のような日本思想史研究者の目から見ると、日本には明らかに反知性主義の伝統があると感じます。尾原宏之さんの『「反・東大」の思想史』(以下、『反・東大』と表記)で扱っているのは明治以降の時期ですが、これに江戸時代以前の思想史を補助線として加えると、それが分かりやすくなると思います。
江戸の反知性主義を考える時には、その反対、つまり東アジアの知性主義を考える必要があります。中国大陸そして朝鮮半島、いずれも科挙による能力試験を導入していました。試験に受かった人が権力を握るという制度が社会的に実装されていたわけです。これに対する江戸の社会は世襲の軍人による支配です。
つまり、中国大陸や朝鮮半島が「勉強すれば偉くなれる社会」だったのに対し、江戸の社会はそうではない。江戸時代の人々にとって「勉強し過ぎるのは良くない」というのが普通の感覚であって、むしろ勉強すると人格が悪くなるとさえ思っている(笑)。
森本 そこに「門閥制度は親の敵(かたき)」という福澤諭吉が、『学問のすすめ』を掲げて登場するわけですね。
河野 まさにその通りなんですが、これもまた『反・東大』に大変興味深いエピソードが出てきます。『学問のすすめ』で、勉強ができる者が出世するメリトクラシー的な社会を目指していた福澤が、東大と対抗していく中で、徐々に「反・学問のすすめ」としか呼びようのない主張に転じていく。
森本 ああ、あそこは面白かったですね。貧乏人に高度な教育を与えると、気位が高くなって自らの境遇に不満を抱き、社会の安寧を乱すようになるとか、今の時代からすればとんでもない主張を福澤が始めるんですが、明治日本の強い上昇志向社会を背景に考えれば、理解できるように思います。
河野 東大が創設されて、日本の科挙とも言うべき高等文官試験が行われ、官僚が我が物顔で幅を利かすようになると、「勉強ができるからって、それだけがすべてじゃない!」というメンタリティが出てくる。これは江戸以来の「日本の反知性主義」の逆襲として見ることができるのではないか。
政治家の学位が低いのはなぜか
森本 そうか! 今でも「勉強だけがすべてじゃない」という考え方はありますが、そのルーツは江戸時代まで遡ると見えてくるのですね。まあ、実際にその台詞が出てくる場面を考えると、確固とした信念というより、勉強嫌いの言い訳みたいに聞こえそうだけど。
河野 よく言われることですが、いまだに日本の政治家の学歴はそう高くない。いや、東大とか慶應とかごろごろいるじゃないかと言われるかもしれません。また『反・東大』のなかではマスコミと並んで政界に人材を多数送り込んだ早稲田のことが扱われていましたが、たしかに早稲田も多そうです。「雄弁会」とか(笑)。ただそこで言われているのは専門的には「学校歴」のことで、「学位」という意味での「学歴」ではない。端的に言えば、修士号や博士号を持っている政治家はいまだにごくわずかです。これに対し、たとえば欧州では多くの政治家が当然のように博士号を持っています。
森本 そうなんです。その点では日本はちっとも学歴社会なんかじゃなくて、「教育後進国」です。その一方で、さっき河野さんが言われたように、「だから何なんだ」と開き直る人も多いでしょう(笑)。大学教員の立場からするとやや複雑な気持ちですが、その意味では日本はとても平等な社会と言えるのかもしれません。
河野 おっしゃる通りです。欧州の高学歴の政治家たちが、エリート意識丸出しの政治を行って国民の反感を買っている姿を見ていると、むしろ日本の方がいいんじゃないかとさえ思えてくる(笑)。実際、たとえばヤシャ・モンクのような政治学者は欧米における議員の極端な高学歴化をリベラル・デモクラシーの危機の要因の一つに挙げていますが、その心配は、幸か不幸か、日本にはなさそうです。
いま文科省は博士号取得者を増やしていこうと躍起になっていて、私もそのこと自体は悪い話ではないと思っていますが、はたして反知性主義の土壌がある日本社会で受け入れられるかどうか・・・。
森本 企業の側も、博士号を取った30歳過ぎの人材を採用するよりも、学部を卒業したばかりの若い人材にオン・ザ・ジョブ・トレーニングを施した方がいいという発想が根強くあるように見えますね。
「キッザニア」から見える職業観
河野 このギャップは、欧米とのあいだにだけでなく、東アジアの諸国とのあいだにもあります。春木育美さんの『韓国社会の現在』に紹介されていたのですが、職業体験テーマパーク「キッザニア」では、韓国と日本でその内容に違いがあるそうですね。
森本 へぇー、そんなに違うんですか?
河野 一言でいうと、日本の「キッザニア」には職人やブルーカラー労働が子どもたちが体験できる職業として用意されているのですが、韓国にはそれはないのだそうです。かわりに外交官とか国連職員とか、そういう仕事が用意されている。
森本 それは知りませんでした。なるほど違いますね。
河野 関連して言うと、日本では、大学を卒業した人が、パン屋やケーキ屋を始めたとしても大して驚かれないと思うのですが、それはもしかしたら世界的にはあまり当たり前のことではないかもしれない。
たとえばドイツでも、職人を尊重する文化自体はあるそうですが、子どもの進路として見た場合、職人を目指す子どもと、大学に入る子どもとはかなり早い時期に分かれることになります。大学を卒業した人が料理人になることを選択しても別に何の不思議もないということそれ自体が、先ほどお話しした江戸時代以来の言うなれば反知性主義的な構造の産物といえるかもしれませんし、そしてそのことは明らかに日本の強みでもあると思うのですね。
日本の反知性主義の「軸」はどこにあるのか?
森本 こうしてお話ししてみると、たしかに、日本には独特の反知性主義の土壌があることがわかります。ただ、それが正面切って知性主義に対抗する「別の軸」となるかどうか。何となく隅っこでぶつぶつ言っている感じです。
かつて丸山眞男は、日本では学問も芸術もみな政治集団と相似形をなして権力に従属してしまう、と書いています。政治的な価値を超えた価値へのコミットメントが弱い。だから大学も学問もみな政治権力の前に一列に並べられてしまうのではないか。
河野 『反・東大』でも、東大とは異なる価値や教育方針を掲げる教育者・思想家が次々と登場するものの、むしろ学生や父兄の側から東大的な価値、偏差値教育的なものを求められて、四苦八苦する様子が描かれていますね。
森本 中世の聖俗二権論以来、その「別の価値」を提示してきたのが宗教です。日本でもキリスト教系や仏教系の大学が多く存在し、その教育目標などを読むと「国家の大学」とは別次元の内容が掲げられています。私の母校の国際基督教大学(ICU)なんて、名称に基督教を入れた段階で、日本的な「大学」の通念への挑戦です。しかし、それらの大学がどこまで宗教的な軸を学生たちに伝えられているか、また学生の側がどこまでそれを期待しているのかと言えば、心もとないですね。
河野 『反・東大』の第5章では、同志社の新島襄が登場します。せっかく学生たちにキリスト教に基づく教育を授けても、その後に立身出世を求めて東大に進学すると、キリスト教から離れてしまうと嘆いていますね。
森本 身につまされる話です。東京女子大学もキリスト教系の大学で、「高い知性と独立した人格をもつ女性」を育てるのが創立時の理念でした。ところが、いつの間にかみな何となく偏差値や大学ランキングを気にするようになってしまう。そういうものとは異なる教育をするために設立された大学なのに、偏差値やランキングを維持しないと日本では大学として生き残れない。なかなか厳しい闘いです。
河野 日本には、儒教的なメリトクラシーに対抗する反知性主義の伝統が根強くある一方で、東大的なものとは異なる「別の軸」に基づく教育をしようと思っても、それにはなかなか付いて来てくれない。本当に不思議な国ですね(笑)。
森本 いくら大学改革で多様性のある教育を求めても、偏差値に代わる「軸」となる思想がないから、結局は序列化されて「ミニ東大」のような大学が増えてしまう。
河野 そもそも大学選びの際に重視されるのは、各大学が掲げている理念や教育内容よりも、キャンパスの立地だったりしますからね。『反・東大』では、法政大学に勤務していた哲学者の三木清が、東大人気の源は、文化都市・東京のど真ん中にあるという「立地の良さ」にあると喝破していた話が紹介されていました。
森本 リベラルアーツの大学は、あえて都会の外にキャンパスを求めるのが本筋なのですけれどね。拙著『反知性主義』では、日本には強力な知性主義もなければ、強力な反知性主義もなく、あるのは「半」知性主義だけだという教育社会学者の竹内洋さんの見立てを紹介しましたが、それを打破するのはなお難しそうです。
河野 尾原宏之さんの『「反・東大」の思想史』は、そのような日本の反知性主義/半知性主義のあり方を見事に浮き彫りにしていると思います。ぜひ本書を足掛かりとして、日本の反知性主義の思想的な「軸」が明らかになることを願っています。
(おわり)
-
尾原宏之 /著
2024/5/22発売
公式HPはこちら
-

-
河野有理
1979年、東京都生まれ。東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。日本政治思想史専攻。首都大学東京(当時)法学部教授を経て、現在、法政大学法学部教授。主な著書に『明六雑誌の政治思想』(東京大学出版会、2011年)、『田口卯吉の夢』(慶應義塾大学出版会、2013年)、『近代日本政治思想史』(編、ナカニシヤ出版、2014年)、『偽史の政治学』(白水社、2016年)、『日本の夜の公共圏:スナック研究序説』(共著、白水社、2017年)がある。
-

-
森本あんり
1956年、神奈川県生まれ。東京女子大学学長。国際基督教大学(ICU)人文科学科卒。東京神学大学大学院を経て、プリンストン神学大学院博士課程修了。国際基督教大学人文科学科教授を経て、現職。専攻は神学・宗教学。著書に『アメリカ的理念の身体』(創文社)、『反知性主義:アメリカが生んだ「熱病」の正体』(新潮選書)、『宗教国家アメリカのふしぎな論理』(NHK出版新書)、『異端の時代』(岩波新書)、『キリスト教でたどるアメリカ史』(角川ソフィア文庫)、『不寛容論;アメリカが生んだ「共存」の哲学』(新潮選書)など。
この記事をシェアする
「河野有理×森本あんり「日本の『反知性主義』を問い直す」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 河野有理
-
1979年、東京都生まれ。東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。日本政治思想史専攻。首都大学東京(当時)法学部教授を経て、現在、法政大学法学部教授。主な著書に『明六雑誌の政治思想』(東京大学出版会、2011年)、『田口卯吉の夢』(慶應義塾大学出版会、2013年)、『近代日本政治思想史』(編、ナカニシヤ出版、2014年)、『偽史の政治学』(白水社、2016年)、『日本の夜の公共圏:スナック研究序説』(共著、白水社、2017年)がある。
-

- 森本あんり
-
1956年、神奈川県生まれ。東京女子大学学長。国際基督教大学(ICU)人文科学科卒。東京神学大学大学院を経て、プリンストン神学大学院博士課程修了。国際基督教大学人文科学科教授を経て、現職。専攻は神学・宗教学。著書に『アメリカ的理念の身体』(創文社)、『反知性主義:アメリカが生んだ「熱病」の正体』(新潮選書)、『宗教国家アメリカのふしぎな論理』(NHK出版新書)、『異端の時代』(岩波新書)、『キリスト教でたどるアメリカ史』(角川ソフィア文庫)、『不寛容論;アメリカが生んだ「共存」の哲学』(新潮選書)など。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら