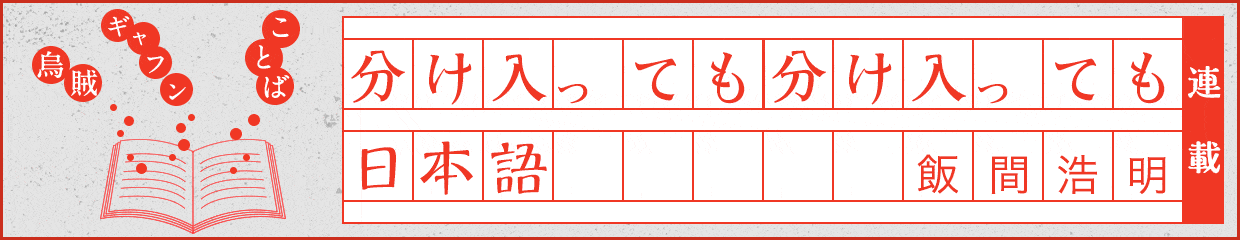小学生向けの新聞のコラムで、「意外で面白い語源のチャンピオン」は何だろうか、と考えてみたことがあります。「意外で面白い」というと、どうもこじつけの疑いがある語源が多いのですが、そういうのとは別に、何かこう、気分が壮大になるような、スケールの大きさを感じさせる語源を考えてみたのです。
私にとって、それはさしずめ「ブドウ」の語源です。ブドウはごく日常的な果物です。子どもでも知っています。ところが、この「ブドウ」ということばが、中国よりさらに西方、中央アジアからやって来た外来語だと聞いたら、どう感じるでしょうか。
私が「ブドウ外来語説」を初めて知ったのは、日本語学者・山田孝雄の著書『国語の中に於ける漢語の研究』(1940年)の記述によってでした。この本には漢語に関する面白いことがいろいろ書かれていて、語源についての記述もありました。
山田によれば、「ブドウ」は〈希臘語Botrus〉(ボトリュス)から来ているといいます。これが本当かどうかは後で考えますが、本当なら、私が今言った中央アジアよりも、さらに遠くから来たことばということになります。「ブドウ」の先祖に当たることばが、遠く古代ギリシャから、シルクロードを経由する長い旅路を経て、中国、さらには日本に渡った――もしそうなら、これほど壮大な語源はありません。
『広辞苑』の編者として有名な新村出は、もう少し慎重な姿勢を取ります。「ブドウ」ということばについて〈古来東西の学者がギリシャ語と漢語とが同じ語源から出ているというaffinity(親近性)を肯定している〉(『語源をさぐる』1951年)。つまり、ギリシャ語と漢語(中国語)の関係には言及しているものの、「ブドウ」がギリシャ語から中国語に伝わったとまでは言っていません。
中国語の「葡萄」(古くは「ブダウ」に近く発音した)は、直接的には中央アジアのことばから入ったという点は間違いなさそうです。
中国前漢の政治家・張騫は、筆舌に尽くしがたい苦労の末、中央アジアの大宛国(フェルガナ)に至ります。『史記』の「大宛列伝」によると、大宛国はブドウ酒(蒲陶酒)と、汗血馬という名馬とを産する土地でした。「蒲陶」は「葡萄」と同じで、中央アジアのことばを漢字で表記したものです。中央アジアではこの果物を「ブダウ」に近い名前で呼んでいて、それが中国に輸入されたと考えられます。
つまり、日本語の「ブドウ」の語源は、古代の中央アジアの言語まではさかのぼれることになります。中央アジアから日本までの距離は、5000キロを超えます。「ブドウ」ということばは、実にはるかな旅をしてきたわけです。
では、さらに遠く、9000キロ以上離れたギリシャまで、「ブドウ」のルーツをさかのぼることはできるか。残念ながら、これは難しそうです。
ブドウの原産地がギリシャでないことは明らかです。『日本大百科全書』を参照すると、ヨーロッパ系のヨーロッパブドウは〈中央アジア起源で、野生種は今日でもアフガニスタン北部から黒海、カスピ海の南部まで分布する〉。したがって、「ブドウ」を表すことばも中央アジアが起源で、そこから周辺に広まったと考えるのが自然です。
アメリカの人類学者ラウファーは、著書『Sino-Iranica』(1919年)の中で、中央アジアから「ブダウ」ということばが中国に輸入されたと考えつつ、古いペルシャ語の「ブダーワ」とも関係があるだろうと述べています。一方、ギリシャ語との関係に関しては否定的です。
ラウファーによると、中国語の「葡萄」が古代ギリシャ語「ボトリュス」(ひと房のブドウ)から来ているという説は、すでに19世紀からあるそうです。でも、彼はそれを否定します。ブドウはギリシャよりも早くにペルシャで栽培され、西アジアからギリシャに伝わりました。だとすれば、「ブドウ」を意味するギリシャ語が中国語に入るはずはありません。
日本語の「ブドウ」はギリシャではなく、中央アジアからやって来たものと考えられます。それだって十分スケールの大きな話です。ごく身近な「ブドウ」ということばが、そんなにも遠くからやって来たというのは驚くべきことです。「意外で面白い語源のチャンピオン」と呼ぶにふさわしいでしょう。
古代ギリシャ語の「ボトリュス」が中央アジアに伝わったのではないにせよ、逆に、中央アジア語の「ブダウ」が古代ギリシャ語の「ボトリュス」になった可能性は残ります。つまり、中央アジア語から日本語へ続くルートとは別に、中央アジア語からギリシャ語に続くルートがあったかもしれない。その場合、日本語の「ブドウ」と古代ギリシャ語の「ボトリュス」は、中央アジアのことばを起源として、間接的につながっていることになります。
日本語がヨーロッパ語と間接的につながっている例として有名なのは「お茶」です。日本語の「お茶」は、言うまでもなく中国語の「茶」から来ています。茶の原産地は中国です。中国語の「茶」は、一方では17世紀にヨーロッパに渡って、英語の「tea」などのことばになりました。つまり、日本語の「お茶」と英語の「tea」は、中国語を起源として、間接的につながっています。
これと同様に、古い時代の日本語とギリシャ語が、間接的につながっていたかもしれない。そう思うと夢が広がります。でも、これは「その可能性もある」という程度に考えておくのがよさそうです。あくまで「日本語の『ブドウ』は中央アジアのことばから来た」ということを、ここでの結論としておきます。
ひとつ、おまけの話を。先に触れた山田孝雄の著書では、花の「牡丹」も元はギリシャ語だとされています。これはさすがに無理でしょう。中国の『本草綱目』によれば、牡丹は主に苗で増える植物(=牡)で、花の赤い(=丹)ものが上等なので、そう呼ぶらしいのです。中国語で「牡」のつく植物は多く、「牡丹」も中国語と考えて差し支えありません。
-

-
飯間浩明
国語辞典編纂者。1967(昭和42)年、香川県生れ。早稲田大学第一文学部卒。同大学院博士課程単位取得。『三省堂国語辞典』編集委員。新聞・雑誌・書籍・インターネット・街の中など、あらゆる所から現代語の用例を採集する日々を送る。著書に『辞書を編む』『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか? ワードハンティングの現場から』『不採用語辞典』『辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術』『三省堂国語辞典のひみつ―辞書を編む現場から―』など。
この記事をシェアする
「分け入っても分け入っても日本語」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 飯間浩明
-
国語辞典編纂者。1967(昭和42)年、香川県生れ。早稲田大学第一文学部卒。同大学院博士課程単位取得。『三省堂国語辞典』編集委員。新聞・雑誌・書籍・インターネット・街の中など、あらゆる所から現代語の用例を採集する日々を送る。著書に『辞書を編む』『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか? ワードハンティングの現場から』『不採用語辞典』『辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術』『三省堂国語辞典のひみつ―辞書を編む現場から―』など。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら