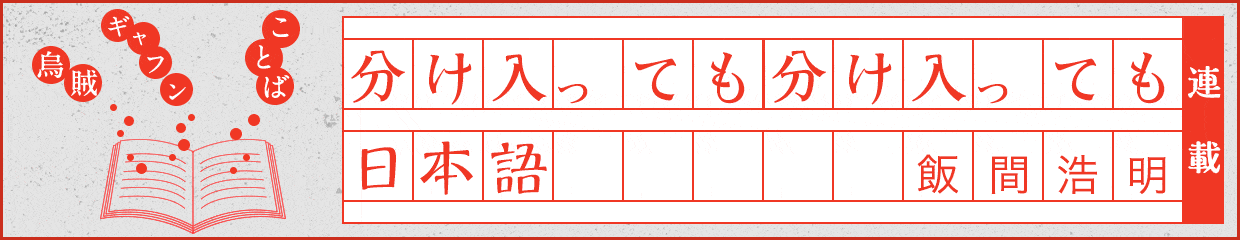夭逝
大学でかつて私の授業を受け、今はことばに関わる仕事をしている優秀な教え子がいます。あるとき私は、彼の手になる詳細な調査報告書を読んでいました。その水準の高さに何度もため息を漏らしたのですが、あるくだりを見て「おや」と思いました。
〈山田美妙は出版を待たず夭逝〉
作家の山田美妙は、『大辞典』という辞書史に残る国語辞典を編纂したが、その完成を見ないままに逝去した、というのです。
ここに使われた「夭逝」は、「夭折」と同じです。「夭」は若いことで、全体として「若死に」を意味します。中国の『三国志』にも出てくる由緒正しい漢語です。
美妙は42歳で病没しました。今なら若死にですが、美妙の亡くなった明治末期の平均寿命は44歳ぐらい。彼の年齢で没することは珍しくありませんでした。
「この当時、40代で亡くなるのを『夭逝』というのはおかしくありませんか」と、私は彼にメールを送りました。報告書の内容には触れず、いきなり枝葉末節の部分について指摘するというのも失礼な話です。
私はつねづね、「自分のことばの選択には厳しく、他人のことばの使用には寛容に」と考えています。もし、相手が一般の書き手であれば、私は決してその人の表現にケチをつけることはしません。それどころか、初めてその表現を知り得たことを喜び、いそいそとデータベースに加えます。
私が教え子の「夭逝」の使い方に言いがかりをつけたのは、いわば同じ業界の人間だったからです。私どものように、ことばを観察する立場の人間は、それぞれのことばの意味や歴史をなるべく頭に入れておく必要があります。でないと、ある表現に接したとき、それが伝統用法か、新用法かが分からないからです。一般人なら、いちいちことばの歴史なんか考えずに表現する自由がありますが、専門家はそうはいきません。
後に、彼からは「おっしゃるとおり、美妙は夭逝するには年を取りすぎています」というメールが送られて来ました。
話はこれで落着したかのようですが、まだ終わってはいません。実際のところ、「夭逝」「夭折」は何歳ぐらいまで使われるのか、という問題が残っています。このことを論じた文章は、ネットなどでもたまに見かけますが、改めて論じましょう。
年齢の低いほうは、誕生して数か月から数年で一生を終えた赤ちゃんにも使えます。森鴎外の文章を見ると、〈生れて四歳にして夭折した〉(「伊沢蘭軒」)、〈三歳で夭折した〉(「渋江抽斎」)などという例があります。
年齢の高いほうは問題です。手元の雑多な資料をあさってみると、たとえば〈樋口一葉は明治二九年二四歳で夭折〉〈二十六歳で夭逝した〔石川〕啄木〉〈金子みすゞは26歳で夭折した〉など、20代の例が多く拾われます。私の個人的な感覚でも、この年齢ぐらいまでなら「夭逝」と言えます。
では、30代はどうか。新聞では、「夭折の詩人 中原中也を偲ぶ」という小冊子が記事になっています。中也は30歳で亡くなりました。
あるいは、俳人で歌人の正岡子規が34歳で没した時、ジャーナリストの古島一念は「天がその才幹〔=才能〕をねたんでこのひとを夭折させた」と言ったそうです。これは司馬遼太郎「坂の上の雲」に出てくる話です。
詩人など文学者の例が多いですね。これは、私の集めた資料が偏っているからではなく、詩人は若い頃にいい作品を書くため、早世した後にも名が残るということでしょう。他の多くの分野では、早くに世を去ってしまえば業績を残せません。
もっと上の年齢で亡くなった人にも使った例があります。
〈三木助の作品の一部は見事に完成された名篇だった。五十二(ママ)歳の夭逝はあまりにも惜しかった〉
落語家の3代目桂三木助についての文章です。3代目は実際には58歳で亡くなっていますが、落語家は80歳を越えても現役でいられるのですから、それからすると早い死だったと言えます。この場合、「夭逝」と言うのは、いいのか、悪いのか。
賛否両論があるでしょうが、私は、問題ないと考えます。50代を指すのは希少例ですが、意味は通じるからです。
「夭逝」は、要するに「若死に」のこと。誰しも、「若死に」が何歳までかは気にしません。それが、漢語で「夭逝」となると、何か意味ありげに思えるのは不思議です。書き手自身が「若死にだ」と思えば、「夭逝」を使っていいのです。もっとも、山田美妙のように、当人が平均寿命近くまで生きた場合は、さすがに無理があるでしょうが。
自分から議論を始めておいて何ですが、「夭逝」「夭折」の年齢制限を論じること自体、実はナンセンスでした。ただ、20代あたりで亡くなった場合に使うイメージが強いのは確かです。したがって、それよりも年がいってから亡くなった場合は、「○歳で夭逝した」と年齢を明示しておいたほうが、相手に誤解を与えずにすみます。
この話は、「初老は何歳からか」という問題に似ています。「初老」は日本で使われてきた漢語で、元来は40歳を指しました。ところが、戦後、平均寿命が伸びるのに伴い、「40歳はまだ若い」というわけで、ことばが指す年齢も上がってきました。
『三省堂国語辞典』の場合、1960年の初版では、「初老」を〈四十才〉とだけ説明していました。それが、74年の版では〈おもに五十代〉、2014年の版では〈おもに六十代〉と手入れがなされました。今の時代、異論はさほど出ないでしょう
-

-
飯間浩明
国語辞典編纂者。1967(昭和42)年、香川県生れ。早稲田大学第一文学部卒。同大学院博士課程単位取得。『三省堂国語辞典』編集委員。新聞・雑誌・書籍・インターネット・街の中など、あらゆる所から現代語の用例を採集する日々を送る。著書に『辞書を編む』『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか? ワードハンティングの現場から』『不採用語辞典』『辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術』『三省堂国語辞典のひみつ―辞書を編む現場から―』など。
この記事をシェアする
「分け入っても分け入っても日本語」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 飯間浩明
-
国語辞典編纂者。1967(昭和42)年、香川県生れ。早稲田大学第一文学部卒。同大学院博士課程単位取得。『三省堂国語辞典』編集委員。新聞・雑誌・書籍・インターネット・街の中など、あらゆる所から現代語の用例を採集する日々を送る。著書に『辞書を編む』『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか? ワードハンティングの現場から』『不採用語辞典』『辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術』『三省堂国語辞典のひみつ―辞書を編む現場から―』など。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら