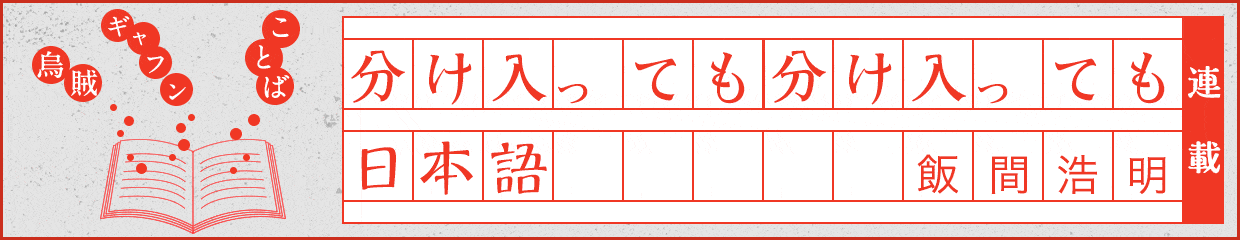日本語学者の金田一秀穂さんが2003年に出した新書に、「大人の流行語・若者の流行語」について書かれたくだりがあります。
〈〔最近は〕「御社」というのもよく聞く。「御学部」と言われて、「音楽部」のことかと勘違いしたことがある。かつては「貴社」「貴学部」と言っていたものだ。これは大人系流行語である〉(『新しい日本語の予習法』)
若い人は意外に思うのではないでしょうか。就職活動中の学生は、面接で「御社」「御社」と連発します。その「御社」は、「大人の流行語」だというのです。
「御社」は、一種の業界用語とも見られています。糸井重里監修『オトナ語の謎。』は、会社ムラの用語を集めた面白い本ですが、そこには「御社」「弊社」も出ています。
〈御社 あなたさまの会社。そちらさまの会社。/弊社 わたくしどもの会社。手前どもの会社〉
私自身も、「御社」は新しいことばという感じを持っています。あるとき、作家の丸山正樹さん(1961年生まれ)がツイッターで〈社会人になって初めて「御社」なる言葉を知った〉と書いていたので伺ったら、ご本人が学生の時代は〈正確なことは思い出せませんが、「貴社」と言っていたような……〉とのことでした。私(67年生まれ)も、だいたいそんなところだったと記憶します。
ところが、歴史を調べてみると、「御社」はもっと前からあります。日本史で習う細井和喜蔵『女工哀史』をめくってみましょう。近代女子労働者の過酷な生活を記した書物です。著者の娘が工場に採用された時の「誓約書」が載っています。
〈私儀今般御社職工トシテ御採用相成候ニ就テハ……〔=私は、このたび御社の職工として採用された以上は……〕〉
これは1923年の誓約書です。つまり、「御社」は遅くとも大正時代には存在したことになります。『日本国語大辞典』編集部が公開している用例の中にも、さらに数年遡る雑誌の文章の例があります。
戦後に活躍した作家・源氏鶏太のサラリーマン小説にも、次のように出てきます。
〈どうも、娘の教育が不行届でして、御社にもご迷惑をかけて申しわけありません〉(「鏡の中の顔」54年)
女性社員の父親のせりふです。明治生まれと思われる人の発言であり、少し古めかしい語感があったかもしれません。
このように「御社」は以前から存在し、手紙文にも使われました。とは言うものの、一般には長らく耳遠いことばだったと考えられるふしもあります。
雑誌『言語生活』83年12月号に、「御社」に関する読者の投書が載っています。
〈先日、業者と打ち合わせをしていたときのこと、しきりに「オンシャがそうおっしゃるのでしたら」と言われました。仕方なしに分かったような顔をしていましたが、あとで考えるとオンシャは“御社”のことだったんですね。当方、公共機関ゆえ全く見当がつきませんでした。“おたくの会社”とか“そちら様”とか言うかわりにオンシャと言うのは珍しくないことなのでしょうか〉
この投書からは、いくつか重要なことが分かります。まず、80年代初めに、会社勤務でないとはいえ、公共機関に勤務する普通の人の中に、「御社」と言われて分からない人がいたこと。また、担当編集者(この雑誌は言語研究者が編集しています)が、その報告を興味深いものと考え、雑誌に掲載したこと。それから、報告者にとっては「お宅の会社」「そちらさま」が普通の言い方だったということです。
後の号には、これに関連する別の投書も掲載されました。「自分は『オンコウさん』(御行さん。相手の銀行のこと)が分からなかった。現在、『御社』も『御行』も時々使う」という趣旨の内容でした。
これらをまとめると、80年代初め、「御社」は、言語関係の雑誌で話題にされる程度には珍しかったようです。書きことばとしては使われても、口頭で使われると意味が取りにくい、という感じだったのでしょう。80年代に学生時代を過ごした私も「御社」を知らなかったのは、前述したとおりです。
ところが、その後、「御社」は口頭語として急速に広まります。「大人の流行語」と認識されたのはこのためです。織田裕二主演で映画化もされた杉元伶一「就職戦線異状なし」(90年)では、就職面接で「御社」を決まり文句的に使う学生が描かれます。
〈御社は業界で確固たる地位を築き、かつまた新規事業にも積極的に進出し、二十一世紀の日本の産業構造を想定した場合、現在のような……〉
また、滝田洋二郎監督の映画「僕らはみんな生きている」(93年)にも「御社」は登場します。発展途上国で、ゲリラから逃れて彷徨する日本の商社マンたちがジープを買います。費用を割り勘にしろと言われ、ある社員は「領収書は?」と尋ねます。
〈ああー、領収書もない金が出るわけですか、御社は。あいにく、当社はですね、通らないんですよ〉
この作品では、異境の地で、生きるか死ぬかという時にも「御社」「当社」と会社語を使い、帰属意識を丸出しにする男たちが風刺的に描かれています。
このように、90年代初めには、「御社」は口頭語で普通に用いられるようになっていました。長らく書きことばだった「御社」が、ここに来て急に話しことばとして使われるようになったのはなぜでしょうか。それは次回「おたく」で改めて述べます。
-

-
飯間浩明
国語辞典編纂者。1967(昭和42)年、香川県生れ。早稲田大学第一文学部卒。同大学院博士課程単位取得。『三省堂国語辞典』編集委員。新聞・雑誌・書籍・インターネット・街の中など、あらゆる所から現代語の用例を採集する日々を送る。著書に『辞書を編む』『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか? ワードハンティングの現場から』『不採用語辞典』『辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術』『三省堂国語辞典のひみつ―辞書を編む現場から―』など。
この記事をシェアする
「分け入っても分け入っても日本語」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 飯間浩明
-
国語辞典編纂者。1967(昭和42)年、香川県生れ。早稲田大学第一文学部卒。同大学院博士課程単位取得。『三省堂国語辞典』編集委員。新聞・雑誌・書籍・インターネット・街の中など、あらゆる所から現代語の用例を採集する日々を送る。著書に『辞書を編む』『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか? ワードハンティングの現場から』『不採用語辞典』『辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術』『三省堂国語辞典のひみつ―辞書を編む現場から―』など。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら