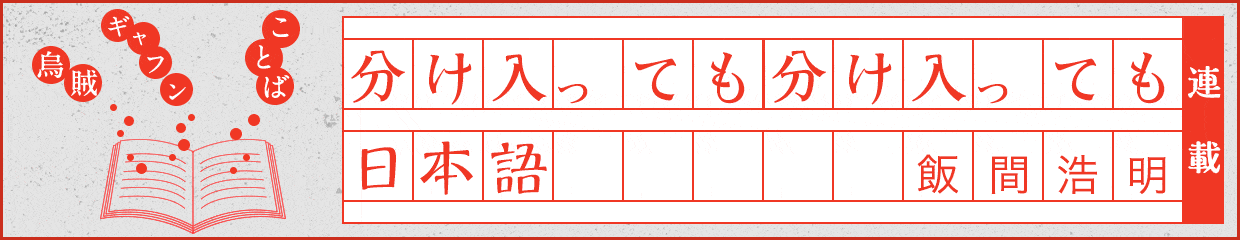私が「イマイチ」ということばに初めて接したのは、小学校高学年か中学生の頃、つまり1970年代の終わりから80年代の初めで、場所は近所の歯科医院の待合室でした。備えつけの雑誌にテレビ番組の紹介記事が出ていました。
「最近人気がイマイチのレツゴー三匹」
レツゴー三匹は往年の漫才トリオです。このトリオにも人気がイマイチの時期があったのでしょう。この文章を読んで、「いまひとつ」を「イマイチ」と言っているらしいことは分かりましたが、業界用語なのか何なのか、よく分かりませんでした。
「イマイチ」は、1970年代の終わりから使われていたのは間違いないようです。『日本俗語大辞典』には、『週刊朝日』1979年5月18日号から「イマイチ」についての解説が引用されています。私が歯科医院で「レツゴー三匹」の記事を見たのもほぼ同時期であり、つじつまが合います。強調形として「イマ三」「イマ四」「イマ八」「イマ十」「イマ百」などもあったそうですが、これらは淘汰(とうた)されました。
発生してしばらくの間は、「イマイチ」は「いまひとつ」の俗語、若者語という意識で使われていました。やがて、「いまひとつ」よりも普通に使われるようになり、俗語という意識も薄れてきました。
私が大学で教え始めたのは1990年代の終わりからですが、すでにその頃、学生のレポートに「イマイチ」が使われていました。わざとなのか、それとも俗語という意識なく使っているのかと、いぶかしく思ったものでした。
今では、学生が文章中で「イマイチ」を使うのはごく普通のことで、いちいち驚かなくなりました。たとえば、こんな具合です。
〈前後の文といまいち
〈この説明でもいまいちピンと来ないが、要は寒い場所に用いられる表現のようだ〉
丁寧な指導者であれば、ここで学生に注意を喚起します。日本文学者の石原千秋さんは、文章指導で次のように説明するそうです。
〈レポートは書き言葉で書くこと。たとえば、「いまいち」ではなく「いまひとつ」であり、「やっぱ」ではなく「やはり」であり、〔下略〕〉(『学生と読む『三四郎』』)
「イマイチ」の元は「いまひとつ」なので、「いまひとつ」のほうがきちんとした書きことばという感じを与えるのは当然です。
ところが、調べてみると、実は「いまひとつ」も戦後の例しか見つからないんですね。手元の資料の範囲では、言語学者の阪倉篤義が使ったのが古い例です。
〈〔初期のひらがなが記されている資料について〕これらはいずれも模写ないしは単なる伝えにすぎないものであって、〔初期のひらがなかどうか〕いまひとつ明確な徴証を欠くものであった〉(『言語生活』1955年7月号)
小説の例としては、柴田
〈ぼくは、君の言うことが判るような気もし、また、今一つ、判らない気もした。が、ぼくは何も言わず、黙っていた〉
当初「いまひとつ」は、このように「いまひとつ……ない」など否定の形で使うものでした。それが、言語学者の稲垣吉彦によると、関西から「ウーン、もうひとつやな」など、「いまひとつ」「もうひとつ」だけで独立して使う形が広まったということです(「話しことばと日本人」=金田一春彦他『変わる日本語』所収)。
かりに「いまひとつ」が1950年代ぐらいに広まったとして、「イマイチ」はその30年後ぐらいに広まったわけですから、2つの語の新旧の差はさして大きくありません。「いまひとつ」だけがよくて「イマイチ」はだめ、とは言えないわけです。「イマイチ」が「いまひとつ」と同様に普通の書きことばになるのも、時間の問題でしょう。
ただ、昔を舞台にしたドラマで使われると、時代考証的には気になります。
NHKの朝ドラ「あさが来た」での一場面。明治の世になり、父と弟が断髪にします。主人公・あさは父を見て〈ようお似合いだすなあ〉と褒め、弟を見て〈久太郎のほうは、イマイチやけど〉とけなします(2015年11月21日放送)。
ドラマのせりふは、舞台となった時代のことばそのままである必要はありません。でも、明治時代に「イマイチ」が出てくると、新語だという意識を持つ視聴者(私とか)に違和感を与えるのは確かです。
では、何と言い換えればいいか。これが難しいんですね。「いまひとつ」が戦後の例しか見つからないことは、すでに述べました。明治時代の人が「いまひとつや」と言うのも、「イマイチや」と同じくおかしいわけです。
二葉亭四迷「平凡」(1907年)には、主人公の書いた小説を、友人が〈
正岡子規の「歌よみに与ふる書」(1898年)には、短歌の添削例を批評して〈これも結末に今一歩と思ふ所なきにもあらず候〉とあります。添削の結果がイマイチよくない、ということです。この「いま一歩」ならば、音も「イマイチ」に近く、「髪型はいま一歩」と言っても悪くないように思われます。
ここまで苦労して言い換えるのは、いささかマニアックかもしれません。もうそろそろ、時代ドラマも「イマイチ」でいいじゃないか、と言われそうです。
-

-
飯間浩明
国語辞典編纂者。1967(昭和42)年、香川県生れ。早稲田大学第一文学部卒。同大学院博士課程単位取得。『三省堂国語辞典』編集委員。新聞・雑誌・書籍・インターネット・街の中など、あらゆる所から現代語の用例を採集する日々を送る。著書に『辞書を編む』『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか? ワードハンティングの現場から』『不採用語辞典』『辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術』『三省堂国語辞典のひみつ―辞書を編む現場から―』など。
この記事をシェアする
「分け入っても分け入っても日本語」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 飯間浩明
-
国語辞典編纂者。1967(昭和42)年、香川県生れ。早稲田大学第一文学部卒。同大学院博士課程単位取得。『三省堂国語辞典』編集委員。新聞・雑誌・書籍・インターネット・街の中など、あらゆる所から現代語の用例を採集する日々を送る。著書に『辞書を編む』『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか? ワードハンティングの現場から』『不採用語辞典』『辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術』『三省堂国語辞典のひみつ―辞書を編む現場から―』など。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら