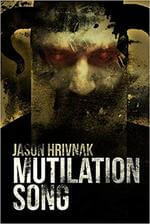今回は、以前に特異なデビュー作で感銘を受けた若手作家二人の、やはり特異な第二作を取り上げる。
まずは、カナダの作家ジェイソン・フリヴナク。第一作『苦境の家』(The Plight House, Pedlar Press, 2009) は、自殺した一人の女性と子供のころ共有した空想世界をたどり直す男が、四択式の問いを使って語りを進めていく不思議な小説だった。たとえば最初の問いは――
Childhood. Walking in the countryside, you encounter a dark rider upon the road. He challenges you to a battle of wits. Your intellect is keen, sharpened by sums and precocious reading, but the rider is confident of victory. He says that there is a subject on which young girls believe themselves to be great thinkers but on which none, in truth, are qualified to speak. It is on this subject that he aims to riddle you. To what does the rider refer?
A. Music.
B. Beauty.
C. Love.
D. Death.子供のころ。山道を歩いていると、黒い服を着て馬に乗った男に出会う。男は君に知恵較べを挑む。君の知力は鋭く、計算と早熟な読書によって鍛えられているが、馬に乗った男は己の勝利を確信している。男は言う。若い女の子たちが、このテーマについてなら自分はすぐれた思考者だと信じているものの、実は語る資格すらないテーマがある。このテーマについて、男は君に謎をかけようというのだ。そのテーマとは?
A 音楽
B 美
C 愛
D 死
――といった具合。形だけ聞くと遊びっぽく思えるが、実際に読み進めていくと、だんだんと語り手の精神の闇に降りたっていくように感じられて、独特の重さがあとに残る、ほかのどんな本とも似ていない一冊だった。
去年刊行された第二作『切り刻みの歌』(Mutilation Song――日本語の題はあくまで仮題。第一作もそうだが、内容を意図的にぶっきらぼうに伝えている優れたタイトルで、訳すのは困難である)は、一人のデーモン(demon)が主たる語り手である。たとえば以下は、30ページくらい進んだ時点で始まる章の冒頭。
In time he gained the capacity to hear voices other than mine, his brain attuning to those infernal wavelengths employed by my fellow demons. It first happened on a windy night as he crossed the vast industrial lands on the northeast side of the tracks. The street was home to a massive abattoir and greatly favoured by rats, their constant presence in the shadows forcing him out to the distal edge of the sidewalk. He’d reached a zone roughly halfway between thoroughfares when a sudden powercut blackened the street and almost immediately there poured from the darkness ahead of him a stream of soft malignant chatter. This choir of disembodied voices exhorted him to turn back, assuring him that by retreating immediately he would save himself untold suffering. “You were not meant to take this route,” said the voices. “You stand upon ground that is forbidden to mundane feet, but if you reverse your course this very instant your trespass here will be forgiven.” By this point in the training he was too familiar with the ways of demonkind to place any great stock in such promises of amnesty and he was too accustomed to the phenomenon of sonic assault to fold under such a soft initial salvo. So he pressed on. He shuffled down the street at a blindman’s pace, using the distant glitter of skyline as a beacon to guide him forward. Meanwhile the voices that assailed him grew louder and the threats they uttered grew steadily more frightening, steadily more personal and detailed.
やがて彼は私以外の声も聴く能力を獲得した。私のデーモン仲間が用いる地獄の波長に、脳が適応していったのだ。初めてそれが起きたのは、風の強い夜、彼が線路の北東側の、巨大な産業用地を横切っているときだった。その道路は、大規模な食肉処理の場となっているせいで鼠たちに大いに好まれ、影に鼠たちが常時いるため彼は歩道の外側の端を歩くことを余儀なくされた。大通りと大通りのおおよそ中間のゾーンまで来たところで、突然の停電により道路は真っ暗になり、ほぼ寸時のうちに、闇の中から、静かな、悪意あるお喋りが前方に流れ出てきた。肉体から離脱したこれら声の合唱隊は、引き返すよう彼に勧め、いますぐ戻れば計り知れぬ苦しみを免れられると請けあった。「お前はこのルートを通るはずではなかったのだ」と声たちは言った。「凡人の足には禁じられている地面にお前は立っているのだ。だがいますぐ進路を逆転させれば、ここへの侵入は許される」。訓練がここまで進んだいま、デーモン族のやり方に彼も馴染んでいるので、そんな恩赦の約束を信じたりはしないし、音の襲撃にも慣れているから、こんな甘っちょろい初期攻撃に屈したりもしない。かくして彼は先へ進んだ。盲人のペースで、足を引きずって道を行き、遠くの高層ビルのきらめきをビーコンと頼って歩いた。一方、襲ってくる声たちももっと大きくなり、口にされる脅しもますます恐ろしく、ますます個人的で詳細になっていった。
今日び、デーモンの世界もなかなかシステマチックである。凡人たち(mundanes)の世界を離れてデーモンになるべく訓練を受けている者たち(trainees)は、規定の講習(program)を受けて一段一段ステップアップしていく。そのなかでデーモンたちは、トマスという名の(どうやらトレイニーとしては劣等生らしい)若者に向かって語り、加えて、彼のかつての友人や、母親、さらにはたったひとりつかの間の恋人だった女性も現われ、語る。その内容はおおむね、彼が今後受けるであろう苛酷な仕打ちか、彼の現状の無残さであり(特に彼の母親による呪詛的語りはすさまじい)、たまに彼に対して好意的な言葉が発される場合、それを発する者はまったく無力である。
そうした言葉の恐ろしさ、状況の悲惨さが、ホラー小説として評価されるひとつのポイントになっているのだろうが(この本を出した、トロントにあるホラー系の小出版社CZPの経営者は、“If we haven’t made you unwell, we haven’t done our job.”〔あなたの気分が悪くならなければ私たちは仕事をしていない〕とインタビューで言っている)、僕自身はそのへんのことにはあまり興味がない。この本で僕が惹かれるのはむしろ、 そうした陰惨な内容が、ほとんど端正と言ってもいい職人的な文章で語られ綴られ、その落差が不思議な効果を生んでいるところである。Trainee, programといった事務的な言葉が多用されるのも、決してパロディ的面白さを狙っているのではない。この本に棲むのは、職人的文章とも呼応している、不思議と律儀な、だからこそ独自の気味悪さを持つデーモンたちなのである。
そうやってデーモンたちが、幻聴のようにトマスに語りかけるなか――というか、すべてはトマスが聴いている幻聴だというふうにも考えられるだろう――トマスの内面はいっさい語られないし、彼が誰かと話したり一緒に何かをしたりする場面もまったく出てこない。これによって、トマスという人物がいわば不在の中心のように浮かび上がってきて、その孤立、孤独がじわじわ伝わってくる。ここが僕にとっては最大のポイントである。その侘しさ、よるべなさは、ほかの本ではなかなか得られないたぐいのものだと思う。
一方、アダム・アーリック・サックスの2016年刊のデビュー作『遺伝性障害』(Inherited Disorders, Regan Arts, 2016)は、ユダヤ系文学の最大のテーマである「父と子」を徹底的に歪め、茶化し、矮小化した小品を117本収めた何とも風変わりな一冊だった。たとえば、父を徹底的に糾弾した本を書いた息子が、最後の最後でひるみ、父への糾弾は母に対しても有効であるはずだと考え、ワードの検索・置換機能を使って「父」をすべて「母」に変換して送ったら「最初のページで、『母のペニス』って3回言ってますけど、これでいいんですか?」とエージェントから問い合わせが来る、といった具合(117本のうち5本は、『MONKEY』14号で松田青子さんに訳してもらいました――松田さん自身による見事な「返歌」1本付き!)。ここまでふざけているからには、作者にとってこれは実はものすごく重要なテーマであるにちがいない、とも思えてくる一方、いやこの人はただただ笑っているだけではないか、とも思えてくる、何だかよくわからない、まあとにかくムチャクチャ面白いにはちがいない本だった。
今年の5月に、大手のファラー・ストラウス・アンド・ジルー社から刊行される第二作であり初長篇の『感覚器官』(The Organs of Sense)は、若き日のライプニッツが、1666年6月30日正午に皆既日食が起きると予言した、目のところに両方とも穴が空いている謎の天文学者に出会い、数時間後に迫った日食を山上の天文台において二人で待ちながら、いかにして目の部分に空洞を持つに至ったかを天文学者が語るのを聴く。このときの経験を綴った文章をライプニッツは『フィロソフィカル・トランザクションズ』(現実に存在する雑誌で、1665年創刊、現在も出ている最長寿の科学雑誌)に投稿したが、なぜかこれは掲載されずに終わった、と語り手は述べている。
で、この天文学者の話が、なかなか先へ進まないのである。
He likewise, unlike Kepler, had always denied himself all goulash and all roasted meats served after the hour of four o’clock in the afternoon, and as a result of this lifelong self-denial was always “preternaturally crisp in the head” by the time the stars began to shine. The astronomer’s firm conviction was that anyone who eats foods like goulash or bread dumplings after about four in the afternoon, or five at the latest, cannot (unless we’re dealing with a ludicrously light dumpling, a dumpling you hardly feel in your belly, the kind of divinely light bread dumpling we could theorize about forever but that in practice we never actually encounter anywhere on Earth, much less in Prague) call himself an “astronomer,” perhaps he can call himself a “mathematician” or a “philosopher,” but he cannot in good faith call himself an “astronomer,” and that includes the gastronome Tycho Brahe. “You simply cannot eat such a meal at such an hour and afterward expect to see,” the astronomer told Leibniz. “I mean truly see.”
When he said the words “truly see” he pointed at his empty eye sockets.
彼はまた、ケプラーとは違い、午後4時を過ぎて出されたシチューやロースト肉はすべて己に禁じてきたのであり、生涯にわたるこの自制のおかげで、星が輝き出す時間にはつねに「頭が超自然的に冴えている」。この天文学者が固く確信するところ、午後4時ごろよりあとに、あるいは最悪5時よりあとに、シチューやブレッドダンプリングのような食べ物を食べておいて(もちろん馬鹿みたいに軽い、ほとんど腹の中で感じないようなダンプリングであれば話は別だが、神々しいくらい軽いブレッドダンプリングについて我々は永遠に理屈を並べているものの現実にはそんなもの地上のどこでもお目にかからないし、ましてやプラハになんかあるわけがない)それで「天文学者」を名のることなどできはしない。まあ「数学者」か「哲学者」なら名のれるかもしれないが、誠意をもって「天文学者」を名のるのは不可能であり、むろんそれはあの食い道楽ティコ・ブラーエについても言える。「そんな時間にそんな食事をして、そのあと見えるわけがないのだよ」と天文学者はライプニッツに語った。「つまり、本当に見えるわけは」
「本当に見える」という言葉を言うとき、天文学者は自分の空っぽの眼窩を指さした。
なぜ天文学者の眼窩は空っぽなのか、どうやって空っぽになったのか、空っぽなのに本当に見えるのか(天文学者は話しながら、定期的に望遠鏡を覗いては、何やら数字を紙に書いているのである)、という興味を読者は当初から抱くわけで、天文学者の長い長い話を読みながら、さっさと答えを教えろ、と思ってしまうか、それとも、人間の頭そっくりの機械を作ろうとした天文学者の父親をめぐる話や、天文学者のパトロンとなった王とその息子・娘たちのややこしい関係をめぐる話に惹きつけられて当初の問いを忘れるか、でいわばこの本の勝ち負けが決まるわけだが、日本の一読者は、あっさり本に負けました。
というわけで、特異な第一作を書いた作家の特異な第二作、という妙なくくりで二冊紹介したが、実はこの二冊、もうひとつ共通点がある。すなわち、どちらもブライアン・エヴンソンが推薦文を書いているのである。
Reading like the occult love child of Georges Bataille and David Lynch, Hrivnak’s Mutilation Song is an unnerving and surreal meditation on the demons that haunt us and on the nature(s) of evil. Compelling and unsettling, and definitely worth the read.
ジョルジュ・バタイユとデヴィッド・リンチとのオカルト的私生児のように読める、我々人間に取り憑く悪魔たちをめぐる、そして悪の(さまざまな)本質をめぐる、読む者を落ち着かなくさせるシュールな考察。不安に陥りながらも、読み続けずにいられない。間違いなく読むに値する一冊である。At once erudite and comic, The Organs of Sense is an absurd and beautifully finessed pseudo-historical novel which deftly circles around a dark core.
博識にしてコミカル、途方もなく馬鹿馬鹿しい、見事に組み立てられた、実は暗い核の周りを巧みに回っている擬似歴史小説。
小説も次々書き、大学もフルタイムで教え、子育てもちゃんとやりつつ、エヴンソンは若手の作品に近年もっとも多くの推薦文を書いている作家ではあるまいか。驚き呆れるしかない。
最新情報
スチュアート・ダイベック『路地裏の子供たち』拙訳が白水社から刊行されました。5月2日(木)3時~、下北沢B&Bでデイヴィッド・ピース、黒原敏行両氏と、ピースさん著、黒原さん訳の『Xと云う患者 龍之介幻想』(文藝春秋)刊行記念イベント「芥川龍之介REMIX/REPRISE~文学と翻訳のインターアクション」。5月9日(木)、村上春樹さんとの共著『本当の翻訳の話をしよう』がスイッチ・パブリッシングから刊行。5月13日(月)7時~、銀座蔦屋書店で同書の刊行記念トークイベント。5月18日(土)2時~、梅田蔦屋書店4階ラウンジで、互盛央さんとサントリー文化財団設立40周年記念イベント「ことばの力」。5月19日(日)1時半~、名古屋猫町倶楽部で読書会「柴田元幸が月曜会にやってくる第9弾!!」に参加。新潮社の『波』5月号から、バリー・ユアグロー『オヤジギャグの華』拙訳の連載をはじめました。その1は「サクラ族」。