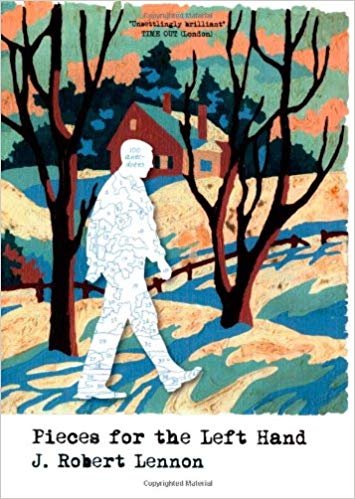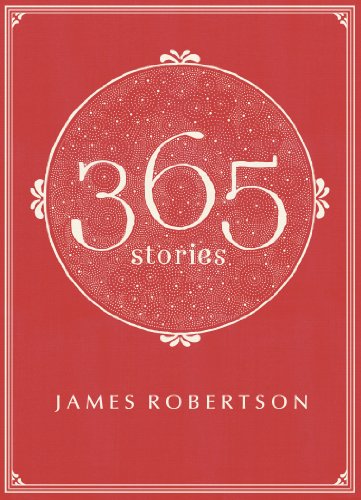(12)365×365
ショートショートの新しい可能性を拓く一冊
James Robertson, 365: Stories (Penguin, 2014)
著者: 柴田元幸
英語で書かれたショートショートで僕が一番好きな作品は、日本ではかつて「回転ドア」のタイトルで訳された作品である。回転ドアにどうしても入れない男が、ある日意を決してデパートの回転ドアに入ると、今度は出られなくなるのだが、気づけばそこには先客がいて、この初老の紳士、先週の木曜から入っているという。やがて男は、思いきって出ていこうと思います、靴下を買わないといけないので、と紳士に告げると、そうだな、私はもう年だが君はまだ若いのだからな、では気をつけていきたまえよ、と男を送り出す――
“Good-bye, old man,” said Mr. Weech, shaking my hand warmly, his eyes welling with tears. “It was darned good meeting up with you; and if you ever come through this way again you must be sure to stop in for lunch.”
“I will, oh, I will,” I promised. “I’ll make a definite point of it.”
“Don’t forget,” said Mr. Weech. “Second compartment to the left; you’ll find me right here. And if by any chance you should ever happen to run into Mrs. Weech,” he added, “will you please tell her I’m quite well, and send my love?”
“You bet,” I said; and then, watching my opportunity, I took another deep breath, bade Mr. Weech a last farewell, and leapt suddenly through the opening. And when I picked myself up, I discovered I was out on the street where I started from.
Anyway, you really don’t need socks in hot weather.(Corey Ford, “Here We Go Round Revolving Doors,” from The Gazelle’s Ears 〔1926〕)
「それじゃ、さよなら」私と暖かく握手したウィーチ氏の目に涙が湧き上がってきた。「君と会えてよかったよ。もしこのへんにまた来ることがあったら、ぜひ昼食に寄ってくれたまえよ」
「ええ、そうします」私は約束した。「かならずそうしますとも」
「忘れるなよ、左から二番目のコンパートメントだ、私はここにいる」とウィーチ氏は言った。「そしてもし」と彼は言い足した。「私の妻に出くわすことがあったら、伝えてくれるかね、私が元気でやっていると、そしていまでも愛していると」
「承知しました」と私は言い、それから、チャンスに目を光らせ、ふたたび深く息を吸って、ウィーチ氏にいま一度別れを告げ、一気に開口部から飛び出した。起き上がるとそこは、そもそもの出発点であった通りだった。
どのみちこの暑さじゃ、靴下なんか要らない。(コーリイ・フォード「ぐるぐる回る 回転ドアは」)
この作品が何年に書かれたかは不詳だが、短篇集に収められたのは1926年。ウィーチ氏が自分の妻のことを“Mrs. Weech”と呼ぶあたりにも時代が感じられて楽しい。
こんなふうに、奇抜な発想、気の利いたエンディング、といったあたりがショートショートの肝だというのが日本でもアメリカでも長年相場だったが、1986年にSudden Fictionと題した、70本の超短篇を集めたアンソロジーがアメリカで出たあたりから、様子が変わってきたように思う。ひとことでいえば、ショートショートが「文学」に昇格した感じがするのである。Sudden Fictionにはグレイス・ペイリー、ジョン・チーヴァー、レイモンド・カーヴァーといった、日本では村上春樹訳で知られる作家も入っていて(Sudden Fiction全体も、日本では村上・小川高義訳で出ている――『Sudden Fiction超短編小説70』文春文庫)、奇抜なアイデア+ウィッティな結末で勝負するというよりは、人生の一断片を切りとった、より正統的な短篇に近い味わいを持っている作品が中心である。
Sudden Fictionは大きな成功を収め、その後、続篇的なアンソロジーが英語圏では数多く出されている。まあこの成功の原因は、あまり文学的なことではないかもしれなくて、大学の授業などで短いテクストが求められることが多くなったから(それと、創作科の教科書にも好適だから)ではないかと思うのだが、それはともかく、ショートショートはいまやフラッシュ・フィクションと呼ばれ、立派な文学的サブジャンルとしての地位を確立したように思える。
もちろん、こうした超短篇のなかには素晴らしい作品もある。『Sudden Fiction』に入っているペイリー「マザー」、チーヴァー「再会」、カーヴァー「生活の中の力学」などはどれもさすがである(特に「再会」は見事)。が、個人的好みから言うと、短いだけあって「人生の一断片」がかなり薄切りになっていることが多い気もし、生ハムの薄切りなどは歓迎なのだが短篇はやはりもうちょっと厚みがあってもいいんじゃないかと思えて、そうすると昔の「回転ドア」みたいな馬鹿っぽいショートショートがなつかしく感じられたりするのである。
そういう薄切り感を打破して、新しいことをやっているなあと感じさせてくれる仕事が3つある。まず、アメリカの作家J・ロバート・レノンのPieces for the Left Hand(左手のための小品集)と題した、超短篇を100本収めた作品集(2005年刊)。フランス人観光客にたどたどしい英語で「たそがれ(twilight)はどこですか」と訊かれ、いやーこの町の夕焼けは本当に綺麗なんですよ、と熱く答えるものの、相手が探していたのは単にトイレ(toilet)だと判明する……といったように気の利いたアイデアが盛り込まれている。しかもアイデアだけには終わらず、その観光客たちがたそがれに見入っている姿に語り手が見入る、という叙情的な情景で作品は締めくくられ、単なる「オチ」にとどまらない文学性も感じさせる。
次に、これもアメリカの作家マシュー・シャープが、2013年5月から、オンライン上に毎週1本ずつ、52本の作品を一年かけて発表したvery short stories r usという企画(ToysЯUs=トイザらス のもじりですね)。たとえば“Olivia had just gotten a coffee and was trudging to work”(オリヴィアはコーヒーを飲み終えて、とぼとぼ職場に向かっていた)といったわりと普通の始まり方もあれば、“After Charlie died he was more at ease”(死んでからというもの、チャーリーは気が楽になった)といった奇っ怪な始まり方もあるが、とにかくどれもどこへ連れていかれるのかいっこうに予測がつかず、おそらくは作者も次がどうなるかわからないまま書いていると思える即興感に満ちていて、zany(イカレた、たわけた)という形容詞がぴったりの面白さがある。
さて、上の二人についてはよそでも少し紹介したので、今回の主役は、スコットランドの作家ジェームズ・ロバートソンが書いた超短篇365本を集めた、ズバリ365というタイトルの本である。
マシュー・シャープとほぼ同時期ということになるが、ロバートソンは2013年の1月1日から毎日一本ずつ超短篇を書きはじめ、1年かけて365本の短篇を書いた。そしてこれを、2014年1月1日からオンラインで公開を開始し、ほぼ大半を公開した2014年11月、365本すべてをおさめた単行本を刊行した。
内容・スタイルは多種多様だが、365本の作品にはひとつ共通点がある。すなわち、どの作品も、365語から成っているのである。
“The Beginning”と題された1月1日の作品は、こう始まる――
Before the beginning there was nothing. And nothing came from nothing, since nothing can. But something, somehow, did, and that was the change. Was it a moment or an aeon – and who among us is bold, clever or foolish enough to define the difference?
始まりの前には何もなかった。そして何もないところからは何も生まれようはないから、何も生まれてはこなかった。ところが何かが、なぜか生まれて、それで変化が起きた。それが一瞬のことだったか、それとも永劫の長い時だったか――そもそも私たちの中で、その違いを定義できるほどの大胆さ、賢さ、もしくは愚かさを持つ者がいるだろうか?
――という具合に、まさに「始まり」をめぐる考察。そして355語めから始まる最後のセンテンスは: ‘The beginning was when the storyteller first said, “In the beginning . . .” ’(始まりは、物語を語る者が初めて、『まず初めに……』と言ったときだった)
――と、storytellerが主役となって1月1日が終わったのを受けて、1月2日は‘Story’と題された作品。一人の少年が森を通って牛乳を買いに行くが、帰り道に妖精たちにつかまってしまい、7年間こき使われたのちに解放される。少年は家に駆け戻って両親に一部始終を伝えるが、父も母も、面白い話だね、でもお前は20分出かけていただけだよ、と答える。ところが、買ってきた牛乳を開けてみると、中身はすっかり凝固している: ‘. . . it is shrunken and solid, like cheese, and – according to the stamp on the carton – seven years out of date’(牛乳はチーズのように縮んで固くなっていて、そして――パックにスタンプしてある日付によれば――7年経っている)。
このseven years out of dateというのが実に巧みである。かりにx年に少年が出かけたとすれば、本当に20分しか経っていないのなら帰ってきたのもx年のはず。では、seven years out of dateとはいつのことか? 解決不可能な矛盾がここには埋め込まれているのである(と、偉そうに言うが実は僕も翻訳教室で受講者の方に指摘されるまで気づかなかった……)。
このあとの363本、すべてがこういうふうにしりとり式につながるわけではないが、全体としてある種の流れは確実に感じさせるし、ところどころではミニシリーズが出来ていて、古いバラッドの語り直しが数日続いたり、10月1日が‘Varieties of Madness in France, 1665’(フランスにおける狂気の多種多様さ、1665年)と題されているのを受けて10月2日は‘Ways of Dying Gently in Scotland, 1790s’(スコットランドにおける静かな死に方、1790年代)となっていたり、11月2日はOutside the Bookshopで3日はInside the Bookshopだったりする(2日は本屋のことを“an awful dear library”〔ものすごく値の張る図書館〕だと思っている女性たちの話で、3日はノンフィクションならぬnun fiction〔尼僧小説〕を探しに来た男の話)。
ジャックという少年と母親の対話、というパターンは一種定番になっていて、一年を通して頻出する。対話はいずれもスコットランド方言で語られる――
‘Jack,’ his mother says one day, “that auld dug has had it. Aw she does is eat and sleep. Tak her doon tae the sea and droon her.’
‘Och, Mither, I canna,’ Jack cries, but she insists.
Down to the sea he trudges, with the dog limping at his heel. When they reach the water’s edge, Jack sits for an hour and the dog sits with him. Then they go back to his house.
‘I couldna dae it, Mither,’ Jack says. ‘She wasna ready for droonin.’
‘I’ll mak it easier for ye,’ she says. ‘Tak this auld sack wi ye and when ye get tae the sea pit the dug in it and droon her.’(12 October, ‘Jack and the Dog’)
「ジャックや」と母親がある日言う。「その老いぼれ犬、もうおしまいだよ。一日じゅう寝て食べるだけだ。海に連れてって溺れさせてきな」
「母ちゃん、俺そんなことできねえよ」とジャックは声を上げるが、母は耳を貸さない。
足を引きずる犬を従えて、ジャックはとぼとぼ海に降りていく。水際まで来ると、ジャックはそこに一時間座っていて、犬も一緒に座っている。それから彼らは家に帰る。
「母ちゃん、俺できなかったよ」とジャックは言う。「こいつ、まだ溺れる気なかったよ」
「じゃあやりやすくしてやろう」と母は言う。「この古い袋持っていきな、海に行ったらこれに犬を入れて溺れさせるんだ」(10月12日「ジャックと犬」)
〔auld: old / dug: dog / Aw: All / Tak: Take / doon: down / tae: to / droon: drown / Och: Oh / Mither: Mother / canna: cannot / couldna: couldn’t / dae: do / wasna: wasn’t / droonin: drowning / mak: make / ye: you / wi: with / pit: put〕
ロバートソンは標準的な英語で小説を数多く発表しているが(2006年刊の長篇は邦訳も出ている――『ギデオン・マック牧師の数奇な生涯』田内志文訳、東京創元社)、こういうスコットランド英語を使って児童書を何冊も書いているし、『プー横丁の家』のスコットランド英語訳(The Hoose at Pooh’s Neuk)も出している――‘I’m Pooh,’ said Pooh. ‘I’m Teeger,’ said Teeger. ‘Oh!’ said Pooh, for he hadna ever seen a craitur like this afore(「ぼく、プー」とプーはいいました。「ぼく、ティーガー」とティーガーはいいました。「わあ!」とプーはいいました。こんないきものはいままでみたことがなかったからです).
スコットランドの元の言語であるゲール語で詩を書く詩人の話もある。ゲール語を解しない、英語しか話さない聴衆の前で、詩人は自作をゲール語と英語の両方で読まねばならないことに憤る。自分で訳したものの、英訳は限りなく貧しい……。そうおっしゃいますが英訳でも素晴らしいと思いますよ、と語り手が言うと、結末は――
He looked very mournful. ‘They are inadequate,’ he said as he signed his name. I felt that he knew what he was talking about, and that I too was inadequate. Then he smiled at me, as if to apologise for making me feel that way.
That smile has stayed with me.(12 November, ‘The Inadequacy of Translation’)
彼はひどく暗い顔になった。「翻訳では不十分です」と自分の名前をサインしながら彼は言った。まあじっくり考えた上で言っているのだろうなと私は感じ、私自身も何だか不十分であるような気分になった。それから彼は、そんな気持ちにさせたことを詫びるかのように、私に向かって笑顔を見せた。
その笑顔が、ずっと私の胸に残っている。(11月12日「翻訳の不十分さ」)
日々翻訳の「不十分さ」を痛感せざるをえない翻訳者としては、この「笑顔」とともに終わる一行にはものすごく勇気づけられる。
ところで、すべてを365語に統一することにどういう意味があるのか? と思われる方もいらっしゃるかもしれない。僕もはじめはそう思ったのだが、読んでいるうちに、これは実に必要だと思った。音楽がたとえば16小節でひとつのユニットを成すように(あるいは俳句や和歌の文字数を考えてもいい)、続けて読んでいると、同じ長さであることが快いリズムを生み出すのである。
という具合に、なるほど超短篇でこういうこともできるのか、と唸らされることしきりの一冊なのだが、最後に異色の傑作を一本。‘My Real Wife’(現実の妻)という作品で、作家の妻が、あなたはどうしていつも私をそうやって魅力なく書くの、と文句を言うと、これは君じゃないよ、語り手だって僕じゃないんだから、と弁明すると今度は、じゃあどうして私のことを書かないのよ、愛しているなら私のことを素敵に書いてくれるはずよ、と新たな文句が飛んでくる。で――
Just then my real wife came into the room, bringing me a cup of coffee. She leaned over my shoulder and read what was on the screen. This is something I wish she wouldn’t do.
‘Is she bothering you again?’ she asked. ‘Tell the sad cow to leave you alone, or she’ll have me to answer to.’
‘It’s okay,’ I said. ‘I’m dealing with it.’
‘Well, deal with it,’ my real wife said.(28 June, ‘My Real Wife’)
ちょうどそこで私の現実の妻がコーヒーを持って部屋に入ってきた。彼女は私の肩越しに画面を覗き、書いてあることを読んだ。正直言って、これはやめてほしい。
「あの女、またぐじょぐじょ言ってるの?」と現実の妻は訊いた。「うるさい引っ込んでろ、って言ってやんなさいよ、じゃなきゃあたしが黙っちゃいないって」
「大丈夫だよ」と私は言った。「僕が対処してるから」
「ええ、対処しなさいよ」と現実の妻は言った。(6月28日「現実の妻」)
*コーリイ・フォード「回転ドア」は井上一夫訳、『アメリカほら話』(ちくま文庫)所収。
*Pieces for the Left Handに収められた100本のうち6本を拙訳し、ピアニストのトウヤマタケオさんと組んで音楽+朗読のCDを作った。『たそがれ』(ignition gallery)
*100本のうち「ありそうな」「道順」「軍服」はMONKEY2号に、「模倣者たち」はMONKEY9号に拙訳を掲載。
*100本全部の翻訳は某所で進行中と聞く。
*マシュー・シャープの52本は、「マシュー・シャープの週刊小説」として、雑誌MONKEYの定期購読者対象に毎週一本拙訳を公開中。
http://www.switch-pub.co.jp/membership-join/
*52本のうち3本(無題)はMONKEY2号に、1本(「あの、すいません」)はMONKEY9号に、1本(「雪」)はMONKEY12号に拙訳を掲載。
*マシュー・シャープの原文very short stories r usはここで読める↓
http://sharpestories.blogspot.com/
*ロバートソン「ビッグ・マック」「牛乳」「カフェの死神」はMONKEY13号に拙訳を掲載。
*「翻訳の不十分さ」は、『世界』2018年3月号に掲載したシンポジウム報告「翻訳という創造空間」に拙訳を組み込んだ。
最新情報
7月6日(土)午後11時~12時、J-WAVEのRADIO SWITCHでMONKEY18号について喋ります(ほとんど朗読ですが) 。7月25日(木)山口市小郡地域交流センター、26日(金)福岡市ブックスキューブリック箱崎店、27日(土)熊本市橙書店で朗読会(詳細未定)。7月25日、1989年に国文社から刊行された拙訳モリス・バーマン『デカルトからベイトソンへ』が文藝春秋から30年ぶり復刊。「波」7月号にバリー・ユアグロ―連載「オヤジギャグの華」第3回「タワー・クレイジー」掲載。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら