インタビュー 内田樹
一行たりとて意味がわからないレヴィナスとの出会いから始まった
ユダヤへの果てしない旅
割り切れないもの
卒業論文は、メルロ=ポンティの身体論でした。身体というリアルな現実を哲学の言葉ですくい取ろうとするメルロ=ポンティの理説は、力業でもあり、あちこちに何とも言えない手触りの、すっきりしない重たいものが残るんです。でもそこに惹かれたんですね。うまくいかないんだけど、何とかできる限りのことをしようとするメルロ=ポンティのあり方が好きだった。頭の切れるサルトルだと全部すっきり説明しちゃうんですよ。余りがない。でも説明過剰なんじゃないか、もっと対象への節度を持たなければいけないんじゃないか、という気がしていた。
僕の知的な関心の方向性はこのあたりでだいたい決まったのかもしれません。世の中はある統一的な理説ですべて説明できるという行き方と、人間の欲望の構造とか、身体感覚とかいうものは、逆立ちしても説明しきれない、それでも、その説明できないものに限りなく近づいていこうとする哲学の行き方。抽象的な議論にとどまっていれば、整合性のある理説を成り立たせることはできるけれど、生身の現実に肉薄すればするほど説明できないことが増えてくる。リアルになればなるほどわかりにくくなる。当然、それを記述する言語もわかりにくくなってゆく。僕はこっちの「生々しくリアルだけれど意味がわからない」経験に惹きつけられたわけです。
修士論文のテーマはモーリス・ブランショでした。鳥肌が立つほどかっこいいけれど、意味がわからない文章を書くという点で、この人は現代フランスの文人中突出しています。ブランショはフランスの古い家柄の人で、頭が恐ろしく切れて、感受性が尖っていて、ヨーロッパ的知性を蒸留して、その最も純良な部分を体現したフランス文化の精華みたいな人なんですね。
ところが、文学や政治を論じるときには精緻で切れ味のいい文章を書くブランショなのに、ことがユダヤにかかわると、論理が微妙に破綻して、文体が均衡を失って崩れてゆく。いったい何が起きているのか。僕は不思議に思ったわけです。これほど自分の文体を自在に操作できる人が、その技巧を以ってしてもコントロールできない主題というものが存在するのだろうか、と。
修士論文を書いているとき、ブランショの研究書の欄外に「哲学者エマニュエル・レヴィナスの影響を受けてこのような概念を使ったと思われる」という一行がありました。レヴィナスって誰だか知らないけどブランショがあまりにわからないので、「藁をもつかむ」気持ちでフランスにレヴィナスの本をいくつか注文しました。最初に読んだのが『困難な自由』という本。これが読み始めたらとんでもない本で、上には上があるもんだということがわかった。レヴィナスのわからなさはブランショのわからなさどころではないんです。もうまったく一行とて理解できない。ただ、この人が身体の奥底からわきあがるような確信をこめて、きわめて深遠な人間的経験を語っているということははっきり伝わってくる。何を言いたいのかはわからないけれど、言いたいことがあるのはわかる。言葉が持ち重りのするかたまりのように身体にドンと当たってくるんです。
ブランショとレヴィナスが出会ったのは、二人が二十歳くらいの大学生の頃です。リトアニアからやって来たばかりの、フランス語もドイツ語もろくに話せない、小熊のような顔をしたユダヤの青年レヴィナスにブランショは出会う。二人はほどなく親友になります。何が二人を結びつけたのか、それについては二人ともほとんど何も説明していません。でも、ブランショはおそらく自分がそれまで全世界だと思っていた世界が「ヨーロッパ・ローカル」でしかなかったということを思い知ったのではないかと思います。レヴィナスのうちにブランショは恐ろしいほどの深みをもつ非ヨーロッパ的な知の伝統を望見した。そしてレヴィナスを相手にして、いわばヨーロッパ的知性を代表するという立場から、生涯にわたる知的な格闘を演じてゆくことになる。
レヴィナスはブランショについて、「何でも知っていて、フランス文学のことを教えてくれるいい人でした」と書いている(笑)。「歩くフランス文化」みたいなブランショからはいくらでも吸収するものがある。一方、ブランショはレヴィナスと親交を深めるにしたがって、混乱を深めてゆく。自分たちフランス人が世界の中心で、自分を涵養してきた文化が最も優れたものだというフランス中華思想が揺らいでゆく。レヴィナスの背後にある、何か深いものに感応してしまうわけです。
ブランショは二〇〇三年に九十五歳で亡くなるまで、ユダヤ的なるものと、ヨーロッパの知性を代表して四つに組んで、格闘し続けた。結局ユダヤ的なものをヨーロッパの枠組みに取り込むことはできなかった。ヨーロッパの枠組みが破綻するところを実演してみせただけなんです。でも、そこまで徹底的にユダヤにつきあった人って今のところブランショ以外にはいないんですよ。同時代のサルトルの場合、ユダヤなるものは歴史的状況の産物ですから、実存主義の歴史理論で簡単に説明がついてしまう。ユダヤとはこれこれである、証明終わり、なんです。だから、ユダヤに特段の興味がなかった。ずいぶん後になるまでレヴィナスの名前さえ知らなかったんですから。
『困難な自由』と合気道
フランス最良の知性をもってしても遂に理解しつくせないレヴィナスのユダヤ思想が、一九七〇年代の日本に生きている僕にわかるはずがない。でも、自分に理解できない精神の運動が肉薄してきて、それをいま経験しつつあるということは別にそれほど例外的な出来事ではない。レヴィナスのわからなさというのは、赤ちゃんがお母さんから話しかけられているときに母語がわからないのと似ている。言葉の意味はまだわからない。でも身体に何かがしみこんでゆく。僕も母親の語りかけを聴く「まだ日本語を知らない赤ちゃん」の気分でレヴィナスの本を読み続けたんです。そのうちに、これも赤ちゃんの場合と同じですけれど、この著者は僕自身の成熟を要求しているということがわかってきた。今の僕のままではこの本は絶対にわからないよ、と。今と違う人間にならないといつまでたってもわからない。違う人間になるためには哲学用語辞典的な知識をいくら増やしたって、何の足しにもならない。
レヴィナスのわからなさというのは根源的なものなんです。たとえば「私」とか「他者」とか「関係」とか「神」といった言葉は、僕たちが今生きている社会のなかでは、こういう意味で使うという了解がある。ところがレヴィナスの文脈では、どうやら「他者」という概念そのものを書き換える必要がある。僕たちが知っている「他者」という概念をそれとはまったく違う意味で解釈し直さないと一行も読み進められないのではないか。そういう手ごわさに出会ったんです。
じゃあどうすればいいのか。今まで「主体」とか「他者」とか「顔」という語をレヴィナスのような使い方で使った人がいないのだから、哲学用語的知識なんか何の役にも立たない。とにかく浴びるようにレヴィナスを読むしかない。わからなくても読む。「四書五経」の素読と同じです。
ところが素読を続けているうちに、ある日ふとしたはずみで、トランプの神経衰弱のカードがマッチするように、あっちのカードとこっちのカードが「合う」ということが起きる。一組カードが合うと、横によけておく。そういうことをしていると、一行もわからずテコでも動かなかった『困難な自由』が、少し動くような感じになるんです。三十歳前後の頃はそんなふうに朝の九時から五時まで『困難な自由』の翻訳をして、六時から八時まで合気道の稽古をするというような毎日でした。知性のレベルでは何が書いてあるのか意味はまだわからない。でも、身体の方は少しずつレヴィナスの言葉になじんでゆく。
僕は二十五歳から合気道を始めたんですが、身体感受性というのは武道の修練の中で最優先に開発されるべき資質なんです。相手が何かの行動を起こしてから、それに応じていたのではもう遅い。武道は「先の先」を取るものですから、相手の潜在意識のレベルで何かが発生したときに、まだ本人さえ感知していないその生成中のノイズを感じ取らなければいけない。相手が動き出したときにはもう受信が終わっている。シグナルになる以前のノイズを聴き取る。そういう点で武道的な身体感受性の開発というのは、赤ちゃんの母語の習得と構造的に同一なんです。
合気道とレヴィナスの両方をやっているうちに、合気道の多田宏先生が教えていることと、レヴィナスが言っていることは、言葉遣いは違うけれども、どうやら本質的には同じらしい、少なくとも問いのかたちは同じものであるということに気づきました。人間は他者からのメッセージをどう受けとめるのか、理解も共感も絶した他者とどうやって共生してゆくのか、どうやって共同体を成立させるのか、ひとりひとりに与えられた心身のパフォーマンスを最大化するというのはどういうことなのか。人間存在の本質にかかわるきわめて始原的な教えにふれるという点において、合気道とレヴィナス哲学は同じ問いをめぐっている。それを確信するようになった。もちろんそういう言葉で理解できていたわけではありません。でも身体的には同じ一つのことをしているという確信があった。そうでなければ、僕がそのようなルーティンを十五年間続けたはずがないんです。
レヴィナスの翻訳を何冊か続けているうちに、意味がわからなくても彼が次に何を言うのかがわかるようになってきました。形容詞がこう並んだら、次はこれでしょう、条件法の疑問文が来たから、こんな感じで着地するんだろう、と。呼吸が合ってくる。そうなってくると、関係代名詞と同格形容詞と無冠詞名詞が延々と並ぶ、どこまで続くぬかるみぞ的な、たっぷりした肺活量がないと耐えられないようなレヴィナスの文章についてゆけるようになる。
子育ての効用
八〇年代だったと思いますけれど、フランスで教育改革があって、リセで哲学を集中的に教えてきたプログラムを廃止するという判断を政府が下したことがありました。これにはフランス中の哲学者が猛反発した。デリダを先頭にして、哲学はフランスの子どもたちの知的成長に必須の教科であると訴えた。そのとき、ひとりレヴィナスだけが「いいんじゃないの? 別に」ときわめてクールに反応したんです。子どもには哲学はわからない。そもそも哲学は大人のためのものなんだから、高校生なんかに教えてもしようがない、歯の生えそろわない子どもにステーキを食べさせるようなものだ、と。これはユダヤ教のタルムード(ユダヤ教の口伝律法とその注解の集大成)学習の伝統なんです。タルムードは子供が読むものではない。学ぶ側がある程度の知的・情的な成熟に達しない限り、タルムードにアクセスすることは許されない。愛したり、憎んだり、苦しんだり、失望したり、子どもができたり、親を失ったり、愛する人に裏切られたり、人を殺しかけたり、殺されかけたり……というような経験を積むなかで人間的に成長すれば、薄皮をはぐようにいろいろなことがわかってゆく。哲学はそのような現場での検証を受けなければならない。レヴィナスはそういう考えなんです。
僕自身も、子どもが生まれて、育ててゆく過程で、レヴィナスの理解のしかたがやはり変わった。子どもができたとき、もう死んでもいいんだという感覚と、生きねばならぬという二つの感覚が同時にやってきました。生物の個体として次世代にDNAを継承する使命は終わったけれど、この子のDNAをさらに次にバトンタッチさせるまでは子どもを保護しなければいけない。「死ね」と「生きよ」という二つの相反する命令に引き裂かれる状態になるわけです。ああ、これが親になるということなのか、と。それまでは自我をピュアで透明な鉱物的なもののようにとらえていました。それが子どもが生まれた瞬間にバリバリと引き裂かれた。中から血や涙が出てきた。自分は硬い鉱石でもなんでもなくて、「なまもの」だったんだということがいやというほどわかった。そう思ってレヴィナスを読んでいくと、昨日まで意味がわからなかったところが、突然わかる瞬間がやってくる。
五年前にはさっぱりわからなかったところを読み直してみると「あれ? これって今オレが考えていたことじゃないの? そうなんだよ、まさにオレはこのことが言いたかったんだよ!」というようなことが起きる。わかるというのは「そうか!」と膝を打つものじゃなくて、「そうだよ……そんなの当たり前でしょ」と、気づいたら血肉化していたというふうに起こるんだということがわかりました。ロジックでは攻略できなくても、生きるという経験値を蓄積しただけでわかることはわかるようになる。やっぱりレヴィナスは「大人になれよ」と言っているんだ。「私の本を読んでわからないのは君が子どもだからだ、成長しなさい」と。
友人の氷のような批判
大学の同級生でアラブ近現代史をやっていた男がいました。友だちのなかでは一番ユダヤに詳しかったその竹信悦夫は、七五年に大学を卒業して朝日新聞に入りました。その頃は日本語で書かれたユダヤ関係の文献は非常に少なく、彼は僕がレヴィナスを研究していることを知っていたので、「もうこういうものはオレは読まないから」って何冊か専門書をくれた。それも修士論文で参考にした。竹信はそれまで僕に対しては本当に寛大な人で、批判というものを彼からされたことがなかったんです。だから修士論文を書き上げたときも、「おかげでこんなものが書けました」とお礼の気持ちもあってコピーを竹信に渡して読んでもらった。きっと「いやあ、面白いねえ」と言ってもらえると思って。ところが読み終えた竹信がそれまで一度も聴いたことのないような氷のように冷たい声で言った。
「内田、これではだめだ。おまえにはユダヤがわかっていない」
竹信の灘高時代の同級生の高橋源一郎さんに言わせると、竹信というのは、灘高時代はほんとうに氷のように冷たい理知的な断定を下す人だったんだそうです。高橋さんが知っている中学高校時代の竹信のイメージと、僕の知っている大学以降の竹信のイメージは全然違う。僕の知っている竹信は、大黒様みたいな顔をした、ケラケラ笑ってバクバクご飯食べて、麻雀やって……まことにお気楽な男だったんですけどね。しかし、つきあい始めて十年目にして初めて、竹信の取り付く島のない拒絶に遭った。これにはもうびっくりしました。中途半端な知識ではユダヤのことは絶対にわからないと言われた。
この友人の批判を奇貨として、僕はユダヤの勉強を始めることになりました。ヘブライ語の勉強を始め、正攻法だけでは芸がないので、側面からも攻めてみようと、反ユダヤ主義の研究も始めました。ある種の人々にとってユダヤ的なるもののいったいどのあたりが恐怖をかき立てるのかと。それを明らかにすることでユダヤに近づくこともできるのではないかというふうに考えたのです。
反ユダヤ主義者の書くものというのは極めて明快でわかりやすいんです。人の気持ちを巧みにつかむ扇情的な文章だし。はっきり言って知的にはちょっと問題のある人が多いんですけれどね。彼らが描くユダヤをめぐる物語は実にシンプルなんですけれど、その底には「自分たちより知性が抜きんでた存在がいて、彼らの考えていることが理解できない」という怯えた心理が透けて見える。彼らの恐怖はどうやら、彼らの知的枠組みではどうしても理解できないことに対する根源的な恐怖なんです。反ユダヤ主義というのはひとことでいえば、ユダヤ人の発想法が理解できないということに対する恐怖なんです。それはなぜ、ユダヤ人は抜きんでて知性的な存在なのかという問いと表裏一体になっている。ユダヤ思想とは何かという問いと、反ユダヤ主義とは何かという問いを併行して進めてみると、この二つの問いのあいだに位相のずれがあることがわかる。この「ずれ」はどうして発生するのか。小林秀雄賞をいただいた今回の本で、僕なりに考えてみたのはそのことでした。
女子大生に伝えること
僕は十二年間父子家庭で子育てをしてました。子育てなんてやっていたら文献も読めないし集中して研究もできないとよくいわれますけれど、そんなことはなくて、子育てをするんだったら、ちゃんとした方がいい。子育ての中には哲学的洞察への無限の素材が含まれているわけですから。僕はレヴィナスからそのことを教わりました。もちろん学会や研究会での研究発表はやってましたけれど、主題が主題ですから、ほとんど黙殺されてました。当時はそんなことに誰も興味を持ってくれなかった。ただ僕にとっては必然性のある、というよりも、ここを通っていかなければ先には進めない、という避けようのない経由地だったんです。
気がついたら、二十年以上、レヴィナス、ユダヤ教、反ユダヤ主義のことをごりごりと研究していた。二〇〇四年に、旧約聖書学とアメリカのユダヤ文学の専門家の二人の同僚と、勤務先の神戸女学院大学で「ユダヤ文化論」という半期だけの講義をすることになりました。しゃべりたいことがいろいろ出てきたので、翌年にかけて今度は僕一人で半期だけ同名の講義をしました。その時の講義録が『私家版・ユダヤ文化論』の土台になっています。
授業で取り上げようと思ったのは、五十四歳になった自分が、今の二十歳そこそこの女子大生たちに、言っておかなければいけないことがあるんじゃないかって、何となくそういう気がしたからです。きわめてコアなユダヤ研究者でなければ通じないような話であっても、何の予備知識もないこの子たちに、哲学用語はひとつも使わず、リアリティのある言葉で何かを伝えられるんじゃないか、と。いざ講義を始めてみたら、想像していた以上に反応がよかった。たとえば千三百万人しかいないユダヤ人が、ノーベル医学生理学賞の受賞者の二十六パーセントを占めている——こんなことだけ伝えても彼女たちにとっては驚きなわけです。音楽の世界でも、文学の世界でも、哲学の世界でも、ユダヤ人たちの存在感は圧倒的です。あらゆる分野でつねにイノベーションを担っているのはほとんどユダヤ人たちです。でも、わずか千三百万人の民族集団にどうしてそのような歴史的業績が集中するのか。その理由は誰も説明できない。
この千三百万人は国籍も違えば言語も違うしライフスタイルも違う。にもかかわらず集団としての求心力を保持している。そして中世以来繰り返し巨大な規模の迫害を受けて虐殺されてきた。彼らはいったい何者なのか。僕らが知っている国民国家とかナショナリズムというような概念ではユダヤ人が集団を形成できている理由は語り切れないわけです。サルトルのような「迫害がユダヤ人を民族集団として凝集させた」という説明も、そもそもなぜ迫害の標的がユダヤ人たちなのか、その理由については語っていない。なぜ反ユダヤ主義者はユダヤ人を憎むのか、という問いにはついに誰も答えてはくれなかった。
もちろん僕の講義を聴いて、彼女たちがこれでユダヤはわかった、と思ったはずはありません。しかし彼女たちには、世の中には僕たちの日常的な論理をどう駆使しても説明の届かない、巨大なスケールの謎があるということはわかってほしかった。それがわかってもらえれば、それでいいかなと思っていました。君たちの常識だけでは理解も想像も及ばない人間的事象が世界にはまだまだいっぱいあるよ。君たちが人間っていう存在をだいたいこの程度のものだと思っている範囲より、人間の生活できるエリアははるかに広く大きいものなんだ、ということを言いたかったんです。それさえわかってもらえれば、僕の教育目標は達成されたに等しい。講義が終わった後で「ユダヤ人が結局なんだか、わかりませんでした」と言ってくれれば、「はい、それでよろしい」と笑顔で答える。そういうものなんですね。
対話性と師弟関係
書き下ろしでは本を書かないというのは、そんな時間がないということもありますけれど、そもそも本に限らず、自分がすべてをコントロールすることなんかできないと思っているからです。いくら僕が書きたいものを書いたとしても、出版しましょうっていう編集者が出てこなければ本にはなりませんし、それから先もブックデザイナーとか営業の人とか次々現れて、ああでもないこうでもないというやりとりがあって、さらに本になったとしても書店員の人がどう並べてくれるかとか、誰が書評を書いてくれるかとか、様々な役割を担う人たちの複合的な運動がある。その総合的な運動の結果として初めて本が読まれるという状況ができ上がる。こっち側に発信者が立っていて、向こう側に受信者が立っていて、「はいよ」と手渡すというようなシンプルなものじゃないですよね。その途中にいろいろな人のそれぞれ異なる欲望や夢がかかわっている。書きたい、売りたい、並べたい、読みたい、コメントしたい……そういった無数の思いの複合的な効果として「本を読む」という行為は成立している。僕ひとりが「書く」と力んでも、それだけでは始まらない。
原理的には「読みたい」という欲望に引き出されてゆくのでないと、書く動機付けは起動しないような気がするんですね。だから、僕はよく学生に言うんです。キャリアパスのドアというものは、こっち側にはノブがない。向こう側からしか開かないよと。本だって同じだと思うんです。ご縁がなければ、いくら頭のなかに壮大な構想があっても本にはならない。僕が今物書きになっているのも、インターネットが登場しなければ、なかったことなんじゃないかと思っていますから。
僕はもともとコンピュータ・リテラシーがきわめて低い人間です。自分のホームページを始めるときも、ゼミの学生がセッティングをしてくれて、管理もすべてやってくれた。その後も、とにかくややこしいことは全部やってあげますから先生は書くことに専念してね、という皆さん方の善意の上に(笑)、成り立っているんです。彼らが協力してくれなかったら、自分ではなにひとつできなかった。そうやって用意されたホームページに好きなことを書いていたら、今度は「本にしませんか」という人が現れたので、「はい、お願いします」ということになった。僕が青写真を描いて事態が動いているわけではなくて、集団的な営みなんです。
だから、僕の書き物は対話的なんですね。レヴィナスについて、というような誰に頼まれなくてもどうしても書いておきたいものもありますけれど、それ以外のものは、読みたいという要請、話を聴きたいという要請にしたがって書いたり喋ったりしていることから本になっていったものがほとんどですから。要するに僕は「オンデマンド・ライター」なんですよ——こういうことを言うからどんどん仕事がふえちゃうんですけど。
ただ誤解されると困るんですが、インターネットの対話性というのを僕はそれほど信用しているわけじゃありません。基本的にネットでのやりとりは身体的なものじゃないですから。もちろん、ネットでしか会ったことがない人でも、文章に肌触りが感じられる人もいます。しかし、インターネット・コミュニケーションの上に身体性をのせていくというのは、実は相当な表現力が必要です。それをクリアできるだけの筆力を持っている人は滅多にいない。やっぱり具体的に呼吸や表情がともなった生々しい関係がないと、面白くないんです。
もうひとつ、対話性ということで言うと、僕が今も武道を続けている大きな理由は、師弟関係ということです。師というものがいて、引っ張ってもらわなければ絶対にブレイクスルーできない壁がある。個人的努力では行ける距離に限界がある。
レヴィナスにもモルデカイ・シュシャーニという師匠がいました。家族を持たず、定住する家を持たず、世界を放浪していた人です。シュシャーニ師は気が向けば富裕なユダヤ人家庭に寄寓して、そこでタルムードを教えて、わずかな謝礼を手にしていたそうです。「師はひとからは乞食のように見えたであろう」とレヴィナスは書いています。その人をレヴィナスはわが家に招いて、起居をともにして、タルムードを学んだ。レヴィナスのいう対話というのは、その師弟間の息づかいや体温のようなものの上に実際に基礎づけられた、身体的なものなんです。
今度あらためてレヴィナスの『困難な自由』を訳し直して出すことになりました。八五年に翻訳書を出したときは、全体のうちで意味がわかっていて日本語にできたのはせいぜい全体の三分の一くらいでしたけれど新訳ではなんとか六割ぐらいまでは理解できた。四割ぐらいは一応フランス語から日本語にはしましたけど、実は書かれていることの意味は僕にもわかっていません。でも、まったくのゼロから始まって、やっと六割わかるところまで来たのだから、上等じゃないかな、と思ってはいるんですけれど。
1950年、東京都生まれ。東京大学文学部卒。東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。同大学助手を経て、現在、神戸女学院大学文学部総合文化学科教授。専門はフランス現代思想、映画論、武道論。著作に『「おじさん」的思考』『先生はえらい』『下流志向』ほか多数。(受賞当時)
● ● ●
選評
感謝の気持ち
加藤典洋
内田樹さんの『私家版・ユダヤ文化論』は本になったときに時評と書評で取り上げたのでほぼ一年ぶり、三度目の読書だった。今回の読書が一番味わい深かった。
この本には言ってみるなら三つの層がある。第一の層は、全四章のうち第二章、第三章に述べられる近代日本および近代ヨーロッパにおける反ユダヤ主義のありようを述べた部分。興味深い歴史的な鳥瞰がなされているけれども、私には少し物足らなく感じられた。第二の層は、主に「はじめに」と第一章で提起されている本書の主題に関わる部分中、社会構成主義的なアプローチでは不十分な所以が述べられる部分。「問題の次数」を「一つ繰り上げ」た斬新な問いかけが、終章で、「ユダヤ人問題」こそが「キリスト教ヨーロッパ」なるものを作り上げる母胎だったのではないかという、驚くべき結論にたどり着いている。一年前読んだときには、このスリリングな展開に強い印象を受けた。第三の層は、主に終章で、ユダヤ的思考の精髄がエマニュエル・レヴィナスの引用によって語られる部分。ここでのカギは「始原の遅れ」である。われわれはそのつど遅れて世界に登場しているので、自己を始点にはできない。これが、ユダヤ的思考の原型であると、述べられている。
このたび読んで、もっとも私の心に響いたのは、この第三の層である。旧約で、筆舌に尽くしがたい理不尽な目に遭ったヨブが神を問責するのに、神が応える。「私が世界を創造したとき、おまえはどこにいたか」。この話はかつて、私に神の不合理、理不尽さ、絶対、隔絶を示すエピソードとして聞こえていたが、今回の読書で、神の「教え」の声調を届ける、静かな挿話として受けとめられた。
自己を始点にできないとは、何という慰めだろう。でも自己をそこから考えはじめるにあたっての、何という希望でもあるだろう。そう思いました。
ハイデッガーは、人間は、存在するのではなく、そこに存在するのだと言って、現存在(世界内存在)と述べたのだが、レヴィナスは、これを、——ハイデッガーが空間的に述べたところを——時間的に変位する。人間は、存在するのではなく、その刻限に存在する、つまりそこに、到来するのだ、というように。あの、いつもポストモダニスティックに響く「始原の遅れ」という言葉。これが私の中で、はじめて、「が、自分といふものは、目がさめたらゐたんですからね」という、二十歳の時に読んで目を射た中原中也の言葉と結びついた。内田さんはこれまで何度もこのことを書いているわけだが、なぜか、このたびの本ではじめて私にはそう思えた。今回は、気づいたら、感謝の気持ちで、選考会に臨んでいたのでした。
つねならぬ緊張
堀江敏幸
白黒つけない姿勢を貫くのは、いまの時代、とてもむずかしいことである。ただしそれは、どっちつかずのまま、いつまでも煮え切らない言動で相手をいらだたせる、という意味ではない。その程度のごまかしなら誰にでもできる。なぜ自分が右にも左にもつかないかを論理的に語りつづけ、どちらか一方に吸収されないように揺らぐのではなくいかなる状況下でも中央にある道を見出し、攻撃を攻撃と感じさせないうちに双方を攻めたてて欠点を暴いてみせること。それが至難のわざなのである。しかしそれがみごとになしとげられてしまうと、攻められた側は、反論の余地なく示された隘路をまえに、それまでまったく使っていなかった思考の筋肉をもみほぐされたような快感を覚える。
なにが言いたいかといえば、要するに、それが内田樹氏の「ためらい」の力線であり、方法であるということだ。これさえあれば、力強い中線を引けないような問いはなくなってしまう。文学にも、哲学にも、政治にも、教育にも、武道にも、どんな主題にも柔軟に対応して、問いかけた側の思考のツボを刺激することができる。それが鮮やかにすぎると、凡人にはかえって怪しまれることもあるのだが、だから御本人もそれを敏感に察知し、逆に切れ味をほどほどにとどめておくために、抵抗としてのユーモアを、要所要所に半田付けしてきたのではないかと思う。
ところが『私家版・ユダヤ文化論』において、内田氏はそのユーモアを極力抑え、ユダヤ人とは何かという長年の「研究」によって十分に熟成された「主題」を、ほかのなにものでもない、他に代えがたい「この主題」として差し出してみせた。「ためらい」の手法が「主題」そのものと分かちがたく結びつき、どちらを欠いても行文に力がなくなるぎりぎりのところで論が進められた結果、行文につねならぬ緊張感が生まれている。その硬さに、私は打たれた。
「立ち姿のよい」人と本
関川夏央
他の誰によっても代替し得ない使命を課せられているという「有責意識」を持ち、そのうえ、群を離れて「ユニークであろうとする存在者」は、憎まれる。迫害される。
内田樹は若い頃、日本ではかえりみられることまれな、モーリス・ブランショ、エドゥアール・ドリュモン、モレス侯爵などの本を熱心に読んだ。ときに地べたにすわりこんで読み、その「ユニーク」な姿は道行く人を気味悪がらせた。
それら反ユダヤ主義者たちはみな、「わりといいやつ」だったし、本はおもしろかった。
一方、迫害される側のエマニュエル・レヴィナスからは深い示唆をうけた。啓示といってもよい。以来、レヴィナスは内田樹の「先生」となった。が、そのレヴィナスとブランショが親友同士だったりする。世界は複雑なのである。
若い内田樹自身、「ある種の人間」たちを「死ぬほど怒らせる」ことがしばしばあった。しかし理由がわからなかった。ユダヤ人とユダヤ文化への興味は、元来その謎を解明したいという意欲から発したのであるが、三十数年の歳月ののち、この本『私家版・ユダヤ文化論』となって大きな実をむすんだ。
ところで、自分を棚上げしていうのだが、この年頃の人には「痛い」印象の人が多い。体験の「痛さ」の展示によって、人を圧伏しようとするのである。
そういうところが内田樹にはみじんもない。「有責感」の欠如した人には冷眼をもってむくいるが、その余の視線は穏やかだ。そして単純な言葉で複雑な事態を語ろうとつとめる。そんな彼の文章からは、ユーモアが春の水蒸気のように立ちのぼっていて、読みつつ私はいく度も微笑した。
この人とこの人の本は、ともに「立ち姿」がよい。構えず、すっと立っている。それでいて背中に油断がない。彼は、かりにフランス語やフランス文学の教職を失っても体育の教師で食えるというまれな人だが、その武道(合気道)の鍛練のたまものだろう。
私は、自分で自分の謎を解明したいと願うほど嫉妬深いタチの男だから、こういうデキる人はいつか迫害してやらねば、と考えていた。しかし、とてもかなわぬと見切った瞬間から、うらやみは消えた。それどころか、いつか機会を見つけて「先生」と呼んでやろうと思うに至った。人の心は複雑である。
このたび内田樹とその書きものに、小林秀雄賞をもらっていただけることになった。物語がハッピーエンドに終って、私はとても喜ばしく感じている。
少しだけ注文が
橋本治
かつてこの『私家版・ユダヤ文化論』の中に登場するノーマン・コーンの『シオン賢者の議定書——ユダヤ人世界征服陰謀の神話』を、訳者の内田さんが危惧したように、「際物だったらどうしよう」と思いながら読んだ。ベラボーにおもしろかったので、人に「すごいよ!」と言って奨めた。
内田さんの訳によるノーマン・コーンの本は、たとえて言えば「字幕付きの外国映画」である。つまり、「外国のこと」を擬似外国人になって、「自分の属する世界の出来事」と思いながら見る。しかし、私はその「外国映画」を、「これは日本のことだ!」と思いながら見た。「愚かさ」が「暴力」に変わって行く、そのプロセスが、である。
一方、今回受賞の『私家版・ユダヤ文化論』は、外国人キャストを使った日本人スタッフによる「日本映画」である。だから、ここでの「ユダヤ人問題」は、簡単に「日本のこと」にはならない。それとは逆に、「自分はユダヤ人かもしれない……」という自問が浮かび上がって来る。現に、第一章には《私たちの語彙には、「それ」を名づけることばがなく、それゆえ私たちが「それ」について語ることばの一つ一つが私たちにとっての「他者」の輪郭をおぼつかない手つきで描き出すことになる。私たちはユダヤ人について語るときに必ずそれと知らずに自分自身を語ってしまうのである。》とある。そして終章では《「始原の遅れ」の覚知こそが「ユダヤ的知性」(というよりは「知性そのもの」)の起源にあるものなのである(たぶん)。》とある。私個人のあり方をこんなに明快に説明してもらったのは、初めてのように思った。
今回の内田さんの受賞に異存はない。しかし、私個人としては、内田さんに( )で括った部分をもっと展開してもらいたい。「ユダヤ人問題」には、「あなただってユダヤ人かもしれない」という開き方があるかもしれないし、「ユダヤ的知性」=「知性そのもの」という仮説は、そこにまで踏み込んでいると思う。
言葉の身体性
養老盂司
内田さんの特徴は、思うに言葉が肉体化していることである。そういう表現が通じるかどうか、自信はない。私には強い偏見があって、身体性に惹かれる。それは現代社会での身体性の欠如と関わっている。だから言葉の身体性と表現しても、ピンと来ない人が多いと思う。
武道には「居つかない」という表現がある。内田さんの本は短い。それはおそらく「居つかない」からである。その反対はペタッと座り込むような状態である。最近の若い人を見れば、よくわかるであろう。次の動きに対応できるように、いつも構えていれば、ひとりでに「居つかない」状態になる。論考にもそれが出てしまう。
今回の『私家版・ユダヤ文化論』は珍しく内田さんがゆっくり構えて書いた書物であろう。だから本人の持ち味が十分に出ているとはいえないかもしれない。しかし私はこれでも授賞に十分と判断した。とくに興味深かったのは、レヴィナスを介して「始原の遅れ」を論じた部分である。意識は身体に対してつねに半秒ほどの遅れを持つ。それが人間の現実認識の根本にある。ユダヤ文化は、脳など調べなくても、それを知っているのではないか。内田さんがそこに肝要の点を感じ取ったについては、おそらく武道の修練が基礎になっていよう。身体が核心を悟るのである。それは理解というより、共鳴というしかあるまい。
文科と理科は「二つの文化」といわれるように、かなり違った面を持っている。にもかかわらず、無意識にせよ、それを本質的につなぐような仕事には、なかなかお目にかかれない。作品にはそれ自身の完成度と、その作品自身を超えた大きな世界を示唆するという、二つの評価の目安がある。今回は後者の意味でこの作品を推薦した。
もちろん内田さん自身が現在の言論界で重要な存在であることは、いうまでもない。これまで受賞歴がないと聞いたが、そちらの方がむしろ興味深いことであろう。
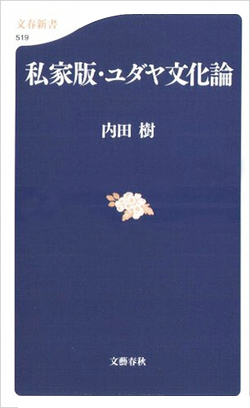
2006/7/1発売
この記事をシェアする
「小林秀雄賞」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら





