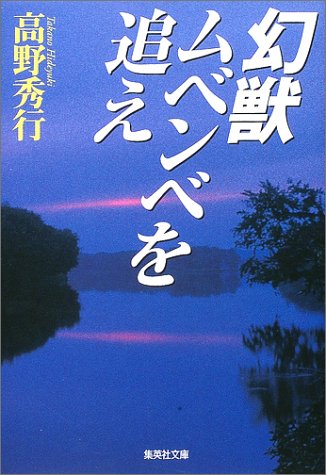2023年5月31日
後篇 オノマトペから言語が発達した?
「言語はジェスチャーゲーム(言葉当て遊び)のようなものだ」という画期的な見方を提示して話題になっている『言語はこうして生まれる』(モーテン・H・クリスチャンセン、ニック・チェイター著)。本書について、辺境ノンフィクション作家の高野秀行氏と、慶應義塾大学SFC教授の今井むつみ氏が語り合った。後半はオノマトペとアブダクション推論から言語習得を考えます。
(前篇はこちらから)
高野 今井先生も最近『言語の本質』(秋田喜美氏との共著)という本を出されましたよね。

今井 はい。この本では、どうやって言語の多様性が生まれ得るんだろうかということを真剣に考えてます。『言語はこうして生まれる』が出るとは知らずに書いたものなんですが、根っこが同じだから、言いたいことはすごく似ていると思いました。
高野 読ませていただきましたが、オノマトペですよね。
今井 そうですね。一つはオノマトペで、もう一つは人間がどうやって推論するのかということ。だからオノマトペと推論です。
高野 オノマトペは音象徴とも言いますよね。
今井 はい。
高野 音象徴という言葉は、最近特に目にするようになったと思うんです。僕は言語学のことはいくらも知らないんですけど、ソシュールが言っていた「記号と意味の恣意性」というのがあります。記号と意味は、直接には関係がないという。日本語では「行く」だけど、英語では「go」で、全然関係がない。そういうのだと思ってたんですけども、いろんな言語をやってるうちに少しずつ、それだけじゃなくて、音自体が似てるものっていろいろあるじゃないかっていうことに気づいてきた。例えば「切る」という言葉だと、大体「k」か「t」の音が入ってるんですよね。日本語だと「切る」でしょ? 英語だと「カット」でしょ? タイ語だと「タット」なんですよ。で、リンガラ語だと「カタ」なんですよ。
今井 へぇー。
高野 大抵「k」か「t」が入ってるんです。切る音というかね。
今井 そうですね。「k」とか「t」って空気を阻害されるので、そのイメージがあるんですよね。私はオノマトペから語彙が発達したというのは、そんなおふざけじゃなくて真剣に考えてもいいんじゃないかなって思います。
オノマトペ言語論
高野 オノマトペから言語ができてくるというのは、かなり画期的な見方なのでしょうか?
今井 立場によりますが、今はわりとそういう考えもメジャーになりつつありますね。最初は「何バカなこと言ってるんだ」という感じかと思ったんですけど。私がなんでオノマトペに興味を持ったかというと、子どもの言語発達を調査するために保育園に行くと、子どもも、保育士さんもよくオノマトペを使ってるからなんです。だから、オノマトペには何か意味があるに違いないと思って、それを実験で示すことを始めました。
高野 なるほど。
今井 そうすると、動詞の学習をするときに、オノマトペを使った時とそうじゃない時で、まったく違うという結果が出たんです。ある動作について、オノマトペじゃない動詞で教えると、半分しか正解できない。でも、オノマトペを使った動詞で教えると、80%ぐらいが正しいほうを選べる。しかも日本の子どもだけではなくて、日本語を全然知らない母語が英語の子どもでも、同じぐらい正解できるというデータが出たんです。
高野 面白いですね。
今井 最初に私が論文を発表したのが2008年だったんですけど、そこからけっこうワーッと火がついたように増えて。言語の最初は、オノマトペやジェスチャーのように世界の模倣であり、それを記号化したものなんじゃないかという考えは、わりと自然だと思います。ただ研究者の中でも、「オノマトペって、世界中、同じでしょう?」と思ってる人が多いんですよね。
高野 ああ、そうなんですか。
今井 実は外国語のオノマトペってほとんど分からないんです。オノマトペのように非常に身体的なものでさえも、母語じゃないと分からないというのは、どういうメカニズムで生まれるのかなということは、個人的に興味があって、その問題を深掘りするために実験しています。
高野 たしかにオノマトペってすごく身体的なものですよね。僕の友だちに、アフリカのスーダン出身のモハメド・オマル・アブディンという人がいます。全盲で『わが盲想』という本も書いています。
今井 ああ、あの本! すっごい面白いし、すっごい正しいと思いました。あの言語学習こそ、記号接地した、生きた知識を作る学習だと思って。
高野 はい。すごい仲よくて。彼は18歳のとき日本に来て、そこから日本語を覚えたんですけど、話すのも文章を書くのも、普通の日本人よりもとにかくうまい。日本語の感覚、語感まで完璧に捉えてる。それなのに、彼はオノマトペが苦手だって言うんですよ。
今井 分かります。自説ですが、「オノマトペ臨界期説」というのを考えています。
高野 オノマトペ臨界期説?
今井 小さいときに、親御さんの仕事の関係で海外で育つ人がいるじゃないですか。そういう人も、両親が家で日本語を話していて、日本語学校とか行っていると、日本語にそんなに問題ない人が多いんだけど、それでもオノマトペだけは苦手という人がけっこういます。
高野 ああ、やっぱりそうなんですね。
今井 うん。オノマトペって一番記号接地することばなんです。音の学習って一番早くて、意味の学習より先なんです。音の学習をして、音と意味をつなげる段階でオノマトペを覚えていくので、その時期にインプットが足りないと、感覚が養われないんじゃないかな。
高野 そういうことなんでしょうね。アブディンは、「『カラカラ』と『ガラガラ』というのは、どこまで『カラカラ』で、どこからが『ガラガラ』なのか、いまいちその塩梅が分かんないんだよね」って言うんですよ。「いまいち」とか「塩梅」とかは分かるのに、それが分かんねえのかってこちらは思うわけですが(笑)。彼は文章でオノマトペを避けるんで、妙に格調が高いんですよ。記号接地が薄いと格調が高いように思われる傾向があるじゃないですか。
今井 わかります(笑)。
宮古語のオノマトペ
高野 2月に宮古島に行ってたんです。ご存じかと思いますけども、あそこは古代の日本語の音が部分的に残ってる地域で、「ハヒフヘホ」が全部パ行で、「パピプペポ」なんですよ。
今井 宮古ってそうなんですね。
高野 奈良時代の日本語はそうだったと言われています。沖縄の言葉は、一説によると1500年ぐらい前に日本語から分かれたらしいんです。宮古の言葉は那覇ともまた違っていて、すごく面白いんです。「光」のことを「ピカリ」と言ったり。
今井 へぇー。
高野 ピカリって要するにピカピカのことでしょう? 今の日本語だと、「光」と「ピカピカ」って何の因果関係も感じないじゃないですか、言葉自体にはね。
今井 はい。でも、「ピカリ」って言うとすごい……
高野 そう、「ピカリ」と言うと、もうそのまんま(笑)。
今井 本当にね。
高野 だから宮古語だと、「ピカリがピカピカとピカってる」と言うわけですよ。そしたら、全部同じだというのがすぐ分かりますよね。
今井 ですよね。
高野 あと、「話す」は「パナス」と言うんですよ。
今井 パナス?
高野 うん。で、「パナス」というのは喋ることも言うし、手放すことも「パナス」なんですね。喋ることと手放すことは、普通は全然リンクしないと思うんですけど、「パナス」と聞いた瞬間に、両方ともパッと出てるものだから、パナスなのかな。そこから動詞が出てきたんじゃないかなとか、ちょうど思ってたとこだったんです。
今井 そうなんだ。それは言語を、宮古語を習いに行ったんですか。
高野 全然違うんですけど(笑)、僕はいれば、日常的にそこの言語をかじるので。
今井 ヨーロッパの人って、エキゾチックな言語をけっこうやりたい人が多くて、いわゆるフィールド言語学というのが盛んなんです。その中心的な研究所がオランダにあるマックス・プランク心理言語学研究所というところで、そこのドクター候補の人が宮古でフィールドワークをして博士論文を書くといって、宮古のデータを取ってましたね。
高野 そうですか。私もユーチューブでフランスの言語学者が宮古語を話している動画を見ました。宮古の言葉でもう一つ面白かったのが、形容詞を2回重ねる癖があるんです。
今井 ああ、はいはい。
高野 例えば「おいしい」ってことを「ンマンマ」と言うんです。それはもう「ンマンマ」としか言わなくて、「ンマ」とは言わないんですよ。僕が行ってるときは、けっこう寒かったんですが、「寒い」は「ピシ」とか「ピシャ」なんですけども、「ピシピシ」って言うんです。1個しか言わないというのはあまりなくて、普通に言うときは「ピシピシ」。「綺麗だ」と言うときも「カギカギ」とかね。
今井 へぇー。
高野 だから、なんかもう既にそこで形容詞がオノマトペっぽいんです。「風が強い」は「カジツーツー」って言うんですよね。本当、カジがツーツーって感じがするわけですよ(笑)。
今井 すごいしますよね。「ピシピシ」って、なんか肌に刺さるような感じ?
高野 そう、厳しい感じがしますよね。だから形容詞がとてもオノマトペっぽいんですよね。
オノマトペと「言葉の密度」
今井 基本オノマトペになりやすいのは、形容詞か副詞なんですよね。名詞はそれほどないですね。
高野 動詞もありますよね。
今井 ありますね。要するに密度の関係なんじゃないかなと思うんです。モーテンの本にも書いてありましたが、名詞って、たくさんの言葉が必要なんです。いろいろなモノを区別して、差異化したいから。そうするとオノマトペだと不都合なんです。
高野 ああ、分かりづらくなるってことですね。
今井 子どもも最初は、「ニャンニャン」とか「ワンワン」とか言うんだけど、例えばネコ科の動物をトラでもライオンでも、みんな「ニャンニャン」と言ってたら、もう区別がつかなくなっちゃいますよね。だからある概念分野で名詞の密度が濃くなると、音象徴は不利になるんです。でも、形容詞とか動詞とかっていうのは、そんなに新しい言葉がどんどん作られるわけでもなくて、わりと密度が一定に保たれているんですよね。
高野 なるほど。そもそも言葉の数も少ないし。ちなみに日本語以外のオノマトペはどんな感じでしょうか。
今井 英語を話す人はいまいちオノマトペについて感覚が薄いのですが、それは英語の中では、漫画の効果音みたいなものしかオノマトペっていう認識がないからなんです。でも実は、英語にもすごく音象徴はあって、それが普通の言葉の中に入りこんでいます。たとえば英語には「歩く」に相当する単語が140あると言われていて、「stroll(ぶらぶら歩く)」「swagger(ずんずん歩く)」「toddle(よちよち歩く)」など、動作の様態がそのまま動詞になっている。これらの動詞を見ればわかるように、音と意味につながりが感じられるものが多いんです。
高野 たしかにそうですね。
今井 私は中国語を習ったことがあり、道半ばで挫折したんだけど、中国語もすごく音象徴的だなと思っていて。いろんな言葉がすごく感覚的に合っているというか。たとえば「蝶々」って「フーティエ(胡蝶)」っていうじゃないですか。
高野 ああ、そうでしたっけ。
今井 日本語でも「てふてふ」と書くけど、「フーティエ」もすごい音象徴的だなと思って。ふわーっと飛んでる感じ。多分、広東語とかのほうが北京語よりももっと音象徴性が強いんじゃないかなと思ってます。
高野 広東語のほうが古いですよね。
今井 そうなんです。古い言語のほうが、より音象徴性を持っている。それこそ、その宮古の言葉に音象徴性が強いのと同じですね。
アブダクション推論とは
高野 僕は今井先生のこの本で、アブダクション推論にも「おお」と思ったんです。僕はアブダクション推論が大好きなんですね(笑)。
今井 分かります(笑)。推論のなかで、演繹推論と帰納推論は、みなさんご存知だと思うのですが、哲学者のパースが唱えたのが「仮説形成推論(アブダクション推論)」です。観察データを集めて全体に一般化するのが帰納推論だとすると、観察データを説明するための仮説を形成するのがアブダクション推論です。結果をもとに原因を推論するというか。
高野 アブダクション推論というのは論理的には間違いなんですよね。
今井 はい。でも、そもそも「論理」という言葉はけっこうトリッキーで、私たちが日常で使ってる論理も、フォーマルな演繹推論のことではないじゃないですか。論理学の真偽でいうとアブダクション推論は「偽」で間違ってるんだけど、人はどちらかというと蓋然性というか、「普通に考えたらそうだよね?」というふうに考えますよね。
高野 ええ。そうですね。
今井 例えば誰かと待ち合わせしていて、その人が来なかったとする。普段から忙しいから仕事が押しちゃって来られなかったのかなと思うわけですが、それは論理的には正しくないわけです。来なかった理由は、仕事が終わらなかったからだけとは限らなくて、ほかの理由もいくらでもあるわけなので。でも、「ああ、かわいそうに仕事終わんなかったのかな」と思ったりするじゃないですか。そういうのも全てアブダクション推論ですよね。
高野 チンパンジーはそれができないんですよね。
今井 そうです。動物はアブダクション推論しないんです。
高野 例えば、三角とリンゴを覚えさせて、三角を見せると、リンゴを持ってくることはできる。でもリンゴを見せても三角には行かない。逆方向の対応づけができない。
今井 そうです。前提と結果をひっくり返してしまう推論を対称性推論と言いますが、これはアブダクション推論と深い関係があります。それを動物はやらないんです。
高野 人間は当たり前にやってるし、やらずにはいられない。
今井 そうです。常に因果を考えてしまう。でもそれは正しいとは限らないんです。
高野 僕がやってることも、すごい手がかりの少ないアブダクション推論を連発してるわけです。もしかしたらムベンベ※2がいるかもしれないとか。僕はそれがすごい好きなんですよね。でも、論理的に正しくないから、だいたいやることが間違ってる(笑)。
※2 コンゴ共和国の湖沼、湿地帯に住むといわれる伝説の生物。高野さんは早稲田大学探検部時代に実際にムベンベを探しに行き、その時の体験談を書いた『幻獣ムベンベを追え』がデビュー作となった。
今井 でも私は、人類を進化させ、文化を作ったのは、論理的に合っている演繹推論ではなくて、間違っているアブダクション推論だと思うんです。それが人間のデフォルトの思考だから、こんなに進化したんだと思う。
高野 いやぁ、本当に素晴らしいことをおっしゃいますよ。僕は今まで自分のやってることを「間違う力」とか呼んでましたし、人からも呼ばれたりしてきたので。
今井 演繹推論は論理的には必ず真だけど、進まないんです。新しい知識を作らないんですね。新しい知識を作るのはアブダクションなんです。
高野 そうですよね。
今井 はい。だから私のセオリーでは、アブダクションをするから人間は言語という体系を作ることができた。
宮古語の行方
今井 次に追究したい言語はまだ決まってないんですか。
高野 今、宮古語が楽しいですね。初めて日本語の親戚に出会った感じです。
今井 そうなんですね。
高野 でも、学習方法がすごく難しくて。今までにないパターンですね。
今井 若い人は話せるんですか?
高野 10人に1人もいないみたいです。学校はもう70年以上前から、少なくとも戦後は全部共通語ですから。僕と同じ56歳の人が、僕から見ると宮古語を完璧に喋ってるんですけども、もっと年配の人から言うと、「薄い」って言うんですよね。「こいつの宮古の方言は、50%ぐらいだ」って。
今井 へぇー。宮古語って文法も違うんですか。
高野 かなり違いますね。僕はいまだによく分かってないんですが。それと面白かったのは、僕は友達のお母さんに習ったんですけど、その88歳のお母さんがずっと「こんなの習っても何もならんさ」って言うんですよ。それは、ほかの集落に行くと違う言い方をするから、「ここではそうだけども、よそじゃ通じん」とかって。
今井 じゃあ、ほかの集落とコミュニケーションをとるためのピジン※3みたいなのあるんですか。
※3 異なる言語を話す人々が意思疎通するために、互いの言語が混合して生まれる通用語。
高野 それは、共通語を交えて方言を薄くするみたいです。
今井 ああ、それがピジンなんだ。
高野 うん。で、今は何ていうのか、沖縄新方言みたいなのがあって、「なんとかするサー」みたいな。あれはもともとの沖縄の言葉とは何も関係がなくて、新しい方言みたいなんですよね。ちょっと語尾に「サー」をなんかつけて、「共通語+サー」みたいな(笑)。
今井 へぇー(笑)。
高野 あと宮古語は、共通語も入ってくるし、那覇の言葉が都言葉のようにして入ってくるんですよ。だから、例えばヤギ汁のことを「ヒージャー」、内地の人間のことを「ナイチャー」とか。それは那覇の言葉なんですよね。
今井 でも、言語ってそうですよね。留まっていられないもんね。
高野 そうそうそう。
今井 必ずコンタクトがあって、それでどんどん変わっていくものだから。〇〇語といっても、それはある時間軸のタイムラインの中の、ある地点においてのもので。本当にオーセンティックな〇〇語というのは実は……
高野 ないんです。それが僕にはとても面白いんですよ。
今井 でも、そしたらまるでフィールド言語学者ですね。
高野 まあ、そうですね。単なるオタクですけど。
今井 いやいや。今度その本を書かれるんですか。
高野 いや、書かないですよ(笑)。だって言語学者じゃないし。
今井 ぜひ書いてください。英語にも翻訳したらいいと思う。すごい貴重なデータだと思うから。
高野 うーん、そうですね。
-
『言語はこうして生まれる: 「即興する脳」とジェスチャーゲーム』
モーテン・H・クリスチャンセン/著、ニック・チェイター/著、塩原通緒/訳
2022/11/24発売
公式HPはこちら
(おわり)
-

-
今井むつみ
1989年慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学。94 年ノースウェスタン大学心理学部Ph.D.取得。専門は認知科学、言語心理学、発達心理学。著書に『ことばと思考』(岩波新書)、『学びとは何か』(岩波新書)、『ことばの発達の謎を解く』(ちくまプリマー新書)、『英語独習法』(岩波新書)など。共著『言葉をおぼえるしくみ』(ちくま学芸文庫)、『算数文章題が解けない子どもたち』(岩波書店)、『言語の本質』(中公新書)などがある。
-

-
高野秀行
1966年東京都生まれ。早稲田大学探検部在籍時に執筆した『幻獣ムベンベを追え』でデビュー。辺境探検をテーマにしたノンフィクションを中心に『西南シルクロードは密林に消える』『ミャンマーの柳生一族』『アヘン王国潜入記』『謎のアジア納豆 そして帰ってきた〈日本納豆〉』『幻のアフリカ納豆を追え! そして現れた〈サピエンス納豆〉』など著書多数。『謎の独立国家ソマリランド』で第35回講談社ノンフィクション賞、第3回梅棹忠夫・山と探検文学賞受賞。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 今井むつみ
-
1989年慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学。94 年ノースウェスタン大学心理学部Ph.D.取得。専門は認知科学、言語心理学、発達心理学。著書に『ことばと思考』(岩波新書)、『学びとは何か』(岩波新書)、『ことばの発達の謎を解く』(ちくまプリマー新書)、『英語独習法』(岩波新書)など。共著『言葉をおぼえるしくみ』(ちくま学芸文庫)、『算数文章題が解けない子どもたち』(岩波書店)、『言語の本質』(中公新書)などがある。
対談・インタビュー一覧
-

- 高野秀行
-
1966年東京都生まれ。早稲田大学探検部在籍時に執筆した『幻獣ムベンベを追え』でデビュー。辺境探検をテーマにしたノンフィクションを中心に『西南シルクロードは密林に消える』『ミャンマーの柳生一族』『アヘン王国潜入記』『謎のアジア納豆 そして帰ってきた〈日本納豆〉』『幻のアフリカ納豆を追え! そして現れた〈サピエンス納豆〉』など著書多数。『謎の独立国家ソマリランド』で第35回講談社ノンフィクション賞、第3回梅棹忠夫・山と探検文学賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら