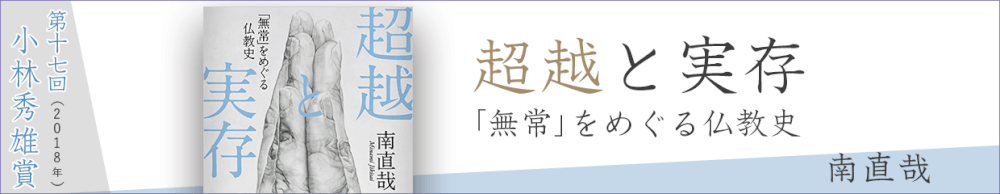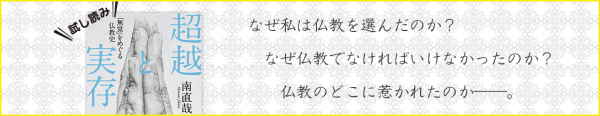僧侶としての「3つの顔」
――南さんのプロフィールには「福井県にある霊泉寺の住職、そして青森県にある恐山菩提寺の院代(住職代理)をつとめる」とあります。僧侶として、それぞれの場所でどのような活動をされているのかについてお聞かせください。
1984年に26歳で出家してから、20年近く曹洞宗の総本山である永平寺で修行生活をおくっていました。多くは数年の修行をもって下山し、それぞれの寺に戻る、というのが一般的なので、20年近く永平寺にいたというと、それだけで珍しいこととされます。
入門して15年が過ぎた頃、ある老師から「お前もそろそろ寺に入りなさい」と言われて、永平寺に籍を置いたまま同じ福井にある霊泉寺の住職となりました。伝統教団においては、住職をしてはじめて一人前みたいなところがあるので、その意味では霊泉寺の住職であることが、私の曹洞宗内の立場を支えています。そこは檀家が30軒ほどの小さな寺で、棚経(註・お盆に檀家をまわって読経すること)や葬式や法事の導師を務めるなど、いわゆるごく一般の住職としていることは変わりません。
恐山とは、永平寺をいよいよ下りるという段になって縁ができ、2005年から院代つまり住職代理として入山しました。だからといって住職をしている霊泉寺を捨て置くわけにはいきませんから、現在は月に一度ずつ、恐山と福井を往復しています。ご存じのように、恐山というのは古くから知られている霊場で、毎年多くの参拝客が訪れる。その応対や宿坊(註・寺院が管理する参拝客のための宿泊施設)の管理などをしています。
加えて、講演や書き物などの仕事が増え、東京にも一定程度滞在する必要があり、その三カ所をぐるぐる回っている状態です。東京では、「相談をしたい」とやって来る人たちと会うようにもしています。
――相談を受けるきっかけは何だったのですか?
永平寺にいた時から、若い修行僧では対応できない電話を回されることが多くありました。「困った時の南さん」とか言われて(笑)。中には、「夫が浮気して困っている」なんて、「そんな相談を世俗を離れて修行している若僧のところに持ってきてもしょうがないだろう」というものもありましたが、結果的に場数だけは踏むことになった。だから「人の話を聞くぐらいはできるだろう」と、相談を受けるようにしたのです。
それに昔、私の師匠が自坊で習字を教えていて、それは月謝も取っていない完全なボランティアでした。「奇特なことをしますね」と言ったら、「バカなことを言うな。お前も坊さんなんだから、ひとつぐらい無償でやりなさい」と。あまり言うことを聞かない不肖の弟子だったから、ひとつぐらいは師匠の教えを守ろうと、時間の許す限り続けています。
――どのような相談が多いのですか?
様々です。親子や夫婦など人間関係のもつれについてのものから、病気や介護、そして「とにかく生きづらい」と訴える人まで。手に余るものも多いですが、話をするだけで楽になる人もいるというのもわかるので、その役には立てるかな、というのがひとつ。ただ、聞くだけではダメな時もある。つまり、嘘をつくわけじゃないけど、抱えている悩みや問題を正直に言わない人もいるわけです。その場合、「なぜこの人はこの話をするのか」を考えないといけない。問題がきつければきついほど、表面に出てくる言葉と距離が生じるので、その距離をはかるためには、会って対面でやらないと意味がない。これも私の僧侶としての活動において大事なことです。
――つまり、僧侶として「3つの顔」がある、ということですね。
それぞれ求められている役割が違うのは確かですね。おかげさまで、移動にやたら時間が取られますが。檀家さんに「住所不定住職」と揶揄されたこともあるぐらい(笑)。
――仏教の〝修行実践者〟という4つ目の顔もあると思うのですが。
それは、それぞれの〝顔〟のベースにずっと通底してあるものです。今でも、忙しくて坐禅をする時間がなかなか取れないと、やはり何となく落ち着きません。
そもそも、なぜ自分がお坊さんをやっているかというと、小さい頃からずっと抱えている問題を解決したいからです。それがすべてのベースになっています。住職をやっていても、院代をやっていても、相談を受けていても、坊さんになったそもそもの理由を、簡単には捨てられない。その問題が消えてなくならない限りは、坊さんであり続けるでしょうね。
「超越と実存」が意味するもの
――加えて、「物を書いて世に問う」という〝顔〟もあると思うのですが。
割と早い時期から何か書いてみたいとは思っていましたね。永平寺に入門してしばらく経ってから、仏教の考え方や言説が世の中に求められているんじゃないかと感じていましたから。というのは、坐禅の指導をしたり、偉い人の代理で話をしていたりすると、グッと乗ってくる人がいるわけですよ。特に若い人が。その手ごたえみたいなものを感じていたんです。
一方で、「あれ? こんな話を熱心に聞いてしまって大丈夫か?」という不安というか不穏な感じもありました。自分自身も他のお坊さんの語る言葉にリアリティを感じなくなっていた時期で、どこかにごまかしがあるというか幻想的なものに聞こえて、核心を突いた言葉に出会う機会が極めて少なかった。だから、いざ自分が語る番になった時、今までのように仏教について話をしていてもダメだと思いましたね。仏教を語る言葉自体を変えないといけない。それで、「論座」という月刊誌に機会をいただき連載を始めたのですが、間もなくオウム真理教による地下鉄サリン事件が起きた。はからずも不穏な感じが的中してしまったわけです。
――受賞作である『超越と実存 「無常」をめぐる仏教史』は、僧侶としての南さんの集大成的作品ではないでしょうか。もともと本書は、仏教史についての講義がもとになっています。
はい。講義は永平寺を下りた2003年から始めたもので、足掛け10年ぐらい続けました。そもそもは、若い修行僧に向けて仏教全体の流れについて話したかった、というのがきっかけです。それも自分なりの考えでもって。「自分なりの」という前提がポイントで、実証的な仏教思想史をやるつもりはありませんでした。仏教に対する私の考え方の根本が詰まっているという意味では、確かに集大成と言えるでしょう。
「ある人間が仏教というものをどのようにとらえたか」というサンプルになるものを作れば、それなりに面白いのではないかと思ったのです。読んで、「なるほど。この人は仏教をこのように見ているのか」と知ってもらえればいい。構想を聞いた友人は、「君は自分なりの家風を作りたいんだね」と言いましたが、我が意を得たりで、極端に言えば、客観的かつ正しい仏教思想史を記そうなんて気はないわけです。私は私の問題意識でもって、仏教史を通観する。すれば何が見えてくるか――ということを講義したかった。また、その人間が仏教外部にいるのではなく、実際に曹洞宗の僧侶であることの意味も大きいと思っています。
――本書は「超越と実存」という、およそ〝仏教書〟らしからぬ題がついていますが、これは講義の際から使用していたキーワードだったのでしょうか?
いいえ。講義の際にその言葉は使っていません。ですが、「超越」つまり形而上学的な思想が一体どのように仏教と関係していくのか――というアイデアはすでにあって、論理を構成するものとして使っていました。
――「超越と実存」の関係性から仏教史に迫る、といってもわかりづらいと感じる人も多いと思います。そのあたりをご説明いただけないでしょうか?
アイデア自体は、大学生の頃から考えていたもので、要は、こちらとしては「仏教とは諸行無常を説くものである」と思ってやっているわけです。つまり「すべての実存は無常である」と。ところがブッダ入滅後に出てきた、例えばアビダルマ(註・部派仏教の論説)や法華経、華厳経などを読んでみると、「無常ではない何かが〝ある〟」という話になっている――そう私には思えるわけです。それはなぜか。「諸行は無常である」つまり「あらゆる実存は無常である」とブッダが説いて始まったはずの仏教に、なぜ「ダルマ」「仏性」「唯識」「浄土」などの「超越的な存在」あるいは「超越的な観念」が後世になって論じられ、加えられていったのか。仏教史をたどりつつ、こうした疑問に対して自分なりの決着をつけたい、というのが目的で、そのための補助線として「超越と実存」というキーワードを使ったわけです。
もちろんそうした超越的存在なり観念なりを否定しているわけではありません。しかし、こうした「超越」が仏教に侵入してくると、もともとブッダが説いたことの意味が変質してくるのではないか。その変質はいかにして起こったのか。それは〝神〟のような「超越的存在」を前提とする、キリスト教やイスラム教といった他の宗教と変わらないのではないか――というようなことを考えてみたいというのが、その意図です。
根拠への欲望
――なぜ「超越的な存在」が仏教に侵入してきたのでしょうか?
いろいろ理由はあると思いますが、ひとつは人間の欲望のあらわれだと思っています。「諸行は無常である」というのは、ある意味非常に切ない話でしょう。「無常である」ならば、〝答え〟も存在しないことになる。「これが答えだ」となった瞬間に、無常ではなくなるわけです。しかし人間は、どうしてもその〝答え〟を知りたくなる生き物です。「悟り」や「涅槃」というものがあるらしいが、それが果たして何であるか。ブッダも明確に言葉であらわしていない。しかもそれを言い出したブッダはとうに亡くなってしまったので、当人に聞くこともできず、〝問い〟だけがずっと残ったまま。それがわからないままでいるのは非常に切ない。だから答えを求めようとする――欲望というのは、そうした意味です。
しかし私には、この「答えがあるから大丈夫」というところが気に入らない。問いは問いのまま抱えるべきで、ブッダも安直に「大丈夫だ」と言ったとは思えないのです。
――本書で、「思想には仏教と仏教以外しかない」とまで言っています。
「実存」を「超越」との関係で考えるのが「仏教以外」で、「超越」抜きで「実存」を考えるのが「仏教」と、ひとまずそのように区別してみたわけです。
「存在するものに根拠がある」と言うのか。それとも、「根拠があるとは少なくても言い切れない」「あるかもしれないし、ないかもしれない」ぐらいのギリギリのところで止めるのか。根拠があるとするか、ないとするか。それが仏教と仏教以外を大きく分けるものだと考えます。
先ほど、欲望という言葉を使いましたが、己の存在根拠を求めるのは、人間の最大の欲望だと思います。いわゆる食欲、睡眠、性欲というのは動物にも共通するものですが、存在根拠への欲望というのは、言葉と自意識を持つ人間にしかないものです。己が存在するのは何か根拠や理由があるはずで、それを発見したい、という欲望は、食べる、寝る、交わるを凌駕するほどのものでしょう。
大体、古今東西のおよそ思想と名がつくものは、その「根拠がある」という方向に奉仕していて、それを「明らかにしたい」という営みでもある。ところが、ブッダやその衣鉢を継ぐ仏教者たちは、少なくとも「〝ある〟とは言えない」「〝ある〟と断言してはいけない」とギリギリのところで止めるわけです。そちらの方が私にとってはリアルなのです。

なぜ仏教を必要としたのか
――仏教にリアルを感じるという南さんは、そもそもなぜ仏教を必要としたのか。それについて本書でも、はっきりと言及されています。いわく、幼少の頃から「死とは何か」「私が私である根拠は何か」という問いを抱えていたことが大きいと。
物心ついた時から強度の喘息に悩まされていたのが、大きかったですね。実際、死にかけぐらいまでは経験しているわけですわ。喘息の症状が悪化して絶息した後に、どうなるのか――そのことについて考えざるを得なくなるわけです。そうすると、確かなものは何であるかとか、「大丈夫だ」とか言われても、それを根本的に信じられない。
一番ショックだったのは、そのことが誰にもわかってもらえなかったことです。絶息した先に、死というものがあるというのはわかるけど、肝心の「死とは何か」については全く見当がつかない。わからないから困って大人に聞いても、「死んだらどうなる」という話を持ち出されるだけで、「死とは何か」という一番肝になる部分は謎のまま。
気づけば、「なぜ人は死ぬのに生きるのだろうか」と、問いが逆転してしまっていた。どうせ死ぬのならば、何をやっても一緒じゃないかと。結果、子供の頃から、生のリアリティよりも死のリアリティの方がはるかに強くなってしまった。普通は死の方が幻想的で、生の方がリアルだと考えますが、それが逆転してしまったわけです。
――それが「死とは何か」という問題に取り憑かれた理由ですね。
そうすると必然的に、私は何で生まれてきたんだろう、そもそも生まれたこの私というのは一体誰なのか、ということを考え始める。それが次第に昂進して、この世の中に確かなものなどあるのだろうかと思うようになるわけです。
――そこで仏教と出会い、20代半ばでいよいよ出家された。
やはり「諸行無常」という言葉と出会ったのが大きかったですね。答えなんてなくても当然だ、ということを言うわけですから。それまでの経験からして、そちらの方がはるかにリアルに感じられたのです。このブッダという人は、もしかしたら自分と非常に近いことを考えていたのではないかと思った。だったらもうそれに賭けてみるしかない。どこに連れて行かれるかはわからないけど、それに乗っかってみようと。
――「曹洞宗で出家したとき、私は仏教や宗祖道元禅師の遺した言説を正しいと信じていたわけでも、成仏や悟りを目指していたわけでもない」とお書きになっています。
私はブッダなり道元禅師に共感したから仏教に賭けてみようと思ったわけで、信心からではありません。なぜ共感したかというと、自分と同じ問題を抱えていると思ったからです。私の僧侶としての実践の土台は、すべて二人に対する共感です。
そうすると次は、その問題をどう解決するかが大事になってくる。ブッダも道元禅師も「こうしてみたらいいのではないか」ということを言っている。言葉であれ、思想であれ、実践であれ、問題を解決するための道具として示されているわけです。ならば、同じような問題を抱えている自分もその方法を試してみるべきだろうと。
「信仰」への懐疑
――「共感によって出家した」と語るお坊さんは珍しいのではないでしょうか?
だから他のお坊さんと話をすると、大体話が合いません。もちろんそれぞれ出家の理由は様々でしょう。ですが、たいていのお坊さんとは言葉や論理の立て方が根本から違うわけです。あちらも途中で、「あ、この人とは同じ土俵に立っていないな」と気づく。土俵が違うというより、競技が違う。あちらは相撲をしているつもりでも、こちらはボクシングをしているつもりでいるのだから、話が合うわけがない。よく先輩方にもアドバイスをされましたが、相撲の取り方を教わっても、まるで役に立たないわけです。しまいには同業者から「南さんには信仰がないね」と言われてしまう。その通りだったから、腹も立ちませんでした。
――なぜ「信仰」がネックになるのでしょうか?
「○○は真理であるから、信じなさい」と言われた瞬間に、ある錯覚の中に溺れていくような気がするんです。その〝真理〟は、時の権力や正義と結びついて、最初の意図とは全く違うところに連れていかれることもある。そうした例は歴史上いくらでもあるし、日本でも経験していることでしょう。
私は〝真理〟という時に生じるデメリットが、メリットよりも大きいと思う。根拠や真理とされるものがなければ、人間の社会と実存を支えられないだろうというのはわかります。しかし私はそこにデメリットを見てしまう。それは副作用と言い換えてもいい。その副作用を牽制するところに、仏教の凄味がある。
仏教という思想の最もユニークでオリジナルな部分は、そのデメリットを見ていることだと思います。もちろん真理や正義とされるものに、メリットもあります。しかし一方で、そこにあるデメリットをきっちり見据えている思想は、仏教以外にないと思う。仏教の中でも、特にゴータマ・ブッダ、そして『中論』(註・勃興期の大乗仏教を理論的に支えた龍樹[ナーガルジュナ]の論書)、それから親鸞と道元。彼らの思想から、私は真理や超越的な理念に対する敏感なる危機意識を感じます。とりわけそれは、「無常・無我・無記」の思想によくあらわれています。
――それは仏教界全体で共有できる問題意識ではないのですか?
共有できないでしょうね。どこの宗派でもいいのですが、お坊さんが顔を合わせれば「寺院は今後どうなっていくのか?」という話に必ずなります。しかし、その前に話すべきことがあるんじゃないかと、私なんかは思うわけです。
世の中、「仏教ブーム」と言われますが、だからといって寺に人が来るわけではない。仏教書がいかに売れたとしても、それ以上のことを知りたくて寺に人が来ることなんてありませんよ。開かれたお寺にするのも、僧侶がボランティアをするのも、大変すばらしいことだと思います。けれど、それをやるのであれば、なぜお坊さんである自分がそうしたことをしているのかを考えなくてはいかんと思う。突き詰めれば、なぜ曹洞宗や浄土真宗を選んだのか、そもそもなぜお坊さんをやっているのか、というところまで問いを下ろして考えなければ、根本的な解決にはならないし、これからはそこが勝負になると思う。
――その意味でこの『超越と実存』は、お坊さんとしての南さんの〝所信表明〟として読むこともできます。なぜ道元禅師を宗祖として仰ぐ曹洞宗に属しているのか、その理由も明確にあらわしています。
そうだといいのですが。でも、それぞれの宗派の祖師たちは、みんな同じことをやってきたわけです。私は、ブッダのいた時代と、法然、親鸞、道元、日蓮がいた鎌倉時代、そして現代は非常に似ているところがあると思います。にもかかわらず、生半可なおためごかしの言葉でごまかしていたら危ない。またオウムみたいなのが出てくる可能性だってあるわけです。そうした時に、自らの足元を見据えて、深い問いを重ねて、しっかりと言葉にしておかなければ、危ないですよ。
――「言葉」よりも「信心」の方をより問われるイメージがありますが。
その通り。ただ私は、人間というのは何かを信じて行動を起こすよりも、問題があって行動を起こす方が先だと思う。ブッダがそうでしょう。彼は何かを信じたわけではなくて、問題を抱えていたからあのような行動を起こした。繰り返しますが私は、何かを信じて行動を起こす、ということをあまり信用できないのです。
人が言葉で提示したことを信じて丸呑みするという態度が信じられない理由は、それが言語の問題に帰結するからです。この本で、「仏教思想の核心にある問題は言語、より正確に言うなら、言語において意味するもの(言葉)と意味されるもの(経験)の間にあると考えている」と書いたのは、そうした理由です。最大の問題は言語なんです。もっと言えば、言語に付随する「超越性」の問題です。なぜ言語によって、普遍的で絶対的なことを話すことができるのか――そこのところが、どうしても腑に落ちないのです。
熱心な読者であるとは決して言えませんが、小林秀雄に共感するのもそこです。それまでは何となく苦手意識があったのですが、大学生の頃にあらためて『モオツァルト』を読んだ。それで、この人は言葉と体験の間について敏感に考え、それを丁寧に掬い取ろうとしているんだなと思って感心しましたね。だから、その名前を冠した賞をいただいて、素直に嬉しく思っています。
話を戻すと、言葉というものに、我々がいかにとらわれているか。それに気づかず、言語に対して距離を保てないと、結局は言語に飲み込まれて支配されてしまう。それこそ現代のようにメディアが発達し、情報に埋もれている状況においては、それを構成している言語そのもののところまで踏み込んで考えなければ、情報の幻想性に惑わされてしまう。
そこで仏教が貢献できることは多くあると思います。培われてきた身体技法で、言語が意味するものを宙づりにしたり、解体したり。あるいは情報内の実存のありようを考える時に、それを全体として俯瞰できる視点をどこかに確保する時などに、仏教は使えると思います。
――しかしその仏教を伝える時にしても、言語を使わざるを得ません。
だから言語で言語を裏切り続けなきゃいけないでしょうね。つまり結論めいたものが出たら、その結論をさらに裏切って次に進まないと。つまり、「真理はこうだ」などと言い切らない。言い切らないで、余りを出し続けるという作業が必要になるでしょう。
――その意味では、南さんの執筆活動においても、この『超越と実存』が集大成ということで終わらず、どんどん次を更新していかないといけない、ということでしょうか。
その通りです。とはいえ、なかなかキツい作業ですが(笑)。ひとつ書き終えたその瞬間、途端に違和感を覚える性格なので、またどこかで重い腰を上げるとは思いますが……。とまれ、道元禅師の『正法眼蔵』については、いずれどこかで落とし前をつけないといけないと思っています。
――期待しています。あらためてご受賞おめでとうございます。
撮影・菅野健児(新潮社写真部)
● ● ●
選評
100度になっても沸点に達しないこと
加藤典洋
南直哉さんの『超越と実存』は、すっと私の中に入ってきた。
この本といっしょに、仏教も、これまでとは違うものとして私の中に足音もなく入ってきた。私は、どうも宗教というものは自分とは無縁だと心の底の底では思っていたようなのだが、いや、そのことが、仏教の本質なのだ、といわれたに等しい。
仏教はふつう悟りにどう達するか、という言語ゲームだといわれる。では、悟りたくない人は参加できないではないか、と私は漠然と思っていたらしいのだが、この本の著者は、鈴木大拙について、悟りなどということを大げさにいっているところが、やはりダメなのだ、という。私はこれまで、仏教以外の人を含めて、そういうことをあっさりいう人を知らなかった。
この本が批評だと思うのは、これまで著者が、数十年、修行し、考えたことを、超越と実存という簡単なストーリーに流し込み、さらにそれを、仏教史というヒストリーの枠で固めて、羊羹のように食べやすくしているところである。
著者は、一神教でない仏教の本質は、「絶対」とか「真理」とかへと超越しないこと、どこまでもその手前にとどまること、つまり実存を生きることだといっている。いうまでもなく、これまでの仏教観とは異なる。しかし、その異端の位置に、ブッダがおり、道元がいる。親鸞も、そうだという。
それで、私としては、仏教と自分の接点がわかった。どこまでいっても超越しないこと。100度で沸騰してしまう水は、それをはるかに超える温度に達することがない。ではどうすれば200度になっても、300度になっても沸騰せずに、いられるか。100度になって、沸騰する。それを悟りだといってもらっては困る。そういう問題に最後、道元はぶつかっているというのを教えられて、はじめて私に、身心脱落の意味がわかった。道元の師の語録に、そもそも身心脱落の語はない、師の理解とは違う、というのにもおどろいた。畏るべし、道元は悟りにいたらない身体技法を考えたというのである。
インド仏教、涅槃、中国化、古事記、空海、法然、親鸞、道元、とりわけ、後二者の存在理由がよくわかった。たぶん、この著者の見方は狭い、これは宗教ではない、という批判もありうるだろうが、ゴータマ・ブッダが前にしたものも、仏教ではなかったのだから、宗教の根源には宗教以前がある。そこでの問題との対し方とは、こういうものではないか、という気もする。仏教とは自分にとって、最初から「使えるかどうか」ということだったと著者はいっている。肉を切らせて、骨を断つ。こういうコトバを聞くと、私などは元気になる。
思想の強靭さ
養老孟司
ここまできちんとした哲学書があっただろうか。まずそう思った。仏教の核心は、言語において、意味するものと、意味されるものの間にある。そう著者は言う。つまり言語以前を視野に入れて語る。最初からいきなり言語に依存する哲学は、弱いというしかない。お利巧さんの哲学である。
著者の問いは簡単である。死とはなにか、自分が自分である根拠はなにか。
これで出家したというのだから、変な人がいるものだとしみじみ思う。でも誰がこうした疑問に一生を賭けるか。同時に頭が下がる。これが著者の強さである。真の強さは、オリンピックの金メダルや、野球チームの優勝だけにあるわけではない。迂闊な話だが、選評を書く段階になって、はじめて自分が評価したのは、この強さだったと気づいた。現代に欠けているのは、まさに思想の強靭さである。真の強さは言葉で飾ることができない。飾っても意味がない。飾るから政治家はバカに見えるし、ネットは炎上する。なにが「炎上」だよと思う。どうでもいいから炎上するのだろうが。
「世の思想には、仏教と仏教以外しかない」。よくぞ言ってくれました。その意味では私も門前の小僧、仏教徒ということになる。道元禅師も強い人だった。「自己をならふといふは、自己をわするゝなり」。
本当にいろいろ教えていただき、ありがとうございました。合掌。
この雄大な歴史観
関川夏央
日本に「超越」という観念が育たなかったのは、日本の共同体が血縁・地縁をもとに安定的につくられ、他民族の「渡来」はあっても「侵入」「征服」はなかったからだ。「渡来」者たちは間もなく生者と死者がともにある日本型共同体に包摂された。そこでは「剥き出しの実存」が問題となる契機はなく、したがって「超越」に救いをもとめる切実さもなかった。そういう状態がはるか古墳時代から現代までつづいたから、日本では「超越」に働き場所はなかったのだと著者・南直哉はいう。
だが平安末期から鎌倉時代にかけて社会は揺らいだ。「院政」や武士の勃興といった律令体制崩壊の危機にとどまらず、貨幣の浸透がもたらす商取引の活発化が既成の社会構造を震撼させ、人々の安定した「自己」は失われた。その結果「実存」はその根拠を必死にもとめ、それが法然、親鸞、道元らの鎌倉仏教を生んだ。宗祖たちは「超越」以外の拠り所を探しつづけた。
釈尊の生きた時代もやはり商業隆盛を原因とした価値紊乱期であった。さらに「グローバリズム」に浸食された現代日本も鎌倉以来の混乱期で、新興宗教や「自己啓発」の流行は「実存」の根拠をもとめるあがきだとするこの人の歴史観は雄大で、構えは大きい。
小児喘息を病み、幼い頃から「死」について考えざるを得なかった著者は、十五歳のとき「無常」という言葉を発見してすとんと腑に落ち、以後の人生を決めたという。
私の場合、「死」について考えはしたものの、すぐに恐怖を感じてあきらめた。なぜ自分は自分でしかないのか、なぜ他者になれないのかという不思議には悩んだが、やがてそれも忘れた。
そういう身としては、「ゴータマ・ブッダ以来道元禅師までの思想的言説を串刺しにして、これを一貫したストーリーとして語」ろうとするこの本の試みの意図と意味はわかっても、身にしみきらなかった。「悪人」のゆえんであろう。しかし他の選考委員の透徹した意見に強く説得され、この本『超越と実存』を授賞作とすることに快く賛成した。
地墨のような明快さ
堀江敏幸
仏教史を借りながら、「死」とはなにか、「私」が「私」でありうる根拠はどこにあるのかという実存の問題を突き詰める、きわめて直線的な思索の書。一本柱を抜いてしまうとたちまち崩れてしまう精巧な掘っ立て小屋か、もしくはトランプで築いた城のような危うさをもった、不要な飾りのない骨組だけの外貌は、しかし膨大な仏典を読み込んだ末に引き出した明快な線分に支えられている。
興味深いのは、言葉をひとつひとつ数珠状につなげていくうち、ある瞬間から、少し先に見えている光点までの道筋が、墨壺でひと息に引いた地墨のように示されることだ。なんというか、それは分析の鮮やかさよりも、問いの立て方の鋭さが読み手にもたらす、一種の覚醒に近い感覚である。この覚醒は《「実体」の無い妄想》を見据えようとする過程にあって、明快な説明の一切ないブッダの「悟り」や「涅槃」のように、「実体」をつかみとったという結果からはあらわれ出てこない。
つまり、本書じたいがひとつの矛盾から成り立っているのだ。言語論や創作論として読みうるのは、この矛盾の輝きによる。「自己」は事実として存在しているのではない。ひとつの観念である。ここにいることを認識している実存としての「私」と、それを外部から承認する「他者」が「共同で仮設している存在様式」が「自己」だとするなら、こうしたホログラフィにもならない「空」なる何かが引き起こす言語の連鎖こそが、あるときは小説になり、あるときは詩になろうとする実体なのだろう。語っている「私」は、それを「私」と名指した瞬間に消えてしまう。「仏」とは、「仏」という実存ではなく、「仏のように行為する」実存だという末尾に至っての指摘は、言語の成り立ちの秘密との齟齬を記して、まことに爽快である。「成仏した」「悟った」と言葉で概念化した瞬間に悟りは成立しなくなる。本書の実存の気配は、明快に語れば語るほど消滅していかなければならない。先に精巧な掘っ立て小屋だと述べたのは、その一点による。
ブッダ以後、仏教史を飾る僧たちの仕事を曇りなく語って、ふっと蝋燭を吹き消したような闇になる。そんな幕引きの予想をずらし、全体を平成の三〇年間を経たあとに向かうべき地平として示した本書は、仏教と無縁の者にこそ読まれるべき指南書となるだろう。
この記事をシェアする
「小林秀雄賞」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら